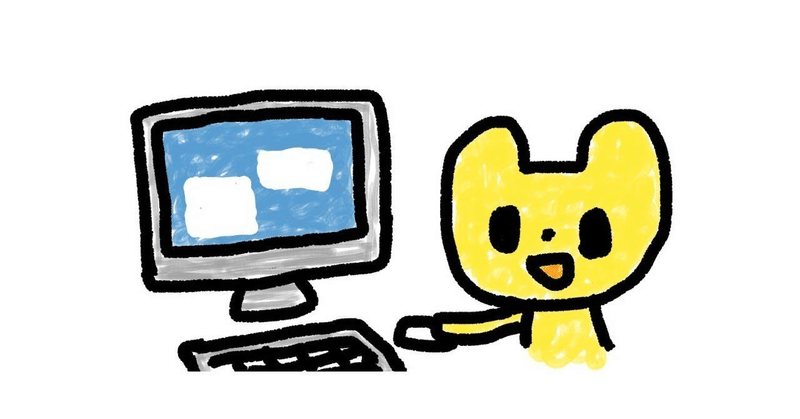
M&A、PMIにおける「文化」という言葉は「OS」と置き換えた方がいいと思う
僕らの状況
23年末に台湾の会社を買収しPMIの100日が終わった。様々なことがあり、その忘備録として今後気を付けたいことを記録しておく。
M&Aの前後でよく「文化」という言葉の表現が各所からあった。「文化が、、」と言われるたびにその都度具体的な内容の確認をしなくていけない。ただ「OS」と置き換えるとこのシステムが違う、という表現になりより建設的な議論が出来ると思った。
OSと置き換えたい理由
iOSなのか、MACなのか、Windowsなのか、Linuxなのか。またはバージョンが違うのか。派生システムなのか。MA前にはその見極めとシステムが違うのであれば2つのシステムを維持すべきか、1つを捨てるのか。バージョンが違うのであればいつどこから統合するのか。文化の融合という言葉は美しいが、OS融合と置き換えるとどれほどの難易度があるのかわかりやすく、それは目指さないほうが無難である。
実際のコミュニュケーションでは「あなたのOSのバージョン低いからうちのOSでいこうね」とか失礼過ぎて中々言えるものでない。ただ大抵の場合は経年とともにバージョンが上がって複雑化するので、初期のスタートアップにはバージョンが古い軽量なOSが最適な場合もあり、感情論は別にニュートラルに議論できる地ならしをするのが望ましい。中小規模のOSはほぼ創業者がそれを代替しているだから、全体を駆動するシステムとして独立していることはほぼないのだから。
CAPSULEのOS
これまで普通と考えてた弊社OSだが、他のOSを目の辺りにすると特徴ある部分が見えてきてここにまとめてみる。下記①と③は5年以上のアップデートを繰り返していて社内に浸透しており、②はここ2~3年で最適解をまだ探しながら浸透し始めている、という状況だ。
①部署別管理会計PL
弊社全体を動かす1番のシステムが部署PLだ。現在は4つの事業部となっていて各HeadがPL責任を全て持っており、数千万円単位の決済権限がある。採用及び解雇、事業投資も事業部主導だ。複数事業部関わる業務はHead同士でシェア比率を調整する。部署数字への強いこだわりと同時にどっちにしろ会社収入という全社意識の両立に初期は苦労したが、今は大きい問題は起きなくなった。そのおかげでCレベルは日々の固定業務はほぼなく、若干の部署間調整及び後述の②と③に関連する業務、全体に統一したガバナンスの管理がほとんどだ。

Cレベルと管理部、PRやエンジニアなどの全社コストは事業部署所属人数で配賦されるようになっていて、事業部HeadからCレベルには「このコストに見合う価値をあなたは部署に提供してますか」と部署PLを見る度に問われ、増減に関しての厳しい指摘もある。Cレベルは事業部のためにバリューを提供するサーヴァントリーダーとなるようなシステムとなっている。
この部署PLは各国法人の税務会計とは別にグローバル統一のSpreadsheetで管理している。また区分の柔軟な変更が必要となる場合があり、投資家向け開示売上区分とも別としている。その分管理部の業務が増えているはずだが、優秀な台湾の管理部がグローバル統合してまとめている。
どのような経緯でこのOSを組み込んだのか記憶が不確かではあるが、確か稲盛和夫さんの本を参考に第1弾を作ってから、各人のモチベーションの方向の変化で調整し、伝わりやすいビジュアルにしていった。ここ数年で見れば状況がわかる、というバージョンまでになったため部長との固定会議はなくせた。各課長レベルのHead向けの週報で気になることがあれば聞くだけになっている。本の言葉を借りるとCAPSULE流のアメーバ経営で社員ひとりひとりが主役となり判断できる状態が出来ている。
②Matrix KPI
このシステムは下記のような目的でここ数年運用している。


ミッション達成
弊社はIP, クリエイター向けのサービス提供を軸に事業が構成されていて、各事業PL以上に中長期でIP, クリエイターに対しての価値提供ができているのか、がミッション達成のために不可欠だ。各事業統一したKPIの数字を事業進捗と年度戦略によって設定する。
事業資産構築
このKPIは事業部ごとの資産の積み上げ、各チームや現場が追う数字となっている。年度単位でそこまで変わることはないが、微調整を加えたり上記KPIとの繋がりを意識するようにしている。
各事業部Headと他のKPIホルダーとの共創促進
部署PLのみの運用にしてしまうとどうしても部署間の協力が促進しにくいため、各KPIをMatrixに交わるようにしていて、これがあることで部署間対立が起きにくくなっている(と思う)。
上記のように変えることを是としているので、現在の課題は投資家向け開示数値をどれにするのかはもう少し時間をかけて検討している段階だ。
③OSのメンテナンス施策、バグを取り除く仕組み
これは結果論ではあるが、上記のようなシステムの駆動が上手くいっている要因は下記のような施策である。
新卒マジョリティ
①のような部署PL、②の中長期の資産を重視する働き方は、特に海外の営業(多くは個人ボーナスがモチベーションとなっている)とフィットしない。海外の社員の勤続年数は比較的短いと言われるように、営業以外の職種も短期的な視点での働き方が多いように思う。弊社のOSもここ数年はうまく機能しているように感じされるが、それは弊社の主要メンバーが新卒及び第2新卒で占められてシステムへの経験的拒否感がなくなったことも大きい要因な気がする。
部署異動
スタートアップ企業においてはどうしてもトライアンドエラーが多いため、社内変化を受け入れる組織が強い。変化に慣れてもらうためには常に変化をしておくことが1番だと持論を持っていて、たまマストではない部署移動を入れる。これも部署PLの達成に強い意志を持ちながらも全体を見て判断できるリーダー陣の育成に役立っていると思う。
報酬制度
海外の中小企業の多くは査定面談や昇給制度などないに等しい状況だ。その中で弊社は初期は四半期に一度、現在は半期に一度の査定、昇給をしっかりと行ってきた。これも個人的な持論として給料を上げず潰れる会社はあれど、給料を上げて(適切な範囲であれば)潰れる会社はない、と思っている。半期に一度人件費総額で約3~5%、各個人で見るとかなり緩急つけて上げている。入社時が若いことも影響しているが、平均20%近くが入社から給与が1.5倍になっていて、給与の中央値もかなり上がった。この会社と従業員の信用の積み上げもシステム駆動に寄与している。


適切な循環
日本では実質的には解雇ができない仕組みで中々実施できないと思うが、現地の労働法を遵守した上で年間で5%近いリストラクチャリングを実施している。この業務はCレベルが人事のサポートとともに主導して行うようにしている。日常的に関係があり、深い感情も生まれやすい事業部Headだとどうしても億劫になってしまう業務だが、非常に大切でありこれができているからこその昇給額の実現が可能となる。
最後に、、
これらの弊社OSの基礎は今回のMAを経なければ、意識しない普通のことだと思っていた。既に浸透しきっていることの弊害である。別組織に触れ、思い返してみても前職でもこのようなものはなかったし、そこそこユニークなものなのかと気づき始めた。今後のMAなどや新規のキャリア採用のためにアメーバ経営のような名前を付けておいてもいいかもしれない。部署PL→HP、MATRIX KPI→MP、のようなものが受け入れやすいかと今のところ考えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
