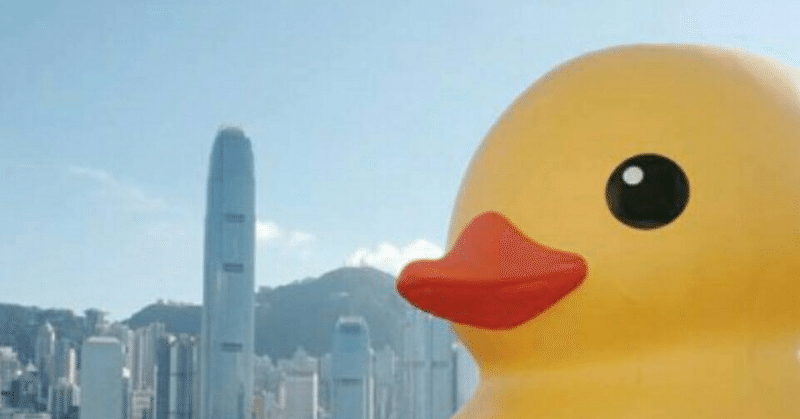
李源朝、汪洋両氏の処遇が焦点─3月の中国全人代(2013年2月)
中国全国人民代表大会(全人代=国会)と国政諮問機関の人民政治協商会議(政協)が3月初めから北京で開かれ、国家機関の大幅な人事異動が行われる。これにより、2012年11月の第18回共産党大会で総書記に就任した習近平氏が国家機関でも国家副主席から主席に昇格し、習氏を中心とする新指導体制の布陣が整う。党大会で政治局常務委員会入りを逃した李源潮、汪洋の両政治局員をどう処遇するかが焦点となる。
■国家副主席は誰か
李、汪の両氏は胡錦涛国家主席が率いてきた共産主義青年団(共青団)派の有力者。第18回党大会で政治局常務委員に昇格する可能性が大きいとみられていたが、高齢者優先の人事でいずれも政治局員留任となった。
李氏については党大会直後から(1)国家副主席(2)全人代副委員長(3)政協副主席―と三つの説が流れたが、先に公表された次期政協委員の名簿に李氏の名前はなく、(3)は外れた。
文化大革命後の国家副主席は当初、政治局員が務めたが、胡錦涛氏(98~03年)から党中央書記局常務書記(幹事長に相当)・政治局常務委員の兼任ポストに格上げされた。その慣例に従えば、党大会で同常務書記・政治局常務委員となった劉雲山氏が国家副主席を兼ねることになる。
しかし、前党中央宣伝部長の劉氏はこれまでの常務書記と違い、党指導部で宣伝工作も担当する。さらに、外交活動に携わる国家副主席まで兼務すれば、仕事量は膨大になる。また、歴代の国家副主席は有力長老や次期総書記、大派閥の実力者だったが、劉氏はそのどれにも該当しない。劉氏は経歴のほとんどが宣伝部門で、地方(省・自治区・直轄市)首脳の経験もなく、格の高い国家副主席としてはキャリアが薄いのが難点だ。
一方、李氏は党内最大勢力である共青団派の大幹部。江蘇という大きな省の党委書記や人事を握る党中央組織部長を歴任し、12年夏までは党中央書記局常務書記への就任が当然視されたほど、キャリアと人望が厚い。
■香港・マカオと外事を担当か
李氏は党大会を機に中央組織部長を退任してから、政治局員として何を担当しているのかは公表されていない。だが、習総書記が12年12月20日、北京を訪れた香港の梁振英行政長官と会談した際、李氏は次期全人代常務委員長の張徳江政治局常務委員や劉延東政治局員(国務委員)と共に同席した。
習氏が兼務していた党中央香港・マカオ工作協調小組の組長は張氏が引き継いだか、近く引き継ぐとみられる。劉氏はもともと同小組の副組長で、続投する見通し。李氏がこの会談に同席した事実は、同小組の副組長になった、もしくは近くなることを意味する。
しかも、香港のテレビが放映した映像によると、習総書記は梁長官に同席者を紹介した際、張氏、李氏、劉氏という順番で名前を呼んだ。したがって、李氏は同小組で筆頭副組長として日常工作を取り仕切る可能性がある。
李氏はさらに、13年1月29日に北京で村山富市元首相とも会談した。外国政府の元首脳と会うのは外事工作なので、李氏は党中央外事工作指導小組の副組長も兼ねるもようだ。そうなれば、李氏は新しい外交担当国務委員や外相の上司ということになる。
中国指導部において、祖国統一事業の一部である香港・マカオ政策は主要国との外交や台湾政策と並ぶ重要事項。もし李氏が国家副主席に就任して、香港・マカオと外事の両副組長を兼ねれば、事実上は政治局常務委員に準じる処遇となる。
ただ、香港メディアやインターネット上ではいまだに、李氏の足を引っ張るような中国本土発と思われるうわさ話が出回っており、党内には李氏の厚遇に反対する意見があるようだ。
■「新政の先兵」
同じ政治局常務委「落選」組ながら、汪洋氏は副首相就任が確実だ。しかし、担当に関しては諸説ある。
汪氏が副首相から政治局常務委入りした張徳江氏の後を継ぐとすれば、工業や交通などを担当する普通の職務になる。しかし、習総書記が12年12月、わざわざ汪氏が広東省党委書記を退任する直前に同省を視察し、汪氏を重視する姿勢を示したことから、汪氏は習近平指導部で特に重用されるのではないかとの見方が出ている。
香港誌「中国密報」3月号は李克強氏(現副首相、次期首相)率いる国務院の新指導部について、常務副首相となる張高麗氏は保守的、国務委員から副首相に昇格する劉延東は能力に限りがあるので、「汪洋は第3の副首相ながら、李克強内閣で疑いなく最も重要な役割を演じることになる」との見方を示した。
香港誌「新維」2月号は、国務院がかつての国家経済体制改革委員会のような機関を設けて体制改革を主導させ、汪氏がその責任者を務めるだろうと予想。香港誌「前哨」3月号も「汪洋は習近平・李克強の新政において、余人をもって代え難い先兵となる」とした上で、習総書記が3月の全人代・政協後に打ち出す所得分配体制改革で汪氏は重要な役割を果たすとの情報があると伝えた。
だが、1月からインターネット上で流れている情報によると、習総書記は12年12月の広東省視察で現地当局者らに次のように語った。
「中国の改革がある分野で停滞しているとする言い方には賛成しない。幾つかの改革しないことや改革できないことは、いくら時間がたっても改革しない」
「西側の普遍的価値と政治制度に沿って改めることを改革の定義とし、そうでなければ改革ではないと言う人がいるが、それはすり替えの概念であり、われわれの改革に対する曲解だ」
これらの発言は習近平版の「南巡講話」とされているが、内容はかなり保守的である。発言内容が事実とすると、習総書記が今後、既得権益集団の抵抗を排除して、大胆な改革を断行する可能性は小さく、改革派の汪氏が実際に手腕を振るう機会がどれだけあるのかは不透明だ。
中国のニュースサイト「財経網」が2月23日伝えたところによると、全人代に提出される国務院改革案に経済体制改革を統括する機関の新設は含まれていないという。(2013年2月24日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
