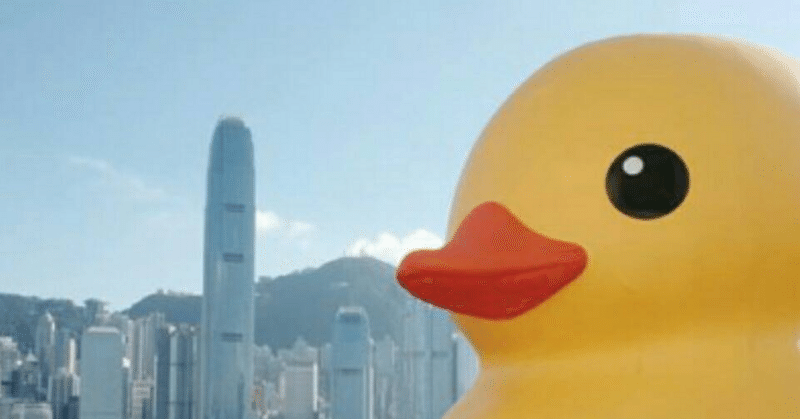
胡派の李源潮氏、国家副主席に─習近平指導部が本格始動(2013年4月)
3月に開かれた中国全国人民代表大会(全人代、国会に相当)と国政助言機関の人民政治協商会議(政協)で国家機関の人事異動が行われ、昨年11月の第18回共産党大会で党総書記・党中央軍事委員会主席に就任した習近平氏が国家主席を兼任した。これにより、習主席率いる党・政府指導部が本格的に始動した。前総書記・軍事委主席の胡錦涛氏は全人代で国家主席も退任し、中国共産党政権のトップとして史上初めて自主的に完全引退。一方、党大会で政治局員から政治局常務委員に昇格できなかった胡派の李源潮氏は国家副主席に選ばれ、常務委員並みの地位に就いた。
■外交・香港を担当
李氏は胡前主席と同じ共産主義青年団(共青団)出身。江蘇省党委書記を経て、2007年から人事を担当する要職の党中央組織部長(政治局員)を務めた。その人脈・キャリアから第18回党大会で政治局常務委入りするとの見方が多かったが、高齢者を優先する妥協人事の結果、政治局員再任となった。
しかし、今回の全人代で、これまで胡、曽慶紅、習の3氏が政治局常務委員として務めた国家副主席に就任し、存在感を増した。副主席就任前から香港の梁振英行政長官や村山富市元首相らと会談しており、党中央香港・マカオ工作協調小組や中央外事工作小組の副組長を兼ねているとみられる。
党中央の各小組は党・政府・軍の高官から成る最高レベルの調整機関で、中央香港・マカオ工作協調小組の組長は全人代の張徳江常務委員長、中央外事工作小組の組長は習主席。李氏は両小組の首脳として、楊潔◆(タケカンムリに褫のつくり)国務委員(前外相)、国務院香港・マカオ事務弁公室の王光亜主任、王毅外相の上司ということになる。
国家副主席は1998年から党中央書記局常務書記(幹事長に相当)が兼務してきたが、第18回党大会で常務書記に就任した劉雲山氏(前党中央宣伝部長)はこれまでの常務書記と異なり宣伝工作も管轄するため、国家副主席にはならなかった。
メディアやインターネット上では李氏について「有力長老に嫌われている」「個人的スキャンダルがある」などと悪いうわさが流され、「全人代副委員長か政協副主席に事実上左遷される」との説もあったが、胡派に反対する勢力の希望的観測だったようだ。実際には、李氏が国家副主席として習近平指導部で重要な役割を担うことは党大会の時点で内定していたとみられる。
■孤立した江派
温家宝氏が首相を退任した国務院指導部は、李克強首相と張高麗、劉延東、汪洋、馬凱の4副首相という布陣になった。李首相と張副首相は政治局常務委員、張氏以外の3副首相はいずれも政治局員だ。
李首相と劉、汪の両副首相は共青団出身で、胡派の有力者として昇進してきた。馬副首相は温前首相に近く、江沢民元国家主席派は張副首相しかいない。官房長官に当たる国務院秘書長にも共青団出身の楊晶氏(党中央書記局書記)が起用された。張氏は筆頭副首相ながら、胡・温派に取り囲まれた形である。
新しい国務院では、李源潮副主席と同様、第18回党大会で政治局常務委入りを逃した前広東省党委書記の汪副首相が注目されている。
汪氏は李克強首相や李源潮副主席と違って団中央勤務がない地方からの「たたき上げ」。広東時代には、改革派として左派の薄熙来・元重慶市党委書記(昨年3月解任)と政策論争を展開したり、市場経済化推進のため「落後した生産力は淘汰(とうた)する」と公言したりして、話題になった。
3月の全人代でも、出身地の安徽省代表団の会議に参加した際、「改革とは刃物で自分の肉を割くことだ」と延べ、政府や企業の既得権益を削ってでも改革を断行する必要性を強調した。
■習主席が頼りに
習氏は昨年12月、総書記就任後初の地方視察として広東省を訪問。汪氏を地元トップとして同行させるため、北京への転任をわざわざ遅らせている。さらに、国家主席就任後初の外遊で3月にロシアを訪れた際も、汪副首相を先にモスクワへ派遣しており、習主席が政治的に汪副首相を頼りにしているのは間違いない。
また、李克強首相は就任記者会見で、市場経済化のため政府の市場に対する余計な関与をなくすべきだとした上で、政府の権限縮小は「腕を切るような感覚」を伴うと強調したが、こうした考えは汪副首相の持論と全く同じだ。李首相は汪氏が広東省で進めた改革路線を全国で実践することになる。
汪副首相は農業・貿易を担当するもよう。農業を担当するのは、李首相が重視する「新型都市化」、つまり、農村出身者を実質的に都市住民化する政策に関わるためであろう。さらに、香港メディアでは、習指導部が今後、所得分配などに関する重要な改革を打ち出した場合、汪副首相が重責を担うとの見方が出ている。
■二重院政?
第18回党大会で決まった政治局常務委人事は、李源潮、汪の両氏が外れたため、相対的にやや江派寄りになった。ただ、軍事委や党中央の部長、地方トップはほぼ胡派の思惑通り。さらに、李副主席と汪副首相がいずれも普通の政治局員以上の影響力を持ったことで、党・政府指導部人事は全体として、江派や長老たちの顔を立てつつも、習主席と胡派がかなり実を取り、勢力が一応、均衡したと言える。
長老たちがこれに満足して、党内の団結維持のため、おとなしくしているのが理想的なのだが、なかなかそうはいかないようだ。
4月4日付の香港各紙によると、江氏は日本のお盆に当たる清明節(4日)を機に故郷の江蘇省揚州市を訪れ、帰省によって健在をアピールした。
江氏は軍のナンバーを付けた警護車両を含む車列で移動。ネット上では3日から、江氏が歩きながら手を振る写真などが出回った。
これに対抗するためか、4日には胡氏が広西チワン族自治区の南寧市を訪れた際の写真がネット上で流れた。胡氏が笑顔で市民と握手している写真だ。
公式序列が大幅に落ちて、普通の長老になったはずの江氏。「完全引退」したはずの胡氏。二人のうち、どちらかが動けば、もう一人も動かざるを得ない。これが高じれば、中国の政治は「二重院政」という異常な状態に陥り、経済改革にも悪影響が生じる恐れがある。(2013年4月7日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
