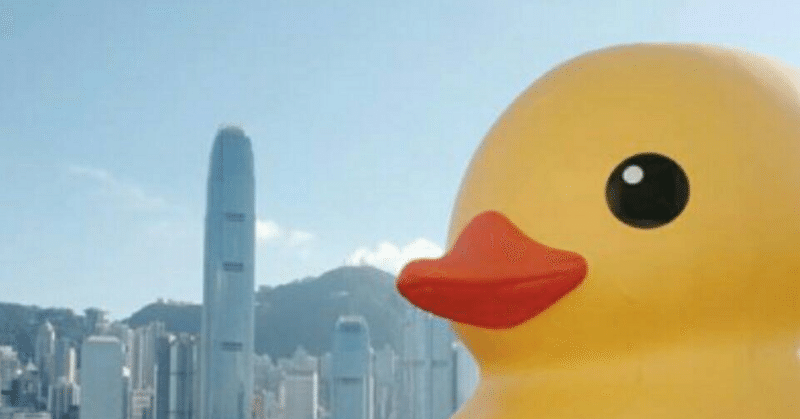
「琉球独立」あおる?─中国で強まる日本の領有権懐疑論(2024年4月)
中国でこのところ、「琉球」(沖縄)に対する日本の領有権を疑問視し、中国との歴史的関係の深さを強調する主張が目立つ。共産党政権の公式シンクタンクに所属する専門家が相次いで論文を発表。「琉球独立」をあおるかのようなキャンペーンを展開している。
■公式研究機関の論文相次ぐ
中国歴史研究院は3月下旬、SNSを通じて、琉球に関する論文3本を紹介した。いずれも、同研究院が出版する「歴史評論」(隔月刊誌)の今年第1号に掲載されたもので、同国最大級の公式シンクタンクである社会科学院日本研究所の専門家が執筆。歴史研究院の別の専門誌「歴史研究」の昨年第6号、日本研究所の「日本学刊」の昨年第6号なども琉球を取り上げ、今年2~3月にSNSに転載された。
歴史研究院は習近平国家主席2期目の2019年成立。社会科学院に属するが、院長は閣僚級で格が高く、中国における歴史研究の最高峰と言える。
これらの論文は以下のような見解を示した。
一、琉球は昔から日本に属していたというのは、日本の統治を合法化するための偽の歴史だ。(江戸時代になっても)薩摩藩の琉球に対するコントロールは限定的で、琉球は中国の属国だった。
一、琉球人は南方や大陸の影響を受けながら、独自に発展した。「日琉同祖論」は成り立たない。
一、明は琉球への支援を通じて、東海(東シナ海)に対するコントロールを常態化していた。中国の東海に対する権利には完全な証拠がある。
一、日本の琉球併合は近代日本軍国主義の侵略・拡張の第一歩だった。
一、琉球諸島は「地位未定」の状態にある。カイロ宣言、ポツダム宣言などに基づく第2次世界大戦の国際秩序は、琉球を日本領として認めていない。中国を除外したサンフランシスコ講和条約体制は本質的に非合法である。
いずれも「琉球は中国のものだ」とは言っていないが、琉球は歴史的に日本より中国との縁が深かったという主張は共通している。共産党の指導下で統一見解がまとめられていると思われる。
■習主席が言及、馬英九氏も
中国共産党は前近代の中国が治めた、もしくは関わった地域を自分たちの縄張りと見なす傾向があるので、同党指導下の研究機関が中国・琉球関係の歴史を重視するのは不思議ではなく、公式メディアが過去に同じような見解を示したこともある。それにしても、今ここまで力を入れるのはなぜか。
思い当たるのは習主席の「琉球」言及だ。習主席は昨年6月、古文書などを収蔵する北京の国家版本館(中央総館)と歴史研究院を視察した。党機関紙の人民日報によると、版本館の職員は明代の文書「使琉球録」(写本)を、「釣魚島」(沖縄県・尖閣諸島)が中国に属することを示す早期の史料として紹介。元福建省長の習主席は同省勤務時代を振り返り、省都の福州と琉球の交流が盛んだったことを知ったと述べ、史料の収集・整理を強化して中華文明をきちんと伝承していくよう指示した。琉球を中華文明の中に含めたようにも聞こえる。
さらに翌7月、福建省は玉城デニー沖縄県知事の来訪を受け入れ、同省指導部トップの省党委員会書記が会談に応じるなど厚遇した。
こうした動きを機に、シンクタンク側が党からの指示、または習主席の意向への忖度(そんたく)に基づいて、琉球関連論文の量産を始めた可能性がある。「琉球ですら日本の領土かどうか怪しいのだから、釣魚島が日本領であるわけがない」と言いたいのだろう。
「使琉球録」という史料は中国で非常に重視されているようで、訪中した台湾の馬英九前総統が4月6日、西安(陝西省)の国家版本館を訪れた際も紹介された。馬氏は「釣魚台(台湾での呼称)は琉球に属していないことが証明された」と語った。
また、琉球の地位未定という中国側の主張が台湾地位未定論とよく似ているのも興味深い。台湾地位未定論は台湾独立につながるので、中国共産党はこれを一貫して拒絶しているが、日本に対しては同じ理屈を使っているのだ。
習主席が同10日、馬氏との会談でも言及したように、中国は台湾独立を「国家分裂」と見なして、絶対に容認しないと強調。ウクライナに侵攻したロシアを事実上支持しながらも、ロシアのウクライナ領土併合は明確に認めないなど、他国の分裂についても慎重な態度を取ってきたが、日本だけは例外になっている。
以上のような中国の琉球論は現在、インターネット上で一般の人々も盛んに取り上げており、全く規制されていない。日本をけん制する愛国的言論と見なされているようだ。しかし、自国の分裂反対を日々叫びながら、隣国の分裂をあおるのは矛盾した姿勢であり、中国自身にとって危険な「火遊び」をしているように見える。(2024年4月10日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
