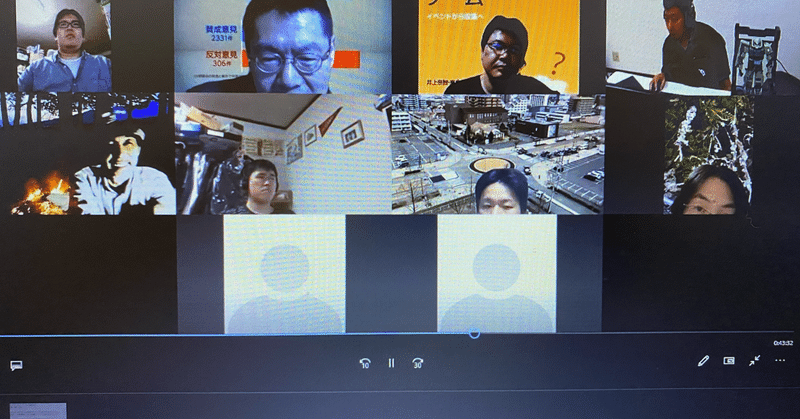
zoom井戸端・座談会として『報・動・力「検証ゲーム条例」』YouTube配信後座談会を行ってみる
前置き
その日、6月27日、香川県・岡山県のテレビ局(朝日系列になるかと思いますが)、KSB(瀬戸内海放送)さん作成のドキュメンタリー系番組の報・動・力で、先ごろ世界的に話題になっております、今年四月施行の香川県の「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」についての特集番組があるとのことで、待ち時間に少し別のことをしておりました。
1974年に作られた、小松左京原作の映画『エスパイ』です。この映画では、いわゆる超能力を持った方たちのエージェントが活躍する「SFとエスピオナージュもののハイブリッドのような作品」とでもいえるのですが、結構突っ込みどころが多いのですがその冒頭で、「これら超能力の存在が、科学的に証明されたのも、つい最近のことである。」というナレーションが入るんですが、いやいやいや、証明されてないだろうと、突っ込みを入れながら見ていたんですが、今思うとそれは非常に示唆的でした。

KSB報・動・力の「検証ゲーム条例」
さて、今年の香川県の香川県ネット・ゲーム依存症対策条例、ですが、実はこの間に、その成立までの過程が、Webニュースの「ITmedia」などで継続的に報道されたほか、ウィキペディア日本語版でも「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」にも詳しい記事が立項されました。さらには、6月16日から24日までの間に5回連続で行われた、「第4回情報法制シンポジウム」(一般社団法人情報法制研究所主催)では、テーマ5として、「“香川県ネット・ゲーム依存症対策条例”を考える」と、この条例自体の立法根拠や、成立過程で行われかつ問題点が指摘されているパブリックコメントについての分析結果も報告されました(そしてこの研究自体は今後オープンにしていくとのことでしたので、またわかり次第こちらにも追記していこうと思います)。
こうした条例制定の過程自体を注目している存在として、香川県・岡山県のテレビ局(朝日系列になるかと思いますが)、KSB(瀬戸内海放送)さんも夕方の報道番組等で継続的に取材を行い、それらをまとめさらに新しい取材を合わせて作成されたドキュメンタリー系番組、「報・動・力」で、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」についての特集番組「検証ゲーム条例」を6月27日に放送、同日21時からはその番組をyoutubeで配信しました。
まだ、しばらくはその番組が見られるようです。
報・動・力「検証 ゲーム条例」〈番組全編を特別公開中〉6/27放送
こちらの番組では、これまで継続的にKSBが取材してきた、ゲーム依存症に関しての問題、条例制定までの経過や、パブリックコメントの問題点、制定における県議会の姿勢等、情報法制研究所の研究会の内容も踏まえながら、条例制定のキーパーソンである大山一郎県議会議員にもスポットをあて、かなりわかりやすくまとめた力作でした(そして、youtubeでは、平日でも60分以内に見れるようにしてくれてあります)。
こうした番組をもっと見ていただきたいし、またそれを踏まえていろいろと課題を整理したり改めて情報をシェアするために、youtubeでこの番組を見てもらい、zoomでの意見交換会を企画してみました。

zoomで井戸端・座談会として『報・動・力「検証ゲーム条例」』YouTube配信後の交流会をしてみた
とりあえず番組がテレビで放送された最中に気が付いて、告知などもその日のうちでだいぶ短い時間でしたし直前までオンライン会議で開始が23時過ぎとかなり遅かったんですけれど、前々からこの問題に関心を寄せてくださっていた方にお誘いした方も含め、結局最大で12名ほど集まっていただき気が付くと、2時間以上にわたり、番組を見ての感想や意見効果、情報交換など非常に興味深く行えました。
前からこの問題に関心を示しておられて、北欧のある国の図書館ではゲームも含めて人々の生活に根差した文化的ツールの一つとしてゲームが位置づいている点に注目されている方から、事前に番組の感想をまとめてきてくださったので、そのあたりの話を最初のきっかけとして話題提供していただきました。いくつかの話題提供があったのですが、そのうち二つの点を以下で振り返ってみます。
まず話題となったのは、「疾病」といいますか、依存症というものをまず何かの身体的な疾患に基く病状と同じように、「治療」の対象といいえるのか、というお話が話題に出ました。これは番組で解説をしていた、井出草平先生も、情報法制研究所の研究会で報告していた点で、いわゆる身体面以上に、家族も含めた環境要因も大きく働きうるし、それだけにサポートが必要な状況とすれば、単に条例を作ってそれで終わりとはならないわけで、まずはその視点自体が非常に単純ではないのかとの懸念です。私もその点は懸念をしており、むしろ、本当にそうしたゲームに由来する依存症に苦しんでいる本人や家族がいるのであれば、その現状の調査と、実態に合ったサポート体制の確立、さらには、その「症状」の分析にあたり、総合的に(例えば家族の問題や、他の精神疾患等の症状がないかどうかの吟味など)その当事者に臨床的に寄り添えるのか、そうした点が条例からは見えてこない点が改めて話題となりました。そして偶然ですが、この日、6月27日に、私は、別のオンライン研究会に参加しておりました。
南山大学社会倫理研究所2020年度第3回懇話会「共通テーマ:依存症と責任」

こちらの研究会では、ゲーム障害とは異なりますが、主に薬物依存のサポートにかかわられている研究者の方からは「依存症は自己責任の病なのか?:精神病理と回復過程を検証する」というテーマでの報告、また哲学史的倫理学的な研究者の方から依存症者に対して「第三者による非難は適切でありうるか:薬物依存症の事例」という視点での研究紹介がされ、ある種の狭い意味での自己責任的アプローチが総合的に「依存症者への対応」としては限界がある点に言及されていました。支援者は、一人一人に個別に向き合い、場合によっては、カーム・リダクションと呼ばれるある種の緩和策をも念頭に置き、一方である状況の中で「薬物」という選択を自分の意志でしてしまった点などに対しても視野に入れつつ、しかし社会規範的な意味での「弱い非難」により個別な対応を構想する、非常に地道かつ総合的な配慮が必要な依存症へのアプローチを垣間見た気がしました。それだけにその支援の手法は科学的な根拠に照らし合わせつつ、かつまた個々の当事者の状況を育成歴も含め理解しながら対応されてもいると。一律で何かの外形的な基準を当てはめるようなアプローチとは全く方向性が異なる点をこの研究会で、垣間見たわけです。
あとこれは、井出草平先生の情報法制研究所での指摘ですが、いわゆるゲーム依存に苦しんでいる方、あるいはゲーム障害とされるような方の場合、ゲーム障害だけでとらえきれない症状が複合的に重なっているような場合も多く、そうした意味でゲーム障害という定義だけでアプローチしていいのかという、臨床的な課題もある点は重要な点かと考えます。
またもう一つの話題としては、この番組でKSBなどで、触れられていたゲームについてですが、取材のなかでも登場したe-スポーツ的なものに目が行きがちであるけれども、実は、そうした、ゲームをすることで効果やある種の能力評価が明確な分野もゲームの一つではあるけれども、実は、広範囲のゲームユーザーに支持されているのは、「あつまれ動物の森」のような、ある種の生活の疑似体験的なジャンルになるゲームなのではないか、という視点でした。こうした条例のような、ゲームやインターネットの制限をかける議論の際に、「ゲームは何かできる」とか、「学習に役立つ」というアプローチもあるが、一方で生活というか文化全般に根差している点への視点も重要であるという視点です。どうしても「〇〇をすれば△△ができる力になる」という切り口であると、ある種の思想善導的なアプローチにも組み込まれる(もしくはそれを知らないうちに刷り込まれていく)点があり、そうした論点もまたある種の陥穽があることをどこかで視野に入れておく必要があるという点でした。
またこうした意見交換の中で、「ゲーム依存症対策条例」的な問題や一方で「読書推進」という形で、結局は、学びのスタートになる個々の人々の探求のきっかけが結局、制限か推奨かの違いはあるが、干渉される点の問題点にも話が及び、私も、ユネスコの学習権宣言における、「成り行き任せの状態から、自分自身の歴史の主人公になる」学びの権利の話や、学びたいという意思を大人がゆがめない自己決定を尊重する教育制度を模索したエットーレ・ジェルピの話など、ついつい話してしまいました。そういえば、子供の権利条約を推進してきた人たちは、この問題を無視できないはずです。子どもの意見表明権が配慮されない状況の中で、すでに子ども(だけでなく大人も)の生活に密接にかかわる、インターネットやゲームの制限をしてしまっていることに対しては、何かの意見表明がなされる必要があるのではないかと考えます。
このほか、県のイメージの低下になっていないか、実際になんでそもそもこの条例を作成したのかなど、多くの話題が意見交換されました。
今後の番組に期待すること
さて、話は尽きず、2時間で出た話題すべてを紹介はできませんでしたが、参加された方共通していたのは、こうした条例はありながらも、条例の問題点はしっかりと指摘しつつ場合によっては長期戦になる前提で取り組み、一方で可能な範囲で児童・生徒や子どもたちに対して知のインフラや文化として定着しているインターネットを含むアーキテクチャーについて触れる場を気づいたものが提供し続ける努力をそれぞれの持ち場で考えていく、という話も話題に上がりました。
私自身は、この問題のキーパーソンとして登場した、大山県議会議員について、ある種の象徴だと考えています。というのも、私は彼の政策といいますかゲーム依存症対策条例を生む思想とは相いれませんが、一方で、すでに2009年ごろから公的な場で発言しておりある種の支持者層も含めた「県民の民意の象徴」であると思うのです。特に、「ゲームがあることで成績が下がる」などと考え、特に因果関係もはっきりしない「ゲーム時間」と学習意欲や生活態度を結び付けて考えている人々が相対的に多数派である限り、この問題は解決しないのだろうと。揶揄的に言えば「科学的根拠が特にない条例を作ってでも成績を上げたい大人」たちの存在です(それは成績上がるわけないですよ、科学的根拠ないんだから、という突込みはおいておいて。なぜなら私は、受験的なものが勉強と考える知性(痴性)にも辟易しております)。
こうした点で気になるのが、香川県内の地方議会の市議会、町議会の議員の方々の存在です。実際この条例が今後問題になるだろう点としては、こうした県の条例を金科玉条のごとくとまではいかないにしてもその(さらに)劣化コピー的な基礎自治体条例ができてこないのかといううことです。その証拠とでも言いましょうか、すでに昨年、e-スポーツに関係する意見書を県議会で取りまとめておりますが、その時すでに、今回の「ネット・ゲーム依存症対策条例」につながる発想の取りまとめが全会派で一致して出されているという事実です。つまり、常にニーズはあるわけです、こういったことを取りまとめて発表しておけば(少なくとも投票する県民には)支持されるという、地方議会の先生方の世界にはこうした前提が存在するのでしょう。
香川県議会で採択された意見書・決議「eスポーツの活性化に対して慎重な取組みを求める意見書」
おりしも、森氏がかつて「ゲーム脳」という言葉を持ち出して、一時期メディアで取り上げられ、その言説の科学的根拠が希薄な状況にもかかわらずマスメディアで紹介されそして地方のPTA組織に広がりある種の共犯関係で学校教育にこの発想が広がった、2000年代前半が思い出されます。そういえば、今回の条例の検討委員会でも招聘され講話をされた岡田尊司氏も森氏同様に雷博士という脳科学者のゲーム依存症者は脳の白質部分に影響が出ているという研究を紹介しているのですが、その研究自体が根拠が希薄である点を指摘している研究がいくつもある点を井出草平先生が紹介しているのでその記事を紹介しておきます。
井出草平の研究ノート(2020-06-26ゲーム障害と白質に関する簡単なメモ)
あともう一つは、前述した、情報法制研究所JILISの研究会で、香川県のネットゲーム依存症対策条例に関する研究会の前に行われた、「テーマ3「デマ・フェイクニュース・炎上とどう向き合うか ~コロナ禍で見えたソーシャルメディアの課題」(期間限定でこの様子が動画で見れます)というテーマの研究会で、フェイクニュースの拡散する現状を分析・研究をされている、笹原和俊先生(名古屋大学講師)がパねえるディスカッションの中で報告された、「フェイクニュースをめぐる世界状況」においておっしゃっていたんですが、そうした偽情報の言説は、「コンテンツとして面白いし、動画など様々なバリエーションを駆使して伝えようとする」そうですが、一方で科学的根拠に基づく言説は、結局「それは科学的ではない」という主張が中心にあるため、言ってしまうとコンテとしては「面白みに欠ける」という点を指摘されていました。その点は今回の条例に関しても、なかなか根深い問題が横たわっている気がしす。そしてこの報告の中で、いわゆる陰謀論や、ワクチンなどに対する偽情報を広める人々の創造する言説は、位置情報で見る分析によれば空白地帯を目指していわば「自説を広める」ように自分の言説にとっての空白地域を埋めていこうとするかの言動が感知されてもいるようで、香川県だけでなく今後どのように今回の条例を生み出す思想がどこまで伝播するのか、非常に懸念もしております。
さて、長々書きましたが、今後もこの番組で取り上げた取材に期待をしていますし、また意見交換の場を作ってほしいとのご意見もいただきました。何らかの形で行いたいと思っております。
とりあえず、予告的には、次回、社会教育、生涯学習系の書評会、それと図書館の今後を見据える論点に関しての雑誌の講評会等、zoomで企画したいと思ってます。
資料
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)のパブリック・コメント(意見公募)実施結果
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(香川県報に記載された本条例条文)
・香川県弁護士会「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に対する会長声明」に関しての要約メモ(会長声明メモ)
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例に対する香川県弁護士会長声明に対する見解
・「検証 ゲーム条例 - 報・道・力 」( 本条例の取材録をまとめた瀬戸内海放送(KSB瀬戸内海放送)のサイト)
・「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」(ウィキペディア日本語版記事)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
