
睡眠を身体的に観る~1日の約1/3は寝具の中~
睡眠というとレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルや、夢を見たかどうかなど、脳波や意識状態に焦点をあてるとなかなかコントロールしにくい領域のものに思えてしまいます。
ですが寝ている時の体の状態に焦点をあてると、より質のいい睡眠へのアプローチポイントがみえてきます。
疲れ具合によって体が欲する睡眠時間はその日によって多少前後しますが、眠りの最適時間は骨格のタイプで異なるといわれています。
例えば2度寝をしたらスッキリする人がいれば、逆に2度寝をするとダルくなる人もいます。
ナポレオンは睡眠時間が3時間だったといわれていますが、彼の骨格は骨盤がキュッと比較的狭く、胸板が厚いです。
逆に眠りが比較的長く、夢をよく見る人の首は比較的太いなど、生まれつきの骨格によって睡眠の性質が異なります。
骨格タイプや体でよく使う箇所や疲労しやすい部位などで、体に合う寝具は人それぞれですが、どの骨格タイプでも共通して〈就寝中に作用する体の状態やポイント〉についてまとめていきます。

【疲れを緩める眠りとは】
その日の疲れはその日の眠りで解消するのが一番の理想です。
眠っている間に体はどのようにして疲れをとっているのか、改めて考えると結構あいまいです。
疲れがあるということは、〈身体のどこかに偏った緊張状態がある→背骨や骨盤のどこかが動きにくくなっている〉ということです。
どこかの動きが鈍くなっていてもその分、呼吸は制限されます。
眠りにはそれ自体、呼吸を深くして骨盤や背骨をやわらかく動かし、〈緊張して固まっているところ=疲れが残っているところ〉をほぐしていくという「自動マッサージ」のような効果があります。
疲れがある程度あっても、眠りの中で呼吸を深くし、呼吸そのものによって緩めていくことができる。
それで疲れがとれるわけです。
呼吸に合わせて骨盤が膨らんだり縮んだりしながら、体にたまった疲れ・緊張を緩めることで、体が回復していきます。
寝相というのは、一番疲れているところを緩めようとするはたらきのことで、ゆるむために体が自然とその体勢を選んでいます。
ところが疲れが慢性化して固定化され、凝り固まりすぎていると、呼吸が大きくなろうとする動きそのものを邪魔してしまう。
そうなってしまうと〈深い呼吸をする〉ことができなくなり、眠りそのものも浅くなってしまう。
それは同時に、疲れがとれないということでもあるわけです。
呼吸と眠りを深くするためには、凝り固まった疲れをある程度、眠りにつく前にはほぐしておく必要がある。
現代は〈全身疲労〉よりも〈部分疲労〉しやすいです。
凝り固まった疲れをそのままにしておくと、眠りの間に緩みやすいところは緩んで、凝り固まっているところはさらに凝るという、緩みと凝りのアンバランスが生じてきます。
凝りと緩みのアンバランスが生じる睡眠よりも、できるだけ疲れをほぐす自動マッサージのような睡眠ですごためにも、寝る前の体に肩や腰など部分疲労が溜まりすぎてないかどうか、体に意識を向けてあげることが大切です。
【睡眠に大切な自律神経】
睡眠時になるべく副交感神経が優位になるように、自律神経そのものに触れてケアすることはできませんが、手で触れるこことで、間接的に交感神経を緩めやすく、ケアしやすいのが「目」になります。
《目の緊張の持続=疲れ》は交感神経の興奮状態とイコールなので、目の緊張が続いている限り、交感神経が休まらない。
このような疲れは、自律神経のバランスを不安定にします。
そして目の疲れ、眼球の疲れは頭の疲れとセットになります。
目のケアをすることは目を労わるだけでなく、頭の疲れや交感神経の緊張を緩めてくれて、
1日の終わりに行う目のケアは、その日の疲れを緩めると同時に、その後の睡眠の質へとつながっていきます。
日中のアイケアでは時々目線を下にすることで、交感神経の緊張を緩めてくれます。
【定期的に体の声を聴く】
日常生活や仕事ではどんな動作が多く、体の部位でよく使うところや疲労が溜まりやすいところはどこか。
日中どんな道具を普段使っていて、それによって体に負担が多くかかっているところはどこで、それに対して定期的に行っているケアは何か。
そういったケアするところが明確であれば、普段から体からでてくる反応や体の声をひろいやすいですし、逆にこれらがあいまいであれば、まだまだ体と仲良くなれる伸びしろがあるということでもあります。
生理がある方は、生理のリズム(骨盤の開閉リズムは頭蓋骨の開閉のリズムにもつながります)にできるだけ合わせたスケジュールを組むことも大切になります。
心身の作用で観ると、《意識→体》よりも《体→意識》からのアプローチの方が変化を促しやすいので、疲れのたまりやすいところをケアして、疲労感・不快感が軽くなったと感じられれば、その分気持ちもラクになります。
【深い睡眠へ誘うセルフケア】
①ゆるゆる・もぞもぞ体操
体幹部は痛みを起こしていなくても、筋肉が縮んで固まっているだけで精神的に不快な状態になっています。
人間の精神状態の一番根底にあるのは快・不快であり、その快感神経は脳幹から出発しており、脳幹の状態がどうなっているかということが、結局快感・不快感をつくりだしています。
そして脳幹は体幹の状態によって左右されています。
私たちは実験でこれを確かめました。
体幹の中をもっとも単純にゆする運動、つまり魚と同じような運動をすると、体幹内の筋肉がよく使われてきわめて劇的に副交感神経が優位になることが実証されたのです。
ゆるゆる・もぞもぞ体操のやり方はとてもシンプルで、仰向けになって魚が水中で泳いでいる動きを腰や肩を緩ませながら脱力するように行います。
*首・肩・背骨・腰などに痛みのある方は、無理ぜずに行ってください。
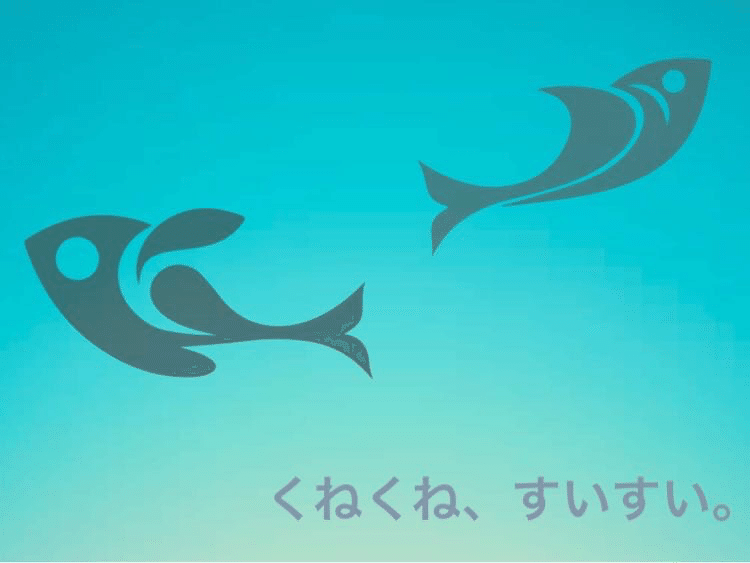
人間の脳は3層構造となっていて、脊椎と接した最も奥深い部位を脳幹といい、中間部位は旧皮質(古皮質・大脳辺縁系)、そのひとつ外側を新皮質といいます。
ざっくり大まかにわけると脳幹・旧皮質は本能の働きを司っており、特にヒトに著しく発達した新皮質は知的思考などの機能をになっています。
情報社会においては処理する情報量が多く、現代によく見られる動作として、目を通して取り入れた情報を処理するのに頭部が前に傾いている状態です。
この状態が続くと頭部と首に緊張がでてきて、背中あたりでは肩甲骨が前にいきやすくなり、それにつられて背中が丸くなるのと同時に呼吸が浅くなります。
魚のような動きのゆるゆる・もぞもぞ体操は、脳幹を軸にした背中・肩・頭など日中にたまった疲れやコリを解消・リセットをするのと同時に、呼吸が慢性的に浅くならないようにするためにもおススメです。
もし背骨全体で行うのが難しければ、頭・肩・腰と各エリアを順番に揺らします。
②温活
お手頃で手間のかからないものが、小豆カイロや玄米カイロです。
目の緊張・興奮と関連して耳の筋肉も働いているので、目の緊張はそのまま耳の緊張につながります。なので目だけでなく耳を温めるのもおススメです。(首も同様です。)
首・肩用の大きいサイズのカイロですと、首と同時に耳まわりや食いしばりで緊張しやすい咀嚼筋周りを温めることができます。
なので緊張しやすいところを同時に温めることができて、緩む感覚が深まりやすくなります。
他には湯船につかるとき、お湯に浸したタオルを首に置いたり耳にあてると同様に緊張がほどけやすくなります。
③背骨や骨盤を整えるストレッチ等
寝るまでにその日の背中や腰の疲れやコリを軽くしたり整えることで、睡眠中の呼吸に合った動きをしてくれる背中や骨盤になりやすく、その分睡眠が深くなり疲れもとれやすくなります。
いろんなエクササイズやストレッチがあるので、〈①背骨を伸ばす②骨盤や股関節を整える〉ストレッチやポーズを、やりやすく続けやすいをポイントにまずは各1つづつ見つけます。
私が息も体温も上がることなく、すぐできてつづけられているポーズは、ピラティスの⑴スワン・プレップ⑵バック・エクステンション⑶レッグ・サークル⑷サイド・キックです。
⑴⑵は背骨、⑶⑷は骨盤や股関節周りを整えます。
うつ伏せや横向きからほぼワンアクションでできます。
【1日の約1/3は寝具に身を委ねた、ある意味放置状態の時間】

身体的に睡眠をみると、体が自動的マッサージのようになって疲労回復する質の良い睡眠は、ある程度コントロール可能だと思えてきます。
布団やベッドに入って目をつむると、そこから約8時間前後はほぼ体の自発性(呼吸や寝相)に委ねることになります。
目をつむるまでの間に5~10分ほど、部分疲労の解消や背骨・骨盤を整えて、スムーズに体の自発性機能にバトンタッチできるケアは、睡眠の質が高まりやすく日中の体の快適さにもつながります。
脳幹・体幹と連なる背骨は、〈首あたりの頸椎・胸や肩あたりの胸椎・腰あたりの腰椎・そして仙骨・尾骨〉で構成されています。
背骨は姿勢だけでなく、①脳から続く脊髄という神経の束を保護しながら、②筋肉や皮膚につながる神経の出入り口を作る役目もあります。
そしてその神経の先には内臓や各器官につながっているので、身体機能にもつながっていきます。
コリだけでみるとその部位だけに症状があると思いがちですが、背骨に慢性的な緊張やコリがある状態は、神経や体のつながりで長期的にみると、少しずつ他の機能を弱める可能性が出てきます。
過去に経験した神経の痛みで、20代前半に帯状疱疹になった5年後に同じようなピリッとした痛みを感じたので、皮膚科で診てもらいました。
帯状疱疹は1度かかると、数年単位で繰り返しはしないといわれ、痛み専門の病院へ紹介状を書いてもらい、紹介先の病院で肋間神経痛と診断されました。
神経痛なので、神経そのものが発症原因かといえばそうではなく、慢性疲労や腕の使い過ぎで前屈姿勢になると、肩甲骨あたりの胸椎3・4番から力が抜けていき、肩甲骨と肋骨についている前鋸筋が硬直します。
次に肋骨筋も硬直すると、肋骨周辺の血管やリンパ節が圧迫され、最終的に肋間神経痛として痛みが発症します。
痛みを感じたのは体の前面ですが、痛みの発症元は背面でした。
このようにはじめは1か所だけの疲労やコリの蓄積が、長期的にみると少しずつ他の箇所に連鎖していきます。
なので部分疲労により疲労が慢性的に蓄積しないように、そして睡眠の質が悪くならないためにも、部分疲労に対する定期的なケアが大切になってきます。
寝ている間に体の自発性に任せて、疲れをとってくれるような自動マッサージのような身体で、心身を回復する眠り。
そんな状態が睡眠時間である1日の約1/3を占めてくれるよう、できる日は5分ほどでもケアをすることをおススメします。
寝起きの体が気持ち良く感じるようになると、ケアしようからケアしたいに体が自然と反応してくれます。(完)
【参考資料】
①自分で「疲れを」とる!日々の整体(片山洋次郎/静山社)
②内臓力を高める「ゆる」呼吸法~病気にならない身体をつくる~(高岡英夫/ベスト新書)
③背骨の実学~痛みと不調を根本から改善する~(石垣英俊/池田書店)
めす子
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
