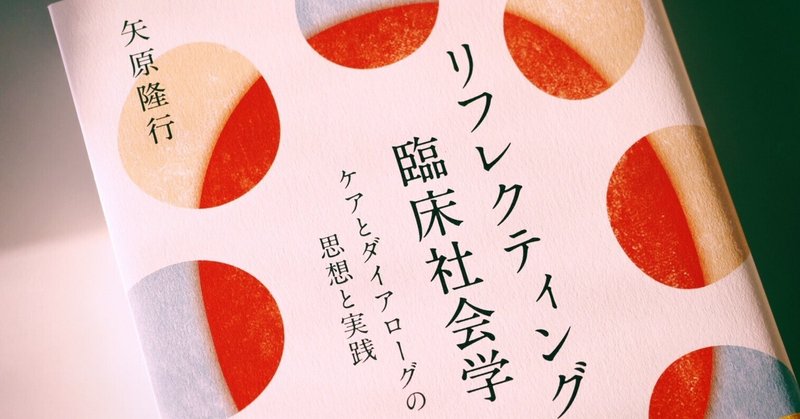
矢原文学とロゴスとレンマ
「矢原文学は」とか、「矢原さんの文章は」という声を聞くときがある。
なかなか一筋縄ではいかないという意味を含んでいるのか。
私は会読会で「嘯く」という漢字が読めなかった。否、見たことがなかったのだ。 たとえ過去に見ていてたとしても阿頼耶には沈着していなかったのだ。
見たことがない、阿頼耶に存在しないということは当然読むことができないし、そこに意味を見出すこともできない。そこにあるのだけれども無いに等しい。そして参加者の方に読みを教えて貰う事で、その読み(音)から見えていなかったものを見たように思う。
本来見えないもの。また言語表現しえないもの。レンマ的存在を、「レンマという言葉」や「レンマ的知性」を使わずに、「ロゴスという言葉」と「ロゴス的知性」で表すことは、シュタイナーの「自由の哲学」という本の在り方に免疫がありまた馴染みがある。
言語化し得ないもの(lemmma)を、あえて言葉(logos)を使って伝える。
言葉で編まれて形あるものとして、見ることの出来る完成した本ではなく、書き手と読み手という糸で編んでゆく。 そしてその縦糸も横糸も、唯一ではなく多種多様な糸が、ズレたり重なったりして共に生きゆく中で編まれ続けていく。
読み手も我一人ではなく、会読という場で様々な声があがり、耳にし自内へ受け容れ内観する。
書き手と多様な読み手の内と外で編まれていく「糸」に目を奪われそうになるが、その糸と糸の「間(あわい)」に存する「空」も編み物を織りなしていることに気づき誘われ、更には糸と糸の「空なる間(あわい)」から向こう側(純粋レンマの世界)を眺め得ることは、唯識の四分の教えや、大乗起信論が思い起こされる。
説一切有部(釈迦が言ったこと)のみにとらわれないで、つまり釈迦が言っていないことにも意味を見出し意味を深めていった大乗の如きである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
