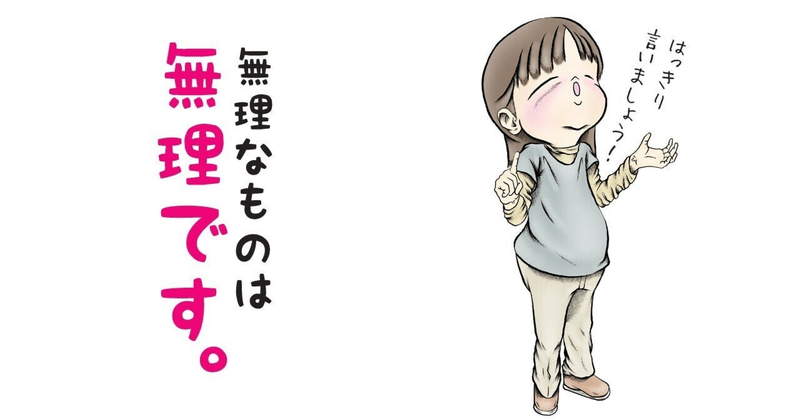
日本海側の風力発電の運転開始時期を決める難しさ
日本海側の風力発電所は、洋上でも陸上でも輸送・建設工程のやりくりがけっこう難しいというのは「常識」だと思っていました。ところが、ラウンド2を落札した事業者の計画が公表され、日本海側の制約を全く分かっていない事業者が選ばれていることが発覚しました。
日本海側では、季節変動が大きく、3月中旬~11月中旬の約7か月間で建設を終わらせることができなければ越年するリスクがあります。日本海側における季節変動要素は、以下の3点です。
強すぎる季節風
高すぎる冬の波
吹き付ける冬の雪
強すぎる季節風
労働安全衛生法では、悪天候の条件に、「10分間の平均風速が毎秒10メートル以上」という規定があります。この条件下では、日本ではクレーン作業を中断するのが一般的です。日本海側では、12月から3月にかけて、この悪天候に当てはまるような季節風が吹きつけます。

「風が強いから風車を建てたいのに、風が強すぎて風車を建てられない」という風力発電のよくあるパラドックスです。
「風車を建てられないなら、この期間中に輸送だけでもできないか?」と思うかもしれませんが、そもそもクレーン作業を中断するぐらいの天候ですから、荷下ろしすらままなりません。
高すぎる冬の波
季節風が吹きつける冬の日本海は、当然しけます。有義波高が2mを超える日が続くようなところもあります。防波堤が小さい港では、有義波高0.5m程度まで下がらないと、港に近づくことすらできません。

有義波高という言葉に慣れていない人のために、有義波高2mの波が、どれだけ厳しいかをイメージしていただこうと思います。トランポリンでゆっくりジャンプしている様子をイメージしてください。

有義波高2mの波に乗った状態をイメージするとしたら、トランポリンで平均2.7mぐらいのジャンプを繰り返しているよう感じでしょう。船が大きければ、そのままの波を体感することはありませんが、千トンくらいの小さい船なら、それに近い状況になります。船になれていない人は、有義波高0.5mぐらいでも船酔いし始め、1mで起きていられないほどの船酔いに襲われます。
ここまでお読みいただければ、洋上輸送や洋上工事に関わる人ならば、有義波高の知識は必要だとおわかりいただけるかと思います。建設会社にとっては当たり前の話ですが、日本で陸上風力発電所の実績のない発電事業者の中には、有義波高の知識を持たずに輸送や工事を計画しているところも見受けられます。これぞまさしく絵に描いた餅です。
吹き付ける冬の雪
日本海側は吹き付ける季節風に伴い、横殴りの吹雪になります。陸上風力では、「日本海側の風車は、11月中に建てきれ!」というのが、現場の常識になっています。

上記3つの条件が重なると、どんなことになるのか、てってりばやくお分かりいただくには、以下の動画をご覧ください。
再エネ海域利用法との兼ね合い
秋田港洋上風力発電所は、2021年から2022年にかけて洋上工事が行われています。基礎工事に1年、風車工事に1年を要しています。
ラウンド1の公募入札では、能代市・三種町・男鹿市沖と由利本荘市沖が、日本海側です。特に占有海域が広く、風車の本数もダントツに多い由利本荘市沖は、基礎工事に2年、風車工事も下手すると2年を要するかもしれません。そう考えると、あながち2030年12月の運転開始時期が遅いとは言えません。
それにもかかわらず、ラウンド1では遅い事業者が選ばれたことが問題視され、入札ルールが変更されました。その結果、迅速性(早期運転開始)という新しい評価項目が追加されました。
ラウンド2では、4海域すべてにおいて運転開始時期の最も早い事業者が落札しました。しかし、前回の記事で解説したように、公募の選考事務局は、迅速性(運転開始時期)に実現性・妥当性のない事業者も選出しました。
風力業界の中の人として、こんな惨状を黙ってみていられません。洋上風力ラウンド3以降のために、日本海側の難しさを理解せずに計画を立てる無邪気な事業者とそれを見抜けないお粗末な選考事務局への入れ知恵、および規制当局である経済産業省の電気安全課へのお願いを、以下に示します。
日本海側の厳しい気象条件への対応
日本海側の厳しい気象条件に対応するために、まず事業者と選考事務局がすべき最低限の波浪情報の確認方法から解説します。
事業者も選考事務局も波浪情報を踏まえて輸送・工事計画を確認
事業者であれば、サイト近傍の波浪情報を調べるのは、当然です。サイト近傍の波浪情報が入手できていない場合は、とりあえずナウファスで過去10年分以上の最寄りの観測点の波浪情報をダウンロードしてExcelで稼働日数を試算することができます。

SEP船の作業限界を有義波高1.5m、起重機船の作業限界を有義波高0.5mとして、日中で作業限界以下の有義波高になる時間が6時間以上ある日を稼働可能日として見なして、月別の稼働可能日数を試算することができます。(実際には作業内容によって必要時間は異なりますが、概算のため6時間以上と想定)
下表は、村上胎内沖を想定して新潟港のナウファスから試算した月別稼働可能日数です。

(S)はSEP船、(起)は起重機船の稼働日数です。ナウファスには観測ブイの故障などによるデータ欠損があります。表中の「有効日数」は、2012年~2021年の10年分の波浪情報からデータ欠損日を除いた有効観測日数です。表中の「稼働日数」は、有効日数を考慮した2012年~2021年の10年間における稼働可能日の平均日数です。
SEP船は、有義波高2mでも作業可能です。ただし、一般的にサイトの波高と風速は追随します。有義波高2mの日は、風速がクレーン作業限界に達することが多いため、SEP船の作業限界を有義波高1.5mと想定しました。

上記のようなサイトの月別稼働日数を確認してはじめて現実的な輸送・建設のスケジュールを立てることができます。このため、事業者も選考事務局も現地の波浪情報に基づく月別稼働日数の確認は必須と心得ていただきたいです。
運転開始時期を段階的に分けられないのか?
風力発電所の風車は地中に埋設された送電線で数珠つなぎされています。ただし、送電線の容量の兼ね合いで、数珠つなぎできる風車の数が決まっています。この数珠つなぎのことを、「路線」と呼ぶこともあります。例えば、30基の計画の風力発電所で、風車を6基まで数珠つなぎできるとすると、数珠つなぎの数は5本、つまり、5路線ということになります。
物理的には、路線ごとに運転開始時期を分けるということは可能です。現に、海外の風力発電所では、そのような事例があります。建設可能期間が短く、遅延時の越年リスクのある日本海側では、なおさらそうしたいことでしょう。
ところが、ここに立ちはだかるのが、昭和の火力発電所を前提とした「使用前自主検査」です。この規制が、路線ごとの段階的な運転開始ができない理由の一つです。

デジタル制御された風力発電機に対する現場での絶縁耐力試験、定格風速の強風が必要な4/4負荷遮断試験など、昭和のアナログ規制を課し続けることで、ただでさえ気候条件が厳しく輸送・建設可能時期の制約が大きい日本海側の洋上風力がより一層、難しくなっています。
日本の洋上風力の適地は、日本海側に多いです。規制当局には、日本のエネルギー自給率向上という国益を勘案して、現代の洋上風力に合わない昭和の規制を緩和していただきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
