
~2021・5・12牡牛座新月に寄せて~
DroppingMellow / vol.3

音はバイブレーションだ。バイブレーションは感情と共にある時にこそ最大限に発揮される。言葉は逆に、感情から少しだけ意識的に離れインスピレーションとして受け取ろうという方向に意識を向ける時、電気的な知性として受け取り変換される。そこはやはり感情は薄い、希薄で、最も大切なところから少し逃げているような気分にもなる。だからいつも言葉に変換する時には、感情そのものが最も言いたいことは伝えることができない。言葉にならない想い、というのはその変換作業のシステムにあるのだと思う。少しだけ離れているもの、違うものだという認識をしていること、それでもそれら二つをいつでも繋いでいるものがあるとすれば、それは肉体であり、身体である。今という時間に生きているという事実だけ。肉体を通じててあれば感情は表現されることが可能なのだ。
言葉にりえない想い、と表現するのはわたしが言葉側だからだろう。これを音の側面から捉えると、表現しえない感情、ということになるのではないだろうか。その距離を温めることができるのならば、それはいつか空間になり、円い宇宙みたいなものが生まれる。説明するための言葉というものはこの宇宙には存在し得なかったはずなのだということも、わたしは夢見の仕事をすればするほどに気付いていった。空間を共有できて、その空間自体が生み出すための母体なのではないか、と。それでは、バイブレーションであるあまりにも分厚い感情フィールドでもある音と、言葉が共あった時のことまで遡れば、それは一体どんな感覚がするものなのだろうか、と想いを馳せる。広大すぎて目眩がする。肉体に戻りたくなる衝動に駆られえるほど広大で自由。戻らなければならない、というのも何となく規制を科しているように思う。戻らなくても良いのかも知れないけれど。「今」とか「現実」にドサッと落ちる。そうするともう想いや夢からは遠ざかってしまう。肉体があるが故に出来ることと、肉体があるが故に毎度「ああ、やっぱ夢は夢よね」と何だか気持ちが冷めてしまうような、そういう連続は結構しんどいものだ。
胸の奥に響き残ったままのその声は、ふいに何かの拍子に蘇っては、わたしを渦中に引き込んだ。それは正しくは、わたしが「もう少し先が聞きたい」と願っているからに違いないわけだけれども。冷静ではいられなくなる、ということはわたしにとってはイコール「危機」だ。何の危機か・・。今までのわたしを保てなくなる危機。何かを認めなければならない、という危機。日々、危機に曝されていたようなことがあったに違いない。
星の子と逸れてしまっていたその頃、わたしはわたしが感じること全てに「今までに経験した全ての感覚」を見出し続けた。どこか遠い昔のタイムラインで「危機」を繰り返し「危機」を恐ろしいと感じたままになっている、そこで止まったままの記憶があると理解した。一つずつ理解してゆくしかなかった。そして、できるだけゆっくりと時間をかけて解放していった。あまりにも細かな、あまりにも膨大な量のそれらと対峙し続けた。
声とは言っても、それは音そのもののようなもので、それを言葉に変換し声として受け取ったのはわたしだということにも夢の中で、はっきりと気付いていた。何せわたしの仕事だから、性分だから仕方がない。無意識でやっていることでもあるし、意識を完全に絞っているとも言える。
広大なものに微少なものも含まれている。微少なものもまた広大なものに含まれている。概念だけがわたしを支える。
「だから大丈夫だって・・」と言い聞かせる。一度そこにはまってみたら思うほど怖くはないはず。うまくやろうとするから怖い。未知が怖いのはうまくやろうとするからだよ。既知も未知も共にあって普段なら気にも留めないようなことでしょ。それと同じ。ただ気づいてしまった…というところが決定的に今までとは違うだけ。それは、いい匂いのする何かでしょう。腐敗ではなく、健やかに発酵してゆくような何かでしょう。その真ん中にいるから、その過程の両極を見つめているから時々怖くなるだけ。だから大丈夫だって。
何でもない普通の言葉であれば口に出して言うことができるのに・・と不甲斐なく思う。これだけリアルにあまりにも個人的な夢と現実を体験しているのに出てくる言葉は、そんな何でもない在り来りな、あっけらかんとして何も考えてやしないように映る、そんなものだったりすることが不甲斐ない。

わたしが人生初書いた物語のタイトルは「DroppingMellow」という。良いタイトルだと今でも思う。
オアシスの“Half the World Away”を爆音で聴きながら書いた。
・・・I would like to leave this city
この街から出て行きたいな
This old town don't smell too pretty and
古くて、いい匂いがぜんぜんしないし・・・
「DroppingMellow」に出てくる登場人物たちは全員揃いも揃って「生きたいような人生をハチャメチャに生きる、その為なら何でもする」人たちだった。単純にその頃のわたしがそう心から望んでいたから、出てくる人すべてがそういう種類の人たちだったのだ。そして何故だかわたしはその物語を書いている最中に「あ、この人たちと近々会うことになるんだわ。」と深く納得していった。書けば書くほど、リアルに肌で感じるようにその世界を歩いているかのように、そして直感という言葉では足りない核心へと近づいていった。それまさにわたしが、物語を書くことで自分の望む人生を先に構築してしまえ、という方法に気付いた瞬間でもあった。わだかまりがないことならば、そして、対象が自分だけのことであれば何でもある程度のところまでゆける。ある日突然「書ける」と思い込んで早朝に書き始め、翌日の早朝に書き上げた人生初のその物語は、あまりにもその後のわたしの人生に大きく関わるようになってしまった。素人がある朝突然「自分は作家なのだわ。」と脈略もなく理由もなく目醒め、そして嘘みたいな話だが、小さなしかし格調高い賞を貰うまでに至った。嘘みたいな本当の話だけれど、一夜のノリで書いたものだけあって決定的な欠落を欠落と認識していない状態の時に起きる一時的な喜びみたいなものを表現出来ていたのかも知れない。束の間の間ではあるけれど、自分が自分になっている状態、その瞬間にサッと動き書き始めたこと、そのことについてわたしは過去のわたしに感謝している。「ここからの道が本番で、君は時々この感覚を完全に忘れる時期もあるし、地獄を垣間見ることもあるよ、でもその完全完璧に満たされている感覚を覚えておいて…。」と声をかけてやりたい。そんなことは叶わないけれども。そして、あの瞬間に動いてくれた直感と体、それは本能として魂を生かすための力動だったのだなと今なら理解できる。
何をしてるのか分かっていないことをしている時、それはいずれにせよ時を経てしわ寄せとして濃度の濃くなった体験をすることになる。本人が気づくまで続く。気づかせるように世界の仕組みがなっているのか、気づきたいから本人が似たような傾向の選択をし続けるのか…鶏が先か卵が先か、だ。物語が先にあり、その物語のトーンに似た現実世界に肉体を曝しながら追体験し生きてゆく。さらにその様子を遠巻きに見つめることができるビューポイントがある、と気付く。自分のためだけにこういう方法を取っていると、いつしか身も心も枯れ果てる。自分のためにだけ何か事が起きるなんていうのは妄想で、事を望んだ時点ですでに元に戻れないものも存在しているということを理解した上で、繊細に動かす必要もある。微生物の種が1つ絶滅したとしても誰も気に留めないけれど、それは思っている以上に大きく余波を残す、というのに似ている。こういう類のことをやっている人は世の中にどれくらい存在するのだろうか。過去の中も歩くことができる、未来がある程度決定しているのならば予め書き記し、ただ知っておくことはできる。いくつかは絶対的に変更できないものもある。それは取り組まねばならない課題なので、物語を書き進めてゆくなかでは決してアイデアとしては浮かんでこない。誰がその変更できない出来事を決めているのかは知らないけれど、明らかにそういう種類の「出来事」は存在している。声の件は、明らかにこの種類の出来事に属しているなあということには気付いている。
「ハチャメチャに生きる、なんてコンセプトを掲げたが為だな」
と今さら思うけれど仕方がない。生きることに心底飽きた人たちに向けたものを書きたかったし、今もそう思うのである意味一貫して揺るがず・・なのだ。
人ってそんな変わらないものだ。
ところで最初の物語が齎した最も驚くべきことは、物語のなかの登場人物である「矢島」と「恭造」という名の友人を物語を書き終えた直後に現実世界で出会ったことだ。コンセプトどおりだ。そこで「書く」ということって何だろう、と考察を深めずに案の定ただ遊びに没頭してゆき、自分自身のための物語を書くことなど簡単に手放し、個人的な依頼として個人的にその人のための物語りを書く、というコンセプトを掲げたオーダー小説家の道を選んだわたしは馬鹿だったかも知れない。あの遊びの最中に自分自身を徹底的に掘り下げて書くということを連動していれば、もっと早くに今現在のわたしくらいのスキルには至っていたかも知れない。オーダーメイドなんて格好をつけてはいたけれど所詮真摯に取り組む気がなかった、お遊びの子供だましのようなことをしていたと今ならば思う。
軌道円の一番外れから真ん中に向かって進む癖がある・・と気付くまでに何十年も費やすなんて。誰かの為に物語りをひとつ書き終えるたびに円の真ん中に辿り付いては、そこには小さな穴だけが存在していることを知り絶望し、また円の一番外側へと弾き飛ばされることも理解した。いつになれどその穴に何か新しい望むもの見つけることはなかった。こんなもんか、と高をくくって、いつでもつまらない顔をして生きた。書くことは楽しい、最高に楽しい。それでもゴールに求めているものは一向に姿を現さなかった。そのうち自分が何を求めているのかなんてどうでも良くなった。それはただの慣れだった。「どうせ何もない、どうせ誰とも完璧にひとつにはなれない。」そんな事実を受け入れるためだけに書き続ける。一人でも強く生きてゆく術が物語りを書き続けることであるなら、それをするしかない。その頃のわたしは小生意気にそんなふうに思っていた。
過去のわたしは今のわたしを振り返りニタニタ笑いながらこう言うだろう。
「分かったようなことを言うなよ。どうせ何もないってことを見つめ続けてきたんじゃなかったの。それなのに何を今更。欲するって何。望むって何。何もないんだよここには。それでも、あなたが今何か欲してるというならさ、それをわたしに教えてよ。何もないんじゃなかったの。ねえ。」
ハチャメチャに生きる時代は過ぎ、どれだけ進めど何もないとしてもという事実を受け入れながら、結局、わたしはやっぱり「物語」を書くことに戻った。闇雲に自分の進みたい未来のためだけに書くことを止め、誰かの為に書くようなふりをしながら、「何もないということに含まれる何かがある」と信じたいと青くさくいつまでも願ってやまないわたしが剥き出しの骨になったまま風化して風に舞い踊っているような気持ちではあったけれど、そんなあり様でも少しずつ少しずつわたしは強くなってゆけた。願いが人を強くする。無があるということを知っておくことは肝心なことだけれど、無は何も生み出しはしない。無の中から何か生み出される瞬間を目撃したい、という希望は簡単には消え失せることのない炎のような情熱を宿している。生きることを諦めさせない強さを保持している。自分を取り戻すための力を毎秒毎秒焚き付ける力動。自分に戻るしかないし、自分であることはどう足掻いても止められないし、わたしという物語にどれほど魅力的な人物が登場したとて、そしてそのような人物と実際に出会ったとしても、結局その人も自分自身であることを止められないように、わたしと全く同じ人ではないのだ・・という境地にたどり着く。そんな「当たり前」みたいに言われていることを身を削って確かめようとする人をわたしは愛するのだと思う。馬鹿みたいな、夢みたいなことに躍起になって、自分にしかできないだろうと本人だけが確信している方法でもって自分自身の全部を注ぎ込んで「わたしは一人である」ということを自らに突きつけ、不安になってそれでもまた飽くことなくその真実を自分自身にだけ突きつけることができる人を愛したい。「自分を愛する」という言葉には正直吐き気をもよおすけれど「一言で言ってよ」と言われたら「ただ愛するだけだよ」とわたしも言うだろう。
「誰かが言った、自分自身を愛するという言葉に唾を吐いている暇があるなら、心から愛してたらいいよ。自分のことも人のことも世界のことも。」

なんつって言葉ではいくらでも言える。現実はそんなわけはなく、落ち込み、ただ亡霊みたいに漂い夜の街をフラフラと歩くしかないような日もある、行く宛てのない散文をノートにただ書き綴る日もある。そしてその宛てのない言葉を捨てることすら出来ず、後生大事に誰にもバレないように懐にしまい込む。とてもダサい。往生際が悪い。
煮詰まるとスケボーに乗り街を流す。公設市場の細い道も通り抜ける。知り合いの刺身屋のお兄さんに挨拶をして世間話をする。景色が移り行く。迷惑そうな顔をする人、珍しいものを見るような目で見る人、一向に気にしない人、いろいろだ。色々いるとわたしもその一部であることが理解できる。溶け込めば一時ではあるけれど「一人である」ことを忘れられる・・何だろう、お酒を大量に飲んだ時みたいに、痛みを忘れられるのと同じように。街っていうのはそういう機能も果たしていたりして偉大だと思う。神聖な場所の周囲には俗な色町が意図的に作られてバランスを保っているのと同じように。混ざり合いようやくバランスを取っている。どちらがより立派、良い悪い、とかではないバランス。しかし世の中では神聖な場所だけが崇められる傾向はある。それと同じく「崇高なもの」「知性的なもの」「美しいもの」だけを見ようとする傾向もある。そしてほとんどの人が綺麗になりたがる。邪や俗に対して無理矢理「美」をこじつけるという厄介なことまでしてしまう。
「本当に人間とは忙しないね。何て大変な仕組みなのだろうか。でもそのデザインだからこそ出来ることがあるよね。泣くとか笑うとか愛するとか。」
星の子ならばそう言うだろう。
わたしが言うと
「両方あって生きてるってことでしょ」
になる。情緒も色気もない。すまない気がするほどだ。
「アイ!どうした!マブイ落とした顔してるよ!兎に角、天麩羅持って帰りなさい。食べて元気出さんと!」
夏の繁盛期に時々手伝いにゆく民謡酒場のまえを通りがかったら丁度ママがお店の象徴でもあるブーゲンビリアを剪定していた。
わたしの顔をじっと見てママは言った。
「ひどい顔だ。」
昨夜のメイクのマスカラを落とし切れていない人に言われたくはないのだが。
民謡が大音量で街路に流れ出している。この街の人は爆音が好きなのだ。わたしもそうなのでとても都合がよい。
「ママよー、争いは何故なくならない?」
わたしの声は日に日に擦れ気味になっていた。自分でも気付いていた。いつの日か本当に声が出なくなっても文章さえ書ければ別にいいか・・みたいなことまで考え始めていた。言いたいことなんてそんなにないし「わたしが求めてやまないのは、ただそれだけ」といつか伝えられたら別にそれでもいいか、とか。内容がないわりに伝えたい台詞だけは明確で、投げやりなのか真実なのかそれすらどうでもよくなっていた。
「お前が争いを選んでいるかぎり争いはなくならないよ。当たり前さ。」
明確すぎて眩暈がするぜ。
イラブチャーとアーサの天麩羅を無理矢理手渡された。
「元気になったらまた来い。新しいカラオケと、お前が好きなテキーラも入れたから。」
「いや今はテキーラは飲めないよ。ところでママこの自販機いつになったら直すのよ。もうすぐ夏だから売れるのに。」
「蹴ってみな。出てくるかも知れないよ。ちょっと渇を入れないといけないんじゃないのか、お前も。ぼんやりしているにもほどがある。」
とママが言うので、むしゃくしゃした気分も晴れそうだし、何せ自販機のオーナーが蹴って良いと承諾しているのだから・・と蹴飛ばした。
ゴロン・・と音を立ててコーラが転がり出た。ボディブローが効いたらしい。
「嘘、マジか。」
笑いたいような怖いような気分だった。
「ママ・・出てきたよ、コーラ。」
「持ってけ。」
「ママ、またね。」
と手を振って別れた。ぬるいコーラをポケットに入れた。また近いうちに会えて話ができる確証のある別れはいいな・・と何故だか思った。それが叶えばなあ、と思うと涙が零れそうになった。意味不明の涙だ。切実な、お腹の底から湧いて出てくるような涙。そしてふと思った。
あ、これ、わたしの涙じゃないな・・と。わたしの涙も含まれるけれど、それだけじゃない、何か。含有し含有されている時に感じる涙。そういう種類の涙。
ヘッドフォンからHipHopが流れ始め、またスケボーを漕ぎ出す。昔の文豪は書くことに詰まるとよく散歩をしたらしいけれど、わたしはスケボー派だ。音楽との相性が良いから。そしてこれは口に出しては決して言わない言葉なのだけれど「どうでも良い」を満喫できるから。わたしが思う「どうでも良い」は「どうなっても良い」に近い。だから口に出して言うことはしない。まだやり終えていないことがあるから。
さっきのママとの会話を吟味する。吟味することは大切だ。どんな些細な出来事にも出口を見出したかった。ただの必死な人だ。クールでも何でもない。
「元気になったらまた来い」というのはつまり亡霊みたいなお前に今は用がない、ということだ。それくらいシビアでないと生きてゆけない時代を生き抜いてきたママらしい言葉だった。これがリアルだ。優しさも慰めもないようなところに癒しは訪れる。
「真実だ。」
声は風に乗って街へと消えてゆく。
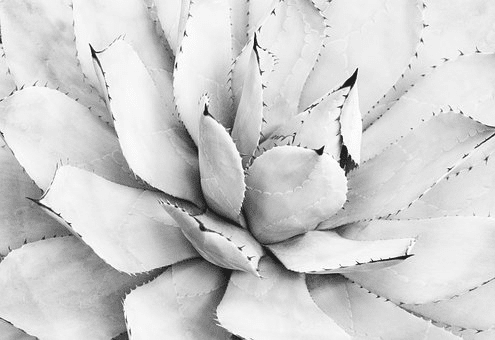
「愛って何すかね。」
とボヤキながら事務所への階段を上る。茹だるような暑さだ。
一階のインドカレー屋のドアが開いていたので覗きこんでナンの生地を仕込んでいるネパール青年に「おはよ」と挨拶する。
「何でこの店、はやらない?あなた占い師、答え分かる。」と彼が言うのでわたしは答える。
「ネパール料理という看板を掲げればはやるよ。」と。
「ははは。正解です。」とネパール人が笑う。彼はとても聡明なのだ。
すべての料理は彼の手から生まれている、それなのにインド料理、それはないだろう。コンセプトのずれが、些細な歪みが破綻を齎す。彼はいずれ故郷に帰り、国にとって役立つ研究者になるだろう。彼の周りに漂う空気がそれを物語っている。
自分以外の人の為に物語を書くにつれわたしが深く学んだことは「その人と同化したらほぼ全てが理解できる」ということ。その人が放っているものに自分が溶けるような感覚。相手が心を開いていればいるほどその純度は高くなる。それから、その人が「わたしは一人であり、何とも比較にならないほど完璧な一人であり、わたしという一人の中に何人もの偏光する存在を有している」と知っていればいるほど、である。だから逆に言えば「誰かのような何か」を目指しすぎるが故に自分を見失っている、そしていつか探すことに疲れ果て自分が何者か分からなくなり、挙句の果てに「一人であること」を楽勝やってのけているように見える人間にたかり出しエネルギーを奪うだけの亡者に成り果てた人と相対すると「兎に角まずはその周りにくっついているモヤモヤから剥がしてゆきましょうか・・」というところから始めなくてはならない。だがしかし、そんなこともわたしは愛していた。何故なら、汚れに塗れたわたしも存在しているからそういう依頼が舞い込んでくるわけだ。セッションとはそういうものでしょう、と思う。白黒つけるためではなく、勝負などない、ただ見つめあう。互いが真摯でなければ成立しない。あまりにも綺麗な世界、整列で、怯えも恐れもない世界をわたしが本気で望んでいるならば、こんな仕事はそもそもしていないだろう。お姫様や王子様が登場したりする御伽みたいな綺麗な物語を書いて、会いたいような人たちだけに会って、自分自身のことは一切曝さず、邪魔なものは平気でその御伽を利用して排除し、或いは乗っ取り、現実を前にしたら不平不満ばかりを言い散らし、最後には死をちらつかせ、人を怯えさせたり、共感を得ようと躍起になる。
矢島と恭造に出会い遊び狂った時のような、そういうモードに入れば、嘘みたいにそれが叶ってしまうように。何をしてるのかまったくの無知であっても葛藤さえなければ、しわ寄せは必ずいつか来るが現実になる。自分が心から許したものに人は成れてしまう。
物語には作者にしか手に負えない魔法がかけられている。魔法の表面は「結果」という側面だけを見せてくれる。けれども興味深いことに、時々その「魔法の仕組み」の側面に愛を持って接しようとする人もいる。長い時間がかかるけれど、根気強く同じ熱量と愛を持って触れてくれたら奥のドアは音もなく静かに開くこともある。一人であることを知り尽くした人。一人であるということを愛しながら現実という矢面に立てる人。鍵はそれだけなのだ。
事務所の鍵を開け、業務用エアコンのスイッチを入れる。汗が引いてゆく。階下から油で唐辛子とカルダモンが焦がされる香りと共に、爆音でフェイ・ウォンが歌う「夢中人」が聞こえてくる。良い感じである。毎朝出勤してすぐに聞こえてくる音楽がインドのチープな音のディスコミュージックだと、どうも気分がチグハグになるのでネパール青年に無理矢理「恋する惑星」のサントラを手渡したのだ。「これを一日中爆音で流すと店が繁盛するよ」とか言って。相変わらずあまり繁盛していないけれど、前よりもお客さんの相が分厚くなっていることは確実だった。あの音楽が持つあの独特なニュアンスは、この街によく溶け込むのだ。インドのディスコミュージックよりかは。人に溶け込み、その人を理解しようと心から努めれば、驚くほど明確な答えを導き出すことができるのと同じく、街に溶け込むものをズレることなく提供したらそれは間違いようがなくひとつの方向性を示しはじめ、要は成功への流れを掴むことになる。小さな店は街のひとつのパーツである、それと同時に、小さな店の在り様そのものが街である。包含されているようで実は包含している。包含しているようで実は包含している。両方を理解できたらズレは生じない。大きなものに含まれている自分自身は理解できても、自分自身がその大きなものそのものを表現しているという可能性には人はなかなか目を開こうとしないものだ。影響を受けあっている、と言葉で説明しても、あなた自身がこのワールドの建築家なのだと言っても、たいてい人は目を伏せたまま「大きなものに含有された自分」を選択し続ける。はみだすことが怖いから。はみ出す前に手も足も止まってしまう。それは死ぬことへの本能的な恐れに似ているということをわたしは知っている。わたしはそう思う。認められなかった記憶が深ければ深いほど、求めるものが容易く手に入らないと知れば知るほど、その恐れは色濃くなる。いつしか影のほうでいいや、なんてことまで思う。死ぬくらいなら影でも何でも生きてたほうがマシだし・・。「マシ?マシなほうをいつまで選択しているつもりなの?」と。どこと比べてマシだよ?と。価値基準は何だ?どのあたりで価値基準を設定したのか?
わたしの場合はこうだ。保育園の頃、腰までの長さがあるストレートの髪を持つ先生がいた。女の子たちは皆、その髪に触れたがった。三つ編みにして遊んだり、櫛を通したり。お人形さん遊びのリアル版だ。ある日、わたしもその遊びに加わろうとしたところ、「あなたは触らないで。」そう言われたのだ。それがたぶん人生初の「拒絶」を学んだ瞬間だった。インパクトが強すぎて今でも忘れ得ない記憶になっている。こんな些細な記憶でも、その記憶のなかに佇んだまま恐怖の為に凍り付いている幼いころのわたしを夢見で尋ねてゆくと「愛されなければならないという幻想から追放され一度死んだような気持ちになった瞬間」に足止めを喰らったままになっていたりする。こういう種類のことを夢見で解きにゆくことは可能なのだ。「強烈なインパクトを食らわしてくれてありがとうよ。さらば忌まわしき思い出。」と図太くなった今のわたしは幼い頃のわたしをしっかりと抱きとめて相手を睨みつけて思うことすらできる。愛されているようで愛されていない、口では愛していると言いながら実は憎まれている、とか、お行儀の良い嘘をつかれればつかれるほど解くのは難解になる。心の底で一ミリも思ってもいないようなことを信じ込ませることほど残酷なものはない、というわたしの価値基準はそのあたりに一つ存在しているということを知り得たことも夢見での収穫だ。拒絶され、無理にでも愛されることを学んで、その嬉しくもない学びに対して忠実でいるつもりなのかわたしは・・そう考えるとマシを選んでいることがアホらしくなって、わたしはやっぱり結局ノソノソと足を引きずりながら、はみ出すほうを選ぶ。はみ出すときは怖いけれど、はみ出したほうへ、一歩足を踏み込んだほうへ必ず世界は彩られてゆく。
その様はまるで、白雪の上を走る馬車が通った後にできた轍に色がついてゆくようにわたしの目にはうつる。変化してゆく時はそういうものだ。だからいつでもそうして選んできたような気がする。原点に引き返して、アホらしくなり、そうだったそうだった、と納得し歩き始める。包含しているし、包含されているのだから、それならば優しくありたい、心の底から愛するとはどういうことなのか最後に一度経験しておきたい。
馬は走る。轍は一瞬虹色に色づく。鉛色の空から雪は絶え間なく降り続ける。
「ミイラ取りがミイラになったのかもな。」と笑う。
冷房が効きすぎて寒くなり、窓を全開にする。商店街の方角から生温い風に乗って、夏を意識した音楽が微かに聞こえてくる。少しの刺激を、どこかで聞いたことのあるような言葉を、遠い昔に体験したことのあるような何かを、わたしたちは無意識にもう一度体験したいと思う癖があるんだな、と何故だか思った。
仕事として何かと同化することに馴染みすぎているわたしは、ついうっかり気を抜くとすぐに何かに溶け込む癖がついていた。忙しい時は良いのだ。もうこれ以上何かに同化することはできません、というところまで自分を使い果たせば容易く他人の話し声や、雑踏の中の匂いや、触れたものの手触りや、そういうものに同化している余裕すらなくなるから。感覚として感じることや感情を受け取ってしまうことを鍛錬で回避してきたはずなのに、今はまるきり駄目になっている。どこかが壊れたみたいにだだ漏れの情報の中を歩いているみたいな気がした。土砂降りの雨の中を傘をさすことも諦めて、「もう勝手にやっといて・・」と言いながら歩いている人のようなわたしに成り果てていた。

眠気に襲われる。
そういう種類の夏というものが存在するのは知っていた。その眠気のなかでどれくらい目を開いていられるかが勝負なのだ、ということも知っている。眠りは快楽だ。しかし現実は眠りの続きだ。眠りは想像と言い換えても良いだろう。一日の気分は目覚めた時に決まる、っていうのも生じか嘘ではない。一度死んで、目が覚めた時の最初の瞬間のフィーリングは、死ぬ一瞬前のフィーリングと繋がっていて円になっているのだから。これは極めれば極めるほど真実だということが理解できる類のことだろうと、まだ極まっていないわたしはぼんやりと「そんなものなのかも」と思い巡らす。入り口と出口が同じ、ということと同じで、この惑星を去るときに全部分かることなのだろうか。たぶんそうなのだろう。だとしたら全部体験してゆくしかないようにある程度のレールは敷かれているのだろう。物語を書くわたしはもしかすると、そのレールを自分自身で敷き、嫌でもそこを走り抜けてきたのかも知れない。「嫌だ嫌だ」言っても通らなくてはいけない道があるのだとしたら後回しにするのは馬鹿みたいだ。得に「飽き飽きしている人間」にとっては。どれほど誰かに邪魔されたとしても、どれほど甘い誘惑のような出来事と遭遇しようとも、そしてその結果がどうなるかある程度の予測ができてもできなくても結局は「体験する」と決めれば足は動くようになる。心地よくなくても進む。痺れて真っ直ぐに歩けなくてもヨタヨタとでも歩く。歩けるようになる、そのこと自体だけが美しい。生の美しさ。血が通いはじめ蒼白の顔に血の気が蘇る。そういうニュアンスを追い求めた結果が「今」だ。
眠りに落ちてゆく。快楽を求めている自分に抗えず。完璧な自堕落。催眠術にでもかかってしまったのかも知れない。でも、どこで。記憶にないのだけれど。何年も律してコントロールしてきたのに、と悔しく思う反面、ちょっとくらい良いだろう赤提灯の誘い文句の「一寸一杯」ってのと同じだ。酔う眠り、か・・悪くないわね。こんなにシビアな状況なのに、まるで甘やかされているかのような眠りだ。
わたしが夢の中で向かいたいのは「夢見」のなかに閉じ込めたままの星の子が住んでいる海岸。そこを目指して堕ちてゆく。
・・・それならできるだけ優雅に・・その時が訪れるまで・・
・・・違う わたしが行きたいのはそっちじゃない・・脈の鼓動が耳の奥で鳴り響く そっちじゃない 空気を震わす重低音 水の揺らぎ 不安を誘う振動 そっちじゃない・・
高速道路は朝方の濃い霧に包まれていた。
「何も見えやしないね。でも夢の中だから運転できちゃうものなのね。楽しい。わたし夜の高速道路走るのってはじめてなんだ。どこまで行こうか。海。いいね。途中でドライブインに寄ろうよ。用事なんてないんだけどね、食券買ってさほど美味しくない何かを食べたり、駄菓子を買ったり、ダサいお土産ものを見て回ったり、薄いコーヒーを買ったり。そういうことがしたいの。急げば夜明けに間に合うね。あなたに見せてあげたい。すごく綺麗だからね。待っててね。」
分厚いタイヤがアスファルトを擦る感触から大きな車に乗っているらしいことが分かった。あまり話もせずに、隣に誰が乗っているのか確認することが何だか恐ろしく思えて、誰かの気配が消えてしまったらどうしようという焦りが心に染み付いて離れないまま、ただ前だけ見て車を走らせた。
夜空に時々、白い輪郭を持った金色のドットで描かれた大きな鳥のような形の何かが渡ってゆくのが見えた。
「夢の中だから何でもありだね。見て、ほら花火みたいに消えて、ほら、また今度は群れで飛んできたよ。」
脈拍が上がる。怖いなにかを見てしまった気がした。タイヤが道を滑ってゆく。重低音と振動。ここじゃない・・でもここのような気がする・・行けるところまで車を走らせて・・
夢のなかのドライブインは思っていたよりも蛍光灯がガンガン光っていて、眩しくて何となく中に入れずわたしは躊躇った。コーヒーだけでも・・と自販機に向かおうと振り返ると、そこには向かう予定の海が広がっていた。
水の冷ややかさを足元に感じた。次の波は崩れ落ちる一瞬前の波がわたしの腰を曝して沖へと押し返そうとした。腹部に痛みを感じるほどの強い波に巻き込まれそうになりながら浜へ向かって泳いだ。波打ち際で座り込んで空を仰いだ。桔梗色の空が辺りを染め上げて、大気にはバラの香りが漂っていた。
このまま夢が醒めたらいいのにと願った。
綺麗なエンディング。最後の場面。
こういう時にかぎって夢は醒めない。夢にも夢の意思がある。勝手に終了することはできないし、終了させたとしても、その後でいつ同じ夢を訪れることができるのかは定かではないので行けるとこまで行くのがわたしの主義だったりもする。こんなとこまで来て仕事モードにならなくてもいいけれど・・と薄っすらと思った。
「海に着いちゃった。これだから夢って嫌だよね。本当にしたいことは全部できなくて。もうあなたはここにはいないのでしょう。この砂浜を探したってきっともういない。」
そう呟きながらもわたしは駆け出していた。足が砂の重みで動かせなくなるまで。湿った砂浜でも何でもいいからもう眠りたかった。体は重たくなる一方で、砂に磁石で体がくっついてしまったかのように身動きも取れそうになかった。
好きにしたらいいよ・・夢のなかでさらに眠るのか・・ああ・・もうこれは駄目だな・・ここから先へまだ落ちてゆく気なのか・・奥の奥へ・・
ぐらりと空が揺れ全身に振動を感じた。砂に奪われた体温の低さに身震いした。
空を仰ぐと漆黒の空に半月が浮かんでいた。月をじっと眺めていると月は滲み出し、真っ黒な孔がそこに顕れた。
・・ああ、あれが夢の在り処なのかも・・
暗転し瞳が閉じられてゆく。
暖かな空気と甘いフルーツの香りに満たされて目が覚めた。大きな木の下でお昼寝をして目が覚めたんだ。鳥の声と草を揺らす微風にまたまどろみそうになる。何度も何度も眠ってしまっても大丈夫だよ、と言われているような気がした。
「あなたといると何も話をしなくても良いような、そんな気分になる」
柔らかな甘い声。確かにそこにいて隣で同じように木々の隙間から漏れる光を眺めている。
「そうなの?もしかすると、わたしがお喋りな気分を吸い取ってしまっているのかも知れないわね。そういうことが一番大切だって知っているはずなのに、どうしてもできなくて。皆だまってしまうの。ごめんね。」
くすぐったいような気配がした。隣に眠る人が静かに笑ったのだと思う。
このままこうしていられたら良かったのにな・・
そう思った瞬間、木々がざわめいて木の葉が舞い落ちた。真っ青な空だけが目の前に顕れた瞬間、わたしは目を瞑った。そして目を開いた。
・・・やっぱり、ここだ。夢の在り処だ・・・
低いモーター音が空の彼方からこちらへ向かってくる。鉛色の戦闘機が巨大な砲弾を雨粒のように落とし始める。晴れ渡った空に砲弾がきらりと光り金色に輝いた。
・・・絶え間ない不安。それでも尚、目を開いていなくてはとわたしが思った理由。負けたくないと思った理由。わたしはただ生きていたかったんだ。ただそのままであんなふうに春の暖かな日に昼寝をしているだけで幸せで、それで十分だったから・・
冷たい砂の感覚をおぼえて目が覚めた。海は凪ぎはじめ波音が少しだけ静かになっている。
「ねえ、分かったでしょう。目を瞑ってしまったあの夢の意味が。そしてあなたがどんな強迫観念に何代も何代もとりつかれてきたのか。あのシーンは怖くてたまらなかった。それでも目を開いた。」
星の子の声だった。
静寂の中に金属音だけが響く。桔梗色の空もゆっくりと東の方角から明け始めた空にその色をゆったりとゆだね明け渡しはじめていた。鳥たちが眠りから覚める。空気は涼しくて少し暑くて、飛行機の中で過ごしている時みたいに薄く、呼吸が少しだけ苦しい。
「ここはあなたの海岸だよ。目を瞑ってしまった夢見もこの海岸で起きたこと。あなたのその恐怖を突き破って、あなたの内側に入ったそれは何?ここはあなたの夢の中でしょう?あなたが夢を拒まないかぎりここへはいつでも来られる。あなたは夢を拒んでいた。想像を拒んでた。夢のほうからそっち側を見ることも出来るってこと知ってた?」
「嘘・・。じゃあ何故早く助けてくれなかったのさ。」
わたしは久しぶりに怒りを感じた。普段、怒るくらいならその熱量を書くほうへ向けてる癖がある。感情はエネルギーなのだ、それを知っているが故に、わたしは感情を全部物語のなかに閉じ込めてきたのかも知れない。依頼主の感情にだって勿論同化するわけなので、できるかぎり昇華させた感情を文章に混ぜ込み、読んだ後に少しでもすっきりしてくれたらと魔法をかけ続けてきた。でも、今だけはそういう合理的な考えに基づいていたくなんてなかった。わたしはわたしを生きたい、と切に願っている証拠として。
「夢に手を伸ばすのはいつだってそっちの現実の世界からなんだよ。混沌の中から手を伸ばさないかぎりはここへは来られない、ってことあなたは知っていたはずなのに、いつしかその法則すら忘れていた。忘れたほうが楽だったから。もう歩かなくて済むように、もうどこへも行きたくないかのような顔をしてメソメソしてた。歩かなくていいのは夢の中の僕だけだよ。だってほら知っているでしょう。僕はどこへも行かないし、行けない。あなたの内側にいつだっていた。内側で知っている場所で繋がる、ってことをあなたは現実が目のまえに迫ってくればくるほど遠ざけた。声のこともそれと同じだと僕は思う。僕はあなたの一部であり完成しているから。ただ眺めているだけだから。ただあなたが何をしているのか目撃して情報を収集するだけだから。ひとつ言っておくけれど、僕の役目は観察ではなく目撃だよ。それが最大の喜びであり幸せ。観察は肉体をもつあなたの仕事。体を動かして起きた現実に対して責任を取ってゆくことと、静止して眺めていられるように保つこと、それが仕事。包含されている関係性だと言うなら、何でそれを認めないの。僕のことも、それから、あなたが今必要だと感じているものに関しても。全て、何でわたしだけは関係ないみたいな顔しているの。」
「マブイらしい発言をどうもありがとう。」
こんなに長く会話することは珍しいことだ。だいたいにおいて夢見では、その夢全体の雰囲気が答えだったりする。わたしはその世界に対して、現実世界で用意した最も端的な質問を投げかける。そうすると星の子はそれに応えてくれる。現実世界に戻ってわたしはその夢見の全体の雰囲気と応えをミックスさせたものを脚色なく依頼主に伝える。なので会話というのはあまりしたことがない。こんなに長い会話が出来ている唯一の理由それは、たぶん「わたしがわたしと話をしている」からだろう。疲れないし、いつものようにただ冷静というわけでもなく、怒りをおぼえ動悸すらしたのが証拠だ。

現実へ降下する。
激しく踊った後みたいに汗をびっしょりかいて目が覚めた。扇風機の低いモーター音だけが事務所に鳴り響いていた。あまりにも長く重い夢を見た後はいつでもしばらく現実に馴染むためにまどろむ時間を取ることにしている。
辿りついた場所がどんな場所でも「今」になる・・ってどこかで聞いた話だな・・。
「お前が書いたんだろうが」
自分で自分のことを笑う。笑えるようになってからが本番だ。それは、痛みとは違う、蔑む、とも違う。「生きてゆこう」と決意するその準備段階なのだ。
よろよろとソファーから起き上がり冷蔵庫へ向かう。グラスにできるだけたくさんの氷を入れてママから貰ったコーラを注ぎ込む。まだ生きてゆけるような、そんな気がした。少し正気を取り戻して夢の回想に勤しむ。
フルーツの木の下の夢のなかのわたしは睡眠薬を大量に飲んで逝ってしまった友人ととても似ていた。現実に彼女はもうこの世界には生きていない。完全完璧にいない。肉体はこの世界を去った。彼女と夢のなかにいたわたしは完全に別人物ではあるけれど、どこかで会った気がする誰かというものは最初から、知ってるかんじがするものだし、相手もそう思うならより一層その結びつきは濃くなる。扱い方を何となく知っているからお互い一緒にいて楽でもあるし、触れてほしくないことには触れずにいることもできる。傷つけあわなくてすむ、というメリットもあったりする。傷つけようと思えば何処までも傷つけることもできる。家族みたいなものだ。縁が濃いが故にできる事と、決してしたくはない事。わたしも彼女も過去のどこかのタイムラインで同じような想いを抱いていた仲間だったのだと思う。会うことは叶わなかったのだろうけれど、目には見えない想いをどこかで共有していたのかも知れない。木の下にいたわたしはいつでも同性で同じような種類の友達が欲しいと強く願っていたから。それでたぶん今この現代において何らかの運命の采配で彼女とめぐり合ったのだろうと思う。そういえば彼女はよくわたしにこう言っていた。
「あなたはまるで素早く動く蜘蛛みたい。情報を運んでくれて、わたしが危機の時にはそっと姿を現して知らせてくれるもの。実際にこうしてお話したりお茶したりして実物のあなたに会うと、本当にあの蜘蛛があなたなのか?と思うほど、おっとりしていたりするから人間って分からないものだね。」
わたしのどこがおっとりしているのか全く分からないけれど、そしてやはり蜘蛛だったか、さすが鋭いな・・と思いながら「ふーん」と頷いた。
「わたしね過去にはあなたみたいに勇敢だったことがあるの。それでも人から見ると、おっとりした何でも許すようなそういう化け方ができるたくましさも持っていたと思う。ふふふ。今はもうそういうのがなくなっちゃった。」
良い香りのハーブティを口に運びながら彼女はうっとりと空を仰いだ。
・・なくなっちゃった・・って知ってるなら探せばいいでしょ。いつかあなたが危機に陥った時に必ずわたしは一度だけはっきりと忠告するからね。過去のなかで会えなくて、今ここで会っていて、生きていて、動いているのだから・・
と思ったけれど言わずにいた。わたしは濃いエスプレッソを飲み干して、居心地の悪さを感じたことを覚えている。もしかするとどこかで彼女が死のほうを選ぶということを察知していたのかも知れない。過去のわたしも今のわたしも彼女ではないけれど、隣接する目には見えない次元を通じて理解してしまえば誰とでもどこか似ていて共有しているものだから。そしてお互いが理解を示そうとしているのなら余計に見る角度というのは一致してくるものだから。彼女にもっと真摯に向き合うべきだったのかも知れない。彼女はわたしのある側面である、勇敢さに気付いていたのだから。そして、わたしは彼女のある側面である、抱擁することの重要性に気付いていたのだから。見出しているものは交換できるものだったのに、それを成すことなくわたしたちは違う道を選んだ。元も子もない言い方かもしれないけれど、同性だったから、という理由もひとつ挙げられるだろう。彼女には恋人がいたし、わたしは仕事に夢中だった。性差など軽がると飛び越えられる愛もあると今のわたしなら知っているから、今ならば違うレスポンスをしただろう。けれど後悔はなかった。またどこかで出会うのだと思う。似たような出来事を通じて、わたしはわたしに出会っている。
夢のなかのわたしと現実の彼女(死んでしまったけれど)は、距離の近さを好み、「こうするしかないの、これが私なの」という重要な言葉を避け、説明することが面倒になるほどくたびれ果てているがあまりに「ごめんね」なんて言い、悪いと思っていたのかも知れないけれどあまりに明確に自分が何をしているのか知り尽くしているが故に持つしかなかった罪悪感と冷酷さを持っているところが似通っているように思った。自分が何をしているのか知り尽くしていても、それがその時代や生きている背景にそぐわない時、やはり人は辛いものだ。奪ってなどいないのに奪っているようなそんな気分が罪悪感を齎し、正確には誰も誰からも何も奪えやしないという真実も霞むほどに罪悪感だけが成長してしまう。時代背景というのは大きかっただろう、夢のなかのわたしよ・・とわたしはわたしを理解した。そうせざるを得なかったよね、と。本当はもっともっとその才能を謳歌したかっただろうけれど、その時代にその特殊なスキルを持っていると認めることは恐ろしいことであると同時に、そういうあなたを必要とする人は弱者とみなされてしまったはずよね。だから、誰も誰一人として真のあなたを必要とはしてくれなかった。踏み込むことが怖いから。あなた自身も誰にも踏み込ませまいとどこかで決めていたのね、いつかのわたしよ。
ただ、もしかすると隣で昼寝をしていた誰かだけはもしかするとあなたを必要としてくれていたのかも知れないね。世界の脆さと、人が持つ危うさの両方が混ざり合ってゆく最中でも、それでも尚、その閉じてゆく世界が孕んでいる小さな灯のような希望を肯定できた人がその誰かだったのだよね。それは二人にとって恐ろしいことでもあると同時に、理解者が一人でも世界にいてくれたのなら生きてゆける、そういうふうに感じていたのだよね、きっと。「そのままの自分である」ということがどれほど難しいことなのか、わたしは今でも考え続けているよ・・
フルーツの木の下のシーンは、わたしの記憶の回想シーンだ。いつかのわたしの最期の瞬間の記憶。目を閉じて永遠の眠りにつくその一瞬前に強く思い描いたシーン。生きていたかった・・そして、ただあなたは生き延びて。ただ生きててほしい、それだけでいいから・・そう願いながら瞳を閉じたのね。そこから先が怖くて恐怖の色に染められているのは、その回想シーンに戦闘という根底がこびりついて眠ったままになっていたから。記憶は時々混乱するの。恐怖に関しては得に。だから恐怖の対象が歪められてしまったんだね。長い時間を経てゆくうちに怖いものは見たくないが故に。でも、わたしが幾世代も先で、そのシーンに目を開いた。わたしにとっては真に怖いシーンだった。それは正しい記憶、だからもうわたしは過去のわたしを責めない。長い時間を経て、理解されたいと願うたびに拒絶を学ばされる、そういうパターンを作り上げたのは、今生きているこのわたしであり、わたしの前に生きたわたしたち。理解する、と決めた今のわたしだからもう大丈夫。理解すると決めて歩いて行ったら愛みたいなものの輪郭くらいは今わたしは感じられるようになったよ。もっと流して流されてゆこう。恐怖を断ち切ることは今ここでしか叶わない。新しく生み出すことも今ここからはじまる。わたしは生きてる。大丈夫。

一つずつ大切なものに近づいてゆく、そのプロセスこそがどれほど重要なものなのか、ということはきっといつか全部を眺められる場所に辿りついて始めて見つめられるのだと思う。優雅に「ああ、良かった。誰かに恋してる時みたいに、世界を愛するように生きられて最高だった。」と思い笑いたい。それまではまだこの世界で遊んでいたい。
「あなたは今生きていて体があるのだから・・」
くすぐったいような安心するような柔らかな甘い声が響いて、体から数センチ離れたところから、ふわりとハグされたかのような温かさを感じた。ほんのりと薔薇のような香りも漂っていた。深く息を吸い込み、また深く息を吐いた。
溶け始めた氷がカランと音を立ててハッと我に帰った。窓から白いハイビスカスの花弁が何枚か風に乗ってひらひらと、とてもゆっくりと舞い込んでくる様子を見つめていた。容赦なく西日が差し込んで、散々雨が降ったらしく窓辺は水浸しになっていた。スコールの季節は好きだ。何もかもが嘘みたいに終わって、また始まるさまを好ましく思う。窓の外を大きな鳥が飛んで行った。
・・・You're half the world away
あなたは正反対の世界にいる
I've been lost, I've been found
失くしたものも見つけたものもあったけど
But I don't feel down
わたしは落ち込んでない
I don't feel down
落ち込んでないから・・・
夢みたいな現実。現実が夢なのか、夢が現実なのか。どちらもそんなに遠くない。手を伸ばせばそこにあるもの。それを見ようとすれば誰でも見られる。そういうふうに世界はいつでも開かれていて、秘密などほとんどない。秘密があるとするなら、それはきっと秘密を持っていたいから秘密が存在するかのように振舞っている世界を生きているというだけ。シンプルなこと。ただ、収縮したり拡大したりしているその最中の真ん中の世界に突然投げ込まれることもある。そこが夢の最果て、夢の在り処、夢の終着点、なのかも知れない。まだいくらでもどれだけでもどこまでも夢みることもできる。それと全く同じペースで現実というワールドも歩いてゆけたら。
もう一度言うけれどDroppingMellowなんて完璧なタイトル今後思いつけないほど完璧なタイトルだなと思う。「意味が通じない英語です。タイトルを変更しないのであれば出版はできません。」と編集者に言われ「じゃあ、出版はしなくて構いません。」と言い切ったあの日のわたしを褒め称えたい。わたしの魂の本にタイトルをつけられるのなら「DroppingMellow」しかありえない。
何度でもわたしはわたしが真に愛するものへと手を伸ばし続けるだろう。
はちゃめちゃを受け入れる。辻褄の合わないことも受け入れる。それ自体がまるで夢のように感じる。そして、この宇宙に生まれ落ちた時に入ってきた入り口から優雅に退出してゆく。最高の思い出を胸に抱いて。迷いようがないほどの圧倒的な美しい真実と共に。
ーThe story continues. ・・・
Thank you for reading. With love.
Screenplay by White Wizard/白い魔法使い
サポートをいただきましてありがとうございます!励みになります! 白い魔法使いより
