
申請書を書きたくない気持ちとの折り合い
2022年5月27日に筑波大学人文社会系の所属教員向けに「申請書を書きたくない気持ちとの折り合い」というトークをしました。これは同組織が行なっている科研費セミナーの一環です。それなりに役に立つ話だと思いますので、当日使ったスライドに簡単に補足する形で公開します。
なぜ「書類を書きたくない気持ち」と向き合うのか?
科研費獲得セミナーというと「やりたい研究をするために科研費を取りましょう。」「わかりやすい書類を書いて忙しい審査員に理解してもらえるようにしましょう。」「大学は予算がないのだから外部資金を取るのは必須です。」「税金を使うのだから国民に対する説明責任があります。」といった声が聞こえてきて、それらはまったく反論の余地がないほどに正しいわけですが、正しいからと言ってそれでやる気が出てくるかというとそれは別の話です。
特に人文学の場合は、研究に必要なのは大きな予算というよりは、安定した雇用とブルシットジョブに煩わされないじっくり本を読んで考える時間なので、例えば考古学者が発掘調査のために大規模な研究費が必要というような事情がなければ、数千万円規模の大型科研費をとる理由がありません。むしろ、新自由主義的な競争を重視する価値観、さまざまな現象を過度に数値化して評価する人間疎外、現実がうまくまわっているという幻想を維持するために官僚制がブルシットジョブを増殖させてしまうことなどを批判する人文学にとっては、科研費というシステムは「なるほどたしかとらないと仕事にならないがとはいえそれには100%はのれないぞ」というアンビバレントな気持ちになる制度です。

だからこそ、そのもやもやとしたやりたくなさに向き合って、どの部分がどのような理由でやりたくないのかを考えるのが、科研費の申請書を書くときの第一歩目として大事だというのが今回のトークのテーマです。このもやもやを分節しないで、例えば科研費申請書のマニュアル本のようなものを読んでそのテクニックを学習しようとすると、本質的にはやりたくないという気持ちのままでいるのだから、個別的なテクニックに引きずられてしまいます。例えば、学振DCに応募する方の申請書を見ると文章を下線や太字や括弧を多用して装飾している人は多いのですが、それはシステムやマニュアルへの過剰適応でほとんど意味がないです。文章に下線を引くべきかで頭を悩ませるくらいなら文章自体の完成度を高めるべきです。

システムやマニュアルに振り回されないようにするために、まずはなぜ自分が申請書を書きたくないのか考えてみましょう。私の場合は上の図のようになります。このようにどういった理由で申請書を書きたくないかを書き出すだけでも、もやもやとした書きたくない気持ちが、単に自分の性質に由来するもの、研究の不確定性に由来するもの、システムや政治に対する異和に由来するものに分節化されます。分節化することができれば、個々の要素に対してどう向き合うかを決めることができます。システムや政治はすぐには変わりませんが、それでもそういったものへの異和を自分の中でどのように処理しながら書類を書くかという方針を立てることはできるようになります。
分節した「やりたくなさ」を自分のゲームのルールに変換する
私は下の図のようにいくつかの書きたくない気持ちを取り出して、「セクション」「パラグラフ」「センテンス」それぞれのレベルでのゲームのルールに変換しました。これは最初からそういう方針で書類を書き始めることができたということではありません。やりたくない理由を具体的に考えながら申請書を書く中で、「だったらこういうやり方で自分ルールを作ってゲームを仕掛けたら楽しめるな。」という瞬間がたびたびあって、それを後からまとめるとこうなったということです。

「セクション」「パラグラフ」「センテンス」それぞれについて説明します。
セクション:申請書の各セクションは未知の臓器のレントゲン写真

学振や科研費の申請書はフォーマットが変わることがあります。というか、科研費の応募区分自体が精度変更もあり複雑怪奇なシステムになっています。あまり記憶が定かではないのですが、学振の申請書に「目指す研究者像」を書かせる項目があった時期があり、「それで何を判断するのだろうか」と思った記憶があります。このような細かなフォーマットの変化に振り回されるのは本当に嫌なので、私は申請書全体を書くことを研究計画という未知の臓器をレントゲン写真として撮る行為と考えました。臓器をレントゲンで撮影するときは直接見えないものの立定的な構造がわかるように角度を変えて場合によってはレントゲンの設定も変えて何度も撮影します。申請書の各セクションは未知の臓器の姿を浮かび上がらせる一連のレントゲン写真の一枚一枚に相当します。
セクションを一枚のレントゲン写真と考えると、個別の細かいフォーマットに合わせることが大事なのではなく全体の中での情報の配置が重要なのだという認識になります。このように認識を変えると、先述の「目指す研究者像」を書かせる項目が仮にあったとして、その質問に素直に答えるのではなく、その質問に答える形式をとりながら研究計画全体を理解してもらうためにどのような情報を配置すればいいかという向き合い方になります。また、こちらのほうがより重要だと思うのですが、研究というまだ実現していない未知の存在を解剖するという手つきを研究計画書に落とし込むことができるので、「どうなるかわからないのに確かな計画なんて書けない」という罪悪感のようなものからちょっとだけ解放されます。
センテンス:人間の一対の声帯で発生できるセンテンスを書く

科研費の書類に限らないことなのですが、文章の修飾的な要素が多いと文章を読むという身体感覚が失われてきてけっこう辛いです。下線や太字を使って強調するということは一般的だと思いますが、これらを使って強調表現をするときに厳密に強調表現のレイヤーを使い分けている人はあまりいません。例えば下線と太字を混在させる場合、1)下線と太字両方、2)下線のみ、3)太字のみ、4)どちらもなしの4パターンが存在するわけですが、この3つの強調の使い分けが研究計画をわかりやすく伝えるという目的に貢献しているという例はあまりないと思います。単に強調する場所とそうでない場所を分けたいだけであれば、文の修飾要素は一種類でいいはずですが、複数の修飾要素を多用する人は一定の割合でいます。
ではどの程度まで文の修飾要素を使うべきかと考えた結論は、私の場合は「一般の人間の一対の声帯で表現できる範囲で使う」です。将来人間が遺伝子操作をすることが当たり前になって、一人の人間の中に複数の声帯があることが当たり前になれば、それらを駆使して和音や不協和音や複雑な音楽要素を取り入れた論理を作ることもできると思いますし、人間の脳もそういった多レイヤー的な論理を理解できるようなるかもしれません。そのくらいになれば複数の修飾要素を使った文章の強調表現を使ってもいいかもしれません。ですが、現状そうではなく、普通の人間はせいぜいちょっと声を大きくしたりといった程度の音声表現しか使っていません。だったら、文章もそのくらいで書かないと読み手の負担が増えるばかりで、書き手と読み手の間で対話が起きているという身体感覚が生まれません。システムに踊らされるのではなく、システムの中にあっても、やはり私は対話をしているという身体感覚を重視したいです。
そんなわけで、私は申請書には太字も下線も使わないということに決めました。下図が一番最近の科研費の申請書で文の修飾要素はまったく使ってません。

パラグラフ:各パラグラフには線的な論理の運動性を作る
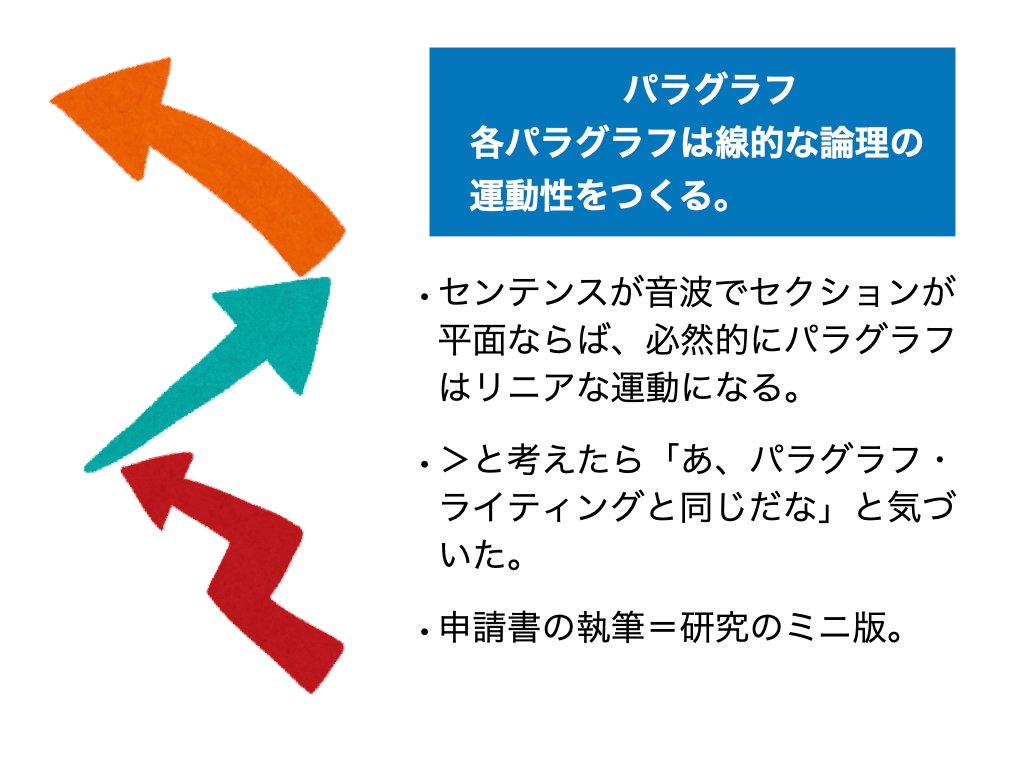
さて、センテンスが人間の声帯が発する音波で、セクションがレントゲン写真の平面であるというところまで自分で原則を作ると、必然的にパラグラフの中には直線的な運動性が必要だなということになります。平面の中に何らかの構造を描き出そうとすると、パラグラフの最初から最後へ向かう小さな運動性を組み合わせて複雑な構造を作りたいということです。もちろんこれは完全にアナロジー的な話で論理的な話ではありません。ですが、このように考えていくと、「あ、パラグラフ・ライティングってそういうことだよね。」という気づきとつながり、センテンスとセクションそれぞれのレベルでの方針がパラグラフ・レベルでの方針を経由してつながり楽しくなってきます。
下図は、現在行なっている科研費プロジェクトの「本研究の目的」部分の冒頭で、パラグラフの中に明確に小さな論理の展開を作ってそれを全体として平面に構成しようという意識で書いたものです。

まとめ:ゲーム盤を自分に引きつけてゲームをしかける

私があげた「セクション」「パラグラフ」「センテンス」レベルでの方針・原則はそれ自体として必ず正しいというわけでも一般的に妥当するということでもありません。そうではなくて、申請書を書きたくない気持ちを分節化して自分なりのゲームのルールに変換することが大事です。もし仮に、科研費をとらないといけないという焦燥感に駆り立てられて、細かなテクニックに走ってそれらしい申請書を書き上げたとしても、それで科研費が通ればいいですが、落ちた時にどう修正していいかがまったくわからなくなります。自分のルールを作り上げて自分のポリシーでゲームを仕掛ければ、審査員との間に対話が生まれ、仮に採用されなかったとしても次はどうするかを考えることができます。
「申請書を書きたくない気持ちとの折り合い」というタイトルですが、この話はやりたくないこと一般にある程度適用できるかもしれません。もちろん「システムの改善を考えずに自分が適応することばかり考えていたら悪しきシステムが変わらないまま永続してしまうじゃないか」という批判はありうると思います。それは全くその通りなのですが、とはいえ目の前にある問題に対処しながら生き延びないといけないというのも事実で、今回のトークは実践的な生き延びの話に注力しました。
