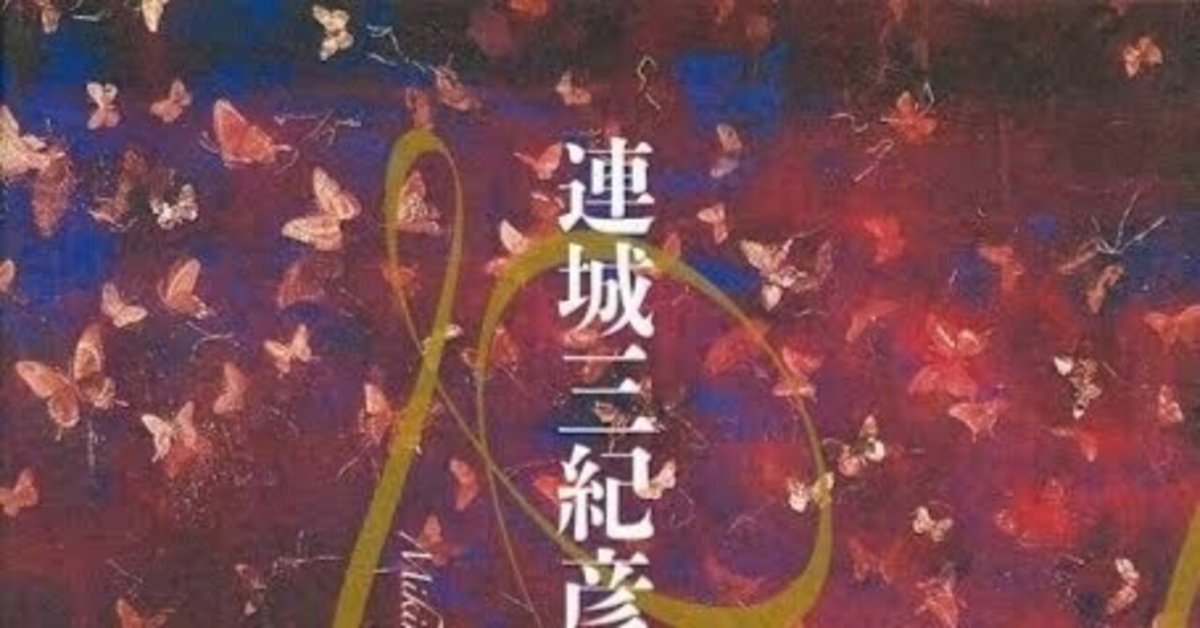
『女王』連城三紀彦
雄大な構想を持った“白鳥の歌”。推敲の叶わなかった終盤に無念【70】
彼は、“芸”―芸術、芸能、文芸等々―を生業とする人々、特に自身の死すら“芸”として昇華してしまおうとする人々を執拗に描いてきた。「変調二人羽織」「戻り川心中」「花虐の賦」「白蘭」「観客はただ一人」『私という名の変奏曲』――。また、彼は〝“私”は本当に“私”なのだろうか〟という問をも発し続けてきた。「白蓮の寺」「紅き唇」「家路」「それぞれの女が…」「喜劇女優」『ため息の時間』――。それでいながら、彼は、“家族”というモチーフにも拘り続けていた。「他人たち」『明日という過去に』『白光』――。なかでも“親子(父子)”というモチーフは彼の得意とした誘拐ものの中でよく見受けられるものである。「過去からの声」「邪悪な羊」「ぼくを見つけて」「小さな異邦人」『人間動物園』『造花の蜜』――。
『女王』はまさにこれらのモチーフを散りばめた集大成である。そして、彼自身もそれを意識していたはずだ。物語の中核を為すのは、ミステリファンにはおなじみの邪馬台国論争である。しかし、彼は邪馬台国に関する新説を強く打ち出すことよりも、それに関する“ある人物”の不可解な日記を導入し、その解明を「魏志倭人伝」の解読方法と二重写しにすることを選んだ。彼はこの手法によって、歴史の謎の解明部分が鮮やかであればあるほど、現代の事件が色褪せて見えてしまう歴史ミステリの弱点を、半ば解決した。と同時に、その日記の導入は過去へのタイムスリップをも可能にしたのである。そういった意味で本書の白眉は“卑弥呼”と対峙する二章と、改行なしで自らのアイデンティティの追求を行う三章ということになるだろう。それだけに、意想外の真相があまりにもあっけなく開示される力ない終章は、残念といようよりも無念であった――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
