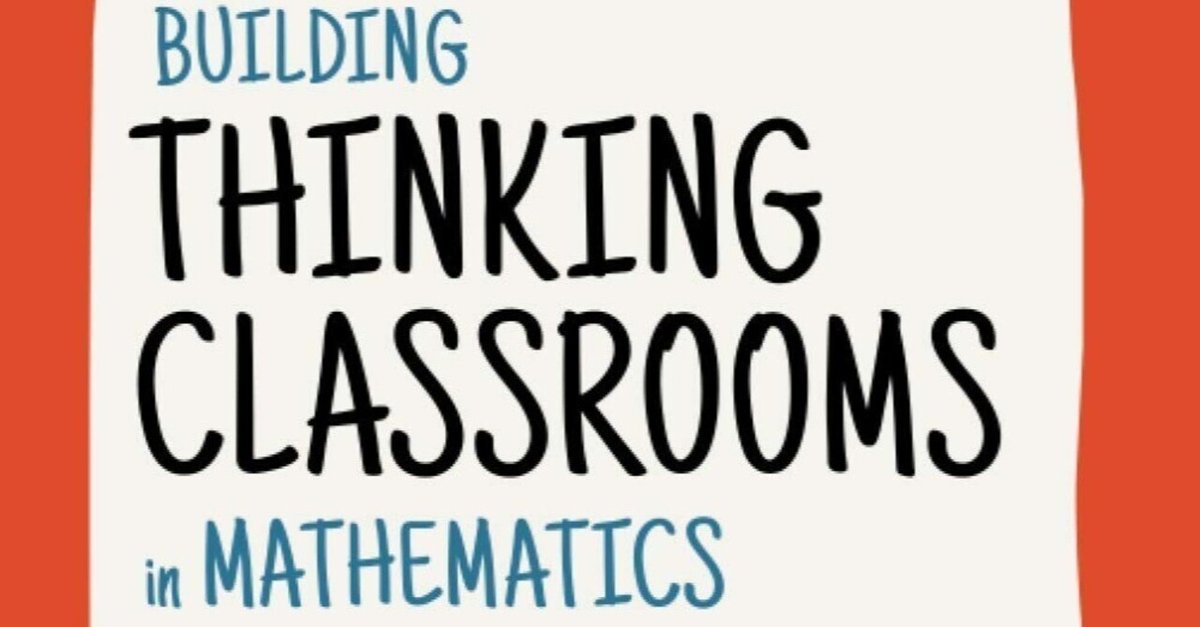
THINKING CLASSROOMSのIntroductionをちょっと見てみませんか?生徒も先生もシアワセになる授業ができるんです。
「私がジェーンに初めて会ったのは2003年だった。ジェーンは中学校の教員歴15年のいわゆるベテラン教師。彼女にとって数学を教えることはたやすいことだったけど、新しいカリキュラムの導入のうわさがあった。その新しいカリキュラムではどうも問題解決すること(プロブレム・ソルビング)や問題解決することを通して教えるということに重点がおかれているらしい。15年間の教員生活の中で、そのどちらも彼女はやったことがなかった。新しいカリキュラムの先取りをして、問題解決するとはどういうことかを知るためにも彼女は自分のクラスで実践してみようと思った。」
という書き出しで始まる Introduction、「問題解決することを通して教える」って一体何なのだろうか?

【問題】※2003年のお話
もし6匹の猫が6匹のネズミを6分で捕まえることができれば、何匹の猫だと100匹のネズミを50分で捕まえられるか?
ジェーンはこんな問題 を出して数学の授業を始めた。これまでに問題解決-ploblem solving を通して数学を教えたことがない教員がそんな授業を行ったのだ。それはすなわち、そんな授業を受けたことのない生徒がその授業を受けたことになる。するとどうなるだろうか。
「この情報をもとに、ジェーンにとっての彼女の生徒とのはじめての問題解決を使った授業がどうなったか想像がつくだろうか?そう、あなたの想像通り破滅的な結果だった。彼女が白板に書いた問題を解くように生徒に言うと、たくさんの手が上がり、ジェーンは動き出した。彼女は生徒から生徒へと移動しながら、何をすべきなのかといった質問や、解き方はこれで合っていますかといった質問、この答えで合ってますかといった質問を答えて回った。早々に生徒はやる気をなくし、あきらめだした。そしてジェーンはまだ問題に取り組んでいる生徒のサポートもさることながら、あきらめずに解き続けるようにと励ますことに同じくらいの時間を使っていた。」
そして、生徒や保護者からは「元の教え方に戻して欲しい」という依頼や苦情がくることになるのだが。時間の経過とともに、その授業を見学していた著者の言葉を列挙する。
・3日目の見学が終わるころ、2つのことに気付く。1点目は、この3日間一度として生徒が考えている姿を見たことがない。
・生徒は授業の最初から最後までやること尽くしだった。ノートをとったり、問題やプリントを解いたり、宿題を始めたり。彼らは忙しかった。でも彼らは全く考えていなかった。
・2つ目の気づきは突然私をおそった。それは、ジェーンが授業を準備するうえで、生徒一人一人が自ら考えようとしない、考えることができないという前提をもとに教えているということだった。
・毎日のように世界中の先生と呼ばれる人たちはこのジレンマを抱えている。
・つまりそれは授業内容を統一してなるべく多くの内容をなるべく効率的に生徒が一切考えることなく進めること。
・パターンを見つけたり、データを予想したり、一般化したりする過程は数学のレシピ本になりさがってしまった。20分もしないうちにすべての生徒はこの課題を終えることができた。でもそれはその間一切生徒が考えてないことを代償にしてなりたっていた。
・最終的には40の学校と40のクラスを訪問することになった。そしてそのどこを訪問しても私は同じ問題を目撃する。生徒は考えることをせず、先生は生徒は考えられないまたは考えようとはしないという前提で授業計画を立てる。ジェーンがそうであったように、みな評価の高い先生ばかりだった。
・これはもはやジェーン一人の問題でも、ジェーンの学校の問題でもなかった。学校システム全体の問題だった。
この続きは、「THINKING CLASSROOMS」日本語翻訳版の書籍が出版された時か、あるいは、英語版で良ければすでに出版されているのでよろしければ目を通して欲しい。
この後、Introductionにはこんな小見出しが並ぶ。
・考えない生徒たち
・制度上の変わらない常識
・シンキング・クラスルーム(考える教室)に向けて
・この本をどう読むか
「どの先生でもどの環境下でもうまくいく実践法」が書かれているのがこの本だ。著者は算数・数学を取り上げて説明をしているが、北米を中心に全世界に広がりつつある THINKING CLASSROOMSは様々な教科で活用されている。
あなたの授業で、生徒たちは考えているか?、を想像して欲しい。そして、「うーん、考えてないかも、、、」と思う場合は、一緒に授業の作り方を考えてみませんか?
さて、こちらのプロジェクトは現在、日本語翻訳の出版社と調整中。7月には実験授業を東名阪で行う準備をしている。教員向けの勉強会も企画中。たくさんの学校の先生に興味を持っていただけると嬉しい。何よりすごいのは、ステップにある通りに実行していくと「考える教室」の授業ができてしまうという素晴らしい仕組みなのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
