
[特別無料公開]『池袋ウエストゲートパーク』が始動した2000年代|成馬零一
成馬零一さんの新著『テレビドラマクロニクル 1990→2020』発売を記念して、本書から2000年に放送されたドラマ『池袋ウエストゲートパーク』についての章を無料公開します。
宮藤官九郎が脚本を手掛け、長瀬智也や窪塚洋介といったキラ星のごとき若手俳優たちが出演していた本作は、以降のテレビドラマの方法論を劇的に変えることになります。
2000年の『池袋ウエストゲートパーク』
『ケイゾク/映画』が公開された直後の2000年4月。堤幸彦は石田衣良の小説をドラマ化した『池袋ウエストゲートパーク』(以下、『池袋』)をTBSで手がけることになる。
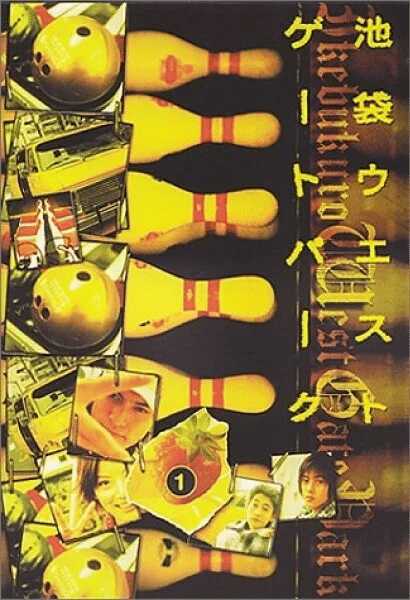
▲『池袋ウエストゲートパーク』(2000)
物語の舞台は東京都豊島区にある池袋。くだもの屋の実家で母親と暮らす真島マコト(長瀬智也)は、仲間たちとつるんで楽しい日々を送っていたが、ある日、友達のリカ(酒井若菜)が何者かに殺される。リカが援助交際をしていて、あやしい男に付きまとわれていたことを、ヒカル(加藤あい)から聞かされたマコトは、カラーギャングのGボーイズたちの協力の元、独自の調査をはじめる。やがて世間を騒がしている性犯罪者・絞殺魔(ストラングラー)に犯人の目星をつけたマコトたちはストラングラーを捕獲。リカを殺した犯人とは別人だったが、この事件をきっかけにマコトの名前は池袋中にとどろき、警察には相談できないイリーガルな事件の解決を依頼されるようになる。
リカを殺した犯人はいまだ不明だったが、トラブルシューター(便利屋)として池袋で起こる事件を次々と解決していくマコト。一方、池袋では勢力を拡大するGボーイズに対抗するカラーギャングのB(ブラック)エンジェルズが勃興、やがて、池袋を巻き込んだ抗争へと発展する。
『池袋』は今となっては伝説的な作品だ。まずは豪華な出演俳優。主演の長瀬智也を筆頭に佐藤隆太、山下智久、窪塚洋介、坂口憲二、妻夫木聡、高橋一生、加藤あい、酒井若菜、小雪といった、のちに頭角を表す若手俳優が勢揃いしている姿は壮観だ。同時に脚本を担当したのが大人計画の宮藤官九郎だったこともあって、阿部サダヲ、荒川良々、池津祥子といった大人計画所属の俳優も脇で活躍しており、大人計画以外にも古田新太、河原雅彦、きたろう、峯村リエといった小劇場系の俳優が出演している。三谷幸喜という先行例はあったものの、小劇場系の才能がテレビドラマに一気に流入してくるきっかけとなったという意味でも画期的な作品である。
この見事な配役を行ったのが、プロデューサーの磯山晶。『ケイゾク』の植田博樹と同じ1967年生まれ。1990年にTBSに入社した二人は同期である。
『池袋』は、今はなくなった金曜夜9時枠で放送されていたドラマで、夜10時からの金曜ドラマでは植田がプロデュースする『QUIZ』が放送されていた。
『QUIZ』は『ケイゾク』にあったアメリカン・サイコサスペンスの要素をより強めた劇場型犯罪を題材にしたもので、閑静な住宅街で起きた誘拐事件を精神を病んだ女刑事・桐子カヲル(財前直見)が追いかけていくというドラマだ。チーフディレクターは『ケイゾク』に参加した今井夏木が担当した。
一方、『池袋』には『ケイゾク』に参加していた金子文紀がセカンドディレクターとして参加している。磯山と金子、そして本作でプライムタイムの連続ドラマの初執筆となった宮藤が『池袋』でチームを組むことになる。後にクドカンドラマと呼ばれる一連の流れはここから始まったのだ。
植田と磯山という、TBSの二人のプロデューサーがドラマ界に新しい風を吹き込んだのでは?という質問に対して植田はインタビューで以下のように答えている。
「磯山の『池袋』もそうですけど、それまでのTBSのドラマ作りのフォーマットを大きく変えたとは思いますね。スタジオ2日、ロケとリハで3日みたいな、それまで何十年も続けてきたクラシックな撮り方ではなく、オールロケで、編集室を3ヶ月押さえっぱなしにして編集し続けるとか、音楽も、劇伴をそのまま使うのではなく、コンピューターに取り込んで音の要素だけを使うとか。『JIN-仁-』(2009年TBS系)も、音楽は『ケイゾク』のチームが担当しましたし、その後のTBSのドラマは、当時のチームの分派が作ってるものが多い。『ケイゾク』や『池袋』で始めたドラマ作りのノウハウは、今のTBSドラマに着実に受け継がれていると思いますね」(1)
植田が語るように、2000年代のテレビドラマについて考える時、『ケイゾク』と『池袋』がTBSのドラマを変えた側面は大きい。
制作面では植田の語っている通りだが、内容面では情報量が圧倒的に増えたことがあげられるだろう。物語が複雑化する一方で、小ネタと言われるマニアックな知識を元にしたギャグや過去作からの引用やパロディが増えたこともあげられる。
こういった複雑化は、視聴率という側面で見た時にはマイナス面の方が多く、植田と磯山が手がけた多くの作品は低視聴率で終わっている。
だが一方で、レンタルの回転率やDVDの売り上げは高く、のちにスペシャルドラマや映画化といった続編が作られることで、大きい息の長いコンテンツに成長することが多い。
今の日曜劇場の流れに繋がるような『華麗なる一族』等の文芸路線がTBSドラマの表のエースだとすれば、磯山、植田のマニアックな作品は裏エースとして熱心なドラマファンの間で話題を呼び、多くの作品が今も鑑賞に耐え得る作品として今も愛されている。
なお、日曜劇場の文芸路線で、演出家の福澤克雄と共に多くのドラマを手がけるプロデューサーの伊與田英徳も、『池袋』に演出補として参加している。他の演出補には『JIN-仁-』の平川雄一朗、『ATARU』の木村ひさし(SPドラマ「スープの回」のみ)といった、後にTBSドラマでチーフ演出を務めるオフィスクレッシェンド・スタッフの名前もある。
つまり、かつて『金田一』によって堤が日本テレビのドラマの方法論を変えたことと同じことが『ケイゾク』を経て、『池袋』でも始まったのだ。
だが、今の視点で振り返る時、ドラマ制作の方法論が同じだからこそ、植田と磯山が作るドラマの決定的な違いが見えてくる。それはそのまま、堤幸彦のドラマと宮藤官九郎のドラマの違いでもある。
特にこの『池袋』は、『ケイゾク』の堤幸彦がチーフ演出を努めているからこそ、後の『木更津キャッツアイ』以降のクドカンドラマとは決定的に違う部分が露になっている。
タメグチの映像
まず、演出面について考察したい。『ケイゾク』を通過した『池袋』の映像は、『ケイゾク』にあったトリッキーなレイアウトの画面を断続的な映像でつないでいくという手法がより際立っている。舞台は池袋に限定されており、オールロケで撮影されている。そして宮藤が参加したことで堤が今まで取り入れようとしながら、うまく咀嚼できなかった小劇場演劇の会話のエッセンスの取り入れにも成功しており、今作で堤演出の方法論はすべて出揃ったと言ってもいいだろう。(2)
音楽の使い方も進化している。『ケイゾク』ではギターやサックスの音が細切れにされ効果音とも劇伴ともわからないような使い方をされていた。それが作品全体に不穏なムードを醸し出していたが、『池袋』の世界観はラッパーのKREVAが参加していることもあってか、ヒップホップのテイストが強く、レコードをコスるスクラッチの音やリズムマシーンのキック音の連打が多用されている。元々、ヒップホップはDJが、ジャズやソウルのレコードからフレーズの一部を切り取って、そこにラップをのせるというスタイルからはじまっているのだが、本作の作り自体がフリースタイルラップのような勢いのある台詞の応酬にのせて、DJプレイのように映像が切り替わっていくライブ感がある。カラーギャングのファッション自体がヒップホップの影響下にあることを差し引いても、ストーリーだけでなく映像全体にヒップホップのテイストが漂っているからこそ、高い評価を受けたのだろう。
放送評論家の松尾羊一は、そんな『池袋』における堤の映像を「タメグチの映像」と書いている。
では、堤幸彦はなぜロケーション撮影にこだわったのか。
それは素朴なリアリズム信仰からではない。虚構を現実化するのではなく、現実をより虚構化するための「逆説の手法」なのだ。短いショットの積み重ねと断続感によって、ドラマの仮想性が強調されるのだ。なぜなら、未来都市ふうな「虚栄の市」のチャチな構造そのものが、人類が創ったおおいなる虚構なのだから。
堤幸彦はいわば映像を絶えずタメグチで語っている監督なのだ。「年上の人にも平気でタメグチをきく最近の若者」と非難される、独特の仲間言葉をタメグチという。
風俗や世代、そして時代を描くとき、一般にカメラの目線はどうしても説明や解釈といった「距離」をとって測る。傍観者の目線の方が分かりやすいからだ。
しかし、堤幸彦は鋭い若者の目と「等価」な映像言語で紡ぐ。映像を媒介にタメグチを言い合う、独自の映像コミュニケーション関係といってもいい。(3)
「タメグチの映像」という印象は、撮影方法が大きく関わっているのだろう。堤のドラマは、カメラ一台で順番に撮影していく。これは早撮りとオールロケに対応するための機動性はもちろんだが、「一台しかない方が人間の目線に近いから」(4)と、堤は語っている。
また、ロケにこだわる理由について、堤は宮藤官九郎との対談の中でこのように語っている。
北川悦吏子さんと対談したときに、北川さんが言ってたことなんだけど、あれだけ衝撃的なものを、2001年の9月11日にポーンと見せられて、それもテレビで繰り返し繰り返し。そのとき、作り物って、本当に色褪せたよねっていうことを、いみじくもおっしゃっていたんだけど、僕もそうだなぁと思うんですよ。ドラマっていうのは、いくら、完成されていても成り立ちとしてキツくないかって最近は思っているんです。かえって、場所的にリアルであって、でも、その中で、めちゃくちゃ虚構っていうほうがいいのかなって。(5)
補足しておくと、9.11が起きたのは2001年なので、2000年に放送された『池袋』の映像に直接影響を与えているというわけではない。ここで堤が語っているのはドラマ以上に圧倒的な事件が現実に起きた時に、フィクションの作り手はどのようなアプローチをすればいいのかということだろう。
その時に堤は、場所はリアルだが物語は虚構の度合いを高めた方が現実に拮抗するフィクションを作れるのではないか? と語っているのだが、9.11を3.11の東日本大震災や福島の原発事故に置き換えた時に真っ先に連想するのが、「現実 対 虚構」という宣伝コピーで、2016年に庵野秀明が監督した怪獣映画『シン・ゴジラ』だろう。
おそらく、『池袋』の映像に一番近かったのは庵野が1998年に監督した援助交際を題材にした映画『ラブ&ポップ』ではないかと思う。
カンパニー松尾やバクシーシ山下といったAV監督の影響の元、当時普及し始めた安価なデジタルビデオカメラを多数使用して撮影することでカット数の多い映像を東京ロケで撮影した本作は、当時の東京の風景を切り取りながらも、どこか現実感の薄い虚構性の高い作品となっていた。
映像面においては『ラブ&ポップ』のアップデートと言っても過言ではない『シン・ゴジラ』の映像は、iPhoneで撮影されたものも含めた、あらゆる映像が等価のものとして並んでいたが、リアルな舞台で虚構を作るという方法論において、堤の映像は「現実 対 虚構」というテーマを先取りしていたと言えるだろう。
アナログテレビが生み出した映像の可能性
ロケを多用しながら「短いショットの積み重ねと断続感によって、ドラマの虚構性が強調される」と松尾が指摘した堤の映像は、Instagramにあがっている写真や、YouTuberの動画に近いのではないかと感じる。動画アプリ「Tik Tok」(ティックトック)などは最たるものだが、ネットの普及と安価で高性能のデジタルカメラやカメラ機能の充実したスマートフォンの普及によって、誰でもその場のノリで気軽に映像の撮影・加工・編集・配信が可能となっている。
現在、ネット上に上がっている動画や写真と『池袋』の映像と親和性が高く感じるのは、当時のテレビの画面比率(アスペクト比)の問題もあるだろう。『金田一少年の事件簿』や『ケイゾク』もそうだが、この頃のテレビドラマはまだアナログ放送で、アスペクト比が4:3というほぼ正方形に近い画角だった。今の地上波デジタルに以降したテレビのモニターは16:9、つまり映画のスクリーンとほとんど同じものである。
テレビの映像は、地デジに対応するかたちで16:9へと移行していった。そのため現在の横長のテレビで2000年代初頭以前のテレビドラマやアニメを再放送すると、両サイドが黒く潰れてしまい何とも言えない違和感を醸し出すことになる。つまり、テレビ映像における新旧の時代区分が画角によって現れているのだ。
2018年に公開された行定勲監督の映画『リバーズ・エッジ』は、作中の舞台が1990年代前半であることを強調するために、あえてアナログテレビのアスペクト比を用いている。同様のことはアニメ『キルラキル』等でも用いられており、ノスタルジー表現として使用されることが増えている。
現在のテレビドラマの映像は、デジタル技術の進歩と画像加工ソフトで色味を調整できることもあってか、画面の印象だけなら映画に引けを取らないものとなってきている。ただ『ケイゾク』や『池袋』といった当時の堤幸彦演出のドラマの映像の独自性は、この正方形のテレビモニターで見られることに特化していた面が大きいのではないかと思う。ノスタルジーを抜きに見た時、4:3の画角の長所は、縦の構図・つまり高さを活かせることだ。例えば『池袋』では西口公園全体を捉えたカットの背後にビル群が写り込んでいて中心にマコトたちが立っているという構図が多用されている。
『ケイゾク』でもすごく引いた絵で人が立っているバックに建物が映っているカットがあったが、縦長の構図を使うことで、人物の全体図や高くそびえ立つ建物の描写は、横長の構図よりも印象的に見せることができる。と言っても、アナログテレビの画面も実は横長の構図である。そのため堤の作品では、魚眼レンズを用いることで全体を収めることもある。極端なアップの多用や、カメラの移動ではなくカット数の多さで見せる映像表現は、アナログテレビの制約があったからこそ生まれたものだと言えるだろう。
やや余談になるが、このアスペクト比の問題は、スマートフォンで映像や写真を見ることが日常化するに従って、縦長にも横長にも対応可能となっており、今はむしろ、縦長の画角を魅力的に見せることが問われている。Instagram配信のドラマ『デートまで』や、アイドルグループlyrical schoolが2016年に発表した「RUN and RUN」のMVは、スマホの縦長のモニターに対応した映像表現となっていたが、これらはまだ実験的なもので、縦長のスタンダードと言える映像文体は試行錯誤が続いている状態だ。堤がアナログテレビ時代に作った映像表現は、縦長の映像について考える時、大きなヒントになるのではないかと思う。
その意味でも、まだ映画とテレビの壁が高く、YouTubeすら存在しない時代に撮られた『池袋』の“タメグチの映像”は、映画もテレビもWEBもすべて当価値の映像となった今の動画アプリ全盛の映像を先取りしていたと言える。
原作者が見た『池袋』
石田衣良はシナリオ本の解説で、小説とドラマの違いについてこう書いている。
メディアが違うから、原作(寒色系シリアス)とドラマ(暖色系コメディ)のトーンは違うけれど、両者はもっとも大切な部分で共通していたとぼくは思う。
それは圧倒的なスピード感とキャラクターの立体感だ(もうひとついうなら池袋という現実の街のライブ感)。ぼくも作家なので、文体にはかなり気をつかう。IWGPでなにを一番大切にしているかというと、人物の描写と文章のスピード感なのだ。それを宮藤さんは即興性豊かな組み立てと特異なコメディセンス(その場の思いつきともいう、だがなんと切れ味のいい思いつきか)でしっかりと再現してしまった。(6)
石田はドラマ化に際して「小説とテレビではメディアが違います。原作に気兼ねなどしなくていいから、とにかく思い切りフルスイングしてください。そうしたら空振りだって納得できますから」(7)と磯山に伝えたそうだが、ドラマ版『池袋』と小説を比べると、物語の流れは大筋では同じだが、細部が微妙な変更が施されており、その改変の仕方が見事だというのが当時の印象だった。
のちに数々のオリジナルドラマを手がけることになる宮藤だが、本作は原作モノだったこともあり、作家性に関してはまだ未知数だったが、まずは優秀なアレンジャーとして、その才能を大きく印象づけたと言えよう。
「ダサさ」をまとうことで見えてくるもの
原作の改変ポイントは多数あるが、中でも大きく変わったのは主人公のマコトの造形だろう。小説はマコトの一人称で進むハードボイルド小説の構造となっている。台詞もカッコよくてクールだ。
それをドラマ版では工業高校上がりの馬鹿なヤンキーで素人童貞という側面を強く打ち出している。
原作小説の第1巻が発売されたのは1998年、ドラマ化されたのは2年後だが、最先端の都市の風俗(ストリートカルチャー)というものは、活字になった時点でどんどん古びてしまう。
小説の『池袋』もその側面は強く、情報の鮮度という意味ではドラマ版は圧倒的に不利である。また、小説では成立したカッコいい語りも生身の人間が喋ったら台無しになることも多い。仮に小説をそのまま映像化していたら目も当てられない作品となっていただろう。
だが、宮藤の脚本はカッコよく書かれていた石田衣良の世界を少し斜めから見て、あえてかっこ悪く──宮藤がドラマ内で用いる言葉で言うなら「ダサく」──することで、物語を読み替えていった。
それはそのまま、トレンディドラマで描かれていたような匿名性の高いおしゃれな街としての東京ではなく、地元(ジモト)としての池袋という、具体的な土地の持つ固有性を打ち出していくという作業だった。
宮藤の脚本は、構成がとてもごちゃごちゃしているが、一つ一つのディテールはとても具体的だ。会話の中には固有名詞がたくさん登場し、その延長で、実在するテレビ番組や芸能人が登場する。
権利関係の処理の問題もあってか、実在する商品名や固有名詞を出すことをためらうドラマは今も少なくないが、固有名詞が具体的であればあるほど、そこに描かれている人間たちの実在感は増していく。すべてのものに固有の名前があり、ワイドショーや雑誌で語られる記号としての東京や女子高生やカラーギャングではなく、くだもの屋のマコトや風呂屋のタカシといった、固有名を取り戻すことで、流行り廃りの激しい風俗の根底にある地に足の付いた感覚を取り戻したことこそが、テレビドラマにおける宮藤の最大の功績だろう。
それは人間関係の描き方にも現れている。特に画期的だったのはマコトの母親・リツコ(森下愛子)の描き方だ。
原作小説では、ほとんど描写されていないリツコのディテールはコミカルではあるが、シングルマザーながらにマコトを育ててきた母親としての優しさやたくましさが描かれていた。
のちに織田裕二主演の連続ドラマ『ロケット・ボーイ』(フジテレビ系)の脚本を宮藤に依頼するプロデューサーの高井一郎は『池袋』の脚本について「よく見ると普遍的な親子愛や友情が隠れて描かれていますよね」(8)と語っている。
小ネタで彩られたサブカルドラマとして語られがちな宮藤の作風の奥底にある本質を高井は早くから見抜いていた。それは一言で言うと、家族も含めた共同体(仲間)に対する信頼である。
1980年代のトレンディドラマ以降、テレビドラマで家族が描かれる機会は年々減っていた。橋田壽賀子・脚本の『渡る世間は鬼ばかり』(TBS系)を例外とすれば、家庭内暴力や不倫といったネガティブな形でしか家族は描かれなくなっていた。
『未成年』(TBS系)等の野島伸司のドラマは、その反動もあってか、家族再生を試みるのだが、そこで描かれたのは血の繋がらない中間共同体的なもの、『池袋』で言うとGボーイズ的な共同体だった。そういった共同体は反社会的な性質を帯びて、やがては暴走して崩壊する。それは学生運動末期の連合赤軍事件やオウム真理教の地下鉄サリン事件などに連なる、日本の疑似家族共同体の失敗の歴史の反復とも言えよう。
対して宮藤が面白いのは、一方で疑似家族的な仲間のつながりを描きながら、対立軸として血縁関係にある親子を描かないところだ。むしろ、親子も友達のように付き合ってしまうことで、今まで重々しいものだった家族という概念自体を軽いものとして扱っていたのである。
原作小説とドラマ版の大きな違い
ドラマ版『池袋』は原作小説の1巻と2巻(『少年計数機 池袋ウエストゲートパークⅡ』)のエピソードの一部と、オリジナルエピソードの7話、8話で構成されている。
物語は一話完結だが、主軸となっているのは原作小説第1巻に収録された「池袋ウエストゲートパーク」(ドラマでは第1~2話)と、第4話「サンシャイン通り内戦(シビルウォー)」(ドラマでは第9~11話)。独立したエピソードだったこの2作を一つの事件としてつなげることで、全体の流れを作っている。
小説では、絞殺魔を追い詰めるところまではドラマと同じだが、リカの殺害がヒカルに頼まれたドーベルマン山井(坂口憲二)の犯行だったことがあっさりとわかり、ヒカルに性的虐待をしていた父親に、マコトが鉄槌を食らわすことで物語は幕を閉じる。
対して、ドラマ版のヒカルは父親から受けた性的虐待の影響で多重人格となり、別の人格・ホワイトがヒカルを困らせるために山井を利用して暗躍していたことが最後に明らかになる。
BエンジェルズとGボーイズの抗争が激化するきっかけとなった松井加奈(小雪)の刺殺もシュン(山下智久)の死も、根本の原因はヒカルなのだが、面白いのはBエンジェルズを利用して池袋に勢力を広げようとするヤクザの京極会と、この抗争を利用してカラーギャングを一掃しようという警察の横山礼一郎(渡辺謙)といった大人の思惑が絡んでくるところだろう。それぞれが疑心暗鬼になって抗争が激化する中、中立であらゆるコミュニティを行き来できるマコトだけが真相にたどり着くことができるというのが物語の肝だった。
この混乱状態を描いたクライマックスは屈指の仕上がりで、今見ても面白い。一話完結ドラマとしても帯ドラマとしても秀逸だ。
だが、ヒカルが多重人格だったという描き方だけは、サイコサスペンスの亜流のような展開で、今見ても古く感じる。ここだけは悪い意味で1990年代的で、本作の大きな欠点となっている。
おそらく宮藤もこの欠点を自覚していたのだろう。劇中でトラウマという言葉を何とか茶化そうとしていたが、あまりうまく描けていない。ヒカルやリカといった女性の描き方は、男からみた女の理解できない部分を抽出した描き方だ。まだアイドル女優という印象が強かった加藤あいに、ギャルっぽい少しおバカな女の子を演じさせることで生々しさを生み出していた。つまり、マコトの視点でみれば女という時点で理解不能な怪物なので、多重人格という余計な要素はいらなかったと思うのだ。
本作のホモソーシャルな男たちの共同体に女が入り込み、色恋沙汰が起きることでグループに不協和音が起きるという構造は、後のクドカンドラマで繰り返し描かれることになるのだが、基本的に宮藤のドラマは男女の恋愛よりも仲間同士のつながり、それも異性を排除した共同体に理想を投影している。
茶化してはいるものの、宮藤のドラマには家族や地縁共同体といった仲間という単位のつながりに対する信頼がある。対して、学生運動の挫折を経由した堤は、共同体よりも個人の美学、もしくは恋人同士という二者関係に対する信頼の方が強いのだろう。最終的に『ケイゾク』がメロドラマに向かったことを筆頭に、彼の代表作の多くが男女のバディモノであることからも明らかだろう。
堤幸彦と宮藤官九郎の違い
そんな堤の立場が投影されていたのが、おそらく池袋西署の署長・横山だ。
小説版の横山は「サンシャイン通り内戦」で初登場するのだが、マコトとは子供の頃から面識があり近所のお兄さんだった。マコトに対しては警察内部の仲間という感じで刑事の吉岡(きたろう)と役割はあまり変わらない。
対してドラマ版の横山は池袋の外からやってきた男である。最初はマコトといっしょに馴れ合っていても、いざ、事件が起こると警察として容赦なく取り調べをする。マコトとは共闘関係にあるが、いつ対立してもおかしくない緊張感が横山とマコトの間にはあり、最終的には抗争を利用してカラーギャングを一掃しようとする。
この緊張感を高めているのが渡辺謙のシリアスな演技だ。
若手俳優や小劇場系の俳優が宮藤の日常会話のノリに近い台詞をノリノリで喋る中、渡辺謙の演技は宮藤の会話劇のリズムにあえて乗ってこない。大河ドラマ『独眼竜政宗』(NHK)の主演を筆頭に時代劇の出演が多い渡辺は、はっきりとした滑舌で丁寧な日本語を喋る。現代劇に出ると堂々たるたたずまいが違和感をもたらすのだが、その存在感自体が若者の町である池袋でGボーイズに対して苛立ちを抱えている横山の在り方とリンクしている。
おそらく横山は、当時、40代だった堤の分身としての側面が大きかったのではないかと思う。
その意味で、堤が本作で一番やりたかったのはクライマックスのカラーギャングの抗争とその騒動を利用しようとする警察やヤクザたちという大人と子供の対立だろう。
西口公園で果たし合いをおこなうGボーイズのリーダー・タカシ(窪塚洋介)と、Bエンジェルズのリーダー・京一(西島千博)を警察が取り囲むビジュアルは、浅間山荘事件のような立てこもった若者たちを機動隊が取り囲むビジュアルを彷彿とさせるものがある。
カラーギャングの若者たちは、堤が『ぼくらの勇気 未満都市』等で描いてきた子供たちの共同体をアップデートしたもので、その根底にあるのは学生運動の記憶だろう。だから彼らは最終的に警察とヤクザという大人たちの思惑によって潰されそうになる。
一方、宮藤と磯山がやりたかったことは、マコトと仲間同士が楽しくつるんでいる場面だったのだろう。磯山は『池袋』について以下のように語っている。
(引用者注:『池袋』は)カラーギャングの抗争が描かれるんですけど、私はあまり暴力的なものは好きではないのでだんだんきつくなっていって、原作がなかったら絶対最後までできなかったなあというのがあったんですね。とにかくハードなハンサムシーンが満載で(笑)。で、そうなることが分かっていたので途中の7話と8話はなるべくくだらなくて楽しい回にしようと宮藤くんと言ってたんです。(9)
『池袋』第7話はマルチ商売にハマっている母親をマコトが何とか脱会させようという話で、第8話は、マコトの親友のマサ(佐藤隆太)が15歳の女子高生を妊娠させてしまい、仲間のギャルたちから慰謝料を請求され、マコトたちが慰謝料を稼ぐために奮闘するという話だ。どちらも、宮藤が執筆したオリジナルエピソードだ。この二つのエピソードの手応えから『木更津キャッツアイ』は着想されたのだが、確かに宮藤が後に描くことになる仲間同士でドタバタしている楽しさはこの二つのエピソードに強く現れている。
逆にクライマックスにおけるカラーギャングと警察の抗争や、横山とマコトの間に流れている、大人と子供の緊張関係は後の宮藤の作品からは消えていくものだ。
表面上は対立していても、宮藤のドラマにおいて父親や母親は戦い乗り越える存在ではなく、友達のような存在で、時に子供以上に弱くて情けない姿をさらけ出す。こういう友達親子的な感覚は、年代が下るほど、現実にも多くなっているのだろう。
例えば、漫画やロックンロールは、かつては大人の理解できずに忌み嫌う表現として、ポップカルチャーを愛好する若者たちの文化的なアンデンティティとなっていた。しかし今や、親世代の多くがポップカルチャーを享受して過ごしてきた世代であり、父親の本棚にあった手塚治虫の漫画やビートルズのCDを幼少期から享受してきた世代が、当たり前のものとなってきている。藤圭子の娘の宇多田ヒカルがデビューしたのは1998年。古谷一行の息子の降谷建志がリードボーカルと務めるミクスチャーロックバンドのDragon Ashがヒップホップを取り入れてブレイクしたアルバム「Viva La Revolution」を発表したのが1999年だと考えると、その時期からJ-POPにおける二世ブームは始まったのだろう。こういった文化的基盤があったからこそ、2000年代に宮藤が受け入れられたのだ。そして、2013年に連続テレビ小説『あまちゃん』(NHK)で国民的ヒットを記録したのは、そういった友達親子的な世代が現れる時代の変わり目を、彼が記述してきたからだろう。
そんな宮藤と比較した時に堤の持つ1950年代生まれの学生運動を経由したがゆえに、常に大人と子どもは対立するものだと捉える堤の屈託は、やや古臭いものに見えてしまう。
その意味で、『池袋』は堤が描いてきた学生運動の挫折が招いた共同体への不信感と、後に『木更津キャッツアイ』で展開される2000年代的なマイルドヤンキーの空気感が同居している奇妙な作品となっている。
前述した対談において、宮藤と堤は意気投合しており、『池袋』もお互いに描きたいことの棲み分けがうまくいったと語っている。また、撮影自体がアドリブや俳優のアイデアを積極的に取り入れたものとなっており、宮藤の脚本に堤の演出が加えられ、そこに現場で生まれた台詞が付け足されていくという形となっていた。最終話でマコトが叫ぶ「ブクロさいこー!」という台詞も、現場で生まれたアドリブだったという(10)。宮藤は本作について「お祭りだって思ってた」(11)と語っており、堤や俳優陣がいろいろと要素を足していく状況をむしろ楽しんでいたようである。
その意味で、作家性における対立やわだかまりはなかったようだが、『池袋』のSPドラマ「スープの回」の後、脚本家として宮藤が堤と組んだ作品がない(役者としては『ご近所探偵TOMOE』(WOWOW)に出演)。一方、磯山晶も堤とはSPドラマ『四谷くんと大塚くん/天才少年探偵登場の巻』以来、組んでいない。これは、堤と宮藤✕磯山の資質が似ているようで核にあるものが違うものだったからかもしれない。
窪塚洋介の遍歴──『池袋』から分岐した第3の流れ
『池袋』を経由して宮藤と磯山は『木更津キャッツアイ』以降のクドカンドラマへと向かい、一方の堤幸彦は『池袋』で掴んだオールロケ撮影と小劇場的な俳優同士の即興性の高い芝居を『TRICK』(テレビ朝日系)に持ち込むことになる。また本作で本格的に開花したと言える堤のヤンキー性はマコトを演じた長瀬智也が主演を務めた、ヤンキー上がりの新米医師を主人公にした植田博樹プロデュースのドラマ『ハンドク!!!』(TBS系)へとつながっていく。
大きく分けるとこの二つに分類されるのだが、もう一つ注目すべきは、本作でGボーイズのリーダー・タカシを演じた窪塚洋介の動向だろう。
『池袋』で注目を浴びた窪塚洋介はこれ以降、映画やドラマで引く手あまたとなり、またたく間に主演級の若手俳優として頭角を現すようになる。
中でも転機となったのは行定勲監督が宮藤官九郎脚本で映画化した『GO』だろう。本作で窪塚は在日コリアンの杉原を演じた。
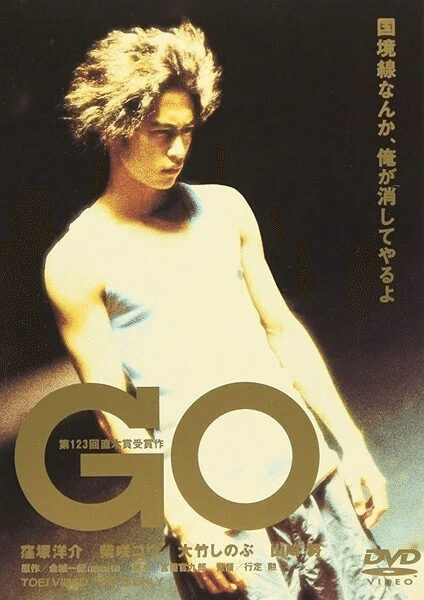
▲『GO』(2002)
直木賞を受賞した金城一紀の原作小説を映画化した本作は『池袋』で見せた窪塚の魅力をより活かした青春ドラマで、何より身体能力の高さに圧倒される。
本作は在日差別という題材をテーマにしながら、社会問題として声高に主張せずに、ポップな青春映画として描いていたのが新しかった。
差別の問題は、杉原が日本人の恋人とセックスをする時に自分の生まれを告白したところ、「韓国人や中国の人と付き合っちゃダメだ。」「中国や韓国の人は血が汚い」とパパに言われていたと言って拒絶された時、はじめて露わになるという形で描かれていた。(12)
本作の成功によって、宮藤の脚本はもちろん、窪塚の演技も高く評価されたのだが、本作に出演したことは、アイデンティティの問題において窪塚に大きな影響を与えた。
その後、窪塚は俳優の傍ら、文化人として発言するようになっていくのだが、その過程で杉原が「在日コリアンとしての自分」に悩んだように、「日本人としての自分とは何者なのか」と考えるようになり、ナショナリズムに傾倒する。そして企画段階から大きく関わった映画『狂気の桜』で主演を務めることになる。

▲『凶気の桜』(2003)
ヒキタクニオの同名小説を映画化した本作は『池袋』のタイトルバックに参加していた薗田賢次が監督だ。物語はネオ・トージョーというナショナリスト団体を結成した3人の若者、山口進(窪塚洋介)、小菅(須藤元気)、市川(RIKIYA)が、“本当の日本を取り戻す”ために、堕落した日本人(ギャルやヤンキー)に暴力で制裁を加えていくのだが、やがて右翼系暴力団の抗争に巻き込まれていく。
本作で窪塚は坊主頭に白い衣装で登場する。無軌道な若者たちの暴力を描いたという意味では『池袋』で演じたタカシを彷彿とさせるが、タカシと山口が決定的に違うのは思想の有無だろう。
タカシに思想はない。あるとすれば「悪いことすんなって言ってるんじゃないの。ダサいことすんなって言ってるの」(池袋『第7話』)という美意識だけだ。
この「ダサい」という言葉は、宮藤のドラマで反復される言葉で、『池袋』では、若者から見たかっこ悪いことという意味合いで使われていた。それが『あまちゃん』になると、使われ方が変わってくるのだが、おそらく同じ意味合いで使われるのがマコトの口癖の「めんどくせー」である。複雑な事件が起こる度にマコトは「めんどくせー」と言いながら、事件解決に赴くのだが、最終的にタカシから「めんどくせーの好きなんじゃん」と言われる。
おそらく宮藤の中で「ダサい」という言葉の意味は「めんどくせー」と同じように二重の意味があり、「笑い」と並ぶ、彼の中にある明文化されない思想のようなものだ。
これを深く掘り下げず、家族や地元で楽しく過ごせるマイルドヤンキー的な感性こそがクドカンドラマの強さなのだが、ここで「ダサい」という言葉に安住できずに、それ以上の生きる意味をタカシが求めてしまうと、『GO』の杉原や『狂気の桜』の山口になるのだろう。
興味深いのは右翼思想を扱っている『凶気の桜』もまた『池袋』と同様、ヒップホップを劇伴としていることだ。劇中で山口が苛立つのは腐った日本だが、その背景にあるのはグローバリズムに侵食されることで日本的文化が破壊される様。それを劇中では「アメポン」(アメリカナイズされた日本)という言葉で表現しているのだが、そのバックで流れているのがもっともアメリカ的な音楽であるヒップホップを日本人のラッパーが歌っているという倒錯は見過ごせない。これは『池袋』で描かれた地縁共同体や家族の復活とは地続きであり、日本のヒップホップが抱える、もう一つの側面である。
それにしても今回、『GO』と『狂気の桜』を改めて見直したのだが、当時、真逆の作品と言われた本作の印象は驚くほど似ている。一方は在日韓国朝鮮人の青春、一方はナショナリズムに傾倒する日本人青年の青春を描いており、思想的には真逆のものに見えるのだが、どちらも根底にあるのは若者のアイデンティティに対する不安であり、「自分が何者か知りたい」という自分探しの欲求である。
むしろ、極右思想にかぶれる山口が大人たちに良いように利用されて滅びゆく姿を描いているだけ『凶気の桜』の方が教育的だとすら思う。
陳腐な表現になるが、おそらく窪塚洋介は憑依体質の俳優なのだろう。彼自体は空っぽの器で、自分探し的な求道者でもあるため、演じる役に同一化して大きな影響を受けてしまう。『狂気の桜』では、不良と戦っている時に、仮面ライダーV3に山口が同一化する場面が唐突に描かれるが、このシーンを見ていると彼にとって同一化できれば極右思想でも仮面ライダーでも何でもいいのではないかとすら思えてくる。
だが、どんな思想やスピリチュアルに没入にしても、窪塚本人には何もないためか、毎回、過剰な肉体性は感じるのだが、どこか空虚さが漂っている。
この肉体性はマコトを演じた長瀬智也のものとはまったく違うものだ。長瀬の身体性が、かつて三船敏郎や萩原健一が体現していたような野獣的身体性だとすれば、窪塚の身体性は漫画やアニメの役をそのまま演じても違和感がないような、どこかツルンとしたキャラクター的身体性だろう。
そんな何もない空虚さを強さとして読み替えたのが『池袋』のタカシと宮藤官九郎が脚本を手がけた『ピンポン』で演じた卓球選手のペコだった。

▲『ピンポン』(2002)
松本大洋の人気卓球漫画を2002年に映画化した『ピンポン』の監督は『池袋』でCGを担当していた曽利文彦。CGを駆使して漫画の卓球シーンを巧みに再現しようとする本作は、ある種、原作漫画以上に漫画的な映画だが、窪塚が演じるペコはそこに違和感なくハマっていた。
本作もまた『池袋』から派生した一つの流れだと言える。
当時の窪塚洋介の姿を痛々しい自分探しだったと退けることはたやすい。しかし、彼の遍歴もまた、『池袋』から派生したものであると同時に『池袋』では回収できなかった当時の若者のシリアスな心情だったのだろう。2003年に放送された『池袋』のSPドラマ『スープの回』に登場したタカシは、修行僧のような姿で全世界を放浪しているということになっている。王様(キング)ラーメンというラーメン屋をGボーイズの仲間と始めたので、究極のスープを作るために究極のダシを求めて全世界を旅しているというギャグだが、修行僧のような窪塚の姿は『池袋』以降に窪塚が辿った痛々しい遍歴が反映されているように見えて、妙に生々しいものがあった。

2004年。窪塚はマンションから飛び降りる。 転落理由について窪塚は「覚えてない」と、真相は語っていない。一命は取り留め、1年後、俳優業に復帰した。2000年前半にあった圧倒的なカリスマ性は、ここで途絶えたが、その後も俳優としての評価は高く、2016年にはマーティン・スコセッシの映画『沈黙-サイレンス-』でハリウッド映画デビューを飾っている。また、2019年にはBBC×Netflix制作の海外ドラマ『Giri/Haji』に出演し、国内外で高く評価される俳優に成長している。
(了)
【公式オンラインストアにて特別電子書籍つき限定販売中!】
ドラマ評論家・成馬零一 最新刊『テレビドラマクロニクル 1990→2020』
バブルの夢に浮かれた1990年からコロナ禍に揺れる2020年まで、480ページの大ボリュームで贈る、現代テレビドラマ批評の決定版。[カバーモデル:のん]
▼著者プロフィール
成馬零一(なりま・れいいち)
1976年生まれ、ライター、ドラマ評論家。テレビドラマ評論を中心に、漫画、アニメ、映画、アイドルなどについて、リアルサウンド等で幅広く執筆。単著に『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)、『キャラクタードラマの誕生 テレビドラマを更新する6人の脚本家』(河出書房新社)がある。
(1)【テレビの開拓者たち/植田博樹】「地上波のドラマもできるし、ネットで見ても面白い、というドラマを作るのが理想」(2/3)https://thetv.jp/news/detail/141714/p2/
(2)堤は『クイック・ジャパンVol.35 (2001年2月発売号)』(太田出版)の「特集・宮藤官九郎」に寄せたコメントで、小劇場演劇のセンスに憧れ、ナイロン100°や大人計画のセンスを盛り込もうとしたが、中々うまくいかなかったと語っている。
(3)松尾洋一『テレビドラマを「読む」』(メトロポリタン出版)より)「タメグチの映像 ──堤幸彦ワールド『池袋ウエストゲートパーク』にみる仮説」
(4)伊藤愛子(『視聴率の戦士』(ぴあ)「堤幸彦 制約への反発からたどり着いた堤的ドラマの撮影方法」
(5)堤幸彦『堤っ』(角川書店)「お笑い社会派×宮藤官九郎」
(6)(7)宮藤官九郎『宮藤官九郎脚本 池袋ウエストゲートパーク』(角川書店)「風を切ってフルスイング 石田衣良」
(8)『クイック・ジャパンVol.35 (2001年2月発売号)』(太田出版)「特集・宮藤官九郎」
(9)『木更津キャッツアイ 日本シリーズ公式メモリアルブック』(角川書店)「GAME1 [リーグ戦]2002.1.8-2002.3.15 『西船橋死ぬ死ぬ団』はいかにして『木更津キャッツアイ』になったか?」
(10)宮藤官九郎『いまなんつった?』(文春文庫)「2008年9月11日号」
(11)堤幸彦『堤っ』(角川書店)「お笑い社会派×宮藤官九郎」
(12)もう一箇所指摘するとしたら、チマチョゴリを着た韓国人の学生にいじめられっ子の高校生が罰ゲームとして告白させられる場面。ここで杉原の友人が女性をかばおうとしたところ、ナイフで刺されて命を落とす。ビジュアルのインパクトこそあるが、差別を糾弾しようとして描いたという印象は薄く、「唐突に訪れた親友の死」の前フリ以上には機能していない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
