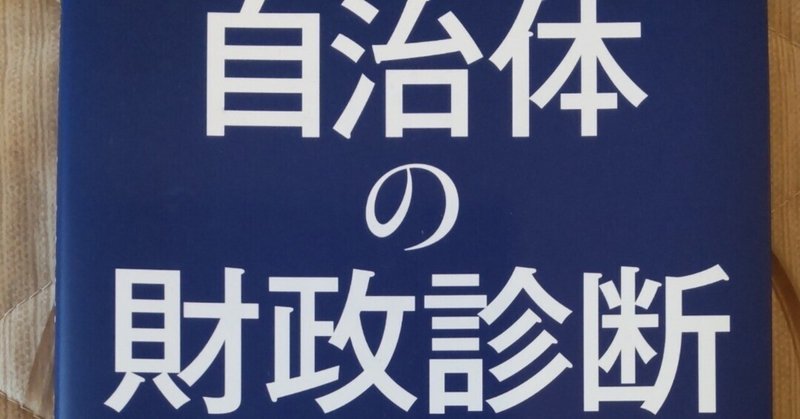
No.275【令和5年9月定例市議会一般質問原稿】
9番議員会派市民協働の脇本啓喜でございます。
通告内容に入る前に、私がSNS等で《食い逃げ》との表現をしたことに関する謝罪要求についてお応えします。パワハラもセクハラも同様ですが、受け手がそう感じるのであれば、つまり私の主張がどうであれ不快に感じられた方がいらっしゃるのであれば、真摯に反省しなければならないと思いますので、その方に向けて謝罪申し上げます。申し訳ございませんでした。
続いて、議会初日に上程されました高レベル放射性廃棄物最終処分場誘致に関する8件の請願をめぐる採決結果について所見を述べます。
採決の結果、文献調査の受け入れさえ反対議員が8名、最終処分場誘致までも賛成議員が10名となり、最終処分場誘致はもちろん文献調査の受け入れさえも反対する多くの市民がいらっしゃるにもかかわらず、そのご期待にお応えできなかったことにつきまして忸怩たる思いであり、大変申し訳なく、この場をお借りして深くお詫び申し上げます。
この上は、議会最終日の比田勝市長が文献調査受け入れ拒否を表明なさることを、切に要望します。
さて、ここから通告に従い質問を始めます。
一昨日、小島議員は一般質問で、対馬市が掲げるSDGs推進の理念を市民に浸透させられていたならば、高レベル放射性物質最終処分場誘致をめぐる動きは、そもそも発生していなかったのではないかと主張なさいました。私も小島議員ご主張に強く共感を覚えました。
最終処分場誘致推進派は、対馬市の財政逼迫を誘致賛成の理由の一つに挙げていらっしゃいます。確かに、自治体債務総額を単純に自治体人口で割った対馬市の一人当たり債務額は全国ワースト3位です。しかし、ぼんやりとしたイメージではなく、データはもちろん表面的データからだけでは把握し難い事情をも踏まえた真の対馬市の財政状況をわかりやすく市民に伝える必要があると私は思います。
対馬市の現在の財政状況はお世辞にも潤沢であるとは言えませんが、巷で囁かれている「対馬市は第二の夕張市になるのではないか」との心配には及びません。
なお、誘致推進派は文献調査に伴う交付金で活性化を図ることがチャレンジであり、交付金が無ければ対馬は現状維持に陥り座して死を待つかのようだと主張しているようです。しかし、対馬は行政も民間も既に交付金頼みの体質が進んでおり、その体質から少しでも脱却するために、市民協働で自立の島を目指すことこそが、チャレンジであると私は認識しています。
つまり、以下に挙げる財政規律に基づく財政政策や正確なデータ分析と客観的事実に基づいた政策立案を実施し、適時適正な検証を実施して政策見直しを繰り返すことで、高レベル放射性廃棄物質最終処分場を敢えて誘致するに及ばないと、市民及び誘致推進派議員各位にもご理解頂けるよう、今回の質疑応答に臨みたいと思います。
1.財政規律に基づいた財政政策・正確なデータ分析と客観的事実(エビデンス)に基づいた政策立案の実施について質問致します。
ここ数年、財政秩序が疑われるような予算計上が見受けられます。各種計画については、財政規律や正確なデータ分析とエビデンスに基づいた事業への考察が充分に行われているようには思えません。この際「財政構造見直し」や「財政基盤強化」と「財政構造の改善と健全性維持に向けた財源確保と経費縮減」に具体的に取り組むための『財政規律ガイドライン』を作成し、財政の健全性維持への意識改革を図るつもりはないか市長の答弁を求めます。
2.対馬市におけるデジタル市役所の構築について質問致します。
国のデジタル庁の発足とデジタル田園都市国家構想の発表以来、全国の自治体で「デジタル市役所の構築」に向けた取組みが広がっています。
この流れは、行政情報や様々な行政手続きのデジタル化とオンライン化によって住民サービスや行政の効率化を格段に向上させられると認識しています。
行政事務のデジタル化による行政経費の大幅な削減や職員の働きやすい環境整備にもつながり(働き方改革)そのプロセスや成果を市民や地元企業に提供することにより、企業活動の後押しや誰一人取り残さない暮らしやすい対馬の実現に向けた取り組みへとつながるものと認識しています。
対馬の強みである全島・全集落に張り巡らせた光ファイバー網を使い国境離島のアナログの島から自然や歴史・文化と調和した市民が暮らしやすい対馬を創り上げることができると考えますが、デジタル市役所構築の要となる「市のデジタルトランスフォーメーション」の進捗状況と今後の展望について市長の所見を求めます。
【再質問】
1.財政規律に基づいた財政政策・正確なデータ分析と客観的事実(エビデンス)に基づいた政策立案実施については、2つに分けて質疑応答を進めさせて頂きます。
⑴「財政構造見直し」や「財政基盤強化」と「財政構造の改善と健全性維持に向けた財源確保と経費縮減」に具体的に取り組むための『財政規律ガイドライン』を作成について
データは、その見方によって内容が全然違って見えてきます。確かに対馬市の財政は決して潤沢とは言えませんが、借金の中でも特別交付金の償還率が高い借金が多かったり、合併特例債等の優位な債務の残高が多いなど、対馬市はそのことに配慮した借り入れをしていると言うことが、市長の答弁から市民の皆様にも伝わったと思います。
次に、⑴の改善のための具体的手法としては、以下のようなことが考えられると思います。
①指定管理の見直し・撤廃
②公共施設の縮充(詳細は次項のデジタル市役所で触れる)
③その他物件費の削減
④各種補助金支給事業採択基準の厳格化
⑤外郭団体から外れた一般社団法人や一般財団法人への運営費補助支出の根絶
⑥雞知地区のコンパクトシティ化による島民の島外流出抑制
その中から、①④⑤について再質問致します。
①湯多里ランドの指定管理者は、今年度契約期間満了による入札が執行され、島内企業から島外企業に代わりました。市長がよく仰られている地域循環経済の好循環を生み出すといった考えからすると疑問です。今後も、島外企業との指定管理契約を粛々と締結していくのかについて市長の答弁を求めます。
④小職から予てより要望をしていましたが、国の方針もあって新規ビジネス支援補助金や雇用拡充支援補助金の支給を審査する委員会には、金融機関からも委員として参画頂くようになっています。指定金融機関の行員が、指定を受けた自治体に異を唱えるのは憚るところがあるでしょう。しかし、補助金支給対象事業者へ、当該金融機関からこの事業への融資を条件とすれば、厳格な審査となるのではないでしょうか。
⑤一般財団法人対馬市農業振興公社に対して、そば道場や伝承館のコロナ禍による経営不振を理由に令和5年度対馬市一般会計予算から445万円の運営費補助金が支出されています。令和5年3月31日現在、貸借対照表流動資産の現預金及び預金は23,337,640円と固定資産の特定資産の預金は44,500,000円も保有しています。また、経営困窮を理由に運営費補助まで受けておきながら従業員給与を増額していることに市民の納得が得られるか疑問です。
例えば、市が公社へ対州そばの生産拡大に向けた事業委託に伴う事業費補助金支出は当然適法です。しかし、通常民間企業が経営困難に陥ったからといって簡単に運営費補填をしないのと同様に、民間企業たる一般財団法人に運営費補助金は支出すべきではありません。
このことについては千葉県成田市が『団体運営費補助金の見直しのための方針及び基準について』という大変素晴らしいガイドラインを作成されています。少々長いですがゆっくり読み上げますので、後ほど市長あるいは総務部長の所見を求めます。
抜粋
2.見直しの方針
令和2年度における団体運営費補助金の見直しに当たっては,次の3つの方針により見直しを行います。
(1)ゼロベースの見直し
団体運営費補助金においては,一度予算化されると,当初の目的が相対的に低下した場合であっても,廃止等の抜本的な見直しが出来ず,長期にわたり継続して交付する傾向があることから,ゼロベースでの見直しを実施することとします。
なお,財務会計上,自己負担能力があり,自主的な運営が可能と認められる団体に対する運営費補助金は,原則として廃止(段階的な縮減を含む。)する方向で検討します。
(2)事業費補助金への転換
各種団体の運営費については,本来,会費などの自主財源で賄うべきものです。団体の設立時には自立を促すための補助が必要となる場合はありますが,団体の運営が軌道に乗った段階において,当該団体が実施する公益上必要とされる事業に対して補助すべきものと考えます。そこで,今回の見直しにおいて,団体運営費補助金から事業費補助金への転換を促進するものとします。
(3)終期の設定(サンセット方式)
交付団体の設立時には,運営基盤が脆弱であることから,自立できるまでの間,団体の運営費に対して補助することがありますが,公益上の必要を認め,一度補助金を交付してしまうと廃止をすることは困難となります。
また,社会経済情勢や本市をとりまく環境の変化に伴い,市民ニーズが高度化・多様化していることから,補助の公益性,必要性等について定期的に検証する必要があります。
そこで,団体運営費補助金については原則として終期を3年間に設定し,今回の見直しでは,令和3年度から令和5年度の補助金を対象に審査します。
令和6年度以降の補助金については,令和5年度に再度ゼロベースでの見直しを行うこととします。
【再質問】
⑵財政規律に基づいた財政政策・正確なデータ分析と客観的事実(エビデンス)に基づいた政策立案実施について
データや証拠に基づいた政策立案であるEBPMを実施するには、データ収集と分析及び総合し、市長がビジョンを示すことが必要です。
またEBPM策定に当たっては、その事業目的を達成するためのKGI(重要目標達成指標)及びその数値目標を達成するためのKPI(重要業績評価指標)の正しい設定が肝要です。
重要施策は単年度であるいは一部所のみで完結しないことがほとんどです。ロードマップを示して、庁舎内に留まらず外部との調整・連携をも図ることが求められています。更に計画の達成には、PDCAつまり、企画立案し、実行し、評価して改善する業務管理体制の構築が必要です。
具体的にはどのようなガイドラインを作るかと言えば、線引きが大事だと思います。安高田市は多額の補助金をつぎ込んだがそれに見合う成果が挙げられなかったとして観光物産協会への補助金を半額にしました。それを受けて観光物産協会は自ら解散しました。対馬市においても補助金支給団体が、その補助金受給額に見合った成果をあげているのか検証する必要があると思われます。
また、一般財団法人対馬地域商社の設立目的の主な1つは、自社ブランド以外の市内事業者の地産製品販売促進があります。どのように対馬のものを売っていくのか考えて成果をあげるべきです。そのためには、市役所内部での検証ではなく、目的に合った事業を展開しているかの外部評価導入も必要だと思います。
【再質問】
2.対馬市におけるデジタル市役所の構築について再質問致します。
【自治体DX推進の主旨】
対馬市でも、副市長を本部長として大原情報化統括補佐官を民間から招聘して、DX推進が図られていることは、6月27日に大原氏やデジタル推進課長からご多忙にもかかわらず長時間に渡り詳細に伺いました。各部署から若手職員を選抜して市役所全体にDX推進についての理解を促進しており、大原氏も手応えを感じていらっしゃるようで心強く感じました。
DX推進の目的は、単にデジタル化することではありません。DX推進によって市役所職員の事務負担が減らすことができ、職員を振興部や行政センターに戻すことが可能となります。そして、その帰還職員がそれぞれの地域に直接出向き、まちづくり支援や住民サービスの向上を図ること、それこそがDX推進の本旨だと私は思います。
これが順調に進めば、市役所本庁舎建替え費用も大きく削減可能なデジタル市役所とできます。本庁舎勤務職員を削減し、更に紙ベースの保存がほぼ不用となることでキャビネットのスペースが無くなります。本庁舎はかなりコンパクトな庁舎で済むようになります。
市の公式見解では、新庁舎建設総工費は約60億円で、30億円程度の基金を積む予定であり、現在約10億円が基金に積み立てられているようですが、上述の理由から建設予算は大幅に削減できるのではないでしょうか?
そうなれば、その大幅削減予算を対馬市の課題解決のために活用できると思われます。このことについて市長の所見を求めます。
対馬市の地理的条件を鑑みて、現場にいかないとできない仕事が滞りなくできるようになれば良い。直行直帰が可能となれば、移動時間も含めて例えば介護認定時間に費やす時間の確保や、報告書作成時間の短縮できるのではないか。また、カンファレンスもリモートでも可能となると思われます。このような分野での活用を積極的に進められたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
