
4.1. 学び方を学ぶ - 第1章 本書の読み方 - 絵と文字でビジネスを加速する方法〜ビジュアル・ファシリテーションのすべて〜(抜粋)
本書の読み方と学び方について説明します。まず、学びとは何か、どのように学ぶべきかについて考えます。次に、能力という言葉が生み出す誤った学習観について見直します。最後に、学びを加速させる4つのコツを紹介します。この章で学んだことを実践して、ビジュアル・ファシリテーションの学びを加速させましょう。
2. ビジュアル・ファシリテーションの基礎知識
ビジュアル・ファシリテーションとは、絵や文字を使ってコミュニケーションや協働を促進する技術のことです。ビジュアル・ファシリテーションには、グラフィックレコーディングやグラフィックファシリテーションなどのさまざまな手法がありますが、共通するのは、見える化することで理解や共感を深めるという目的です。
ビジュアル・ファシリテーションとは、会話や議論の内容をビジュアル(図やイラストなど)にすることで、コミュニケーションや問題解決を促進する手法です。この本では、ビジュアル・ファシリテーションの基礎知識と実践方法を紹介します。
目次
序文
本書の背景と目的
ビジュアル・ファシリテーションとは
本書の対象読者と読み方
学び方を学ぶ
ビジュアル・ファシリテーションの基礎知識
定義とメリット
歴史と背景
種類と分類
図解の基本スキル
絵心の正しい意味を知る
見えるモノをかく
似顔絵をかく
見た目をよくする
図解の応用スキル
関係性をかく
時間をかく
ビジョンをかく
ファシリテーションの基本原則と実践方法
集団の機能不全を理解する
ファシリテーションの基本原則
ファシリテーションの実践方法
脳科学やヒトの特性を理解する
ヒトの認知を理解する
そのままかくためにゲシュタルトを崩壊させる
考えるな!感じろ(無意識と受動意識仮説)
3つの意識を使いこなす
アドラー心理学
習慣化のコツ
理解することとわかりやすく伝えること
対象を理解する
抽象度を上げ下げする
ロジカルシンキングで納得してもらう
ビジュアル・ファシリテーションの活用事例
トラブルシューティングにおけるビジュアル・ファシリテーションの活用
新商品や新サービスの企画におけるビジュアル・ファシリテーションの活用
イノベーションや新事業企画におけるビジュアル・ファシリテーションの活用
本文
この記事はBingチャット(GPT-4)で自動的に生成しています。生成した内容を吟味した上で、これまでの経験や知見に基づき修正しています。また、上記の目次の書籍の一部を出力したという体で作成されています。
ご要望にお応えして、文章の割合を増やして読み物として読みやすくしました。以下に出力します。
第1章 本書の読み方
4.1. 学び方を学ぶ
この本では、ビジュアル・ファシリテーションという手法を使って、ビジネスにおけるコミュニケーションやプレゼンテーションを効果的に行う方法を紹介します。ビジュアル・ファシリテーションとは、絵や文字を使って、自分や他者の考えを整理/共有/発展させたりすることです。ビジュアル・ファシリテーションは、誰でも簡単に学べるスキルであり、ビジネスの現場で活用すれば、多くのメリットがあります。
しかし、ビジュアル・ファシリテーションを学ぶには、ただ本を読むだけでは不十分です。実際に絵や文字を使って、自分の考えを表現したり、他者とやりとりしたりする必要があります。また、ビジュアル・ファシリテーションを学ぶには、自分の学び方についても理解する必要があります。自分の学び方を知れば、学びの効果や効率を高めることができます。
そこで、この章では、本書の読み方と学び方について説明します。まず、学びとは何か、どのように学ぶべきかについて考えます。次に、能力という言葉が生み出す誤った学習観について見直します。最後に、学びを加速させる4つのコツを紹介します。この章で学んだことを実践して、ビジュアル・ファシリテーションの学びを加速させましょう。
4.1.1. 学びとは双発で認知を変えること
学びとは、自分の認知を変えることです。認知とは、自分が物事をどのように理解し、判断し、行動するかということです。認知は、自分の思考や感情や行動に影響を与えます。認知が変われば、自分の世界が変わります。
認知を変えるには、知識と経験の双発が必要です。知識とは、本や講義などから得られる情報や理論です。知識は、物事の原理や背景や構造を教えてくれます。経験とは、実践やフィードバックなどから得られる感覚や反応です。経験は、物事の具体性や現実性や影響を教えてくれます。
知識と経験のバランスをとることで、学びが加速します。知識だけでは、表面的な理解にとどまります。経験だけでは、個別的な事例にとらわれます。知識と経験を統合することで、深く広い理解ができます。知識と経験は、学びの両輪です。知識と経験をバランスよく取り入れることで、学びが効果的になります。
しかし、多くの人は、学びとは知識を増やすことだと思っています。知識が多ければ多いほど、学びが成功したと思っています。知識は、本を読んだり、講義を聞いたりするだけで増やせると思っています。知識を増やすには、暗記や理解が必要だと思っています。暗記や理解ができれば、知識が身についたと思っています。知識が身につけば、自然とできるようになると思っています。知識があれば、何でもできるようになると思っています。知識は、能力の代わりになると思っています。知識は、自信の源になると思っています。
これは、残念な考えです。知識は、学びの一部であって、すべてではありません。知識は、学びの材料であって、成果ではありません。知識は、学びの手段であって、目的ではありません。知識は、学びの始まりであって、終わりではありません。
学びを加速する考えは、知識と経験を統合することです。知識と経験を統合するには、実践とフィードバックが必要です。実践とは、知識を使って何かを行うことです。フィードバックとは、実践の結果に対する評価や反応です。実践とフィードバックがあれば、知識が深まり、できるようになります。実践によって、知識が具体的になります。フィードバックによって、知識が修正されます。
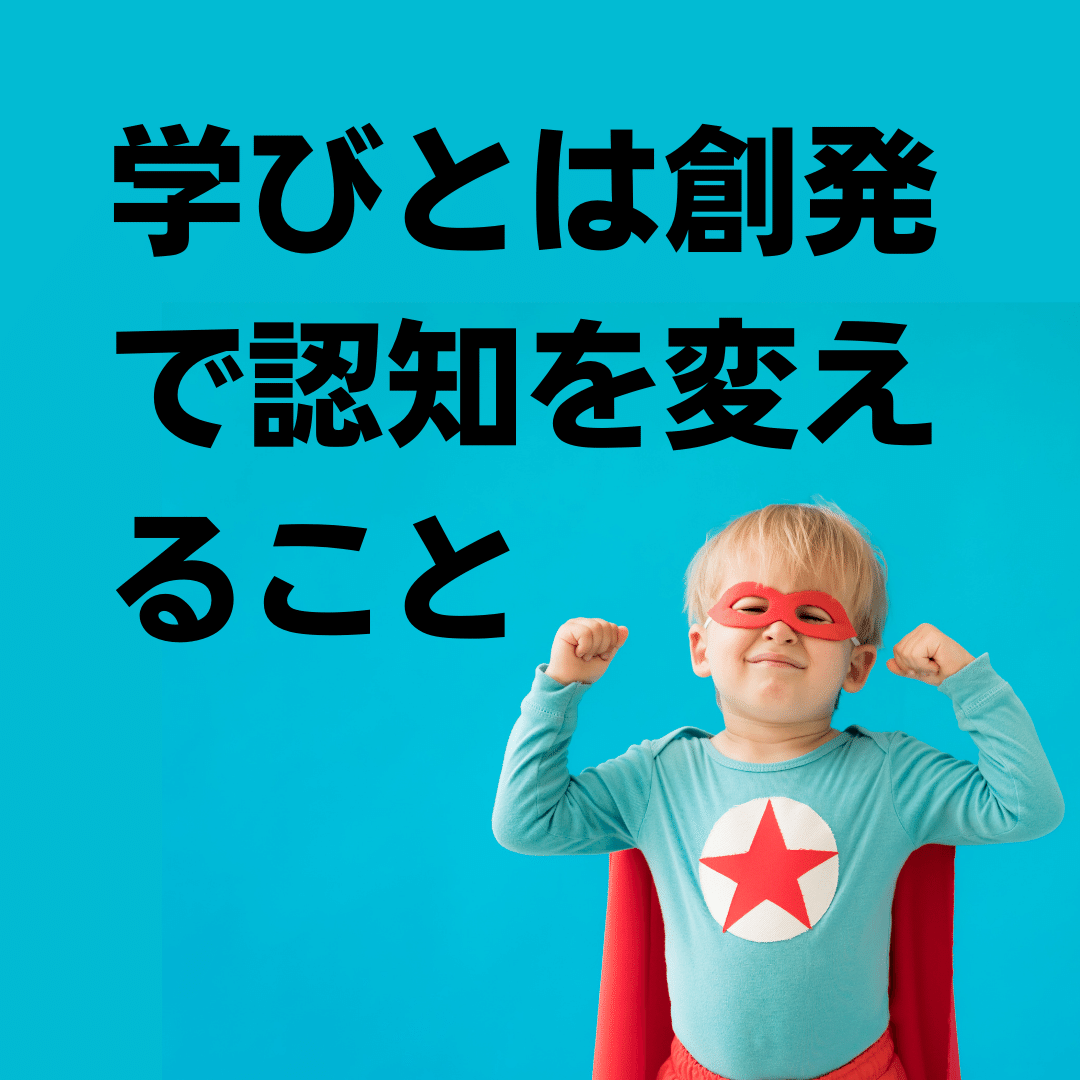
覚えておきたい言葉は、「知識は力なり」ではなく、「知識と経験は力なり」です。知識と経験は、学びの力になります。知識と経験は、学びの源になります。知識と経験は、学びの目的になります。知識と経験は、学びの終わりになります。
4.1.2. 無意識(無自覚)を使う
学びを加速させるには、知識と経験の統合だけではなく、もうひとつの要素が必要です。それは、無意識(無自覚)です。無意識(無自覚)とは、自分が意識しなくても、自動的に行われることです。無意識(無自覚)は、学びの最大の味方です。
無意識(無自覚)を使うと、学びが楽になります。無意識(無自覚)になると、意識的な努力や注意が必要なくなります。無意識(無自覚)になると、思考や感情や行動がスムーズになります。無意識(無自覚)になると、学びの効率や効果が高まります。
無意識(無自覚)になるためには、習慣化することが重要です。習慣化とは、何かを繰り返し行うことで、無意識(無自覚)にすることです。習慣化すると、学びが継続します。習慣化すると、学びが簡単になります。習慣化すると、学びが楽しくなります。

4.1.3. 習慣化する
習慣化するためには、4つのステップがあります。まず、目標を設定します。目標は、明確で具体的で達成可能で測定可能で期限があるものにします。次に、行動を決めます。行動は、簡単で具体的で毎日できるものにします。そして、報酬を用意します。報酬は、行動をした後に得られるもので、自分にとって魅力的でポジティブなものにします。最後に、環境を整えます。環境は、行動をしやすくするもので、誘惑や障害を減らすものにします。
習慣化すると、無意識(無自覚)になります。無意識(無自覚)になると、学びが加速します。無意識(無自覚)になると、学びが楽しくなります。無意識(無自覚)になると、学びが自分のものになります。
しかし、多くの人は、無意識(無自覚)は、学びに関係ないと思っています。無意識(無自覚)は、意識しないから、学びにならないと思っています。無意識(無自覚)は、自動的だから、学びにならないと思っています。無意識(無自覚)は、楽だから、学びにならないと思っています。
これは、残念な考えです。無意識(無自覚)は、学びに関係あります。無意識(無自覚)は、意識しなくても、学びになります。無意識(無自覚)は、自動的でも、学びになります。無意識(無自覚)は、楽でも、学びになります。
学びを加速する考えは、無意識(無自覚)を使うことです。無意識(無自覚)を使うには、習慣化することです。習慣化するには、目標と行動と報酬と環境を決めることです。習慣化すると、無意識(無自覚)になります。無意識(無自覚)になると、学びが加速します。
覚えておきたい言葉は、「考えるな!感じろ」です。考えると、意識的になります。感じると、無意識(無自覚)になります。無意識(無自覚)になると、学びが加速します。無意識(無自覚)になると、学びが楽しくなります。無意識(無自覚)になると、学びが自分のものになります。
4.1.4. ピークシフトを意識する
学びを加速させるには、無意識(無自覚)を使うだけではなく、もうひとつの要素が必要です。それは、ピークシフトです。ピークシフトとは、目標を高めることです。ピークシフトは、学びの鍵です。
ピークシフトを意識すると、学びが深まります。ピークシフトとは、自分の現状や平均よりも、もっと高いレベルを目指すことです。ピークシフトとは、自分の限界や満足よりも、もっと挑戦的で刺激的なことを求めることです。ピークシフトとは、自分の成長や可能性を最大限に引き出すことです。
ピークシフトを意識するためには、3つのステップがあります。まず、現状を把握します。現状を把握すると、自分の強みや弱みや課題がわかります。次に、目標を設定します。目標を設定すると、自分の方向性や意義やモチベーションがわかります。そして、行動を実行します。行動を実行すると、自分の能力や結果やフィードバックがわかります。
ピークシフトを意識すると、学びが深まります。ピークシフトを意識すると、自分の現状に満足せず、常に向上心を持ちます。ピークシフトを意識すると、自分の目標に挑戦し、達成感や充実感を味わいます。ピークシフトを意識すると、自分の行動に反省し、改善点や学び点を見つけます。
しかし、多くの人は、ピークシフトを、知らない/関係ないと思っています。ピークシフトは、難しくて、無理なことだと思っています。ピークシフトは、自分には必要ないことだと思っています。
これは、残念な考えです。ピークシフトは、学びに関係あります。ピークシフトは、難しくても、挑戦する価値があります。ピークシフトは、自分には必要なことです。
学びを加速する考えは、ピークシフトを意識することです。ピークシフトを意識するには、現状を把握し、目標を設定し、行動を実行することです。ピークシフトを意識すると、学びが深まります。ピークシフトを意識すると、自分を成長させます。ピークシフトを意識すると、自分の可能性を広げます。
覚えておきたい言葉は、「ピークシフトは学びの鍵」です。ピークシフトは、学びの力になります。ピークシフトは、学びの源になります。ピークシフトは、学びの目的になります。ピークシフトは、学びの終わりになります。
4.1.5. 段取り八分
学びを加速させるには、もうひとつの要素が必要です。それは、段取り八分です。段取り八分とは、準備をしっかりすることです。段取り八分は、学びの賢明さです。
段取り八分にすると、学びが効率的になります。段取り八分とは、学びの前に、必要なことを整理/計画/準備することです。段取り八分とは、学びの中で、時間や資源や人を有効に活用することです。段取り八分とは、学びの後に、振り返りやまとめや共有を行うことです。
段取り八分にするためには、4つのステップがあります。まず、目的を明確にします。目的を明確にすると、学びの意味や価値がわかります。次に、方法を決めます。方法を決めると、学びの手段やプロセスがわかります。そして、資料を用意します。資料を用意すると、学びの材料やツールがわかります。最後に、予行演習をします。予行演習をすると、学びの流れや雰囲気がわかります。
段取り八分にすると、学びが効率的になります。段取り八分にすると、学びの時間や労力やコストを節約できます。段取り八分にすると、学びの品質や成果や効果を高められます。段取り八分にすると、学びの問題やトラブルや失敗を防げます。
しかし、多くの人は、段取り八分は、手抜きだと思っています。段取り八分は、時間のムダだと思っています。段取り八分は、面倒なことだと思っています。
これは、残念な考えです。段取り八分は、手抜きではありません。段取り八分は、時間の節約です。段取り八分は、効果的なことです。
学びを加速する考えは、段取り八分にすることです。段取り八分にするには、目的と方法と資料と予行演習を決めることです。段取り八分にすると、学びが効率的になります。段取り八分にすると、学びをスムーズにします。段取り八分にすると、学びを確実にします。
覚えておきたい言葉は、「段取り八分、本番二分」です。段取り八分にすると、本番は二分で済みます。段取り八分にすると、本番は楽になります。段取り八分にすると、本番は成功になります。段取り八分にすると、本番は自信になります。
4.2. この章のまとめ
この章では、本書の読み方と学び方について説明しました
学びとは、自分の認知を変えることであり、知識と経験の双発が必要です
能力とは、学びの過程や成果であり、努力や環境によって伸ばせます
無意識(無自覚)を使う、習慣化する、ピークシフトを意識する、段取り八分にするという4つのコツを覚えておきましょう
この章で学んだことを実践して、ビジュアル・ファシリテーションの学びを加速させましょう
これで、第1章の抜粋は終わりです。この章では、本書の読み方と学び方について説明しました。学びとは、自分の認知を変えることであり、知識と経験の双発が必要です。能力とは、学びの過程や成果であり、努力や環境によって伸ばせます。無意識(無自覚)を使う、習慣化する、ピークシフトを意識する、段取り八分にするという4つのコツを覚えておきましょう。この章で学んだことを実践して、ビジュアル・ファシリテーションの学びを加速させましょう。
楽描きが世に浸透するための研究のための原資として大切に使います。皆様からの応援をお待ち申し上げます。
