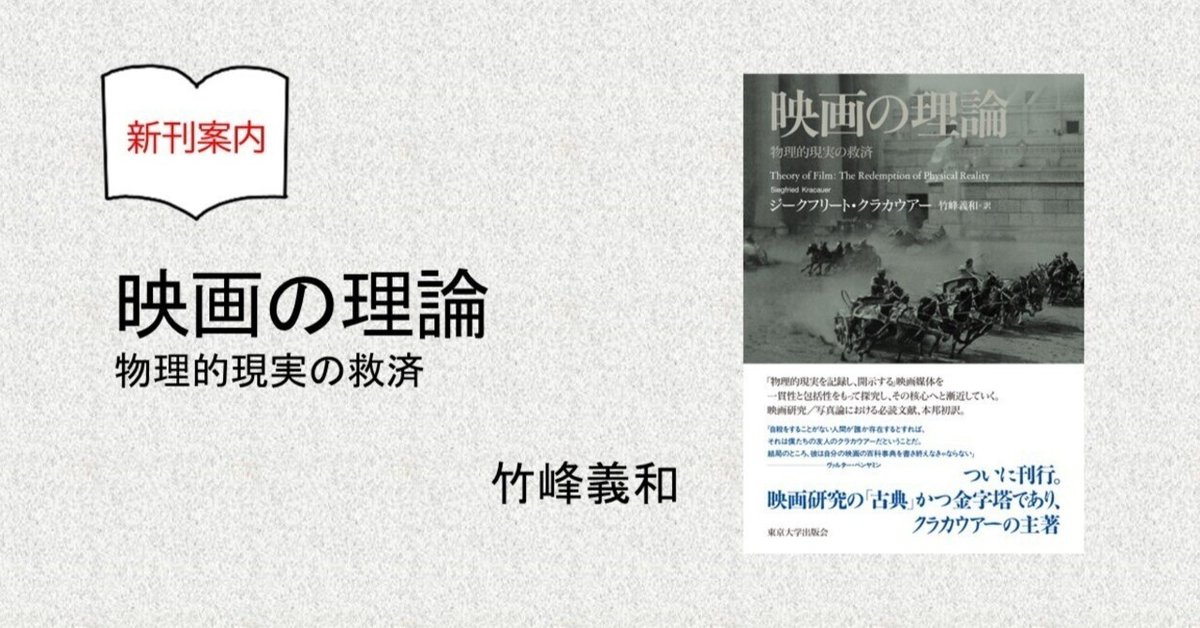
『映画の理論』──物理的現実の救済
ドイツ出身のジャーナリストで映画学者でもあるジークフリート・クラカウアーの主著である『映画の理論』の本邦初訳がまもなく刊行となります。待望の翻訳となりますが、以前に本書について竹峰先生が書かれた一文
(『映画論の冒険者たち』東京大学出版会、2021所収 ※注と原書の頁数は省略しています)を以下に公開します。本書への導入としてぜひご一読ください。
フランス亡命中のクラカウアーは、オッフェンバック論の脱稿後、映画を主題にした理論書を執筆することを計画していた。当初構想されていたのは、映画の歴史、社会学、美学を包括的に論じるという壮大なプロジェクトであり、そのための準備として、とりわけ1940年6月から翌年2月にかけて、マルセイユでアメリカ行きに必要なヴィザの交付を延々と待ちつづけるあいだに、全集版で260頁におよぶ最初の草稿──いわゆる「マルセイユ草稿」を執筆する。もっとも、「草稿」といっても、実質的には見取り図に近く、「どこへ?」「コメント」「例」「見出し語」「構成」「片付けるべきこと」という計5つの項目からなる表に、メモやキーワードが覚書的に記されたものである。そのあと、ニューヨークで『カリガリからヒトラーへ』を完成させたクラカウアーは、1940年代後半より映画理論の書物にふたたび取り組むのだが、生計を立てるために引き受けた他の仕事──アメリカの雑誌への映画評の寄稿も含まれる──の影響もあって、執筆の作業は何度も中断を強いられるのであり、ようやく1960年になって『映画の理論──物理的現実の救済』を完成・刊行するにいたる。
これまで日本では、クラカウアーの映画論が取り上げられる際──『映画の理論』の邦訳がなおも存在していないという事情もあり──『カリガリからヒトラーへ』にもっぱら焦点が当てられてきた。それにたいして欧米圏の映画研究でクラカウアーの名前に言及されるとき、『映画の理論』の著者としてであることが圧倒的に多い。そして、そこでのクラカウアーの位置づけは、映画的リアリズムの擁護者という場合がほとんどである。ごく大雑把に定式化すれば、映画表現の基礎原理をモンタージュによる人為的構成に求めるというエイゼンシュテインに代表される立場にたいして、クラカウアーは、アンドレ・バザンらとともに、現実をそのまま写し取った表現にこそ真に映画的なものが存在するというリアリズムの陣営に属する代表的な理論家として扱われてきたのである。
『映画の理論』は、原著で本文だけでも300頁を超える大著だが、そこで展開されている議論は、ひとまず〈構成主義〉対〈リアリズム〉という二項対立的な図式を完全に踏襲しているように見える。クラカウアーがまず前提として強調するのが、「映画とは本質的に写真の延長である」という点である。「写真とともに映画は、生(なま)の素材を多少なりともそのままの状態に保ちつづける唯一の芸術なのだ」。つまり映画は、ありのままの現実──クラカウアーはそれを「物理的現実」や「物質的存在」と呼ぶ──を歪めることなく表象するという基本的特性を写真から受け継いでいるのであり、このメディア的な特性に忠実であるということが映画の根本的な美的原理をなすというのである。クラカウアーにとって映画とは、何よりもまず「物理的現実を記録し、開示する[reveal]」メディアなのだ。
もちろん、写真と同じく映画でも、たんなる自然の複写に甘んじることなく、芸術的な創造力を自由に発揮しようとする試みがつねに見られる。あるいは、絵画、演劇、文学のようなすでに確立した伝統的な芸術ジャンルに由来する諸要素を積極的に導入しようとする作品も多い。映画のうちには、このような「造形的傾向」と写真に由来する「リアリズム的傾向」という、対立しあう2つのベクトルがつねに存在してきた。両者は映画史においてはすでにリュミエールとメリエスによってそれぞれ体現されていたのだが、しかしながらクラカウアーは、映画において「造形的傾向」が美的に認可されるのは、それが「リアリズム的傾向」に従属しているかぎりにおいてだと強調する。
さらにクラカウアーは、写真というメディアには4つの「親和性」──「演出されていないもの」、「偶然的なもの」、「無限性」、「不確定のもの」──が備わっており、おのれに親和する対象に引き寄せられる傾向が内在していると主張する。逆にいえば、人為的なもの、必然的なもの、有限性、確定されたものは写真の被写体として不向きだというわけである。そしてクラカウアーは、映画というメディアにたいしても、この同じ4つの「親和性」の存在を認めたうえで、そこにさらに──写真と異なり映画には時間的な運動を表象することが可能なために──「生の流れ」という新たな「親和性」を付け加える。そうした「親和性」の例としてクラカウアーがたびたび例に挙げるのが街路である。先に触れた『蠱惑の街』のみならず、ルイ・デリュックの『狂熱』(1921)やヴィットーリオ・デ・シーカの『自転車泥棒』(1948)
などを例に挙げつつ、クラカウアーはこう主張する。大都市の街路を無数の群衆が行きかうとき、そこでは思いがけない出来事や偶然の出逢いがたびたび生じるだけでなく、匿名の群衆が見せる無限にして無定形な動きそのもの
が「生の流れ」の典型的な表現になっており、それゆえに街路は「映画に相応しい」主題である、と。かつてクラカウアーがヴァイマル時代に執筆した映画時評と比べると、強調点は断片性から連続性へと移行しているが、作為的な演出や構成を拒絶し、偶然性という契機を重視するという基本方針はまったくぶれていないといえる。
『映画の理論』では、序章と第I部「基本的性格」において、以上で素描した映画メディアの「リアリズム的傾向」について集中的に論じられる。そのあとは、一般論から個別的・具体的な次元へと徐々に移行していくかたちで、第II部「領域と諸要素」では、歴史映画とファンタジー映画、俳優、会話と音響、映画音楽、観客の問題が、第III部「構成」では、実験映画、ドキュメンタリー映画、演劇的なストーリー、映画と小説の関係、物理的現実に根差したストーリー、内容という問題が順番に扱われる。このようにしてクラカウアーは、映画というメディアの根幹をなす「リアリズム的傾向」や「物理的現実」との親和性という主題をさまざまに変奏しつつ、映画の製作・受容にまつわる多様なテーマを論じていく。映画をめぐる理論的言説の歴史において、ここまでの一貫性と包括性をもってこのメディアを論じたものはほとんど類例がなく、その意味でもこの書物は映画理論の古典という位置を占めるに相応しい。また、そのなかで、演劇と映画の差異といった伝統的なトピックに加えて、オーディエンスや音響など、近年の映画研究(フィルム・スタディーズ)でとりわけ関心が高まっているトピックが取り上げられていることは、まさにクラカウアーの慧眼を示しているといえるだろう。
1960年に『映画の理論』が出版されたとき、一部に賛同や称賛もあったが、批判の声の方がはるかに大きかった。たとえば、当時アメリカでもっとも影響力のある映画批評家だったポーリン・ケイルは、『映画の理論』について、深刻な顔つきで映画について小難しい理屈をこねるだけの「偏執狂的(モノマニアック)な理論」にすぎないと酷評した。他の批評は、クラカウアーの問題提起をより真摯に受けとめているものの、とりわけ問題とされたのは、この書物の基調をなす本質主義だった。つまり、歴史的に異種混交的なメディアでありつづけた映画からその本質的特性として「リアリズム的傾向」を導出したうえで、この規範に合致しないあらゆるジャンルや作品を「非映画的」というカテゴリーに包摂するという排他的な身振りに、批評家たちの非難が集中したのである。また、旧友のアドルノは、映画を社会的側面から切り離して論じるという傾向を問題視した。そうした批判に首肯すべきところがあることは確かだが、だからといって、『映画の理論』でクラカウアーが試みようとしたことを、たんなる「ナイーヴなリアリズム」として片付けることは慎まなくてはならない。重要なのは、クラカウアーの「映画的リアリズム」が、たんなる外界の記録や〈真実らしさ〉の表象効果だけを指すものではないという点である。
クラカウアー自身がクロースアップやスローモーションを例に強調しているように、映画によって開示される「物理的現実」のうちには、カメラによってはじめて捉えることのできる世界、日常生活では知覚から零れ落ちるような世界、つまりはベンヤミンの「視覚的無意識」に相当するものが多分に含まれている。さらに、この文脈において、クラカウアーが「映画に相応しい」主題としてまっさきに規定したのが大都市の「街路」であったことはきわめて重要である。つまり、クラカウアーのいう「物理的現実」とは、何よりもまず、モダニズムによってラディカルな歴史的変容を遂げた近代都市生活の物質性にほかならず、人間と事物、時間と空間、現実と虚構のダイナミックな相互陥入のなかで顕わになる、われわれの日常世界が孕みもつ偶然的で非均質的な物質的位相にアプローチすることが、「リアリズム」の名のもとに要請されているのである。
さらに、アドルノがクラカウアーをめぐるエッセイのなかで、「リアリズム」の語源となるラテン語の「res」が事物を意味していることにあらためて注意を喚起しているように、クラカウアーの「リアリズム」とは、諸事物が織りなす物質世界の優位を認め、諸事物に徹底的に忠実であろうとする一種の倫理的な姿勢でもある。人間による恣意的な意味や価値付与、硬直した形式、さらには制約された感覚といったものに歪められたり隠蔽されたりしていないあるがままの純粋な諸事物。クラカウアーにとって、映画というメディアは、そのようなユートピア的な理念を観客の一人ひとりが身体的なレヴェルで知覚し、具体的に経験することを可能にしてくれるのであり、まさにその瞬間において、クラカウアーが「物理的現実の救済」と呼ぶものが成就されるのである。
映画史的な文脈から見れば、「偶然」や「救済」をめぐるクラカウアーの議論は、ハリウッド古典様式の基盤をなす説話的な連続性にたいする異議申し立てとして解釈することもできるだろう。ディディ゠ユベルマンが述べるように、「クラカウアーの目指す批判的リアリズムは、写真や映画の「歴史主義」が人工的に提示する連続性を断ち切ることによってしか得られない」。クラカウアーの映画美学にあって、ストーリーが「リアリズム的傾向」と相反するものでありながらも、映画作品において完全に撤廃されるべきでないのは、対象をひたすら映し出すことによってではなく、人為的に構成されたストーリーの連続性が切断される瞬間においてこそ、「ありのままの自然」が開示されるからにほかならない。つまり、「演出されていないもの」、「偶然的なもの」、「無限性」、「不確定のもの」という写真゠映画のメディア的特性に親和する契機は、それぞれに対立する契機がいったん宙吊りにされるとき、その〈中間休止〉(ツェズーア)のなかではじめて知覚されるのである。『映画の理論』という書物が、1950年代後半にスタジオ・システムが崩壊を迎えた直後に上梓されたことは示唆的である。このあと、フランスのヌーヴェル・ヴァーグのように、古典的なストーリー映画の桎梏から逃れて、オルタナティヴな表現スタイルを模索する試みが盛んにおこなわれるようになるが、クラカウアーの『映画の理論』は、まさにそうした新たな感性と呼応しているのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
