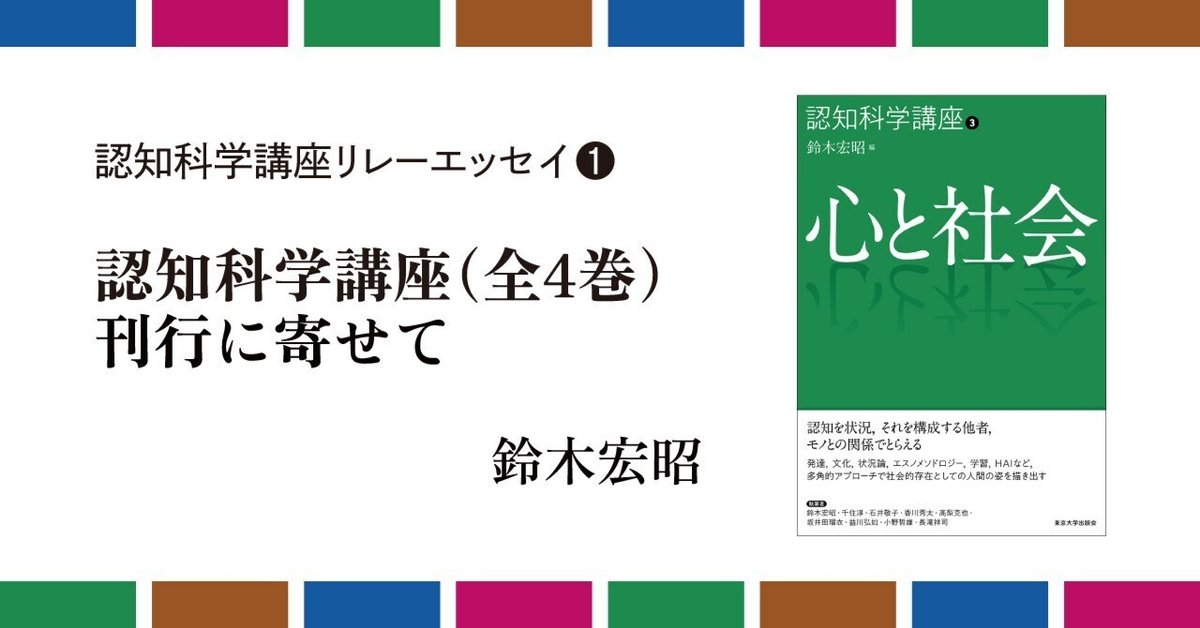
認知科学講座(全4巻)刊行に寄せて/鈴木宏昭
2022年9月から10月にかけて、「認知科学講座」全4巻が刊行された。
第1巻『心と身体』(嶋田総太郎編)
第2巻『心と脳』(川合伸幸編)
第3巻『心と社会』(鈴木宏昭編)
第4巻『心をとらえるフレームワークの展開』(横澤一彦編)
このような次第で4人の編者たちによるリレーエッセイを書く機会をいただいた。第1回目のこの小文では、認知科学に起きた大きな変化を取り上げ、なぜこの4巻になるのかも含めて、本講座との関連性について述べていこうと思う。
認知科学の第一世代――情報処理
認知科学について、もうあれこれ定義のようなことを語る必要はないと思うが、心の科学的探究を進める学問の一つとして認知科学が出現当初からだいじにしてきたことがある。それは多様性と対話だ。認知科学の発祥の地と言ってもよい米国の認知科学会(Cognitive Science Society)のロゴの中には、心理学、神経科学、人工知能、言語学、哲学、人類学、教育学の七つの学問領域が含まれている。各々の学問は長い歴史の中で独自の理論、手法を用いて人の心にアプローチしてきたが、それらを持ち寄り、対話を通して融合させ、心についての理解を深めていこうということを意味している。必ずしも統合理論を作ろうということではなく(むろんそれを目指す人もいるが)、交流によって各々の領域の探究を進展させるという意味合いも強いと思う。そこで最近はCognitive Science ではなく、Cognitive Sciences と呼ばれたりするようにもなった。
以上のように、認知科学は学際的な研究領域となっている。ただ、学際的研究というのは言うは易く、行うは難しの代表例のようなものだと思う。私は心理学出身だが、工学者、神経科学者、法学者との共同研究をしてきた。しかし、なかなかすぐにうまく行くわけではなかった。それは使っている言葉が全く異なることが大きい。単に単語がわからないという意味だけではない。言葉というのは世界を分節化するものだから、言葉が違うということは、いわゆる世界観が違うということを意味する。
1970~80年代に花開いた認知科学がこうした学際研究をめぐる難しい課題を克服したのは、情報とその処理(表象と計算)という共通言語、つまり世界観を提供し、皆がその世界観を前提として交流を進めたからと言える。その結果、人間が様々な場面で見せる多様な認知の構造、機能、発生を情報とその処理としてとらえてみる、またこれまで各々の分野で蓄積されてきた知見を情報処理の観点からとらえ直してみる、そうしたことがこの時代に活発に行われるようになった。
こうした次第で、心の中でどんなデータが、どんなプログラムによって処理されるのかを明らかにすることが、認知科学者の使命ということになっていたと思う。まさにコンピュータ上での情報処理のような形で人間の知性を記述しようとしていた。
こうしたアプローチは当時の人工知能とも相性がよかった。またこの時代の、人工知能は「おもちゃの問題(toy problem)」を抜け出し、現実の問題にチャレンジし始めた時代でもあったからである。当時のAIのコミュニティでは、人間の持つ知識を明らかにし、それをコンピュータ上に実装すればよいという考え方が基本にあり、人間の知識を明らかにするという認知科学は人工知能の研究者の多くに受け入れられ、活発な相互交流が生まれた。
第二世代の勃興1――身体の復権
しかし、1990年代あたりになると、認知科学の前提である情報処理が含む問題が、様々な領域で指摘されるようになってきた。一つは身体の問題である。第一世代の認知科学のメインストリームでは、身体は周辺的な扱いしか受けてこなかった。というのは、身体は情報の入り口と出口、つまり末端の感覚器、効果器という以上の意味を持たないと考えられていたからのように思う。これらは中央での処理とコントロールによって動く、半ば奴隷のようなものなのだから、認知科学は中央で行う情報処理を研究すればよいということである。また、中央での処理を支える知識は、まさにコンピュータのプログラムのように記号として表現され、明確なアルゴリズムによって動作すると、多くの研究者が考えていた。
ところが1990年代以降、様々な研究は、身体の状態が認知に影響を与えることを示してきた。実際、知覚的な判断、人物の評価、文章の理解、発想が求められる問題の解決など、一見身体とは無関係な様々なタイプの認知活動が、その時の身体の状態、個人の身体の形状によって変化する。また、ジョージ・レイコフたちによって生み出された「認知言語学(cognitive linguistics)」は、抽象化されたシンボルと考えられてきた言語が人間の身体に基盤を持つことを、比喩などの研究を通してきわめて説得的に論じたりもした。
物理的な身体はむろん大事だが、より大事なことは、それが行為を通して環境を変化させるという点にある。環境を変化させることにより、知覚風景は変化し、それによってまた異なる行為がとられる。このように、人間と世界は身体を通した行為によって一つのループを形成するようになっている。こうした考えはロボット科学にも取り入れられ、環境の知覚と行為が一体になった、つまり表象と計算という過程をスキップした新しい設計原理を生み出したりもした。こうした考え方は、1991年に刊行されたフランシスコ・ヴァレラたちの『身体化された心』に述べられていたものである。この本は生理学、心理学などの科学的な知見の章の後に、必ず仏教思想からの考察が述べられるというもので、当初は違和感が強いものだったが、今では「エナクティビズム(enactivism)」という形で、認知科学の中に根づいている。

こうした流れは「身体性認知科学(embodied cognitive science)」という新しい領域を生み出した。海外の大手学術出版社では、これのハンドブックが2010年以降何種類も出版されたりしている。またこうした動きは、反表象主義の立場にあったジェームズ・ギブソンのアフォーダンスの心理学の再評価、また認知科学勃興時には犬猿の仲と言ってもよかった現象学との出会いも可能にした。
このように言うと、そもそもの出発点にあった表象、計算はどこに行ったと考えられる方もいらっしゃると思う。しかし、アンチ情報処理という立場の研究との出会いによって、表象と計算という考え方はさらに強力に洗練されたものへと変化したというのが私の考えだ。初期に行われたコンピュータの情報処理と人間の認知の間のメタファーにおいては、不適切な部分が混入していたが、それが身体との出会いによって除去されたということである。たとえは悪いかもしれないが、「焼け太り」と言ってもよいかもしれない。
以上のような背景のもとで、本講座第1巻『心と身体』には、認知と身体の常識的な関係を覆す研究を主導してきた研究者7名による章に加えて、哲学において身体を復権させた現象学の研究者による章が収められている。
第二世代の勃興2――脳との出会い
第一世代の認知科学でも、脳が認知を支えるものであることには誰もが同意していたし、脳波を用いた研究、脳の損傷をベースに認知機能を研究する神経心理学という分野もそれ以前から存在していた。また、基礎的な認知過程である知覚などの研究では、脳の働きを一定程度取り込んだ研究も行われていた。ただ、これらは第一世代の認知科学の中で中心的な位置を占めるには至っていなかったと思う。
しかし、1990年代になると、認知科学と神経科学との本格的な交流が始まる。これは特にfMRIやNIRSなどの非侵襲的なイメージング技術の発展が支えたと言える。こうした技術によって、健常な人の脳を傷つけずに認知と脳の研究ができるようになった。また、これによって文字や文を読む、一定以上複雑な判断を行うなど、人間に固有な認知機能の脳内基盤に切り込むことができるようになった。こうしたことから「認知神経科学(cognitive neuroscience)」という分野も生まれた。
この分野の発展により、多くのことがもたらされた。もちろん認知機能の神経基盤を探るという重要な目標の達成に近づいたということはある。ただそれだけではない。脳のレベルでわかっていることから、認知をとらえ直すこともできるようになった。脳機能の局在性は古くから知られていたことである。たとえばブローカ野は発話機能を司ることが神経心理学などの研究からわかっていた。しかし発話とは異なる心理機能、たとえばある種のプランニングでもブローカ野が活動することから、発話とは何か、プランニングとは何かについての新しい知見が得られたりもした。また、ある認知機能を実現するためのアルゴリズムが複数考えられる時に、脳の処理と親和性の高いものを候補として挙げるなどの可能性も出てきた。

また脳科学との出会いは、研究の精度を上げることにもつながった。一般に心理学的な実験の場合には、刺激を与え、行動レベルに現れる反応を測定するというのが基本であった。しかし、刺激が与えられて、それが観察可能な行動レベルにまで変換されるには、数多くのステップが存在している。だから、ある刺激によってある種の認知的な処理が行われたのだが、それが反応にまでは影響を与えないケースがあることは容易に想像できよう。しかし、新しく開発された各種の計測機器を用いることで、行動レベルまで到達しない脳内の神経的、認知的な処理に迫ることが可能になった。これによってより微細な、詳細なレベルでの認知研究が一挙に展開し始めることになった。
本講座第2巻『心と脳』では神経科学をベースに知覚、感情、社会的認知、人類進化、意識、哲学における自然主義などきわめて包括的なトピックが取り上げられている。
第二世代の勃興3――関係性の中の知性
もう一つ1990年代に活発になったのは、関係性の中で知性、認知、人間をとらえるというアプローチである。個体内部の認知機能の解明に焦点を当てていたため、第一世代認知科学においては、関係性という視点はきわめて弱かったと思う。
1990年代あたりから始まる関係性に注目したアプローチは単一ではない。まず挙げるべきは「状況的認知(situated cognition)」だろう。人間はある状況の中で、その状況に存在する様々なモノ、道具の助けを借りながら行動している。たとえばノートをとったり、人に話したり、書籍やネットワークから情報を得たりしている。だからこれらの状況のリソースは、いわゆる認知と不可分に結びついている。そして私たちはこれらのリソースとうまくつき合えるように、徐々に自分の認知を変えたりもする。また私たちの認知はバッチ処理のように、虚空の中で、沈思黙考して認知を行い、すべてがわかった後に、スタートボタンを押して行為を実行するわけではない。少しだけわかったらまずちょっとやってみて、その具合を確かめてまた次の行為をプランする。つまり、状況とかけ合い漫才のようなことをしながら認知を進めている。このような意味で認知は「状況に埋め込まれている」。だとすれば、そうした周りのモノから切り離した純粋な(?)認知というものは、実験室内で作り出される虚構ではないのかというきわめて辛辣な批判が状況論からなされた。むろん彼らは批判だけをしたのではなく、現実の世界の中の人間の認知活動を、エスノグラフィー、エスノメソドロジー、相互行為分析などの社会学由来の方法で緻密な分析を重ね、認知の状況依存性を明らかにしてきた。

関係性のアプローチのもう一つのラインは、進化、発達にかかわるものだ。言うまでもなく人間は、系統発生的にも、また個体発生的に見ても社会を形成し、その中で生活を行っている。特殊な例外を除けば、人はロビンソン・クルーソーのような生活をすることはできない。社会からの放逐は多くの場合、その個体の死を意味するし、子どもも生まれた時にそばに誰もいなければ確実にほぼ死を迎える。だから、社会、人どうしのつながりというのは、ヒトという種にとっての適応すべき環境なのである。このようなことから、進化人類学者、動物行動学者、比較認知科学者たちは「社会脳(social brain)」と彼らが呼ぶものを生み出した。つまり、複雑な社会的環境に適した知性が系統発生的に進化するということだ。そして個体発生の過程でも、こうした知性が育まれていくわけである。こうして、対人認知、他者の心の理解などの社会的認知機能の発達研究は、自閉症児の研究ともども大きく進展した。またヒトの近縁種であるチンパンジーなどとの比較を通して、社会脳の進化に迫る研究も盛んに行われるようになった。
関係性へのアプローチの三つ目は、情報科学からのものである。第一世代の人工知能では人間並み、またはそれを超えるシステムの構築に注力が傾けられた。しかし、やはり1990年代前後から、人の認知をサポート、増幅するための人工物の開発にも注意が向けられるようになった。これは情報科学の中でも、マン・マシン・インタフェース、ヒューマン・インタフェースなどという分野を生み出した。当然、こうした研究には人の反応の分析が欠かせない。このような経緯で認知科学の研究者たちも、使いやすいデザイン、愛着の湧く人工物の開発にかかわることになった。これらは21世紀に入ると、さらにヒューマン・エージェント・インタラクション、ヒューマン・ロボット・インタラクションなどの研究として花開くことになる。
このような背景のもと、本講座第3巻『心と社会』には、社会性の発達、文化と人間、協調を基盤とする学習と教育、ロボットと人間の間のインタラクションなどのテーマについて、心理学者、対話分析研究者、AI研究者、哲学者などによる章が収められている。
第三世代へ向けて
第二世代が始まり、かれこれ30年が経とうとしている。学問は一般的に一つの場所に安住してはいない。認知科学においても身体性認知科学、認知神経科学、様々な関係論的アプローチをベースにしつつも、次の展開を狙う研究がいくつも提案されている。第4巻には、これらの中で近年活発な活動を行っている七つのアプローチを主導してきた研究者による章が集められている。

これらはまさに認知科学らしく、行動実験をベースにした心理学由来のもの、神経科学の知見に基づくもの、圏論やベイズ推論などの数理的な概念に基盤を置くもの、システム構築を目指すもの、またこれらの組み合わせなど、多様な構成となっている。これらは個別の現象の説明のためではなく、認知全般をカバーする、つまり新しい人間観を提案するものが多いのも特徴である。
おわりに
1990年代に種が蒔かれた第二世代の認知科学は、21世紀に入り大きく展開し、現在佳境を迎えている。また次の世代を目指す試みもいくつも提案されてきている。こうした成果を伝える良書はいくつも出版されてきた。ところが、こうした現状の全貌を概観できるようなシリーズは国内には存在していなかった。これが「認知科学講座」を企画した理由となる。
また出版社にかかわるもう一つの理由もある。東京大学出版会は、まだ認知科学が定着していない時代から、この学問の強力な応援団の一つであった。1980~90年代には「認知科学選書」全24巻を刊行している。1980年代に大学院生であった私はこれらの書籍によって単に知識を得ただけでなく、認知科学のスピリットに感銘したり、探究の方向もガイドしてもらった鮮明な記憶がある。「認知科学選書」は、「コレクション認知科学」として2000年代に再発行されてもいる。また、名前は「認知心理学」だが、深く関連する講座本も2回にわたって刊行している。これらのシリーズは私だけでなく、当時若手だった多くの研究者の血肉となったと思う。ところが新たなシリーズの企画はここ20年くらい全くないという状態が続いてきた。ということで、「ぜひまた応援を!」という思いを込めて企画を持ち込んだところ、快く引き受けてくださり、企画から2年、執筆依頼から1年程度で全巻刊行することができた。
この講座を通して、認知科学の展開の全貌が関連分野の方に周知され、新たな共同研究が進むこと、そして認知科学の研究を目指す学部生、大学院生が自らの研究を学問の中に位置づけるとともに、それを飛躍させることを心から期待している。
文・鈴木宏昭(すずき・ひろあき/青山学院大学教育人間科学部教授)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
