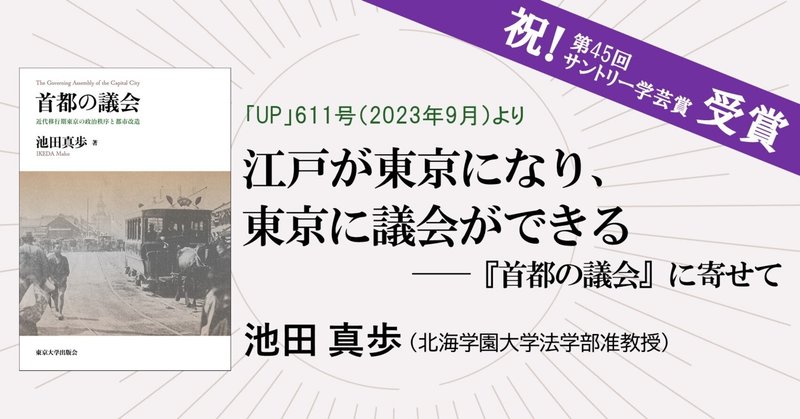
【サントリー学芸賞受賞記念!】江戸が東京となり、東京に議会ができる/池田真歩
今年3月に刊行致しました池田真歩 著『首都の議会』が、第49回藤田賞〈奨励賞〉につづき第45回サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を受賞しました。受賞を記念して、「UP」611号(2023年9月)より池田先生のコラムを以下に全文公開致します。
「首都の議会」の始動
東京都議会の前身である東京府会が開設されたのは、幕末維新期の混乱から東京が抜け出し、「開化」の先進地としての性格を強めつつある、明治12(1879)年のことであった。この東京府会に、そのさらなる前身ともいえる東京会議所(明治5年開設)と、府会から都市部の主要事業を引き継いだ東京市会(明治22年開設)とを加えて、同時代の東京人にとって新奇な機関にほかならなかった議会をめぐり、政治的な営みが始まる過程を論じたのが、筆者が3月に上梓した『首都の議会――近代移行期東京の政治秩序と都市改造』(以下「本書」)である。
明治維新の開始から20–30年間の――「江戸」と「東京」のはざかいにある「東亰(とうけい)時代」と呼ばれることもある――東京は、これまで様々に論じられてきた。だが、それらの議論のなかで、同地の議会はだいたいの場合、影がうすく、ようやく姿を見せてもその来歴がいまひとつはっきりとしない。この時期の東京をめぐる政治過程として最もよく知られているのは、この巨大な旧城下町を根本から改造して、近代都市としての機能・堅固さをそなえさせようとする首都計画(同時代的には「市区改正計画」)のそれだろう。しかし、実質的に国家事業とされた同計画の立案をめぐって、明治政府の高官たちがしのぎを削る過程に分析が集中するなか、府会はよくて脇役であった。東京の議会(もっぱら市会)が社会的注目を集めはじめるのは、この時期の終盤つまり20世紀に入るころであり、それは圧倒的にネガティブな文脈においてである。市事業の遅れ、議員の人材難、汚職、不毛な党派間対立といった市会批判の見出しは、「伏魔殿」という蔑称とともに今日見かけても違和感がなく、近代日本における都市政治の「腐敗」と改革運動の起点として研究者の関心も集めてきた。しかし、この種の市会論で、それ以前の時期は総じて古き良き日々または星雲状態として、ヴェールのむこう側に置かれがちである。
筆者が卒業論文で世紀転換期の東京市会を揺るがした政治対立に着目したのち、関心がそれに先立つ時期へとむかった一因は、今思えば上記のような議会像に腑に落ちないものを感じていたためだったかもしれない。「将軍のお膝元」から「輦轂の下」の都市となり、江戸の旧町人、旧幕臣、苦学のすえ立身を遂げた地方出身者などが入り混じる空間と化していった当時の東京には、地域を掌握する伝統的名望家も、組織的な発達を遂げた近代的政党や業界団体も見当たらない。しかし、だからこそ、同地の議会がどう始動したのかを徹底して掘り下げることで、多元的で流動的な都市社会で「政治」のありようが根本から再編されるプロセスが観察できるのではないか。このような期待を抱えつつ、〈江戸から東京へ〉の変化と、〈問題としての東京市政〉の浮上を串刺しできる視点を探して議事録・行政文書・新聞記事などを行きつ戻りつするなかで、本書の骨格はできあがっていった。
加速する社会、翻弄される議会
そこで見つけた視点とはなにか。いざ言葉にすると拍子抜けするほど単純だが、明治維新のインパクトを、決定的な一撃というより時差をともなって日本社会に押し寄せた複数の波として理解し、それらが東京の議会にかかわった諸主体の認識や行動を方向づけていく局面を考察する、というのがそれである。
とりわけ重視したのは、以下の二つの波であった。第一に、近世身分制の解体と議会制の導入にむかう動きという、明治初年の政治変動そのもの。そして第二に、明治政府が推し進めた殖産興業政策を前提として明治中期に本格化した産業革命の、政治的な作用である。第一の波の産物にほかならない議会が動き出す本書の前半(第一章「実業家なき議会の出発」・第二章「「民力休養」時代の都市改造」・第三章「区民団体の政治機能」)と、その議会が第二の波に大きく揺さぶられる本書の後半(第四章「「経営」と「速成」の時代へ」・第五章「政治焦点化する首都の自治」)を、ひとまとまりの歴史経験として描くことを、本書では試みた。
その際にあわせて注目したのは、都市改造にかかわるインフラ整備をめぐる動向であった。道路の拡幅からガス・水道・市街鉄道の新設まで、多面的に進められたこの整備は、しだいに都市政治上の焦点となっていく。近代的なインフラの整備は、もともと明治日本の政治的経験を語るには欠かせない要素である。本書の表現を用いるなら、この時期は「いわゆる「上から」の押し付けとして始まった近代的社会資本の整備に、地方制度の確立や産業化によって「下から」の需要が追いつき追い越した」とでもいうべき時代にあたっていた。その「追いつき」さらにはいわゆる「積極主義」の広がりが、第二波の時期にどう東京で起こるのか。この点を、首都の近代化を急ぐ藩閥政府・東京府と、負担増大に抵抗する議会・政党勢力のあいだの対立として単純化されがちだった第一波の時期を再考したうえで、探ろうとしたわけである。
第一波にかかわって本書では、明治10年代の東京府会の指導者として知られる沼間守一・田口卯吉ら民権派言論人たちを、かたや負担抑制、かたや近代化の必要に対する強烈な確信をあわせもち、その両立に腐心した勢力としてとらえなおし、都市改造に懐疑的な旧町人議員とのあいだに緊張関係を見出した。府会開設に先立って東京会議所を率いた渋沢栄一・福地源一郎たちをふくめて、この時期の東京の議会には洋行・官僚経験をもつ旧幕臣たちの姿が目立つ。幕末維新期の動乱のなかから生み出された特異な傍流エリートともいえる彼らのうち、一足早く辞官した渋沢・福地たちの政治・経済横断的な「民権」追求が失速すると、彼らと入れ替わるように議会での存在感を強めたのが沼間や田口であった。彼らは旧町人議員の反発を議場・(政論新聞の)紙上・(演説会の)壇上を貫く弁論の力によっておさえこみつつ、江戸の「御救」資金だった旧七分積金を部分的な都市改造に投入していく(第二章)。並行して議会の足下の地域では、旧幕臣と旧町人がむしろ協調し、新置された「区」ごとに男性有産者≒(市制上の)「公民」≒有権者団体をつくり、議員─有権者間関係を枠づけていった(第三章)。明治維新によって他地域にも増して流動化した東京で、議会政治の始動、地域行政機構の変革、そして社会関係の再編が相互作用のもとで進む様子が、ここには窺える。
しかし、東京の議会は、明治20年代中盤以降に第二波が同地をのみこみ、社会全体が一種の加速を遂げるなかで窮境に陥ることとなる(第四章)。これに先立って東京府と市会のあいだでは、市制施行にあたって東京市の自治権が制限されたことを背景として対立が昂進していた。中堅新聞記者・弁護士が増え、かつてのような啓蒙的近代化志向も弱めた当時の市会は、府知事への対抗と市区改正事業への批判を相乗的に強め、事業の減速・縮小要求に専心していく。しかし、そのころ市会の視野の外で着実に進んでいたのは、全国的な電気鉄道熱を背景とする市街鉄道の出願競争や地価上昇であり、さらには大阪などとの都市間競争も意識した「都市経営」要求の高まりであった。あえて工期を定めない、市区改正計画の緩やかな時間スケールも、ここにいたっては機会損失の原因としか見なされない。日清戦後にこの趨勢が決定的となるなか、市会は自治権をめぐる闘争に勝利すると一転して市区改正事業の「速成」を目指しはじめる。だが、この転換は遅きに失していた。
この局面で議会が経験した誤算と混迷に、筆者は強く惹かれている。先見の明を欠いたゆえの失敗といってしまえば、それまでかもしれない。だが、産業革命の進行によって都市行政・政治に対する社会的期待が激変するなか、それに翻弄される議会の姿は、時代の潮目が変わるときの容赦のなさを、集中的に体現しているように思われる。新たな期待をすばやく察知するための回路――市政関連の調査機関にせよ、ロビイングに従事する業界団体にせよ――がいまだ不在ななか、時宜を得た反応の難度はなおさら上がっただろう。「速成」政策をうまく進められない市会は、実業重視や大衆化が進んでいた府下のメディアから「市政不振」の元凶として批判され、閉塞感を強めていった。
政党と地方議会が出会うとき
本稿の冒頭で20世紀初頭の市会批判の見出しをいくつか挙げたが、ひとつ省略したものがある。それは「市政の政党化」批判であり、この批判だけは今日そのまま流通することはないだろう。本書の後半はこの批判の対象、つまり自由党(→憲政党→立憲政友会)が東京市会に組織的に進出しようとする過程を論じることに、多くの力を注いでいる。
それ以前の東京の議会が、政党と無縁だったわけではない。東京府会を率いた民権派言論人が立憲改進党の結成に深くかかわったことは、広く知られた事実である。ただし彼らは、府会内での党派形成や組織的な選挙運動にはほぼ取り組まず、府会指導と政党指導を組織的にリンクさせなかった。日清戦後の自由党はこれとまったく異なる。同党の領袖だった星亨は、地方レベルの支持基盤の確立に強烈な関心を寄せた。明治32(1899)年に自ら東京市会入りした星(当時は衆議院議員と兼職できた)は、その2年後に白昼の市庁舎で刺殺されるまで、市会で多数派を固め都市改造事業を加速させては、その果実を党勢拡張に結びつけようとした。実際にこれ以降、市会内部には政党色を帯びた会派が定着し、会派間関係が審議を方向づけていく(第五章)。
自由党はなにをきっかけとして東京市会に進出しようとし、いかにして一定の成功をおさめたのか? 東京市政に同党が注目した直接的な契機は、市街鉄道の敷設をめぐって出願競争が過熱し、利害関係が錯綜したことであった。さらにその背景には、都市行財政の急膨張と商工業者の政治的活性化を目撃した同党の、「都市の時代」の到来に対するいささか前のめりの確信があった。藩閥政府と提携するため、自由民権運動以来の負担軽減要求を自党にいったん捨てさせた星もまた、この時勢認識に突き動かされていたわけである。そして当時にあって、監督官庁との交渉、競願者間の周旋、議会の説得ないし圧伏といった、政府・民間、政治・経済、中央・地方にまたがる調整が可能なのは――組織的な力量はいまだ低く、星個人の手腕に依存していたとはいえ――複数領域に浸透はじめた政党をおいてほかにいなかった。鉄道の敷設計画や国庫補助を地元へと引き寄せる、典型的な「地方利益」誘導とは若干異なるかたちで、政党が利益の調整・集約と党勢拡張を自覚的に結びつけようとした局面として、この時期の東京市会をめぐる同党の行動は理解できよう。
しかし、おそらくこれと同じくらい重要なのは、加速し錯綜する社会状況のなかに東京進出の動機と好機を見つけた自由党─政友会もまた、その状況を統御しきれずある意味では翻弄されていくということである。同党は実際、その後一気に東京で覇権を握ることはできなかった。誤算のひとつは、都市大の議会という「頭」をおさえれば意のままになる政治空間では、東京がなかったことである。星による急速な市会支配を目撃した各区の「公民」団体は、これをローカルな秩序の攪乱と見なして政治的に活性化し、市街鉄道問題などをめぐって全市的な対抗運動を繰り広げた。彼らが唱えた「市政の政党化」批判は、ここにおいて明治地方自治制に内在する官僚的な政党排除志向、米国の市政改革論に依拠して広がりつつあった都市社会主義的な都市自治=非「政治」=政党不要論、そして特定党派による利権独占への憤激などを包摂し、盛り上がっていく。実態以上に政党化し腐敗した東京市会のイメージは、星の死後も大衆紙をふくむメディアを通じて拡散された。日露戦後の政友会は、原敬の主導下で「地方利益」(とりわけ鉄道)要求の集積・統御システムを確立したことで知られるが、東京版の当該システムは築かれず、同地の党勢は安定しなかった。政党なくしてはもはや成り立たないが、政党による地域支配の拠点となりきれない東京の議会は、国政にむけられた不満までも引き寄せては現状打破志向の政治エネルギーを供給する舞台となっていくのである。
おわりに
筆者は先日、別媒体に寄せた自著紹介を、「その〔東京の議会が時代の転換期に始動する―筆者注〕プロセスが、東京の歴史に関心がある方はもちろん、今日の議会政治に対して期待・不満・不可測性を様々に感じている方の興味も惹くことを、著者として願っています(1)」と締めくくった。
この希望はかなうだろうか? 選挙などに関するデータ量の差から、新旧憲法のあいだの制度的な断絶(そもそも本書の前半は憲法制定前である)にいたるまで、本書の歴史分析と今日の議会論のあいだにはいくつもの溝がある。それでもなお、平成・令和日本に育ち、上記の「期待・不満・不可測性」の感覚をほかでもなく抱えてきた筆者が執筆した本書には、現代的な関心と共振する知見がなにがしか埋まっていることを期待したい。中央─地方関係や都市─農村関係の形成・変容と絡み合いつつ展開した近代日本の議会政治・政党政治に対しては、なお興味と疑問が尽きない。今後は本書での取り組みをふまえつつ、それらをいっそうしつこく掘り下げたいと考えている。
(1) UTokyo BiblioPlaza(https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/A_00229.html)。
(いけだ・まほ 日本近現代史)
初出:『UP』611号 (2023/9)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
