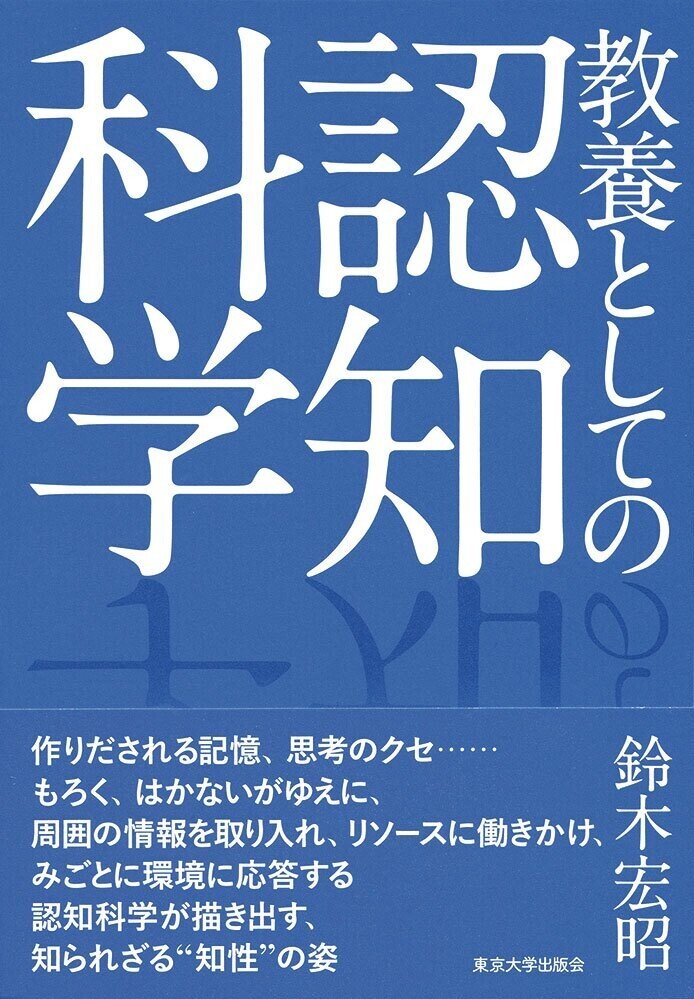【21世紀を照らす】『教養としての認知科学』(2016年)/解題: 鈴木宏昭
20世紀の後半は情報の時代の幕開けの時期と言える。世の中のさまざまな現象を情報とその処理として捉えようという動きが一挙に広がった時代であった。こうした中で認知科学は、人の知性を、世界から与えられる情報、自らが生み出す情報を処理することと捉える立場を取る学問である。
私が認知科学と出会ったのは、1980年代初頭であり、東京大学本郷キャンパスに大学院生として在籍していた時であった。学部時代に心理学をかじっていたが、なんとも物足りない思いをしていた自分にとって、認知科学は福音のように響いた。なぜかと言えば、頭の中で起きていることがわかる、と感じたからである。つまり、この学問のフレームワークを用いることで、どういう情報を得て、それをどのように組織化し、蓄えるのか、また蓄えたもの(知識)を新たな情報の処理にどのように用いるのか、これらを詳細なレベルで明らかにすることができるのである。実際、この時代の研究者たちの努力により、知識の構造、認知のプロセスについての知見は飛躍的に豊かになった。私や仲間たちは、情報科学由来の馴染みのない概念や、プログラムなどと格闘しながらも、その価値をさまざまな研究領域で確認し、楽しくて、楽しくて仕方のない院生時代を過ごした。
しかし21世紀に近づくにつれ、徐々に伝統的な認知科学のアプローチの限界も明らかになってきた。情報処理という枠組みを取ると、世界の中にある無数の情報のどれを取り込むのだろうかという問題が起こる。仮にそれを絞り込めたとして、その処理に必要なプログラムは前もって頭の中に存在していなければならない。そしてそのプログラムはそれが必要とされるさまざまな場面に適用できるようになっていなければならない。それらのプログラムはいったいどうやって作られるのだろうか。いずれも大変に困難な課題である。
こうしたことから知性の捉え方を変える必要が強く認識されるようになった。人も含めた生き物は身体を持っている。身体はなんのためにあるかと言えば、環境(社会)と相互作用するためである。何を通して相互作用をするのかと言えば、行為である。つまり情報処理の主体と考えられる脳は、身体-行為-環境のループの中に埋め込まれているのだ。こうしたことに気づいた認知科学は、新たな時代を迎えることとなる。ここには新たな人工知能、神経科学、進化心理学に代表される進化的アプローチ、生態心理学などにインスパイアされた知見が豊富に盛り込まれている。
これらの知見が、学生はもちろん人間と関わるさまざまな職業の人々に与える影響はとても大きい。そうしたことで、伝統的なアプローチ、新たなアプローチがもたらした知見を、学生、一般の方にわかりやすく伝えることはできないかと考え、誕生したのが本書である。幸いなことに、出版1年で5刷、6年目を迎えた現在は10刷に至っている。驚きの気持ちはもちろん大きいが、多くの読者の方と知性の新しい姿を共有できる喜びに浸っている。
文・鈴木 宏昭
初出:創立70周年記念リーフレット:21世紀を照らす 第2弾(2021年8月)