
太宰治という迷宮(ラビリンス)ーー『太宰治論』を執筆して/安藤 宏
『太宰治論』刊行直後に、本書について、そして収まりきらなかった著者の思いを綴ったエッセイを、小会PR誌『UP』にご寄稿いただきました(掲載は2022年2月発行予定の2月号となります)。その一部を先行公開いたします。
卒業論文の思い出
東大のよき美風、とでもいうべきか、学生時代、卒業論文の手取り足取りの「指導」というのは一切なかった。ただ、年に一度5月に、研究室で一人5分程度、粗々の構想を口頭で報告する会があったのを覚えている。実は何を題材にしたものか決めかね、前日まで押入れの段ボール箱に押し込んであった文庫本を読み散らしていたのである。その中で、久しぶりに繙いた太宰治の『晩年』が妙に心に沁みた。かつて太宰に単純に自己同化し、夢中になって読んでいた時期もあったのだが、あらためて読み返してみると、そこには読者をそのように誘っていく巧妙な仕掛けやワザがある。さらにはそのはざまにたゆとう道化師の悲哀、とでもいったらよいのだろうか。現実に傷つく前にあらかじめそれを先取りして傷ついてみせる一人芝居のむなしさのようなものが、言いしれぬペーソスをもって胸に迫ってきたのである。読んだ本がかつてと印象がまるで違っていて驚く、というのは読書人なら誰でも経験することだが、当時、一学生であった自分には、おそらくこうした体験自体が新鮮だったのだろう。そういう自分が何やらすっかり気に入ってしまい、よし、これで書こう、と思い立ったのが、結局、その後40年にわたって研究を続けるきっかけになったのである。
当時から太宰は人気はあったけれども、まだ比較的新しい作家、というイメージもあり、漱石、鴎外、荷風、藤村など、明治・大正期を代表する作家たちに比べると本格的な研究は緒についたばかりだった。大学教員の中では太宰の卒論にいいものはない、というのが定説だったらしく(もちろん、当時の話である)、あの有名な奥野健男の『太宰治論』の口マネになってしまったり、太宰になりかわるようにして弁護を始めてしまう〝感情移入型〟の卒論が多かったようである。「この小説は失敗である」と告白してみせたり、「君にだけ教えよう」とささやきかけてくる太宰の話術を対象化し、そのメカニズムを分析するのはなるほどたしかに難しい。それは作者の作戦であり、その背後に「真の意図」があるのだ、と指さしてみた瞬間、実はそれもまたテクストの仕掛けだったのではないか、という疑念にとらわれてしまう。回っているルーレット盤を図解するためには、回転を一度止めてみなければならないのだが、止めた瞬間、あのめくるめくような迷宮(ラビリンス)の魅力もまた霧消してしまうのである。
迷宮をいかに対象化するか
大学院に入って、これはなかなか厄介な対象だ、ということに遅まきながら気がつき、後悔しかけた瞬間もあったのだが、乗りかかった舟、というべきか、多少の意地もあり、太宰的話法の魅力をあきらかにすべく、使える手だては何でも使ってみようと決心した。おそらくそのためには、「君にだけ教えよう」という誘惑には乗らず、本人(太宰)がもっとも嫌がるであろう方法をとるのが有効なのだろう。「太宰治」を一度徹底して実証と論理の俎上に載せてみるというのがその作戦である。たとえば原稿・草稿の抹消跡を日に透かしてもとの表現をたどる作業など、おそらく書いた当人から見たら、まさに「悪魔の所行」であるにちがいない。だが、あえてストイックな手立てを通してみなければ、「好き/嫌い」の二分法を乗り越えていくこともまたできないわけで、結局、そう思いながら40年間、迷宮の中をさまよい続けて来たような気もするのである。
太宰は人を「学問」に駆り立てる偽善を極度にきらい、最後まで「文学」を「お勉強」しようとする「学者」たちの虚栄心を攻撃していたのだから(「如是我聞」)、そうした作家を1200頁の研究書にしてしまうなどというのは、まさに最大の裏切り行為であるにちがいない。その意味でも太宰の研究者は、まず何よりも、キリストを売ったユダの屈折した愛憎(「駈込み訴へ」)が覚悟として問われるのである。
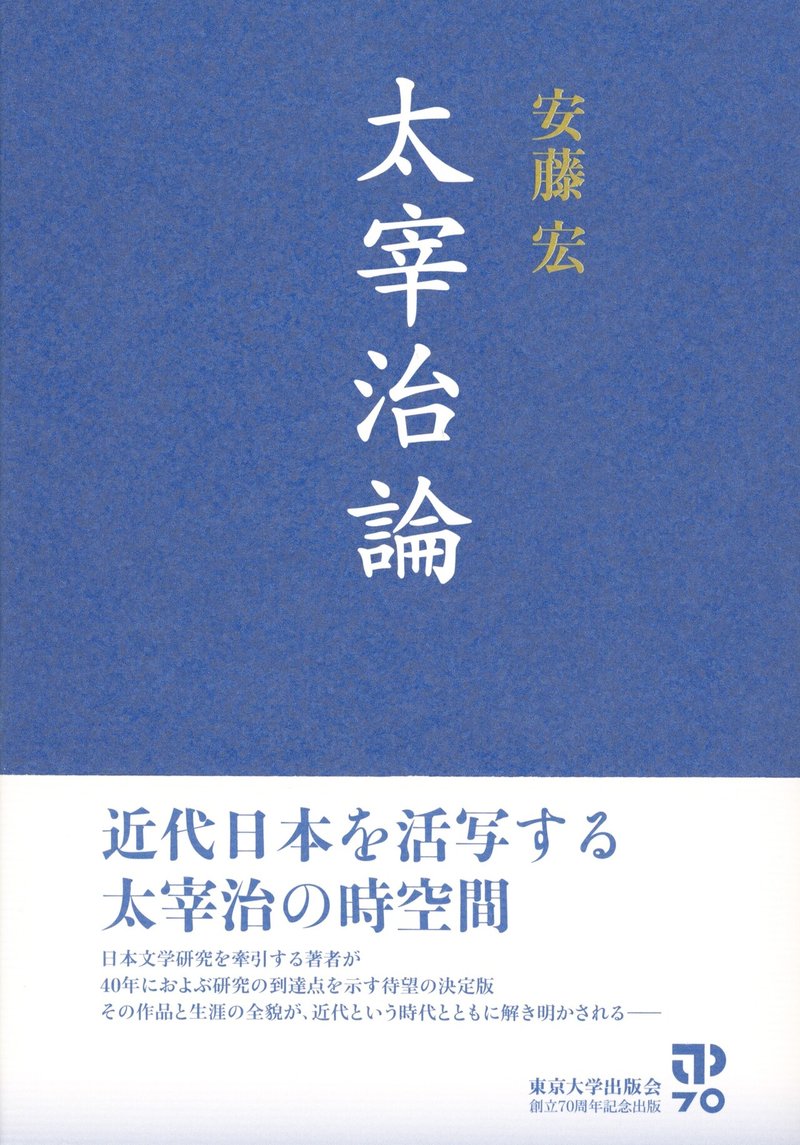
太宰治論
安藤 宏 著
ISBN978-4-13-080068-6
発売日:2021年12月17日
判型:A5
ページ数:1218頁
時代とともに作家のイメージや、作品の読まれ方も変化しつつも、多くの読者から支持され続ける太宰治の文学を総合的に解き明かす。激動の時代を忠実に生き、不器用さから時代錯誤を演じ続け、絶望を深めながら自身の宿命に殉じていく一人の人間像、そして日本の近代のあり方までも浮き彫りにする日本文学研究を牽引する著者による太宰治研究の決定版。
[東京大学出版会創立70周年記念出版]
主要目次
序 太宰治の時空間
第Ⅰ部 揺籃期
第一章 「百姓」と「貴族」
コラム1 新出史料・津島家関係文書
コラム2 生い立ち
コラム3 津島家の女性たち
第二章 〈自尊心〉の二重構造
コラム4 回覧誌「星座」と阿部合成
コラム5 中学時代の直筆資料
コラム6 「青んぼ」の時代
第三章 〈放蕩の血〉仮構
コラム7 「細胞文芸」について
コラム8 草創期の映像文化
コラム9 新派・新劇の影響
コラム10 ノートの落書き――高校編
第四章 「哀蚊」の系譜
コラム11 浄瑠璃語りの影響
コラム12 習作期の詠草
第五章 津軽と東京と――〈二百里〉の意味するもの
コラム13 津軽文壇の状況
第Ⅱ部 『晩年』の世界
第一章 習作から『晩年』へ
コラム14 非合法活動
第二章 『晩年』序論
第三章 山中の怪異――「魚服記」論
第四章 回想という方法――「思ひ出」論
コラム15 文壇デビュー(1)――「海豹」前後
第五章 寓意とはなにか――「猿ケ島」「地球図」論
第六章 自殺の季節――「道化の華」論
コラム16 アンドレ・ヂイド『ドストエフスキー』
コラム17 「道化の華」四題
第七章 自意識過剰と「死」の形象
第八章 「小説」の小説――「猿面冠者」論
第九章 詩と小説のあいだ――「玩具」論
第一〇章 散文詩の論理――「葉」論
第一一章 『晩年』と〝津軽〟――「雀こ」ほか
第一二章 転向・シェストフ・純粋小説
コラム18 文壇デビュー(2)――「鷭」「青い花」
コラム19 「彼は昔の彼ならず」
コラム20 井伏鱒二との〝共働〟――ナンセンスの系譜
第一三章 〈嘘〉をつく芸術家――「ロマネスク」論
第一四章 現実逃避の美学――「逆行」論
コラム21 「陰火」――幻想小説としての「尼」
コラム22 演劇との関係(昭和三―一四年)
コラム23 『晩年』の刊行
第Ⅲ部 中期の作品世界
第一章 〝罪〟の生成――『晩年』の崩壊
第二章 「太宰治」の演技空間――「ダス・ゲマイネ」を中心に
コラム24 〝芥川賞騒動〟前後――佐藤春夫との関係を中心に
第三章 第二次“転向”の虚実――未定稿「カレツヂ・ユーモア・東京帝国大学の巻」を中心に
コラム25 キリスト教の受容
第四章 〈懶惰〉の論理――「悖徳の歌留多」から「懶惰の歌留多」へ
コラム26 荻窪というトポス
第五章 〈自己〉を語り直すということ――『愛と美について』論
コラム27 石原家
第六章 「生活」と「芸術」との齟齬――「富嶽百景」論
コラム28 美知子夫人と「太宰治文庫」
第七章 「女生徒」の感性
第八章 女がたり
コラム29 「千代女」と「生活綴方」運動
コラム30 映画とのかかわり
第九章 「小説」の条件――「女の決闘」論
コラム31 画家・版画家たちとの交流
コラム32 「善蔵を思ふ」と棟方志功
第一〇章 メロスの懐疑――「走れメロス」論
第一一章 太宰治と〝東京〟――「東京八景」を中心に
コラム33 「新ハムレット」の舞台化
第Ⅳ部 戦中から戦後へ
第一章 戦中から戦後へ
コラム34 戦争の影――三田循司のことなど
第二章 蕩児の論理――「水仙」「花火」
コラム35 二人の女性画家
コラム36 「右大臣実朝」――原稿を中心に
第三章 「津軽」の構造
第四章 翻案とパロディと――「新釈諸国噺」論
コラム37 『惜別』執筆関連資料から
コラム38 「お伽草紙」の本文
第五章 「八月一五日」と疎開文学
コラム39 「パンドラの匣」とGHQ
第六章 〈桃源郷〉のドラマツルギー――「冬の花火」と「春の枯葉」
コラム40 新劇とのかかわり――戦後を中心に
第七章 戦後文学と「無頼派」と
コラム41 戦中、戦後の三鷹
第八章 戦後の女性表象――「ヴィヨンの妻」を中心に
第九章 「斜陽」における〝ホロビ〟の美学
コラム42 「斜陽」執筆の背景
コラム43 伊豆というトポス
第一〇章 「悲劇」の不成立――「人間失格」論
第一一章 関係への希求――「人間失格」の構成
コラム44 信仰と文学と
第一二章 「人間失格」の創作過程
コラム45 草稿研究の課題
第一三章 最晩年の足跡
コラム46 「井伏鱒二」への想い
コラム47 「志賀直哉」への抵抗
コラム48 肖像写真
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
