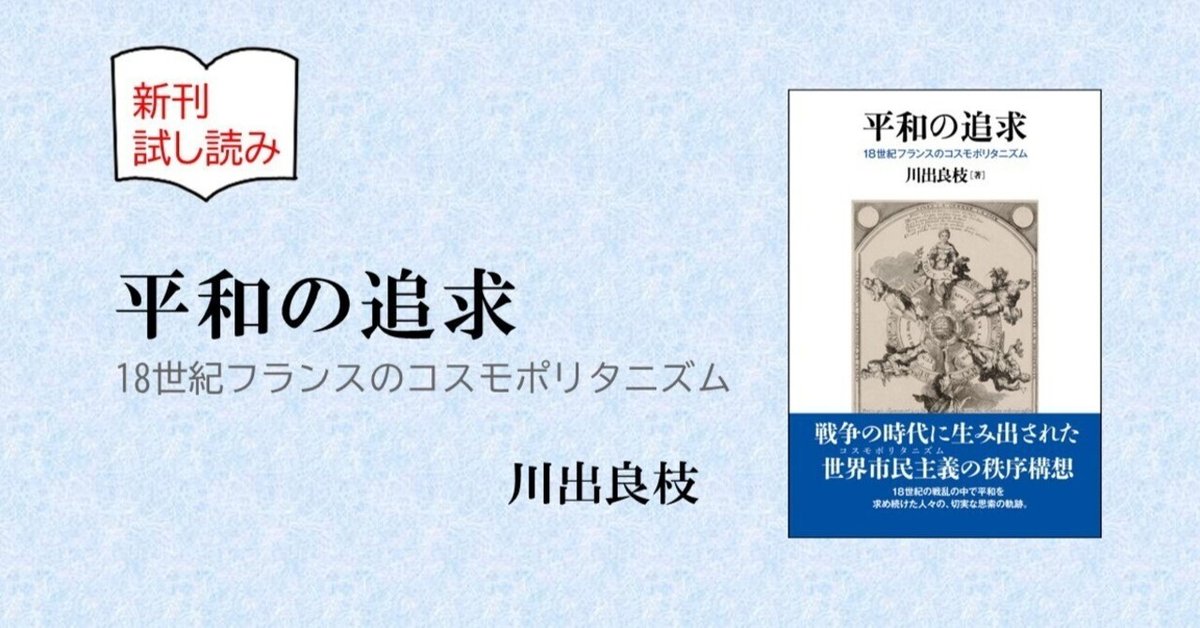
『平和の追求 18世紀フランスのコスモポリタニズム』川出良枝
川出良枝『平和の追求 18世紀フランスのコスモポリタニズム』がまもなく刊行となります。18世紀の戦乱の中で平和を求め続けた人々の、切実な思索の軌跡を丹念にたどります。本書冒頭の「序論 1 コスモポリタニズムの再興」を公開いたします(*注は省略しています)。ぜひお読みください。
戦争のない世界の実現は人類の長期にわたる夢である。だが、それは、何度も裏切られ続けてきた夢であったと言えよう。東西冷戦の終結により、平和と安定の未来を約束されたかに思われた国際秩序は、またたく間に、戦争や内戦や軍事介入、テロリズムを含む様々な暴力の脅威にさらされることになった。ついには、力による一方的な現状変更を試みる陰惨な侵略戦争がウクライナの地で勃発し、第二次世界大戦後の安全保障の枠組みが揺るがされる事態ともなった。その一方で、市場秩序のグローバル化、国境を越える人や情報の往来は、もはや止めがたい流れとして定着しつつあるかのようである。こうしたグローバル化の進展は今のところ複雑な様相を呈している。それが、新たな紛争の火種となることもあるし、また、政治的・経済的な地域統合の動きを加速させ、全世界において統一的な制度や法を制定する試みを生み出すこともある。こうした状況を背景として、主権国家を単位とする既存の国際秩序を抜本的に見直し、地球大の世界秩序のあり方を構想すべきであるという主張を耳にすることも多くなった。
だが、地球大の世界秩序を構想するという試みは、今に始まったことではない。従来、インターナショナリズム(internationalism)や平和主義(pacifism)の名の下で、こういった構想がさかんに展開されてきたが、今日では、むしろこういった観念よりもはるかに歴史の古い観念が、再び脚光を浴びている。すなわち、世界市民主義とも訳されるコスモポリタニズム(英cosmopolitanism, 仏cosmopolitisme, 独Kosmopolitismus)がそれである。後に詳しくみるが、この言葉の元になったコスモポリタン(英cosmopolitan, 仏cosmopolitain)やコスモポリット(仏cosmopolite)という表現の語源は、古代ギリシア語のコスモポリテース、すなわち「世界の市民」(英citizen of the world, 仏citoyen du monde, 独Weltbürger)であった。言葉のみならず、コスモポリタン思想の源流は、古代のキュニコス派やストア派の諸思潮に求めることができる。本書が分析の対象とする18世紀のヨーロッパ、とりわけフランスにおいて、この「世界の市民」という概念は新たな装いの下に華々しい復活を遂げる。本書においては、世界を一つの全体的共同体とみなした上で、自らをそこに帰属する一員(まさに「世界の市民」)であると認識し、またそのことに積極的な価値を見出そうとする思想一般のことを指す分析概念としてコスモポリタニズム、あるいはコスモポリタン思想という表現を用いることにしたい。
18世紀に隆盛を極めた世界市民の概念は、その後、退潮の時期を迎える。19世紀に入ると、インターナショナリズムという新語が登場し、19世紀後半以降、とりわけ第一次世界大戦後に活発に用いられた。その傾向は第二次世界大戦後も引き継がれ、コスモポリタニズムの語は次第にこれに圧倒されるようになる。ところが、20世紀の最後の10年の中頃から今日に至るまで、あるべき将来の平和な世界秩序を積極的に提言しようという現代の論者の中に、自らの提言にあえてコスモポリタニズム、ないしはコスモポリタンという古い名称を好んで冠する傾向が顕著にみられるようになった。この立場を奉じる一人であるウルリッヒ・ベックが1998年に発した「コスモポリタン宣言」(cosmopolitan manifesto)に広範な応答があったのはその一つの証左である。
実際に用いられる際には、コスモポリタニズムとインターナショナリズムが互換的に用いられる場合もあるが、両者の差異を強調し、両者を区別すべきだとする議論もある。その興味深い一例が、ノルウェーの平和運動家にして、ノーベル平和賞受賞者クリスティアン・ランゲの『インターナショナリズムの歴史』における平和主義、インターナショナリズム、コスモポリタニズムの定義である。ランゲによれば、平和主義は、人類が道徳的にも生物学的にも基本的には一体であるという確信に基づき、戦争は功利主義的にみて悪であり、倫理的にみて不正であり、また紛争解決の手段として不効率であると考える思想である。この平和主義を実際に建設し、組織化するための理論がインターナショナリズムである。だが、それはコスモポリタニズムとは一線を画す理念である。「インターナショナリズムは定義上コスモポリタニズム(cosmopolitisme)とは対立する。コスモポリタニズムとは一元的なもので、人類全体が単一の社会集団となることをめざす。インターナショナリズムは、諸国民(nations)の上に築かれることを望むもので、諸国民の体制を自律的な社会集団とみなす。それは、諸国家(Etats)を、諸国民からなる大きな社会の部分集団の、なおも不完全ではあるが正統的な代表として認める」。
この定義はコスモポリタニズムを国家を否定する点において特徴づけるもので、本論の立場からみれば、コスモポリタニズムを限定的に、あるいは矮小化して捉えたものである。なるほど、国家の存在を全否定するコスモポリタニズムがあることは事実であるが、世界市民の理想を唱える議論の一翼には、ここでインターナショナリズムと呼ばれている議論と同様、人類が単一の社会集団となることに批判的であり、国家あるいは何らかの政治共同体が個人と人類の共同体を媒介するあり方を理想とする議論が確実に存在した。本書に登場する諸思想の多くは、こうした議論に他ならない。ただし、国家を想定するにしても、コスモポリタニズムの場合、議論の出発点はあくまでも個人であり、個人が家族や国家に帰属し、それと同時に人類全体に帰属すると考えるところに顕著な特徴がある。そのため、この点ではランゲの見立ては正しいのであるが、国民国家が国際秩序の正統な代表権を独占するという発想はコスモポリタニズムには希薄である。第一次世界大戦前後に理論を構築したランゲにとって、インターナショナリズムとは、国民国家の存在とその存続を基本的条件とした国際秩序構築であったが、本書が主要な分析対象とする18世紀フランスにおいては、なるほど国民国家形成へと向かう要素はすでに散見されるものの、いまだそれが自明の存在として立ち現れるには至らない時期の世界秩序構想であった。
ひるがえって、今日、インターナショナリズムではなく、むしろコスモポリタニズムというより古い時代に起源をもつ語に脚光があたっているのは、ランゲの判断とはむしろ反対に、国民国家を人類の共同体の不可侵の前提とすること自体への懐疑が底流にあるからであろう。平和な国際秩序は、国家(国民)と国家(国民)の間の関係を律することによってのみ実現するという前提を見直そうとするならば、いきおい、国民国家が確固とした政治の単位となる以前の時代に平和の構想の起源を求めることになろう。人間のアイデンティティを「国民」としてよりは、「世界の市民」として捉える思想の伝統に、いわば先祖返りするかのような現象が生じるのは、十分理解可能である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
