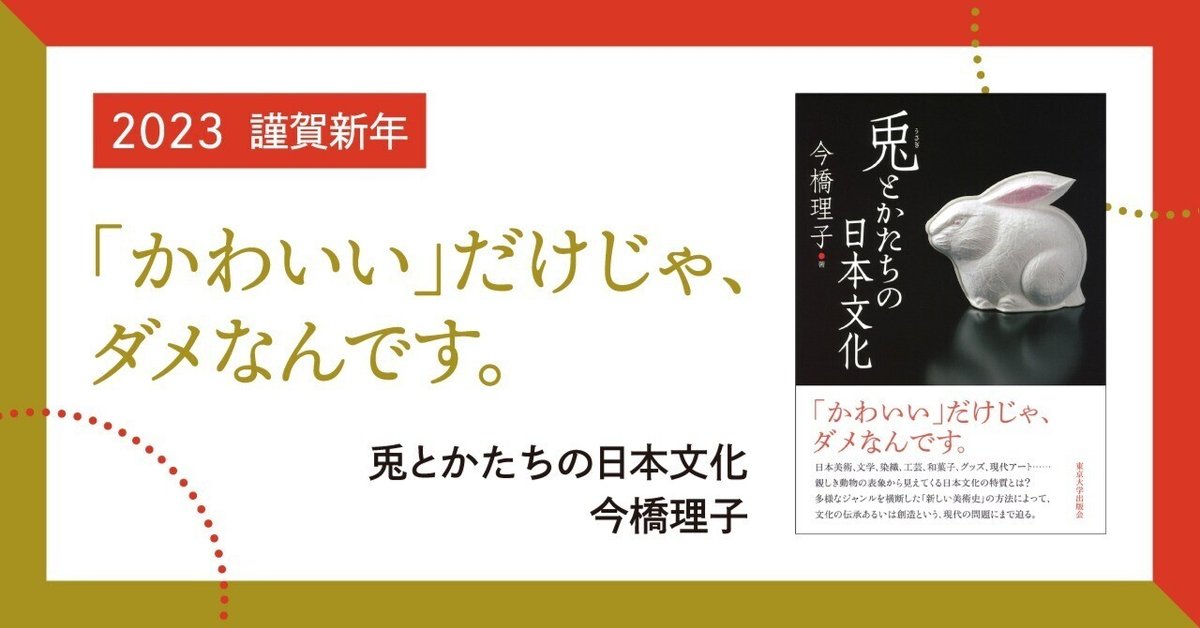
「かわいい」だけじゃ、ダメなんです。/『兎とかたちの日本文化』あとがき
本年2023年は卯年。その新年の読書としておすすめしたいのが、今橋理子『兎とかたちの日本文化』です。以下で、「兎の足あと――「あとがき」に代えて」の一部抜粋をお楽しみください。そう、「かわいい」だけじゃ、ダメなんです。
実は今だからこそ正直に告白するのだが、私自身は決して「兎好き(ウサギマニア)」ではない。そんな私が気がつけば、兎とのつき合いもかれこれ20年近くになってしまった。
はじめは、江戸時代花鳥画研究の一テーマとして選んだ対象であったが、絵画だけでなく工芸品の文様も見てゆくうちに、すぐにもその伝統的な「かたち」のバラエティの多さに圧倒されると同時に、それらの「かたち」ひとつひとつの背景に存在する豊かな「ことばの世界」にも触れることで、私は瞬く間に「兎のかたち」の虜になっていった。そしていつの頃からだろうか、意識的に収集しようと始めた訳でもないのに、私の研究室や自宅の書斎のデスクの周りには、兎にちなむ様々なグッズや民芸品が溢れ出し、さらにそれを見た家族や親しい友人たちまでもが半ばあきれ顔で―けれども皆いつも楽しそうに笑顔で、旅先や買い物途中で見つけたという小さな陶器の置き物や根付の類を贈ってくれるようになった。それらに囲まれ日々眺めて過ごすうちに、あるとき新たに検証すべき課題が見えてきたのである。
すなわち、私たち現代日本人はウサギを、「かわいい動物」と普通見做している。しかし日本の美術・文化史上に歴史的に残されてきた兎をめぐる造形は、果たして本当に「かわいい」と呼べるものであっただろうか?―ということである。現実のウサギの耳より遥かに長く、そしてまるでトノサマバッタのような異様に長い足をもった、中世期の陶片に残された兎の模様。あるいは、江戸時代中期の沈南蘋流や円山四条派画家たちが描く、鋭い眼を持ちリアルなまでに毛描きされた写生画の兎たちの姿。さらには、明治初期の飼兎ブームのなか多数発行された「兎絵」のような浮世絵の中のウサギたちは、半獣の姿で擬人化され、おおよそ「かわいい兎」と言うにはほど遠い顔かたちである。
――ところが、である。例えば全国の美術館や博物館で、夏休み期間に合わせてよく企画される〈親と子のための美術どうぶつ園〉のような展覧会を思い出してみたい。こうした展覧会で兎は必ず取り上げられ、まとまった数の作品が並べられることが少なくない。先に上げたような耳長・足長の兎はもちろんのこと、奇妙にリアルな写生画の兎や擬人化された兎絵の類も、必ずと言ってよいほど展示される。だが現代日本人たちがこうした兎の造形ひとつひとつに対し、その形が内包してきた歴史的意味を、きちんと理解しながら鑑賞しているかと問えば、おそらくその答えは「ノー」であろう。兎が犬や猫と同じように、大人から子供まで親しみ易く、身近な動物であるだけに、かえって現実の兎を眼差す「かわいい」という感覚から、私たちは自分たちを引き離すことが容易ではなくなっているのである。実際の動物園内にしばしば設けられている〈子どもどうぶつえん〉のコーナーでは、小さな子供たちが子ウサギやモルモットなどを抱っこしたりできるが、兎という動物へのそうした親しみ深さや距離の近さが逆に、本来は「かわいい」とは無縁の造形としての「兎のかたち」という歴史や文化を、見え難くしているとも言えるのである。
ましてやミッフィーやピーターラビットのような西洋渡りのかわいい兎が、キャラクターグッズとなって日常雑貨に増殖し、さらにそうした人気にあやかるように、今でも「かわいい兎」の新しい形が次々と生み出され続けている日本の現状である。その様に氾濫し続ける「兎のかたち」の洪水の中で、過去より伝統として受け継がれてきたはずの「かたち」やそのかたちをめぐる「ことば」の世界はいつしか忘れ去られ、「かわいい」と言うことばによってのみ全てを単純化して表現するような、そんなある種麻痺した感覚で現代日本人は伝統と向き合っているのではないか――。私は、私の周りに集って来た多くの「兎のかたち」を手に取りながらそんな危機感を抱き、この本を書く構想を練っていったのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
