
座談会「『知の技法』をめぐって」〈第1回〉
『知の技法』刊行直後の『UP』第23巻第4号(1994年4月号)には、座談会「『知の技法』をめぐって」(1994年1月14日実施)の記録が掲載されています。メンバーは編者のお二人と、当時、文学部助教授(社会学)でいらっしゃった上野千鶴子先生。今回はその中から、本書のなりたちについて語られている部分を抜粋、一部を割愛してお届けします。当時の大学改革の中で生まれた本書が、なぜビジネス層はじめ多くの一般読者に広がったのかを窺い知ることができます。社会にも通用する技術としての教養と、気鋭の研究者たちが体現し垣間見せる学問のおもしろさの組み合わせの妙については、ぜひ『知の技法』でご確認ください。
※文中、「駒場」と「本郷」が頻出しますが、東大では1・2年生全員が駒場(教養学部)で学び、その後、専門に分かれ、教養学部・理学部数学科以外の3・4年生は本郷で過ごします。
○『知の技法』を作ったわけ
(……)
船曳 『知の技法』をどうしてつくろうとしたかという問題ですが、最初言い出したのは小林さんでしたね。
小林 理由はいっぱいあるんですよね。複数のファクターがあるんですが、一つは93年度に行なわれた駒場のカリキュラム改革で「基礎演習」なるものができたこと。英語Iだけが目立っていますけど、ほかにも重要な改革があって、そうしたカリキュラムの大改定に対応するポリシーの一環であるわけです。(……)大学教育のあり方そのものが根本的に変わらざるをえない、という直感がまずあったわけですね。実際、手応えも全く変わってきてしまってる。
上野 それはいつごろから変わったという実感があります?
小林 いつごろからでしょうね。ちょっと個人的なことになりますが、去年駒場で「大学で何ができるか」だったかな、学生が主催した「大学を問う」という趣旨のシンポジウムがあったんですよ。それに教師の側から僕と小森陽一さん〔日本近代文学〕と二人で呼ばれた。何人かの学生パネリストと対話するということになって、企画としてはおもしろかったんですけど、そこで愕然としたことがあるんです。つまり、教師を呼んで問い詰めるという場なんだから、「大学とは何か」というヴィジョンくらい持ってるべきだと思うんだけれども、むしろ彼らの問題は大学は社会に出るためのワンステップであり、それ以外の意味を見出せない。存在理由を見出せない。「で、どうしてくれるの?」「どうしていいかわからない」という不安や疑問をぶつけてくる。
上野 何とかしてちょうだい、っていうだけ?
小林 そう。だから、いまの大学教育はこうで、これを自分たちはこうしたいんだ、というヴィジョンとヴィジョンの対決じゃなくて、ともかく自分たちには大学の意味がよくわからない。それを何とかわからせてほしい、ということなんですよね。
○「学生は変わった」のは本当?
上野 その学生の変貌を肌で感じたのはいつごろからですか。
船曳 (……)少なくとも書くということに限定していえば、戦前から戦後のある時期くらいまでは、ある方式みたいな定式みたいなのを感じていて、それをきちっと教わったかどうかは別として、それに則って書くんだと。そのあとから僕が”古今主義”〔『知の技法』の「結び」〕と呼ぶところの、思ったところをそのまま率直に、というのをどこかで吹き込まれてる。
小林 ここから変わった、とはっきりは言えないな。
上野 偶然か必然か、ここにいる三人はたまたまベビーブーマー世代、学園闘争世代ですけど、私たちが大学大衆化の先駆けでしょ。
船曳 うん。そのときにもすでに教師はそう思ってたかもしれない。
小林 でも、大学生であることには、ある一定の特権性か、エリート性か、そういうものに裏打ちされたある種の使命感があった。何かを学ばねばならない、社会にアンガージュマンしなければならない、と。僕は、実は理科系なんですけど、理科のクラスでも、ともかく大学に入ったという理由だけでマルクスの『資本論』全巻を買って読む人が何人もいたわけですよ。あれは何だったのか。あのモチベーションって何だったのかわからないけど、それが僕らの時代にはあった。いまでは、大学に入ったというだけで『資本論』でもほかの何でも買ってこなくちゃいけない、という認識はなくなったと思う。どこからなくなったかははっきり言えないけど。
船曳 (……)社会の変化と同じで、それ以前から、そしていま、さらに進みつつあるということで、これはある一時点からぽっと変わったりするようなもんじゃないしね。(……)ふまじめというんじゃないけれども、大学で要求されてることをつかみ損ねてるという場合がある。
上野 それは学生のせいですか、教師のせいですか。
船曳 それは両方だと思いますけど、教師のせいでもあることは確かです。
小林 つまり、大学で何を学ぶべきかということを大学が明確に提示していない。僕がこのテキストをつくるべきだと思ったもう一つの大きな理由はそれですよね。これこれの専門分野の知識ではなくて、文系として最低限これだけの技術は学ばなければならない、ということを提示すべきだと思ったのです。
上野 これまではエリート教養主義の内面化のおかげで、学生は教養を勝手に身につけてくれたわけですよ。放し飼いでも。その放し飼いがきかなくなった、という現状認識は多分全員共通してるんだと思います。だから、駒場で基礎ゼミをやろうというコンセンサスができたんですね。それは何年前なんですか。
小林 去年の4月からスタートしたんだから、1年前じゃないですか。カリキュラムの構想自体は2年前ですね。
船曳 でも、その前からそういうようなことをしないといけないなというのは、多分どこの教養課程の教師も感じてたと思う。
小林 改革委員会みたいなものはずっと存続してたからね。
船曳 でも、それをやると手取り足取りだから、みんな大変だなと思ってた。
上野 とりあえず現状認識と危機感が共有されているということはけっこうなことですね。でも、基礎ゼミをやるとき、大学教師というのはお互いに独立性の高いものだから、レッセ・フェールで自分のところにあずかった学生は勝手に自分のところで飼育する。自分の流儀ってものがあるという相互不干渉の伝統があります。これは共通の教科書をつくろうという発想になかなかなじまないものなんですよね。
小林 正直なところ、やってみてやっぱりいろいろ抵抗を感じますから、必ずしも圧倒的に支持するコンセンサスができてやってるわけじゃないですね。
上野 でも、勝手にやってるわけでもないでしょ。
小林 勝手にやってるわけじゃありませんけど、これが必要だということには第二の理由がある。それはさっきの本郷と駒場のライバル関係にも関連するんですけど、いまわれわれは大学院重点化という大きな問題を抱えている。つまり大学院を重点化したときに、その力がちゃんとジュニアの学生にまで及んでいる、ということをわれわれとしては示す必要がある。大学院を重点化すると、1、2年のほうは手をぬかれるんじゃないですか、という危惧に答えるということもあるしね。しかし、それよりももっと大事なことは、かなり高度な最先端の学問を1、2年生にフィードバックする必要があるということ。一方では、1、2年生にこれは絶対覚えなくちゃならないという最低限の技術を示すと同時に、いま最もアクチュアルな学問の先端も示すべきだと思う。そうじゃなければ教育できない。1、2年生なんだから初歩的なことをやってて、最後の大学院で一番おもしろいことをやりましょうねという構造は絶対だめで、最もおもしろいことをまず彼らに教えなくちゃだめだと。
上野 そうです。それをやらなきゃ学生はついてきませんよ。(……)
小林 その二つがドッキングしているのがこの「基礎演習」テキストなので、片一方だけじゃだめなんですよ。一人の先生に習うとどうしてもその先生の専門しか見えないわけですから、文系のほかの最先端でどんなことをやってるのかということをきちんと見せておくことが必要だという認識なんですよね。
○『知の技法』をどう使う?
船曳 (……)教科書をつくろうと思ってもみんなしないのになぜ駒場で、という問題ですけど。つくろうと思ってもしないのは二つ理由があると思う。一つはたとえば理科系でいえば、これは実験に対応するというふうに僕らは考えてるわけ。実験は理科系のどんな分野にも必要なことで、それは基礎的に学ぶべきことだからそれを1、2年生がやるわけです。それは文系では何かというと、やっぱり読み書きだろうと。別に文学だけととらえるんじゃなくて、広い意味で「文」だと思うんです。しかしながら、教科書をつくるのは方法としてはこちらのほうがむずかしいということが一つ。もう一つは、やっぱり教育の現場の聖域化というのがあって、ほかの人に入ってこられたくない。自分と学生との間にできるもの、それが教育なんだから、その間にほかの人が入ってくることはよくないんだ、ということですね。それは一理あると思うんですけどね。
小林 一種の文人主義ね。私の人格全体が文なのであって、「文は人なり」、私を学びなさい、共通に使える技術体系などというものをここに入れる必要はない、というやり方。
上野 昔の徒弟奉公制度みたいですね。
船曳 それはほかの人に評価されたくないということと結びついている。その二つの問題があって、教科書をつくろうという試みはあまりなされないできたんじゃないですか。
上野 それを突破するだけでもなかなか大変なことでしょ。
船曳 そうです。そこは小林さんの頑張りだったんですけれども。
小林 というよりも、駒場全体がいま、すごく動いてるから、いまはともかく前に出ることに関しては、それを後押しする空気が支配的だからね。(……)
上野 改革を受入れるしか仕方がない。これは後発のよさですね。
船曳 どうしてつくったかはそういうことで、(……)学生は基礎演習に出る前に読んでおくとよろしいということ。それと僕の考えでは、隠れた読者としてはもちろん一般の人もいるんだけれども、大学に行こうとしてる高校生に読んでほしいというのがありますね。(……)大学に行ったらどんなことをするのかというのを、受験勉強しながらでも、つまり入る前に知っておいてほしいと。だから、これは4月に基礎演習が始まる前に読んでおくもんだ、という意識ですね。
上野 教育的かつ啓蒙的ですねぇ。ほれぼれ……(笑)。
船曳 そうです。だからほかの先生たちが、これは私の授業では使わないかもしれないと言うのはもちろん構わないんです。
上野 私はもうちょっとプラグマティックなチャート式みたいな参加型の使える本になってて、ユーザーズガイドとか、ユーザーズマニュアルみたいなものがついてる、そういう実用的な本になってるんではないか、という期待があったんですけどね。
船曳 そういうところも3分の1くらいはあります。
上野 わりと教養本になってるという感じがしましたけど。
小林 さっきの大学院の研究と1、2年生をつなげるということと、最低限の技術の修得目標を示すということ、この二つから出発したわけですが、つくり方そのものはいわば入試の参考書のようなプラグマティズムには貫かれてはいないね。僕の編集する意識のなかには、これは持っててくれることが一番大事だと。将来、レポートや卒業論文、修士論文書くときにつまんないことでぱっと役に立つことがあるということがありました、と。
船曳 会社のプレゼンテーションでもいいです。
小林 うん。そういうふうにも使える。
上野 それにしてはちょっとマニュアル度が低いですね。
船曳 二つのねらいがあるんですよね。さっき小林さんが言った、いま先端の学問で何をしてるかを教えたいというのとマニュアル的な部分と二つに分かれてるんです。僕はマニュアル的なところは別冊にして、ほんとにハンドブックにしてもいいんじゃないかと思ってるんですね。
上野 プレゼンテーションの仕方とかですか。
小林 うん。量としては、それが支配的ではないようにつくってるわけです。
上野 確かに分冊方式で理論編、実践編、応用編とかがあってもいいような気がします。私は自分のゼミで1時間使ってオーラル・プレゼンテーションの仕方、リサーチとは何かをレクチャーしましたよ。(……)でもはっきり言って、この技術はまず教師が修得してもらいたいですね(笑)。
小林 それを大きな声で言ってください。それにしても、いままでの大学は、特に文系は、あまりにも技術的なものを無視しすぎてきてるんですよ。ある意味では技術的なものだけが確実に身について、いつでも応用がきくものなんだけど、それを知識とか自分の信念などで覆い隠してた。自分の信念とか知識を伝えるのが大学だと思っている人たちが結構、多いんですよ。これはそれに対する一つの改革ですよ。
(第2回につづきます)
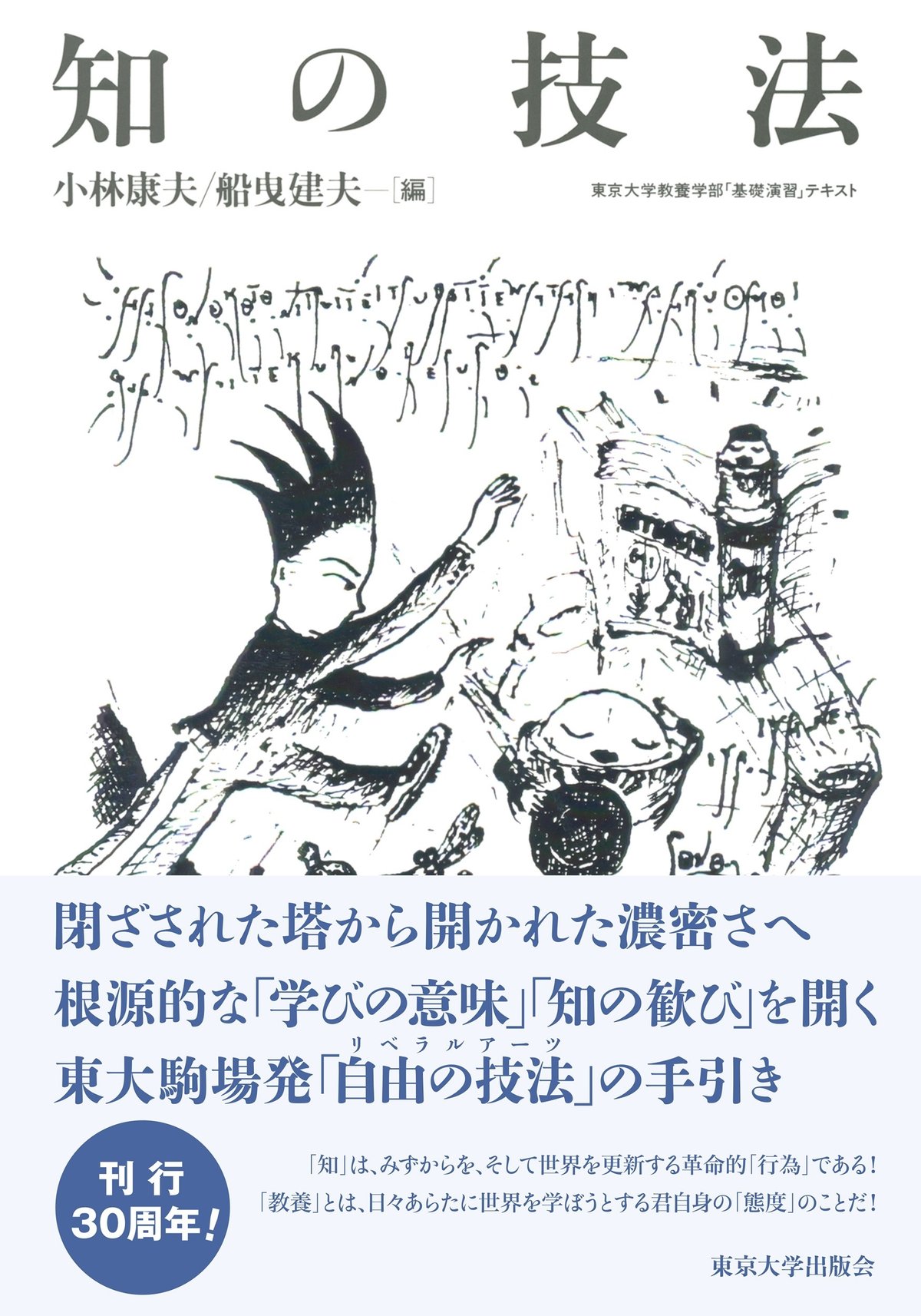
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
