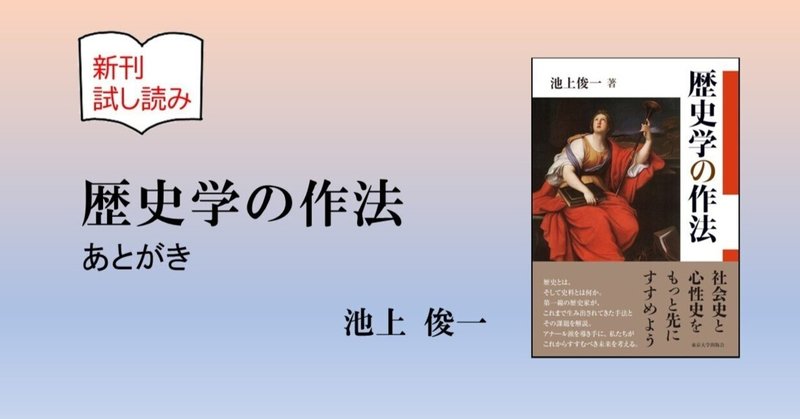
【新刊試し読み】『歴史学の作法』「あとがき」より抜粋
池上俊一『歴史学の作法』が発売となりました。事前からSNSで注目を集めていたこともあって、早くも多くの読者のみなさまに手に取っていただいているようです。PDFで公開している「はじめに」とともに、以下の「あとがき」の一部抜粋もご参考ください。
このところグローバル・ヒストリーや感情史、そして歴史叙述の問題をめぐって議論がかしましいし、歴史教育も大いに話題になっている。また大学でのテクスト用の著作もずいぶん出ている。とはいえ、歴史学が抱える多くの問題のすべてをまとめ、全体を関連づけた書物がないので、その穴を埋めよう、というのが本書執筆の動機である。
しかし、たんなる研究案内とか史学概論として総花的におとなしくまとまった書物――そうしたものが多いように見受けられるのだが――ではなく、全体史を射程に収めたこれからの歴史学のあるべき姿、という自分の主張を本書には思い切り込めたつもりである。「言語論的転回」「物語論的転回」「文化論的転回」「批判的転回」「空間論的転回」「時間論的転回」「感情論的転回」「パフォーマティブ・ターン」など、目が回るような回転ジャンプの連続を傍目に、地に足をつけてあるべき歴史学を構想してみたかった。
もう一つ、良く生きるには、なぜ歴史を学ぶことが重要なのか、ということを伝えたいという思いもあった。伝えたいというより、それを自分でもあらためて考え直したかった。自分を知るためには他者を、日本を知るためには世界を、現代を知るためには過去を、しかも中世や古代まで遡って知ることが不可欠であり、そうしてこそ、晴朗な意識を持って未来に歩みを進めることができるようになる。というのも、私たちの生きている時代そして社会は、長い歴史によって規定されていて、またその時代・社会によって誰もが規定されているのだから。
近年、「歴史認識」の問題が、国と国との政治問題化しているのに、そして学校教育においても、「英語」をグローバル言語と位置づけて小学校から教えようとしているのに、その傍ら、「歴史」は高校で「世界史」が必修からはずれて「世界史探究」という選択教科になるなど、とくに前近代史が軽視されるのはどうしてか。
もちろん、短慮な政府のみに責任があるわけではなかろう。今は「現在主義」が蔓延し、歴史的感覚をもって文化や社会を捉える気運がなく、誰もが歴史と切り離された「記憶」に覆われた「現在」にあたふたと感情的に反応するのが精一杯になっているからだ。そんな時代に歴史の重要性を説くのは荒野で叫ぶ預言者のようだが、一歴史家としてできるだけのことはしたかった。
各分野の動向や課題を示そうと私が取り上げ紹介した文献は、出版当初話題をさらったもの、私の専門に近くてもともと親しんでいたもの、たまたま目に止まったものなどさまざまだが、日本史や東洋史への目配りが手薄になり、例示する文献がほぼ西洋史とくにフランス史――中でも中世史――に偏ってしまった。またそれらの文献は、古典としてすでに万人に認められている名著を除けば、すぐにも乗り越えられ古びてしまうものも多いかもしれないし、より本格的な研究がやがて現れるかもしれない。しかしたとえ古びるとしても、これから歴史学を研究しようと考えている人への羅針盤の役は、なんとか果たしつづけてくれるのではないかと期待している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
