
コチ
あらすじ
コチは小さな蛾。
あだ名は『木枯らし』
枯葉色した小さな羽で飛んでる姿を見て誰かがそう叫んだ。
今は春。
厳しい冬が終わり、ようやく訪れた春。
そのあだ名は、春色の世界で悲鳴を産んだ。
コチは小さな蛾。夜にしか飛ばない。
そんなコチが工事現場で咲いた春を待つ花を見つけた。
青い四角のキャンパスに燻んだ白いシミ。
濁った色が重ね塗られてもうすぐ四角は灰色。
気づけばシミが白くチラリ。
青い四角に光が覗いた。
そこにあったのは、空だった。
風が雲を流さなければ、
カラスが騒がしく通り過ぎなければ、
月がひょっこりと顔を出さなければ、
太陽が輝かなければ
この空が偽物だって言えるのに・・
四角い空の下、花が一輪咲きました。
轟音が響き渡る。
ここは、工事現場。
力強く回るタイヤが地面を削り砂煙を出しながら移動する。
目隠しフェンスに囲まれたこの場所では砂煙と轟音が溢れかえっていた。
そこで動く機械は、何かを作っているのか、破壊しているのか、理由も聞かず無表情。
無表情の割に、動けばいちいち騒がしい。そこでまた人間も叫ぶように怒声をあげるから、この場所では音がギュウギュウに顔を寄せながら満員状態だ。
大きなショベルカー。
こいつもまた無表情。
ショベルカーがその大きな手で壊れかけの建物を引っ掻くと建物から灰色の瓦礫が崩れる。
灰色の砂煙がその一帯を包み込む。
無表情のショベルカーはきっと知らない。
その瓦礫が今、
今朝咲いたばかりの小さな花に降り注いだ事を。
機械は無表情でいちいちうるさい。
無表情に悲鳴を飲み込む。
もうここにはこれ以上の音は入りきらない。
入れるものかと他の音がひしめき合うのだ。
半分瓦礫に埋もれた花の声はここではどこにも届かない。
太陽だけは、砂煙の間から半分埋もれた淡いピンク色の花びらを照らしていた。
夜になる。
夜空には半分欠けた月がひっそりと雲の隙間から暇そうにぼんやりと光っていた。
声がした。
ん?
下を覗く月は、
「見えないよ。」
と取り巻く雲を風に頼んで追い払った。
すると流れる雲の間からチラリ。一輪の花が月明かりに浮かんだのだった。
「君かい?」
花は俯いたままだった。
月はあるはずもない首を傾げながらその花を見つめていると夜露で濡れた淡いピンク色の花びらから一滴の雫がきらりと落ちるのを見た。
「あらま。泣いているじゃないか。どうする?どうする?」
月はそわそわ辺りを見回す。
花の周りには誰もいなかった。
あるのは瓦礫と砂の山。
花はひっそり独りぼっちで咲いていた。
「おーい。こっち。こっちだよ。私はここにいるよ。」
ひっそりとしたその場所に不機嫌な音で車が走り去る。
ヘッドライトの光は煌々と伸び、
そびえ立つフェンスを駆け上がり
そのまま上空に飛び立って
いとも簡単に月明かりを消した。
車が去って、再び現れた月明かりと静かな夜。
無力感でいっぱいになった月は「誰かいないか?」とキョロキョロと辺りを探していた。
すると、夜道、決められた仕事をボケーっとこなす外灯に一つの小さな影がパタパタと通り過ぎた。
あ。
月は目を凝らす。
街灯の光を辿りながら、その小さな影は工事現場の方に向かっている。
あれは?
月は見失わぬようにその小さな影を追いかけた。
忙しなくパタパタと羽を動かすその小さな影の正体が分かると、月は、ホッと息を漏らす。
「あいつ。やっと来やがった。」
もう一度、風は静かに雲を月の前から追い払った。月明かりが、その小さな影を照らせるように。

その影の正体は、小さなガだ。
チョウじゃなくてガだよ。
チョウとガ。
区別はなかなか難しい。
チョウは美しくて、ガは汚い?
誰かの目で見たならそうかもしれない。
でも誰かの目で見たらそうじゃない。
残念ながら月はどちらの目も持ち合わせてはいない。
そのガは、月の顔なじみ。
このガをなんと呼ぼう。
ガは、そこら中にいるし、
ガなんて呼びづらいし、
読みづらい。
そうそう。このガには、あだ名があった。
その名も「木枯らし」。
その名の由来は、こいつの小さな羽だ。
こいつの小さな羽は、
まるで枯葉のような色をして、
欠けた葉のように不揃いだ。
そんな羽を忙しなくパタパタと動かし飛ぶ姿は、
まるで木枯しが枯葉を運んでいるようだと
誰かが、
春色の輝く太陽の下で、
こいつを「木枯らし」と呼んだんだ。
木枯らしなんて呼ばれて誰かが笑うならまだいい。
「木枯らしが来た!」
なんて聞いた奴らは
みんな顔を引きつらせた。
特に今は春だから、
全く縁起の悪い名である。
せっかく春がやってきたってゆうのに、またあの寒い冬に戻りたいなんて奴はそうはいない。
冬と春は隣同士。
なのに春は急に冬が怖くなったらしい。
このガにとって「木枯らし」というあだ名は、全く、居心地の悪い名だった。
でも、今は夜。
「木枯らし」は、
太陽のいるイロトリドリの世界での呼び名。
今は、太陽のいない遠慮がちな月が唯一輝ける夜。
今は月の知っている名前でこいつを呼ぼう。
そうそう。こいつの本当の名は「コチ」だった。
コチは、外灯を点々と辿る中、月の光に気がついた。
「なんだ。お前。今日も独りかい?」
月は、いつでも不機嫌にコチの言葉を無視するので、皮肉なコチの言葉は、そのまま自分に返ってくる。
「今日はやけに明るく光ってるじゃないか。太陽のいる世界じゃ。まるでおとなしいのに。全く情けない奴だ。あれ?お前、また太った?」
コチは、羽をパタパタと動かしては、電柱や外灯に止まり呼吸を整えた。
平然を装った口調で月に悪態を吐くコチだが、コチの呼吸は乱れていた。
小さな羽のコチは、あまり長い時間飛ぶ事は苦手だ。
しかし、今日はいつもより、なんだか呼吸が乱れて息苦しい。
鼓動が騒がしいようだった。
コチはまっすぐ工事現場の方に向かっていた。
休み休みだから進む速度は遅い。
いつものコチなら、今頃、行きつけの自動販売機でくだらないおしゃべりをしているはずだった。
なぜコチが工事現場に向かっているかは月も知らない。
でも月はなんとなく分かるんだ。
コチは月の顔なじみだからね。
コチが、夜にしか飛ばない理由だってコチは話さないけど、月はなんとなく分かってしまう。
意地っ張りで嘘の下手くそなコチは簡単に見抜かれてしまうんだ。
コチはその事を知らないけど。
「おいおい。なんだよ。これ?」
コチは震える声を誤魔化すように月に聞いた。辿り着いた場所で目にしたのは見たこともないとても高い壁だった。
その場所を覆い隠しそびえ立つ工事現場の目隠しフェンスは、見上げるコチにとっては空まで届くほどにどこまでも高かった。
そして、目の前のフェンスは威圧するようにコチを見下ろし、コチの立ち入りを無言で拒んでいるかのようだった。
いつものコチであったなら、フェンスに掲げられた「立入禁止」の文字が読めなくとも悩む事なく中に入らない選択肢を選んでいただろう。
コチの身体は正直に震えていたからだ。
「どこの誰が建てたかは知らないけど、この壁は趣味が悪いな。高すぎだよ。無駄に壁が偉そうじゃないか。この中が見たい奴の事を考えてちゃんと建てたのかい?全く中が見えやしない。責任者はどこのどいつだ?」
月は何も答えない。
コチの独り言を月は静かに見守っていた。
「一体中はどうなっている?静かじゃないか。いつもの下手くそな歌声が聞こえないぞ。」
コチはちょっとだけフェンスに近づいてみた。
「なんだよ。こんなのが建ってるから皆んなビビって黙っちまったのか?」
コチは体に着いた恐怖を払うようにぶるっと羽を動かした。
そしてそのまま勢いをつけ、フェンスの頂上に向かって飛んだ、
が半分にも届かずその勢いは止まった。
羽をいくら動かしても体が上に持ち上がらない。
右へ行ったり、
左へ行ったり、
同じ高さの所を彷徨うかのようにただ浮いていた。
不憫に思ったのか風がコチの重いお尻を押す。
風が何度押してもコチの体は持ち上がらない。
コチはすぐに力尽きた。
落ちる体はなんとかフェンスにしがみつき止まった。
ヘッピリ腰でフェンスにくっつくコチは、ジリジリと短い手足を動かし、ちょっとずつフェンスを登ることにした。
這って登った方が早いって事に気づいたようだ。
なんとか、フェンスの頂上まで登ったコチは、ゆっくりフェンスの中を覗き込んだ。
しばらくの間、コチは黙ったままだった。きっと頭の中で何度も繰り返し問いかけたのだろう。
「本当にここ?」
コチが絞り出した声が虚しく空に響く。
月はいつものように何も答えてはくれなかった。

ここは空き地だった。
その空き地には、廃墟がぽつんと立っていた。
廃墟には止まったまま、時間を忘れた時計が空き地を見下ろすようにかけられていた。
でも誰も見ない。ここには時計の針を気にするものなど誰も残ってない。
そこは人間が忘れ去った場所だった。
その場所を空き地と呼ぶのは人間だけ。
人間のいないその地で、草はボーボーと張切っていた。
誰が1番先に青い空にタッチできるかと競争するように草はぐんぐんと空に近づいた。
普段、必死に羽を動かし低空を飛ぶ虫たちもその草によじ登れば恐れのない大きな空を鳥のように感じる事が出来た。
特に夜は最高だった。
伸びた草によじ登れば、星に手が届きそうだった。
風がふわっと草を揺らす。
持ち上がる体、あともう少しと星空に向かって手を伸ばした。
月だってすぐそば。
淡い光が揺れる葉を照らす。
自然とそこに音楽が生まれた。
コチはここで生まれる音楽が大好きだった。
コチの知っていたこの場所は、人間の仰る通り本当に誰もいない空き地になっていた。
今は、張り切って伸びる草はなく、音楽も聞こえない。
月だけが取り残されたようにぽつんと空に浮かんでいた。
月明かりが照らしているのは、色のない瓦礫の砂山と崩れかけの廃墟、冷たい大きな手を地面につけて眠って動かない重機達だけ。
他には、何もない。
コチはぐるぐると靄がかかった頭の中のように工事現場の上をただ飛んでいた。
いくら飛んでも、目に入ってくるのは同じ。
色のない世界。
崩れた瓦礫は至るところでクズ山になり、コンクリートの塊から血管のように突き出た針金が山から覗く。その山を潰した形でそこを通り過ぎた車輪の跡が模様のように散らばる。
月まで届きそうだったあの伸びた草達はもういない。あのどの草よりもどこまでも高いフェンスがこの場所を四方で囲み閉ざしていた。
月が太陽のように輝かなくて良かった。
コチは眠る大きな機械の上に恐る恐る着地した。
どこだか知らないが機械の顔色を伺う。
冷たく動かない機械はどうやら動きそうもない。
「やれやれ。世界はこうも簡単に変わってしまうものかね?」
平静を装ったコチの声が虚しく夜空に消える。
「君、見かけない顔だよね?ここに何をしに来たんだい?」
機械の上から下を覗くと、今にも大地が割れそうなほどの重そうな足には、何度、潰されたのだろうか、潰れた土や小石が足にへばり付いていた。そして、イビツなほど大きな手の指の間には色のない塊のカスとわずかな緑の草が絡まっている。
機械は答えているのに、コチはその答えをはぐらかすように重機の手から視線を外らした。
こいつが何者で何のためにどこから来たのか知るはずもない。
コチの周りには、コチの知らない大きな力が溢れかえっていた。
「どうして?」なんて、それをいちいち考えていては切りがない程だ。
知ってもコチにはきっと理解ができやしないのだろう。
今、この大きな機械は動かない。だからコチに危害を加えない。いつもはそれが一番重要な事だった。
それでいいじゃないか。
抑えようとしてもコチの鼓動は激しくなった。「叫び」に化けて、飛び出してきそうな鼓動を口から吐き出さぬように、ぐっと堅く口を閉ざす。でも、コチの脳裏に何度も一匹のチョウが通り過ぎ、それを邪魔する。コチは、そのチョウを追い払うようにゆっくりと深呼吸をして、暴れまわる鼓動を落ち着かせて、言葉に変えた。
「どうしようもないだろ?僕に何が出来たっていうんだ・・」
コチは、何もかもを追い払うように羽を動かした。
「帰ろう。」
コチは、独りぼっちの月をちらっと見上げる。
「また、あの高い壁を登るのか。全く。趣味の悪い壁だ。」とコチは、気を紛らわすように近づいてくるフェンスをわざと煩わしそうに見つめた。
すると突然声がした。
「あなたはチョウチョ?」
コチは声に驚きすぐに瓦礫の影に隠れた。大きく鼓動が鳴る。コチはすぐに辺りを見回した。コチの目に映っているのは、やっぱり不規則に積み上げられた瓦礫の山。空耳だろうか。
「しゃべった?」
激しくなり続ける鼓動の音に気付かないフリをして月を見上げるコチ。
気のせいか、なんだか月はさっきよりも輝いているように見えた。
月明かりはゆっくりと下降する。
コチは月明かりに誘われるようにそこに視線を追いかける。さっき通り過ぎたあの瓦礫の山と山の間。
その谷間に光が降り注いでいる。
そんな気がした。
コチは、羽を小刻みに動かし、さっき通った光の落ちるその場所に恐る恐る、それでもパタパタパタとうるさく羽を動かし近づいた。
高鳴る鼓動を抑えるように息を殺す。
もうすぐ。
そして、
チラリと谷間を覗いた。
あ、
いた。
そこには半分砂に埋もれた一輪の花が咲いていた。

「やっぱり来てくれたのね、チョウチョさん。チョウチョさん?」
コチは、何も見なかったかのようにそのままその花の上を通り過ぎていった。
半分灰色の砂を被った花は、確かにコチを見て「チョウチョさん」と言っていた。
コチの体の中を何かがこみ上がる。こみ上げたものは困っただろう。せっかく来てもらったのに行き場所を失ってしまった。コチは、出て行かせるものかと、目と口を必死に閉ざしていたからだ。
さっきから、コチの中には、色々なものが閉じ込められている。
「チョウチョさん。私はここよ。」
コチは、確かに聞こえる花の声に気づいていないふりをした。
そして、何も見ていないと訴えるようにキョロキョロと下手な演技をする。
「なんだろう?気のせいか?」
三文芝居で空を見据えるコチの言葉は、棒読みで滑稽なものだった。
バタバタと動かす羽はいつもより増してぎこちないものである。
「ここよ。ここにいるわ。」
背中を追いかける花の言葉を無視してコチは花が見えないであろう所までやってくると急いで逃げるようにその場を離れた。
無我夢中で羽を動かしたコチは、あれだけ苦労した高いフェンスを難なく乗り越え、滑り落ちるようにフェンスの外側にしがみつく。
「ここよ・・」
最後に微かに聞こえた花の声は力なく、ただコチの耳にはしつこく鳴り響いた。
コチの呼吸は乱れていた。
呼吸を整えるには随分と時間を費やした。
その間、コチの様子を月は呆れたように見ていた。
コチは月のそんな顔に気がついて、誤魔化すように話す。
「見た?こんなに高い壁を簡単に飛び越えたぜ。どうだ。やればできるだろ。」
コチがいくら花の出現をなかった事にしたくても、月の冷たい視線は、はっきりコチに訴えかけた。
コチはすぐに月から目線を外す。
「別に逃げたわけじゃないよ。」
コチはチラッと視線を上げるが、またすぐに逸らした。
「あの花。俺をチョウチョだって?失礼しちゃうぜ。俺のどこがチョウチョだよ。」
コチは、さも怒ったかのように振舞うが、月の視線は変わらない。
都合が悪くなると、突然怒ったふりをするほど、カッコの悪い事はない。
コチだって羞恥心くらい残っている。
「まあ、別に勘違いなんて誰にでもあるよな。」
コチはさっきの怒りを撤回するように、ボソっと囁いた。
「ムキになるなよ。ただの勘違いさ。」
コチは冷静に自分に言い聞かせた。
「木枯し」というあだ名。
時に花の悲鳴だって起こす奇跡のその名を何度も勘違いだって、コチは自分にそう言い聞かせてきたんだ。
「行ってしまったわ。」
壁の向こう側から声が聞こえた。
花の声だ。
「せっかくチョウチョさんがここに来てくれたのに。私に気付かずどこかに行ってしまったわ。」
コチは壁の奥に耳を傾けた。
そして、何度も頭の中で繰り返し聞こえてくる花の悲しいあの声を消して上書き保存できないものかと耳を研ぎ澄ました。
でも、聞こえてくるのは、また、悲しい声かもしれない。
コチの心臓の音が花の声を聞く事をやたらと邪魔をした。
「ねえ。お月さま。私は本当に花を咲かせたの?ここじゃ誰も教えてくれないわ。」
「なんだ、あの花も月と話すのか。」
コチは月を見上げると月はまだ呆れた様子でコチを見ていた。
「なんだよ。文句あんのかよ。」
コチは月を睨み返すが、バツが悪くなったのかすぐに月から目を逸らした。
都合が悪くなると突然怒ったふりをする。
変わらずコチはカッコが悪かった。
ただ、どうする事もなく。
羞恥心を見て見ぬふりをした。
「俺をチョウチョと勘違いするなんて、あの花はなんて馬鹿なんだ。俺をチョウチョと勘違いする奴なんて…。子供と同じさ。全く馬鹿な花だよ。」
コチに、一瞬、虫取り網を持った人間の子供に追いかけられた記憶が蘇るがすぐに消えた。
背筋が震えるような記憶だったが、さっきコチ自身がやってしまった三文芝居の方が、よっぽど背筋が震える記憶だった。
無邪気さとは程遠い。
少し歪んだ表情で再び空を見上げるコチ。
コチの見上げる空にはやっぱり呆れた月がぽっかり浮かぶ。
あの花の見る月も呆れ顔なのだろうか。
月がいつ返事を返したのか。再び花の声がフェンスの奥から聞こえる。
「そうよね。きっと私には綺麗な花が咲いているわ。なぜ、あのチョウチョは私に気づかなかったかしら?やっぱり私が砂に埋もれてしまったせい?」
月は、こいつのせいだと言わんばかりにコチを睨んでいる。
「いえ、そんな事はないわ。たくさんお月様の光を感じるもの。きっとあれね。実は、私、よく見えなかったの。お月様はさっきのチョウチョの顔を見た?きっと間抜けな顔をしていたはずよ。だって私の素敵な花に気付かないもん!」
コチはフェンスの奥の一点を見つめた。
「口が悪いね。」
ふふ、と笑う花の声にコチはムスっとしながらも、どこか、花の言葉に救われたようだった。
良かった。笑っている。
「よし。帰るか。」
コチが欠伸して見上げた空。
月は、まだコチを睨んでいた。
「うるせえ。うるせえ。俺に何が出来るっていうんだ。帰るよ。」
突然、コチのとまっているフェンスが激しく揺れガタガタと轟音をたてる。
ん?
次の瞬間、ビューっと強い風がコチを襲った。
コチの羽は激しく乱れ、コチは振るい落とされないようガタガタと揺れるフェンスに必死にしがみついた。
「ナ、ナ、ニ、ナニ、何?」
コチの言葉も揺れる。
コチはまるで風に煽られる旗のように上に下に右や左にと体をゆさ振られ、小さな細い手でなんとか飛ばされないようにフェンスに必死に掴まりながら持ちこたえる。
風はフェンスの上から下へ、そして、フェンスの隙間からその中へ入ろうと何度も何度もフェンスを激しく揺らす。
急に風は止んだ。
何かを連れ去るかのようにヒューイとどこか遠くへと消えていった風の音。
後には、また静けさが戻った。
「何?今の?」
静けさに、コチの声が響く。
コチの体の向きが気づけば逆さを向いていた。コチは乱れた羽を整えるように小刻みにブルッと羽を揺らしたが、ぴょんと寝癖のように一本羽が逆立った。
静まり帰ったこの時間に突然歓喜の声がフェンスの奥から聞こえる。
「わあ。見て!お月様。風が砂を連れてってくれたよ。」
どうやら、さっきの風が花にかぶった灰色の砂を吹き飛ばしたらしい。
コチは、あまりにも喜ぶ花の声に、フェンスの中の様子が気になった。
でもコチは、ちらっとでもフェンスの中を覗く訳にはいかなかった。
空には月がいる。
気になっている所なんて見せる訳にはいかないのだ。
「だったら、逃げるなよ。」
なんて痛い所突いてくるに違いないのだ。 コチは月の言わんとする事は全てお見通しなのだ。
ここで花の声に耳を傾けている分には問題ない。
ここなら幾らでも言い訳が言える。
「花の声なんか聞いていない。そんなの聞こえた?」とか。「疲れたからここで休んでいる。」とか。「根拠を出せ!根拠を!」とか。言い訳なら得意だ。
くだらない思考を喜ぶ花の声が消した。
「今度またあのチョウチョさんが、ここに訪れてくれたら、今度は私の花に気づいてくれるかしら?」
花の声は希望に満ちていた。
「いくら間抜けさんでも今度は大丈夫よね。」
ふふふ。そよ風のような笑い声。
コチは、ちらっと月の顔色を伺った。
やっぱりコチの予想通り、「早く戻れ」と急かすようにコチを睨んでいる。
「だから、俺はチョウ何かじゃないよ。俺が戻った所であの花は、きっと間違いだって事に気付くんだ。もう少し、お前の光を俺にあててごらん。きっとお前も納得するだろうよ。」
コチは月に訴えるように話すが、月はただ睨むだけで、コチの言葉に納得していない様子だ。
コチの羽が揺れる。
勢いはないが、風がまた戻ってきた。
コチは、少し嫌な予感がした。
「なんだ風君?また戻って来たの?」
風はしきりにコチの羽を揺らしていた。
「おいおい。また急に暴れたりするなよ。君たちの仕事はもう終わったはずだ。あの花の砂をどかしてやったんだから。よくやったじゃないか。」
コチは、不安いっぱいにさらさらと揺れる羽を見ていた。
「なあ。いつまで俺の羽を揺らしているつもりだい?」
「そうか。さっきの事?俺に謝りたいのかい?いいってもう。過ぎた事だ。」
生暖かい風は、今にも走り出しそうだ。
「ほら、もうどっかに行きな。ほら、あの花の頭でも撫でてこいよ。」
そう言いながらもコチの手足には力が入っていた。
春疾風がいつまでも黙っているはずはない。
今か、今かと吹くかもしれない強風に対して身を構えていた。
すると風が止んだ。
「風さん。ありがとう。そうね。今度はきっと気付いてくれるわ。」
風は本当に花の頭を撫でに行ったのか。壁の奥から、花の声が漏れる。
風が離れた事を知り、コチの体の強張りが溶けた。
次の瞬間、凄まじい突風が吹いた。
待ってましたとばかりに、風は猛スピードでコチに襲いかかった。
不意を突かれたコチは、空中に投げ出される。
ビューっと吹いた風は、遊んでいるかのように、コチを無邪気に上下左右と宙に転がした。
空中でコチの羽はくるくると絡み合うようにに踊り狂う。
悪態を口にする余裕はコチにはなかった。
回る頭の中で、言葉が一緒になって回る。
どんだけ激しく飛んでいたのだろう。
「今、俺はどんな状態?」
くるくると回る朦朧とした意識の中で、どっちが空でどっちが地面か、答えを探した。
進んでいる先が地面だと分かるのがもう少し遅かったならコチは、風の勢いに乗って、工事現場の瓦礫の山の中に突っ込んでいただろう。
急ブレーキをかけるようにコチは空中に止まった。
恐怖で閉じていた目をゆっくり開く。
コチの目の前に月光にきらめく花が再び現れた。
こんなに近ければ、もう見て見ぬフリなんて出来やしない。
遠のく意識の中コチは言った。
「やあ。」
「やっぱり見つけてくれた!」
静かな夜だから安堵と喜びに満ちた花の声が月まで聞こえただろうか?
さっきまでコチを乱暴に運んだ風が優しく花びらを揺らし通りすぎた。
花は小さな声で「ありがとう」と囁いた。
そして、コチは、くるくると回る視界の中でとうとう意識を失っていた。喜びを分かち合おうとやってきた風のハイタッチに、叩かれるように飛ばされそのまま地面にポトリと落ちた。

「チョウチョさん?」
コチの耳にようやく花の声が届いた。
コチはいつの間に眠ってしまっていたらしい。
いや、あれは気絶だっただろう。
暴風がなかったかのようにやけに夜は静かで、何も見なかったとばかりに月も雲に隠れ、ぼんやりと淡い光を浮かべる。
静寂な夜。
花の声だけがそこに響いていた。
「チョウチョさん。大丈夫?どこにいるの?」
何度も聞こえる花の声。
花の声はコチのすぐ近くから聞こえた。
雲に隠れた朧月を見上げながら、コチは、聞こえてくる声を辿った。
目の前に花が現れてそこからよく覚えていなかった。
ポテッと落ちてコロコロと瓦礫の山を転がっていったのだろう。
瓦礫の山を一つ隔てて、コチと花は隣にいるらしい。
どうやら花の場所からはコチの姿が見えないようだ。
なんとなく今の状況を把握したコチは、ムクッと起き上がり、体の調子を自分の体に伺った。
特に痛むところはないし、羽も傷ついてはいなかった。
ただ、体を動かすとそれに反応して胸糞悪い化け物が、頭をぐるぐると這いずり回った。
「うぅ。気持ち悪い。」
コチは頭を押さえ、なんとか化け物を落ち着かせる。
月は、雲に隠れ、コチの様子を伺っている。
不機嫌に体の砂をはたくコチ。
月がコチのご機嫌を伺うようにそぉっと雲の間から顔を出した。
コチは月を見ようともしなかった。
コチは、静かに少しずつ羽を動かし、動くたびに、気持ち悪くなる頭を宥めながら、山を登る。
その頂まで来ると花に気付かれないように屈みながらゆっくりと谷底を覗いた。
花の横顔を見つけた。
花にかぶった砂は綺麗に風が運んでいた。
花びらは月明かりに照らされ、淡いピンク色がかすかに夜に浮かんでいる。
心配そうにキョロキョロと辺りを探している花。
声には、悲しみが現れ始めていた。
月の気持ち。
月はコチを見ていて心配になっただろう。
それもそうだ。
いたずらな風に無理やり運ばれてきたのだ。
あんなにめちゃくちゃに飛ばされた虫を見て、何故だろう、思い出すと笑いそうになるじゃないか。
そんなはずはない。
あんな勢いで飛ばされたんだぞ。
気を失うくらいで済んでまだ良かった方だ。
怪我でもしたらどうするんだ。
笑うなんてけしからん。
そう思えば思うほど、笑いそうになるはずだ。
まだ、雲の間から顔を出すには早かったんじゃないかな。
月が心配なのは、今のコチを見て吹き出して笑ってしまいそうな事だけじゃない。
あんな飛ばされ方をされたコチの気持ち。
あんな飛ばされ方をされたのに笑いの対象にされているコチの気持ち。
ちっぽけなコチの気持ちを考えると心配だ。
きっと、あいつはヘソを曲げている。
月の嫌な予感。
コチは、今、必死にコチを探すあの花の言葉をきっと無視するだろう。
さっき、やったみたいにきっと花を傷つける。
ましてや、闇雲に暴言なんて吐かなきゃいいが。
月は心配そうにコチを見ていた。
「間違いだったのかな・・・?」
「違う。私はちゃんと見たわ。大丈夫よ。大丈夫。」
しきりに自分に言い聞かせる花の声が静かな夜に悲しく悲しく響く。
もちろんその声は、そばにいるコチの耳にも届いていた。
ほら、やっぱり。あいつは無視をするだろう。
月は、もちろん知っていたさ、と予想の範疇であると自分に言い聞かせ、溢れ出てくる苛立ちを抑えようとしていた事だろう。
声がした。
「ここだよ。ここ。」
・・あれ?
月は「え、あいつ?」と宙を舞う風に問う。
「ここにいるよ。僕が見える?」
恥ずかしそうに、でも優しいコチの声が確かに月まで届いた。
ぼんやりした月明かりじゃなかったなら、コチの真っ赤に染まった顔が見えた事だろう。
でも月はその顔を知っている。
月の安堵したため息を夜風が運ぶ。
夜風が花の頬を撫でる。
花は、積もったばかりの悲しみを息と一緒にふーっと吐き出した。
その風は閉ざされたひとりぼっちの部屋の扉を開いた。
「ど、どうも。えっと、ごきげんよう。えっ、いや、こんばんは?」
花の声は緊張した様子で、所々上ずっていた。それでも、なんとか、明るい印象を与えようと、何度言葉がつまずいたり、転んだりしても話し続けた。
「お、お会いできてとても嬉しいわ。えっと、あなたはどこにいるの?ここからでは、あなたが見えないみたいなのです。」
花は、必死で見えない相手の顔色を伺うように話していた。
コチはというと、なにやらモゾモゾ動いている。
コチは、「話をする事くらい別に大した事じゃないだろ?」と自分に言い聞かせ、自分は余裕であると月にアピールするかのようにその場所で、楽な体勢がないかと、何度も体の向きを変え、月と花の見える絶好の位置を探していた。
「こりゃ良い。」と最適な体勢で月を見上げるコチ。
早く返事をしろ、と、そんなコチを月が睨む。
そこでは、横を向くと花の横顔が見えた。
花の横顔は、コチの返事を待ち望んでいた。
コチは、ばれないようにゴクリと大きく息を飲む。
そしてゴッホンっと息を整えた。
「君の近く。とっても月が良く見える場所だよ。」
花は、まだコチの事を探していた。
声から近くにいる事はわかる。
でも見つける事は出来ないようだ。
その体勢とは裏腹にドキドキと瓦礫の山の上に寝転がるコチだったが、コチは花が自分の事を探せない理由をすぐに理解した。
コチの羽の色はくすんだ色の瓦礫によく溶け込んだ。弱い月の光では、発見は難しいのだろう。第一に花はコチの事をチョウチョだと思い込んでいる。
見つかるわけがない。
「私の場所からも月がとっても良く見えます。きっと近くにいるんですね。でも、ごめんなさい。やっぱり暗がりであなたを見つける事が出来ないわ。」
花はお月様とは言わず、コチに合わせるように月と呼んだ。
「見えなくて当然さ。月の光は弱いから、月の世界は、音の方が良く見えるのさ。だから話をするには、なかなか良い世界だよ」
月は自分のせいにされている事が不服だったに違いない。
「ここは、月が良く見えて寝心地の良い場所だから、今日はここで君とお話をしながら眠る事にしよう。いいかな?」
不服そうな月の視線に気がつかないコチ。
でもコチには、それは花にとっても最良の方法だと思ったのだ。
「もちろん。」
「嬉しいです。ずっと誰かとお話しがしたかったから。」
優しくコチの耳に触れる花の声。花は、もう、コチの姿を見たいとは言わなかった。
「それは良かった。」

コチは話をしようと言っときながら何を話していいか、分からなかった。
花はずっとコチに気を使いながら話をしているし、コチはそんな風に話される事に慣れていない。
コチも花に対して、そうやって話さなければならないような気がする。
相手に気を使った言葉をコチはいくつ知っている?
そんな事を考えていると、自然と沈黙が現れる。すると、花から口を開いた。
「とても月が綺麗な夜ですね?」
せっかく花から話を振ってくれたのに、空に浮かぶ月を花に合わせて褒める気にはコチはなれなかった。
月の話をしていると、月の視線が気になって仕方がない。
見上げると月は澄まし顔。
コチは月に言うように答えた。
「そうかな?いつも通りさ。今日もお月様は不機嫌そうな顔をしているよ。」
花は思ってもいないコチの返事に少し戸惑った様子だったが、花もコチと同じように、きっと、この堅苦しい不慣れな会話がこのまま続いたらどうしようって思っていたに違いない。
何か解放されたかのように花は少し語気を強めて答えた。
「不機嫌?私には、お月様が笑って見えるわ。」
コチも一緒に語気を強めて話す。
「月が笑うだって?俺は月に笑いかけられた事なんて一度もないよ。ひどいやつだ。あいつは。きっと相手を選んでいるんだな!」
真面目に言っているのか、花は月をけなすコチの言葉が妙に月に対して親近感があって可笑しかった。
花は、クククッと笑った。
笑わせるつもりではなかったのに、花の笑う横顔を見てコチは何だか不思議な気分だった。
悪い気分じゃない。
フェンスの外からでは覗けなかった花の笑う横顔が、ようやく見えたからだ。
「お月様が相手を選んでいるなら、光栄だわ。お月様は、いつも私のそばに来て笑っていてくれるから、私はとても安心するのよ。だからあなたと一緒にお月様の悪口は言えないわ。」
花の言葉からは、もう緊張の糸は解けていた。
「それは残念だ。今日は月に言ってやりたい文句が山ほどあったのに。君が参戦してくれないならやめておくよ。月も君に感謝すべきだな。」
「そうね。やっと少し恩返しできたかしら。」
そして、花はクククッと笑った。
コチはきっと気がついていないだろうが、この時コチも一緒になって笑っていた。
なかなか良い雰囲気じゃないか、と見ていていたのは、やっぱり月。
その会話のほとんどが私の会話だとまんざらでもない表情だったが、コチはほとんどもう月など見ていなかった。
花がよく笑うものだから、その表情を見る事で忙しかったのだ。
なかなかうまくやれている。
コチもきっとそう思っていたのだろう。
でも一瞬忘れていた事が突然、花の言葉によって思い出された。
「ねえ。チョウチョさん?あなたはどこから来たの?」
花は、笑いながらあまりにも自然にコチをチョウチョさんと呼ぶものだから、コチも危うく「なんだい?」なんて返事をしそうになってしまった。
そうだった。
花はコチの事をチョウだと思い込んでいるのだ。
勘違いは継続中だった。
そうだったろ?
だから、あんなにたくさん笑っているんだ。
あの笑い声はコチに向けられたものではない。
コチは返事に困ってしまった。
コチは、何も答えない。
そして沈黙が、なんだい?と現れた。
月は、どうした?そこは「なんだい?」と答えればそれで良いだろ?何が違う?
と心配そうに遠い空からコチの様子を見守った。
「チョウチョさん?・・」
花は、どうしてお前がやってきたのかと訪れた沈黙を追い出すようにコチに聞いた。
意を決したコチの不自然な笑い声が夜空に響く。
「俺がチョウチョだって?何を言っているんだよ。俺はチョウなんかじゃないよ。」
「えっ?」
やってしまった、と月が頭を抱えるようだった。
コチはまるで降臨してきた大魔王のように、空を見上げ、ハッハハハ、と声を出し笑う。
また、あの三文芝居だ。
うんざりするような月の視線を感じる。
でも、そうする事で、花の悲しむ顔も悲しんだ声も聞かなくてすむ。
耳を閉じるようにコチは大きな声で笑っている。
異様な笑い声の隙間から、花の声が聞こえた。
「・・なさい。」
うるさいコチの笑い声が花の一言によって止まった。
なんて言ったのだろう。
悲鳴ではなかった。
コチは、恐る恐る花の横顔を見た。
花の表情はやはり曇っていた。
花の笑っている顔は、まぼろしのように遠くへ行ってしまった。
仕方ないよ。
コチには、瓦礫に溶け込むくすんだ羽がはっきりと見える。
「大丈夫。大したことじゃない」とコチは羽で瓦礫の表面を軽く撫でる。
静かになった夜。
月の世界では、花の声はやっぱりよく聞こえた。
「ごめんなさい。私、ひどい勘違いをしてしまったのね。失礼な事を言ってしまって本当にごめんなさい。」
花の言葉は案の定、悲しみに満ちていた。
でも、それは、悲鳴のようなコチを追い出す悲しみではなかった。
花の悲しみの中にはちゃんとコチがいたような気がした。
大声でバカみたいに笑っていた自分が急に恥ずかしくなった。
「おいおい。謝らないでくれよ。別に構わないよ。俺はそんなチョウのような大したやつじゃないから、間違えてくれて光栄さ。」
コチは花を慰めるため、今まで思ってもみなかった事を口にした。
コチはすぐに自分が言ってしまった事を後悔する。
思わずチョウなんかを褒めてしまった。
小さなコチの小さなプライドだ。
そんな小さな舌打ちはきっと花には聞こえなかっただろう。
「本当にごめんなさい。恥ずかしいわね。飛んでいるあなたを見てチョウだと思い込んでしまったみたい。実は、私、この世界のことをあまり良く知らないの。ここには、ほとんど誰もこないから。お話するのも久しぶり。最初、私の会話おかしかったでしょ?どこかで笑われてしまわないか、ヒヤヒヤしてたわ。」
コチは、フェンスの中で広がる瓦礫の山を見回した。
ここで独りぼっちの花が謝るにはどうしてもおかしい状況だ。
「実はさ。君が不自然に「ごきげんよう」とか言った時、必死で笑いを堪えていたんだよ。でも、心の中では爆笑さ。だから、もう謝らないでくれよ。そんなに謝られたら、今度、ふと、君を思い出した時に思い出し笑いがしづらくなっちゃうだろ?」
コチは笑いながら話す。
花は、恥ずかしくなったのか、大きな声を出した。
「ひどいわ。やっぱり笑っていたのね。」
「だから笑っていないって。必死で堪えたって言っただろ?でも、君は見たかな?あの時、月は腹を抱えて笑っていたよ。やっぱりあいつはひどい奴だな。デリカシーを知らない。」
呆然と空にぽつんと浮かぶ月。
「嘘ね。あなたはさっきお月様の笑った顔を見た事がないって言っていたわ。また、お月様を悪者にして。ダメよ。」
ホッと月は空に浮かぶ。
「やっぱりダメか。君と一緒に月の悪口を言うのは、どうやら今日は本当に難しいみたいだ。もう諦めるよ。」
花は、また、クククっと笑っていた。
「私とお月様の関係は特別よ。お月様が来てくれなかったら夜が寂しくて仕方がないわ。」
「それは、お邪魔しました。悪い事しましたね。」
「謝らなくてもいいわ。あなたも私の失礼を許してくれたんだから。これでお相子になるかしら?」
どんな方程式を使ったらそれがお相子だと導く事が出来るのだろう?
人間だってきっと解けやしない。
コチは少し後ろめたさを感じながらも「うん。」と小さく頷いた。
「良かったわ。これであなたも思う存分、思い出し笑いができるわね?」
「そうだね。なるべく控えるよ。」
優しい風が羽を花びらを揺らす。
「あら、優しいのね?」
クククっと笑う花の笑い声は確かにコチに向けられていた。

「ねえ。さっきの話だけど、ここには誰も来ないの?」
何気なく聞いてしまったコチだったがコチはすぐに後悔した。
一瞬黙ったその悲しい花の表情を見つけてしまったからだ。
ここで隠れて花を見ている自分が恥ずかしくもあった。
でも花の顔はすでに笑顔に変わっていた。
花はコチなんかよりもずっと強かった。
「そうね。誰も来ないわ。でも、お日様が昇るとね、ここには、人間がやってきて、とても賑やかになるの。」
花は、弾んだ声で話をした。
「げぇ。人間か。」
コチは、大げさに嫌な声を出した。
「あなたは、人間が嫌いなの?」
コチは花の表情を探っていた。
憎しみなどどこにもなかった。
少しして、また恥ずかしくなった。
「嫌いって訳じゃないけど、苦手だよ。だってあいつら不気味だろ?いったい。何を考えているか全然分からない。」
「そう?」
花は、どういう事なのか、コチの言葉にコチの世界を探していた。
「例えばだよ。人間が歌を歌う姿を想像できるかい?」
花はクククッと笑った。
良かった。
今度は無理に作った笑顔じゃない。
「あなたはびっくりするかもしれないけど。私、人間が鼻歌を歌っている姿を見たことがあるわよ。」
「おいおい。冗談だろ?」
コチは、からかうように花に言った。
「本当よ。人間は歌も歌うし、とても物知りなのよ。人間は私に色々と知らない事を教えてくれるの。」
「おいおい。そんな事言って、君は人間の話す言葉がわかるの?」
「ええ。わかるわ。」
花は自慢気に言う。
「どうだかねえ。」
コチは半信半疑にそう言ったが、どうでも良くなった。
花の嬉しそうな表情が現れたからだ。
花は話を続ける。
「ここは、賑やかな場所だから、普段聞こえる人間の声は、叫ぶような声だけど。音が止まるとね、人間の声は穏やかで、人間同士で話を始めるの。まあ、物を知らない私だから、物知りな人間の言う話はほとんどチンプンカンプン。」
コチは、当たり前のように人間の話を続ける花に困惑しながらも聞き耳を立てていた。
「でもね。今日、人間が話していた話は、私にも理解出来て、とても素敵な話だったのよ。」
急に花の声色が変わった。
「ねえ、人間が今日話していた素敵な話を聞きたい?」
花は、弾むような声でコチに聞いた。
コチは、はしゃぐ花を見て少し照れてしまった。
それは、花の言っている事が馬鹿げた事だとか、そういう訳ではない。月は徐々に遠のいて行くのに、楽しげに話す花が眩しいほどに輝くのだ。花が人間の話を聞けることなんて別に大した事ではないなんて思えてしまう。
「どうせ、人間の言う事なんて嘘ばかりさ。」
コチは照れを隠すように、興味のないふりをした。
「いいから聞いて。今日は特別な日なの。あなたは流れ星を見たことがある?」
「ナガレボシ?」
「そう。流れ星。時々、夜空にヒュンって、光の線が見える事があるでしょ?あれをね、流れ星っていうの。」
「へえ。あの走る星にそんな名前があるのか。」
「そうよ。素敵な名前でしょ?でね。人間が話していたんだけど、その流れ星には、不思議な力があるのよ。」
「不思議な力?」
「流れ星が空にヒュンっと現れるでしょ。流れ星が現れて消えるまでのその間に願い事を言うの。そうすれば、その願い事を叶えてくれるんだって。」
「なんだそれ?やっぱり人間はとんだホラ吹き野郎だな。」
「でも素敵な話でしょ?私は信じるわよ。」
クククっと笑う花。
花が信じる空には、月がまだ端の方で、「お邪魔かな?」と淡い光を夜空に照らす中、星がちらほらと小さな光を撒き始めていた。
「今日、流れ星は来るのかな?」
コチがそう言うと、花は、その言葉を「待っていました。」とばかりに話を始めた。
「人間の話には、まだ続きがあってね。今日は特別な日なの。」
「特別?」
コチは花の横顔を見ながら答えた。
「特別」の意味は知っている。
「流星群よ。」
花は、自分が集めた宝箱から、一番とっておきの物を出すようにコチに言った。
「なんだ。それ?」
「流星群っていうのはね。流れ星の集まりよ。流れ星が、空一面に現れて、空は降り注ぐ星でいっぱいになるのよ。」
「ふーん。なんで?」
「流れ星が空に現れるのって、一瞬でしょ?突然現れて、願い事をする前にすぐに消えてしまうから、みんな願い事が出来ないのよ。だから、きっと流れ星は、みんながお願い事できるように、集まる約束の時間を決めたのよ。でね。でね。」
「あー。特別な日?」
「そう。今日がその約束の日なのよ。」
楽しげに話す花の声。
傍で聞くコチが見つめる先には、一面の瓦礫と、大きな機械。
コチは静かに口を開く。
「今日が?」
「ふふっ。信じていないのね?」
「だって人間が言った事だろ?人間はろくな事をしないからな。」
「でも、私は信じるわ。今日は本当に素敵な夜だから。」
花は微笑みながら答えた。
そっと風が花びらとコチの羽をそよそよと揺らす。
あまり相手にされなくなった月がもう遠くへ移動し、それでも、二つの揺れる影をしっかり浮かばせていた。
二人の間を何度も戯れるように優しい風が通り過ぎる。
コチと花の間に優しい時間が時を刻む。

「ねえ。流れ星に何を願う?」
花は思い立ったようにコチに聞いた。
「えっ?」
コチは突然の花の問いかけに言葉を詰まらせた。
「だって、流星群は今日なのよ。ちゃんと準備しとかないともったいないよ。ねえ、何を願うの?」
花は、コチの答えを待ち望んでいた。
願いなんてものは、近頃コチは考えた事もなかった。
まだ葉っぱを齧っていた頃は、願いはすぐ近くでパタパタとたくさん飛んでいた。
いつからだろう。
「こっちに来るな」と遠ざけていた。
今は遠く、もう見えないところまで行ってしまったようだ。近頃、とんと音沙汰がない。
花をずいぶん待たせた気がした。
「世界征服かな。」
そう言うと、コチはあの大魔王降臨の笑い方をした。
コチが出した答えに対して、花は吹き出しながら笑った。
「出た。ホラ吹き野郎だ。」
花は笑ってくれた。
花はまだ近くにいる。
「じゃ君の願いはなんだよ?」
「えっ?私の願い?」
花は少し言葉を詰まらせて、でもコチのそれとはちょっと違う。
手探りで適当に今探している訳じゃない。
逃げないように、大事に握りしめていたそれを、少し照れながら壊れないように開いていく。
「ねえ。あなたは虹を見たことがある?」
「えっ?虹かい?」
コチは何かを思い出した。
✳︎
コチにとってずいぶん懐かしい話だ。
今、音沙汰のないあいつがまだ傍にいた頃コチは虹を見たことがあった。
それはまだコチの羽が生まれたばかりの頃だった。
コチはまだうまく飛ぶことのできない羽を夢中で動かし、飛ぶ練習をしていた。
コチの空にはまだ太陽がまぶしいほどに輝いていた。
「次はあそこまで行くぞ。」
必死に羽を動かすコチの上を鳥が風に乗って空高くで追い抜く。
「すごいな。高いな。」
少し飛んでまた休む。
コチはすぐに草の葉の上に体を休ませた。
「次はどこだ?」
昨晩降った雨だろうか、少し先に水たまりがあった。
水たまりはキラキラと太陽の光を集めて何やら見たことのない光を放っていた。
「次はあそこだな。」
その見たことのない光に向かってコチはまた羽を動かした。
バタバタと不器用に羽を動かすコチの頭上にヒラヒラ3匹の蝶が現れた。
「見てみろ。枯葉が飛んでいるぞ。」
チョウは優雅に羽ばたきながら太陽の眩しい空で笑っていた。
枯葉?コチは、蝶が一体何を言っているのか分からなかった。
コチは「こんにちは」と声をかけようとするものの、まだ飛びながら話す余裕はコチにはなかった。
チョウを見上げながら印象悪くしないよう顔だけは必死に笑顔を作っていた。
「あれはなんだ?木枯らしか?」
「やめろよ。縁起でもない。せっかく春が来たって言うのに、木枯らしが吹く訳ないだろ?・・あれ?本当だ。木枯らしだ。」
ゲラゲラと笑う3匹は、コチを馬鹿にしたままコチの上を通り過ぎた。
「みんな逃げろ。木枯らしがやって来るぞ。」
遠くの空から3匹のチョウの笑い声がこだまする。
木枯らし?
「よし。やったぞ。」
コチは無事に水たまりまで辿り着くことが出来た。
3匹のチョウの笑い声はもう届かないほど遠くへ行っていた。
コチは「こんにちは」とチョウが見えなくなった空に呟いた。
きっともう届かない。
コチは、あの3匹のチョウが話していた意味が分からないままだった。
辿り着いた水たまりの水面を見下ろすと、七色の光が風に揺れゆらゆらと揺れていた。
「わあ。これが虹か。」
虹の傍に、ゆらゆら揺れるもの。
「ん・?」
コチは、初めて虹を見た。そして、この時、初めて水面に映った自分の姿を見た。
さっき、上を通り過ぎた3匹のチョウの笑い声が脳裏に再び現れる。
木枯らし?
水たまりの脇に咲く名も知らぬ花がコチを見て、怯えていた。
「そういう事か。」
コチが空を見上げても、虹は空にかかっていなかった。
虹は、水たまりの中に閉じ込められたまま。
水たまりの中には、虹とコチがゆらゆらと揺れていた。
一緒にゆらゆら揺れる太陽。
コチにはあざ笑っているように見えた。
✳︎
空は、太陽のいない暗い夜に戻る。
花は静かに話し出した。
「私も虹を見たことがないの。」
虹の話をする花の声は、流れ星の話のように弾むようなウキウキした声ではなかった。
「ねえ。虹の特別な話を聞きたい?」
「なんだよ。また、人間に教えてもらった話かい?今度はどんなホラ話さ。」
「残念。今度は、あなたが大好きな人間が教えてくれた話じゃないわ。これは、人間も知らない話よ。私だけの知っている特別な話なの。」
「君だけの話?」
「そう。私の特別な話。聞いてくれる?」
花は遠慮がちにコチに聞くものだから、ひねくれ者のコチは、聞きたくて仕方がなかった。
「人間のホラ話にうんざりしていた所だから、君の話だったら大歓迎さ。」
花はふふっと笑って少し不安そうに話を始めた。
今にも消えそうな揺れる灯をそっとコチに差し出すかのように。

まだ花が蕾だった頃の話。
蕾の頭上を空高く伸びる草の葉がグルグルと重なっていた。
小さな空から見えるのは、ほっそりとした光でひっそりと空に浮かぶ月。
賑やかに音楽を奏でる虫たちの歌の間から声がする。
「やあ。可愛らしい蕾だね。」
蕾が小さな空を見上げると、淡い月明かりに月影が羽ばたいていた。
「あ、また来てくれたのね。」
思いがけない言葉とその嬉しそうな声にチョウは一瞬たじろいだ。
「あれれ?僕に会った事あるの?」
チョウは、生い茂った葉っぱの一つにそっと腰を下ろした。
「あ、ごめんなさい。憶えてないよね。私、なかなか花が咲かないから。あなたとね、前に約束をしたのよ。」
さっきよりもだいぶ萎んでしまった声にチョウは慌てた。
「約束?そうか、えっと、待ってよ。そうだな。うーん。ヒントがあるのかな?」
「私の花が咲いたら春のお祝いに来てくれるって話。どうだ?思い出したか?」
蕾は笑いながらそう言うと、チョウは一瞬言葉を詰まらせた。そして、明るく蕾に話す。
「ははーん。残念でした。それは僕じゃない。他のいけ好かない野郎だな。おかしいと思ったよ。僕がこんなに可愛い蕾を忘れるわけがない。でも、安心しなよ。チョウは約束を破らない。そのチョウはきっと君との約束を覚えているはずさ。」
その優しいチョウの声は蕾を安心させた。
「ごめんなさい。間違えちゃったのね。」
「いいって。いいって。世界は広いんだ。羽を生やした奴なんてそこらじゅうに飛んでいるさ。その中で僕は君に会えた。幸運の羽の持ち主って事だね。」
「嬉しい。じゃ私は幸運の蕾?」
「ははっ。そうさ。君は僕に会えたんだからね。」
調子の良いチョウの言葉に蕾はクククって笑った。
「じゃ幸運の花が咲くかしら?」
「そらそうさ。とびっきり幸運の花が咲くよ。でも残念だな。先約がいるんだもんね。」
「そのチョウが憶えてくれているかはわからないけどね」
「憶えているさ。言ったろ。チョウは必ず約束を守るんだよ。」
「そうだった。」
蕾は優しく微笑んだ。
「チェッ。悔しいな。そうだ。決めた。僕も君と約束しよう。」
「え、何を?」
「君さ。虹を見たことあるかい?」
「虹?」
「大空を架ける色とりどり大きな光の橋だよ。」
「え、なにそれ。見てみたい。」
「これは自慢だからよく聞いてね。僕が小さくまだ葉っぱを齧っている頃さ。あ、もう心配ない。もう僕は大人さ。君の葉っぱを齧ったりしないよ。」
「ほ。良かった。」
「僕が夢中で大きな葉っぱを齧っていると見上げた空に大きな虹が架かっていたんだ。それはとても美しくて、空一面、手を繋いだようにどこまでも伸びているんだ。それから、僕は空にかかる美しい虹によじ登ろうと短い手を必死になって伸ばしているとさ。どうなったと思う?」
「何?」
「僕に羽が生えたんだ。」
「え、本当に?」
「ほら見て。」
チョウは自分の羽を翻した。
「じゃ幸運の羽で虹の羽なのね?」
「はは、そうだね。ねえ。君も見たいだろ?」
「虹?‥見えるかな?」
「君が花を咲かせたらさ。」
「うん」
「虹をここに連れてくるよ。」
「ここに?」
「そうだよ。ここに虹を呼んで。君の春を祝福しよう。」
「素敵ね。もしかしてそれが約束?」
「そうだよ。」
「本当に?」
「もちろんさ。僕には幸運の羽があるんだぞ。」
ふふっと花は笑った。
「私も幸運の花が咲くもんね?」
チョウも笑った。

花の話は静かに終わった。
「それから、そのチョウはここに来たのかい?」
花は静かに首を横に振る。
「きっと虹を探しているのよ。」
コチは、透き通るような花の声を聞き、苛立ちを覚えた。
(馬鹿やろう。虹なんてただの揺れる光だろ。)
コチは、花に聞こえないように誰かに囁いた。
「ねえ。あなたはチョウを知っているの?」
コチはもちろんチョウを知っていた。
コチのよく知っているチョウはただ一匹だ。
「俺の知っているチョウは、ロクでもない。チョウなんて奴は現実も見ずに大きな羽で夢見がちにただひょうひょうと飛んでいるだけさ。自分勝手で。マイペースで。おまけに大層口が悪い。ただ約束を破るような奴じゃないかな。」
「良かった。やっぱりチョウは約束を守ってくれるのね。」
「あんまり信じない方が良いよ。これは俺の知っている小さな世界の話だから。」
「うん。」
花は頷いた。
夜風が砂か何かをさらっと運ぶ音がする。
本当にここは静かだ。
「虹かぁ、それが君の願い?」
「うん。」
花は静かに返事をした。
「でも、星はこんな願いを聞いてくれるかしら?」
「まあ。そうすれば、今、必死に虹を探しているそのチョウもきっと助かるだろうね。」
空には、相手にされず、すねてしまったのか月はいなくなっていた。
次第に星が夜空に集まり、光をチカチカ。
何を話しているのか、やけに楽しげだ。
すると一筋の光が夜空を翔ける。
流れ星?
コチはすぐに花の顔を見る。
花も夜空を見つめていた。
時が止まったかのように空を見つめていた花の顔がみるみる輝く。
花は歓喜の声を上げた。
「わあ。」
満点の星空の間を次々と光の線が降り注ぐ。
「見て、見て。ほら、流星群だよ。」
花は急かすようにコチに言った。
一筋の光から、溢れかえるように、次々と夜空を翔ける星がコチの小さな世界に現れた。
「うわぁ」
コチも思わず声を漏らした。
夜空に溢れるような星たちは、次々と降り注ぐ流れ星によって夜空一面に次々に生まれ落ちているようでもある。
そうだったよね?
て、コチに聞いてみるといい。
コチは、きっと、あやふやに答えるだろう。
コチはきっと覚えていない。
コチはというと降り注ぐ流れ星に一瞬心を奪われながらも気がつくと花の喜ぶ横顔ばかりを見ていたからだ。
「いけない。忘れていたわ。早くお願い事をしないと。ほら、あなたも。早く、早く。」
花は、急いで願いを込めた。何度も繰り返すように。
コチも花の急かす声に後押しされて焦って考えた。
願い事、願い事。なんだったけ?
世界征服?
違う、違う。そんな事どうでもいい。
なんだ?なんだ?
焦るコチの瞳に必死にお願い事をする花の横顔映る。
コチは静かに流れ星に願いを込めた。
夜空は、落ち着きを取り戻した。
時折、集合時間を間違えたのか、一筋の光が夜空を翔けるだけとなった。
「本当に今日は素敵な夜だった。ね、人間の話を聞くのも時には良いものでしょ?」
「まさか。本当にあんなに星が降るとはね。世界は不思議だ。」
「ホラ吹きだなんて言って、人間に謝らなくちゃね?」
「謝るのはまだ早いよ。願い事は叶っていないもん。」
クククッ。
花の変わらない笑い声。
「願い事。叶うといいね?世界征服。」
「そんな願い事をいう奴はきっとホラ吹きさ。」
コチは咳払いをして花に聞いた。
「君は虹が見れたらいいね?」
「あっ、いけない。私、急いでいたから別の願い事をしてしまったわ。」
「えっ?嘘?!別の願い事って?」
「それは、内緒。」
「嘘でしょ。さっきはペラペラ虹の話をしてくれたのに?」
「何?ペラペラって。私の大事な話なのよ。」
「じゃ教えてよ。」
「ダメ。教えたら願い事が逃げちゃうでしょ」
「え、そんなルールがあるの?」
「知らないよ。」
「うわ、出た。ホラ吹きだ。」
クククッ。
「じゃ、あなたの願いも教えて?」
「だから、世界征服。」
「出た。ホラ吹きー。」
クククッ。
花はどうやら眠ってしまったようだ。
空はだんだんと闇が溶け、薄く白けた空が広がっていく。
もうすぐ太陽が空に現れ、色とりどりの世界を見張る時間になる。
コチは短く息を吐く。
コチは花が目を覚まさぬように、そっと花に声をかけた。
「そろそろ行くね。」
コチは、花から去っていった。
コチは太陽の視線に見つからないようにコソコソと寝床に向かった。

空に太陽がいた。
コチはいつもの寝床にいた。
コチの寝床は、老木だ。
誰もいなくなった民家の脇にひっそりと立つこの老木は、もう長い間ここにいる。
近隣に、新しい住宅地が建ち並ぶ中、ここだけが、まるで時が止まっているかのようだった。
老木は、隣に立つ古い民家の屋根を覗く。
朽ちていく民家の屋根に、落とした葉が散らばり風に身を任せ飛んでいく。
雨樋には風に選ばれなかった葉が幾重に重なり山となる。
老木は積もる枯葉を数え、過ぎた年月を思い出し風に揺れる。
青々とした木の葉が風に吹かれサラサラと音を出す。
コチは、この老木の優しい声が好きだった。
コチはこの寝床である老木を「ジイさん」と呼ぶ。
ジイさんはいつもコチを優しく迎えた。
出会った頃のジイさんは、枯れ木であった。
太陽の視線から逃げるようにやってきたコチは、同じ色をした枯れ木のジイさんの体にしがみつき隠れた。
ジイさんは何も言わない。
目を伏せるように、ジイさんの体にうずくまるコチ。
声がした。
風かな?
顔をあげるとジイさんの枝先から産まれたての小さな緑がキラリと陽光に反射した。
その葉にコチは、ため息しかでなかった。
「ここから出ていけ」
と緑が睨んでいるような気がした。
コチが何度目かの身支度を整えていると再び声がする。
いらっしゃい。コチ。
忌々しい太陽がいる間中、コチはこの寝床にいる。
ずっとジイさんの葉が作る影の下に隠れ時間が過ぎるのを待っていた。
ジイさんはコチの話す言葉にそっと耳を傾け、風にのせて頷いた。
いつものこの時間に何かが足りない。
「なあ。ジイさん。今日、ホリデイは来ないのかな?」
揺れる葉の隙間から光がチラチラとコチを覗いた。
朝の汚れない光の中から、ホリデイの声が聞こえる。
それは、いなくなってしまった朝の記憶。
「おはよう。コチ。今日も太陽がこの世界に生まれたよ。」
ホリデイが、ジイさんのいる庭にやって来たようだ。
いつもホリデイは、コチがジイさんの寝床で「さあ、寝よう」というタイミングにやって来る。
だから、いつもコチはそれに返事をしない。
それは、もう寝ているというアピールだ。
それでも、ホリデイは、庭から老木の枝で寝ているコチに向かって気にせず大声で話しかける。
「コチ。公園にまた、シワ帽子が現れたぞ。しかも、自転車のカゴにお弁当まである。きっと遠出だよ。どこに行くんだろうな?急ごう。置いてかれちまうよ。」
ホリデイは、ジイさんの庭をヒラヒラと飛び回っている。
そう。ホリデイは蝶なんだ。
コチの小さな羽とは違い、ホリデイの羽は大きい。
ホリデイの透き通るような大きな羽は、朝の光を閉じ込めたように、羽を翻す度にキラキラと輝き、ヒラヒラと飛ぶ姿は、朝に輝きを与えているようでもあった。
ホリデイは、ヒラヒラと、そこらに生える草花に止まり調子よく声をかける。
草花は、どこか、嬉しそうに、朝の光に向かって大きなあくびして、1日の始まりを迎える。
コチは、なかなかこっちにやって来ないホリデイにイライラしながら、眠い目をこする。
本当に眠った所で、ホリデイに起こされるに決まっている。
「おはよう。ジイさん。今日もいい風が吹いているよ。なんか素敵な便りがあるんじゃない?」
この老木をジイさんと呼ぶのは、コチとホリデイだけだ。
ホリデイがようやくコチの隣にやってきた。
陽光に美しく煌めく大きな羽がコチの隣で惜しまれながらにゆっくりと閉じる。
ホリデイと出会って、まだ間もない頃、コチはホリデイの美しい姿に恥じらい、傍にいるだけで小さいコチが、ミジンコのようにもっと小さく縮こまるようだった。
でも、それもいつの間にかになくなった。
気づいた時には、コチは、ホリデイに対して恥じらいを持たなくなっていた。
しつこく毎日やってくるホリデイに馴れてしまった事もあるけれど、それよりも、もっと効果があったのはホリデイがコチと同じくらいに口が悪かったからだろう。
「おーい。コチ。生きてるか?あれ、死んじまった?」
もちろん。コチはその言葉を無視した。
瞼の奥でホリデイの影がコチの顔を覗く。
「地獄に行ってもマヌケ面だな。」
ホリデイは吹き出して笑った。
コチはなんとか寝たふりで堪えている。
「おーい。コチ。いつまでその顔で俺を笑わせる気だ?起きろよ。」
ホリデイの声は大きかった。
「おーい。コチ?コーチー。」
上空では「チュンチュン」と不気味に鳴く鳥の声が聞こえる。
ホリデイの騒ぐ声に気づき、餌になるのはごめんだ。
「しー。ホリデイ。静かにしろ。」
コチの焦る顔を見てホリデイは、いたずらな笑みを浮かべた。
「なんだ。起きてるじゃないか。」
「うるせー。誰の顔がマヌケ面だよ。マヌケ面しているのはお前だろ?」
いつもホリデイは、無邪気に笑う。
「おはよう。コチ。」
朝の光がそうさせるのか。ホリデイの汚れない笑い声がそうさせるのか。怒ることさえ、馬鹿馬鹿しく思えてしまう。
「ホリデイ。「おはよう」じゃない「おやすみ」だ。こっちは今から寝る所だ。何度言えば分かってくれるんだ?」
「おいおい。こんなご機嫌な日に眠るような奴がいるのか?その間抜けは一体どんな間抜け面をしている?」
そう言うとホリデイはコチの顔を覗き込んで言った。
「間抜け面見っけ。」
ホリデイがまた笑う。
「早く行こうぜ。コチ。日が暮れちゃうよ。」
「分かってないな。俺はチカチカと鬱陶しい太陽とホリデイがいなくなるのをここで待っているんだよ。」
いつものコチとホリデイの朝の始まりだった。いつからこんなやりとりが始まったのか。この2匹が初めて顔を合わせたのもジイさんの木の上だった。

それは、コチがまだ飛ぶ練習をしていた頃だった。
ただ、この頃のコチは、あの頃のように自分の羽に、多くの希望は持ち合わせてはいなかった。
コチは寝床であるジイさんの周りだけで、飛ぶ練習をしていた。
老木の幹を離陸し、ある程度の距離まで飛べたらまた老木の幹に着陸する。
その繰り返し。
太陽の目を気にしてか、すぐに隠れられるようにコチはなるべく老木から距離を離れずにいた。
そんな中、一匹の蝶がヒラヒラとコチの小さな領域に入ってきた。
これが、ホリデイだった。
コチは急いで、老木の幹の上にある薄暗い影になる部分に移動して息を潜めた。
侵入者が現れると、いつもこうして隠れた。
老木の葉は大きな影を作ってくれ、コチの身体を包むように隠してくれた。
コチは、いつものように侵入者が早く出て行くのを待っていた。
でもホリデイはなかなか出て行かなかった。
ホリデイは、ヒラヒラ飛んでは、そこに咲く草花に次々と降り立ち何やら話している。
それはコチが目も合わせた事のない草花。
コチは近所に咲く草花と話をした事はない。
せっかく見つけた寝床だ。
住みづらくなっては困るのだ。
人の住んでいない空き家には、草は伸び放題、私を見つけてと、そこから花がひょっこりと顔を出している。
ホリデイを目で追いかければそこに花が咲いていた。
コチはそこに花が咲いている事を知らなかった。
ホリデイは、ひとつ、ひとつに、陽気に声をかけていた。
コチは黙ってその様子を見つめていた。
コチの視線の先がどんどん近くなる。
まずい。
と思った時にはもう逃げる事ができない距離にホリデイはいた。
動いては見つかってしまう。
ホリデイが、老木の広がる枝葉を見上げながらコチの方にどんどん近づいてくる。
かなりの近さだ。
ホリデイがコチの隣に止まった。
コチの息はさっきからずっと押し殺されていた。
ホリデイは光を包むように大きな羽をゆっくり閉じる。
コチは、こんなに間近で蝶の羽を見たのは初めてだった。
コチの隣にいる蝶の羽はコチのおかげでよく輝いた。
コチは老木にへばりつき、コケのようにピクリとも動かない。
どうか、俺の羽、見つからないでくれ。
「産まれたての葉だね。おはよう。今日の風乗りはどうだい?」
ホリデイは、風のようにふわりと老木に囁いた。
ホリデイは、隣で息を殺すコチには全く気付いていなかった。
とても失礼な事だが、コチにとってはありがたい。
このまま気づかずどこかに飛んで行ってくれる事を息を殺してただ祈るだけ。
でも、コチの祈りはすぐに遠くに逃げていった。
ホリデイの驚いた声が、コチの耳に届いた。
「ん?・・うわッ。びっくりした。なんだよ。いたのかよ?」
コチは、ドキッと体はそのままに、心臓だけが飛び跳ねた。
それでも、まさか、自分に声を掛けている?
そんな訳ない。
隠れる事には自信があった。
声のする方に、ゆっくりと静かに顔を動かした。
目が合う。
その蝶は確かにコチを見つめている。
見つかっている。
コチは、すぐに視線を反らした。
宙を向き、黙ったまま動かないでいると、ホリデイは羽を翻し、コチの見上げる宙に現れた。
「おい。今、目が合ったよな?なんで無視すんだよ。」
ダメだ。完全にバレている。
ホリデイは大きな羽を優雅に羽ばたかせながら、見上げるコチの顔を覗いた。
陽気に話すホリデイに対して、コチの顔は、強張り、怒りに満ちた表情だ。
「ここから出ていけ。ここは、俺の場所だ。」
コチは力一杯、目の前の美しい蝶に向かって叫んだ。
ホリデイも、いきなり「出て行け」なんて言われたものだから、黙っていない。
「なんだ。口を利けるじゃん。でも残念。不正解。ブーだ。正解は、ここは僕の場所だ。空を見上げてみろよ。青い空があるだろ?なら、ここは僕の場所なんだ。」
老木は、ただ風に揺れている。
「うるせー。いいから出て行け。」
「なんで出て行かなきゃいけないんだ?ここは僕の場所だって言ってるだろ。嫌ならお前がどっかに行けばいい。」
お互いが、この場所を譲らなかった。
場所というのなら、ここは老木の枝。
文句一つ言わず老木は、黙って2匹のやりとりを見守っている。
2匹の言い争いは、お互いが「出て行け」の一点張り。
でも、口の悪いホリデイの何気ない一言で簡単に終わった。
「だったら、どっちにいてほしいか。この木に聞いてみようぜ。きっとこの木は僕を選ぶはずさ。お前を選ぶ奴なんか、どこにもいやしないよ!」
ホリデイは、そう言うと噴出すように笑い出したが、それを聞いたコチは、突然、黙ってしまった。
「ジイさんは、選んだりなんかしない・・」
コチは、そのまま小さな羽を広げ、老木から飛び立った。
「え?行くの?おい、終わりかよ?」
ホリデイは、不器用に羽を動かし飛ぶコチの後ろ姿を目で追った。
ホリデイは一匹、老木にぽつんと残された。老木の葉が風に揺れる。
「なんだよ。あいつ。冗談もわからないのか?つまらない奴だよ。なあ?」
ホリデイは、不貞腐れたように老木に呟いた。
風で老木の葉が揺れる。
「確かにセンスのない冗談だ。」
ホリデイは、居心地が悪そうに頭をぽりぽりと掻きながらジイさんの葉で作られた影を見つめた。
「あんた。ジイさんって言うんだな。」
出て行ったあいつが呼んでいた名前。
ホリデイの知らなかった名前。
「ジイさん。あいつ行っちゃったね。まあ。僕が追い出したのか。」
若い葉が風に揺られてチカチカとホリデイの羽を照らす。
「分かったよ。あいつをここに連れて帰るから許してよね?ジイさん。」
ホリデイは面倒くさそうに羽を広げた。
「探してくるからさ。教えてよ。あいつの名前は?」
葉が優しく風に揺れる。
「そっか。」
ホリデイは、飛び立ち、コチの後を追った。
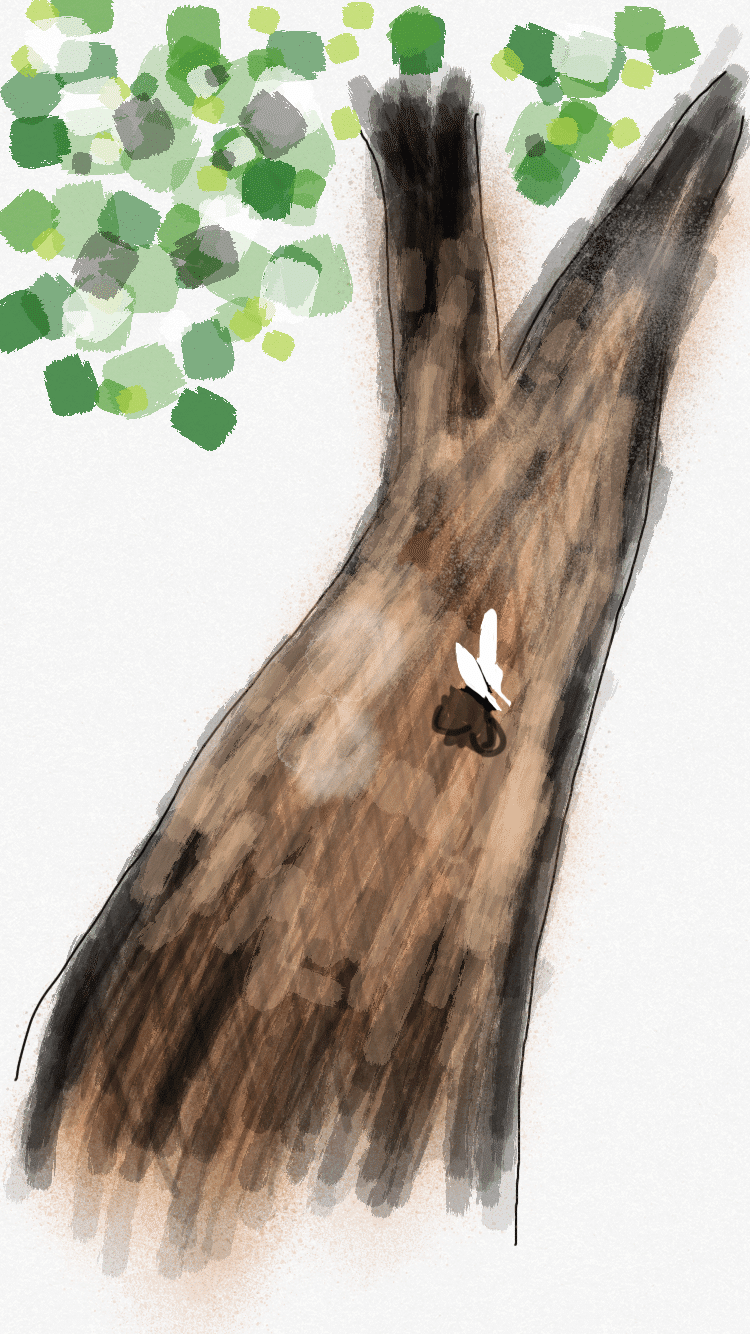
コチのぎこちない飛び方は知っている。
ホリデイの飛ぶ速さであれば、もうすでに追いついてもおかしくなかった。
「何処行ったんだよ、あいつ。おーい。コチ。」
コチは、飛ぶ事に疲れ、休んでいた。
上空で、ホリデイらしき蝶が、叫びながら過ぎ去った。
コチは、道路脇の街路樹が作る影の下にいる。
「まったく、そんなにはしゃぐなよ。」
今日は良いお天気だ。
太陽は張り切っている。
日陰に馴染んだコチの目は、はしゃいだ太陽の光が視界をぼやけさせ、すぐに回した。
呼吸もまだ乱れているし、もう少しここで休む必要がありそうだ。
コチにしては、ずいぶんと長い距離を飛んできた。
見知らぬ木から、木漏れ日が届く。
「戻ってもいいのかな?」
コチはジイさんを想った。
せっかく見つけた寝床だったのに、突然現れた蝶のせいで帰りづらくなってしまった。
コチはジイさんの優しい声が好きだった。
ジイさんは俺を迷惑だと思っているのだろうか。
答えを聞かずに、コチは今ここにいる。
「別に逃げた訳じゃない。」
コチは自分に言い聞かせた。
揺れる木漏れ日までもなんだか、自分を嘲笑っているかのようだった。
休むコチ。
足元は透明、まるで宙に浮いているようである。
ここに止まった理由なんてない。
疲れたから止まっただけだ。
「嫌だ。気持ち悪い。変な虫がくっついている。」
男女二人の人間の若者がやってきて、車のフロントガラスに貼り付いた虫を見ながら何やら話している。
この日の為に、男がピカピカに磨いた車に付いた虫を見て、女は、眉間のシワを寄せ、その深いシワを見て、男は苦笑いを浮かべる。
「車が走り出したら、きっと飛んでいくよ。」
男が、なんとか女の機嫌を取ろうと陽気に声をあげ、二人組は車に乗り込んだ。
もちろん、コチは人間の話す言葉はわからない。
言葉はわからなくても、車の中から、コチの腹を憎憎しく見つめるその眼差しは、言葉以上に伝わるものがある。
「そう睨むなよ。どいつもこいつも俺を追い出したいんだな。誰が出て行くものか。俺はここを離れる気はないよ。」
突然、地響きが鳴る。
車のエンジンがかかったのだ。
振動するガラスは、そこにいるコチを小刻みに激しく揺らした。
揺れる体、慌てふためくコチの吐き出した言葉もまた揺れる。
「お、おい。ど、ど、どうなってる、るんだ?」
車は、徐々に走り出し速度を上げる。
コチの体は、だんだんと強く向かってくる風に押されて、体がガラスに張り付いていた。
生意気な口もガラスと風に押され、言葉を封じた。
なかなか、飛んでいかない虫に対して、イライラしている運転手。
ますます、車はスピードを上げる。
コチは、振り落とされないよう、ぎゅっと力を入れる。
ただ、そうする事に何の意味があるのかコチにもわからない。
何もしなくたって体はガラスに張り付いている。
コチは動く事さえ出来ないのだ。
ガラスに押しつぶされていない方の片目で空を見上げると、青い空にはゆっくりとちぎれ雲が流れている。
「のどかだねえ」
意識がどこかに飛んでいきそうになった時、急に車は止まった。
信号の色は赤だ。
コチはこの大きな物体が、突然止まった意味もわかりはしない。
成す術もないほどの強靭な力の持ち主がルールという檻の中で、清く正しく行動しているとは、コチは想像もしていないだろう。
「全く馬鹿みたいにはしゃぎやがって、いいかげ・・」
コチの捨て台詞が終わらないうちに信号は青になった。
青は走れ、だ。
まだ、目の前を張り付く虫を振り落とそうと、車は勢いよくアクセルを踏まれ走り出した。
コチは風に押されてガラスにまた張り付いた。
二人の人間の不快な顔。
いい加減、この顔に何の感情も湧かなくなる。
「いいから、ここから早く下ろしてくれ。」
さっきの意地は、とっくのとうに消えている。
コチは、ここを「どかない」って言っていたけれど、今は、どけない状況が問題だ。
次の信号は、まだ先だ。
コチも信号のルールはこの際覚えておいたほうが良い。
「ジイさんは今、どんな風に揺れているのだろう?」
風に押されガラスに張り付きながらも、コチは、今、なぜ?そんな事を考えているのだろう?
いや、さっきと同じだ。
気が遠くへと旅立とうとしているのだ。
だから気がつかない。
横から勢いよく何かが迫っている事を。
コチの目の前に突然黒い影が勢いよく突進してきた。
ワイパーだ。
ワイパーはコチを空高く吹き飛ばした。
運転席の男は、フロントガラスを見回した。
どうやら、ガラスは汚れていないようだ。
運転手の顔色が明るい色に変わる。
コチは、残念ながら、その顔を見る事は出来なかった。
コチは、対向車線の空をくるくると回っていた。
くるくる回る視界は、笑う太陽と冷ややかな道路を交互に映す。
そして、コチの目に一瞬迫り来る車が映り、また太陽がニンマリ笑った。
「わっ」と思った時には、車はコチの目の前にあった。
物凄い速さでコチの脇を通過していった車が起こした風は、コチをさらに吹き飛ばした。
そして、コチの意識も吹っ飛んだ。
コチが、意識を飛ばしたのは、これが初めて。これっきり。もう2度と意識を飛ばす事が起こらなきゃいいな。コチは、意識を失う前にきっとそう思ったに違いない

コチは知らない声によって起こされた。
そして、コチが目を覚ますとコチの体は動かなかった。
自慢の小さな羽もぎゅっと何かに縛られているかのようだった。
体を横に引っ張っても、縦に動かそうとしても動かない。
それどころか、動こうとすればするほど何かがコチの体をより強く締め付けた。
コチの体にはネバネバと白い糸がまとわり付いている。
コチは蜘蛛の巣の中で目を覚ました。
蜘蛛の巣は、走る車が止めどなく流れる国道の路肩に植えられたツツジにあった。
蜘蛛の巣は、ツツジの上を這って緑の上に白い雲のように広がっている。
遠い空には、まだ太陽がニヤニヤと笑っていた。
太陽を拝むなら格好の場所であるが、残念ながらここの空気は美味しくない。
これでもかと息の臭い車が通れば無理もない。
こんな地獄のような環境に植えられたツツジも住めば都と開き直り、春の身支度で蕾を付けている。
そんな中を、勝手に作られた白い糸の巣が、車が作る通り風によって不機嫌に揺れていた。
「おーい。誰かいない?ここから出してよ。」
コチの声は、虚しく車のエンジン音でかき消された。
何度声をあげても、声は空には届かず無情に走り去る車は、コチのなげやりな予想よりも絶望なほどに多かった。
葉の裏に付く大量のアブラムシの群れを見て「お前ら気持ち悪いな。」とからかうように笑う事があったが、灰色の道に溢れる車の群れを見れば、笑う事も出来ない事を知った。
コチを捕らえる糸がビンビンと波打つように揺れる。
糸を伝ってきた声がコチの耳に届く。
「ここはわしが作った完璧な世界。どうして逃げる事があるのじゃ?」
声は糸を伝ってやって来るが、相手の姿は見えない。
何かを諭そうとするような声が、全身を縛る糸に伝わり、コチの体は逃げられないと訴える。
「あなたは救われたのよ。」
別の声が糸を伝ってやってきた。
明るい声だがどこか空虚な音がする。
「救われた?」
コチは、辺りを見回すが、誰の姿も見えなかった。
気づいた事は白い糸が、コチの目では見えないところまで広がっているという事だ。
コチは見えない相手にどう返事を送れば良いのか分からなかった。
すると、再び白い糸が揺れ、コチに言葉を届けた。
また、違う声だった。
「ソトはキケンがいっぱい。」
「ここにいればダイジョウブ。」
違う二つの能天気な声は、合わしたかのようにリズム良く並んだ。
「君は選ばれたのじゃ。君は導かれてここにきた。何も恐れる事はないのじゃよ。」
聞こえてきた声は、最初に届いた声だった。
コチは見えない相手を探すことを諦め、空に向かって口を開いた。
「どこの誰だか知らないけど、ここから出してくれよ。俺は帰りたいんだ。」
コチの声は、糸を伝わり、相手に届いたようだ。
「帰るだって?一体どこに?君の場所はここだ。君は、導かれてきたのじゃ。」
「帰るなんて言わないで。ここは安心よ。私たちと同じ、あなたは選ばれたのよ。」
「ソトはキケンがいっぱい。」
「ここにいればダイジョウブ。」
一斉に返信がコチに届く。コチは、誰に向かって言葉を返すべきか、すべてに応答すべきなのか分からない。
もうなんだかとても鬱陶しいシステムだ。
コチはとりあえず最初に届いた声に応答することにした。
「導かれてきたってどういう事だよ?」
「それはな。おま・・」
「ソトはキケンがいっぱい。」
「ここにいればダイジョウブ。」
何?
コチには最初の声が遮られて良く聞こえなかった。
すると白い糸からプツンプツンと音がする。
「回線を変えてやった。これで邪魔も入るまい。どこまで話したかな?ああ。そうだ、そうだ。お前がここにきたって事は、お前にはきっと羽があるはずじゃ。どうじゃ?」
「まあ一応ね。あんたには、俺が見えるのか?」
「わしには、お前のすべてが見える。なぜだかわかるかね?ここはわしの作った世界だからだ。」
「よく分からないな。」
「わしはすべてを知っている。お前の運命もじゃ。」
「運命?」
「お前は導かれてここにきたのじゃ。何が導いたと思う?その羽じゃよ。選ばれた羽を持つ者じゃなければここにはたどり着けない。お前は幸運の羽の持ち主じゃ。」
声は高らかなにそう言った。コチは冷静に言葉を返す。
「いや。違うよ。俺をここに運んだのは、幸運の羽じゃない。俺はあそこを走る車に運ばれ、飛ばされ、ここにきたんだ。どうやら間違ってここに落ちたらしい。」
しばしの沈黙の後、糸から声が聞こえて来る。
「お前は、幸運の車によってここに来たのじゃ。」
「いやいや。幸運とかそんなデタラメいいから。ここから出してくれよ。」
コチに絡まる糸からプツン、プツンと音が聞こえる。回線がまた変わった。
突然、コチの背後からサササッと物音がした。白い糸で固められたコチは、振り向く事は出来ない。
何かはコチをじっと観察して
「はああ。やっぱりか。」
とぴょんと再び奥へと消えていった。
見えない何かがボソッと呟き再び気配を消した。
身動きが取れない恐怖。
相手の姿が見えない恐怖。
この二つの恐怖だけで、恐怖は繁殖するかのように、次々と新たな架空の恐怖を造りあげる。
コチは何かにすがるように声をあげる。
「おーい。声さん。どこ行った?」
返答はない。
「おーい。」
沈黙が秒針を数えるようにコチを見つめる。
応答のない時間は、コチの心に不安が大雪のように降り積もっていく。
その雪が、コチの心を真白く埋め尽くされるとようやくコチの耳に声が届く。
「わしを。呼んだかね?」
コチは必死に声を追いかけた。
「なんだ。突然いなくなってしまったから心配したよ。」
コチの声は安堵に満ち溢れていた。
声の主はその声を聞いて、ほくそ笑む。
「何も心配する事はない。君は、白い糸で結ばれている。その白い糸は、君を幸せに導く幸運の糸。その糸を決して離さなければ君は報われる。」
「この白い糸のせいで動く事が出来ないのに?」
「わしの声に従いなさい。今にその白い糸が君を包んで、太陽さえ君を見つける事が出来なくなる。そうすれば、チュンチュンとうるさい小鳥だって君を探せない。君は恐怖から解放されるのだ。君は、私の作る完璧な世界の居住者だ。」
コチの耳から頭にすんなり向かって、声が鳴り響く。
もがけばもがくほどコチの体を強く縛る白い糸は、コチの思考力も奪っていく。
何が正しくて何が間違っているのか。
考えるのも億劫になる。
気持ちが上がってこない。
重い塊のような沈んだ気持ちがコチを地底深くに引っ張るようだ。
やたらと太陽が遠くに見える。
「ここにいれば。忌々しい太陽の視線から逃げる事はない。この白い糸が守ってくれるんだ。」
コチは、暗く沈んだ景色の中で、手っ取り早い希望を見つけた。
「そうじゃ。君はここでこの完璧な世界で喜びを感じるのだ。春の日差しの中、飛ぶ蝶のように。」
小さな蜘蛛はニヤリと笑った。
小さなコチの青空がくすんだ。

突然、コチの耳に懐かしい春の日差しのような笑い声が届いた。
コチが見上げた空に太陽の光を背に浴びて黒い影が羽を翻し宙に舞う。
それは一匹の蝶。
「どこに行ったかと思えば、お前、こんな所にいたのかよ。で、どうした?」
ホリデイだ。
ホリデイが腹を抱えて笑っている。
「お前・・。」
この状況で笑っているホリデイには、「なんて奴だ」と腹が立ったが、
いつの間にかコチの空はくすんだ色から青色に戻っていた。
「お前、この状況で‥。何で、笑っているんだよ。」
コチは、思った通りの言葉をホリデイにぶつけた。
「こんな状況に対面して、笑わない方がどうかしているだろ。お前はいいよな。お前の姿が見えないから。こっちの立場になってみろよ。」
ホリデイは、空を転げ回りながら笑っている。
そんなに間抜けな姿なのか、何度首を動かしてみても、自分の姿を見ることはできなかった。
「ここに何しに来たんだよ。冷やかしに来たなら、早くどっかにいけ。」
コチは、なんとか強がってホリデイを突き放した。
「お前は、どこに行っても僕を追い出す気だな。何度も言わせるなよ。ここは僕の世界だ。嫌ならお前が出ていけよ。」
コチは、一瞬何かを考えた。
そして、違う事にすぐに気づく。
「この状況。見てわかるだろ。出て行きたくても出て行けないんだよ。」
コチは、怒鳴りつけるように、ホリデイに言葉を叩きつけた。
それを聞いたホリデイは、また宙を転げ回って笑う。
「なんだよ?助けてほしいのか?」
コチは、意地で固めて作った泥のような盾を下に降ろそうかと勿体ぶっていると、糸を伝って、奇声が聞こえてきた。
「なんたる幸運。やっとやっと出会えたぞ。」
またあの声だ。
さっきに比べるとかなり興奮した声だった。
「おい。おい。お前の上を飛んでいる蝶は、お前の友達か?」
コチはホリデイを見る。
「ほら。助けて欲しいって言っちゃえよ?」
変わらずそうはしゃぐホリデイ。
ホリデイには、この声は聞こえていないみたいだ。
「こんな奴。知らないよ。」
糸に向かって答えるコチ。
「ん?何?」
とホリデイは眉をひそめる。
すると、糸から答えが返ってくる。
「いいか。耳をすませて、よく聞くんじゃ。その蝶を捕まえるのだ。その蝶は、私の作ったこの世界に必要な存在じゃ。」
コチは、どういう事かわからなかった。
だから、聞き返す。
それだけの事がさっきは、なぜ出来なくなっていたのだろう。
ホリデイは、様子のおかしいコチを不思議そうに見ている。
「なあ、声よ。こいつは、あんたの作った世界を気に入らないと思うよ。こいつは、太陽の世界が好きらしいから。第一、この幸運の白い糸のせいで動けやしないよ。捕まえるなんて無理だよ。」
コチの答えに声の主は少し怒りで震えていた。
「うるさい。黙ってわしの言う事を聞くのじゃ。いいか。お前は動けなくても、その蝶に助けを求める事が出来るだろ?そうすれば蝶はこの白い糸に触れるだろう?そうすればこの白い糸はこの蝶にべったりとくっつき離さない。そして、もがくうちにもう逃げる事が出来ないほどに身体中に糸が絡みつくのじゃ。お前は動かなくて良い。助けを求めるだけじゃ。あとはわしの自慢のこの糸がやる。簡単だろ?」
そして、声は、続けてコチにこう言った。
「あいつを捕まえる事が出来たら、お前を白い糸から解放してやる。そしたらお前の言う通りここから逃がしてやる。自由だ。」
コチは下を向き黙っていた。
様子のおかしいコチにホリデイの顔はもう笑っていなかった。
「お前、さっきから何ブツブツ言っているんだよ。大丈夫か?」
コチが見上げると、ホリデイが真面目な顔をして近づいて来る。
コチの脳裏に、糸からの言葉がこだまする。
ホリデイが、コチを縛り付ける白い糸に手を伸ばそうと、すぐそこまで来ていた。
「どっか行けって!」
コチの怒鳴り声は、空高くまで響いた。
その勢いで、困惑した表情のままホリデイは固まった。
続けてコチは、言い放った。
「俺はお前が嫌いなんだ。いいから、俺の前から消えてくれ!」
ホリデイの困惑した顔はたちまち怒りに満ち溢れた。
「そうかよ。じゃ勝手にしろ。勘違いするな、俺だってお前なんか好きじゃない。」
そう言うと、ホリデイは、大きな羽を翻し、青空へと飛び去った。
ホリデイは簡単に空に消えた。
「なんて事をしてくれたんだ!」
コチの耳に発狂した声が届く。
もうさっきまでの飾り付けた声じゃない。
ホリデイの出現によって、本当の姿がお出ましだった。
蜘蛛は、すーっと糸を伝って、コチの前に降りてきた。
別に驚きはしない。
こいつは蜘蛛の巣の主人で、小さな蜘蛛だ。
小さなコチよりももっと小さい。
その小さな顔は怒りで歪んでいた。
「なんで、あの蝶を逃したんだ?」
怒りのせいなのか、蜘蛛のぶら下がる糸が右へ左へと振られる。
「別に逃したわけじゃないよ。あいつが勝手に出て行ったのさ。」
そう言えばやっとあいつを追い出す事が出来た。
一勝一敗だな。
コチは思った。
怒りに震える蜘蛛を少しでも落ち着かせようとおどけて首をかしげるコチだったが、やられた蜘蛛の怒りはヒートアップしていくばかりだった。
でも、さっきまでの恐怖はコチにはなかった。
さっきは知らないというだけで、恐怖はいくらでも大きくなり、絶望はコチの空を飲み込んでしまった。
小さな蜘蛛がいくら怒っても、コチの見上げる空は今も青いままだ。
「なんで、助けを請わなかったんだ?知らんぷりして、助けてもらうふりだけしていれば良かっただけだ。お前は頭が悪いのか?おー。あいつが嫌いなんだろ?嫌いな想像も簡単につく。おー。あの蝶が、糸に絡まってしまう事はただの事故であって。誰もお前を責めたりなんかしない。完璧な作戦だったじゃないか。お前がいくら正義感を振りまこうが、誰もお前を認めてなんかくれやしない。お前は、小さく、汚い、クソ不味い、嫌われ者の蛾なんだからな。」
怒りで、右へ左へと糸は激しく揺れる。
コチは揺れる蜘蛛の奥で広がる青い空を眺めていた。
「よせって。そんな事、あんたに言われなくても知っているよ。まあ、不味いって言うのは初耳だけど。」
そして、突然、蜘蛛はしくしくと泣き始めた。
どうやら情緒不安定のようだ。
「わしの世界にようやく春がやってきたと思ったら春は突然、姿を消してしまった。わしはこの場所を作ったんだ。わしの設計図で作ったこの世界にどうして悲しみが訪れるのだ。喜びに満ちた春はどうやって作るのじゃ?春の恵みはいつやってくる?ここに来るのは、こんな小さな蛾やハエばかりじゃないか。」
悲しみを背負った蜘蛛が糸にぶら下がりゆらゆら揺れる。
「なあ。蜘蛛のおじさん。春を待っているなら俺は邪魔だろ?俺は、春には縁起の悪い名前を持っている。その名も「木枯らし」どうだ?俺がここにいたら、いつまでもここには春は訪れないよ。俺をここから解放してみてはいかがかな?」
悲しみを背負った蜘蛛は、糸がねじれてしまったのだろう。
お次は、その場をくるくると回っている。
蜘蛛は、悲しみの世界で、ポツリポツリと言葉を落とす。
「なぜ?わしに意見を言う。ここはわしの世界じゃ。この世界はわしの思い通りじゃなきゃならん。木枯らしか。わしの悲しみの世界によくお似合いだ。」
悲しいおじさんの姿にコチは口を歪めた。
「そんな事言うなよ。希望を捨てるなよ。春はまたすぐやってくるよ。」
道路は騒々しく車が行き交う。
コチは少しづつ排気ガスの臭いにも慣れてきた。
でも蜘蛛は臭い臭いと泣き喚く。
蜘蛛はツツジの蕾の花に気がついているのだろうか?
蜘蛛は自分の世界しか見ていない。
もう春はすぐ近くまできているのに。
蜘蛛はいつまでも排気ガスの漂う曇った世界を作り続けている。
コチにはツツジの蕾を見ることができる。
心の白い糸はどうやら解けたみたいだ。
コチは蜘蛛の世界の居住者にはならなかった。
コチは思った。きっと、あの蝶はコチを助けなかったわけじゃない。
あの蝶が来てからここは、やたらと空が綺麗に見える。
「コチ。おい。コチ。」
声がした。誰かを呼ぶ声。コチ?
見上げるとあの蝶がいた。
「待っていろよ。今、助けるからな。」
コチは、何がなんだか分からなかった。
「え?なんで?」
コチは分からなかった。
「なんで、またいるんだよ。」
コチの近くを飛ぶ蝶に蜘蛛も気が付いた。
蜘蛛のおじさんは血相を変えてホリデイを追いかけた。
「春だぁ。春の恵みじゃ。」
先ほどの落ち込みが嘘のように、蜘蛛のおじさんは糸から糸へぴょんぴょんと跳ね。ホリデイを追いかける。
「わっわっ!なんだ?こいつ。」
ホリデイは慌てて逃げる。
蜘蛛のおじさんは、逃がさないようにお尻から糸をぴゅっぴゅっとホリデイに向かって発射する。
ホリデイは、それをヒラヒラと上手にかわした。
それでも何度も飛んでくる糸、ホリデイはコチの背後に回り、上手にコチを盾にして糸から逃げる。
「おい!お前。何してんだよ?」
コチが叫ぶ。
「そんな怒るなよ。僕が捕まったら僕たち終わりだぞ。」
蝶の言い分もわかる。蜘蛛は時折奇声をあげて我を失っている。
「なんで戻ってきたんだよ。」
慌てて羽を翻し、糸を避けるホリデイにコチは冷静な声で聞いた。
それもそうだ。
コチは動けない。
今、忙しいのはホリデイだ。
「青空の下飛んでいて気がついたんだよ。ここは僕の場所だろ?なんで俺が出て行かなきゃならないんだってな。出て行くのは、お前の方だ。だから、お前が出ていけるように、仕方ないから助けてやるよ。」
ホリデイは息を切らせながら、そう言った。
「どんだけ負けず嫌いなんだよ。」
コチはこんな状況で少し吹き出した。
そしてコチは忙しそうな蝶に向かってずっと気になっている質問をした。
「なあ。お前さ。一体俺をどうやって助けるつもりなの?作戦はあるのかよ。」
ホリデイは何も答えなかった。するとホリデイは、逃げるように空高く飛び去ってしまった。
「えっ。」
コチは突然の出来事に、呆然とホリデイが見えなくなるまでただ目で追うことしかできなかった。
蝶が空に消えてコチは答えを探した。
「‥諦めた?」
空を見つめたまま止まるコチ。
「行っちゃったの?」
蜘蛛のおじさんもコチに呆然と聞いた。
コチは誰もいなくなった空を眺めていた。
蜘蛛のおじさんも空を見ていた。
時間の経過がコチに答えを導き出す。
「なんだよ。あいつ、結局逃げちまったじゃないか。」
コチが文句を言っていると、隣で同じ空を見ていた蜘蛛のおじさんが言った。
「諦めるな。大丈夫。春の恵みは戻ってくる。あいつは、お前に助けると言ったじゃないか。蝶は必ず約束を守る。まだ希望は残っているぞ。」
蜘蛛のおじさんの話す口調は落ち着いていた。そして、ホリデイが戻って着たときの為にと新たな白い糸をお尻から出し、黙々と蜘蛛の巣を紡ぎ始めた。
あの泣いていたおじさんの目は、今、イキイキとしていた。
感情の起伏が激しい蜘蛛だ。
「へえ。蝶は約束を守るのか。」
コチが空を見上げていると、空から叫び声が聞こえてきた。
あの蝶だ。
本当だ。戻ってきた。
「ィヤァー!!」
ホリデイは叫びながら慌てた様子でがむしゃらに羽を動かし、まるで空から落ちるようにコチに絡まる蜘蛛の巣に突進し、そのまま、蜘蛛の巣に捕まった。
呆気にとられるコチ。
「‥嘘だろ?これがおまえの作戦?捕まっちゃったじゃん?」
コチの言葉を蜘蛛のおじさんの狂喜した奇声が打ち消した。
「ひゃー。ついにやったぞ。春だ。春を手に入れた。」
ホリデイはコチと目が合うと、合図するように上を見上げる。
ピエー!
空が暗くなった。
いや、大きな影だ。
そのまま大きな黒い影が勢いよく蜘蛛の巣に絡まったコチとホリデイ目掛けて突っ込んできた。
ピエー!
鳥だ。
勢いよく降り注ぐ鳥のクチバシがコチとホリデイの横すれすれに通過し、そのまま蜘蛛の巣を突き破った。
ツツジの枝の中で体勢を整える鳥。
翼に白い糸のついた鳥は気持ちが悪いのか、それを振り落とそうとその場で羽をバタつかせ暴れ回る。その度、蜘蛛の巣は、破壊されていった。
コチはあまりにも突然の事で一体何が起きたのか分からなかった。
「もしかして、この鳥、お前が?」
「どうだ?良い作戦だろ?」
ホリデイは、鳥が突っ込んだ衝撃で、ほつれた糸をひっぺ剥がしながら得意げにそう答えた。
ピエー
白い糸にイライラした鳥の声。
突然、鳥は動きを止め、糸で縛られたコチと目が合った。
コチを縛る糸は、まだしっかりとコチを捕まえていた。
まずい。
すると突然、コチの目の前に、ひらりとホリデイが現れた。鳥は、コチではなく、ひらりと動く蝶に標準を合わせた。
「いいか。一瞬だぞ。」
ホリデイは、鳥に意識を集中しながら、後ろのコチに合図を送る。
鳥の丸い目がキラリと光ると鳥は、勢い良くホリデイ目掛けて突進する。
「さあ。行くぞ。自由の空へ。」
ホリデイは、鳥の突進をひらりと交わし、空へと向かって羽ばたいた。
ひらりと獲物が目の前からいなくなった鳥は、ホリデイの後ろで捕まるコチの方に突っ込んだ。
コチのすぐ隣を通過する鳥のくちばしをコマ送りにコチの見開かれた目が捉える。
すれすれだった。
息を飲む。
まだ体は固まっていた。
ホリデイの叫ぶ声が聞こえる。
「今だ。飛べ!」
コチは、羽に意識を向ける。
動く。
糸がほつれふわふわとコチの周りに漂っている。
コチは思い切って羽を羽ばたかせる。
ダメだ。
羽は動いても、白い糸がまだコチの足にしつこく絡みついて離さないでいた。
もう少し。
コチは、力いっぱい小さな羽を動かす。
ムクッと起き上がった鳥が、小さなコチに気がついた。
鳥はその場を離れる事のできないコチにゆっくり近づいてくる。
「何をやってんだよ。早くしろ。」
上空でホリデイの苛立つ声が聞こえる。
「足に絡まった糸が取れないんだよ。」
確実に近づいてくる鳥。
その瞳に映る自分のもがく姿が見えた。
焦るコチの前に再び、ホリデイが降りてきた。
「こっちだ。こっち。」
ホリデイは必死に自分に注目させるように鳥の前で騒ぎ立てる。
鳥の目線は少しだけ、ホリデイに向くが、すぐに標準はコチに再び合わされた。
コチの見上げる上空には、青い空にゆっくりと流れる真っ白な雲。
それと太陽がいた。
太陽は何を見つめる?
そこから美しい世界は見つかったかい?
コチは、まだ諦めていない。
鳥の目が光る。
「自由の世界だ。」
そして、弾けるように、糸が外れた。
外れた糸は、弾くようにコチを上空に飛ばした。
間一髪。
コチに逃げられたクチバシが再び蜘蛛の巣に突っ込んだ。
「よしっきた!」
ホリデイは、上空飛び上がったコチを確認し、空に向かってはしゃぎながら飛び上がった。
ホリデイがチラっと下を見ると失った世界を呆然と見据える蜘蛛がいた。
鳥は、破壊された世界で、絡まる糸を取り除こうとまだ暴れていた。
ホリデイは、はしゃぐ気持ちを抑え鳥に気づかれないようにそっと空まで羽ばたいた。

「コチ?」
2匹は、自転車を漕ぐ年老いた人間の被る帽子の上で、ヘトヘトに疲れきった重い体を休ませていた。
あれから、コチとホリデイは蜘蛛の巣を破壊したあの鳥に見つかり、合流した2匹は鳥に追い回された。
鳥は執拗にホリデイを追いかけた。
目立つ羽は大変らしい。
コチは、うまい事木陰に隠れるがホリデイはすぐに見つかった。
コチが隠れていても、ホリデイがコチを追いかけるものだから、結局2匹で追われる事になる。
自転車を漕ぐ人間の頭に飛び込もうと言ったのはホリデイだった。
ホリデイは、鳥が滅多な事がなければ人間に近づいてこないという事を知っていた。
そして、飛び込むなら帽子をかぶったお年寄りの頭だって事も。
ようやく羽を休める事が出来たコチはずっと気になっていた事をホリデイに聞き、ホリデイはそれに答えた。
「名前、コチって言うんだろ?あの木、あー、ジイさんが教えてくれたぞ。」
「コチ?」
「なんだ。驚いた顔をして。誰だって名前くらい持っているもんだ。名前がなければなんてコチを呼べばいい?あ、そうそう。僕の名前。ホリデイね。」
カタカタと揺れる。
自転車の走るスピードは、心地良い風を作った。
「あー。まだあんなところで太陽が笑っているよ。もうヘトヘト。何て長い日なんだ。これもコチに会っちまったせいだな?」
ホリデイは笑いながらそう言った。
コチには太陽が笑っている顔が分からない。
だから、ホリデイの笑う顔を太陽に重ねてみた。
これなら、不思議と居心地が悪くなかった。
「本当に疲れた。これもホリデイが俺を見つけちまったからいけないんだ。」
気づかないうちにコチも笑っていた。
太陽の下でこんなに笑うのは、初めてかもしれない。
「コチを見つけたのは太陽さ。ほら、コチにもしっかり影がある。コチのすぐそばに太陽はいるって事だ。この世界でかくれんぼしたってすぐに太陽に見つかっちまう。みーつけたって影が言ってるだろ?文句言うなら、笑っているあの太陽に言うんだな。」
ホリデイは、コチの笑う横顔をチラっと見た。
いつの間にか笑っていた口を急いで閉じてコチは聞いた。
「ねえ。あの鳥をどうやって連れてきたんだよ?」
ホリデイは少し考えていった。
「まー。冗談を言って怒らせたんだな。本気で追いかけてくるから本当に焦ったよ。でもお陰で助かった。僕のデタラメな冗談も時には役立つだろ?」
「そんな怒らせるって何て言ったの?」
「馬鹿げたことさ。もういいだろ?僕も反省しているんだ。」
「まあ、二度とあんなに逃げ回るのはごめんだからな。聞かない方が良さそうだ。」
「そうさ。あの鳥も忘れてくれたら嬉しいもんだ。」
「甘いな。」
「だろ。」
「言われた奴は簡単には忘れないよ。」
「言ったやつは簡単に忘れちまう。」
「ホリデイ。まさか鳥に言った冗談をもう忘れたのか?」
「バレた?」
「忘れるか?普通。」
「忘れるみたいだ。」
「ひどいやつだな。そういえばさ、あの蜘蛛の爺さんが言ってたけど、チョウは約束を必ず守るって言ってたぞ。」
「おいおい。まだそんな迷信を信じている奴がいるのかよ。あの蜘蛛、ピュアじゃない。」
「どうせ約束も忘れたっていえば良いって魂胆だろ。チョウは汚い、ホラ吹き野郎だな。」
「おい、チョウをそんな悪く言うな。そもそも僕はチョウじゃない。」
「え?」
「僕はホリデイだ。」
「そう言うの、うるせーな。」
「お前は口が悪いな。」
「ホリデイよりマシさ。」
2匹はまた同じタイミングで笑った。
「でも。追いかけられている時のホリデイの顔。めちゃくちゃ面白かったな?」
「知らねえよ。残念ながら自分の顔は見れないからな。」
「最高に笑えたよ。」
「でもよ、蜘蛛の巣に絡まってぶら下がっているコチの姿も最高に笑えたよ。」
「あれは笑っちゃいけないだろ。」
「まあ。お互い最高に笑えて良かったじゃないか。悲しいときの思い出し笑いはこれで決まりだな。」
「そうなのか?」
コチとホリデイはまた顔を合わせて笑った。
「それよりもこの帽子は一体どこに俺たちを運ぶ気だい?」
「そんな事、僕が知るわけがないだろ。僕たちがどこに行くかは、この羽次第さ。僕たちはあの蜘蛛から自由の羽を手に入れたんだからな。」
本気で言っているのか。ホリデイは笑って言うからいつもわからない。
「なんか、うるせーな」
コチも笑って答えた。
「そういう事でそろそろ戻るか?」
「えっ?どこに?」
「決まっているだろ。ジイさんの所さ。」
それから、毎朝、ホリデイは、ジイさんの所にやってきた。
眠ろうとしているコチはいつもホリデイの声で起こされた。
ホリデイは朝の光とともにやってきて、コチを太陽のいる世界に誘う。
「僕たちは、自由の羽を持っているんだぞ。」
そう言って、ホリデイは嫌がるコチを無理やり連れ出した。
「俺の自由はどこにあるんだよ?」
そう言って、コチは、しぶしぶ太陽の下をホリデイと一緒に飛んでいく。
ホリデイは陽だまりを飛び。
コチは日陰を飛んだ。
ある日の公園には、ずいぶんと人間がうじゃうじゃといた。
小さい人間が公園を走り回り、それを大きい人間が見守った。
コチとホリデイが、2匹で公園を飛んでいると、突如、網を持った小さな人間がホリデイを捕まえようとホリデイを追いかけ回した。
「人気者は大変だな。」
それを見てコチが笑っていると、ホリデイに逃げられた小さい人間が向きを変え、次にコチを追いかけ回す。
「チョウチョ。チョウチョ。」
無邪気に追いかける子供は、虫取り網を投げつけるように何度も振りかざした。
必死に逃げるコチを見て今度は、ホリデイが笑っていた。
「おい。バカ。やめろ。俺は、蝶じゃない。」
子供がめちゃくちゃに振り回す網がバタバタと必死に逃げるコチを捕らえた。
「えっ。まずいじゃん。」
嬉しそうに、網をそーっと覗き込む子供の背後でホリデイは慌ててそれを覗いていた。
子供は、誇らしげに大人を呼ぶ。
網の中で必死にもがくコチ。
「お前。よく捕まるな。」
コチと目があったホリデイは戯けた顔で言った。
「そんな事言ってないで早く助けろよ。」
コチは懇願するようにホリデイに言った。
「待ってろよ。今、考えてる。」
すると、子供が呼んでいた大人がやってきた。
子供は急かすように大人に網の中を見せつけた。
そして、子供が網の中に手を突っ込みコチに触れようとする。
悲鳴がした。
出したのは大人だ。
大人は、必死にそれを阻止した。
そして、大人は、網を子供から取り上げ、それを振り回し、コチを自由の空に解放した。
外に放り出されたコチ。
生きているかと恐る恐る開けた目の前には、驚いた顔のホリデイがいた。
「コチ、どうやったんだよ?」
「何が何だか。」
小さな人は泣いていた。
「チョウチョ。」
子供を嗜めるように、膝を曲げた大人は何かを伝えた。
子供は泣き止まない。
コチには、人間の言葉がわからないが、泣いている理由は分かる気がした。
コチにだって小さな幼虫の時代があった。
きっと、あの子は、区別のつかない小さな幼虫なんだ。
小さい頃には分からない事がいっぱいある。
「コチ。君はもの凄い力を持っているんじゃないか?」
ホリデイが、真面目な顔をしてコチに聞いた。
「なんだよ。それ?」
「だって、あんなに大きな人間がコチにビビっていたぞ。僕に隠している力があるんじゃないか?見えない力だよ。」
コチは、ホリデイの真面目な顔がなんだか可笑しかった。
「そうさ。黙っていたけどな。」
はっははは、とコチは、大魔王が降臨したかのような笑い声で演技してみせた。
「震えるな。コチ演技下手すぎ。」
ホリデイは、冷めきった顔でコチを見て、それからいつものように吹き出し笑った。
きっとホリデイは、小さい頃から、何も変わっていないのかもしれない。
ホリデイは見えていないものがたくさんあるの?
いや、違う。
幼虫の頃見えていたものがまだ見えているのかもしれない。
「あれ、なんだ?」
太陽の下、公園には、不思議なモノが飛んでいた。まんまるで透明で、キラリキラリと風に流され、ふわふわと飛んでいる。
「見ろよ。コチ。小さい虹が閉じ込められている。」
ホリデイは、小さな人間の作ったシャボン玉を見て興奮しながらコチに言った。
「虹?どこ??」
ホリデイは、無数に空をのぼっていくシャボン玉を追いかけた。
そして、ホリデイがシャボン玉に触れた瞬間、シャボン玉はパシャンと泡となって弾けた。
気づけばホリデイとコチは一面のシャボン玉に囲まれた。
キラキラと浮かぶシャボン玉、空の青も漂う白も公園の緑もはしゃぐ子供たちもキラキラと映し煌めいている。
コチの知らない不思議な光景。
楽しげに笑うホリデイの声。
美しい太陽の世界だ。
ホリデイは、まだ、懲りずにシャボン玉を笑いながら追いかける。
追いかけているのか、遊んでいるのか、シャボン玉を割る度、水しぶきを浴びながら「ひょー」っと奇声をあげた。
「コチもやってみろよ。」
風に漂うシャボン玉がコチに当たる。
パシャン。
「ひょー!」
結局、2匹は笑いながらシャボン玉を夢中で追いかけた。
シャボン臭い2匹は、公園のベンチに座る年老いた人間の帽子の上で、濡れた体を乾かしながら、空に浮かんでいくシャボン玉を眺めていた。
「コチ。虹見えたか?」
ホリデイは空を見ながら隣にいるコチに聞いた。
「その前に全部弾けたよ。」
コチも空を見ながら隣にホリデイを感じていた。
「コチは虹を見たことがあるか?」
コチは少し考えて答えた。
「あるよ。水たまりの中でゆらゆら揺れていたよ。」
「空を駆ける大きな虹だよ。」
ホリデイは得意げにそう言った。
「知らない。興味ないよ。」
コチはつまらなそうに返事をしたのに、ホリデイはイキイキと話し続けた。
「僕は、見たことがあるんだよ。」
だから興味ないってと言おうと思ったがコチは言葉にする事をやめた。
弾むホリデイの声を遮るのはなんだか惜しい気がした。
「僕が、青い空を飛ぶことを夢見ていた時だよ。真っ暗だった視界に急に淡い光が現れて僕は光に包まれたんだ。そしてバリって視界が破けたその先からまばゆい光さ。僕はあまりの眩しさに顔を何かで覆ったよ。そして少しずつそれをずらして光の先を覗いたんだよ。現れたのはなんだと思うコチ?」
「虹だろ?」
「そうなんだよ。コチ。よくわかったな。青い空に大きな、ものすごい大きな虹が、空一面に伸びているんだよ。虹の終わりが見えないくらいさ。」
ホリデイは興奮して身振り手振りで一所懸命にその虹の大きさを表わそうとした。
ホリデイの興奮した様子とは反対に帽子の下のお年寄りが大きなあくびをして、立ち上がり歩き出す。
揺れる帽子の上でもホリデイは変わらず話を続けた。
「僕はもっとその虹を見たいと思って顔を覆っていたものをどかして気づいたんだ。なんだと思う?」
「うーん。なんだ?」
「生まれたばかりの僕の羽だよ」
コチは、揺れる帽子の上でバランスをとりながらホリデイの話を聞いた。
「僕の羽が生まれた日、空に虹がかかったんだ。この世界が僕を祝福してくれたんだよ。どう、臭うか?」
「臭うな。」
「だろ。」
2匹は笑った。
「ホリデイを祝福するほど世界は暇じゃないよ。虹なんて、ただの光の反射だろ?」
コチはホリデイのふざけた話をふざけた様子で答えた。
「バカだな。虹を見た事ない奴が、虹を語るんじゃねえよ。」
ホリデイは、コチのふざけた話をふざけた様子で答えた。
二人の子供が、老人の帽子を指差している。老人は、上を見上げ、帽子に手を差し伸べた。2匹は慌てて、シワ帽子から飛び立った。

「コチ、いつまで寝ているんだ。早く行くぞ。」
「これから寝るところだよ。」
コチは、いつも気怠そうに、眠い目をこする。
でも、本当はホリデイのせいで、太陽の世界での疲れを、月の世界で取るような日々が続いていた。
少しずつ、コチは太陽の世界で多くの時間を過ごすようになっていたのだ。
それでも、太陽の悪口は、欠かさなかった。
自分が仕方なくこの世界にいるという通行手形を差し出しながら、飛んでいたからだ。
誰かが、文句を言ってきたってこの通行手形とホリデイがいれば、許される気がした。
コチは、朝焼けと夕焼けのオレンジ色の空が好きになっていた。
太陽の世界の始まりと月の世界の始まり。
コチには、世界の終わりだった光、あの光が始まりに変わったからだ。
ホリデイにあのオレンジ色の空が好きだって事を言えたらどんなに良いだろう。
きっとホリデイは喜んでそれに答えてくれるだろう。
悪ふざけな答えでも良い。
それをホリデイが知っていると言う事でオレンジ色の空がもっと輝く気がした。
でもホリデイはきっと知らない。
コチは相変わらず朝の不機嫌な演技をやっていたからだ。
けど、それも止める事が出来ない。
コチは無理やり誘われているという通行手形を失ってしまったら、この太陽のいる世界で一体どう振る舞えばいいのかが分からず、急に居場所がなくなってしまう気がしたからだ。
太陽の世界で、シワ帽子を見つければ必ずそこに飛び乗った。
休んでいればシワ帽子は色々なところに連れて行ってくれる。
その間ホリデイはコチにこの世界の事を色々と教えた。
でも、それはコチに太陽の世界を好きになってもらいたいというそんな想いとはちょっと違う気がした。
自分の世界に引きずり込もうなんて、蜘蛛のおじさんのような趣味は持ち合わせていないのだろう。
ホリデイがコチに何かを教える時、ホリデイは最後にはいつも笑っていた。
それが真実なのか分からない。全部、冗談だって言われた方がしっくりとくる。
まあ、真実やら正解なんて本当なんて結局分からないし、存在すら怪しいものだ。いちいち探していたら、面倒だから、ホリデイの話は安心だ。最初から冗談のように聞こえるから、わざわざ疑う必要もない。
ある時、ホリデイが人間について話していた。
人間が、下向いてばかり歩いているのは、探し物を探しているからだと言う。
人間は持ち物が多いからしょっ中ものを落とす。
だからいつも落し物を探していると言う。
でも落としたものが何かも分かっちゃいないからずっとああやって探しているらしいのだ。
「不気味だろ?」
「ホラーかよ。」
ホリデイもコチと同じように人間を不気味に思っていたらしい。
ある時、ホリデイが鳥について話していた。
ジイさんの枝に小鳥が止まっているのは、ジイさんの枝に実る果実を待っているかららしい。
「卑しい奴らだ。せっかく実ったじいさんの実を狙っているなんて。俺がもう少し、腕が太かったらぶっ飛ばしてやるのに。ごめん。ジイさん。俺の細い腕を恨んでくれ。」
怒るコチに、やっぱりホリデイは笑っていた。
「おい。じいさんをよく見てみろよ。怒っているか?じいさんは嬉しいんだよ。じいさんはあの鳥が好きなんだ。」
「おいおい、冗談はよしてくれ」
コチはジイさんを見上げた。
ジイさんの葉の上で、チュンチュンと2匹の鳥が日の光を浴びながら何やら話をしている。
鳥は、今にも襲いかかってきそうで、見ているだけで、背中が震えてきた。
あんな野蛮な鳥をジイさんが好きだなんて、コチには、どうもいい気分ではない。
「もっとマシな冗談はないのかい?」
コチが眉をひそめているとホリデイは続けた。
「ジイさんの実には、ジイさんの思いが詰まっているんだよ。要は、ジイさんの分身みたいなものさ。その実を鳥の翼がどこか遠くに運んでいくんだ。ジイさんは遠くの知らない世界で、また、芽生えて、長い時間を生きるんだよ。どんな世界か、そこでどんな出会いが待っているのか。ジイさんは、その実に夢を見ているんだよ。」
コチは不思議そうに、ホリデイの話を聞いていた。
「だから、ジイさんは、あの鳥に、果実を与える事を心待ちにしているんだよ。ジイさんにとっては夢と時を運ぶ希望の鳥なのさ。迷惑だなんて思うものか。ジイさんにとって迷惑なのは、コチくらいのものさ。」
ホリデイは笑いながらこう言った。
ジイさんも今度は笑っている。
ジイさんだってホリデイをもう知っている。
コチだけが、いつものホリデイの冗談に少し、黙って考え込んでいた。
「あのウルサイ鳥がジイさんの夢と時を運ぶ?」
ホリデイの話を聞きながらコチは想像した。
ジイさんが、花を咲かせ(どんな色の花?)、
実がなり(どんな形?)、
それを運ぶ鳥(腹立たしい顔だ)
大空に飛んでいく。
コチは緑色の葉を風に揺らすジイさんを見上げた。
「ホリデイはジイさんの花を見たことがあるのかい?」
「ないさ。」
「じゃあ、なんで知っているの?」
「風の噂さ。」
「ジイさんにも花が咲くのか・・」
コチがなんだか居心地悪そうにしていると、ジイさんの葉が優しく揺れる。
そんな優しいジイさんの揺れる葉を見ながらホリデイはボソッとつぶやいた。
「見る事が出来たらいいのになあ。」
ホリデイは、まるで見る事が出来ないって知っているかのようだった。
いつも夢心地のホリデイにしては珍しい事だ。
この世界では、コチやホリデイの知る事のない途方もない時間が流れているらしい。
ホリデイは言う。
今は、誰かがつないでくれた時間を持っているだけ。
いつか、その時間を手放さないといけない。
それがいつなのか?
きっと長くない。
もう背中には羽がある。
知っているさ。
ホリデイは笑った。
釣られてコチも笑う。
「ジイさんの実は、知らない世界に行っても俺を思い出すかな?」
コチは、チカチカと揺れるジイさんの木漏れ日に当たりながら、ホリデイにそう、聞いた。
「当たり前だろ。そんな間抜け面、忘れるわけがない。」
コチは、笑って、ホリデイを小突いた。
「ねえ。ジイさん。だからって僕の事も忘れないでくれよ。」
2匹の声に、風に揺れる葉はそっと答える。
「あの鳥が、ジイさんの時と夢を運ぶなんてね。なかなかやるじゃないか。今度からは、ウルサイ鳥の鳴き声も少しはましに聞こえるかもな。」
どこからか、聞こえてくる鳥の鳴き声は、小気味なリズムで世界に音を作る。
コチとホリデイは、その世界に耳を澄ませた。
「コチ。僕たちにも誰かの夢を運ぶ羽があるんだぞ。」

それを話すホリデイは少し舞い上がっていた。
ホリデイとコチはいつもように青空の下を飛んでいた。
ホリデイが浮かれた様子でコチに話しかけた。
「コチ。僕ってさ。ものすごい人気なんだよ。知ってた?」
「俺はその事にものすごく興味がないよ。」
「きっとコチは僕の人気を知ってびっくりするさ。」
コチはいつものように、太陽の世界を拒む通行手形とホリデイの人気なんか興味ないという通行手形を新しく手に入れて、ホリデイと共に、その場所に向かった。
そこは、お花屋さん。
お花屋さんには、色とりどりの花達が、色別に分けられ、綺麗に並んでいる。
「ほら。笑って。」
綺麗に並べられた花は、合図に合わせて笑顔を作る。
ここの花はみんなが笑っている。
みんなが同じ顔で、にっこりと決まった笑顔を振りまく。
怒った顔した花なんてここにはいない。
笑っていない花を見て、ご機嫌になる人間なんていないからだ。
離れた場所からでも花の蜜の匂いが溢れかえっていた。
沈むコチとは裏腹にホリデイのテンションはみるみる上がっていく。
「さあ。見ていろよ。コチ。僕の勇姿を。」
コチは、おう、と気の抜けた返事をして、仕方なくその様子を電信柱の陰から見守った。
ホリデイが言っていた通り、確かにホリデイは、花屋の花たちからすごい人気だった。
でも、コチはそんなに見せびらかさなくてもホリデイに対する花の喜びは知っていた。
いつもジイさんの庭で見ていたからだ。
いつもと違うホリデイは明らかにコチを意識して飛んでいた。
「ホリデイもやっぱり蝶だな。」
コチは、そんなカッコ悪いホリデイを小馬鹿に笑う。
まんざらでもない表情で、コチの視線を探しているホリデイ。
自分の為に飛んでいるホリデイはいつもと違って窮屈そうだ
コチは、まゆをひそめて、間抜けなホリデイに視線を送る。
別のところでも花の歓声が聞こえた。
花屋に別の蝶が3匹やってきた。
こちらの3匹の蝶も、花の歓声を聞き、まんざらでもない表情だ。
「やっぱりどこの蝶も間抜けなものだ。」
コチは電信柱の影でそう思った。
電信柱は意外にコチの体の色と馴染み、この世界からコチを程度よく消してくれた。
間抜けな蝶の行動に飽きて空を見上げていたコチであったが、声が聞こえた。
「こいつだよ。蕾に変な事を吹き込んでいる奴だよ。」
何やらホリデイが3匹の蝶に絡まれているようだ。
「変な事?おいおい。君、僕を変態扱いするなよ。」
ホリデイが笑いながら、そう言うと他の蝶が話に入ってきた。
「お前さ。勝手な事を言ってくれたら困るんだよ。蝶は花の夢の運び屋なんかじゃない。お前、まだ幼虫なのか?」
3匹は、合わせるように笑った。
「君のおかげで蜜を頂くのに、いちいち期待されてちゃ面倒なんだよ。」
「そうだ。」
「そうだ。」
取り巻きが騒ぎ立てる。羽の大きさはホリデイには及ばないが、声だけは大きい。
「必死に俺たちは飛んでいるんだ。ただ待っているだけの花に夢やおとぎ話を言ってくれるな。約束を破らない蝶の中に、こんなホラ吹きがいたら蝶の評判が下がってしまうだろ?分かってくれるか?モドキ野郎」
3匹は、合わせるように笑っていた。
「また、ホリデイが面倒くさい事になっているな」
と面倒臭そうにその光景を見ていたコチだったが、コチは、その3匹の蝶の嘲笑う笑い声を聞いて、ふと、思い出した。
木枯らしだー。
遠くの空から聞こえてきた笑い声。
ホリデイと一緒にいて、つい忘れていたあの感じが蘇る。
青空がどんどん遠ざかっていくあの感じだ。
そうだった。僕の居場所はここじゃない。
このまま、見つからないように、そっと、この場から離れよう。
ホリデイには、つまらないから先に帰ったと後で伝えればいい。
コチは誰にも見つからないように電信柱の背後に移動していると声がした。
「なんで、僕がここから離れないといけない?」
ホリデイの声が聞こえた。
コチは振り向いた。
3対1。
ホリデイが小突かれる。
「ここは、別にお前らだけの世界じゃない。ここは僕の場所だ。」
見上げたら、そう。
青空があった。
「また、言ってるよ。」
そして、息を吐いて、コチは3匹の蝶に目掛けて飛び出した。
「どけ、どけえ。」
一匹の蝶がコチの体当たりによって、宙を回る。
他の2匹の蝶は何事かと、飛んできたコチを見る。
ホリデイがコチに駆け寄ってくる。
「コチ。いいタックルじゃねえかよ。」
ホリデイは嬉しそうにコチを小突いた。
蝶たちは突然現れたそいつを見て、何かを思い出したかのように突然、騒ぎ出した。
「大変だ。エライ事だ。春に木枯らしがやってきた。」
宙を回っていた蝶も、一緒になって騒ぐ。
「木枯らしだ。みんな逃げろ。」
花屋は、異様な雰囲気に包まれた。
「みんな気をつけろ。こいつに近づいたら枯れてしまうぞ。」
3匹の蝶は、「木枯らしだ。皆んな近づくな。逃げろー」と方々に叫びながら去っていく。
叫びは笑い声となって徐々に小さく消えていった。
「木枯らし?なんだ。あいつら?」
ホリデイは、3匹の蝶が何を言っているのかが分からなかった。
首をかしげるホリデイに対して、コチは黙ったままだった。
「これで、邪魔がいなくなったな。やっぱり僕は邪魔な奴を追い出す才能があるみたいだ。」
ホリデイはいつもの調子で笑う。
コチは黙ったままだった。
花屋の花の様子がおかしい事はコチはすぐに気がついた。
花は恐ろしいものを見るようにコチを見ていた。
それだけじゃないホリデイに対してもそうだった。
様子のおかしい花に、ホリデイが近づくと、悲鳴が生まれた。
拒絶するような叫びだ。
「嫌。来ないでー。」
飛ぶホリデイが、その上を通るたび悲鳴が続く。
その時のホリデイの表情が、コチの目に焼きついた。
ホリデイは、すぐにいつものふざけた表情に戻り、コチの方を向いた。
「おいおい。僕の人気はいったいどこにいっちまった?」
すると、ホリデイは、花の上ギリギリに飛んで、次々と聞こえる花の悲鳴の波を作った。
「なんだよ。皆んなどうしちまったんだよ。僕が恐怖の大魔王にでも見えるのか?」
ホリデイはいつかコチがやっていた「ハッハハハ」と空から大魔王が降りてきたような笑い方をしながら飛び回った。
コチと同じ、下手くそな演技だったが悲鳴を次々と生んだ。
「コチ。なあ。コチ?」
黙ったままのコチをホリデイは呼んだ。
「一緒に飛ぼうコチ。一緒に笑ってくれよ。」
悲鳴をまとったホリデイが笑っていた。
めちゃくちゃだ。
「下手くそだな。」
コチも飛び上がって大魔王の笑い声をホリデイと一緒になってやった。
2匹は、ちゃんと腹を抱えて笑って空を転げたよ。
「せっかく僕の人気ぶりをコチに見せてやろうと思ったのに、カッコ悪いところ見せちまったな。」
2匹は、花屋を離れ、オレンジ色の光が伸びる空の下を飛んでいた。
「だから、最初から言ってるだろ。そんな所、俺は見たくないんだよ。」
コチはホリデイの本当の顔を知っている。
毎朝、ジイさんの庭に咲く花の顔を見ていれば誰だって分かる。
ホリデイを見た時の花の顔。
春の訪れを喜ぶ顔を見れば誰だって。そして、太陽の下、嬉しそうに花を覗くホリデイの顔を見れば、ホリデイの生きる喜びに気がつくだろう。
それが、コチの大好きなホリデイだ。
悲鳴はホリデイのものなんかじゃない。
コチは、自分のせいで本当のホリデイの喜びの顔が消えてしまうのではないかと怖かった。
「ホリデイは、あんな悲鳴を聞いたのは初めてだろ?」
ホリデイは、いつもと違うコチの沈む声にぽりぽりと顔を掻きながら首をかしげた。
「まあ。あれだ。あの悲鳴は、俺のせいだ。ホリデイには関係ない。」
コチは、ホリデイから目を逸らしながらそう言った。
ホリデイは、何かを探すようにじっと下手に笑うコチの横顔を見る。
「何言ってる?あいつらは僕に向かって叫んでいたぞ。ひとり占めするなよ。どんだけコチは僕を追い出したいんだ?」
ホリデイはケラケラと笑った。
コチは、ホリデイのこの作り上げた笑いが嫌だった。
ホリデイが急に大人になってしまったかのような気がした。
そして、コチは、ホリデイを見ずに飛び立った。
「じゃあな。そろそろ行くよ。俺には月の世界が待っているからな。」
ホリデイが呼び止める声を何度も無視して、コチは、終わりゆくオレンジ色の世界を飛んで行った。

それから、コチは青空の下を飛ぶことはなかった。
いつもの朝に、ホリデイがやってきても、ジイさんの木の上で、ふざける事はあっても、何度もしつこいホリデイの誘いがあっても、一緒に飛ぶことはなく、ホリデイは結局ひとりで、しぶしぶ青空の下を飛んだ。
太陽が昇り、降りるまで、コチは、ジイさんの木の上で、なるべく太陽の移動に合わせて、日の当たらない影に移動した。
小鳥の歌に耳を澄ませた。
まるで遠い世界だった。
コチと太陽の世界をつなぐのはホリデイとジイさんの優しい声だけ。
ただ、ひたすら太陽が消える時間を待った。
でも、なぜだろう。
沈む真っ赤な太陽を見ても、世界の始まりはやってこなかった。
ただ、暗い夜が来るだけだ。
いつもの夜だ。
いつの間にか、月が夜空に浮かんでいた。
いつも気づかないうちに、月がいる。
夜には、月以外の光が溢れ返っているから、昼も夜も結局、月は、目立たない。
そんな月を冷やかすように見上げると、見上げた夜空に一匹の蝶が飛んでいた。
「よお、コチ。そろそろコチの大好きな月の世界とやらに案内しろよ。まあ、期待はしてないけどな。」
ホリデイは、太陽の光のような笑顔を、夜に浮かべた。
ホリデイが初めて夜に現れた。
月明かりに浮かぶホリデイの羽はやっぱり綺麗だった。
なんだか、月がさっきよりも輝いて見える。
「なんだよ、ホリデイ。いきなりやって来るなよ。まったくいい迷惑だ。そんな間抜け面が、急に現れたら月がびっくりするだろ。」
コチはいつものように、心の中に生まれた感情をひっくり返して、ホリデイに言葉をぶつける。
「おいおい。ここでも僕を追い出す気かい?お月さん、間抜け面も慣れたら良いもんだぞ。太陽が言ってた。最近見ない間抜け面のせいで日々の笑いが少なくて物足りないってさ。どうやら間抜け面には依存性があるようだな。」
笑う2匹の間に風が通る。
心地よい風だ。
コチは、こんな優しい風を感じた事はない。
それは、月の世界の仕業?いや違う。
それは、結局、後になって気づく。
大事な事はいつも後になってやってくる。
「月の世界のおすすめスポット紹介してよ。」
ホリデイはコチに言った。
コチは、困ってしまった。
いつも太陽の世界の悪口をホリデイに言う癖に、コチは、月の世界でホリデイに自慢できるような場所が全く浮かんでこなかった。
不味い事になった。
これじゃ月の世界の惨敗だ。
青白い顔をしたコチは、あてもなくホリデイを背に夜空に飛び出した。
「まだ着かないのかよ。」
ホリデイの言葉により、ますますコチは焦る。
どうしよう。
「もうすぐさ。慌てるなって・・」
考えれば考えるほど、渦のようにくるくる回って落ちていく。
そして、次第に頭が真っ白になる。
「おーい。」
遠くから、声がした。
焦ったコチには聞こえなかったが、それをホリデイは聞いていた。
「なあ。コチ。誰か、呼んでるぞ。」
えっ?と、コチは辺りを見回した。
闇にぼんやり光る自動販売機があった。
不味い。
いつの間にか、ここに来ていた。
「おーい。こっちに来いよ。」
古い自動販売機には、存知あげないパッケージの飲み物が光に浮かび、その光に無数の小さな影が集まっている。
ダメだ。
ここにホリデイを連れて行ってはいけない。
こんな所をホリデイに見られてはいけない。
コチは、何も聞いていないとばかりに、羽を動かす。
気付かれない程度に飛ぶ速度を上げた。
返事をしないコチに自動販売機から次々と声が聞こえて来る。
「おーい。寄っていかないのかよ。」
無言で飛ぶコチに対して、ホリデイが話しかける。
「おい。コチ。あそこで誰かが呼んでいるぞ。」
すると、突然にホリデイが自動販売機の方に向かって飛んでいく。
「おーい。呼んだか?」
ホリデイがコチの代わりに答える。
呼ばれたのはお前じゃないだろ。
と、小さく舌打ちをしたコチは、しぶしぶホリデイの後を追いかけた。
「お前、見ない顔だな。それに気取った蝶のようにヒラヒラ飛びやがる。気に入らないね。」
たくさんの虫の群れから、誰かがホリデイに話かけた。
ホリデイは、キョロキョロと見回し、どこを向いて答えればいいかを眩しい光の中で探していた。
ここに降りると眩しい光によって視界が奪われる。
「誰だい?俺に話かけたのは?」
ホリデイの問いに、誰も反応しない。
無数の黒い影は光で誰が誰だが分かりやしない。
ここでは誰も名乗らないし、ここで話したものの素性を明かさない。
こんなルール、ホリデイに理解できるかな?
ここでは、真実かどうか知らないが、たくさんの話題が上がる。
面白い話題や、危険な話題。
それぞれが持ち集めた話題で、素性を明かさないものたちが、あーだの、こーだの、つぶやくのだ。
今、話題を集めているのは、蜘蛛の巣に捕まった蛾を蝶が助けた話だった。
「勇気ある行動だ。」
「嘘くさい。気取り屋の蝶がそんな事するわけがない。」
「そもそも鳥が、突っ込んでうまい事蜘蛛の巣を破壊して、逃げる事ができるなんて、そんな話はきっと作り話さ。」
「子供が真似をしたらどうするの?」
「羽根が生えた幼虫がどこにいるのですか?どうやって真似をするのですか?簡潔にお答えてください。」
ホリデイは、隣のコチの耳元で囁いた。
「なあ、これ。僕たちの話じゃないか?なあ、コチ?お前コチだよな?」
コチは、聞こえてないふりをした。
もちろんこの話をここで最初に披露したのはコチであった。
でも今では、この話が自分のものであったかさえ分からなくなってきていた。
自分たちの話を見てもいないものたちがあれやこれや評価し勝手に話を壊して作り変える。
なんのために?暇つぶし?コチはここで話した事を後悔していた。
大事な宝物を叩いたりつねったり伸ばしたりと形を変えられその上に汚い液体で色を塗りつぶされているような、そんな気分だ。
ホリデイはこの場所が嫌いだろうな。
こんな所で時間を潰していたなんて知られたくはない事だった。
このまま、不愉快に時間が過ぎる様子をホリデイはどう思っているのだろう。
「さあ、もう行こうぜ」というべきか?
いやどこに行く?
「もっと楽しい所があるんだよ。」
あれ、どこかある?
異様な時間はゆっくりと過ぎていく。
この不毛な時間を壊したのは、一匹のカエルの出現だった。
「はいよ〜。待ったかい?」
カエルは、軽快なジャンプで自動販売機をよじ登る。
カエルの出現により、自動販売機の上はもの凄い騒ぎとなった。
さっきまであれやこれやと正義を論じていた者が我先にとそこにいる者をはね退け真っ先に逃げていく。
騒々しい現場で、カエルは呑気に月を見上げて喉を膨らます。
「喉も月もいい調子だ。」
カエルはペロっと舌を出し、目の前で横切ろうとした逃げ惑う小さな虫を反射的に捕まえ口に運ぶ。
そして、口に入った小さな虫を自分の目の前にぺっと吐き出した。
「君には特等席をプレゼントだ。」
吐き出された虫は唾液でベトベトになった体で放心状態のまま目の前のカエルを見上げていた。
「おい、早く逃げようぜ。」
そんな光景を見て、慌てるホリデイをよそにコチは、落ち着いていた。
「大丈夫。あのカエルは俺たちを食べたりしないよ。」
ホリデイは、困惑した様子だ。
「食べないって、じゃあ、あのカエルは一体何しに来たんだよ。」
コチは、いつもひょうひょうとしているホリデイの少し不安な顔を見て、ちょっと嬉しくなった。
「歌うのさ。」
ホリデイの困惑は続く。
「はい?」
コチは嬉しそうに困惑するホリデイに言った。
「まあ聞いてみろって。でも、あんまり近づいちゃダメだぞ。カエルのお口の中に入ってずぶ濡れにされちまうからな。」
陽気に話すコチを横目に、ホリデイは不安そうにカエルを見つめた。
コチの言う通り、カエルは歌い出した。
逃げ惑う虫の混乱した自動販売機のステージでカエルは気持ちよく歌っていた。
この歌をバカにする奴は多いがコチは、カエルの歌う歌が好きだった。
コチはチラチラとホリデイの横顔を伺ったけど眩しい光が邪魔をした。
あれだけ多くいた虫たちは、カエルの歌が終わる頃には数匹になっていた。
「いい歌だったな?」
ホリデイが静かに口を開いた。
「なかなかいいだろ?」
コチは平然と答えたが嬉しくたまらなかった。自分が好きなものを褒められるというのは気分が良い。
それが、ホリデイなら尚更だった。
カエルが去った後、これ以上自動販売機の上にいる理由はなくなった。
コチは、カエルの歌を聴いていて思い出した。
カエルが来てくれて、歌ってくれてよかった。
コチは思った。
自分が好きなあの夜にホリデイを連れて行こう。
月がはしゃいで、草むらで下手くそな虫の奏でる音楽が聞こえて、
あの蕾がいるあの場所に
ホリデイを連れて行こう。
「なあ、一体どれが月なんだよ?」
ホリデイは、四方八方に点々と輝く街灯を見ながらコチに聞いた。
「ほら、あそこだよ。自信無さげに空にぽつんと浮かんでいるだろ?」
ホリデイは首を傾げながら「夜には、月よりも輝いているものがいっぱいあるんだな?」
と、馬鹿にするようにコチに言った。
コチは、チラっと月を見上げて、「チェッ」と舌打ちをする。
「いいから、黙ってついてこいよ。」
コチは、ようやくうるさいホリデイと目的地に辿り着いた。
そこは、人間がいない空き地。
動かない時計がかけられた高い建物が見下ろす広大な敷地一面に鬱蒼した草が生えている。
その草むらで姿が見えないが多くの虫が賑やかに歌っていた。
「ここさ。どうだ。ここなら月が一番、輝いて見えるだろ?」
ホリデイは、わざとらしく空を見上げて、初めて月を見たという表情をした。
「へー。あれが月ですか。どうも初めまして。」
ホリデイがわざっとらしく深々とお辞儀している所をコチは静かに微笑んでいた。
ここに、ホリデイがいるなんてとても不思議な気分だった。
「これからは、いつだってあんたを感じる事が出来そうだ。」
コチは月に話しかけるホリデイを見ていた。
「前から知ってるだろ?」
コチは、優しく笑った。夜にはやたらと優しい風が吹く。
ホリデイはここを「月のすみか」と呼んだ。
「そんな名前なんか付けてこの場所に愛着が湧いたらどうするんだ?」
「会いたくなったら、また、この場所に来ればいい。僕達には自由な羽があるだろ?」
ホリデイは言った。
コチはいつもの顔で笑っているホリデイを見ていた。
ホリデイは、この世界を気に入ってくれたのかな?
なんてコチは考えていた。
「それにしても、ジージージーって下手くそな歌だな。」
ホリデイは、月のよく見える一番高い葉っぱの上で隣に座るコチに笑いながら言った。
「そうだろ。こいつら下手くそなんだよ。」
月を見上げるホリデイの羽が揺れる。
同じ風がコチの小さな羽を揺らす。
穏やかなホリデイの横顔が見える。
ジージーと下手くそな歌も慣れれば心地が良いとホリデイは微笑んだ。
「コチ。こいつ特にひどいな。」
ホリデイは、突然歌い出したとびっきり下手くそな一匹の虫の歌を聞いて笑い出した。
「本当だな。」
コチは笑うホリデイの横顔を見ながら、諦める決心した。
「なあ。ホリデイ。そいつどんな顔で歌っているか見に行かないか?」
「おっ。いいね。爆笑コースだな。」
いたずらなホリデイの顔が、月明かりで輝く。
2匹は、月明かりの下をふらりと移動する。
ホリデイが、下手くそな歌に耳を澄ませそれに向かって飛んでいる中、コチは違う方向に飛んだ。
「え、そっちか?」
ホリデイは自分の耳を疑いながらコチを目で追う。
「おーい。見つけたぞ。」
コチがホリデイを呼ぶ。
「ん?そっちじゃないだろ?こいつだろ。」
音痴な虫はホリデイをジッと睨んでいた。
ホリデイは、音痴な虫から離れコチの方に向かう。
「えー、どこだよ?」
「あっちだ。あっち。」
「どこ?」
「ほら、あそこだよ。」
コチが首を振って指し示す方向に、ホリデイはゆっくり進んで行く。
ふわふわと月明かりの下を飛ぶホリデイが何かを見つけた。
それは、音痴な虫ではなく葉が幾重にも重なる下でうずくまる小さな蕾だった。
ホリデイは見つけた蕾に声をかけた。
「やあ。どうも。月がやけに明るいと思ったら君を照らしていたんだね。」
ホリデイの優しい声を聞いてコチはホッとした。
やっぱりホリデイは見つけてくれた。
コチはふたりの声が聞こえなくなる場所まで飛び去った。
「良かったな。」
コチは月にだけ聞こえる声でそっと呟いた。
月はいつもと同じ。
返事をしなかった。
「なんだよ。そこに居たのか?」
しばらくするとホリデイが戻ってきた。
月明かりでもホリデイの羽は十分に輝いて見えた。
そばにやってきたホリデイは何やらニヤニヤとしていた。
「コチ。どこに歌下手な虫がいたんだよ?」
「あれ?いなかったか?」
「それよりもさ。あの草むらの奥に、蕾が顔を覗かせていたよ。」
「俺は花なんか、興味ないよ。」
コチはいつもの調子でホリデイに言った。
「もうすぐ、あの蕾も花を咲かせるな?」
「知らないって。でも、その蕾も良かったな。ホリデイに見つけてもらってさ。きっとあの蕾にも春が来る。」
「それがさ。「また来てくれたのね。」って僕に言うんだよ。僕は、あの蕾を見たのは今日が初めてだ。僕が忘れるはずがない。一体誰と勘違いしているんだか、失礼しちゃうぜ。」
「へー…。じゃあ、ホリデイ以外に誰かがその蕾を見つけたって事か。まあ、間違っても仕方ない。情けない月明かりだし、あそこじゃ、草が覆っているから相手がよく見えないのさ。」
ゆがんだ顔のコチは平然とした声で言葉を並べた。
「ふーん。」
コチは黙ったまま、俯いていた。
静まる空気は、ホリデイの言葉を一つ一つ丁寧に並べた。
「そいつが誰だか知らないけど、蕾は嬉しそうにそいつの話をしていたよ。僕がいるのにさ。」
コチは、俯いたまま、顔を上げない。
ホリデイは月を見上げた。
沈黙が「呼んだ?」と現れる
「なぁコチ。」
コチは黙ってホリデイを見つめた。
「僕って、実はカッコ悪いって知ってるか?」
「なんだよ、突然。俺はホリデイをカッコいいなんて思った事なんてないよ。」
「そんなら、話は早い。僕はカッコ悪いんだ。」
「だからなんだよ。カッコ悪いを通り越して、気持ち悪いぞ」
「言い過ぎだろ。」
「悪い。」
「どうせコチは、花屋での悲鳴を自分のせいだと思っているんだろ?」
「…」
「僕は悲鳴を何度も浴びてきた。僕は意外に評判が悪いんだ。なんせ、ホラ吹き野郎だからね。」
ホリデイはコチを見ずに空を見上げて話し続けた。
「僕は知らないのに、花が急に悲鳴を上げるんだ。会った事もない花が突然僕を見るなり急に叫び出すんだからびっくりするよ。」
「飛ぶ事が怖くなるよな。本当に。」
コチは黙って、話すホリデイの横顔を見つめていた。
「そんな時にコチに会って、僕は自由の羽を手に入れたんだ。だから、もう怖くない。」
「コチは言わないけど、言うんだよ。僕は僕で、それだけでいいんだよって」
「だから、僕もコチには言わないけど言ってるぞ」
「でもさ、間違ったんだ。僕はよく間違える。」
「鳥が夢と時間を運ぶ話をしただろ?その時、コチの目が輝いたんだ。僕は嬉しかった。一緒だって思ったんだ。それで、コチを花屋に誘った。花に人気な僕を見せたら、コチも僕の世界に来てくれるって思ったんだ。」
「カッコ悪いだろ?全部間違っていた。誰かを自分の世界に引きずり込もうなんて、蜘蛛のジジイと同じだ。花の悲鳴を聞いて助かったよ。もうすぐ僕の自由の羽がもげる所だった。」
「僕に少し蜘蛛のジジイの糸が残っていたのかもしれない。きっとあの花屋にも、あの3匹の蝶にも見えない糸があったんだな」
ホリデイは静かにコチを見た。
「コチ、大変だ。しゃべり過ぎた。月夜は何かやばいものが漂っているのか?」
「でも良かった。月の弱い光で、僕の赤面した顔が隠せている。月は優しいやつだぜ。」
「ホリデイ。お前の恥ずかしそうな顔がよく見えるよ。」
「コチ。やっぱり性格悪いな。」
ふふっとふたりは笑った。
「じゃ、あの蕾もきっと最初にきた奴の顔を覚えているな。なぁ、コチ。」
「なんだよ」
「あの蕾には、蜘蛛の糸はない。真っ直ぐコチを見てくれる。きっと僕らと同じ。この月の光の美しさを知っているよ。」
夜風が優しくふたりを揺らす。
「なあ。ホリデイ。俺の太陽の世界でのあだ名を知っているか?」
ホリデイは、笑って言った。
「知ってるだろ?コチに興味ないよ。」
コチも一緒になって笑った。
「木枯らしって、言うらしい。」
「ふっ。なんだよそれ?お前にはジイさんがつけてくれた名があるだろ?誰がなんと言おうとお前はコチさ。それよりも、コチ。虹の居場所を知っているか?」
「虹?なんだよ、急に。」
「悔しいから、あの蕾と僕も約束しちまったんだよ。花が咲いたら、お祝いにこの空に虹を連れてきてあげるってさ。」
コチは目を丸くしてホリデイを見た。
「バカだろ。なんで、そんな無理な約束しちゃったんだよ。」
コチは呆れた様子でホリデイに言った。
「バカって言うなよ。コチもあの蕾も虹が空に駆けるのを見た事ないだろ。木枯らしなんか信じるくらいなら、空に虹がかかる世界を信じる方がよっぽど趣味がいい。」
ホリデイが笑って言うものだから、それが簡単なように聞こえてしまう。
世界が灰色だって言ってれば、きっと誰も君を責めたりしないだろう。
世界が灰色だって言う方が簡単でいいに決まっている。
「おいおい。どうするんだよ。俺は、虹の居場所なんて知らないぞ。」
「じゃあ、願うしかないな。」
「また、勝手な事を言いやがって。願いなんてこんなちっぽけな俺たちに届くはずないだろ。」
ホリデイは笑って答えた。
「僕は信じないさ。」

ホリデイが月の世界に来たのは、これが最初で最期だった。
太陽の世界で、ホリデイは慌てて、コチの元にやってきた。
「コチ。大変だ。月のすみかに、人間がやってきたぞ。早く起きろ。」
コチは、ホリデイのあんな必死な顔を初めて見た。
コチは、世界があまりにも簡単に壊れてしまうなんて知らなかったから、いつものように、言ってしまった。
「俺は、今から、寝るところだ。月のすみかは夜の世界にあるんだ。太陽の世界のことなんて知らないよ。嫌いだって言っているだろ。」
もうホリデイは無理やりコチを太陽の下に連れ出してはくれなかった。
あの通行手形は出してはくれなかった。
そして、コチは、初めてホリデイの悲しげな顔を見た。
「知っているだろ?世界は一つしかないんだ。僕の世界にコチがいて。コチの世界に僕がいる。あの蕾は、今この時も太陽の下で春が来るのを待っているんだよ。」
コチは、ホリデイの悲しげな顔を見て、胸がキリキリと切られるようだった。
「仕方ないだろ。俺は木枯らしだ。」
「お前が信じたものは結局それかよ。」
ホリデイは出て行った。
そして、二度とコチの前に姿を現さなかった。
ジイさんの葉の隙間からチラチラと光が覗く。
「なあ。ホリデイ。お前はどこに行ってしまったんだよ。あの蕾は花を咲かせたよ。とてもよく笑う花だったよ。」
ジイさんの緑の葉が朝のできたての雫でキラキラ光る。
ぽつりぽつりと落ちる水滴、コチが上を見上げると突然ガサガサと上から何かが降ってきて、コチの目の前を通過した。
鈍い音が地面に響く。
「え、なに?」
コチは恐る恐る遠い地面を覗いた。
「なに?」
得体の知らない生き物が頭をさすっていた。
その変な生き物は辺りを見回し、そして、コチの視線に気づき、不思議な事に消えてしまった。
尻尾だけを残して。
「なに?」
尻尾がジリジリとコチのいる老木を登り徐々に近づいて来る。
消えたはずの自分を追いかける視線に違和感を覚えたのか、そいつはやっと自分の尻尾が消えていない事に気づいた。
そいつは急いで尻尾を消した。そして、今度は尻尾以外の体が浮かび上がった。
「なんて、変なヤツだ。」
コチは、そのへんてこな生き物からいつでも逃げられるように身を構えた。
へんてこな生き物は見られている事に気が付いて再び慌てた。
「もう。なんなんだよ。私の体は!」
突然へんてこな生き物は嘆いた。そして、逃げようとするコチを呼び止める。
「ちょっと待て。ちょっと待てくれ。逃げるな。逃げるな。」
「なに?俺に言ってるの?」
コチはそのへんてこな生き物に言った。
「君しかいないだろ。君も自分が消えているとでも思っているのかい?私は君に用があるんだ。まあ、こんな形で会うとは思っていなかったんだけどな。なんかこう、もっとこう、あれだ。スマートにやるはずだったんだ。まあいい。」
「じゃん。」というとそのへんてこな生き物は全貌を現した。
まあ、尻尾以外が見えていたんだからコチは何も驚きはなかった。
コチは微動打にしなかった。
「なんだよ。もっと驚いてくれよ。君にはサービス精神ってものがないのかい?」
コチは黙ったままそのヘンテコな生き物に冷たい視線を送っていた。
「はい。じゃあ。仕切り直しです。さあ、私は一体誰でしょう?わかるかい?」
コチは疑わしそうな目をして静かに首を振る。
「そう。私は、カメレオンだ。でもこれは本当の姿ではない。騙された?まあ、焦るなって。ここからが本番さ。これは私の仮の姿。本当は、一体何でしょう?」
コチは静かに首を振る。
「難しいかな?じゃサービスヒントだよ。『お待たせしました。』もう分かっちゃったかな?」
コチは黙ったままカメレオンに冷たい視線を送っていた。
「おいおい。嘘だろ。どれだけ勘が鈍いんだよ。ヒント2だ。『それは君だけが知っている事だ。』はい、もう一回聞くよ。私は、一体何でしょう?」
コチは静かに首を振る。
「また、また。ご冗談を。」
「だから、知らないよ。しつこいなお前。早くどこかに行けよ。」
「失敬だな、君は。君が呼んだんだぞ。」
「だから知らないって、何かの間違いだろ。」
「おい。嘘だろ。じゃあ私はどうなってしまうんだ。このままじゃ、本当に消えていなくなってしまうのかい?おい。君。ちゃんと真剣に考えてくれているのか?」
コチは、まじまじとそのカメレオンを見つめて、ゆっくり首を傾げた。
「だから嫌だったんだ。私は反対したんだよ。なんでこんなちっぽけな虫のために・・」
カメレオンはイライラした表情で、ちっぽけな虫を見ていた。
「もうお前いいから、どっかに行けよ。」
イライラしているのは、コチも同じだった。
カメレオンは、観念した様子でちっぽけな虫に言った。
「じゃあ、鈍い君に最大のヒントをあげる。こんな事滅多にないからね。スペシャルサービスだ。『君の願い』は、なんだい?」
願い?コチは、改めてカメレオンに不審な眼差しを送っていた。
まるで、怪しい蜘蛛の巣に誘導されているような気分だ。
空ではチカチカと太陽がほくそ笑んでいる気がする。
甘い言葉の裏にある危険は知っているつもりだ。
「わかった、わかった。俺を食べるつもりかい?残念ながら俺は不味いらしいよ。だからさ、他に行った方がいい。」
そう言って、コチはカメレオンから距離をとって、老木の葉っぱの茂みの上の方へと飛んで行った。
コチが下にいるカメレオンを覗くとカメレオンはまた尻尾だけになっていた。
尻尾がまたコチの方に近づいてくる。
変身がへたくそなカメレオンは、しつこかった。
「おい、また、尻尾が消えていないぞ。」
コチは、呆れた様子でカメレオンに言った。
「あっ」とカメレオンは、消えていない尻尾を確認した格好の全身が現れたかと思うとそのまま足を滑らせ地面に落ちていった。
ひゃっはー。
コチは、落ちたカメレオンを見て腹を抱えて笑った。
「見ろよ。ホリデイ。」
太陽の下で笑う時にはいつもホリデイが隣にいたから、ついついコチは口を滑らせた。
コチはすぐに訂正するようにジイさんに話しかける。
「今の見た?ジイさん。間抜けな奴だな。あいつ一体何者なんだよ?」
ジイさんは答えず黙ったままだった。小鳥がチュンチュンと緑に隠れて鳴いている。
緑に移りゆく光が流れていた。
気がつくと、頭をさするカメレオンの周りには一定の距離を置いて多くの鳥や虫たちがその周りを取り囲んでいた。
なぜなら、カメレオンは人間の作る趣味の悪いネオン街のように頭をさする動作に合わせてチカチカと全身が色取り取り色を変え発光していたのだ。
カメレオンは集まる視線を感じ「はっ!?」と再び姿を消した。
尻尾だけを残して。
カメレオンは尻尾にたくさんの視線を集めて再び老木をよじ登りながらどんどんコチに近づいてくる。
コチは、近づくカメレオンの尻尾とそれを追いかける多くの視線を察知しぎょっとする。
「待て。待て。待てよ!来るなって。」
コチはなんとか突進する勢いで近づくカメレオンを必死に止めようとするがその術は思いつかない。
ここにあんなにたくさんの生き物が集まっていたのかという程に、カメレオンの動向を多くの観衆が見守った。
「分かった。願い。願いだろ?ホリデイだ。ホリデイを探してくれ!それが俺の願いだよ!」
コチは叫びながらカメレオンに願いを伝えた。
するとピタっとカメレオンの足が止まった。
正確には尻尾が止まる。
「ホリデイ?」
宙に浮いた尻尾が聞き返す。
「そう。ホリデイだよ。白い蝶だよ。そいつを探してくれ。」
尻尾はくるくる巻いた尻尾を伸ばしたり巻いたりを繰り返していた。
「そう。」
きっと、ぽりぽりと頭を掻いているのであろうカメレオンは「はーい。ご注文承りました。」と言って本当に消えた。
「なんなんだよ。あいつ。」
コチはそのままカメレオンの消えた跡を見つめていた。
そして、視線を感じた。
まだ多くの観衆がカメレオンがいたその跡を見つめていた。
3羽の小鳥が我先にとカメレオンの尻尾が消えた場所に詰め寄り不思議そうに観察を始める。
コチは見つからないように息を殺して小刻みに足を動かし薄暗い木陰に移動した。
「あいつ。本当にホリデイを見つけてくれるかな?」
コチはジイさんに聞く。
ジイさんは優しく緑を揺らした。
「ホリデイはまだあの花に会いに行っていないみたいなんだ。おかしいよな?ホリデイは絶対に行くべきなんだよ。あの花の笑顔を近くで感じることができるんだから。世界がひっくり返るような笑顔なんだよ。」
ジイさんは優しく頷く。
木漏れ日が、やたらとコチを覗く。
コチは、何度も影に体を移動した。
いつの間にか太陽が赤く燃え西の空に沈もうとしていた。
結局、今日もホリデイはやってこなかった。
コチはじっとしていたせいで固まっていた体をほぐしながらいつものようにジイさんに今日の出来事を聞いていた。
ジイさんはゆっくりと風に揺れながら優しく話す。でもジイさんの言葉が耳に入らない。
なぜならコチの心がソワソワしていたからだ。
太陽が世界から完全にいなくなるとコチの心臓の鼓動はうるさいくらいにドンドンと鳴っている。
いつもいるかいないかわからないのに肝心な時はやけにその存在を主張してくる。
コチは心臓の鼓動を無視しなるべく自然に身支度を整える。
そう。
正直に頭の中を開けば頭の中はあの花でいっぱいだった。
夜ならまたあの花に会いに行ける。
だからソワソワしている。
でも、それを簡単に認めないのがコチだ。
コチはいつものように夜の散歩に出かける。
月の光がコチの道標だ。
街灯の光は中継地点。
月が雲に隠れてサボったりしていると跳ぶ方も気が気じゃない。
道に迷ってしまう事があるからだ。
夜の散歩だって危険がいっぱいある。
一番厄介なのは人間の住処に入ってしまう事。
人間の住処に入ってしまって戻れなくなった奴はたくさんいるらしい。
自動販売機の顔も知らない奴が語った事だからあてになるかはわからないがそいつが人間の住処から戻ってきた話を聞いた事がある。
もちろんそいつの実体験かは怪しいところだが、聞いた時は身震いした事を覚えている。
はて、そいつはどうやって戻ってきたっけ?
だから、夜の散歩だって真面目に取り組まないといけない。考え事なんてしていたら人間の住処の光に飲み込まれてしまう。
コチは、大丈夫。いつもと変わらない。
いや、平然を装っているだけだ。
頭の中は、あの花の事でいっぱいだ。
「ギャー」
闇をつんざくような悲鳴が聞こえると、コチは眩しい光に包まれた。
強い光に視界がぼやけているコチは下で悲鳴を上げうごめく2体の大きなボヤっとした塊をなんとか捉えようとしていた。
慌ただしい動きだ。
徐々に視界が戻ってきて、コチは愕然とした。
やってしまった。
ボヤっとした大きな塊は徐々に輪郭を捉え人間を映し出した。
どうやら、コチは人間の住処に入ってきてしまったらしい。
悲鳴を上げた人間は、蛍光灯に止まるコチを憎々しく睨んでいた。
そして、あたりを見回し雑誌を手にするとまだ読みかけだったのかその雑誌を再び机に戻し、新たな武器を探し回った。
身の回りには、程度の良い武器は落ちておらず、叫び声を上げた高い声の人間は低い声の人間に怒りをぶつけながら武器を探すように促した。
渋々、ソファから立ち上がる低い声の人間は別の部屋へと消えていく。
相手が一人になるとコチは今だと羽を動かした。
月を目指せ出口はそこだ。
コチは必死に羽を動かした。
とにかく早くここから出ないといけない。
何度もコチは月に頭をぶつけた。
何度頭をぶつけても人間の住処から出ることできない。
コチ、それは私じゃなくて蛍光灯だ。
窓の外で心配そうに月が覗くがコチはまだそれに気がつかない。
コチが必死に羽を動かすたび高い声の人間は甲高い悲鳴を上げた。
その奇声はコチにここにいてはいけないという思いを強くし焦らせた。
何度も頭をぶつけるがコチは蛍光灯の存在に気づかない。
そして、慌てた様子でもう一人の人間が武器を持ち戻ってきた。
チラシの束を丸めた武器を誇らしげに掲げたが、声の高い人間の評価は低かった。
声の高い人間の指示のもと低い声の人間はその武器をコチ目掛けて振り下ろす。
及び腰で放った一発はコチを捉えることは出来なかった。
高い声の罵声が轟く。
コチはほっと肩を撫で下ろした。
「お前。そこで何やっているんだよ?」
コチは月に言った。
お前だろ、と月は思ったに違いない。
コチはやっと窓のカーテンの隙間からコチを見つめる月を見つけた。
コチはすぐに窓を目指した。悲鳴が鳴り響く中、コチは飛び、カーテンの隙間を通り抜けて、そして再び頭をぶつけた。
窓はすでに閉められていた。
透明な窓ガラスを這ってみても、出口はなかった。
そして、気づけばコチはいつの間にか人間の目線の高さにいた。
「次は外すなよ!」と訴えかける高い声のプレッシャーを背中に浴びながら、大きな人間は武器を片手に振り上げ、コチにそーっと近づく。
コチはカーテンの後ろに移動した。
姿を隠したコチに向かって、逃がさぬように人間はカーテンの上から何度もチラシで作った武器を振り下ろした。
バンバンバンと部屋に鈍い音が響きわたる。
窓の外から、月が心配そうに覗いている。
「カーテンが汚れるじゃない!」
きっとそんな事を言ったのだろう。
冷静さを取り戻した人間は武器を捨て恐る恐るカーテンをめくった。
コチの姿はなかった。
何度も叩いたところを確認するも、潰れたコチの姿はなかった。
ガミガミと苦言をいう高い声を背に低い声の人間はできる限りのことはやったと不貞腐れながらソファに座りリモコンを手に取り、テレビのチャンネルを変えた。
殺伐とした空気をテレビの賑やかな音が濁らせた。
コチはソファの横にある小さな部屋にいた。
部屋と言っても格子状の柵で覆われた小さな檻だ。
コチはそこから人間の行動を見守った。
狂ったようにカーテンを叩き続けた人間。
もちろんカーテンが憎かった訳ではないことくらいコチには分かった。
怯えたようにカーテンを覗く人間。
本当に怯えているのはコチの方だった。
こんな小さなコチの存在も許してはくれない人間。
何者の侵入もこの住処では許されないのであろう。
とりあえず、今、目の前の危機は乗り越えたようだった。
ぎくしゃくした二人の間の空気はまだ危機的な状況かもしれない。
なんとか落ち着きを取り戻しコチが辺りを見回すと見たこともない生き物と目があった。
今日は得体の知らない生き物とよく会う日だ。
この檻はこいつの部屋なのか、そいつは、怯えたように檻のすみで震えながらコチを見ていた。
だから、怯えるのははコチの方だ。
そいつは、長い耳をピンと立てこちらを伺っている。
人間はこちらの様子には気づいていないようだ。
コチが少し羽を動かすとそいつはビクンと動き、助けを求めるかのように檻をカリカリと叩いた。
コチは人間に気づかれないようにそっと身を隠す。
カリカリと音を出すその必死な生き物に対して人間は知らん顔。
「助けてくれ」とカリカリと檻がなる。
「ポン太!」
人間がポン太にうるさいと一括した。
ポン太は、この生き物の名前らしい。
ポン太はそれでも檻を叩いた。
「俺が、でかい図体したお前を食べるとでもいうのか?」
ここにいる連中は、小さいコチに対して過大評価しすぎる。
うるさいポン太に対して、カランと餌箱にクッキーが投げ落とされた。
求めていた事はそんな事ではない。
コチでもそれはわかった。
どうやら、ポン太は人間と話す事ができないようだ。
コチは、ようやくほっと一息つく事が出来た。
ポン太はきっとこちらに危害を加えてはこない。
あんな怯えた生き物はさすがに見た事がない。
ポン太は、カリカリする事の無意味をようやく悟ったようだ。
じっとコチを見つめ、落とされたビスケットをちらっと見た。
怯えていても食欲はあるようだ。
だんだんとポン太の視線はコチよりも餌箱に転がったビスケットに時間を注ぐようになり、ポン太は恨めしそうにコチを見つめるようになる。「食べたきゃ食べればいいだろう。」とコチは思う。
いるだけで加害者になる事にはとうに飽き飽きしているつもりであったが、やっぱり腑に落ちない。
でもコチはポン太の視線に嫌気がさし、がビスケットを取れるように少しづつ餌箱から離れるようにゆっくり移動した。
慎重に移動しながらも少しでも羽を動かすものなら、ポン太は後ろに仰け反りながら驚くものだから、少しの距離の移動も大分時間がかかる。
でもポン太から見えないところまで遠くに行けばそれはそれでポン太を不安にさせるだろう。
見えない恐怖っていうものはコチも理解している。
しかし、どうしてここまでポン太に気を使わなければならないのか、コチが離れ、動かないか疑いながら何度もコチの様子伺うポン太はのそりのそりと餌箱に近づきビスケットを咥えてすぐに檻のすみに戻った。
そして、すぐに鋭い目でコチの位置のズレを目で測り、動いていない事を再確認。
ビスケットを一口だけかじった。
ビスケットの味により少しだけ落ち着いたのか、ビスケットをかじりながらポン太の耳が少し垂れ身体の強張りが抜けていくのがわかった。
少しするとコチの耳に鼻歌が届いた。
もちろんコチの知らない歌だ。
ビスケットをかじりながら鼻歌を歌うのが、ポン太のいつもの癖なのだろう。
自然と歌っていたポン太は何かを思い出したのか、突然停止した。
ポン太は鋭い目でコチを再確認すると、動いていない事を知り、また、ご機嫌に歌い始めた。
少しでも動く事に気を使うこの場所でコチはどうやってここから抜け出すかを考えた。
そういえば自動販売機の上で話していたあいつは人間の住処からどうやって抜け出したのか?コチはやっぱり思い出せなかった。
情報があっても肝心な時に出てこない。
自動販売機から生まれた話はどうも肝心なことがボヤける。
ポン太の檻からはテレビと月がよく見えた。
透明なガラスの向こうにある月、もう一つガラスの向こうからは賑やかな映像と音が漏れる。
月はとても遠くに行ってしまった気がした。
格子状の檻はなんだか蜘蛛の巣を思い出した。
でもあの時とは、少し違う。
コチはどこかで何とかなるって思えた。
少しホリデイの楽観主義が感染したのかもしれない。
またどこかでホリデイが現れる気さえした。
「ホリデイはいなかったぜ。」
突然声がした。
すると、再び尻尾が現れ徐々にカメレオンの全貌がコチの前に姿を現れた。
カメレオンは、人間とポン太が観る華やかなテレビの前に齧り付いた。
どこか、憧れの表情だ。
カメレオンは少ししてため息をついた。
カメレオンはとぼとぼとコチに近づく。
ポン太と人間には、見えていないのだろうか?
いや、そもそも人間はテレビを見ず自分の掌ばかり見ていたし、ポン太はテレビの内容に集中していた。ポン太はコチをチラッと見ては、テレビ番組の内容に置いてかれないようにしがみつくように見ていた。
「ホリデイがいなかったってどういうことだよ?」
「いないっちゃ。いないって事だろ。そんな事より、君、嘘ついただろ?君の本当の願いは、ホリデイを探す事じゃないだろ?」
カメレオンは、うんざりした顔でコチに聞いた。
「願い、願い、ウルサイな。俺の願いは見ればわかるだろ?ここから出してくれよ。」
カメレオンに負けないくらいうんざりした顔でコチは言った。カメレオンはキョロキョロと周りを見渡す。
「それは君の本当の願いじゃない。勘違いはするなよ。私は便利屋じゃないのよ。ホリデイの件はサービスだ。でも、もうこれ以上は無理。君は見ようとしていない。そんな君には付き合いきれないのよ。」
呆れた様子のカメレオンにコチは苛立ちながら答えた。
「知らないよ。お前が勝手に俺の前に現れたんだ。それよりもホリデイは一体どこに行ったんだよ?」
カメレオンはコチの質問に答えることなく再び消えた。
「あ、また消えやがった。」
もう驚くことはなかった。そんな事より目の前に映るテレビの方がよほど信じられない光景だ。
「ホリデイがいないだって?あいつ勝手な事ばかり言いやがって。」
窓越しに見上げた月はただコチをまっすぐ見つめていた。
「おい。やめろ!やめろ!くそっ。またあの野郎チャンネルを変えやがった。まともに見ていないくせによ。」
見た目に反してうさぎのポン太は口が悪かった。ポン太はニュースには全く興味がない。
なぜなら、ニュースを知ったところでうさぎにとっては何も意味のない事だからだ。
人間の片手にあるリモコンのボタン一つで、テレビ画面が切り替わる。
どこの世界も、人間の都合の良いようにできている。
「おい。CMだぞ。チャンネル変えろよ。」
うさぎは、懸命に人間に訴えるが、人間は聞く耳を持たず中身の無くなったグラスを片手にソファを離れる。
ポン太はテーブルに置かれたリモコンに悲痛な眼差しを送るが羽のないリモコンはじっとしたままだった。
テレビ画面はあのリモコンが支配している。
あのリモコンさえあれば、この世界はポン太の物でだ。
「なんだよ。ドラマの続きを観せろ。馬鹿野朗。」
口の悪いうさぎは「あーあ」と言いながら、背筋を伸ばした。
そして、何気なく餌箱に近づいて行くとようやくコチの存在を思い出した。
はっ、とコチの方に目をやるとコチは先ほどの位置から動いていなかった。
死んだ?
少しホッとしたポン太は動かないコチに小声で話しかけた。
「おい、お前。死んだのか?」
コチは何も答えなかった。ポン太がそーっとコチに近づいてくる。
コチはじっとその動きを観察していた。
近づくポン太がコチの許容範囲を超えてきたところでコチは羽を少しだけ動かした。
それを見たポン太は、仰け反りながらコチから一番離れた檻の隅に必死な形相で逃げて行った。
「騒々しい奴だ。」ホリデイがここにいたのならきっとこの状況も笑えるのだろうが独りぼっちのコチにはこのうさぎは、鬱陶しいだけだった。
再び「助けて」とカリカリ檻をひっかくうさぎに人間は目もくれなかった。
コチがすでに飽き飽きしているようにこの臆病もののウサギに人間も飽き飽きしているのだろう。
普通見たことない同士はお互い警戒するものだ。
知らないってことは恐怖だ。
でも逆手に取れば、時に自分を怪物に変えることだってできる。
だから、簡単に逃げてはいけない。
自分は怪物なんかじゃないってことが、すぐにバレてしまうからだ。
ポン太は怪物ではないってことをすぐに教えてくれた。
全く馬鹿正直なやつだ。
馬鹿正直が怯えた声でコチに言った。
「おい。お前いつまでそこにいるつもりだ。」
声は震えていたが、口調は相手より優位に立ちたいと強がっていた。
コチは、ポン太の声を無視した。
答えた所でコチにとっては何の得はないだろう。
「僕があの二人にお前の居場所を教えてやってもいいんだぞ。そしたらお前はあの世行きさ。早くここから出て行った方がいいぞ。」
コチは、何度も人間にコチの居場所を知らせようとしていたポン太を見ていた。
ポン太は正直者だ。
嘘がすぐに分かる。
「きっとここが一番安全だ。」
何も答えないコチに対してポン太は喋り続けた。
「分かる?ボクガ、ニンゲンニ、ツタエル。」
今度は身振り、手振り合わせてコチに言った。もちろんコチは何も答えない。
全く動かないコチを見て、だんだんとポン太の耳は垂れ下がっていった。
「ここは僕の部屋なんだ。勝手に入るのはマナー違反なんだよ。年頃の女の子だったらパパにブチ切れているぞ。」
ポン太は徐々に体勢を変え、いつものポン太のスタイルなのであろうだらしなくその場に寝転がって、話を続けた。
「窓は閉まっているから外にはいけないだろ?残念。僕がオススメする場所はあそこだよ。」
ポン太はテーブルの上のリモコンを指した。
「僕ならあそこに行く。そうすれば好きなテレビ番組が見放題だ。なんで僕はこんな狭い部屋に閉じ込められているんだ?」
ポン太の話はコチを無視して勝手に進んだ。
「お前はどこから来たんだ?」
「ガラスの向う側にはさ。お前みたいな奴がいっぱいいるのかな?あー嫌だ。嫌だ。反吐が出るね。」
コチは何も答えなかった。それでもポン太は話を続ける。「月はこんな気持ちなのだろうか?」とコチは思った。
「僕はすごい所から来たんだよ。お前に教えてやろうかな?どうしようかな?知りたい?仕方ないな。教えてやるよ。」
黙ったままのコチに対してポン太は容赦なかった。
コチは今ままで月に言った数々の発言を振り返り謝罪したい気分だった。
ポン太に「結構です。」と一言伝えれば黙ってくれるだろうか?きっとまた鬱陶しく慌てふためく。
それもまた煩わしい。
「きっとお前も驚くぞ。僕がこんな所に好き好んで住んでいるとでも思ったか?おいおい。やめてくれよ。僕には帰るべき故郷があるんだよ。」
イライラする。「こんな時どうすればいい?」そう思ってコチは月を見上げるとポン太の声が聞こえる。
「月から来たんだ。」
思わずコチは月を二度見した。
「さあ、どうする?」
聞いてもいないのにポン太は、自分は月から来たんだと言った。
ポン太は正直者だから嘘を付いている訳ではないらしい。
嘘ならすぐに分かってしまうからだ。
詳しい話を聞きたがったがポン太自身、故郷の事をあまり覚えていないらしかった。
故郷の事は人間から聞いたのだと。
怪しい。
でも・・。コチは昨夜の事を思い出し、キュッとなった。
コチは夜空を見上げるがポン太はうるさく話を続けた。
鬱陶しい。
動かず何もしてこないコチを気に入ったのか、ポン太は、独りで話を続けた。
今、テレビで流れていたドラマの話。
ここに住む二人の人間の癖や二人の関係。
気が付いた時には、気持ちよさげに身振り手振り話している。
ずっと話し相手を探していたかのようだ。
「僕は、ビスケットが大好きなんだ。ここにある餌はどうも口に合わない。食べられない事はないのだけれど、あえて残すんだ。そうすれば心配した人間が僕にビスケットをくれるからね。」
突然、ポン太が、テレビを見ろと言った。
「これこれ。」
ポンタは鬼の首を取ったような顔をしてテレビ画面に集中していた。
テレビ画面にはコマーシャルが流れていた。
そのコマーシャルはスプレー缶から噴射された煙が部屋いっぱいに充満し、目をバッテンにした様々な虫が次々と死んでいく様をとてもコミカルな描写で描いていた。
殺虫剤のコマーシャルだ。
「一撃噴射。これでイチコロだ。」
そのコマーシャルを見てポン太は笑いながら勝ち誇っていた。
いつの間にか部屋の電気が消され夜になった。人間はこの部屋から出て行きポン太はイビキをかいて寝ている。
太りすぎだ。
コチはそーっとポン太の檻から抜け出した。
そして、部屋の窓に近づき、カーテンの隙間から、月を覗いた。
「なあ。ホリデイを見なかったよな?」
今にも窓の外にホリデイが現れるんじゃないか、なんて思ってしまう。
開かない窓ガラスにペトっと張り付いたままどれくらいの時間が経っただろうコチはじっとしていた。
じっとしている事に苦痛があるはずがない。
太陽がいる世界ではじっとする事に慣れていたから。
自分はこの世界には存在していないかのように。
自分が動かなくても勝手に時間は流れた。
世界は光輝いていた。
遠い昔、羽が欲しかった。
春を運ぶ喜びの羽。
遠い昔の記憶さ。
もうどこかで無くしたよ。
広げた羽は悲鳴を残した。
花屋の花の悲鳴が聞こえる。
人間の悲鳴が聞こえる。
月のすみかで咲く花の悲鳴が聞こえる。
ホリデイになんか会わなければ良かった。
あの花に会わなければ良かった。
月はもう遠く離れていた。
「嘘です。」
コチはボソッと言う。
「それだけは無くさないで。」
じっとしている事に苦痛はないなんて嘘である。
うるさい音で目がさめた。
窓の外が明るい。
いつの間にか窓に張り付いたままコチは眠ってしまったらしい。
窓の外には人間の住処が広がっていた。
こうやってみるとほとんど人間の住処だった。
コチが窓から見える景色を眺めているとコチの瞳に知っている何かが映った。
ドクンと胸が騒ぐ。
「嘘だろ?」
コチが愕然とその光景を見ていると窓ガラスにゆっくり近づいてくる人間の顔が映った。
気づくと人間は先ほど届いた朝刊を丸めて作った武器を振り上げていた。
まだ読んでいない朝刊だと一瞬躊躇したのかその隙をコチは見逃さなかった。
ここで、死ぬわけにはいかない。
早くここから出ないとあいつがあの場所で暴れている。
バン。
鈍い音が部屋中に響き渡る。
窓ガラスが震えていた。
恐る恐る人間が丸めた朝刊の先を覗いた。
人間がふり下げた朝刊は、また、空振りだった。
再び、ポン太の檻に逃げてきたコチ。
動いたコチを見て、寝起きのポン太は慄いた。
「また、お前か、いい加減にしろ。」
ポン太は昨夜と変わりすぐに落ち着きを取り戻した。
ポン太にとってみれば一晩中話をした仲だった。
こちらが何もしなければコチは何もしてこないということをようやく理解したのだ。
コチは再び窓へ向かうか躊躇する。
まだ、人間は窓の近くでコチを探している。
もう一度外を見たい。
砂けむりの間から止まった時計のかけられた崩れかかた建物が見えた。
コチは悪いイメージを払拭しようと首を振る。
違う違う。あそこは月のすみかなんかじゃない。
ガガガ、と破壊音がガラス窓を貫き部屋に響き渡る。
あの眠っていた大きな機械が目覚めあそこで暴れている音。
コチは再び首を振る。
窓の下に置かれたソファで朝刊を読まず掌の中ばかり覗く人間。
コチは「早くどっかに行け!」と言葉を漏らした。
「え?」
ポン太が怪訝そうに顔を歪めてコチを見た。
「お前。なんか言ったか?」
言葉が聞こえるのか?コチは駄目元でポン太に言った。
「なあ。この音は何の音だ?」
ポン太は口をあんぐり開けて口からビスケットをポトリと落とした。
「しゃべった。」
ポン太は辺りを見回すがそこにはコチしかいなかった。
「おい。ポン太聞いてるか?」
コチの苛立った声にポン太の体がビクリと動く。
「え、ああ。あちらのテレビの音の事ですか?」
ポン太はテレビを指差しながらコチに言った。
「違う、違う。窓の外から聞こえる音だよ。」
ポン太の体がもう一度ビクリと動く。
「ああ、外ですね。」っとポン太は頷き、コチに恐る恐る教えた。
「あれは工事の音だと思います。」
「工事ってなんだよ?」
コチはすぐに聞き返した。ポン太は一瞬何かを考えて咳払いした。
「ねえ。それよりも君さ。喋れるの?」
「いいから答えろよ。工事ってなんだよ。」
コチの勢いにポン太の耳がピンと逆立つ。
「工事って、何かを壊したり、作ったりする事だろ。お前、そんな事も知らないのかよ。」
ポン太は少しだけ刃向かってみた。
「その工事ってやつはいつ終わるんだ?」
「そんな事を僕が知るわけがないだろ?ここ数日、朝から夕方までずっとこの音さ。おかげでテレビの音が聞こえないのよ。嫌になっちまうだろ?」
ポン太がちらりとコチを覗くとコチのとんでもない落ち込みようにびっくりした。
「そうか、お前もテレビ観たかったよな?」
コチはポン太の言葉に何も反応しなかった。ポン太はどう慰めて良いのかわからないでいた。
「なあ、元気出せよ。僕のビスケットほんのちょっとなら分けてあげるぞ。」
ポン太はビスケットを削りカスほどに小さく割ってコチに差し出した。
コチは反応しなかった。
今、コチの頭の中でグワングワンと轟音が鳴り響いていた。
そして、轟音と砂煙りの中を必死に耐える花の顔が頭をよぎる。
花は、「ここには誰もこない」と言った。
来るのは人間だけだと笑って言った。
「誰が来るんだよ。」
コチは、何度も自分を責めた。
どうして、あの化け物が、もう動かないなんて思ったのか。
他の誰かがきっとあの花を見つけてくれるなんて思ったのか。
自分が傷つかないように。
そう思い込んだのは、全部、自分の為だった。臆病な自分の為だった。
「なあ。食べないのかい?僕、全部食べちゃうよ。」
ポン太は、すでにビスケットを平らげていた。
最初から、自分だけで食べる気だったのだろう。
今、コチはポン太を見つめる。
そして、頼りないポン太に必死に伝えた。
「ポン太。助けてくれ。」
ポン太は戸惑った表情で首をかしげる。
コチはポン太に工事現場で咲く花の話をした。
なんとか伝わってほしいと正直に自分の思いを話した。
だからここから出る方法を教えて欲しいとポン太に必死に頼んだ。
冷静に考えればポン太に花の話をした所で「だから?」と聞き返される事などすぐに想像できたはずだろう。
ポン太は、なぜか、その花の話を泣きながら聞いていた。
ポン太は涙を拭いて、コチに教えてくれた。
ここに住む人間の「みっちゃん」と呼ばれる人物がひどい花粉症でこの時期なかなか窓を開けないという。
そんな中、この家に侵入してしまったのだからコチはひどく運が悪いという。
「あの日はもう一人の「ひー君」がとても臭いオナラをしたもんだから仕方なく窓を開けたんだ。そしたら君が入ってきたからめちゃくちゃ「みっちゃん」は怒っていたよ。「みっちゃん」は何よりも虫が嫌いなんだよ。」
ポン太はコチに少し気を使ったのか「僕はあそこまで君を嫌いじゃないよ。」と補足した。
「玄関まで行ければいいが、そこに行くまでにまだ扉があって、几帳面なみっちゃんは、必ずその扉を締めるんだ。「ひー君」がいれば開けっ放しにして「みっちゃん」にいつも怒られているから、チャンスがあったんだけどな。「ひー君」はもう仕事に出かけたよ。使えない奴だな。」
ポン太は、なんとか、コチを外に出そうと考えてくれた。なかなかいい奴なのかもしれない。とコチが考えているとポン太がコチに言った。
「きっとその花はコチに会ったら喜ぶだろうな。」
コチが黙っていると奥からガチャっと音が聞こえた。外出していたみっちゃんが、帰ってきたらしい。みっちゃんは部屋に入るとバタンと扉を閉めて、買い物袋をテーブルの上に置いた。
「ほらね。」ポン太は悔しい顔をした。
でもすぐに何かを思い出したように表情を変えた。
ポン太は、テーブルの上に置かれた袋をまじまじと見る。
ポン太はその袋の中にビスケットがあるか確認するのが日課だった。
ポン太がビスケットではない何かを発見した。
「おい。コチやったぞ。あれ見ろよ。」
買い物の袋の中出てきたのは、テレビコマーシャルで見たあの殺虫剤だった。
「おい。嘘だろ。死んじまうじゃねえか。」
慌てるコチをポン太が落ち着かせる。
「落ち着けよ。」
「裏切り者!」
「だから、落ち着けって。これはチャンスなんだ。」
ポン太はコチを落ち着かせ、脱出作戦をコチに聞かせた。
人間が買ってきた殺虫剤は、部屋全体を毒の煙で多い。
その部屋にいる全ての虫を殺してしまうものだった。
聞いているだけでコチは恐ろしくなったが、その煙は、もちろんポン太の健康にもよろしくないから、その煙が発射される時、ポン太の檻はきっとベランダの外に出される。
だから、このまま檻の中で隠れていればコチは外に出られるんだと言った。
「間違いない?」
コチは不安そうにポン太に言った。
ポン太は自信に満ちた表情で頷いた。
この殺虫剤は以前もこの部屋に撒かれたから間違いないとポン太は言った。
以前もその毒ガスがこの部屋で撒かれたと思うとコチは背筋が凍る思いだったがコチはポン太のこの作戦を信じてみようと思った。
「いつアレは部屋に撒かれるんだ?」
コチはまだ不安そうにポン太に聞いた。
「すぐさ。それだけコチは嫌われているんだ。」
嬉しそうにそう言うポン太に悪気はないのだろうが、コチは複雑な気分だった。
「ほら、みろ。始まったぞ。いよいよ作戦開始だ。」
みっちゃんはポン太の言った通り、早々に殺虫剤の準備に取りかかった。
嫌われ者も時には役に立つとコチは思った。
みっちゃんの準備は着々と進められ、慣れた手つきで外に出すもの封をするものと仕分けられ部屋は完全に締められた。
隙間ひとつない。
そして、思いがけないことが起こった。
みっちゃんは、ポン太を部屋に残したまま、殺虫剤の煙を噴射しそのまま外に出たのだ。
「嘘だろ?」
ポン太は、蒸気をあげる煙を見ながら呆然としていた。
「おい。お前の作戦、どうなっているんだよ。おい。」
焦るコチは、煙を見ながら叫んでいる。
「こんな所で死ねないんだよ。」
呆然と煙を見つめるポン太の耳に叫ぶコチの声が届く。
やっと現実を見つめたポン太は必死で何かを考えていた。
そしてコチに言った。
「僕に掴まれ。」
コチは急いでポン太の胸の中に飛び込んだ。
ポン太は以前、脱走した日の事を思い出したのだ。
「すぐ出してやるからな。」
檻の天井は空いている。
ポン太を狂ったように何度も飛び上がり檻に体をぶつけた。
左右に揺れる檻はバランスを崩し、鈍い音をたてて横に倒れた。
ポン太はコチを抱き寄せ、檻の中から飛び出した。
そして、隣の部屋に行くための締め切られた引き戸を必死の思いで引っ掻く。
「チクショー。僕の事を忘れやがって。」
ポン太は泣きながら、引き戸を引っ掻いた。
「コチ。しっかりしろよ。大丈夫だからな。」
ポン太に掻き毟られた引き戸の隙間があいた。
ポン太はその狭い隙間に顔を無理やりねじ込ませ、隣の部屋に入りこむ。
煙はもくもくと隣の部屋まで入ってきた。
「花粉は大丈夫?」
どうでも良いことがポン太の頭をよぎる。
ベランダのドアが開いていたのだ。
「おいコチ。見ろ。開いているぞ。ほら、行け。」
「よし!きた。」
コチは、開いた窓の隙間に飛び込んだ。
そして、弾かれた。
網戸だ。
コチは何度も窓の外に出ようと試みたが、網戸の網に弾かれた。
「コチ。任せておけ。僕のビスケットで鍛えた前歯がある。」
隣の部屋から、もくもくとターゲットを追って煙が入ってくる。
そんな中、ポン太は必死に網戸をかじってくれた。
それも脱走を企てたあの日以来だ。
脱走を企てたあの日、あの時は、みっちゃんから小便ちびるほど叱られたらしい。
「大丈夫だ。」というポン太の目が少し怯えていた。やっと網戸が切れた。
「ほら、行けよ。」
ポン太とのサヨナラがふらりとやってきた。
ガチャンと大きな音がした。
人間が急いで戻ってきたようだ。
「やっぱりね。僕が忘れられるはずがないんだ。」
安堵の顔を浮かべるポン太は破れた網戸を見て再び顔が引きつった。
きっとまたみっちゃんに怒られるのだろう。
みっちゃんが奥からやってくる。
離れないコチは言葉を探していた。
ポン太は言った。
「早く行けよ。みっちゃんに見つかるぞ。」
「ありがとう。」
コチは、恥じらいもなく感謝を伝えた。
「やっとコチがいなくなって、部屋も広く使えるよ。」
「俺は、そんな場所をとっていたつもりはないけどな。」
「いいか。飛んで行ったら絶対こっちに振り返るな。そして、また会いに何か戻ってくるなよ。」
「誰がこんな地獄に戻ってくるか。」
どいつもこいつも正直ものだ。
虚勢がよく目立つ。
コチはもう一度ポン太の胸に飛び込もうと考えたがやめた。
人間の観るテレビドラマじゃあるまいし。ダサい。ダサい。
「なあ。コチ。僕らは友達かな?」
飛び立とうとするコチを引き止めるようにポン太が言った。
ポン太はコチの真剣な話をしっかり受け止めてくれた。
言わなくてもわかるもんだ。
「だったら、別れがきっと寂しいはずさ。」
みっちゃんが走ってこっちに来る。
「ごめんね」と言いながら、ポン太を拾い上げる。
拾い上げたうさぎの胸から一匹の蛾が空に飛び立った事を人間は知らない。
ポン太は、人間の腕の隙間から空を見上げていた。
うさぎの赤い目が今日やけに赤いのは、きっと煙のせいだろう。
「ポン太!」
人間のヒステリックな声がする。
きっと引きちぎられた網戸がバレたんだ。
コチは振り返る事なく空に向かった。
コチだって煙が目に入ったんだ。
広い空。
大嫌いなあの太陽がやけに懐かしく思えた。

パタパタパタと不器用に空を進むコチ。
不恰好であるがこれがコチの全速力だ。
「じゃあ。コチだけがあの場所に花が咲いている事を知っているんだね?」
ポン太は言った。
砂煙はすぐに、空を飛ぶコチのところにまでやってきた。
何かがぶつかり崩れる音が聞こえる。
無表情の怪物が周りを気にせず轟音を立てている。
容赦なく建物を破壊していく。
高いフェンスのせいで、その下がどうなっているのかが分からない。
また、重いコンクリートがその下に崩れ落ちていく。
もう少しだ。
コチが何かに気が付き、空を見上げると太陽はいる。
「お日様は、そばにいてくれるから。」
花の声が蘇る。
「そうだよな。」
太陽も知っていた。
あそこに小さな花が咲いている事を。
太陽の眼差しを砂煙が邪魔をする。
あんなに大嫌いだった太陽。
コチはボソッと呟いた。
「お前はずっとそばにいたんだね。」
それは急に訪れた。
「あれ?」とコチの羽が突然、動きが鈍くなった。
苦しい。
そして、あの恐ろしいコマーシャルがコミカルにコチに笑いかける。
ポン太が必死にこじ開けたドアの隙間から、仕事に貪欲な殺虫剤がコチの羽を追いかけていたのだ。
コチの体はしびれ、枯葉のようにひらひらと地面に落ちていく。
道路の片隅、コチが落ちていく場所には、冬の忘れ物、春の訪れを見る事のなかった落ちた枯葉がまだ残っていた。
落ちるコチ。
枯葉に乾いた音がなる。
ぐるぐる回る景色の中、コチの耳には、工事現場の重機が何かを破壊する音が鳴り響く。
「くそお。くそお・・」
枯葉に埋もれるコチから聞こえるかすれた声は、工事の音で簡単に消された。
「ポン太。あのCMは嘘じゃなかった。あの殺虫剤は、かなり効いたよ。」
ぐるぐる回る視界の光がどんどん遠ざかり、暗闇が堕ちていくコチを迎える。
「ホリデイ。やっぱり俺は、ダメだな。」
枯葉に紛れたコチ。
意識は暗闇に消えていく。
(光?)
眩しい光がコチを包む。
(ここはどこ?)
(天国?地獄はやめてよ?)
コチの前に懐かしい景色が広がる。
(ここは、あそこだよな?)
(なんだ。思い出しているのか。)
コチの前に現れたのは、昔の記憶。
コチの近くにまだあいつ、今じゃ音沙汰のない希望がいた頃の記憶だ。
まだ、飛ぶのが下手な一匹の小さな蛾が三日月の下で、草むらに埋もれる小さな蕾を見つけた。
結局忘れる事なんて出来ない。
あの時と同じようにコチの胸は高鳴った。
あの夜のコチ。
その場を何度も行ったり来たりを繰り返す。
大きく深呼吸をしてようやく決心したコチは蕾に近づいた。
茂った草の間から小さな影がひょこっと顔を出す。
咳払いをして喉の調子を整えてから、照れ臭そうにそっとその蕾に囁いた。
「やあ。もうすぐ君にも春が来るね。」
蕾は聞こえてくる声の方向に耳を傾ける。
きっとその蕾には、飛ぶ影の赤面した顔は見えなかっただろう。
「君が花を咲かせた頃には、俺ももう少し飛ぶのがうまくなっているかな?待っていてくれる?一緒に春をお祝いしよう。」
蕾はこくりと頷いた。
記憶は鮮明にあの日の記憶を映し出した。
「木枯らしのくせして大層な事言いやがる」
コチはあの日のコチに言った。
聞こえる訳がない。
あの日のコチは振り返る事なく何度も飛ぶ練習を繰り返していた。
コチは、黙って流れるままの記憶を見つめる。
記憶は、次々とコチの意思に反して、映し出される。
「木枯らしだ。」
声だって聞こえる。
親切に水たまりに閉じ込められた虹だって映してくれた。
怯えた顔も映った。
「なぜじゃー。」
これは、蜘蛛のおじさんの悲鳴だ。
「いやー。来ないで。」
これは、花屋の花の悲鳴。
「ぎゃー」
これは、人間の悲鳴。
「わあーん。」
これは、人間の子供の泣き声だ。
(全く。よく嫌われたもんだ。)
コチは、傍観席であるこの場所が、何だか安心した。
この場所なら、静かで良い。
悲鳴も遠くの方に聞こえるだけだ。
ジイさんの葉っぱが風に乗り、優しく擦れる音がする。
その間から、キラキラと降り注ぐ声がする。
「おい。コチ。」
それと、笑い声。
(あれ?記憶じゃない。確かに聞こえたぞ。気のせいか?)
(ホリデイ?)
気づくと、コチの前にホリデイが飛んでいた。
ホリデイはこちらに振り返る事なく前に向かって飛んでいる。
(おい、ホリデイ。どこに行くんだよ?)
ホリデイは、黙ったまま飛んでいる。
(ホリデイ。待てよ。俺を置いて行くなよ。)
コチは、何度もホリデイを呼びかけてもホリデイは、振り向いてくれなかった。
ホリデイが遠くに行ってしまう。
(待ってくれ。どこ行くんだ。ずっと探していたんだぞ。)
振り向かず先を急ぐホリデイ。
まるで何かに導かれるようにどこかへ向かっている。
「行くなよ、ホリデイ。行っちゃダメだ。俺を独りにしないでくれ。」
記憶と一緒に大粒の涙が溢れる。
「その蝶は、ここにやってきたのかい?」
月のすみかに咲いたあの花は、首を横に振った。
もしかしたら、あの時から気がついていたのかもしれない。
もうホリデイはこの世界にいないって事に。
だって、ホリデイだったら、あの花に会いに行く。必ず…
「知っているか?蝶は約束を守るんだぞ。」
そんな迷信や面子の為じゃない。
ホリデイはそんなの簡単に裏切る事が出来るんだ。
ホリデイがあの花を放って置ける訳がない。
(知っているんだ。)
なんで、ホリデイの羽は美しいのか?
「ただ蝶の羽を持っているからだろ?」
知らない奴はきっとそう答えるだろう。
だったら、あのコチを木枯らしと嘲笑ったあの蝶たちの羽も美しかったのかい?
(一緒にするな。)
コチは知っている。
ホリデイと同じ空を飛んだのだから。
ホリデイの羽はいつも誰かの為に飛んでいた。
ホリデイの羽は誰よりも春の喜びを知っていた。
(知っているよ。馬鹿野郎!)
コチは、遠くに飛んでいくホリデイに向かって叫んだ。
ホリデイの羽が止まる。
突然、ホリデイがコチの方に振り向いた。
「おい。コチ。さっきから、ごちゃごちゃとうるせぇぞ。」
いつものホリデイの笑顔。
遠くなのにとても近くに感じる。
「いつまでも寝たふり何かしていないで、早く行くぞ。あの花はお前を待っているんだ。」
いつもの朝のように、ホリデイがコチを起こす。
いつも寝たふりをしていたから気づかなかった。
コチを起こすホリデイの微笑み。
「大丈夫。どんな時も僕が腹を抱えて笑ってやるからさ。」
ホリデイの笑い声。
あの笑い声で何度救われた事だろう。
世界で聞こえるのは悲鳴だけじゃない。
コチは、フッと笑って頷いた。
「いいから、早く行け。」
(おう。)
「なあ。コチ。お前のおかげで、楽しい春だった。」
(俺もさ。ありがとう。ホリデイ。)
「お、めずらしく素直じゃない?」
2匹は、青空の下で笑ったように笑った。
「またな。コチ」
そして、ホリデイは笑い声を残して消えていった。
視界がゆっくりと開かれて、うっすらとコチの世界が現れた。
いつの間にか、道路脇の家から年老いた人間がホウキを持って、家の前の道路脇に積もる枯葉の掃き掃除をしていた。
シャー、シャー、と年老いた人間はゆっくりとその鼓動に合わせた調子でホウキを掃く。
冬の面影の残る枯葉を春に相応しくないとばかりにホウキは奏でる。
年老いた人間は、そこにコチがいる事には気づかない。
枯葉色の羽を持ったコチと枯葉を区別するには、年老いた人間の弱った視力では困難な事だろう。
コチと一緒に集められた枯葉は山になると、年老いた人間はちりとりを取りにまた家に戻っていった。
コチの体はまだ動かない。
空には暗雲が覆い、太陽の姿が消えていた。
そして、いつの間にかあのカメレオンがコチを見下ろし立っていた。
「全く馬鹿げているよ。こんなちっぽけな虫の願いを聞くなんてね。ほらね、もう時間切れだ。見てみろ。消え始めている。今度は尻尾もちゃんと消えているだろ?」
ポツポツと雨の雫が空から落ちてきた。
雨の雫は、消えかかった半透明のカメレオンの体を通過して地面に落ちる。
「あーあ。もうどうでもいいけど。君の願いは、一体何だったんだろうね?」
力ない声。
カメレオンはスーッと消えていく。
星が降り注ぐ夜。
「青空の下で、君と虹を見たい。」
確かに、あの時、コチは星に願いをかけていた。
「虹が見たいんだ。」
コチは消え入りそうな声を振り絞って声を出した。
消えゆく体のカメレオンは、うっすらと笑みを浮かべて、ふっと笑う。
「なんだ、その願い?」
カメレオンは消えていった。
遠くでカエルが鳴いていた。
コチの羽に雫が落ちる。
雨が降っていると知った年老いた人間は大慌てでちりとりを持って戻ってきた。
ホウキに、掃かれて、ちりとりに枯葉とコチが運ばれる。
用意されたビニール袋が開かれ、ちりとりに集められた枯葉とコチがその袋に導かれる。
「まだ。行くもんか。」
必死に体を動かそうとするコチの目を風は見つけた。
「もう少しだ。俺が春を連れて行くからね。」
突然、突風が吹き荒れた。
枯葉とコチは宙を舞う。
突風は雨を避けどこまでもコチを運ぶ。
そして、イタズラな風がコチの羽を動かした。「さあ飛んで」と。
風に運ばれるコチ。
風に靡いて少しづつ羽が動いていく。
コチは、イタズラな風に2度も救われた。
必死に羽を動かすコチ。
それでも、やっぱり遅い。
それに雨の中、重くなった羽を動かすのは、やはりしんどいものだ。
コチは、電信柱に張り付くように止まった。
雨の中、道路を行き交う車。
「またか」と言って、コチの口は少し緩んだ。
「もう慣れたものだ。」
コチは走る車のフロントガラスに向かって飛び降りた。
雨のおかげで、フロントガラスに落ちた体は吸い付くようだった。
また、窓越しに人間の不快な様子の目と鉢合わせになるが、すぐにワイパーはコチの体を運んでいった。
フロントガラスの下の方まで運ばれたコチは、雨と風に負けないようになんとかしがみつく。
不快な様子の運転手が送る視線は、コチを追っかけていた。
「少しくらいいいだろ。もうお前らの視線も飽き飽きだよ。」
ワイパーは容赦なく滝のようなしぶきをコチに運ぶ。
何を思ったのか、人間がワイパーの回転速度を上げたせいで、何度も、何度も大量の水がコチの全身に降り注ぐ。
コチは、溺れないように呼吸の居場所を探しながら、車の進路を確かめた。
方向は間違っていない。
月のすみかまではもう少しだ。
はて、どうやってここから降りよう。
ずぶ濡れで重くなったコチの羽はもう使い物にならない。
やる事は一つしか思いつかなかった。
コチは高速に動くワイパーにしがみついた。
体が勢いよく揺さぶられ、感じたこともない圧がコチに襲いかかる。
激しく揺れる体、なんとかコチは気を失わないように、手を離すタイミングを図った。
「ここだ。」
コチの目が工事現場の高いフェンスを捉えた時、コチは思い切って手を離した。
粒のような小さな塊が、宙を飛んだ。
コチのずぶ濡れで重い羽は、空では開かず、コチは工事現場の高いフェンスの前で、体を削るようにアスファルトに落っこちた。
あと少しだ。
でも、体が動かない。
重い雨の雫がコチの体を何度も打ち付ける。
もう少しだ。
あの花に春を届けるんだ。
動け。
そっと風が雨に混じってコチの体を揺らす。
もう少しだ。
「あと、少し・・」
横向きに倒れ、半分水たまりに沈んだコチの体。
沈んでいない片方の目から、空が広がる。
太陽がいない。
厚い灰色の雲が空を覆っている。
「なんだよ。情けない太陽だ。あの花を独りぼっちにするなよ。」
アスファルトに体をこすりつけるように体を揺らすコチであったが体は前に進まない。
暗雲が風に流れて、一瞬、厚い雲の隙間から光が漏れる。
お前こそ。
あの花を独りぼっちにさせるなよ。
太陽が、厚い雲をかき分けてコチに光を与えた。
風がコチを包み込む。
コチの薄れゆく意識。
オレンジ色の光の中、ひらひらと羽ばたくホリデイの影が何度も現れる。
「俺たちには自由の羽がある。」
足が動いた。
足が硬いアスファルトをしっかりと握る。
ぐっと体が前に進む。
もう一度、コチはゆっくりと体を引きずり前に進む。
もう一度。
いつの間にか、雨は止んでいた。
コチは、フェンスの隙間をくぐりようやく月のすみかにやってきた。
そこには、人間の姿はなかった。
きっと、突然の雨で工事が一時中断されたのだろう。
先ほどまで暴れ狂っていたあの機械の化け物は大人しく座り込んでいる。
「あの花はどこ?」
いつの間にか、空に居座る太陽を見上げた。
体を引きずって、どうやってあの花を見つけるつもりだ?
風がコチの羽を揺らした。
羽が動く。
いつの間にか太陽のあたたかい光とそよぐ風が、コチの羽を乾かしていた。
コチは何度も思っていた言葉を口にした。
「みんな、ありがとう。」
どうってことはない。
と、はじめて太陽が笑った。
再び、風でコチの羽が揺れる。
その羽は太陽の光で輝いていた。
「どれだけ、待たせるんだよ。」
コチの目の前には、あのカメレオンが立っていた。
変わらない口調だったが、どこか様子が違っていた。
カメレオンの体が七色に光っている。
その奇妙な姿を見ようとどこから連れてきたのか、また、賑やかにたくさんの鳥や、虫たちの群衆に囲まれていた。
「ほら、あそこだ。きっと待ちくたびれているだろうよ。」
カメレオンは、右手を広げて、あの花がいる場所を教えた。
「お前は?・・」
「いいから早く行ってくれ。これ以上待たせるなよ。」
コチは、カレオンの変わっていく姿を見つめる。
「そういう事か。」
コチは、カメレオンに一瞥すると、瓦礫の大地で、負けないとしっかりと立っている花を見つめた。
待ってるだけの花なんて嘘さ。
俺は知っている。
「ホリデイ。準備はいいか?見ていろよ。俺の勇姿を。」
コチは迷うことなく羽を動かした。
コチの小さな羽はしっかりとコチの体を持ち上げた。
「ごきげんよう。春だよ。」
花が見上げた空には、太陽の色に輝きはばたく小さな羽と、空一面に大きな虹がかかっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
