
サングラスをかけたライオン 4/5
第4章 出発
1.旅の支度
けれど、いざ出発するとなると、いろいろ準備が必要だった。
「まず、このうちを、すっかり掃除しなきゃ。母さんがいつも言ってた、たつ鳥あとをにごさず、って」
たしかに、トザエモのうちは、すっかり掃除する必要があった。何といってもトザエモは生まれてこのかた掃除なんかしたためしがないのだし、ことに最近ときたらみんなの持ちこんだ花が枯れてそこらじゅうをうずめていたのだ。全く、このうちをちょっとでもきれいにするものがあると言ったら、壁のすきまから吹きこんでくる雨風くらいなものだった。
ところが、地下室を探しまわってみて分かったのだが、このうちには、大掃除に必要なものが、ぜんぜん、ないのだ。古ボウキくらいあるかと思ったら、それもない。仕方がないから、家のまわりに生えている棕櫚の葉を切り取ってきて、束ねて枝にしばりつけて自分でホウキをつくった。それでもって、まず二階から一階へごみを掃き落とし、次に一階から地下室へ掃きおとして、さいごに地下室にたまったごみをすっかり掃き集めて、ぜんぶいっしょに外で燃やした。それから粗布を割いてぬらし、壁から床から家具から、みんなきれいに、磨いてまわった。
すっかり終わるころには、空に星が瞬きはじめていた。トザエモはさすがにくたびれて、木の間に腰を下ろした。雨はやんでいた。
こんどの旅のことも、みんなに言うわけにはいかなかった。ライオンの一件のあとだ。彼女の出発を、まず許してくれまい。けれど、そんなに心配してくれるのに、黙って出てゆくのも気が引ける。そうだ、あした、足指亭に行こう。久しぶりに顔を見せて、元気になりましたって、みんなに伝えよう。それから彼らの好きな歌を歌ってこよう。
けれど、あの人にだけは、ほんとうのことを言わないわけにいかない。あの私立探偵には。そこまで考えて、そう言えば最近あの人に会ってないな、と気がついた。考えてみれば、ジープに乗せてもらって帰ってきた、あの日以来だ。たぶん、何か会いたくない理由でもあるのだろう。それでも、発つ日までには、何とか会わなくては。
夜空にくっきりと浮かびあがったオレンジの木の影が、ゆれていた。たわわに大粒の果実をつけて。オレンジの実のなる季節だった。
それを眺めていて、トザエモは、ずっと昔のことを思い出した。母さんといっしょに住んでいたとき、よくこのオレンジを煮てジャムにしたことを。陽のあたるテーブルの上にまるいガラス瓶をならべて、きらきら光る透明な金色のジャムを次々に詰めていく。みつばちの、眠たげにブンブンいう音。幸福なひととき、ゆったりとまどろんで流れる時間───。
そう。今、もいちどあれをつくるべきなんだな。トザエモはひとり考えた。大統領のうちは、ずっとずっと遠くだ。いつ帰ってこられるかも分からない。これまでのお礼に、みんなに一瓶ずつ進呈しよう・・・そうだ、母さんのところへも、一瓶持っていってあげよう。ずいぶん、久しぶりなことだろう。娘のあたしが、一人でジャムを煮られるようになったことを知ったら、きっと喜んでくれるよ。
その晩、トザエモはしばらくしまいこんでいた<緋色の研究>を出してきて、さいごの十ページを読んだ。そこの場面で、犯人が心臓の病気で死んでしまうのだった。想像もしない結末だった。泣きはらした目をあげたとき、森の上を大きなオレンジ色の月がゆっくりと渡って、西の空へ沈んでいった。
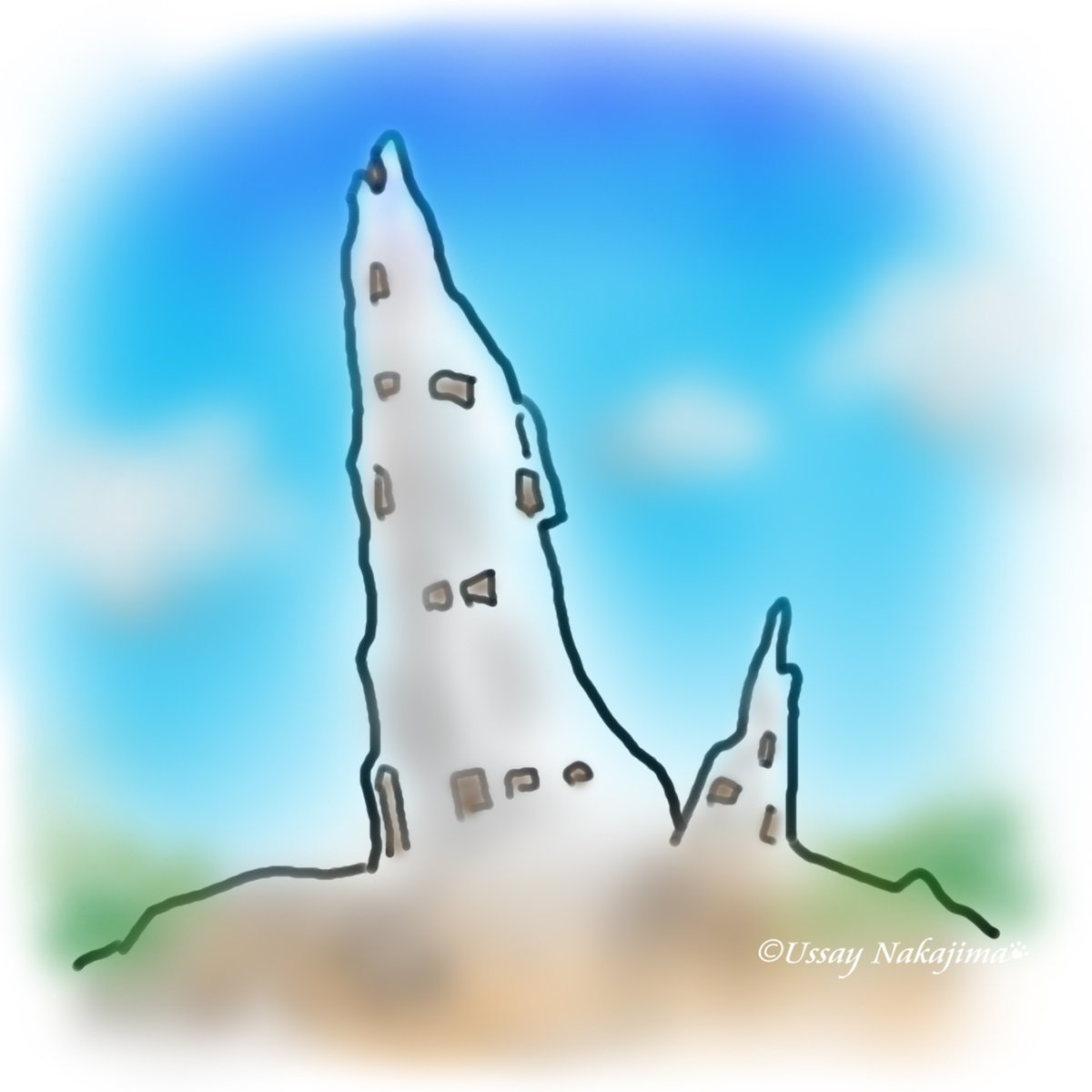
2.ピムシュク
次の朝、トザエモとアルヌマーニクは、ジャムのためのガラス瓶をどっさり仕入れるために遠出をした。いつだったか、ジープの男が教えてくれた店まで出掛けていったのだ。
その店の名は、ピムシュクといった。低い灌木の生える荒地の真ん中にぽつんとたっていて、その姿はまるで突き出た岩山か、鼻づらをまっすぐ天へ向けて遠吠えするオオカミみたいだった。
「あのひと、こんなところまで、何を買いにくるんだろ」
トザエモは意外に思ってひとりごち、中へ入っていく。店の中はほとんど真っ暗で、わずかにひどく凝ったデザインのランプシェードから、ぼんやり、黄色い光がもれていた。よくは分からないが、やたらごたごたとものが置かれている感じだ。
だいぶちゅうちょしたあげく、とうとうトザエモは大声を出した。
「誰かいませんか?」
長いこと間があった。それから、だしぬけに頭の上から、
「はいはい、今行きますよ」
という声が降ってきた。
「今行くから、ちょっと待って」
その声はこだまのように頭の上をぐるぐる回りながら、とっとっと目に見えないらせん階段を小走りにかけおりて、下まで降りてくる。
すぐそばに置かれていたランプが持ちあがり、深くしわの刻まれた老人の顔をやっと照らし出した。

「ガラス瓶がほしいんです」
と、トザエモは言った。
「ガラス瓶、ガラス瓶と・・・さあ、いろんなのがありますよ。まるいの、四角いの、三角の、六角形、花のかたち、鳥のかたち、動物のかたち、取っ手つきもあります。色も豊富です。七月の夜明けの空の色、アマリリスのつぼみの色、日曜の午後の湖水の色、真夏の夜に見る夢の色。材質も、クリスタル、くもりガラス、ひび入り、透かし模様、網細工・・・」
大きな棚の中から、美しいガラス瓶が次々に光の中へ取り出された。まるで魔法の手によって、たった今、つくり出されてくるみたいだ。トザエモは目を見開き、息をのんで見つめていたが、ようやく思いきってさえぎった。
「すみません、たしかにみんな、きれいなんですけど、あたしがほしいのは、ごく普通のガラス瓶なんです。ジャムを入れる、コルクのふたのついた、ただのまるい瓶なんです」
老人の声が、ふっと途切れた。それから、
「おお、これぞ美の究極───もっとも単純なかたちの中にこそ、あらゆる美が集約されている。もちろん、ある。こちらへおいで」
ランプが再び持ちあがって、動いていく。
トザエモはそのあとを追いかけていきながら、尋ねた。
「ここ、どうしてこんなに真っ暗なんですか?」
「なぜ真っ暗なのか? 闇の中にすべての光が宿るからだ」
と、老人は答えた。
「何でもそういうものだ。夢の中にこそ真実がある。死に脅かされて命は光り輝く。失ってはじめて、得ることができる。───ところで、わしの方も一つ聞こう」
老人のランプがちょっと立ち止まった。
「お前さん、前にも一度ここへ来たことがなかったかね?」
「あたしが?」
ランプがゆっくり後戻りして、その光がトザエモの顔を照らし出した。
「おやおや・・・ふむ、よく似た別人なんだな」
と、老人はひとりごちた。
「お前さんにそっくりな、オレンジ色の髪をした女が、こないだもここへ来おったじゃ」
トザエモは胸をドキドキさせた。
「それ、あたしの母さんです! たぶん」
「ずいぶん前のことだが。ここへ来て、空虚の穴をふさぐ妄想を、きっちり十ポンド量って買っていった」
「母さんが、妄想なんかを買うわけないわ」
「いや、自分のためじゃないんだ」
と、老人は言った。
「いつもは、別の人間が来るのじゃ。毎月毎月、きちょうめんにやってくる。この危険な妄想を買いに、りっぱな馬具をつけた馬に乗り、上着には四枚の翼を持ったトーテム・ポールを刺しゅうした使者が。お前の母さんは、その代理だったのじゃ」
「ふうん、そうか」
と、トザエモは言った。
トザエモは二つの大きなかごにうす緑色のジャム瓶をいっぱいつめこみ、それをアルヌマーニクの背中の両側から下げて帰った。

3.ジャムづくり
午後の陽もだいぶ傾いて森にさしかかったところで、向こうからやってくる私立探偵に出会った。私立探偵の方も、ちょうどトザエモのところへ出向いてきたところだった。
あいかわらず、上から下まで緑づくめで、口の端にパイプをくわえ、ひょろひょろした体を持て余すように歩いていた。そして、トザエモが手を振ると、困ったように笑った。
「一体今までどうしてたのよ。ずいぶん長いことごぶさたしてたわね」
トザエモが言うと、私立探偵は答えた。
「うん、そうだけど、さいごのところは、やっぱり自分で解決しなきゃいけないのさ───この種の事件の場合はね」
「その通りよ。あたし、解決したわ。あす、出発するの」
「でかした!」
それを聞いて、私立探偵は顔を輝かせた。
「都へ、母さんに会いに行くわ。それからあの軟膏も持っていって、ばかな大統領の頭につめこんでやるわ。そして、あいつの銃にも」
「ばかだな。奴のことだから、銃なんか山ほど持ってるに違いないぜ」
「あんた、あたしの本当の力を知らないのね」
トザエモは、頼もしく言って、笑った。
「分かったよ」
と、私立探偵は言った。
「がんばれよ。君の力を信じてるよ」
「ありがとう。あんた、確かにシャーロック・ホームズの素質があるわ」
うちに着くと、トザエモは納屋から長梯子を持ち出してきてオレンジの木に掛けた。はだしの足の裏で枝の感触を確かめながら器用に登ってゆき、茂った葉の中に輝くその実を、端っぱしからもいでゆく。それが終わるとこんどは大鍋を見つけ出してきて、その前に座りこみ、ナイフで皮をむいてはどんどん放りこんでいった。
その間、私立探偵は窓に腰かけて陽をあびながら、<緋色の研究>や、本棚で見つけた他の本をぱらぱらめくって読んでいた。
トザエモがひと休みしに台所へ入っていくと、私立探偵は読みかけの本から目を上げて、言った。
「最近、自分の生まれた町のことを思い出したよ」
「何で急に?」
トザエモは、彼の方を横目で見やって聞く。
「何でって? まあ、聞いてくれよ。ぼくは、海ぞいの工業地帯にある小さな町で生まれたのさ。ひどいところだったよ、息がつまりそうだった。工場では毎日、きっちり同じ型の部品がどんどんつくられてはベルトコンベアにのって流れていくんだ。君、ベルトコンベアって知ってるかい、どんなものだか? それでもって、通りには高さもはばも同じ四角い家が、どこまでも同じ間隔で立ち並んでいるのさ。町全体に、ガソリンと機械油の匂いがたちこめていた。へいに腰掛けて───こんなふうに───部品の山を眺めていると、うるさい連中がやってきて、うるさいことを言うんだ。労働の義務とか、社会秩序だとかさ。
そんなのが、本物の暮らしであるわけないだろ? それでぼくは心に誓ったのさ、いつかはここを出ていって、本物の暮らしを手に入れてやるって。ビッテムロシュナのことを聞いたとき、ああ、これだ、と思ったんだ。でも、実際こっちで暮らし始めてみると、全部が全部、思ったようじゃなかったな。こっちに来ても変わらない問題があることにも気づいたし」
そこで私立探偵がふっと黙りこんでしまったので、トザエモは先をうながした。
「それで?」
「でもさ、ともかくそういうことだって、実際やってみなきゃ知らずじまいだったんだし───それに今だって、だんぜん、ここが好きだな、うん」

4.たのしい晩
日が暮れるころ、アルヌマーニクの背にジャム瓶のかごをのせ、トザエモと私立探偵は虹の足指亭に向かった。もう遠くから、アコーディオンの音色と笑いさざめく声とが聞こえていた。誰かが先回りして、伝わっていたらしく、トザエモが戸を開けるなり、
「おーい、お出ましだぞ!」
という声があがって、その場が沸いた。
顔見知りが、ほとんど全員そろっていた。みんなは、トザエモの回復を祝して乾杯し、トザエモの首に花の首飾りをかけた。
トロピカル・ジュースとパンケーキが回され、ビールを注いだ大ジョッキがぶつかりあう。楽しい晩だった。騒がしいお喋りはいつ果てるともなく続き、トザエモは声が涸れるまで、知っている歌を次々に歌いまくった。おもてには、紺の空に星がきらめき、木の葉をそよがせる風の涼しさはもう、かすかな秋の気配だ。
「この次、ここに来るときには・・・」
と、トザエモは、半ば郷愁にも似た気持ちで思う。
トザエモと私立探偵は四つ辻のところで別れた。
「明日の夜明けよ。村の入り口で」
と、トザエモが言うと、私立探偵は答える。
「うん、分かった」
「誰にも言わないでね」
「もちろんさ」
家路につく前に、カデンツァの噴水に寄ってみた。パイナップルの輪はいつものように、明るい光を放ちながら水のまわりをぐるぐる回っている。
噴水の外側の壁に、強烈な色づかいで動物や風景の絵が描かれているのに気がついた。いつかここで出会った旅人が描いたのだ。彼は再び自分自身を見つけ出したのだった。

向こうから、ほっそりした黒い人影が近づいてくる。顔は見えなくても背格好で分かる。愛すべき、やせぎすのレンカだ。
「こんばんは」
と、声をかけると、トザエモの方を見て、微笑んだ。
「こんばんは。いいお晩ね」
少しの間、二人は黙って噴水の水をながめている。時々、レンカのつけている銀色の三日月形の耳飾りが、月あかりにきらりと光る。
「・・・ねえ、」
と、だしぬけに、トザエモは言う。
「覚えてる、いつだったか、サングラスをかけたライオンの話をしてくれたことがあったでしょ? ねえ、もしよ、ほんとにもし、そのライオンがまだ生きていたとして───そして、もし誰かがそいつの傷を治してやれる薬を持っていたとして───そしてある日、実際にそのライオンを探しに行って、治してやろうとしたとしたら。そうしたら、そのライオンは、どうしたと思う?」
レンカは、ちょっと首をかしげて、考えていた。
「どうかな。素直にそれを受け入れるかしら。分からないわ。あまりにも深い悲しみを経験してしまった者の心には、時として奇妙な自己憐憫の気持ちが育つものよ。それは逆に回復を憎んだり、するかもしれない」
「そうなのかな」
と、トザエモは言い、考えに沈んだ。

5.夜明け
トザエモは家に帰ったが、眠る気にはなれなかった。窓にもたれて、夜明けまでずっと、空の色がゆっくり変わっていくのを眺めていた。旅の支度はもうできていた。
東の空が白みはじめ、鳥たちがめざめて歌いはじめたころ、トザエモは窓のそばから立ち上がった。それから外へ出ていって、少しばかりぼうっとした頭に、冷たい沼の水を勢いよくぶっかけた。そうしてあざやかなオレンジ色の髪からぽたぽた雫を滴らせながら家の中へ入ってくると、小さな荷物を持って再び外へ出た。森を吹き抜けてくる朝風に向かって大きくのびをして、それから鋭く口笛を吹いて、アルヌマーニクを呼んだ。
「さあ、都へ行くんだ」
なじみ深いざらざらしたアルヌマーニクの背に手のひらをのせ、トザエモは宣言する。今や主人のいなくなった家は、がらんとして淋しげに見えた。そして、風にゆれるオレンジの木も。

まだ暗い森の中を進んでゆくと、ライムの木の下に、紺色のマントを着た人影が立っている。黒ぶちの丸めがねをかけ、つる草のような髪が肩までのびて、年はぜんぜん、見当もつかない。目を閉じて、天に向かって腕をのべ、まるで大地と一体になったようにじっと立ちつくしている。けれど、トザエモには一目で分かった、それは奇術師カデンツァだった。
「お久しぶりですね」
トザエモはそっと言う。
「ようこそおいでくださいました」
「本当に久しぶりだ」
奇術師は、静かに答えた。
「しかし、みんなは変わっていないことだろうな。あいかわらず歌を歌い、ジョッキを傾けながら、楽しくやっていることだろう。どうか、カデンツァがやって来たことを、もうしばらく秘密にしておいてくれ」
「もちろんです」
と、トザエモは言った。そして、まだ誰も知らない秘密に胸をわくわくさせながら、静かなビッテムロシュナを横切っていった。
村はずれには、二つの人影があった。私立探偵と、もう一人はいつぞや足指亭で会った旅がらすだった。
「なんだ、誰にも言わないでって言ったのに」
トザエモがふくれて言うと、私立探偵は困ったように隣りを見やった。
「ぼくは何も言ってないんだけど」
「そうとも、この人はなんも言っちゃいない」
と、旅がらすは平気な顔で言ってのけた。
「ただ、俺があの子は今日発つのかねって聞いたら、うなずいただけさ」
「ともかく、事件は一応の解決を見たね」
と、私立探偵が言った。
「そうね、たぶん」
トザエモは、荷物の中から<緋色の研究>を取り出して、彼に渡した。
「今まで、ありがとう。これ、あげるわ」
「あんたの母ちゃんに、よろしく言ってくれよ」
と、旅がらすが口をはさんだ。
「あんたなんかからよろしく言ってどうすんのよ?」
「いいから、伝えておくれよ」
「分かったわ」
トザエモはアルヌマーニクの腹を軽く蹴って、前へ進み出させた。それからちょっと振り返って二人に向かって手を振り、
「ごきげんよう!」
と言った。
まぶしい朝日の光が、大地を染めはじめていた。大地はいつでも大いなる未知と希望とを孕んでいる。恐れることなくそこを進みゆく、全ての者の前に。

お話はこれで終わりです。
読んでくださりありがとうございました。
よろしければあとがきに続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
