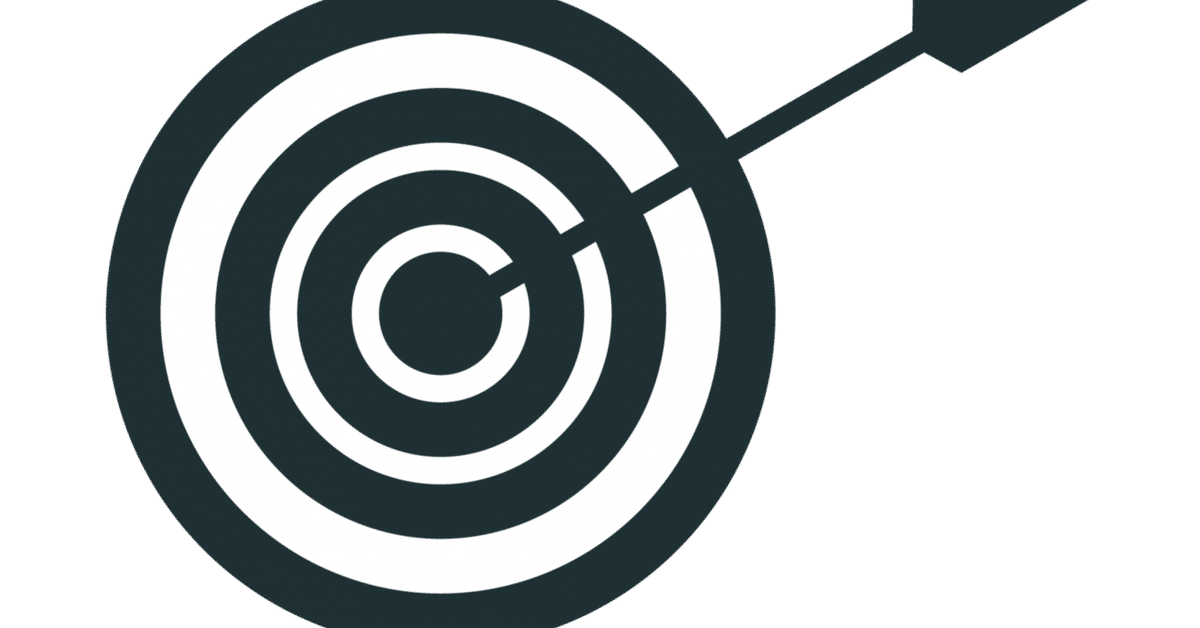
#46 正鵠考
物事の要点をつかみ、的確な指摘をすることを「的を射る」または「的を得る」と表現する。かつては「射る」が正解で、「得る」は誤用とされていた時期もあったが、現在ではどちらも正しいと考えられている。これは、『三省堂国語辞典』第三版(1982年刊)が初めに誤用として記載し、第七版(2013年刊)で改めて正しい用法として掲載したという経緯がある。「的」は弓矢の的(まと)であり、弓矢ならば射るものだろうという常識的判断や「い」と「え(ゑ)」は混同されやすいという日本語独特の発音の問題もあり、誤用とされたらしい。
実は戦前はあまり「的を射る・得る」という表現は少なかったそうで、中国伝来の「正鵠を得る」、「正鵠を失わず」など「正鵠(せいこく)」の方が多く使われていたという。正鵠とは、弓矢の的の中心の黒点のことであり、当然、矢を放つ方は大きな的全体に当てることが目的ではなく、中心の黒点(正鵠)を目指すわけだ。正鵠であっても、弓矢で射るのだから射るが正解なようだが、正鵠を射たものには褒美として本物の鳥が与えられたとする俗説があったり、そもそも「得る」は手に入れるの意であるから、得るでも正解とする見解が示されている。
さて、字義をさらに深掘りしてみると、筆者の心酔する漢字学者、白川静博士の『字統』(平凡社、1984年刊)によれば、「鵠(こく)」は声符(発音)「告(こく)」に「鳥」で、鳳(おおとり)の一種、高擧遠翔する霊鳥であるという。「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」の「鴻鵠」である。また、「告」には木枠の意味があり、弓矢の的とされたともいう。
ちなみに、「告」の字形は、祝詞を捧げる器を木の枝に掛ける形であり、神への願い事を捧げる原意がある。そこから転じて上告、やがて広く「告げる」意味合いで使われるようになった。弓矢で的を射ることは、もちろん神事でもあったわけであるから、正鵠を射ることは、正鵠(神意)を得ることにも通じるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
