VISLA MAGAZINE ウウォンジェ インタビュー 日本語訳
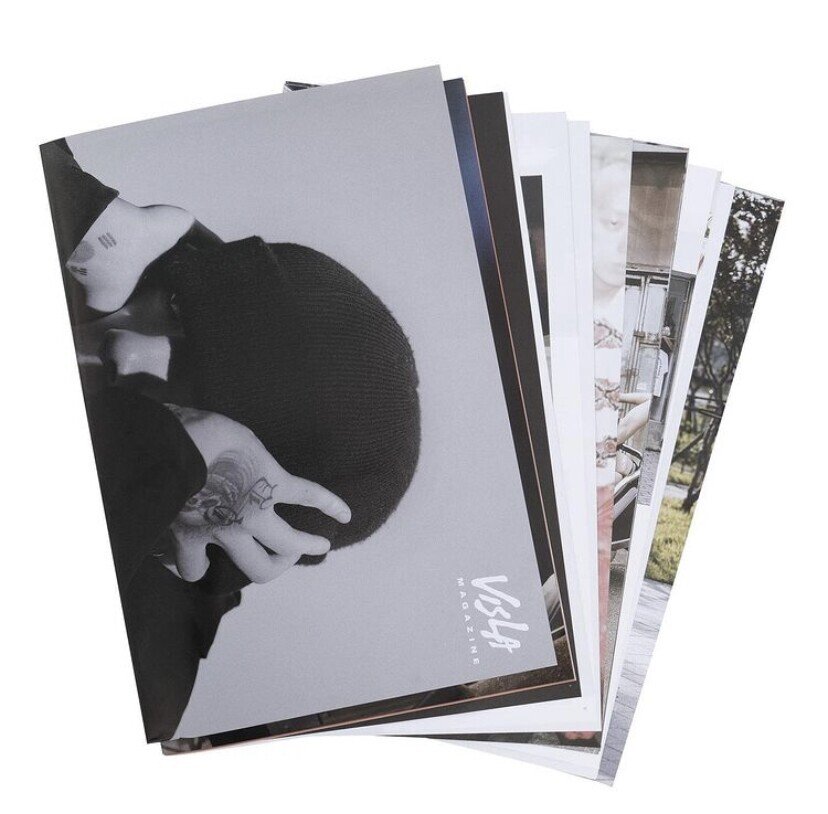
ウウォンジェは自身の初正規アルバム[BLACK OUT]を通して一種の確信を感じたようだ。突然掴んだ成功と平凡な日常の時差からこれからは自由なように、むしろ変化を喜んで受け入れる。プロデューサー KHYOと一緒に完成した[BLACK OUT]は明らかに今までのウウォンジェと区分をつけることができる分岐点に近づく。悩んだ青春の肖像が一人のプロフェッショナルなラッパーになるまで、再び変化する彼のスペクトラムをファン達は今回も楽しい気持ちで喜ぶだろう。
前回のEP[af]とは参加陣からジャンル的作法まで全体的に相反するアルバムの雰囲気がまるで違う服を着てきたような印象だ。前回のアルバムと[BLACK OUT]の間の時間にヒップホップというジャンルに職を置く立場として、また一人の音楽家として発見したアイデアや経験があるなら何か?
[af]以降の変化が思ったより大きかった。事実サウンド、ラップスタイル、ジャンルのような音楽的な変化を意図したというよりは自分自身に関する悩みが結果にも反映されたと言う方がより適切だと思う。前回のアルバム当時には他人から見る自分自身についての悩みが多く現れたなら今回[BLACK OUT]はすごく基本的ですが自分で整理できなかった質問を思い浮かべながら作業に入った。ここにはプロデューサーKHYOがとても大きい比重を占めているが、彼は私に"だからお前がしたいことは何?"、"お前は誰?"を続けて聞いて、その質問をある程度整理した時音楽が大きく変わっていた。
KHYOと全曲を作業した。どんな理由で彼と全曲を一緒に行う考えをしたのか気がかりだ。アルバムの方向性を決めながら交わした会話、テキストなど記憶に残ることはあるか?
当然プロデューサーを信じたから最初から最後まで一緒に行った。もちろん初正規アルバムだったので自分自身でも意地を張った。私がKHYOに従う時もあったし彼が私に従ってくれる時もあったしお互い摩擦が起こる時もあった。KHYOにとても感謝していることは私が本心で話した時はどんなことでも触れなかった。一緒に住みながら作業したのでその日その日に私に起こった事件と気分をすぐ感じたようだ。なのである日は"お前これカッコつけようとしてる言葉ぽい"と言われたらすぐに認め歌詞を捨てた。KHYOというプロデューサーが他のミュージシャンと作業する時どんな方法でするかよく分からないが私には"ウウォンジェは歌詞を書く人だ。"、"ラッパーは自分の話をしなければいけない"といつも強調した。よく考えてみたら私が一番好きな仕事も歌詞を書く職業だからKHYOはウウォンジェという人と長所をそういう風に見て私は認めた。
[BLACK OUT]を作るとき一番大きいヒントになったり核心的な素材またはキーワードがあれば教えてほしい。
アルバムの題名、[BLACK OUT]それ自体が核心キーワードになった。実は今回のアルバムは特別な目的を決めて作らなかった。プロジェクトの窓を開けておいてただそれだけ考えた。以前にはAという曲はBというサウンドで表現したいという方法である程度、型とコンセプトを設定し歌詞を書いたなら今回のアルバムは本当にただ出たままにした。ただ何かが出てくる時歌詞を書いたし、これをどうやって作るかは録音してから決定した。
"BLACK OUT"、"R.I.P"を一貫する主題意識は'過去の自身に向けての別れの挨拶'のように感じられるが過去のある特別な時点と現在を区分しようとする意図なのか?それとも現在のウウォンジェは常に過去を殺してから存在するという意味なのか?
後者だと思う。私は自分に変化が起こる時正直とても嬉しい。昨日の自分を否定する気がする自分自身を我慢することが一つも苦ではない。今にでも分かって良かったと思う方なので。音楽が変わり好みや考えが変わることまたは昨日の自分はそれ程重要ではないと思うからだ。
今までのウウォンジェはその卓越した演技力のためなのか技術的な面よりも歌詞の訴える力、伝達力により傍点を打たれる方だと思った。本人自らラッパーとして実体性を重点に置く部分なのか?また今回のアルバムで変化を試そうとしたならどんな点で悩んだのかその形跡を話して欲しい。
ジャンル音楽はある程度アクティングという言葉に共感する。なのでジャンル的な悩みをあまりしたくなかった。そうしたらより明らかなジャンルで焦点を合わせることも不思議だ。ある日KHYOが私に"お前は全てのリスナーが聞く話をなぜ俺の前では出来ないんだ"と尋ねたことがあった。その言葉を聞く前までは全く認知することが出来なかった。振り返ってみると私がとても大切な歌詞は誰かに聞かせてあげるための目的で書いたものではなかった。ただ適当に書いたものを発表するときに恐れがなかっただけで。曲ごとに立場と悩みが千差万別だからトラックリストは自分なりに時間順に配列した。2番から9番までは本当に作った順番で並べた。今日こうやってインタビューしても家に帰って次の日になると今日自分が言った言葉が恥ずかしいと思う。私は毎日こうやって反復されると思いそのままアルバムもその当時の感情を書いておいたことを並べた。
青春の悩みがにじみ出る感受性よりは一人のはっきりとしたプロフェッショナルとしてラッパーの色が目立つ分岐点ではないかと思うが、自身は今回のアルバムをどのように受け入れているか?
私も似たように感じた。理由はよく分からないが、今回のアルバムに確信したし、こんな気分は初めてだ。以前までは常に歌詞を書いて曲をだして後にその曲を疑心したりしたが今回のアルバムで歌詞を書くときは全く恥ずかしくなかった。考えが変わったならまた変わった考えを書けばいいから。こうやってとても小さい内的な変化だが音楽ではよく目立つ。結局確信する一つは私はずっと変わって、これからも変わるし過去の自分がいるから今の自分がいること。だから恥ずかしくない。
最近歌詞に影響を与えた同僚アーティストまたは作業があったなら何か?
Mokyoという友達でありミュージシャンに多くの刺激を受けた。その友達は自分自身に堂々としていないことは口の外に出したり、歌詞に書いたりしないようだ。自己検閲が確実な彼の態度を見ながら多くのことを学んだ。
"しゅっしゅっぽっぽっFreestyle"、"JOB"、"ジンギスカン"のビートや歌詞の引用でMemphis Rapの影響がうかがわれる。特別なきっかけがあるのか?
突然ハマった。言及したように5、6、7のトラックがMemphisの影響を受けた結果なのだが、先に私が時間順にトラックリストを組んだと言ったけど。その当時にMemphisにすごくハマっていた。KHYOとSIMOがMemphisを聞かせてくれた時その出る感じがすごくかっこよく感じた。それがまた良くてその日暮らしのようにそこに合わせて歌詞を書いた。
このように"SMTM"で見せた姿とは違ってジャンル的な形式美に気を使っている様子だ。何を悩んだのか?
Memphisラップに影響を受けたトラックたちを作業しながら感じたことは歌詞を高密度で書くとダメだということだった。最初から終わりまでフリースタイルをするように、さっと書かなければいけない。歌詞に計算が入るとむしろつまらなくなると思った。誰かに良く聞こえるという問題ではなくそうしなければ自分自身そのムードが出ない。
ジャンル的な背景まで間接的にでも体験しようと思ったのか?
私は赤ん坊も雰囲気を感じると思う。これは肉感的なものなので意図することも出来ず自分勝手に解釈することも出来ない。直感的なこと。ある瞬間ただそうやって作られていくものだ。なのでMemphisラップの雰囲気を一番重要だと思い作業に入った。
反面So!YoON!(ファンソユン)と一緒にした"Do Not Disturb"や"USED TO"でまるで聴き手を近い距離に置いたような自己告白的な歌詞は相変わらずウウォンジェにとって特技とも感じられるが。
この二つのトラックはもっとさっと書いた。さっき言ったMemphisトラックたちはその雰囲気に慣れるまで捨てた歌詞があまりにも多かった。私は攻撃的な性向が少ないからなのか絶対そのような歌詞を書かなければならないということは無いがそのMemphisラップの雰囲気を自分の方法で解釈することに時間がかかった。しかし"Do Not Disturb"や"USED TO"はただすごく自分自身だから。何も考えずその日の気分を書くようにした。
まるでその日その日の日記を見ているようだった。
日記帳と似ていると言えるだろう。その日ではなかったらその歌詞は出てこない。明日にはまた違う歌詞が出てくるから。
"俺はなりたい男Björk"以降の節はどんな意味を含んでいるのか?ラッパーの口からBjörkとBrian Enoを言及したという点も興味深いが。
私は音楽に関する知識が該博な人ではない。ジャンルを上手く区別したり沢山聞く方でもないし。しかし私がBrian EnoやBjörkはジャンルではなくただその雰囲気で聞いている。Brian Enoを聞いてみるととても平和で何か自分の人生がこの音楽みたいだったら良いなと思う。Björkを見ると本当に勇気のある人だと感じた。この方たちの音楽は一種のグループ、ムードのように感じられる。
少し戻って"SMTM"という生態系の中でウウォンジェはとても珍しいキャラクターのように見えた。お金も無くコネも無い平凡な学生が特定のきっかけを通してスターに生まれ変わる一種のシンデレラのような典型的ながらも劇的な話が演出されたが。実際"SMTM"以降の人生はどのように変化しているか?
やはり戸惑って不思議だった。金儲けや私が置かれた環境を話すと本当にダイナミックに変わった。成功の基準がそこにあるなら成功したと思う。しかし個人的には大きく変わったことは無い。変わらず会う友達、家族、それがただ自分だと思う。お金を沢山稼いで人々が好きになってくれるから当然嬉しい。時々不思議だ。どう見ても完全に他人の人生なのに私の話を愛してくれるファンたちがいるということ。だが家族と友達、私が好きな人たちが消えるならお金というものも大きな意味は無いと思う。音楽を特に職業だと思っていないからそうなのかも分からない。頭では職業だと信じているが、心はそうではないと思う。ただ好きだからしてると思うんだけど。
音楽さえあれば一生楽しく生きていけるというドラマティックな瞬間に出会った時はあるか?
私は関係を一番大切だと思う人だ。音楽が高い順位にあるのは事実だが、これがなくても生きていけると思う。実は夢を一つに決めるということも恐ろしい言葉のように聞こえる。正確な目的地を決め走り抜けることを自分が出来るか分からない。目標を決め走り抜けるならそのくらいの推進力はあると思うが臆病で毎日考えが変わる人だからいつか目標が変わった時ぶつかる何かが怖い。
運動選手のようには生きていけないということなのか?
なので生まれ変わったらしてみたいことは運動選手だ。そのような方たちはチャンピオン、1位のような明確な目標がある。また運動選手はその順位により選手の価値がつけられている。私はそういう雰囲気を極度に耐えられないからその領域で孤軍奮闘することをかっこいいと思う。私はそんな負けん気がなくて。
"We are"は本人にとってどんな意味を持つ曲なのか?競演では決勝戦用で初公開させる曲たちは全般的に過剰になったり競演用の無理数が見えたが"We are"は本来GRAYのプロデューシング下で素敵に作られたトラックだった。優勝の欲は無かったのか?
全く無かった。毎回上手くやりたいという気持ちだけだった。'自分が恥ずかしくなければいい'ぐらいの心構え?"We are"はその当時に自分が言いたかった話だ。そして私のサークルの先輩、Loco、GRAYと一緒にしたかった。さらにGRAYは20歳の時音楽を初めて教えてくれた先生でもあるから。私にとって意味のある方たちだから一緒に最後を整理したかった。
以前Maalibとのプロジェクト[Stretch]のような場合ローカル基盤の創作者たちと一緒にしこれをトゥクソムにあるローカルショップを通して流通しスケーターたちとアルバムを一緒にするスケートボードビデオを制作した。どんな意図でこのようなことを選んだのか?当時に"SMTM"でウウォンジェに接した立場として少し首を傾げた。
私は当時メロンチャート1位を記録した"We are"と"Stretch"が何が違うかよく分からない。いずれにしても私が好きなものだから。ストリートブランドが好きで、スケートボードに乗ることも好きだし、ただそれが自分なのに。自分の姿をよく知らない人が多いからそれが意外な行動だと言うんじゃないかな?なんといっても"SMTM"で名前を知らされたから。その質問も本当に沢山聞かれた。驚いた。
大衆の期待とは無関係な行動だった。思いっきり楽しんだのか?
その当時にはAOMGに入り広告を撮りイベントを行ったりしたからすごく忙しかった。面白かったが、とてもその状況が慣れなくて慣れるまでの時間が必要だった。こんなに時間は早く流れるのに、歌詞はもっと書きたくてその忙しい情緒が反映されたプロジェクトのようだった。内容の流れで何がなんだかごちゃごちゃで、その当時の自分だった。Maalibのビートもその感じとよく合っている。
作業しない時間を耐えることは大変か?
私は今日作った曲は今日出したい。今日の自分の考えだから。それが多分表出欲求だろう。今日の考えを今日書きあまり遅く出さないように出したいと言う気持ち。
大衆がウウォンジェに送る愛情や期待より本人自身が次の行動を決め動くような印象が強い。周辺の創作者と続けて協業を続ける理由があるなら何か?これがよくメインストリームと呼ばれる同僚アーティストと進行する作業との差があるなら?
そのような差はほぼ無い。はっきりした事実は自分が素敵だと思うことたちは自分の仕事をしっかりすること。曖昧だと中途半端になる気がして。メインストリームであろうとアンダーグラウンドであろうにせよ確実にするこれらの足跡はその姿と似ている。死ぬほどディギングし、練習し、それを楽しみながらする。
AOMGと契約した後に音楽的な側面でどんな影響を受けたのか気になる。一人では無いクルー、レーベル単位の活動を通して変わった点があるなら?
数えることも大変なぐらいに多い。まず所属アーティストたちはそれぞれ24時間を過ごす方法が全て違う。なので私はそれをただ眺めて尋ねることだけでも楽しい。そうしてみると音楽だけでなくただ生きていく上で助けになる多様な影響を受けていると思う。音楽または生きていく方法の中の一つだから。実務スタッフの方たちも私を単純に会社の所属アーティストではなく一人の人として接してくれる。そうではなかったら勇気を持って近づけなかったと思う。人間として弟として近づいてきてくれてありがたさを感じる。
コロナ以降の生活はどうか?コロナウイルスが与えた余波は個人的な日常そしてミュージシャンとして生活にどんな影響を与えているか気になる。
まず公演がない。公演をそんなに楽しむ方ではないが、今はその公演がしたいぐらいだ。反面、日常的では新しくなった側面では人生が少し遅くなったこと?私はもともと少しのんびりしている方なのでこんなことを言っていいか分からないが少し楽になったと思う。比較的時間を速く過ごす人たちは決定も速いし思考も論理整然としているが、私はいつももっと多くの時間を必要とする。悩みも多いしゆっくり過ごす時間がなければ音楽をする人として生きていけると思う。
その間の曲を通してかなり有名になったウウォンジェに向けた要求と期待にそれほど忠実に応えていないだろうということ、大きい野望より自分自身のままで生きていくというニュアンスが漂った。ここで言う'自分らしさ'の意味は平凡な日常を奪わず享有することという脈略からなのか?関連した話を聞きたい。
この答えが疑問な理由は何かを規定したくない自分の気質からくる。特に'私はどんな人だ'、'私は誰々だ'と言う瞬間その言葉に閉じこもると思う。なので少しほっといておきたい。例えば'私はなんでこれをしたいか?'という疑問を聞いた時正確にその理由を言葉で説明出来ないが自分はこう感じているという直観を信じたいということだ。なので言葉で説明する大変な理由を無理に探さずほっといておく方だ。しかしお金を沢山稼ぎたい。高い物を買ったり贅沢を楽しみたいという気持ちではないが、確実にお金は不幸を遮ることができる装置だと思う。明日を生きていけるようにする防波堤と言えばいいかな。普通の人は最悪の状況に陥った時はほとんどお金の問題が結びつけられてないかな。不幸を遮る道具として必ずお金は必要だ。
音楽を始める草創期にウウォンジェを動かした動力は一般的な社会基準に一致しない自身が感じた乖離感、青春の素顔のようなことだと思う。しかし今は当時との立場がすごく変わってアルバム内の歌詞では大きな野望は無くてももっとこの人生を続けていくことだと話す。今はどこを見渡しているか?
曲でも話したように、ミュージシャンとして大きな野望や明らかな里定標を決めておいてはいない。4〜50歳ぐらいに地元に近いところで家族、友達と一緒に住めば楽しいと思う。何をしているかは分からないが。違う仕事をしていても歌詞は書けると思うし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
