
自薦他薦と「良い曲」の定義について
ページを開いてくださったみなさんこんにちは。裏白Pと申します。
「うらじろぴー」と読みます。
2022年4月1日から「ボカロP」として、界隈でもみくちゃにされながら日々を過ごしております。
さて、ボカロPとして様々な投稿祭やコンテストが目白押しな季節がやってきましたね(恐怖)!
みなさん進捗状況いかがでしょうか?
大きな投稿祭やコンテストがあると、必ずといっていいほど起きる
「自薦他薦」に対する論争
「良い曲」がちゃんと評価されるべき論
この2つのレイヤー違いの平行意見が、なぜか交差点になってぶつかり合う構図が生まれがちです。
「音楽的に良いものがちゃんと評価される業界になんちゃかんちゃら!」
「良い曲が正当にリスナーに届くような仕組みなんちゃらかんちゃらー!」
的なね。

この、何となく耳にしている「良い」という言葉ですが、
「良い」って何?と言われて説明できますか?
「良い」の定義を明確に示せないまま、個人的な感覚や好き嫌いを他人に押し付け合う水掛け論の合戦を、果たして議論だといえるでしょうか?
逆説的にいえば、「良い」の定義や発現条件を共有することで、他人の活動指針やアクションプランに対し寛容になり、建設的な議論を展開できるようになるのではないかと考えています。
そこで今回は、
について一緒に考えていきたいと思います。
対戦よろしくお願い致します!
①「良い曲」とは何?

前述した通り、ボカロ界隈では「良い曲がもっと評価されるべき」
いわゆる「べき論」というものが蔓延っているわけなんですけども、そもそも「良い曲」ってなんやねん?って話ですよね。
音楽は点数制ではありませんし、道徳の授業に成績とか付けられなくね?みたいなことになりがちです。
無理に「再生回数=良い」みたいな乱暴で画一的な定義を設けると、世界で一番良い曲は
サメのかぞく(Pinkfong Kids)「Baby Shark」現段階での再生回数約160億 みたいなことになってしまいます(悪いとは言ってない)。
当然、時間をかけたほうが良いみたいな時給計算的な思考はアーティストとして論外ですし、「MIXやマスタリングの技術や演奏能力=良い」と定義すると、「往年の楽曲や心揺さぶるロックバンドのガムシャラさ=悪い」という図式が生み出されてしまうため注意が必要です。
ですので、この場における良し悪しを決める要素は「再生数」「独創性やセンス」「好み」「かけた時間や労力」などではないのは勿論、「音質」「技術や能力」などについても要素の対象外として話を展開したいと思います。
(音質、技術や能力がいらないとは言ってないよ)
じゃあ何?
という話ですが、この場において提唱したい定義はコチラ!
↓↓↓
良い=期待を上回る
悪い=期待を下回る
この定義に沿って検討するのが妥当ではないかと考えます。
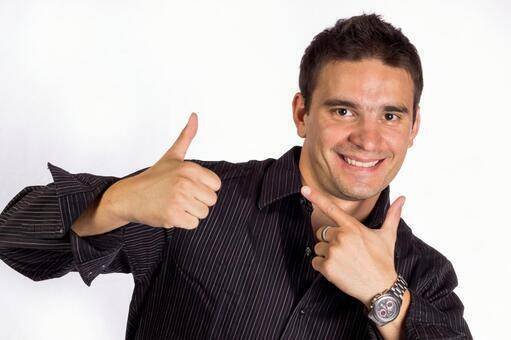
①認知(知られる)→②評価(伝わる) のプロセスを経て、 「思ったよりもすごかった!」 「驚かされた!」 「面白かった!」 などの高評価を生み出すことができたとき、他者から「良い」という印象付けがされる。
といった感じに、「良い」が発現する条件に着目して論理展開すると、楽曲の多様性を損なうことなく議論が可能です。
※自画自賛の「良い」は、共有できない「好み」として除外の対象とします
①認知(知られる)→②評価(伝わる)の2層構造が「良い」を生み出す
他者が「良し悪し」を決めている
このステップワークを簡潔に説明する公式として、
良い=期待を上回る
悪い=期待を下回る
という定義にしてみました。
「良い曲」の説明もこれに肖り、
良い曲=期待を上回る曲 と定義することとします。
ここまでよろしいでしょうか?
②「自薦他薦」は有効か?

良い曲=期待を上回る曲
①認知(知られる)→②評価(伝わる)の2層構造が「良い」を生み出す
他者が「良し悪し」を決めている
この定義を基に、界隈で賛否を巻き起こしている活動のひとつ
「自薦他薦」の有効性を考えてみましょう。
①認知(知られる)数をブーストさせる手段として、「自薦他薦」は有効に働きます。
説明するまでもなく、同業者たちに結託しようと声をかけた営業回数がそのまま認知数に直結するのは当たり前のことで、事実に即しそれを否定することは不可能です。
このあたりが、自薦他薦やった派の「聴いてもらうための努力をしてないで僻むんじゃねえダボが!!」的な発信を生み出す源になっていると思われます(テキトー)。
知らないものを評価することはできない。期待の持ちようがない。
①認知(知られる)→②評価(伝わる)の2層構造が根底的に成り立たない。
その問題を打破するために「自薦他薦」をする。
まずは知られることで評価される土俵に立つ。
その観点において、「自薦他薦」は立派な生存戦略だといえます。
が、
②評価(伝わる)を目的とした手段としては、「自薦他薦」は有効に働きにくくなります。
理由は様々ありますが、今回の定義に沿って解説すると
①認知の段階で期待値を高めすぎると、期待を上回りにくくなる
というジレンマが起きるということが大きな理由として挙げられます。
例えば、
知人から「このアルバムめーっちゃ神でマジ勉強になるから絶対聴いて?」と言われて聴いた「A」という曲。
ふとアルバムのジャケットに興味が湧き何気なく聴いた「A」という曲。
同じ「A」という曲なわけですが、
さて、期待を上回りやすいのはどちらでしょうか?
という話です。
「自薦他薦」は「薦め合う」という相互活動なので、必ず期待値が上がってしまいます。けなし合う活動じゃないですからね。
そのため、期待を上回るハードルが引きあがることにより
悪い曲=期待を下回る曲
に転じる確率が上がります。
さらに、
・「自薦他薦」に付与された界隈内の印象の悪さを被るリスク
・中長期的に伸びるリターンは特段約束されてない
・ブランディングに被害が及ぶ可能性
・過剰に営業するとミュートやフォロー解除につながる
・投稿祭やコンテスト以降、互いに死にアカ化し、非アクティブユーザーを抱えるソンビアカウントと認識されるリスク(多分考えすぎ)
などの理由も無視できません。
①認知を得る代わりに失う②評価 を鑑みると、
「自薦他薦」については、個人的に諸刃の剣だという印象を感じます。
※ダメとは言ってない。
ここで一度、乱暴に話をまとめてみましょう。
自薦他薦をすると
①認知(知られる)数が上がるが、②評価(伝わる)の難易度も上がる
=「期待される分、期待を上回りにくくなる」
自薦他薦をしないと
①認知(知られる)数は上がらないが、②評価(伝わる)難易度が下がる
=「期待されない分、期待を上回りやすくなる」
ここまでよろしいでしょうか?
③私たちはどうすればいいのか?

良い曲=期待を上回る曲
①認知(知られる)→②評価(伝わる)の2層構造が「良い」を生み出す
他者が「良し悪し」を決めている
自薦他薦をすると
①認知(知られる)数が上がるが、②評価(伝わる)の難易度も上がる
=「期待される分、期待を上回りにくくなる」
自薦他薦をしないと
①認知(知られる)数は上がらないが、②評価(伝わる)難易度が下がる
=「期待されない分、期待を上回りやすくなる」
以上の結論をふまえて、私たち活動者はどうすればいいのか?
いくつかご提案がありますので最後までお付き合いいただけますと幸いです。
※重ねていうけど「自薦他薦」はダメって話はしてないよ。
①「べき論」をやめる
「何かを悪いと云うのはとても難しい 僕には簡単じゃないことだよ」
「自薦他薦」はたくさんの人たちに知ってもらえるけど、期待を超える難しさがある。
この前提を理解すると、「自薦他薦」に対するネガティブな印象は少し過剰だと考え直せるかもしれませんし、投稿祭などの裁定基準に倣うならば、「自薦他薦」は立派な努力だと思うこともできます。
極端なことを他人に強要したり否定したりせず、自身にとって最適な活動指針を立て、自分の活動に集中するのはいかがでしょう?
②「黙る」も有効に働く
自薦他薦をしないと
①認知(知られる)数は上がらないが、②評価(伝わる)難易度が下がる
=「期待されない分、期待を上回りやすくなる」
と示した通り、実は「黙る」という行為、
「期待されない分、期待を上回りやすくなる」恩恵を多分に受けることができます。
これもまた、②評価(伝わる)難易度を下げる生存戦略だと言い切ってしまって差し支えないと考えます。
すぐに結果が出ない、苦しい活動になるかもしれませんが、中長期計画で「黙る」を選択したんだと胸を張って活動できれば、過度に比較して病んだり、「自薦他薦」をする方々に物申すこともなくなり、伸び伸びと自由に活動を楽しむことができるのではないでしょうか?
③技術や能力が高いと期待を上回れる

良い曲を決めるのは技術や能力ではないと説明しました。
それは①認知(知られる)に必要な要素ではないからであって、②評価(伝わる)ためには必要な要素です。
(ゴメンねぇミスリードさせるような言い方になっちゃってねぇ)
自薦他薦をすると
①認知(知られる)数が上がるが、②評価(伝わる)の難易度も上がる
=「期待される分、期待を上回りにくくなる」
この、「期待を上回りにくくなる」という現象、何も「自薦他薦」だけに起きる現象ではなく、知られるための活動全般についてまわるものです。
この現象を打破する方法は至ってシンプル。
高まった期待の、さらに上をいけばいい。
それを可能にするのが、日々の鍛錬で培った技術や努力です。
認知もされるし評価もされる。その理想を叶えるためにも
「毎日やんねん、ちゃんとやんねん」
結局のところ、活動者によって①認知と②評価に対するバランス感覚の相違がありますから、あまり極端なことを言わず、自分に合った活動をするのがいい。
というありきたりなお話で幕を閉じそうな今回のお話、いかがだったでしょうか?
今後開催される投稿祭やコンテストなどでしんどい気持ちになったとき、他人が羨ましくなったとき、この記事のことを少しでも思い出していただけると幸いです。
異論は大いに認めておりますので、ご意見ご感想もお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ではでは。
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
