
南波照間通信 No.4 1996. 9.16.
すべてが終わり、すべてが始まった
具志堅 邦子
すべてが終わり、すべてが始まった。
ただいま、私はワーカホリックです。「仕事」が、わたしのアイデンティティになっています。「すべてが終わり、そして、始まった」私は、何処に行こうとしているのだろうか。こんな問いなんて、二十代で処理しておきべきことだはずなのに。今頃、どかんときてしまったものだから、混乱しています。
三月まで私の「仕事」だった高校教師のことが、どっかにふっとんでしまいました。前回の流れからすると、「邦子のハイスクール放浪記②」を書くはずなのに。
いま、私は完璧なワーカホリックですから、「仕事」のこと以外語れない。
書くことが「癒し」になるのなら、ここで、たっぷり「仕事」のことを書くことがもしかしたら、この疲れからの脱却になるのだろうに。
まず、簡単なあらすじ。人生のあらすじ。
「すべてが終わり、すべてが始まった」ということは、「すべての恋愛的感情におのずと終止符を打てるコトが必然的にやってきて、恋愛的感情をいだいていたようなことに対して具現化しなければならなくなってしまった」ということである。わざと難しく言っているのだが。。。
恋愛的感情を抱いていたと思われるコトは何だったのか。学校教育?学校図書館?マンガ文化?遠い記憶では、有機農業、環境問題。それらは、本当に、私の目の前で、私を誘い、私は惹かれたようにかかわりあい、たくさんの時間を彼らに投資していた。いや、ほんとうに誘っていたのは、そのキーワードではなく、私の浮遊感覚なのかもしれないが。つまり、ちょっとばかりオシャレなオトコと雰囲気のいいお店で気分転換していたようなことを、恋愛と錯覚していたのと同じかも。こんな錯覚も行き着くところまで行くと、私のような人間にも根源的なことを悟らねばならないことが向こうからやってくるのである。そんなオトコと別れて、ほんとうに、ホれたオトコと日常的にむかいあいなさいと。比喩は素晴らしい!
やっと、そういうお相手にさよならする技術と成熟さを意識しはじめたら、突然状況が一変してしまった。
そしたら、やっぱり、三ヶ月でワーカホリックになってしまった。「恋愛」は三秒、三時間、三週間、三ヶ月、三年間だと日頃から思っていたが、三ヶ月「仕事」にホれていると、来ますね。甘美な充足感。世間から逸脱した「仕事」から来るハイな状態。その持続と賞味期間は、ナマであればあるほど、正確な振幅で来る。
それでは、その「お仕事」を紹介しよう。四月、私は無職なのをいいことに寝ていました。いくらでも、眠れました。「春眠暁を・・・」、どころではありません。病んでいたのです。こんこんと寝ていました、産婦のように。三月に修学旅行(五泊六日で生徒たちに日本の文化を凝縮した体験をさせるという無謀なイベント)の引率の緊張感と、指導要録を二日間で書き上げるというスケジュールをこなして過労で、ビョーキになっていました。
はっきりいって病んでいたのです(しかし、その間、二つのイベントを企画していました。レターカウンセリングについての◯◯君の講演を高教祖で、◯君の漫画についてのトークを‥)。
だから、五月も無職なのをいいことに寝ていました。しかし、貧乏な私は、貧乏がきらいですから、体と心は正直に休めと信号を送っているのに、「お仕事」探しをしていました。もちろん、高校教師の臨時的任用の道を。ところが、若年の就職が難しいだけではなく中年の就職も難しい沖縄では、なかなか就職できません。ぼやいていたら、友人のひょんな話の中から「仕事」にありついてしまったのです。
それは、「(財)おきなわ女性財団」というところで、「嘱託」という身分で6月から働くことになってしまったのです。
ご無沙汰しています。
残暑お見舞い申し上げます。と言いたいのだが、この時候の挨拶は正確かな。
そうなのです、現在、私は、財団で働いているせいで、時候の挨拶が正確かどうか考えるような人間になりました。本音ではこんなことどうでもいいじゃないかとはツユほども思っていません、いや少しは思っております。
ただ、どの地方の季節を基準にしたらいいのだろうか。日本って北から南まで長いし、沖縄の独自性を強調している「県」だし、なんて考えあぐねていました。
やはり、暦の上の慣例に従えばいいのだろうが、時候の挨拶のお決まりに私の季節感覚があわない。使う人にその気持ちがあれば、それはリアリティがあるのですが、私にはない。
やっぱり、文書には、時候の挨拶なんていらないのではないだろうか。で、情報化社会だし、要点がすぐ分かる文書のほうが親切だと思い、省略したら、ここが、私の認識の甘かったところでした。
オヤクショの「お仕事」では、このことがたいへん重要なことの一つなようなのです。県の外郭団体ですが、オヤクショですので、このような、私の論理は少しも通りません。まして、立て割り行政の感性に最も遠い個性の私であり、事務能力のない私ですから、オヤクショ的になれません。起案文書は未経験。「嘱託」というのは名ばかりで、地位・役割は使い捨てのアルバイトなのに、起案文書作成を命じられました。そしたら、私が作成した起案文書に、たっぷりの添削入りの起案文書が上司から戻ってきた。企画の内容ではなく、時節の挨拶がないということで。。。
また、電話の応対も、県民からの電話と県のトップぽいところからくることが多い。慣れていない。知事公室長と知事公舎を間違えて「知事公室長から電話下さいとのことです」と館長に伝えて、館長は知事公室長に電話をいれる。知事公室長はそんなことを言った覚えが無いとのことで、館長に恥をかかせてしまいました。これを笑える人は、人の不幸が嬉しいのか、おおらかな人でしょう。今の私は、他人がこんな失敗したら、同情はするが、こんな人のお仲間にはいるのは遠慮したいなと思う。そんなこんなで、毎日毎日が、張りきっていて、ハリ・針の筵。そのなかで、バリ、バリにお仕事を三ヶ月してしまったから。当然、バランス失ってしまった。
しかし、担当が事業部門で、講座やイベントの企画なものですから、好きな分野なのでつい力が入ってしまって、「仕事」以外は、何もしたくない、「仕事」以外、何も見えない、本も読む気がしない、お酒に誘われても気が進まない、家に帰って家族に向かうのもゆとりなくしてしまうという、そんな状態になってしまった。
実は出だしの「ただいま、私はワーカホリックです」と宣言の言葉を書いてから、今、一週間以上たってしまっています。ほんの四・五日前に次のようなことを確認してしまってから、日毎に回復していきます。基本、ゲンキンなのです。
企画した「保育ボランティア養成講座」が成功したこと。
「てぃるる女性学講座」が順調にすべりだしたこと。
私は無能なのではなくて、オヤクショの「仕事」に慣れていなかっただけなのだということがわかったこと。
県からの出向職員に慣れたこと。
そしたら、急に開き直ってしまい、「肩書き」と「形式」と、「女性学」と「フェミニズム」と「ジェンダー」が渦巻いている空間の中で、四十二年間の人生、テンネンに純粋培養されていた私の人生の何かが、醗酵しようとしはじめたのです。
すべてが終わり、すべてが始まったのです。
ちなみに、九月二十五日に四十二歳になります。

WHAT'S「文化行政」?
具志堅 要
残暑お見舞い申し上げます。
去年の十一月に突然、那覇市の国民健康保険課から文化振興室に部署替えになりました。お・気楽に引き受けたのですが、脳細胞は一八〇度ぐらい向きを変えられたので、しばらく混乱を引きずっておりました。
国民健康保険の窓口はどちらかというと制度から振り落とされた人々が対象の窓口でした。平均以下の生活を強いられるか、そういう現実に直面せざるを得なくなった人々が対象のほとんどでした。文化振興室で出合うのは、平均以上の人達です。
そこでしばらく暢気に文化とはあるいは文化行政とはなにかというふうなことを考えておりました。その結果徐々に僕の脳細胞に判明してきたのは、文化振興室が行っている事業は文化振興ではなく芸術あるいは芸能の振興ではないのかということです。
絵画・彫刻・演劇・音楽などは、すべて芸術表現の分野に含まれるものと思われます。行っている事業にせよ、接触する市民との話し合いにせよ、すべてそういう分野を振興することを前提に予算化したり、話し合いがもたれているような気がします。
芸術も当然文化の領域に含まれますが、それは文化の領域の一分野を占めることにすぎないことはあきらかでしょう。たぶん現在行われている文化行政は順序が逆なのであって、まずは文化振興を図るべきであり、母体になる文化自体の水準が上がれば、当然芸術の分野もその土台とともに豊かな振興が図られるものと見なければならないでしょう。
文化という言葉の意味には①世の中が進歩し文明になること。②文徳で民を教え導くこと。(以上『広辞苑』より)という語義の他に、cultureという英語を訳した語義があります。そちらの語義が文化という言葉の意味として常用されているものと思われます。
cultureとはなにかというと、いわゆる日本語の文化という意味とともに耕す・栽培する・飼育するなどという農業や畜産業の分野の言葉としての意味も持っています。そこから派生して文化という概念ができあがったようです。
そこから考えられるのは、歴史の時代が狩猟採集の時代から農耕・牧畜の時代に移ったときにできあがった言葉だろうなということです。あるいはその印象を保持した状態の言葉だろうなということです。
cultureは生産方法と生活様式が同じ意味であり、両義を兼ねてもかまわない時代にできあがった言葉だろうという推測ができます。では、その時期の生産とはどのようなものであったのか。
「常陸国風土記」の行方郡の部のなかにその印象を探るのにふさわしい挿話があります。
「継体天皇の時代に麻多智またちという人がいた。この人が郡役場の西方にある谷を占有して、ここを開墾して新たにを開いた。この時、夜刀(やと)の神が群れをなし、仲間を引き連れて、あれこれとさまざまな妨害をし、田の耕作をさせなかった。夜刀の神とは頭に角のある蛇のことである。麻多智はたいそう怒り、武装して夜刀の神を打ち殺し、追放した。それから山の登り口にやってきて、標識として大きな杖を境界の堀に立てて、夜刀の神に告げた。『ここから上は神の土地とすることを許そう。だが、ここから下は人間の田とする。今後私が神主となって祀るので、祟らないでくれ、恨まないでくれ』と言った」(具志堅意訳)。
この挿話からうかがいしれるのは、土地の開墾は初期においては神々との戦いであったということです。夜刀(やと)はアイヌ語で沼沢を意味するヤチのことで関東周辺では谷の字をあてます。
つまり、夜刀(やと)の神は谷の神であり、本来この谷の所有者でした。開墾するという行為は、神の所有するものを侵略するという行為でした。ここに言葉さえあれば耕作という行為と祀るという行為が両義で表現できるでしょう。
日本において文化という言葉の意味を考える時、生産に関する要素ははぶかれます。祀るという要素からその語義を考えることができるでしょう。祀るという行為からは、祈る・踊る・歌う・演ずる・描くなどの行為が派生します。それぞれの要素が芸能・芸術へと特殊化されていきます。その発達していくエネルギーは、生産への喜びとともに神の領域を犯すことへの恐怖を源泉としていました。
文化の結果としての芸術ではなく、芸術を産み出す原因となる文化を考える時、喜びと恐怖の両義を、現在においてどのように捉えることができるのかを考えなければなりません。
すでに生産は具体性を持たず、神は見失われてしまった現在においてです。そのためには私たちが日々の暮らしの中で、何に喜びを感じ、何に恐怖を感じるのかを見極めなければなりません。
行政においては、各種市民層の個別的な分析が必要です。市民が直面している喜びと恐怖へのその答の出し方の中に文化行政はあるといえるでしょう。恐怖に打ち勝つ喜びへの答が見つかった時に行政は自ずと文化化し、芸能が現在によみがえり、芸術は生活を癒すものとなるでしょう。
逆な方面からアプローチする場合は、現在すでにある芸術と芸能を育成することが、とりあえず必要です。その次に、いまだに文化として公に認知されていないサブカルチャーを公認することが必要です。
サブカルチャーとは、絵画・文学に対するマンガ、古典音楽に対する歌謡などその時代において公認されてはいないが、大衆の支持を受け続けている文化を言います。へたに公認してしまった場合、その源泉となるエネルギーを枯らしてしまう恐れもありますが、大衆の支持を受け続けているということの中には、単に欲望に流れているということだけではなく、大衆の直面している問題に応えている面も当然含まれるものと思われます。この豊かなエネルギーを利用しないというのは、もったいない話です。
その次には、サブカルチャーにさえもいたる前の大衆の欲望を把握し、分析することが必要です。欲望や暴力は人間の持つ本能のひとつでしょう。共同体社会においては婚姻前の通過儀礼の中でその本能を馴致させ、逆に共同体の維持に役立たせました。
また、祭りや芸能の場において、その力を昇華させ、美にまで高めました。そのような共同体の装置を持たない現在の都市生活においては、そのエネルギーは無目的・野放しのものとなり、あてもなく奔出します。欲望や暴力の持つエネルギーの道標をつけることはできないでしょうか。欲望や暴力が循環できる道標ができたとき、都市は共同体崩壊後の社会を受け継ぐことができるでしょう。
以上ばくぜんとそんなことを考えています。具体的なことは、まだ何も思い付きません。しばらく考えている中で身体も動きだしてくるでしょう。
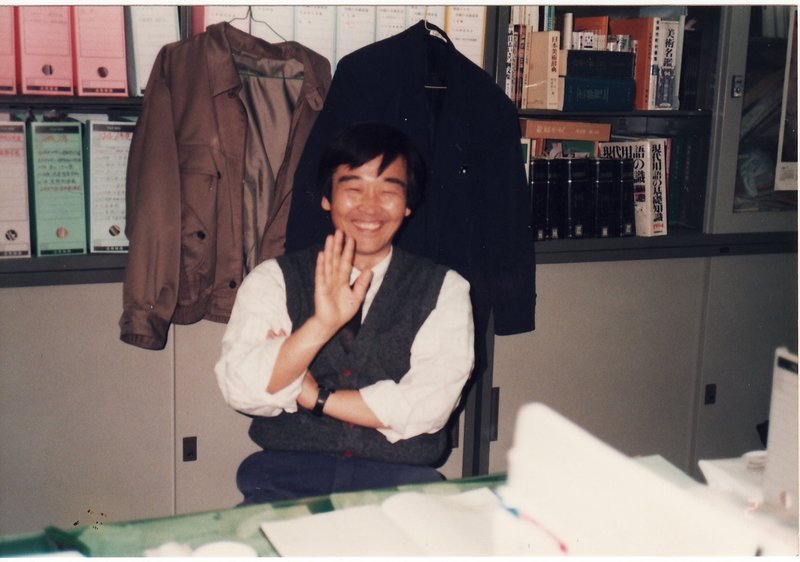
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
