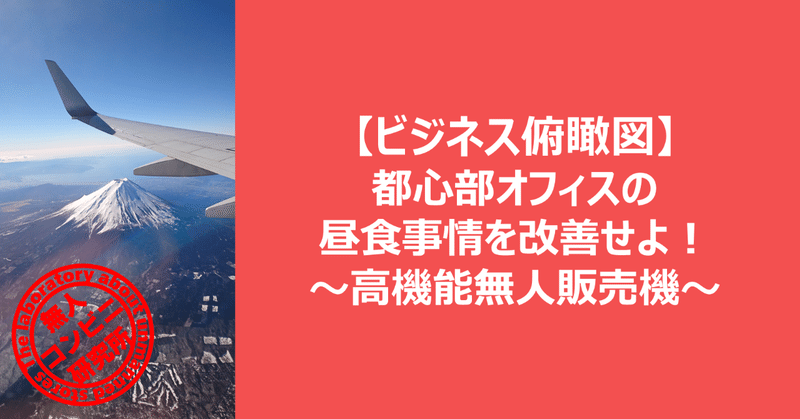
【ビジネス俯瞰図】都心部オフィスの昼食事情を改善せよ!~高機能無人販売機~
オフィスの昼食事情は特に東京都心部においては非常に深刻になっています。お店の数はそれほど少なくなくても、「1時間」という短い時間の間で移動+待ち+食事の時間を全て賄わなければならないとなると、自動的に普通に「お店で食べる」という選択肢の優先度が落ちます。
こうした事情に対してこれまでの歴史の流れと、無人販売機がどう貢献できるのかを考察してみました。
■まず最初に生まれた仕出し弁当
オフィスにおいて食事をする方法はいくつかありますが、一番簡単なものが出前です。ただ、出前をオフィス単位でできるものはない…という発想から生まれたのが「仕出し弁当」です。
仕出し弁当は予め取りまとめをする人(大体総務の人)が決められ、その人が「今日お弁当食べる人~」と言って集めた注文を弁当屋に発注、弁当屋はそれを見越して作った弁当を取りまとめ役の人に届けるというサービスです。弁当の種類は日もしくは曜日で決められていて、好き嫌いで購入数も変わるというもの。
このサービスが成り立つためには「受け取る人(≒取りまとめる人)」の存在が必須です。先払いの無人販売のように見えますが、実際は「弁当屋が受取人に弁当を販売し、受取人の責任で弁当を各人に配る」というビジネスモデルになっています。こうしないと保健所が怒り出してしまうので体裁上こうなっているのですが、実際は弁当屋が指定された場所に置いていくモデルも多く、その結果食中毒なんかが出ると弁当屋ではなく受け取った人が怒られたりして結構適当なモデルでした。
そうなると会社として弁当の食中毒リスクを管理することになり、それを嫌うところから次第にビジネスは縮小していくことになります。
■難しかった自販機による昼食需要の解消
もう少し簡単で責任がないやり方はないものか…こうして生まれたのが「自販機による昼食販売」です。冷蔵が可能で購入目的ではない消費者が勝手に触ることができず、かつ簡単に購入できるもの…物販自販機を使って販売する方法が生まれます。
自販機であればカップラーメンなどの簡易食品も販売できますし、販売タイマー&冷蔵機能付きになればおにぎりやサンドウィッチなど冷温保存が必要なものも売れる…開始当初は「ASD(Automatic Super Deris)」と呼ばれ、飲料自販機と併設しオフィスの簡易ショップ的な位置づけとしてスタートしました。最も有名なのはファミリーマートさんの自販機。発表当時はおにぎりや一部弁当の写真も自販機の中にあり、結構期待したことを覚えています。
ただこのサービス、その後鳴りを潜めます。販売タイマーが付いた自販機が高額であること、そして手痛いのが弁当を入れようとしても販売時に落下するので種類が大幅に制限されることでした。事実上弁当販売は諦めざるを得ず、おにぎりとサンドウィッチの販売にとどまるものばかりとなりました。それでも売れる場所になると一般的な物販機の倍ぐらいの売り上げだそうですから、一定の成功は収めているようです。
副産物として「物販機で簡易食品を販売する」簡易型の食品自販機が生まれたこと。有名なのがブルボンさんの物販機「プチモール」ですが、長期保存パンやカップ麺、カロリーメイトなど、とりあえず短時間で食事ができるものが販売され、オフィスにポットが置かれるようになったのもASDがスタートしたからと言っても過言ではないかもしれません。
■出張弁当販売サービスの隆盛と課題
こうした中、「弁当を買いに行くのが難しいなら弁当屋がくればいいじゃない」という発想で生まれたのがお弁当の出張販売サービスです。フロア人数に依存しますが、休憩所などのスペースにお昼になると簡易店舗を開き、そこで直接弁当を売ってしまおいうというもの。人が売るので制限がなく(実際にはあるのですが守られているのを見たことがな…ゲフンゲフン)、種類も豊富なので非常に便利です。1人付けるだけでかなりの量の弁当が「確実に」売れるので売る側も嬉しいし、総務側も責任を全て業者に押し付けられるので嬉しい…と良いことづくめなのです。
が、残念ながら大手企業のオフィスに限定されます。それなりの売り上げが必要な業者側と、とはいえ管理が必要な企業側からすると、複数企業がいるフロアで共同で管理というのはなかなか難しく、これも決定打としての解決策にはならないというのが実情です。
■登場が待たれる無人販売機と越えるべき壁
自販機の良いところどりをしつつ、人件費がかからず売り上げがそこそこあれば回る仕組みがあればな…と思う人が真っ先に思い浮かぶのが「無人販売機」です。一番有名なのは無人コンビニ600さんでしょうか。あれで弁当が売れれば解決しそうな感じです。自販機と異なり単なる棚なので積み上げが可能ですし、ショーケースと違って認証がないと買えないので特定の人以外商品に触れず、販売時間を設定できれば問題なし。これであれば無人販売可能で、そこそこの需要でも十分回るのではないか…。
ただ、この話が実現するのにはまだまだ越えなければならないハードルが多々あります。
最初にぶち当たるのが「冷蔵保存可能な弁当を作らなければならない」ところです。無人で売るためには「冷蔵保存しても雑菌の繁殖が問題ない状態に維持できる」ことが必要であるため、この検査をクリアする必要があります。もちろんコンビニ弁当などはすでにクリアしているので問題ありませんが、通常の弁当事業者がこれを行うのは難しいのではないでしょうか。
次に直面するのが「配送」。自販機のオペレーションでも高層オフィスは最難関地区の1つとされており、特に飲料と違って「昼までに補充できなければアウト」という制限下で進めなければならない物流については根本的な解決方法がないと結局人海戦術に頼らざるを得ず「じゃあ出張販売で良くね?」となりかねません。
そして最も大きいものが「日本では機材がない」問題…え?さっき無人コンビニ600さんを事例に出さなかったかって?…いえいえ、無人販売機はありますが「保健所の認可を受けた」機材は今のところありません。自販機はすでにその認可を受けており(許認可的なものではなく、どちらかというとお墨付き)、販売自体には問題が発生しませんが、日本では事例も申告もないため今のところ自分で保健所とやりとりするしかないのが実情です。
■それでも目指すべき「オフィス昼食難民の解消」ビジネス
いろいろと苦言ばかり言っていますが、それでも私はここの事業領域(いわゆるマイクロマーケット市場)は非常に有望だと思っています。お昼は選択し多くリッチに食べたい、でも時間は足りない…という需要は今後増えることはあっても減ることはないと思うので、ここで何か確立されたビジネスモデルを生むことができればかなり大きなビジネスになると思われます。
こうしたエリアでの動きはいくつかあるようですが、果たして誰が先頭を切るのでしょうね…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
