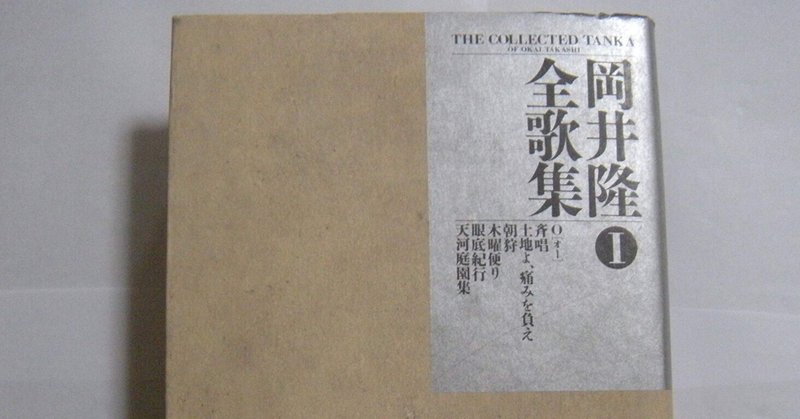
【評論】やがて傍観者の視座へ ~岡井隆『土地よ、痛みを負え』を読む~
2022(令和4)年2月、ロシアはウクライナに侵攻した。その戦況は主にSNSなど、様々なメディアを通じて我々の目に刻一刻と飛び込んでくる。そのさなか、2月24日のツイッター上に一首の短歌が投稿され、反響を呼んだ。
戦争を始めた人が飼っているおれの故郷のうつくしい犬
「戦争を始めた人」とは、他ならぬウラジーミル・プーチンであり、「うつくしい犬」とは、2012(平成24)年に秋田県からプーチンへ贈られた秋田犬のことだ。「おれの故郷」という言葉の意味合いを最大化しながら、エモーショナルな訴えかけで侵略行為に抗議する姿勢は、ツイッター上で多くの共感を得た。現在の日本において、戦争の傍観者の視座として、できうる限りの反戦へのメッセージがこの短歌には込められているだろう。
岡井隆の第二歌集『土地よ、痛みを負え』は1961(昭和36)年2月に白玉書房より出版された。時期的には1956(昭和31)年頃から1960(昭和35)年頃までの約5年間の作品が所収されている。刊行から60余年の時が経過した本歌集は、岡井隆の前衛短歌運動時代の記録でもあり、また当時の時勢を反映したのであろう社会詠も多い。歌集の序盤では、当時世界各地で起こっていた戦争や市民運動にまつわる歌稿が少なからず存在感を放っている。
ブダペスト市街に精悍の牡牛率て一塊のパン・水にありつく
市民兵の最後を聴けり誰よりも低き後方に席を移して
死ぬべきは我らならずやと問うときのいまだ戦闘を知らぬ唇
1956(昭和31)年10月、旧ソ連の衛星国だったハンガリーで、親ソ政権に対して蜂起した市民と、軍事介入を行ったソ連軍との間で戦闘が起こった(ハンガリー動乱)。結果、動乱は鎮圧されハンガリーの民主化は30余年後のソ連の崩壊まで持ち越される。
状況こそ違うが、現在のウクライナの情勢とほぼ同様の構図の紛争を、若き歌人岡井がかように見ていたことを反映する歌群である。一首目、作中主体はハンガリーの首都であるブダペストにいて、その土地の人間としての実感を獲得すべく存在している。岡井は前衛短歌の手法のひとつである虚構を通じて、自らの戦地への思いを作中主体に仮託し、戦争に対しての当事者意識を高揚させていることが読み取れる。
二首目、初句と二句目は、おそらくは市民兵の死を、ニュース映画を介して体験したのであろうか。三句目以降の「後方に席を移して」という作中主体の映画館での行動を通じて、安全圏である日本におり、戦地に対して何もできない忸怩たる感情をありありと読者へ伝える。
三首目、太平洋戦争において岡井は兵士として戦地を知らなかった世代である。当時、終戦後11年を経過した後もなお、外邦には戦地があることに対し、死ぬべきは戦争を経験しつつも、戦闘を知らずに生き延び、かりそめの平和を享受し生きる我々なのではないかと、自己欺瞞を抱えた作中主体の、複雑な戦争への当事者意識が吐露されている。
今日に生きる日本人のほとんどが、戦後70年以上が経過した現在、戦争についての当事者意識は希薄となった。無論それは理想的な状況である。本稿の冒頭にあげた歌の作者である神丘についても、現在の日本人という傍観者としての立ち位置からの戦争を詠むことを通じて、反戦の意思を明確にすることは正しい態度だと感じる。
翻って岡井の本歌集における序盤の戦争詠は、広義の反戦意識というよりは、傍観者となることを許容せず、自身の意識の中に戦争を、当事者として引き寄せているかのような詠みぶりであることに気づく。それは、岡井が当時傾倒していた左翼思想が多分に影響しているからであろう。本歌集に所収されている序盤から中盤にかけての連作にもその思想性は色濃く反映されている。
つややかに思想に向きて開ききるまだおさなくて燃え易き耳
どの論理も〈戦後〉を生きて肉厚き故しずかなる党をあなどる
何となく戦機うしない嗅ぎあいおる羆を腹の底から…… 愛す
甲虫の叛乱、つねに少年は支配者にして傍観者
一首目は「つややかに」と、美しさを寿ぐような初句から少年の耳に入るのであろう思想と、イデオロギーへの憧憬が、前衛短歌の手法によりあざやかに演出されている。二首目は、おそらく同時期に岡井自身の左翼思想の拠り所でもあった共産党を、作中主体は揶揄しているのだろう。
武装闘争には武器が必要。それに武器を操作できなくてはならない。ところがそんなもの何ひとつなく、山村にただ入り込んで人民を教育せよという牧歌的なことを共産党は考えていたのですよ。あれはねえ、「ごっこ」なのですね。
この後年の小高賢との対談での懐述の通り、岡井自身が武装闘争に本気でありながらも、日本共産党の消極的な姿勢に大きな失望があったことが読み取れる。岡井の前衛短歌運動とともに熱を帯びた視座からの闘争への渇望は、連作「思想兵の手記」のころから徐々に失われていくように見える。
岡井の中に燃えていた左翼思想の翳りを、三首目の闘うことなく互いを嗅ぎあう羆たちの姿が、作中主体の闘争からの後退を可視化している。そのさまを躊躇いながらも「愛す」という逆説的な自虐に寂寞が漂う。
四首目ではあれほど希求していた叛乱をカブトムシのことを見やる傍観者である少年の視座までと、作中主体はついに卑下してみせるのである。本歌集の中盤より終盤にかけては、前衛短歌の手法とは対照的に、難解ではない比喩を用いて作中主体の実感を表現した歌が散見され始める。それはちょうど、岡井が北里研究所の医師として、医学研究に没頭し始める時期と重なる。
ゴム手袋鳴らしつつ脱ぐ夕まぐれ何よりも鋭きメスをわが持つ
家兎の眼に熟れてゆく死よ少年の遺骸のごとくわれは惜しまん
かすかなる仮説といえど僚友のごとき十幾匹を犠牲とせし後
一首目は、作中主体が医師としての一日を終える光景が素直な詠みぶりにより立ち上がる。「何よりも鋭きメス」という仕事道具に担わせる不穏さと、実景のリアルな手触りがストレートに伝わる点が、まだ左翼思想的な着想からの歌が大勢を成していた連作「思想兵の手記」の中にあって異彩を放つ。
二首目と三首目については、作中主体の実験動物への思い寄せを、直喩を用いながら動物の命を奪うことに対する感情を直接的に詠んでいる。職務上のこととはいえ、己が扱う実験動物の命へのまなざしは、おそらく左翼思想に傾倒していた頃の岡井の作中主体とは明らかに変容していることが見てとれる。
連作「土地よ、痛みを負え」以降の歌群は、岡井の医師としての職業的生活が、左翼思想の剥落と時を同じくして、前衛短歌の手法から、岡井の短歌的出自である、アララギ的な手法へ回帰してゆく契機となっているようだ。これは歌人・岡井自身の中で作歌の動機となるものが、イデオロギーへの失望を経て、生活に密接する医師としての素朴な生命倫理によるものが次第に優位となったことの証左ともいえるだろう。本歌集最終盤の連作「勝ちて還れ」では、自身の左翼思想との決別を宣言するかのような歌稿が目を引く。
キシヲタオ……しその後に来んもの思えば 夏曙のerectio penis
強硬に日米安保を推進する岸政権と、それに抗う学生のデモ隊の衝突は、 1960(昭和35)年6月15日、東大学生の樺美智子の死という、悲劇的な事件を起こすことになる。「夏曙のerectio penis」という一見騒乱とは無関係な、いかようにも解釈可能な比喩表現をしながら、離れた位置から冷静なまなざしを向けていることが読み解ける。
鉱のごとき体がひしめきて犠祭せり 六月・日本
おそらく樺美智子の追悼集会を目の当たりにした際の一首であり、「六月・日本」という結句が導く日本という国をも客観視する態度が感じられる。そしてこの歌が歌集の掉尾を飾る一首であり、儚く日本を案じつつも、当事者ではなく事態を傍観する視座でしか社会を詠うことができない、当時の岡井の歌人としての諦念を象徴しているように思える。
旗は紅き小林をなして移れども帰りてをゆかな病むものの辺に
じりじりとデモ隊のなか遡行するバスに居りたり酸き孤独嚙み
岡井の師である近藤芳美は、当時の歌壇において社会に対する傍観者的立場を貫く代表的な存在であった。前掲の二首を読んだ近藤は岡井に「君もぼくと同じだね」と笑ったという(岡井隆『瞬間を永遠とするこころざし』2009)
巷間は安保闘争の只中であったが、当時の岡井は博士論文を完成させるために研究に邁進していた時期であり、その自分の立ち位置から、かつて左翼思想に傾倒していた頃の自分を遠望しているようだ。一首目「移れども」、二首目「酸き孤独」の語には、安保闘争に加担できなかった作中主体の、若干の自己批判と悔恨のニュアンスも見てとれるが、この連作「天の炎」では社会の動きに対し、傍観者の視座を獲得している。
ここに至り、岡井が左翼思想を仮託した本歌集序盤の前衛短歌の表現群と、生活としての医師の研究にのめりこむことを素朴に語る中盤以降の表現群のグラデーションがクリアに見えてくる。それは、複層的にあるレイヤーでは「左翼思想への希求」から「傍観者としての生活」への変容の過程を示し、別のあるレイヤーでは「好戦的な態度」から「生命を重んじる態度」への変容の過程を示している。かように流動的な構造のため、本歌集を通読したとき、作品の背後に「ただ一人だけの人の顔」を浮かべることは困難かもしれない。ただ、岡井が遺した数多ある文献・資料から時代背景と彼の遍歴を手がかりとして丁寧に読み解くことで、戦後、闘争への希望を抱いた一人の歌人が、現代にも通ずる傍観者としての視座を獲得した過程が、リアリティをもって迫ってくるのだ。
〈了〉
初出:『短歌人』2022年7月号/短歌人評論・エッセイ賞佳作作品
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
