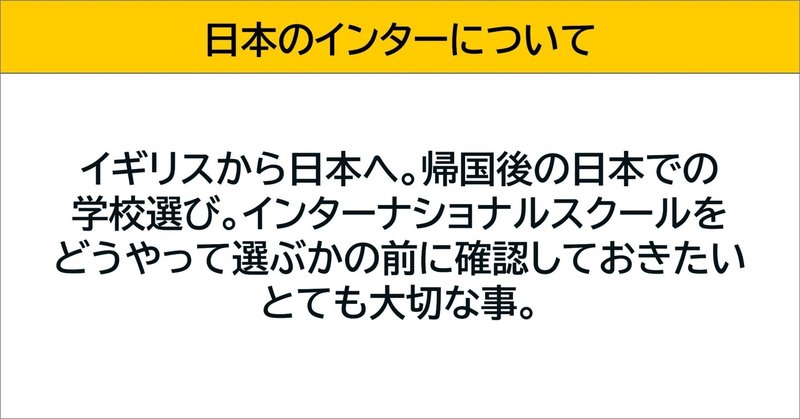
イギリスから日本へ。帰国後の日本での学校選び。インターナショナルスクールをどうやって選ぶかの前に確認しておきたいとても大切な事。
お父さんです。
このブログは地元の公立中高で学び、地方大学を卒業した庶民派お父さんがひょんなことから子供二人の都内私立小学校受験を経て、またまたひょんなことで子供たちがイギリスのボーディングスクールに合格するまでの道のりを綴っています。
今回の記事について
今回はイギリスから日本に帰国する時の学校選びについて書きます。前回の記事では色々と検討した結果、インターナショナルスクールを志望する事を決めましたが、今回はその学校選びの具体的なプロセスの前に確認しておきたい大切な点について書きたいと思います。皆さんの参考になれば嬉しいです。
■卒業時の資格及び、なぜインターナショナルスクールなのか
ここは大切なポイントの一つですが、大学進学を前提にするのであれば、大学進学に向けて、学校がどのようなカリキュラムを提供しているのかの確認は非常に大切です。日本の大学に進学するのか、もしくは海外の大学に進学するのかを念頭に置いて、そのために必要なカリキュラムに対応しているのか、もしくは卒業時にどのような資格が得られるのかを確認した方が良いと思います。
具体的には、インターナショナルスクールは文部省で認可された学校ではないので「高卒資格」が得られません。いわゆる文部科学省の定めている、「一条校ではない」という事です。その意味ではインターナショナルスクールは、「外国人児童生徒を対象とする教育施設」という扱いです。最近は巷でもインターナショナルスクールが流行っていると聞きますが、私自身は個人的にはちょっと違和感があります。自分自身が親としてインターナショナルスクールに子供を通わせておいて言うのも恐縮なのですが、我が家の場合は日本の学校とイギリスの学校に通った結果、「ウチの子供にはインターの方が合っている」という結論に至りました。そのプロセスは過去の記事にも書きましたが、色々と悩んだり葛藤したりした事も少なからずあり、簡単な決断ではありませんでした。その意味で「これからは英語ができないとダメだから」という、僭越ながら短絡的な考えでインターナショナルスクールに子供を通わせるのはどうかなと思います。次回以降の記事で書こうと思いますが、いわゆる「ただのバカなインター生」は我が家の子供たちが通う学校にもいますし、そもそも英語をロクに話せない子供たちもいます。インターナショナルスクールは「英語を学ぶ学校」ではなく「アメリカやイギリスなど海外の教育プログラムに沿って英語で学ぶ学校」にも関わらずです。
その現実を踏まえたうえで、本当にインターナショナルスクールに子供を通わせるのが良いのか考えるべきだと思います。
とても重要な点を下記の文部科学省のホームページから引用します。結論から言うと、インターナショナルスクールに子供を通わせる事は、
「親は子に義務教育を受けさせる義務を履行した事にならない」
と書いてあります。私は昔に中学での授業で「憲法で定められた日本人の三大義務は、納税・教育・勤労だ」と学びましたので、その一つを果たしてない事になるのだなぁとしみじみと考えました。
この前提はインターナショナルスクールを検討をする際にしっかりと考えた方が良いと思います。我が家もこれを見た際には、妻にも見せて一度冷静に考えました。
Q 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合、保護者は就学義務を履行したことになるのでしょうか。
A いわゆるインターナショナルスクールについては、法令上特段の規定はありませんが、一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられています。インターナショナルスクールの中には、学校教育法第1条に規定する学校(以下「一条校」といいます。)として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する各種学校として認められているか、又は無認可のものも少なからず存在しているようです。
一方、学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。
学校教育法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。これは、同法第45条に規定しているように、中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としているからです。
このことを踏まえると、例えば一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望してきても認められないこととなります。インターナショナルスクールの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様です。なお、市町村教育委員会におかれては、憲法に定める教育を受ける権利を保障し、その権利を実現するために義務教育制度が設けられていることに鑑み、経済的な事情、居住地の変更等のやむを得ない事情により学齢児童生徒が実際的に未就学となるような状況が生じないようご留意ください。
より具体的には、大学進学を検討する際に、もし日本の大学を受験する場合はインターナショナルスクールは「高卒資格」が得られないので、受験資格がそもそもありません。その場合どうするかというと、IB(インターナショナル・バカロレア)と呼ばれる国際認定試験を受けて臨むのが一般的です。
もしくは日本の大学には出願せず、海外の大学だけを受験するという選択肢も主流の考え方としてあります。サマリーをすると、
①日本の大学を受験する場合:
IBなどの国際認定試験を受け、IBでの受験に対応している大学を受験する。
慶應やICUなどは対応している学部もあるようです。ちなみに慶應大学のHPには以下の記述があります。基本的には受験資格が無いようですが、法学部だけはIB受験を受け入れています。(下記の入学資格概要を参照)
Q:日本国内に所在するインターナショナルスクールを卒業した/するのですが出願資格はありますか?
A:ありません。出願資格の共通条件①における「海外において外国の教育課程に基づく高等学校に最終学年を含め2年以上継続して在籍し卒業」という条件のうち、「海外において」という点を満たさないためです。なお、卒業した/するインターナショナルスクールで学ぶ以前に海外での就学経験がある場合は、経済学部・商学部の学部別条件(共通条件①に代わる条件)を満たすかどうか確認することを推奨します。

東京大学などの主要国立大学の場合は、海外の高校に通っていればIBでの入学・受験資格はあるようですが、「国内のインターナショナルスクール」に通っている場合は基本的には受験資格が無いようです(本日現在。日々条件は変更されるため要確認です)。
②海外の大学を受験する場合:
最初から海外の大学だけに絞る。欧米の主要大学は、ほぼIBでの受験に対応しています。加えてTOEFL iBTや IELTS Academic Module、SATの提出が必要な場合もあるかと思いますが、基本的にはこちらがインターナショナルスクールに子供を通わせて大学進学まで考える場合の主要な考え方なのかなと思います。
加えて、日本の学校とインターナショナルスクールの簡単な比較も以下に追記しておきます。

今回はインターナショナルスクールに子供を通わせる前に、そもそもインターナショナルスクールの立ち位置および考えた方が良いと思う事について書きました。それでもやっぱり
「国内の学校ではなくインターナショナルスクールが良い」という判断をされるのであれば、もちろん良い選択だと思いますし、我が家の場合も色々と家族内で議論をしてそのような結論に至りました。ただあまり深く考えずに最近の流行りだからと言って安易な決断をするのは、後々の後悔に繋がる事もあるので、ぜひ一度冷静に考えてみていただければと思います。
今回も長々と書いてしまいました。いつも記事を読んでいただきありがとうございます。皆さんの参考になれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
