
陶山研吾さん - 新たな種を探す人
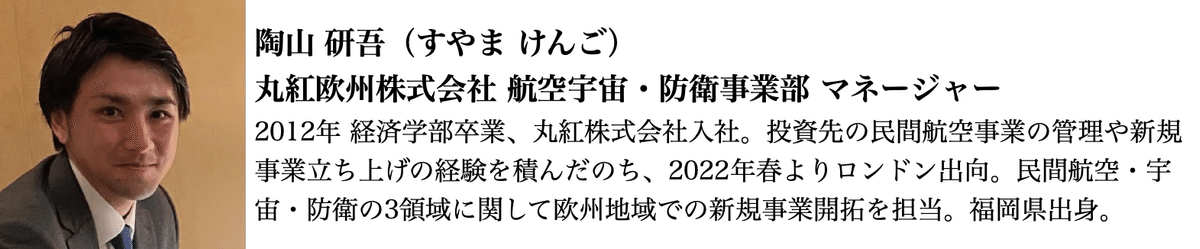
航空に関わるビジネスに惹かれ商社へ
新卒採用活動の時には、分かりやすいモノに関わる仕事がしたくてエアラインやメーカー等も幅広く志望しました。しかし経済学部で経営のゼミにいた私は、飛行機を動かすパイロットでも、商品を設計するエンジニアでもなく、ビジネスが本分である商社でいちばん大きく貢献できるのではないかと考え、最終的に就職を決めました。
いくつか志望した中の希望が通り民間航空分野の部署に配属されました。商社というと、表舞台で売り買いをするトレーダーのイメージが強いかもしれませんが、私が最初に任されたのは営業部内の投資先管理の仕事でした。投資先の会社10社ほどの事業計画の作成や与信設定、運転資金をいくら使いたいかという承認を本社に取り付けるための資料作成などです。
そこで、投資を通じてどのようにビジネスを大きくしていくか、会社を買った後に何を考えるか、何をしなければならないかなどについて詳しくなり、あくまで商社の中での会社運営については一通りのことが分かるようになりました。
投資先への出向で学んだこと
3年目からは、投資先の会社の現場に出向して稼いでくる仕事をするようになりました。赴いたのは、世界約50カ国で展開しているグラハン*の会社・スイスポートです。
*グランドハンドリング(Ground Handling);航空輸送における空港地上支援業務。専用車両を使って航空機旅客スペースの床下部分に搭載される貨物や手荷物の搬出や積込みを行う。

最初の半年間はアメリカのワシントンDCの拠点に出張ベースで出向いて現場研修を受けました。前半3ヶ月は機材調達・営業・経理・人事などの各バックオフィスの部署を巡り、後半は空港の現場でチェックイン業務や荷物・貨物の搭降載、給油などの実務を学びました。
エアライン各社からの受託で業務を引き受けるグラハンの会社はいくつもあります。契約は通常数年程度で、その更新のタイミングが新規売り上げ獲得のチャンスでもある一方で、既存の取引先に競合他社に切り替えられてしまう可能性もある世界です。
アメリカではいろいろと日本とのカルチャーの違いを感じましたが、特に労働慣習は大きく違いました。例えば、ひとつの契約が取れたらそこからサービス開始までの数ヶ月で採用・研修・機材の調達までをする日本のケースとは異なり、アメリカではレイオフが簡単なので、仕切る会社が変わったらそこで働いていた人たちを丸ごと引き抜くようなことができてしまいます。様々な国籍からなるスタッフは組織に対するロイヤリティも低く、仕事はよく言えばフレキシブルですが、悪く言えばいいかげんなものになります。
海外の人から「日本の仕事はなぜそんなに進みが遅いのか」と問われた際に、それはロスバゲなどのエラーが起きないこととセットなのだと、背景に踏み込んで説明できるようになったのは、海外の現場を知って得た力の一つです。
専門性の追求に喜びを感じていた頃
スイスポートジャパンに本配属になってからは、社長直属の部署で新規事業・プロジェクトを担当しました。当初、スイスポートは成田・中部・関空の3つの空港に拠点を持っていましたが、まだ立ち上がって間もない会社だったため、成長途上でぶつかる機会・課題を見つけてはそれに対応するためのプロジェクトチームが立ち上がり、その担当をするものです。現場に張り付く中で目を凝らしていると、機内清掃業務のフローの変更や空港内バスのドライバー不足など、小さな機会はたくさんあり、それが新しいビジネスに繋がりました。
思い出深いのは、某エアラインの羽田空港での仕事を受託した時の仕事です。事務所のないところから、50〜60人を採用し機材も新たに調達するなど、社内で誰もノウハウがないところから、空港に通い詰め、国土交通省への許認可申請も進め、現場マネージャもスイスから一人応援に来てもらい3ヶ月でビジネスを立ち上げました。航空業界や事業に対する知見を深め、その道のプロに近づいていくことに自信と喜びを感じていた時期でした。
実は、空港というのは広いようですが、使える土地は限られています。駐車場やオフィススペースなどのオペレーションの素地がなければ営業提案ができませんが、空港運営会社や国土交通省としては「お客さんがいないところに場所は貸せない」となります。契約が先か場所の確保が先か。それがにわとりとたまごの関係なので、話を進めるのに時間がかかります。「当社の参入により新たなエアラインの就航が可能になり、新たな観光客もくるので地元経済にとっても良いことがあります」というシナリオをもって、国交省や自治体に地道にメリットを説明して回ると同時に、営業担当と足並みを揃えながら商談を進めていきました。そのような活動の末に自分の故郷である福岡空港に進出する提案が実った時にはとても嬉しかったです。
2019年に丸紅本社に戻ってからも、このビジネスに別の角度から関わりました。もともと労働集約的で慢性的な人手不足に悩む空港の業務を根本から変革するため、空港専用車両の自動運転化の開発に関わったり、新技術を導入し効率化を進めるためにパートナー企業と話し合ったりする際には、既存のオペレーションについて知識を深めてきたことが役に立ちました。なにも決まっていないところから、何が現場の肝なのかをひたすら深掘りして考え続け収益モデルを見つけ出すのは、やりがいのある仕事でした。
英国に来て変わった意識
去年(2022年)の春に辞令をうけてロンドンに赴任してからは、ガラッと役割が変わりました。ここでは、民間航空・宇宙・防衛の3領域を担当しています。主な仕事は、欧州地域での新規事業開拓を行うための情報収集や当地企業との面談です。欧州で新しいビジネスの種を見つけ、出資や買収を通じて稼ぎ頭を作っていくことを目指しています。
英国だけでなく欧州各地に拠点があり、航空だけでなく自分が携わってこなかった宇宙・防衛の話まで次々と寄せられてきます。それで早々に気がついたのは、今までの自分の「狭く深く」のプレー・スタイルは通用しないということでした。集まる情報全てを今までと同じ粒度で理解し取組んでいくのは不可能なので、取捨選択と優先順位付けをしなければなりません。周囲にどう動いてもらうかも考えていかねばなりません。マインドセットを変えるべき時がきたと感じました。
英国赤門学友会に限らず、ロンドンでは人種・世代・業種などを超えた幅広いネットワーキングの機会がたくさんあります。自分の業界とは全く違う世界で大きな成果を出されている凄い方と知り合う機会もあります。商社の仕事の面白さとは、本来、そのような全く違う分野で生きている人とのなにげない会話の中に新たなビジネスのチャンスを見出し、形にしていくことではないかと思うのですが、過去の自分は航空業界の中の人としか話してこなかったため、せっかくの機会にも相手の話を理解する素地が足りていないと焦る気持ちもあります。
私は本来シャイな性格で、家でダラダラしている時が一番くつろげるのです。でも今は、そのような交流に積極的にとびこみ、いろんな方の話をあえて臆せずに伺うことを心がけています。少しずつでも自分の幅を広げていって、他の人が気付かないような引っ掛かりをみつけ、自分の仕事と繋げて新たな価値を生み出せるようになっていきたいと考えています。
