[ブックレビュー]森博嗣『歌の終わりは海 Song End Sea』
【ブックレビュー】森博嗣『歌の終わりは海 Song End Sea』(講談社ノベルス、2021)
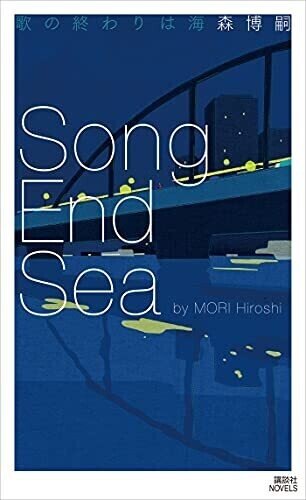
もう傷は癒えているはず。
それなのに、まだそこが痛いと思い込んでいて、触れずにいる。(『歌の終わりは海 Song End Sea』第三章「人生の終わり」より)
『歌の終わりは海 Song End Sea』は、森博嗣が放ってきたそれまでの各シリーズからの延長線上にあり、既刊のシリーズではおなじみの小川令子、加部谷恵美を中心とした物語である。ただ、二人を知らずとも問題なく、二人が織りなす独白や会話は魅力的で、そして冬木糸一の言葉を借りれば、(本作も)「生と死の曖昧な境界をそのまま「わからないもの」として扱」った作品として単独で読むことができる。特に本作は自死の問題が基軸であるが、それについては冬木の解説に譲り、「理想」という視点から少し読み解いてみたい。
小川令子はこう独白する。
毎日を精一杯生きる、というのはとても簡単な逃避だ、と最近では感じている。言葉にすると綺麗だけど、当たり前すぎるし、誰だって毎日を精一杯生きているではないか。それに価値があるように思い込まされている。お前たちは、それで満足すれば良い、そういう階級なのだ、と吹き込まれているような気がしてならない。/ただ、最後には、もう考えるのはよそう、お湯に浸って気持ちが良いな、と思えるだけで幸せだろう、と自分に言い聞かせてベッドに横たわる。/誰も、私の邪魔をしないではないか。この自由な一人暮らしのどこがいけないのか。(『歌の終わりは海 Song End Sea』第一章「輝きの終わり」より)
同系列の前作、並びに本作においても、「日常を生きる」ことの悲しさやそれと同居する微かな喜び、見出される日常の優しさのようなものが丹念に描かれている。特にそれは小川と加部谷の会話――独白が織りなす交流とでも言うべきセリフを読むと感じるところである。ほんとに厭なのだけど、この抜け出せない日常も捨てたものではないと思わせる。
しかし、どこまでも続く「この日常」という枠組みは、それ自体が呪詛のようなものにもなり得て、あくまで現状の生活は変えられるものではないという諦念にもつながる。時には小川の言うように、「毎日を精一杯生きる」という美しい掛け声を受けながら。本作がこうした現状の枠組みに問いを発することは明瞭である(前作『馬鹿と嘘の弓 Fool Lie Bow』にも同様の問題提起を感じるが、前作を論じることはとても難しい)。そしてこれは、第四章「終わりの海」に掲げられたエピグラフである。
完全な自由を明瞭に思いえがく努力をすべきである。ただし、それに到達する望みをもってではなく、現在の状況よりも些かでも不完全ではない自由に到達するという望みをもって。より善き状況は完全な状況との対比でのみ構想しうる。めざすものは理想(イデアル)をおいてほかにない。理想は夢想とおなじく実現不可能であるが、夢想とちがって現実との関連がある。限定/限界としての理想があれば、現実的もしくは実現可能な諸状況を、さまざまな価値の序列にそって並びかえることができる。(シモーヌ・ヴェイユ著(冨原眞弓訳)『自由と社会的抑圧』〔岩波文庫、2005〕より)
本作は、様々な観点から「理想」が語られ、そして日常や感情とのはざまで苦悩し、時に安息する。理想と日常を深く揺さぶる一冊、として終わることもできるのであるがもう一点だけ。
冒頭に掲げたのは加部谷の独白である。この少し前には、「そんなに悪くないかもしれない、とときどき思い直そうとする。/そうすると、頭の片隅の闇の中で影が動いて、まだそこに誰かいるのね、と思い出して、全身がぞっとしてしまう。/それでも、その闇の影と、いつも一緒にいられる。/自分は一人ではない、と考えることだってできるのだ」と。理想や現実という視点だけではなく、加部谷恵美、そして小川令子という視点を通して、変えられない過去に対しても語り掛ける。時にとても優しく。我々は理想、現実、そして過去という三点のどこか一点にのみ留まることは許されないのであろう。そして留まる必要もなく、その間で揺さぶられてもよいのかもしれない。そう思わせる一冊。
【参照】 冬木糸一「森博嗣による、Xシリーズに続く、浮気調査に明け暮れるリアルめの「探偵もの」──『歌の終わりは海 Song End Sea』」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
