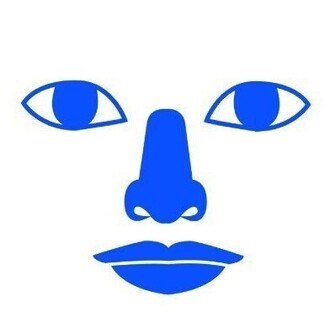ブルーハーツとラーメン屋
最近よく行くラーメン屋がある。個人経営の小さな店で、十人ほどの客でいっぱいになる。常に行列ができている。味が好きでよく行く。店内のBGMはいつも忌野清志郎だ。はじめはラジオかと思ったが、ずっとそうだし、行くたびにそうだし、店主が意図して流しているようだ。清志郎のファンなのだろう。
むかし、別のラーメン屋で、ブルーハーツだけが流れていたことを思い出した。個人経営のラーメン屋で流れる音楽としてブルーハーツはしっくりきた。清志郎も納得はいくかもしれない。ただ、ブルーハーツのほうが納得がいく。清志郎はまあ、あるかもという感じだ。
ミュージシャンとラーメン屋の相性というのは不思議で、たとえばaikoだけが流れるラーメン屋とか、この世のどこかにあるのだろうか。どんな味なのか想像もつかないが、頑固で寡黙な髭づらの店主がaikoだけ流していたら怖い。ふしくれだった指でネギを刻みながら、夏髪が頬を切る。その選曲にふれていいものか迷うが、ブルーハーツだと違和感はない。
ちなみに、清志郎を流しているラーメン屋のほうが、ブルーハーツを流しているラーメン屋よりも味つけがあっさりしていた。不思議と納得した。そりゃそうだろう、と感じた。清志郎とブルーハーツなら、ブルーハーツのほうがスープの味は濃いだろう。
いや、さすがにサンプル2軒で言うのはむちゃくちゃなのだが、真理の断片を握りしめたような不思議と堅固な感覚があった。ラーメン屋で流れるミュージシャンの楽曲とその店の味つけの相関性、みたいな論文をどこかの大学院生が書いてくれないか。たとえば長渕剛だけを流しているラーメン屋とか、まだ見たことはないが日本のどこかに絶対ありそうだし、味はこってりしてそうだし、スープはとんこつベースでメニューは殴りつけるような太い毛筆で書かれている。店名は漢字一文字で「魁」、みたいに、長渕的世界への偏見がどんどん出てくる。
ブルーハーツの流れているラーメン屋を見つけたのは十年以上前のことで、当時、私は杉松の家の物置に住んでいた。近所にオープンしたことを知って杉松と二人で行った。三十歳くらいの兄さんが一人でやっていて、店内にはずっとブルーハーツが流れていた。清志郎の時と同じく最初の一曲はラジオかと思ったが、われわれがメニューを見ているあいだも、注文してラーメンを待っているあいだも、二人でラーメンをすすっているあいだも、店内にはブルーハーツだけが流れ続けていた。
帰り道、杉松は勝手に物語性を見出して、あの店長は脱サラしてラーメン屋をはじめたにちがいない、と熱弁していた。
「やっぱり、思うわけだよ、夜中に、おさけ飲みながら」と杉松は言った。
「おれはこのまま会社づとめでいいのか的なことを思うわけだよ。自問自答だよ。ずっとサラリーマンでいいのか、ひとりでなにかできないのかって頭かかえて、そんなとき、ブルーハーツのCDを押入れから取り出すわけだよ。ほこりまみれのプラスチックのケースだよ! なつかしいなあ、とか思いながら、ひさしぶりに再生してみるわけだよ!」
杉松は興奮して言った。
「そして背中を押されるわけだよ! 甲本ヒロトの歌声に!」
謎はすべてとけた、という顔をしていた。
「ていうか、ブルーハーツ好きなんだっけ?」
「いや、普通」と杉松は言った。
「あたしは普通だけど、でも世代だから完全にわかる。あの店長は絶対そう」
自信満々に断言していて、おまえはどこのインチキ刑事だよ、まったく裏が取れていないよ、と思いもしたが、たしかに、aikoに背中を押されてラーメン屋をはじめる店主の非現実性とくらべれば、ブルーハーツに影響されてラーメン屋をはじめる店主には妙なリアリティがあった。
数ヶ月がすぎて、ふたたび杉松と同じ道を歩いていると、兄さんのラーメン屋は閉店していた。杉松がアッと声を出した。
「田舎に帰ってる!」
いや、田舎に帰ったとはかぎらないだろう、とは思ったが、開店から半年もたたずに店は閉まっていて、われわれは結局、一度行っただけだった。
何がいけなかったのか、普通においしかった気もするのだが、店主の兄さんの表情が、どこか自信なさげだったことは覚えている。弱々しく悲しい笑顔だった。ヒロトに背中を押されてみたものの、ということだったのか。近所にこんな兄さんがいたら小学生はうれしいだろうな、と思うような、朴訥した雰囲気の兄さんだったのだが。
あの兄さんは今頃、どこで何をしているのか。店内に貼られた紙に兄さんの手書きで「めにゅ〜」と書かれていた、あの、ひらがなにニョロニョロの感じを、今でもたまに思い出す。
めしを食うか本を買います