
君子豹変す〜あの時はいいと言ってたのに 「はんこ代」の効果
最近でも遺産分割協議の際に、たまに聞かれる「はんこ代」。それは、将来的に相続が起きた場合、相続人の代表者(例えば妻や長男、はたまた甥や姪の一部)から遺産分割協議書に押印を求められたら、「四の五のいわず、黙って押してね」という風に、被相続人が存命のうちに被相続人や相続の時中心になる代表の相続人が、「その他の」相続人に前もって「謝礼」を渡すことを指しています。
筆者の住むような長閑な地域では、今でもよく聞かれる言葉です。そういった言葉を発信する方が、夫や父親が亡くなったあと、遺言書の存在を確認すると大抵決まって「そんなものは無い!でも大丈夫。ほかの子供たちや甥・姪に、事前にはんこ代「云万円」渡してあるから。大丈夫。大丈夫。」
不躾な言い方ですが、何を根拠に大丈夫というのか甚だ疑問です。きわめて楽観的な希望的観測と言わざるを得ません。事前に渡した「はんこ代」に「遺産分割の時に黙って合意しろ」という法的な拘束力・強制力は無いのです。当たり前ですが。
二昔前ほど、一族郎党が同じムラ内に住んでいた場合は良かったでしょう。
そういった時にハンコを押さずに、ごねた相続人は一族郎党から白い目で見られ、そのコミュニティでの居場所がなくなりました。その時代は抑止力があったのです。
ところが現代。子供たちは東京や大阪などの大都会で就職し、都会に生活基盤が移りました。また例えば子供のいないご夫婦で夫が亡くなった時に、妻が夫の兄弟姉妹や代襲の甥姪に「はんこ」の押印を求めても「ちょと待ってください」と即決してくれるケースは少ないでしょう。彼らは教育の場で、戦後の平等意識の思考を教えられているのです。当然、遺言書が無かった場合、法定相続分は要求するのです。きわめて当然のことです。
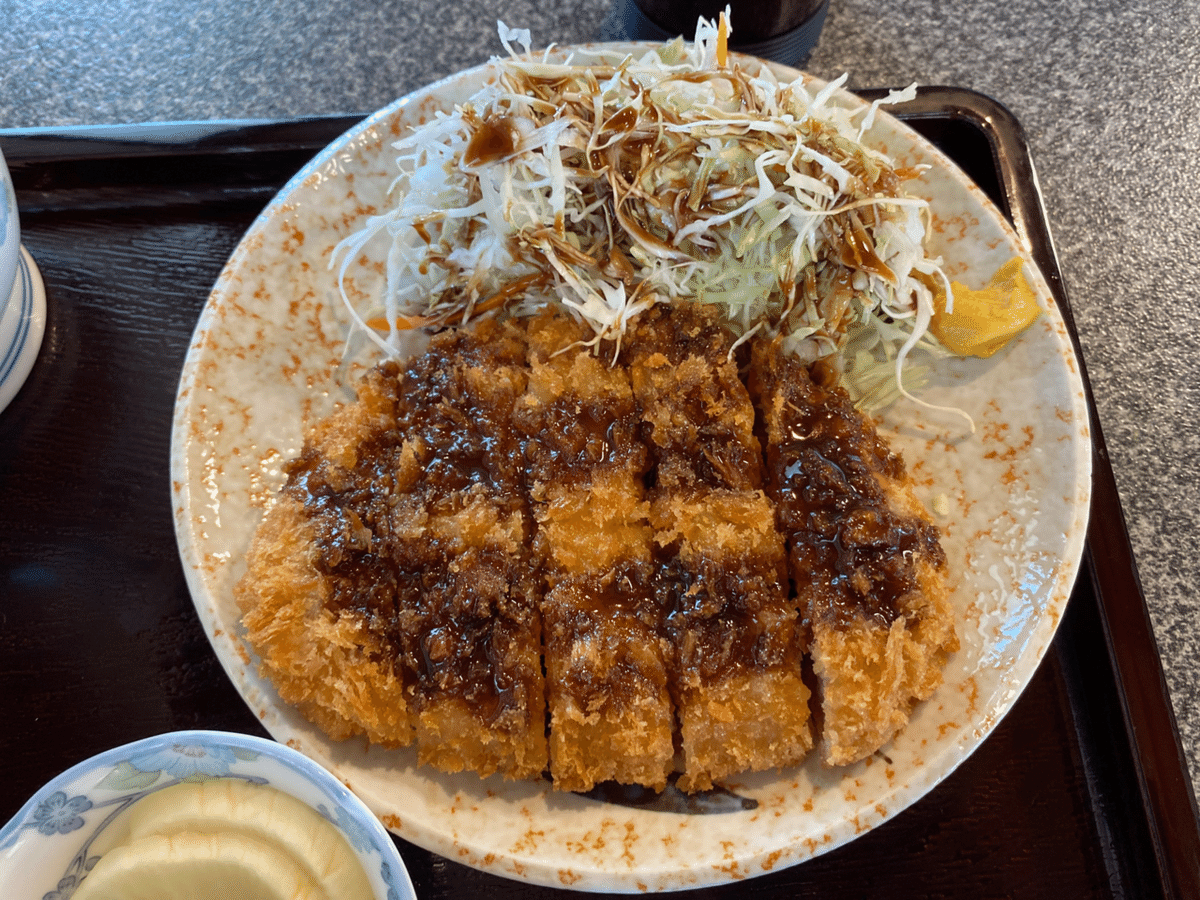
え、「はんこ代を渡したときは、素直に従うって言ってた」⁉
その時はそうだったかもしれませんが、何年前の話でしょう⁉
その当時は「長男である兄貴(あるいは未亡人になったおばさん(被相続人の妻)が全部相続して構わない」と発言したかもしれません。しかし時はうつろうもの。その時合意した二男や長女等は相続の時に、自身のご家庭をもって、それぞれの生活を営んでいるのです。
「お父さん(おじさん)が残したお金の一部でも相続でもらえれば、住宅ローンの繰上返済や自分の子供たちの教育費(もしかしたらその時私立大学を目指していて多額な学費が必要に)の一部に使えるな。」と。
また、相続人たちは現代人。ネット社会に生きています。相続の知識に疎くても秒速でGOOGLE先生が教えてくれます。
「なになに。私(甥・姪)の場合の法定相続分は全体の財産の1/16か。伯父さんは東京23区内に自宅を持っているな。そうすると云千万円は下らないな。すると1/16とすると、自分は云百万円はもらえそう」とソロバンがはじかれてしまうのです。
そういった知識に気づいてしまったその他相続人たちは、遺産分割の話の時に「長男」や「おばさん(おじさんの妻)」がすべて相続するとの話が出たときに、突然と「牙をむく」ようになるのです。いやそういう風にみえるのではなく、以前から相続の時はもらえると思考が変化していたのです。
こういった悲劇を防止するには、遺言の作成を一日も早く実践することだと思います。待った無しなのです。
追伸:いつも耳障りな話を書いてすみません。必ずしもすべてのご家庭がこうとは限りません。円満な遺産分割をされるご家庭も少なからずあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
