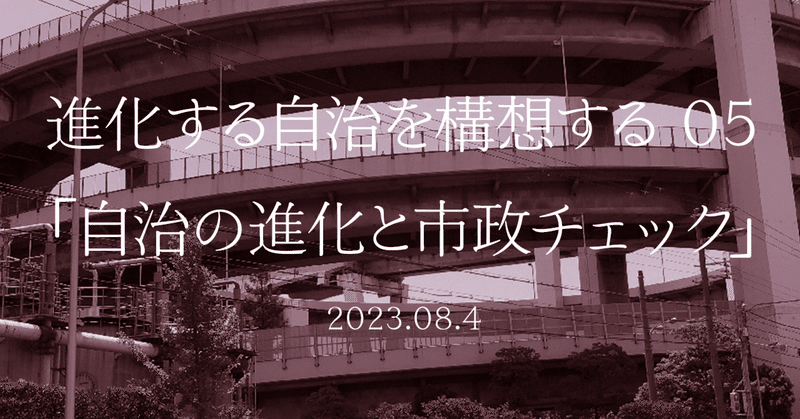
進化する自治を構想する 05「自治の進化と市政チェック」
住民が行政に参加するしくみ
地方自治体で、住民が行政に参加できるしくみは、複数あります。その中でも役所が実施することで参加できる受動的なものと、住民が自発的に、いつでも行える能動的なものとがあります。前者には議員選挙や首長選挙、住民投票、パブリックコメントや公聴会などがあり、後者として、陳情書や請願書、情報公開請求、住民監査請求、住民訴訟などがあります。自治体によっては、石狩市のように、条例で「行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行わなければならない」としている事例もあり、住民参加の頻度が高い精度を持つ自治体もあります。
選挙等の投票結果は別として、パブリックコメントや公聴会などの意見募集は、まったく手続き的に実施するだけのものもあり、内容を公表しても、それが行財政にどのように反映されるかは、行政側の胸先三寸ということが多いです。
一方、住民が能動的に行う住民監査請求の場合、審査結果として棄却された場合でも、住民訴訟というその先の手段が用意されています。また、情報公開請求でも「不開示」となった場合、「不開示」に対する不服申し立て請求というしくみがあり、時間はかかるけれども、結果をもとめつづける手段があります。
情報公開請求のその先へ
今回、山田さんの話されていた、大阪市情報公開審査会への不服申し立て審査請求の現状は、請求人に対し、「意見書を提出するか、あるいは意見書を提出し、なおかつ口頭意見陳述もするかを問われているところです。
これまでの見聞では、情報公開請求して非公開決定された場合、そこで諦めるか、不服審査請求した場合でも、指定文書ではなく、その書類の件名が一覧で開示される、というようなことでした。
今回のケースでは、大阪市が非開示についての意見書(弁明書)を大阪市情報公開審査会に
提出してきたため、その内容を開示したうえで、審査請求人(今回の場合山田さん)に意見書の提出などを問うてきたわけです。
以下は、総務省が提示している「行政不服審査会による裁決までの手続き」の図説です。各自治体によって多少の違いはあるのかもしれませんが、ほぼこれに準じていると思われます。現在の山田さんの位置は、この図説で言う「調査審議」の真っただ中ということがわかります。
今後の手続きがどのように進み、どのように採決されるのかはわかりませんが、まだまだ結果が出るまでには時間がかかりそうです。

市政チェックの先にある自治の拡がり
山田さんの活動から、情報公開請求が市政チェックの大きなツールであることがわかるとともに、思った結果が出てくるまでに、地道な努力と長い時間がかかるということもわかりました。
当初、市民が行政に参加できる仕組みとしていくつかあげましたが、選挙などの大型トピック以外で私たちが実施では切ることと言えば、陳情書の提出であったり、情報公開請求が、ある意味効果的であり、行政のチェックをする中では重要なことがわかります。特に情報公開請求は、公文書がどのように管理されているのか。つまり行政文書として管理・保存しているのかどうか、あるいはどの範囲までを行政文書としているのかなどもわかります。また、公開された文書を綿密に読み込むことで、意外な発見があったりするので、山田さんの話されているように、住民訴訟でも効果的な資料として利用することもできているとのことでした。
現在持っている権利としての行政参加のしくみだけで、ucoが提唱する「進化する自治」が実現するわけではありませんが、いまある権利を効果的に、それを多用することから行政との緊張関係が生れてきます。いま大阪市の行政は、市民をなめていると感じています。少し強めの緊張関係をつくることも、新しい関係性をつくるうえで大切なことだと考えます。そうした関係性の中でこそ、新たな、進化する自治のりあり方が見えてくるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
