
『卒論-僕がレフェリーから学んだ10のこと-』
はじめに 『卒論-僕がレフェリーから学んだ10のこと-』
僕は今サッカーのレフェリーをやっています
見た目からスポーツ何かやってるの?という話をして
「サッカーの審判」
と伝えると必ずと言って良いほど「しんぱん!?」という反応をされます
選手じゃなくて審判なんだ、と
なんで審判なの?という答えは、サッカーが好きだったからです
正確に言うと、
大好きだけど選手としてサッカーに第一線で関われない自分にずっと劣等感を持っていて、
その劣等感をサッカーへの関わり方を変えることで克服したという表現が正しいと思います
審判おもしろいの?という問いの答えは、
求められてもないのにこんなnoteを書いてしまっている時点で察していただければと思います笑
僕は高校2年生の時にレフェリーに出会って、大学2年から本格的に審判活動を始めました。
その経緯はまた後で詳しく書きますが、
僕はサッカーという大きな世界で「レフェリー」という立場に自分の存在意義を見つけたことで今もサッカーに関わり続けていて、中学生の時より、高校生の時よりサッカーが好きになりました。
このnoteはそんな僕の溢れんばかりの(もう既に溢れていますが、)レフェリーへの思いを「学んだこと」として形にするために書きます
noteに書くのは自分の振り返りだけだと途中で終わってしまうタイプなので、
人に宣言して自分を追い込むことを目的としているのと、
人の目に触れることを意識して発信するともう一段理解が深まるなということを感じているからです。
「卒論」という名前は田端さんの『これからの会社員の教科書』に完全に感化されています。笑
田端さんはこの本を「会社員としての卒業」という形で残していますが、
僕の場合は「学生レフェリーとしての卒業」を迎えます。
これからは究極の趣味として、イメージとしては、休日のお父さんのゴルフをめちゃめちゃガチで真剣にやる感じです笑
これから社会人としてレフェリーにどのように関われるか正直まだわからないですが、学生としての自由な関わり方が出来なくなるということだけは明確なので、
時間があるうちに、これまでレフェリーで学んだことを「卒論」としてまとめたくなりました。
これまでレフェリーとして、レフェリーのために多くのことをインプットしてきましたが、最近ようやく自分なりに咀嚼してアウトプットできるようになってきたな、というのを感じています
またその過程と共に、レフェリーから学んだ、レフェリーから身に付けた考え方が、レフェリーのためだけではなく、様々な分野のことと根底では繋がっていることを実感しています。
今回はそんなレフェリーから学んだことで他の分野にも共通する大事なこと10個を取り上げて(もしかしたら増えてるかも笑)、僕がいかにレフェリーに育てられてきたのかを書いていきたいなと思います。
皆さんがこれを読み終わった後に、
「へー、レフェリーもいろいろ考えてやってんだね」と感じてもらい、試合を見る時にちょっとだけ黒い人が気になるようになれば大成功だな思います笑
最後に、
僕がこんなことを書いているのも、
これまでお世話になった先輩レフェリーの方々、暁星サッカー部として関わっていただいた方々、慶應ソッカー部でご迷惑をお掛けした同期、スタッフの方々、
これまでの全ての方との関わりの中での経験が確実に糧になっているからです。
ここに書くことは、現時点で自分が感じていることであり、批判をすることは本意ではありません。
自分が先輩方の世代になってから読んだらガキが何書いてんだって自分自身思うかもしれないんですが、笑
またそれも一つ成長の記録なので、
いつの日か読み返した時に「甘いな」と思えるように成長を誓う意味でも等身大で書いていきたいと思います笑
こんなことを前提に読んでいただければ幸いです。
2020.1.16 津崎泰生
Vol.0 「審判」と「レフェリー」

(本来であれば、今日はレフェリーとの出会いを書くつもりだったのですが、導入から脱線してしまい長くなってしまったので、急遽Vol.0を挟みたいと思います。笑)
僕がレフェリーに出会ったのは高校2年生の時でした
正確に言うと、その時に出会ったのは「審判」であったと思います。
これは完全に僕の中での主観ですが、
日本において「審判」という呼び方と「レフェリー」という呼び方には距離感があるなと感じています。
印象論として、
「審判」:チームの中でジャン負けで渋々やっている人
「レフェリー」:ガチで審判をやっている人
というのを感じます。
はじめに、で書いた「しんぱん!?」という言い方もなんとなく、
ハズレくじの役割をなんでやってんの?というニュアンスを感じます。繰り返しますが、これは主観です。笑
話がそれますが、語源的な話をすると、
「レフェリー:referee」は英語の「refer」=「委ねる」からきていて、「委ねられる人」という意味があります
これはレフェリーという存在が、
サッカーが娯楽から競技になる過程で生じた「勝利」を巡る上での争いを仲裁する役割を委ねるという必要性から生まれ、
その存在を持って、セルフジャッジで成り立っていたサッカーが競技の体を成したという歴史にあるからで、一緒に協力してサッカーをつくってきたというという過去があります
では、日本語の審判とはどのような意味なのでしょうか。
辞書で「審判」を調べると、このように定義されています。
①問題となる案件を審議し、判定を下すこと。(大辞林 第三版)
②スポーツ競技などで、規則への適否・優劣・勝負を判定すること。また、それをする人。審判員。
(大辞林 第三版)
僕は個人的にこの意味に近いのは、"refer"よりも"judge"かな、と思っていて
この"judge"の本来的な意味は世界で最も権威のある辞書、『Oxford English Dictionary (OED)』から語源を遡ると、
"God or Christ considered as a supreme arbiter or adjudicator (1212 or earlier) " (Oxford English Dictionary)
これが元々、キリスト教の「最後の審判」などで使われている「審判」の意味であり、神が人間のことを裁くという構図であったものが、
"classical Latin iūdic- , iūdex individual appointed to decide a case at law, person appointed to adjudicate in a contest, umpire, critic, assessor, person who decides an issue"
(Oxford English Dictionary)
ラテン語において、「裁判官や判事」などの人対人での「裁く人」の意味に変わっていったことが分かります。
例えば、中国ではレフェリーは「裁判官」と書かれるのですが、
日本語における「審判」というのは、"referee"というより「裁判官」に近いのかなという印象を受けます
だからこそ、「一緒にサッカーをやる仲間」というより、
「威厳があり、選手より上の立場から判定をする人」で、正しい判定をすると思ってたのにミスジャッジが起きるので、時として「敵」になってしまうことがあるのではないかな、と思います。
僕が感じる「審判」と「レフェリー」の距離感は、語源的にはそんなところにあるのでは、と思っています。
これは選手側の認識ももちろんそうですが、レフェリー側でも「審判には威厳がなくてはならない」「レフェリーには強さがなければいけない」という固定概念に縛られてしまっていて、その威厳を守るためだけに苦しい思いをしている方がいらっしゃったりもします
僕らレフェリーは競技の中での役割上、笛を吹いたり、旗を降ったりしますが、仲間であることを忘れてはいけないし、
本質的には、まず役割である正しい判定を追求しなければいけないですね
このnoteを通じてここで言う「審判」が「レフェリー」になっていけば嬉しいです。
さぁ、話がだいぶ逸れてしまいました。
長くなったので、レフェリーとの出会いは次回にしたいと思います。笑
それでは。
Vol.1 レフェリーとの出会い編
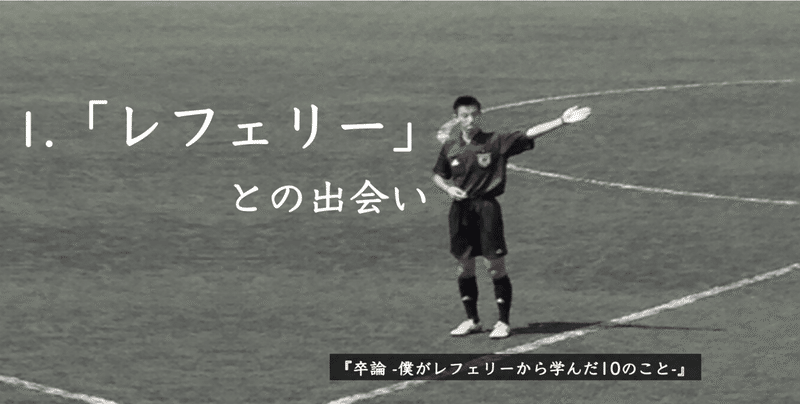
高校2年生の時に出会った「審判」は、
僕もまさしくチームで審判登録をしている人が必要だから、という理由からでした
レフェリーとの出会い方は人それぞれではありますが、
「子どものサッカークラブでのお父さんコーチ」
「学生時代のジャン負け審判」など、
感覚的にこの必要に迫られて始めたパターンが結構多いのかなと思っています
当時僕は高校のBチームに所属していて、
「レフェリーをやることで選手をやる時の見方が変わる」という顧問の考えから、
ここでは、練習試合や地区リーグのレフェリーは全て部員から出すというのが伝統になっていました
この伝統がなければ、僕が今レフェリーとしてサッカーに関わっていることはないので、レフェリーに出会わせてくれたこの環境、顧問には本当に感謝しています
チームの中にはいやいやレフェリーをする人もいましたが、
僕の場合はなぜか不思議と最初から楽しかったんですよね。
一番最初は、はじめに、で書いたような「サッカーへの違う立場への関わり方で、」なんてことは全く考えてなくて、
でも、慣れ親しんだはずのサッカーグラウンドに、「審判」として違和感がありながら立つことの新鮮さが、
スマホも地図もない状態で、初めて訪れる街を散歩しているような感覚で、刺激的なだったなという記憶があります
今でも忘れもしませんが、
実際に僕が初めて笛を吹いたのは、高校2年の時の新小岩での練習試合
よくあんな状態でやったなと思いますが、先輩から「津崎審判やってきて!」ともう両チームの選手がグラウンド中央で整列している状態で言われ、戸惑う間も与えられず試合が始まりました
今ではどこにポジション取って、どう動いてなんて一丁前に考えているものですが、
その当時は右も左も分からず、でも何かしなきゃいけないと思い、無我夢中に走りまわったのを覚えています笑
「初心忘るべからず」なんて言いますが、まさにこういう気持ちを忘れちゃいけないないですね
その試合の終わりに3級審判員である顧問から「よく走ってて良かったんじゃないの」とお褒めの言葉をいただき、
選手ではなかなか褒められなかった僕はすごく嬉しかったんだと思います
これを期に、徐々にチームの中での審判キャラの道を歩んでいくことになります。
その後も選手としての試合をして、レフェリーとしての試合もするという週末が1年間続き高校3年生になった時、
今度はトップチームの監督から、
「お前は審判も出来るし、マネージャーにならないか?ピッチ外のことを全部やってくれ」とお誘いがありました
すごく迷いましたが、
最終的には、ある同期からこれまで監督から直接誘われた人がいないというのを聞いたこと、
選手として関わるよりも近くでチームの勝利の輪に関われるという景色がみえたことからマネージャーになりました。
監督からは事あるごとに、
「お前は判定はまだまだだけど見栄えはいいから大丈夫だ」と
褒めてるのか貶してるのかわからない言い方で評価してもらっていました笑
でも、マネージャー、レフェリーとして
選手では築けなかったであろう監督との関係性を築けたというのは素直に嬉しかったですし、
だからこそレフェリーに誇りを持って過ごしていたなと思います。
大学に入っても、
サークルで選手としてサッカーをするのではなく、迷いなくレフェリーを続けることを選び、
慶應義塾体育会ソッカー部の門を叩きました
レフェリーとして、です。
ですが、残念ながらここではレフェリー専属で所属することが出来ず、僕はマネージャーとして、
審判もするマネージャーとして入部しました。
気づいていただけたでしょうか。
レフェリーとしてのキャリアを強く望んでいたはずが、僕は体育会に入ることと引き換えに、「マネージャー」としてのキャリアを始めてしまいました。
でも、僕も高校時代マネージャーやっているし、ここでもレフェリーも満足に出来るだろうと甘く考えていました。
ですが、いざやってみると、
仕事内容は全く違っているし、
僕自身の未熟さから、中途半端なプライドの高さからミスを連発し、
同期との関係もうまくいかず、
チームがすごく大事にしていた早慶戦にも全く身が入らず、
モチベーションだだ下がりの中、2度も遅刻をしてしまい、
ついにはレフェリー活動の停止を命じられるという全く元も子もない状態にまで落ちぶれました。
(ここに関しては、『プライド編』でもう少し細かく書きたいと思います!)
更にここで僕が未熟だったのは、
この組織にいてもやりたい活動は出来ないと分かっていたのにも関わらず、
僕の処遇を決めるミーティングにおいて「ソッカー部に残りたい」と言ってしまったことです。
僕の中での優先順位は、
一番が「レフェリー」、その後に「ソッカー部」があり、それは絶対的でした
でも当時を振り返ると、
まだ何も確立していない大学1年生、体育会の威を借りない自分の存在は考えられなかったし、
就活のことや、大学での立ち位置を考えると組織から離れるということがあまりにも怖かったんだと思います。
なので、「ソッカー部に残りたい」という発言をする反面、
優先順位は「レフェリー」なので、
部に残るための「ソッカー部のために」とか「同期のために」という発言は形だけで本気で部のことを考えることが出来ませんでした。
自分の思いと反する言動を続けた結果、
僕は同期のミーティングの中で「やめさせられた」形になりました。
今考えるとすごく当たり前のことだな、と思います
むしろ僕が早く「やめる」決断をしなかったせいで、
同期には何度もミーティングを開く手間を取らせてしまいましたし、
「やめさせる」という嫌な思いをさせてしまいました
これは本当に申し訳なく思っています。
この一連の流れを経て、
「俺はレフェリーとして頑張ります」という宣言をして、
僕は大学2年になる前にソッカー部を辞めることになりました。
「辞めた十字架」はずっと背負い続けます。
ですが、僕にとってはすごく大事な経験であったなと今では振り返ることが出来ます。
さぁ、このどん底からどう這い上がっていくのか、
レフェリーとして頑張る宣言をして、覚悟をもったこの時、
ようやく僕の本格的なレフェリーとしての旅がはじまりました。
長い話かつ、重い話で嫌な気持ちにさせてしまった人もいるかもしれません。
それでもこの経験は僕が今レフェリーとして存在している過程では欠かせない経験になので今回書くことにしました。
次回はもう少し楽しい話をしようと思います笑
それでは。
Vol.2 心を動かされた試合編 -レフェリーは感動を支える存在-

前回書いたソッカー部の話の中で、
僕の処遇を決めるミーティングの話をご紹介しました。
「ソッカー部にどうやって貢献するの?」ということが問われる場なのですが、
僕はレフェリーとしての貢献しかできない、ということと
普段の紅白戦や練習試合からちゃんとレフェリーが吹くことがチームの強さの一助になるということを伝えました。
それに対しての反応が僕にはこれまで深く突き刺さっています。
「レフェリーなんて誰がやっても一緒じゃん。別に誰か空いてる選手がやればいい」
もちろん僕への当て付けでその場の勢いで出た発言だとは思います。
ですが、僕はレフェリーによって試合は良くも悪くも大きく変わるということを本気で信じていたのでショックを受けましたし、
ピッチ上でレフェリーとしてなに一つ表現出来ず、それを証明出来ない、言い返せない自分を悔しく思いました
ソッカー部を辞めてからも、
辞めてからも3年が経った今でもこの言葉は僕の中に深く突き刺さっていて、
レフェリーをやる上で、僕の中での大きなモチベーションは、
一つは、「ソッカー部の同期に僕がレフェリーを頑張っている姿を見せること」
そして一番強いモチベーションは、
「レフェリーによって試合が大きく変わることを証明すること」
つまりは、
「レフェリーに力があれば、選手の技術、チームの戦術をもっと引き出して、選手もプレーしてて楽しい、観客も観てて楽しい試合を創ることができると証明すること」でした
自分の実力と想いがなかなか一致しなくて苦しかった、そんな時に今回のnoteのメインテーマである、心を動かされる試合を目撃してしまうわけです。
その試合は、
東京都の高校生の3番目のカテゴリーのリーグ戦
ナイターの試合で、
シーズン終盤で両チーム共に来シーズンの昇格がかかった試合でした
担当したレフェリーは、ある研修大会でご一緒した元Jリーグ審判員で、
その合宿の中でも、試合を観る機会がありましたが、僕がどうやっても話を聞いてくれなかった関西の大学のFWを、別の試合でいとも簡単にコントロールしていたようなすごい人です。
むしろ、従順な犬の様にレフェリーの言うことを聞いて実直にプレーさせていて、
でもパワハラ的なことは全くなくて、
そのレフェリー自身も楽しそうにやっているのです
その姿に僕は衝撃を受け、強烈な憧れと嫉妬を抱きました。
「俺もこんな風なレフェリングをしたい」と。
そんなご縁もあって、「試合あるけど観に来るかい?」とお誘いをもらったというわけです。
話を先ほどの試合に戻します。
試合が始まると、
やはり「昇格」がかかった試合です
両チームとも高いモチベーションと勢いを持って試合に臨んできています。
その中でもレフェリーは、
激しい接触を冷静に見極め、効果的なタイミングで選手に声を掛けることで選手の集中力を保たせます
また、ファウルと判定したときには、そのファウルの質に応じて笛の吹き方で効果的に選手にメッセージを伝え、
再開時には選手の気持ちが切り替わるまで必要に応じた間を取るので、選手は前のプレーを引きずりません
その結果立ち上がりこそ両チームはバタついたものの、
気がつくと22人の選手たちは緊張もほぐれサッカーに集中するようになり、
片方のチームは選手同士が近い距離を保ち、テンポの良いパス回しから何度もゴール前に迫ります
もう片方のチームは決死のディフェンスから奪ったボールを足の速いFWの裏を狙って徹底的にボールを供給し、前線ではどちらがボールを収めるのかという見応えのある駆け引きが繰り返されました
球際は相当激しいものでしたが、両チームとも軽い接触では倒れず、踏ん張りプレーを続けます
その瞬間、レフェリーから「アドバンテージ!」の声が飛ぶので選手も安心してプレーでき、試合がどんどんエキサイティングなものになっていきます
観客は選手の息遣いを感じるピッチサイドで食い入るように試合を見つめ、
ワンプレーごとに喜んだり、悔しがったり声が途切れません。
両チームの技術、戦術が発揮された
選手もプレーしてて楽しい、観客も観てて楽しい試合、最高の試合でした
僕は「これだ」と思いました。
「目指していた雰囲気はこれだ、とんでもない試合を目撃してしまったぞ」、と
極め付けは試合終盤
ショートパス主体のチームが1点リードする中で、
本部とは逆のタッチライン付近からのリードしているチームボールでのフリーキックの再開と、選手の交代が重なった場面がありました
先に選手の交代の手続きが行われるのですが、レフェリーはサブの選手が出てくる本部の方を見ることになります
すると、レフェリーが見ていないところで、フリーキックを行うチームのキッカーが5mほどボールを前に出しました
その行為が見えている観客席の僕は、まぁレフェリーどうやっても見えないから仕方ないよなぁと思っていたのですが、
その瞬間、副審がバタバタっと旗をあげ、ボールが前に出されたことを主審に伝えたのです
この試合の副審は両チームから高校生が1名ずつ行う規定になっていて、
立場としては、僕がこのnoteの中で記したようないわゆる帯同審判であり、さらにそのシーンで旗をあげた副審はなんとキッカーの味方チームからの帯同審判でした
副審が高校生の帯同審判の場合、普通そのような状況ではほぼ旗が上がることはないので、僕はまた衝撃を受けてしまいました
試合後、その副審に話を聞くと「いや、今日の試合でボール出したのはダメだと思って迷わず旗振りました」と話してくれました。
レフェリーは副審にも魔法をかけてしまいました笑
結果的にそのリードを保ったまま試合は終わります。
勝ったチームは昇格、負けたチームは残留です。
喜び抱き合う選手たち、崩れ落ちる選手、またその選手に声を掛け手を差し伸べる相手チームの選手。
中央での挨拶を終えると両チームの選手たちが観客席の方まで来て、相手チームのサポーター、自チームのサポーターに挨拶をします
どちらが勝ってもおかしくなかった、良い試合を見せてもらったと割れんばかりの拍手です
その後、負けたチームの自チームサポーターへの挨拶がグラウンドを感動の渦に包みました。
キャプテンが前に進み出ると、泣き顔ながら、でも堂々とした立ち振る舞いで、
「今日はありがとうございました。
今日の試合は負けてしまったので、昇格はありません。ですが、僕らにはまだ選手権があります。今日の敗戦は切り替えて、また明日からしっかり準備して試合に臨みたいと思うので、応援よろしくお願いいたします!」
その瞬間、相手チームの応援席からも先ほどを上回る拍手が起き、「良い試合だったよ!ありがとう!」と声が飛びます
試合後はその感動を共有した観客の中で言葉は交わさないものの素敵な一体感が生まれていて、多くの観客がしばらくその場を離れることが出来ず、みなさんが動き出す頃にはかなり時間が経過していたのが記憶に残っています
全員がこの雰囲気にもう少しだけ浸っていた気持ちになり、これを邪魔するわけにはいけないと感じていたからだなと思います。
例えば、めちゃめちゃ浸って見入っていた映画が終わり、映画館が明るくなったけど、ちょっとまだ出る気にはなれなくて、中途半端に感想を言うと自分の言葉でせっかくの雰囲気が壊れるような気がして「いやー、、」としか言葉が出てこないような、そんな感覚です笑
これを書いている僕も数年前の出来事ですが、未だに思い返すと心が動かされます。
サッカーの魅力ってこれなんです。
そして、このような試合に立ち合い、その試合を支えることができるのがレフェリーの魅力です。
サッカーの感動は、世界のトップレベルのW杯とかチャンピオンズリーグとか、または同じ高校生でも選手権だとか、大きい試合だけにあるものではありません。
今回取り上げた試合は高校生の3番目のリーグ戦の中の一試合です。
見る人が見たらレベルはそんなに高いものではないかもしれません。
ですが、どんな試合にも「勝利」を目指した選手の思いがあり、その思いがピッチ上でぶつかり、それを見守る観客がいます。
それだけで感動を生む条件は十分揃っています。
それが公式戦であれば、レフェリーが存在していて、
レフェリーはその思いを受け止めて、選手が集中してプレーできる環境をつくるために全力を尽くします。
でも、レフェリーによってはその思いを異なる方向に解釈してしまったり、
受け止めきれなかったりします。
「勝利への思い」が強く出てしまった結果、それがレフェリーに向かって来た時に無慈悲にその行為が異議であるとしてカードを出したり、
選手との間に壁を作り、一切言葉を交わさないようなレフェリーがいたり、というようなことですね。
だから、「レフェリーによって試合が大きく変わる」んです。
もちろん、異議を出さないのが良いレフェリーでもないし、選手と言葉を交わすから良いレフェリーというわけではありません。
その都度、その状況における選手の思いを受け止め、そこにマッチした対応が出来るのが良いレフェリーだと僕は思います。
僕がここで伝えたいのは、
レフェリーの手続きが良い悪いではなく、
「思いを受け止めてから、行動を決めているかどうか」ということです。
この試合を観た当時よりも、僕の受け止められる思いの量や種類はだいぶ増えたと感じていますが、まだまだ足りません。
これからも
「レフェリーに力があれば、選手の技術、チームの戦術をもっと引き出して、選手もプレーしてて楽しい、観客も観てて楽しい試合を創ることができると証明する」ために頑張りたいと思います。
だいぶ長くなったので今日はこの辺で。
それでは。
Vol.3 ルールと審判編

先日、田端さんが『これからの会社員の教科書』を著者自ら解説するという動画の中で、
ビジネスにもルールがあるんだよ、ということをスポーツを例に出して紹介してるのがうまいなぁと思ったので引用します
ラグビーってルールがなかったらゴツいやつのどつきあいになってしまうかもしれないんだけど、
ルールがあって、作法があって、マナーがあって、スポーツマンシップがあって、それに乗っ取ってやるからあれくらいギリギリの体のぶつかり合いがあって、みんなそれに熱狂するんです
サッカーも同じで、ルールがあるからギリギリの戦いができるわけですね
逆に言うと、ギリギリの戦いこそが魅力的な試合であり、それを競技として成立させるためにルールが出来たと言うわけです。
僕がレフェリーを始めたきっかけとなった高校のBチームは、毎年名古屋に遠征に行っていたのですが、
ある年、そこで岐阜協立大学経営学部教授の高橋正紀さんの講演を聞く機会がありました。
高橋さんはドイツのケルンで学び、スポーツマンの心の整え方を精神医学の分野で確立された方で、「一流のスポーツマンのこころ」というテーマで全国各地で講演をされていたのですが、僕らの顧問が大学での知り合いというご縁からたまたま遠征中に話を聞かせていただけることになりました。
当時は、正直ちょっと話が難しくて、
「グッドルーザーになれ」とか、「スポーツは非日常だ」とかキーワードだけがぼんやり記憶に残っていたと思うのですが、
今回noteを書くにあたり僕が当時書いたメモを見返してみたら、びっくりしました。
この「非日常」というのが今回のルールの話に非常に深く繋がるんですね
高橋さんが提案する、心の整え方の方法の一つに「日常」と「非日常」を区別するというのがあります。
ミスをしてもそれは非日常のことだから、それを日常まで引きずっちゃ勿体ないよ、というもので、逆の視点から言うと日常が安定してないと非日常で良いパフォーマンスは出ないよ、というものなんですが、
今回はメンタル的なものではなく、「スポーツは非日常におけるものだ」というところに今回のテーマであるルールとの繋がりがありました
ゲームは非日常のものなんです
スポーツというのは、非日常にあるもので、サッカーは非日常にある究極の遊びなんです。なので、極端な例ですが、例えば日常生活でスライディングなんてされたら事件、事故なわけですが、それがスポーツとして成り立っているわけですね
この非日常空間はみんなが楽しいから存在していて、
その共通認識があって成り立っているあくまで架空世界なので、
一緒に構成する自分、仲間、相手、ルール、審判はリスペクトしましょうねと高橋さんは言います。
僕らは当たり前にスポーツに関わり、当たり前にサッカーのある週末がやってくるわけですが、
それが成り立っているのはルールがあって、それをみんながリスペクトしているという、人間同士の合意が形成された奇跡的なバランスが保たれた世界なんだなということを再認識することが大事かもしれませんね。
さて、この文章の冒頭で、
「ギリギリの戦いこそが魅力的な試合であり、それを競技として成立させるためにルールが出来たと言うわけです。」と書きました。
それを踏まえると、
レフェリーが「ルールを選手に守らせよう」とすると選手のギリギリの戦いは引き出せないかもしれない、と思います。
そうではなくて、
「魅力的な試合を作る上で、ギリギリを超えた行為をしてしまった選手に対して、今のはルールを破ったよね」とルールを根拠に確認をしてあげれば良いのだと思います。
競技規則にも、レフェリーの目標はこのように定められています。
サッカーの魅力を最大限に引き出すよう、試合環境を整備し、円滑な運営をする
競技規則を適用するというのは、僕はこの目標の中の「円滑な運営をする」というところに入っていると考えています。
だから、忘れてはいけないのは、僕らのメインの目標は「サッカーの魅力を最大限に引き出すこと」であり、そのためにやるべきこととして「円滑な運営=競技規則の適用」があるというわけです。
レフェリーはあくまでそのルールの施行を委ねられた存在なので、
「ルール」が選手のことを裁くわけですね
これが、「レフェリー」が裁くようになってしまうと、「あの選手は厄介だ」とか「前の試合で退場している」とか憶測や個人的感情からルールの適用がぶれてしまうことがあります。
レフェリーが公正、公平であれ、というのはここに由来するものだと思います。
逆に言うと、選手みんながリスペクトに溢れる試合で、ギリギリの戦い方を分かってルールを守っている試合であれば、レフェリーはそれを見守っているだけでいいわけです。
競技規則のイントロダクションにもこう書かれています。
最高の試合とは、競技者同士、審判、そして競技規則がリスペクトされ、審判がほとんど登場することのない試合である
選手もレフェリーもこの考え方が頭に入っているともっと良い試合がいろんなところで生まれて、またサッカーが楽しくなるんじゃないかなぁと思っています。
僕がこのように考えるようになったのには、忘れられない強烈な思い出があります。
ソッカー部を辞めた後、
高校、大学の先輩がチームの代表をしていた縁から、関東社会人1部リーグに所属する東京ユナイテッドFCに約2年弱関わらせてもらいました。
最近はあまりグラウンドに応援に行けず、申し訳なく思っています。笑
僕がここにいた期間はちょうど元日本代表のディフェンダー岩政大樹が所属していた時期で、大樹さんと過ごした時間が僕のレフェリーにとっての非常に貴重な財産になっています。
その当時、毎週木曜日には東京ユナイテッドと東京大学で練習試合をやることになっていて、僕はそのレフェリーをやらせてもらっていました。
ある日の試合中、
大樹さんが東大FWのユニフォームを引っ張って倒し、
いわゆる、大きなチャンスとなる攻撃を妨害する、反スポーツ 的行為で警告に該当するファウルをしたことがありました。
ルールに詳しくない方向けに簡単に解説をすると、
サッカーにおいてイエローカード(=警告)が出る状況は二つあります。
一つは、相手を怪我させてしまう危ないプレー(=ラフプレー)
もう一つは、相手のチャンスを潰すプレー(=反スポーツ的行為)です。
今回のファウルは後者のチャンスを潰すプレーに該当し、
このプレーによる警告は、ファウルの種類は関係なく、ユニフォームを引っ張るものでも、足を引っ掛けるものでも、チャンスを潰したことで警告が出ることになっています。
試合に戻ります。
僕はファウルをした大樹さんに対して、
「大樹さん、それはないですよ!」と注意をしました。
僕の中では、手を使って相手を止めることはいけないことだから、当然注意をしなければいけないと思い、「ない」という言葉を使って声を掛けました。
しかし、僕のその言葉を受けた大樹さんは「ないってどういうことだよ!」と声を荒げたんです
やべっ、怒らせてしまった!と思いながらも、笑
この時は僕もレフェリーモードなので、これで怯むわけにはいけないぞと威厳を保つのに必死でした。これが睨んでいるように見えたようです。笑
「その態度も気に食わない、ちょっと試合後話するぞ」と言われて、その場ではプレーが再開されることになりました。
チームのミーティングが終わった後、
僕と大樹さんはフィールドに残り、2人で話をしました。
大樹さんからは
「あの状況で俺は、後ろにカバーがいることを確認していて、あのファウルはチームのために自分ができる最善のことであり、警告されるのは元々わかっていたこと。
選手がチームのために判断し、決断したことだから、それをレフェリーに「ない」と言われる筋合いは全くない。
それに加えて、試合中のあの態度は納得がいかない」と話をされました
僕は、手を使ったファウルがいけないものだと考えていること、
「ない」という表現はその場面で注意をするために出て来てしまった言葉であることで、その選択を否定する意図ではなかったこと、
試合中でレフェリー然とする必要があって、必死だったので睨むような形になってしまったのかもしれない、と伝えました。
すると、
「だったら、「大樹さん、それ警告ね」でいいじゃん。
そうやって言われたら俺もおっけーおっけーってなるよ。
たぶん、これを注意する言葉はないんだと思うよ、選手の判断を否定することになるんだから。どうやっても注意しようとすると、今日の「ない」っていう表現になっちゃうんだと思う。」
僕にとっては衝撃的でした。
ファウルはよくないものだと思っていたのに対して、チームのために警告を分かっててファウルをしていた大樹さん
レベルが全く違いました。
すごいなという思いがありながらも、自分のレベルの低さが悔しくて、
この経験から、僕はファウルの考え方や、選手への声の掛け方を徹底的に考え見直すようになりました。
これが一つ前のnoteで書いた、「選手の思いを受け止める」ことの基礎になっていて、ファウルをした選手の感情を徐々に察するようになっていきます。
魅力的な試合を引き出すためにレフェリーがやるべきことは、
「選手にルールを守らせるのではなく、
ルールを破る覚悟をもってプレーをした選手の思いを受け止め、その選手に、「今の行為はルールを破ってますね」、という確認作業をすること」だと思います
これがまさしく、
「大樹さん、それ警告ね」なわけです。
ちなみに、僕が大樹さんのことを睨んだ疑惑に関しては、
「まぁ俺に突っかかってきたやつで、成長しなかったやつはいないからな笑」と許してもらいました笑
このファウルに対しての考え方があると、先日のマドリードダービーでのバルベルデのファウルを素晴らしい判断だったね、と評価することが出来るのですが、
今日は長く書きすぎてしまったので、
その話はまた別のところで番外編として書きたいと思います。
次回はプライドについて書きたいと思います。
それでは。
Vol.4 プライド編 -分からないって素直に言えますか?-

4回目になりました。
今日はプライドについて書きたいと思います。
みなさんは「プライド高いね」と言われた経験はあるでしょうか?
あるいは、チームメイトや職場の同僚で「プライド高いなー」と感じる人はいるでしょうか。
ここで表現される「プライド高いやつ」というのは、大抵の場合「扱いにくいやつ」という評価とイコールであることがほとんどだと思います。
僕は、まさしく「扱いにくいプライド高いやつ」でした。
でも、「プライドが高い」ことが常に悪いことかというと僕はそうは思わないんです。
むしろ、成功してる人や結果を残す人というのは「プライドが高い」ことが結構よくあります。
扱いにくくなってしまう人と、成功する人の違いはどこにあるのでしょうか。
僕は自分の経験の中から、成功する人のプライドの高さは
自分のやってきたことに対する自信や誇りである、と思っています。
彼らは自分がやっていること、大事にしている価値観に確かな誇りを持っていて、それに見合うだけの努力をしている人です。
この文章を読んでいくと、「プライドが高いとは何か」「誇りとは何か」が少しわかっていただけるかと思います。
「僕自身の未熟さから、中途半端なプライドの高さからミスを連発してしまった」
Vol.1の「レフェリーとの出会い編」で、
僕はソッカー部でのマネージャー生活をこのように記述しました。
この「中途半端なプライド」が一番厄介なんですね笑
ソッカー部で僕がしてしまったほとんどのミスの原因の根底には、
「分からないです、教えてください」が言えなかった、ということがあります。
こんなことを自分で言うのは大変おこがましいのですが、
僕は第一印象で人から悪い評価をされたことはこれまでの人生でほとんどありません。
身長とパッと見ただけの印象で、「出来そう」とか「良い人」と見られたりすることがあるわけです
ソッカー部でも、実は入部の時点では
同期のマネージャーの中で一番最初に入部していて、
練習前のミーティングで挨拶をした時も「あいつ頭良さそうじゃん」とか「出来そうじゃん」なんて先輩から評価を受け、
「なんかあいつレフェリーもやるらしいよ、おもしろいな」という周りからの評価は悪くないものでした。
これは人によっては相当な強みになりますね。
ですが、僕にとってはそれが一番の弱みになってしまったんです。
僕が未熟だったのは、
「あいつ出来そうじゃん」という、他人からの根拠も薄い、掴んでもすぐすり抜けてしまう砂のような評価を崩さないためだけに頑張ってしまったことです。
でもそれだけ、自分に本質的な自信がなかった、ということですね。
同期の中で最初に入部したというだけで、
組織のことも仕事も、何も分かるわけがないんです。
逆に1年生の立場で、それが分からなくて怒られるなんてことはないわけです。
ですが、周囲の目を極端に意識して、
「出来る風」を装うために、自分の周りにバリアを張って、一度「俺出来ますけど」という鎧で全身を覆うことにしてしまったので、もう誰にも何も聞けないわけです。
人は基本的に関わり合って生きていくので、
周りの人は、この「俺出来ますけどの鎧」が見えると「あいつプライド高くて扱いにくいんだよ」と感じます。
その当事者は、自分が重すぎる鎧を背負ってしまって、もう身動きが取れなくなって、潰れそうなことをわかっているのですが、
ここが中途半端なプライドの厄介なところです
潰れてても、そんな状況下でも平然を装ってしまうんですね。
「君がその必死で守っているプライドはそんなに大事なものなのかい?」と言ってあげたいもんです。
むしろ救いの手を差し伸べてくれた人対して、
「俺を下に見るな、助けなんていらねーよ!」とか言ってしまったりして、本当に見捨てられてしまうわけです
なんか出来そうだなという評価を守るというちっちゃいプライドのためだけに、
「分からないです、教えてもらってもいいですか?」が言えず、
僕はその代償として周りからの「信頼」と「レフェリーとしての自分」を失ったわけです。
失ったものは大きかったですね。
信頼は、一度失ってしまうと取り返すことは至難の技です。
信頼を取り戻すには、「あいつ変わったな」と思ってもらう必要があります。
僕の場合は、最後まで、もうとっくに失っていた過去の自分の幻影に戻ろうとしていたので、
信頼を取り戻すことはありませんでした。
これが部活を辞めたもう一つの大きな要因ですね。
世の中では、
その過去の自分との決別を「殻を破る」なんて表現したりします。
僕がその殻を破ったのは、
大学3年生の時に行った、今現在も所属している組織でのプレゼン活動がきっかけでした。
この組織は関東大学連盟に属する、大学生の審判養成コースで、レフェリングに関しての活動はもちろん、人間的成長がレフェリングの向上にも繋がるという考え方をベースに、学生がテーマに基づいたプレゼンテーションすることを活動の一貫として行っています。
僕が3年生の時のテーマは「自分の課題を発表すること」でした。
JFAが示したレフェリーに必要な能力の中から、自分に足りていない能力を選び、1年間を通してその分野の能力改善の指針を示し、また半年後にその結果を共有するという2部構成になっています。
僕はその中でも、
「プレゼンスを改善する」ことをテーマに選びました。
プレゼンスとは、JFAの指針の中で「試合を進めるために、主審としての判断を分かりやすく伝える表現力や存在感」と定義されています。
僕はその当時、
選手に対する注意が人前で表現することの恥ずかしさから中途半端になってしまったり、
大学の仲間から「いいやつなんだけど、面白くはないんだよなぁ」なんて言われることがあり、
ただ真面目風、いいやつ風な自分、思いを表現できない自分に対し、苦しく感じていた時期でした。
そこで、行き着いたのが「俺は殻を破らなければいけないんだ」ということでした。
これに気づくまでに3年もかかってしまいましたね。笑
このプレゼンをやる上で参考にしたのが、
エイミー・モーリンの『メンタルが強い人が辞めた13の習慣』という本です。
この本は著者自身の経験から、
自分を大切にするための13個の学びをまとめているもので、
プレゼンについて悩んでいた時に、大学近くの学生カフェでたまたま手に取った本でした。
僕が参考にした辞めるべき習慣は2つです。
・みんなにいい顔をする習慣をやめる
・自分は特別だと思う習慣をやめる
一つ目は、中途半端なプライドに関わるもので、
「捨てるプライド」と「守るプライド」の線引きをするというものです。
僕がソッカー部で大事にしていたプライドは今考えると、「捨ててもいいプライド」なんですね。
本当に「守るべきプライド」は「レフェリーへの純粋な思い」であり、それを達成するためであれば多少の恥は我慢できるはずです
まぁ付け加えると、上でも書いたように、そもそも分からないことを聞くというのは恥でもなんでもないんですけどね笑
この「捨てるプライド」と「守るプライド」の線引きが出来ない要因には、
自分のポリシー、価値観が明確でないということがあります。
本当に大事なことが自分の中で明確になっていないと、いちいち人からの反応を受けて喜び、傷つき、気づいた頃にはいつの間にか自分の心が疲弊してしまっているんです
例えば、バイトの接客中、ちょっとめんどくさいお客さんがいたとします
上からものを言われたり、自分の態度を理不尽に指摘されるかもしれません
その時、自分の接客や自分自身に自信がない時は、傷付いたり、怒りの感情が生まれてしまうかもしれません。
でもその時、自分の接客に誇りを持っていて、間違っていない自信があれば、そのお客さんに何を言われたって自分の芯はブレないわけです。
文句を言われながら「申し訳ございません」と頭を下げなければいけないことがあるかもしれません。
それは一見「恥」に見えます。
ですが、その行為を「捨てるプライド」と割り切ることが出来れば自分は傷つかないので、むしろお客様が満足するまでいくらでも頭を下げるパフォーマンスができるわけです。
その一方で、自分が本当に大事にしている領域にあまりにもリスペクトがなく踏み入る人に対しては、相手からの反応を恐れず、明確に「それはダメだ」という反応を示すことが大事です
そういう時、意外とその人は相手の感情なんて察することなく無責任に行動に移していることが多いので、明確な態度を示すことで、どんなに近しい相手でもハッとするんですね。
すると、自分に対してむしろリスペクトを持って接してくれるようになります
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉がありますが、この「礼儀」というのは、相手にリスペクトを持って接することを言うのかなと思っています。
この明確な態度を取ることが出来ない人は、チーム内でもどこでも、組織の中で勝手に傷つき、後から相手を責めるわけですが、残念ながらその思いは相手には全く伝わっていないわけです
僕も一度、信頼していたはずのレフェリーの先輩から、
「お前そんなにレフェリー真剣にやってないんだろ」と冗談まじりですが、しつこく言われたことがありました。
その先輩自身、レフェリーに対してすごく真摯に取り組んでいる人で、また僕の取り組みを一番近くで見てきた人であるにも関わらず、そんな軽はずみな発言をすることは冗談とは言え許せなかったので、明確に距離を取って反応しないということがあったりしました。笑
それがあったからと言って、別に関係が終わるわけではないですし、信頼していることにも全く変わりがないですし、
ただ、もうそんなことは二度と言わないよね?という約束が交わされているというだけです笑
ちょっと間で脱線してしまったのでもう一度本の内容を紹介すると、
僕が殻を破るために参考にしたやめるべき習慣は、
・みんなにいい顔をする習慣をやめる
・自分は特別だと思う習慣をやめる
という2つでした。
次は「自分が特別だと思う習慣をやめる」ことについてです。
もう少しだけお付き合いくださいね。笑
「自分が特別だと思う習慣をやめる」というのは、欠点や弱点を認めることです。
自分が出来る、とか思ってる時点でまず一定のおごりがあるわけですが、笑
世の中には完璧でいたい人がいて、そういう人は結局出来ない自分に苦しむことになります。
もしこのnoteを読んでいる人の中でこの苦しさを感じている人がいたら、出来ない自分を認めること、「等身大の自分でいること」が最終的に楽だし、疲れないし、自分を助けるんだよ、ということをぜひ覚えて欲しいなと思います。
僕はテラスハウスが好きで、ファーストシーズンからずっと見てるのですが、
58週目での洋さんの発言がすごく心に残っています。
まいまいがテレビ用の態度を取っているように感じたメンバーが、それはどうなの?と疑問に思い家族会議をする中で、
「ただ自分の評価ばかりを気にしてたってことだよね?
chayとかじゃなくてそういうの取っ払ってそもそも」
「俺も経験者が語るけどちょっと
ミスターパーフェクトの今井洋介のときより、ポンコツ今井洋介のときの方が、
応援してますって声が増えた、直に聞く声が」
ということを話すシーンがありました。
「ポンコツ今井洋介のときの方が応援してますって声が増えた」
それに尽きると思います。
やっぱり人間どんなに飾ってもボロが出るし、
結局は等身大でいるのが一番魅力的なんですよね
その等身大の自分が評価されることが一番喜ばしいし、
その自分を受け入れてくれる人が本当の仲間なんだと思います。
この考え方ってオンザピッチのレフェリーも一緒なんです。
ここまで僕のnoteを読んでいただいた方は、選手とレフェリーは立場が違うだけで、人対人であるということを感じていただいてるかと思います。
レフェリーがミスをした時、
審判という鎧で選手の声を跳ね返すのか、
等身大の自分で「ごめん、今の見えなかったんだ」と認めてしまうのか。
結局、人対人のコミュニケーションなので、
素直に謝ると、「なーんだよ、次はちゃんとみてよ!」と言ってくれたりします。
もちろん得点に関わる場面やPKかどうかの判定で「わからない」なんて言ってしまったら、レフェリーがいる意味がなくなってしまいます。それは素直さではなく無責任と表現されます。
僕がここで伝えたいのは、
全ての場面において、「自分の能力の最大を尽くして判定をする」という大前提の中で、
どうしても見えなかったものがあった時に、
レフェリーのパワーを使って「そうだったことにする」のではなく、「分からなかった」と伝える方が、選手との信頼関係を大きく崩さず次に進める可能性がある、ということです。
あくまで、ミスはミスですからね。
僕は、多くの学生の前で無様に自分の過去の失敗を話すプレゼンをしました。
勇気を出して、弱みをさらけ出して、等身大の自分で人の前に出てみたんです。
人前で弱みを見せて話すというのは相当怖かったです。
ですが、僕はこのプレゼンをしたことで
ソッカー部の当時は得られなかった「信頼」を得ることが出来ました。
「これが俺なんです」って勇気を持って話してみたら、
周りの人からは実はそんなに高く評価されていなくて、
自分が完璧でいたかっただけだったんだな、ということもわかりました笑
これを期に僕は等身大の自分であることを心がけるようになりました。
この等身大の自分で話すというのは就活なんかでも大事にすべきところかもしれません。
企業の大人は、学生が着飾ってるものなんか平気でお見通しなんだろうな、と思います。
今日も相当長い文章になってしまいました。
お付き合いいただいた方、ありがとうございました。
それでは。
Vol.5 裁量と責任編 -その判定説明できますか?-

5回目までやってきました。
まだまだ続いてまいります。笑
前回のnoteで書いた大学生の審判養成コースでレフェリーの後輩たちの試合を観戦しに行く機会があるのですが、試合後フィードバックをする際にこんな質問をよく受けます。
「あのシーン、ファウルスローにした方が良かったですかね?」
「あの時、クイックリスタート認めない方が良かったでしたかね?」
僕はいつも彼らに、
「自分で責任取れるかどうかじゃない?」
と問いかけるようにしています。
彼らが、僕にそのような質問をするということは、
そこで通常ではない何かがあったことに気付ていて、それによって「迷い」が生まれているということです。
試合中に、
ファウルスローであれば投げ方に違和感があったり、近くの選手から声があがったことで迷いが生まれたかもしれません
クイックリスタートの場面であれば、自分自身が用意出来てない時に、選手の早く再開したい思いに押し切られてしまったことが迷いの原因かもしれません。
その「選手の思い」に気づくことが出来ていれば、まずは第一関門クリアです。
では、思いに気付いた上で、ルールをどのように解釈し適用するか、
そこで、レフェリーには試合を進める上での裁量権が競技規則から与えられています。
就活中、学生から企業への
「社員にどのくらいの裁量権がありますか?」
「若いうちから仕事を任せてもらえる会社ですか?」という質問をよく聞きます。
これに対する答えは、「ではあなたはどのくらい責任を取れますか?」
これに尽きると思っています。
裁量権がある、つまり自分の決断に自由な領域があるということは、
その分の責任を背負っているということなんです。
僕らは試合にレフェリーとして派遣されたら、
「サッカーの魅力を最大限に引き出すよう、試合環境を整備し、円滑な運営をする」限りは裁量権が与えられ、
審判団として、全ての判断の責任を追うわけです。
この時に負う責任は、一度グラウンドに立ったら、大学1年生だろうが、4年生だろうが、ベテランの人だろうが関係ありません。
その責任を負う覚悟がなくグラウンドに立つレフェリーは、
様々な思いを持って臨む選手、人生を賭けて戦う選手にすぐに見透かされてしまうし、選手に話なんか聞いてもらえないので、自分が苦労します。
「自分で責任取れるかどうかじゃない?」
というのは言い換えると、
「今日の試合、責任を取る覚悟持ってこのグラウンドに来てる?」ということです。
最初の質問に戻ると、
例えば僕が、質問を受けた時、
「あれはクイックリスタート認めない方が良かったね」とだけ伝えるとしましょう。
すると、彼らの頭では、先輩がダメと言っていたからあれはクイック認めてはダメなんだ、という認識になってしまう可能性があります。
ではもし、次の試合で同じようなシーンがあった時、
彼らはどのように対応できるでしょうか。
彼らの判断の根拠が僕に言われたから、ということにある状態では、彼らが責任を取ることは出来ません。
現場で彼らが苦しみます。
この時、クイックリスタートを認める上での考慮事項が彼らに知識としてないのであればそれは丁寧に教えなければなりません。
例えば、
ボールが静止している、とか
再開する位置が正しいか、というようなものです
この考慮事項を丁寧に教え、
今回の場面では何がいけなかったのかを考えることで、
次の試合では、同じ場面で何が当てはまり、何が当てはまらないのかを自分で考え、自分なりの根拠を見出すことが出来る様になります。
この時、この根拠を選手に伝えられるようになって初めて責任を負う準備が出来たということになります。
でも残念ながらサッカーという競技の特性上、
実際に、グラウンドでそれを適用しようとするとグレーな部分が生まれます。
例えば、ファウルが起きた時、次にフリーキックでプレーが再開される位置は、本来は「起きたその地点から」再開するので、一致しているはずですが、厳密に言うとズレていることはよくあります。
ですが、選手たちが気にせずプレーする範囲のズレであることが多いですよね。
ここのズレが生まれた時に、レフェリーの裁量権というものが必要になります。
もし、この再開されたプレーから得点が入る可能性がある時、
「許容できる再開位置であった」と自信を持って選手に説明できるのであれば、再開を認めればいいと思います。
失点したチームから、「再開のポイントが違ったじゃないか!」と言われて何も言えないのであれば、少しタイミングが遅れてしまったとしても、プレーの再開を認めるべきではないと思います。
同じ現象でも、レフェリーの裁量権によって適用が変わる可能性がある、というわけです。
「再開させてもいいけど、得点入った時に責任取れますか?」
責任取れるならやれば? 責任取れないならやめれば?ということです
冷たく聞こえるかもしれません。
ですが、ピッチ上で判断できるのは自分1人しかいないんです。
自分しか自分のことは助けられません。だからこそ、自分を守るためにもこの考え方は非常に大事になります。
この責任が取れる許容範囲の違いが、レフェリーによって試合が変わるということにまた繋がりますね。
就活の例にもう一度戻ると、
例えば「次の商談やりたいなら任せてもいいんだけど、失敗した時責任取れますか?」ということで、ビジネスでは、
「その損失をどうやって埋めますか?」という金銭的なことも絡むので、この裁量権の質問を聞くといつも、レフェリーよりもっと難しい裁量権だよな、と感じていました。
ちょっとマイナス気味な論調で文章が進んでしまいましたが、
責任を取るということは本来は楽しいことなんです。
元日本代表の監督、岡田武史さんも、あるインタビューで楽しむことの究極は、自分の責任でリスクを冒すことだと話しています。
Enjoyの究極はどういうことかというと、自分の責任でリスクを冒すことなんです。日本の選手は「ミスしてもいいから」と言ったら、リスクを冒してチャレンジをするんです。ところが「ミスをするな」と言ったら、途端にミスをしないようにリスクを負わなくなるんです
例えばギャンブルで、大金持ちのお金を分けてもらって「それで遊んでいいよ」と言われて大もうけしても、失っても面白くもくそもないでしょう。自分のなけなしの金を賭けるから、増えたら「やったー」と思うし、なくなった時に「うわ、やばい」と思う。要するに「ミスするなよ」と言われている中でいかにリスクを自分の責任で負えるか、それが本当のスポーツのEnjoyなんです
レフェリーという立場は、極限までミスがないことを求められる存在です。
ビデオが入っても文句が出てしまうくらいです。
これは立場上の問題なので仕方のないことですね。笑
僕は今、レフェリーを始めた時よりも、責任の許容範囲が大きくなりました。
2つ前のnoteで書いた「選手の思いを受け止める量」が増えてしまったので、また責任の度合いも日々増さないと追いつかないわけです笑
でも、この現状が楽しいです。
責任を取る覚悟があれば、選手から同じ文句を言われるのでも、
「ファウルだろ!」から
「なんでファウルじゃないの?」に自然と変わってきます。
そして、その問いに明確に答えることが出来れば信頼関係が構築されるわけですね。
僕が伝えたいのは、
レフェリーはおもしろいということです。
なぜそれが良くて、なぜそれがダメなのか、自分なりの考え方ができて、説明できて、責任が取れるようになると、もっとレフェリーが楽しくなります。
でも僕にはまだまだ知らない景色があって、
まだまだ知らないレフェリーの魅力があると思います。
それに出会うべく、日々また頑張っていきたいなと思います。
今日はちょっと難しい話になってしまいましたね。
明日は伝え方について書きたいなと思います。
それでは。
Vol.6 伝え方編

6回目の今日は伝え方に関してです。
Vol.4のプライド編でご紹介した審判養成コースでのプレゼン活動をきっかけに、
試合中やプライベートの場面であっても、
僕はこの1年間、「思いの伝え方」に徹底的に拘ってきました。
そこで今日は、僕がこの1年間で感じた「伝える」ということを、
プレゼンでの伝え方をメインに、レフェリーでの経験、気付きを交えながら、
社会で共通して使えるように落とし込んでみたいなと思います。
まずは、僕が「思いの伝え方」に拘るようになった経緯から書いていきます。
プライド編で書いたように、
僕は大学3年時に、飾らない自分自身の姿を「等身大」というプレゼンで発表したことで、このコースで生きやすくなり、「信頼」を得ることが出来ました。
まだ読んでいない方は、ぜひ下のリンクから読んでみてください。
実は大学2年までの期間はこのコースにいる意義を見出すことが出来ていなかったのですが、
大学の3年目にこのプレゼンをしたことで、
僕は自分が変わる第一歩目を踏み出すことができました。
ここまでの2年間は、
「もっとやれ」と言われる声に苦しんだり、
コースの代表とぶつかって、もはや見放される状態になったり笑
苦しかったんですが、
このプレゼンで全てが一変したんです。
“プレゼンの神”として有名な澤円さんが、R25での記事で話していた内容に近いかもしれません。
彼は自分自身がポンコツだと言い、様々なエピソードをお持ちなんですが、
そのポンコツ脱出法としてこんな話をしています。
「ゲームがリセットされる瞬間に動く」ということです。
自分がポンコツとされている「仕事デキるゲーム」が、ある日リセットされて、みんなゼロからのスタートになることってあるんです。
僕自身、ポンコツな自分を変えられたのは1995年にインターネットが普及したタイミングなんですよ。インターネットが出てきたときに、「これだ!」とピンときて、借金をしてPCや最新ガジェットを買って、勉強会に参加しました。
そうしているうちに「社内で一番インターネットに詳しいヤツ」っていう“タグ”が付いて、ポンコツから重宝される存在に、一気にクラスチェンジしたんですよ。
僕の場合は、
明確な「変わる!」という決意を持って、
自分で勝手に、強引にリセットボタンを押したんですが、笑
僕が自分自身の失敗を赤裸々に語り、曝け出したプレゼンをしたことで、
コースでの「良いプレゼン像」というのが壊れたんですね。
これまで、
「論理的である」ことや「数値的な指標がある」ことが重視され、
そこに従ったプレゼンが顔を並べていた中で、
徹底的に自分と向き合って、
「自分自身の経験」「自分自身の思い」をありのままに伝えるプレゼンをした訳です。
そして、そのプレゼンが「良かった」という評価を得ました。
もちろんそこには多くの改善点がありますし、
「思いだけのプレゼン」では、聞いている人には「あいつ熱いな」くらいにしか伝わらないという現実もありますが、
僕は今でもプレゼンに「思いがある」ことを大事にしています。
ちょっと、僕が考える「伝える」ことの定義が漏れ始めてしまったので、
溢れる前にちゃんと本題に入りたいと思います。笑
そもそもプレゼンテーションというのは、
本来は伝えたいことがあって、あくまでそれを人に伝えるためのツールだと僕は認識しています。
それがビジネスの世界では、自社の商品をアピールするために使われたり、経営計画を視覚的に分かりやすく伝えるために使われていると思います。
そしてこのツールは、
話し手の伝えたいことが、伝わったかどうか聞き手の評価を持って、初めて完結すると思います。
なので、自分の思いがいくら強くてもそれが相手に伝わらなければ全く意味がなくなってしまいます。
前提として、僕らのコースでのプレゼン活動は、そもそも話す場が提供されていて、聞き手が一定数いるという状況であり、
話を聞いてもらう段階まで行くのでさえ大変なビジネスの現場と比較すると第一関門を突破できているので、相当恵まれている環境である、ということが言えると思います。
確かに一方で、僕ら学生が「プレゼンという場」と「テーマ」だけを与えられた時、そのテーマに基づく自分の伝えたいことがない場合は、それがプレゼンという形だけの場になってしまう難しさはあるな思います。
さぁそんな前提を踏まえて、
具体的にプレゼンについて話していこうと思います。
究極的な話をすると、プレゼンって、How to say>What to sayで、
つまり、「何を言うか」じゃなくて、「どう言うか」ってことだなと思っています。
スライドがめちゃめちゃ綺麗でもなんか伝わらないプレゼンもあるし、
逆にスライドの作りは初心者なんだけど、なんか響く話があったりするものです
例えるならば、
世の中には歌が上手い人はいっぱいます。
でもカラオケの点数がどんなに高くっても、目の前のお客さんに響かなければ歌手にはなれませんよね?
僕はダウンタウンの二人で歌う「チキンライス」という歌が好きなのですが、
浜田さんが歌が上手いかと言われると、そうではなくて笑
歌い方のテクニックというより、彼らの歌に込めるメッセージによって響く人がたくさんいるんじゃないかなと思います。
これはアーティストの例ですが、
プレゼンをする人はみな表現者になると思うので、根本は同じだと思います。
僕は、響く話が出来る人は、これから自分が話す内容を本気で信じていて、本気で伝えたいなって思ってる人で、
その内容に関してはその伝えたい思い、意思が届いてから初めてフィードバックが出来るんじゃないかな、と思います。
つい先日のテラスハウスで、
スタンドアップコメディアンとしてのキャリアをスタートさせた快のライブで、
「日本の会社員はなぜ自殺しないのか」というテーマで話をし、会場が笑いではなく暗い雰囲気に包まれてしまったことが、テラスハウス内のメンバーやスタジオメンバーの議論を呼びました。
僕はこれに対する山ちゃんのコメントが沁みました。
「自分で経験した上でのコメントではないからなんだろうな。本当に思っていないからなんだろうな。」
これは、快が話した内容が悪かったんではないんです。
放送でもありましたが、これがバツイチのサラリーマンが話すのであれば自虐になって、笑いになるかもしれません。
でも、残念ながら快にはその経験もないし、なぜ自殺しないのか、ということを本気で思っているわけではないんですね。
自分の経験が伴わないと、スタンドアップコメディーっぽい話をしただけになってしまい、薄くなってしまうし、
そもそもちょっとブラックな内容を話すスタンドアップコメディーでは、プレゼンにはない、ただのディスりになってしまう、という大きなリスクがあるという訳です。
だから、
快には「話した内容を振り返る」のではなく、
「自分が本気で思っていないことをスタンドアップコメディー風に話したことを振り返る」ことをしてほしいなと思います笑
僕がこういう風に思うようになったのは、
レフェリーとして海外のチーム同士の試合を担当したことによります。
日本にいても、海外のチームの試合をやる機会はしばしばあるのですが、
初めてその試合を担当した時に、
僕は完全に歯が立たなかったんです。
もっと高いレベルの試合を担当したこともあったはずで、
もっとプレースピードが速い試合をしたこともあったはずなのに、
選手には話を聞いてもらえず、僕はその試合から置いてけぼりになってしまいました。笑
僕はこの時、小手先の英語力と知っている単語で選手に話を聞いてもらおうとしていたのですが、
それでは全く話を聞いてもらえないことが分かりました。
英語力ではなく伝えようとする思いの本気度なんです。
英語は気持ち、という人がいますが、それははあながち間違ってはいないなと思います。
例えば、プレーが再開される時に、守備側の選手がボールの近くから離れない時、
辞書で「離れて」と調べたような「step back」とか「step away」という覚えたての言葉を言ってみるより、
「離れろ!!」と日本語で、目を合わせて叫んだ方が、
言葉は通じずとも、その本気度によって、「なんかこのレフェリーやばいな、怒ってる。離れておこう笑」となるものです。笑
この考え方の根底には、
湘南ベルマーレの前監督である曹貴裁さんの言葉があります。
パワハラ問題で話題になりましたが一回そのバイアスは外して読んでいただければと思います。
昔、J Sportsの番組に選手や監督の対談形式で進む「talking × foot」というものがありました。
この番組のある回に、
当時湘南の曹監督と、当時岡山の長澤監督が対談するものがありました。
同年代のお二人は、どちらもユースの育成を経験されていて、マネジメントの本質はトップチームの大人でも同じであるということを話していました。
育成やってると、
子供達よりも論理は俺たちの方が強いじゃん?
それで論破はできるんだけど、論理では子供達って動かなくて、
「このおっさん本気か?」というのをみてるのであって、
マネジメントの本質ってそこだと思うんだよね
だから最近は育成上がりの監督増えてるよね
僕は、「このおっさん本気か?」というのは、
「このレフェリー本気か?」と置き換えられると思いました。
この文章の初めに、
「響く話が出来る人は、これから自分が話す内容を本気で信じていて、本気で伝えたいなって思ってる人だ」と書きました。
プレゼンも、レフェリーも根本は同じであるように感じませんか?
僕は、審判養成コースの活動の一環でプレゼンをやるのは、
これに気づくためだと思っています。
「言葉には発する理由がある」
これは劇団四季のメンバー、佐藤政樹さんの言葉です。
佐藤さん曰く、
言葉を発する時には我々には3つの意識のスタンスがあります。
一つ目は、頭に意識がある時。
これは、次に何を話そうか考えていたり、メモを読んでいるような時です。
二つ目は、胸に意識がある時。
これは緊張している時や、頑張って一生懸命伝えようとしている時、感情を込めようとした時です。
そして三つ目が大事です。
肚(=はら)に意識が落とし込まれた時、
説得力があったり、動じなかったり、それでいて自然体の自分で話すことができます。
言葉を発する理由をハラオチさせるんですね。
日本では昔から、ハラという言葉はよく使われていて、
ハラを割る、ハラをくくるなど、人間の気持ちの部分の中心を描写することが多いですね。
ハラオチするためには、
なぜ自分がプレゼンでこのことを話すのか。
なぜ選手に「離れろ」と声をかけるのか。
それを徹底的に考えないといけません。
これは就活でも同じですね。
なぜこの業界なのか、なぜ御社なのか。
それが自分の中でハラオチしていないと、いくら論理が通っていても借りてきた言葉では伝わりません。
だから、自己分析をしろと言われるし、業界研究をしろと言われるんですね
就活中でこういう作業を苦しいと感じている人は、
この分析は企業に話すためではなく、
自分自身にハラオチさせるためだと思ってやってみてください。
そうすると控室で自分が作った志望動機を必死に読み込んで暗記しなくても自然に話せるようになりますよ。
まとめになりますが、
このハラオチした言葉の連続するプレゼンが伝わるということです。
僕が3年生の時のプレゼンは、
自分の経験談で、徹底的に自分と向き合ったものなので全ての言葉がハラオチしています。
根拠は全て僕がここまで生きてきたということです。笑
なので、他の人はそれに対して薄いとか、根拠がないとかツッコミようがないんですね。笑
もちろんプレゼン技術は向上させる必要はありますが、
「何を伝えたいのか」
「その伝える内容を本気で信じているのか」
「その時、借りてきた言葉ではなく、自分でハラオチした言葉で話せているか」
この要素が揃えば、伝わるプレゼン、本気のレフェリー、伝わる就職面接になるのではないでしょうか。
言葉をハラオチさせる。
ぜひ人と話す時に意識してみてください。
まただいぶ長くなってしまいました。
それでは。
Vol.7 先輩としての振る舞い編 -後輩のこと、ちゃんと見てますか?-

このnoteを読んできてくださった方はもうお分かりだと思いますが、
僕は出来るタイプの下級生ではありませんでした。
ここで言う、「出来る後輩」というのは、
先輩の話を素直に聞くことができ、
先輩にとって扱いやすい後輩であるということです。
小生意気であったという表現が伝わりやすいかもしれません。
こういうタイプの後輩は、分かりやすく目をつけられて、
潰されます笑
自分の意見を通したいのであれば、
圧倒的な実力をつけるしかないのですが、
そこまでの実力はそう簡単には身につきません。笑
すると、
自分では色々考えてるつもりでも、
必死にやってるつもりでも、
いつの間にか「あいつはバツだ」とか「幸薄だ」とか「いけてない」とか負のレッテルを貼られてしまいます。
その自分の思いと周囲の評価のズレから、
活動が後ろ向きになってしまう、なんてことがあります。
今実際思い返してみると、
そんないちいち突っかかってないで、
「捨てるプライド」を持ちなさいよ、と思いますし、そんなに強く持つはずのポリシーだったかどうかも分からないんですけどね笑
むしろ、突っかかってくるやつは目をつけられやすいので、
自分が何かミスをしてしまった時に、普段突っかかってる分、何倍にもなって返ってきます
「お前いろいろ言ってるけど、できねーじゃねえか!」ってなるんです笑
どんなに理想を語っても、
経験もスキルもないので、そりゃ出来ないですよね
むしろ、出来ないのに理想を語るやつは一番厄介です笑
なので、組織の中で生き続けるためには、
誰にも何も言わせない圧倒的な実力をつけるか、
プライドを捨てるか、
このどちらか2択だと思います。
僕にはそこまでの実力がなく、
プライドを捨てるまでに時間がかかったので、このコースでの後輩としての期間は、「いけてない」「あいつはバツだ」という評価と共に生きてきました。
その苦しんだ経験は、
僕にとって今では誰にも負けない強みです
上級生の中の誰よりも、
「いけてない」と言われるやつの気持ちが分かるし、
先輩の立場になった今、関わり方次第で「いけてないやつ」はいくらでも羽ばたかせられるし、むしろ組織を離れた時の後輩の姿をこっそり覗いてみると案外楽しそうにやっていたりすることに気づきます。
僕らのコースのある後輩で、
普段は「いけてない」と言われていた後輩がいるのですが、
僕がたまたま、彼の所属する大学のグラウンドで試合をする機会があり、
少し早めに行ってみると、フィールド上にはのびのびとレフェリーをしている彼の姿がありました。
彼の試合後、僕は自分の試合が始まるまで彼と色々話したのですが、
思った以上に考えていたし、自分なりの課題を持っていたり、
「なんだ、ちゃんとやってんじゃんね」と僕は思いました。
以前、ファジアーノ時代の長澤監督が密着インタビューでこれと似たような話をしていました。
なんとか育てよう、なんとか教えてあげようって思っていた選手がいたんだけど、
彼らは全然伸びなくて、移籍をしてしまって、
でも、偶然テレビをつけた時にダメだった選手達が生き生きプレーしてたんだよね
選手って生き生き躍動したら、自分で歩んでいくんだなと思いました
そこからどう躍動させるか、と考えるようになりましたね
先輩の立場になると、
人間どうしても教えてあげようとか、指導してあげようとか、「後輩のため」にやっているつもりが、いつの間にか「自分がまだ満足しないから」とか「もっと教えられるはずだ」とか指導が押し付けになってしまっていることがあるんですよね
ダメ出しなんかも本来は必要なくて、けっこう後輩達はやっちゃったなーという空気を敏感に感じ取っているものです。
後輩のことをちゃんとみて、ちゃんと向き合ってあげれば、
もちろん課題はたくさんありますが、
彼の例で言うと、この前の試合はあまり良いパフォーマンスではなかったけど、今日のセミナーでのプレゼンは色々こだわってやってたよね!
とか、良いところを見つけることができるようになります。
最初からなんでもできるわけではないんです。
いつの間にか、「このくらいのことは出来るだろう」とか自分の指標を押し付けていたりするのですが、そうすると、どうしてもそれと比較して悪いところばかりが目についてしまいます。
これを指摘すると、一見アドバイスした風になるのですが、その指摘を聞いた後輩はほとんどの場合前に進むことが出来ません。
なぜかと言うと、その指摘は自分と後輩、一般論と後輩を比較したものなので、一つの指標にはなりますが、後輩個人の成長や得意なことに気づいてあげることが出来ません。
例えば一つ前の例で言えば、
彼のプレゼンが良かったのは、彼が自分の中で多くのことを調べて結びつける作業が得意で好きで、それを前向きに取り組むことが出来たから、という理由があります
これは彼の試合だけを見て、パフォーマンスがいけてない、という目線では気づくことは出来ません。
一つ得意なことを見つけて、それが認められると、
まず自信がつきます。
僕にとってのレフェリーやプレゼンみたいなものですね。
自信がつくとその活動に前向きになるので、その分野のことに関してもっと探求し、得意分野になります。
すると不思議なことに他の分野もそれに引っ張られるように、全体的によくなっているものなんです。
彼が細かいことを調べたり、分析したり、それを組み合わせるのが得意ということから、
今年度僕が開催していた仲間の試合の映像分析企画を来年度彼に引き継ごうと思っています。人の試合を分析して、そこで見つかった課題を共有したり、議論のファシリテーターとなる役目です。
実際今は引継ぎ段階ですが、僕が気づかなかったような観点からの話や、アイデアを準備してきてくれたりしてすごく頼もしいですし、
彼が来年度この企画をやり続けてくれれば、いつの間にかコース内での地位も確立され、レフェリーのパフォーマンスももっと伸びていると思います。
コースでどう見られているか、というような重荷がなければ、のびのびやればできるじゃん、というのを僕は見てしまってますからね笑
もう一つ、僕には印象深いエピソードがあります。
昨年の夏に行われたこのコースでの合宿での出来事です。
この合宿で、提出物の書き方が雑だったり、書き方が間違っていたり、メールの返信が正しく出来なかったりと、私生活の面から
「いけてない」という評価をされてしまっていたある1年生がいました。
周りはみな、口を揃えて「いけてない」と言うのですが、
僕は逆の立場を知っているので、笑
ここまでのミスはほとんど知識がなくて教えてもらっていないことからきてるのではないか、と思いました。
僕ら先輩が、分からないなら聞けばいいじゃないか、と言うのは簡単です。
でも入ったばかりの1年生、聞いたら怒られるんじゃないかと思ってなかなか聞きにくいものです。
僕はその合宿の3日目に彼と同じグラウンドで試合をすることになりました。
私生活面での前評判が悪く、僕は同期から「ちょっと頼むね」的なことを言われて臨むような有様でした。
僕はグラウンドに着くと、
彼とフィールドの外を回りながらこんな話をしました。
「今日一個だけ俺と約束をしてほしいんだけど、
分からないことがあったら全部俺に聞いてほしい。
でもその代わり、聞いてきたことに関しては俺は全部答えるし、怒らない。
もし今日その約束を守ってくれたら、宿舎に帰った後、仮に大人から何か指摘されようが、上級生から何か言われようが絶対にお前のことは守るし、責任は俺が取るから、
これだけ約束してもらっていい?
この2日間、色々怒られて苦しかったと思うんだけど、
それはもう過去のことだからしょうがないじゃん?悔やんでも変わらないし。
だからさ、今日から頑張って、「なんかあいつ最初はいけてなかったけど、後半良かったじゃん」って言われたくない?
だから今日からがんばろうよ」
僕は常々思うことがあって、
世の中の上の立場にいる人がよく、「あいつがこれ出来ない」、「いけてない」という発言を耳にしますが、
「じゃあまずそのこと教えたの?」ということです。
下の人間は知識がないんです。
何をやっていいか分からないんです。
だから、知らないことを絶対に責めちゃいけないんです。
あなたの常識はあなたの後輩の常識ではないんです。
だから、何をやらなきゃいけないのか、なぜやらなきゃいけないのかをしっかり丁寧に教えてあげなければいけないと僕は思っています。
特になぜそれをやらなければいけないのか、は一番大事だと思っています。
断片的な知識ではなく、その理由を伝えることが大事です。
後輩に知識を教えると、言われたことだけをやるようになります。
後輩にその背景を教えると、言われたこと以上のことをしてくれる場合があったり、次の場面で指示が必要なくなっていたりします。
よくある例で、
魚を釣ってあげるのか、
魚の釣り方を教えてあげるのか、というものがありますが、
後者は再現性があるので、もう僕は魚を釣っている姿を見守っているだけで良くなるわけです。笑
後輩とのエピソードに戻ると、
彼はこのコースでのルールや、レフェリングのこと、たくさんのことを質問してくれました。
だよね、やっぱり知らないよね、と思いながら
僕は全ての質問に丁寧に答え、その理由を話しました。
そうなると、これまで起きていた種類のミスなんか起きないんです。
私生活がクリアになって初めて、
今度はようやくピッチ上でどうするか、という話ができるようになります。
僕は彼の試合を見て、
彼がピッチ内でどう動いていいのか分からないことが、悪いパフォーマンスに繋がっていると感じ、
彼と必要最低限のルールだけ決めました。
「全ての場面で、選手と選手の間を見に行ってごらん」
「見えたファウルは迷わず笛を吹いてごらん」
彼は基本的に真面目な性格なので、
実はこの全ての場面で選手と選手間を観にいくというのは体力面、集中力共にかなりキツいことなのですが、
僕が伝えた通りに頑張って動いてくれました。
実はその試合の直前に、僕が彼の前で試合をしていたのですが、2019年のベストゲームを引き出せたというくらい僕自身のパフォーマンスも良く、両チームもほんとに最後まで戦い抜いた良い試合をしてくれました。
彼には、そのイメージも残っていたのかもしれません。
彼はびっくりするくらいのパフォーマンスを見せてくれました。
どこに動いていいか分からなかったのが明確な意図を持って走るようになり、
選手の間が見えるように動いているので、ファウルの判定がしやすくなり、自信を持って笛を吹きます。
ほんとに素晴らしい試合でした。もちろん彼にはちゃんとそれを伝えました。
僕が嬉しかったのは、この試合を見ていたある講師の方が、
夜の研修会で「あいつ良かったよ」ということを全体の前で話してくれました。
やはり認めてもらえると人は伸びます。
彼は結局この大会の決勝戦の副審に任命されました。
「いけてなかったやつ」がです。笑
僕は親みたいな気持ちで嬉しかったですね。笑
今では彼は、研修会の場でも積極的に発言をするし、
発言や積極性では周りをリードしてくれる存在になったな、と思います。
頼もしいものです。
後輩のことをちゃんと見てあげること
分からないことを責めないで、教えてあげること
彼らの中で変化があったら、それをちゃんと褒めること
これが本当に大事なことで、これは誰にでも共通するものだと思います。
1人でも後輩がいる先輩のみなさん、
ぜひもう一度後輩のことを見てあげてください。
見えなかった姿が見えてくるはずです。
今日はそろそろどこかが焦げ付きそうな内容になってきてしまいました笑
傷が深くならない内に終わりたいと思います。笑
それでは。
Vol.8 南米編 -継承するとは?-

8回目まで来ました。
今日は僕のレフェリー人生で欠かせないビッグイベント、南米研修について書いていきたいと思います。
南米について話し出してしまったら、
これだけでも項目10個書けてしまいそうなくらいの勢いなんですが、笑
その中でも僕が特に心に残っている「継承すること」について書きたいと思います。
南米のエピソードに入る前に、
まずは僕が尊敬する先輩がよく話している、伊勢神宮の大工さん達の間で受け継がれる、「継承」と「伝承」の話からしたいと思います。
伊勢神宮では、20年おきに行われる式年遷宮が1300年間続いています。
式年遷宮とは、簡単に言うと20年ごとに社殿を新しくして、神様がお引っ越しをする、というものです。
このための技法やノウハウは、工事を担当する大工さん達の中で脈々と受け継がれているものです。
人間が80年生きるとして、大工さんは20年おきに行われる式年遷宮に、
20年周期×3回転関わることが出来ます。
最初は弟子として師匠の元で技を学ぶ20年間
2回目は、学んだ技術を現場の中心で発揮し、それを推し進めていく存在としての20年間
そして最後は、弟子に「継承する」師匠として20年間を過ごします。
これが教えが途切れずに継承されていく、ということです。
最後の弟子に現場で伝える段階が抜けてしまうと、「継承」が「伝承」になってしまう可能性があるんです。
レフェリーの世界にも、指導者がいます。
彼らは、インストラクター、アセッサーと呼ばれ僕らの試合を評価します。
インストラクターは、基本的に現役を退いたレフェリーが、自分の体はもう動かないけれど、サッカーを支えたい、後進の育成に何か貢献したいという思いのある方が務めています。
ここでポイントとなるのは、
「自分の体はもう動かないけれど」ということです。
僕は指導の現場では、
「やって見せる」ということがすごく大事だと思っています。
Vol.2で書いた感動した試合のように、パフォーマンスで示せることが一番理想的だと思っています。
なぜかと言うと、
いくら理論的な指摘でも、現場では常に状況が変化しているので、そこに対応出来なければ机上の空論となってしまうからです。
「その理論や考え方、実現可能なの?」
言い換えると、「お前それ出来んの?」
の壁を突破しなければ、
いくら正しいことを伝えたとしても、それは実体が伴わない方法論、「伝承」になってしまいます。
その壁を突破するためには、
「やって見せること」が大事で、そこで初めて「継承」の第一歩を踏み出すことが出来るとおもいます。
人生が進み、様々な経験を通じて、
自分の経験値がたまってくると、
一部のトップレベルの人達を除き、人は学びをやめてしまうことがあります。
逆に言うと、学びをやめない人がトップレベルにいけるのだと思います。
自分の経験は財産です。
誰にも否定は出来ない絶対的なものです。
ですが、自分の経験だけで話をする様になると、時代や現場との感覚にズレが出て来てしまうことがあります。
よくある分かりやすい例で言うと、
「俺らの時代は、こうだったんだぞ!」というものですね笑
だから僕も、ここで書いていることは現時点での経験のまとめです。
なので、僕もこれをアップデートし続けなければ全く意味がないんですね。
あくまでこのnoteは、新しい知識を更に入れるために、今ある自分の経験を整理しているという表現が良いかもしれません。
僕は、ウルグアイのトップレフェリー、ブラジルのサンパウロ州のレフェリー達と共に時間を過ごしたことで、
「継承する者のあり方」
「継承されるのあり方」を学びました。
彼らの凄さは、
継承する者としての限界を知っていたことです。
限界とは、自分が出来ること以上のことは教えられない、ということです。
自分が教えられること、伝えられることがある間は全力でそれを伝えます。
しかし、自分が教えられる範囲を超えた時、
「僕から君に教えられることはもうないよ」ということを喜んで認めるんです。
これは本来喜ばしいことなんですが、
日本では、「指導者」という立場である以上、一生教え続けなければいけないんだという先入観や責任感に囚われて、苦しそうな方がいらっしゃったりします。
自分の限界をきちんと知り、
いつまでの自分の手元に置くのではなく、
後輩を次のステップに進めてあげるのが先輩の役割なんじゃないかな、と思います。
例えば、地元のちっちゃい病院で治せない病気になったのに、「絶対うちで手術します!」って言われても、困るじゃないですか笑
「いやいや、ここじゃそんな施設ないんだから、早くおっきい病院紹介してよ」という感じです笑
終身雇用制度の考え方もこの「先輩像」に近い気がしていて、先輩と後輩の縦の関係をすごく大事にしますよね。
日本では後輩が先輩を超えることへの耐性がちょっと低いなぁと思ったりします。
先輩が経験だけで話をするようになった時、
学びをやめてしまった時、
アップデートが止まってしまった時、
本来この関係性は崩れ始めると思うのですが、長い間強固に維持されていますね。笑
でもこれは「指導者側」、「先輩側」だけが悪いわけではないと思っています。
本来は、「継承された者」は、「継承した者」をリスペクトするべきなんです。
これが踏み台にしてやろうとか、先輩の経験を蔑ろにする後輩がいるので、不安になってしまう先輩がいるのも事実です。
ウルグアイやブラジルでは、
この関係性がものすごく心地良かったんです。
ウルグアイのあるFIFAレフェリーは、
「僕はレフェリーのことは全部彼から教わったんだよ」と誇らしそうに僕に紹介してくれました。
俺はもう先輩のことを抜いたとか、
踏み台にしたなんて、ちっとも考えてないんですよね。
それを受けた彼の先輩は、
いやいや、今はもう君の時代だよ、と温かく笑って見守っていました。
サンパウロでお世話になった70歳の現役レフェリーは、
昔はブラジルのトップリーグをやっていた実力者で、「僕にはレフェリーの血が流れているからね」と、今でも現役を貫きながらも、
地域のアマチュアリーグ運営を自ら進んで行なっていました。
彼はこれまで周りのレフェリーみんなを育て、
みんなからの厚いリスペクトを受けていて、
でも、「みんなが活躍してるから、僕はもう裏方でいいんだよ笑」と。
素敵な関係性ですよね。
日本では、
「先輩を敬え」という年長者
「老害だ」という若者がいます。
でもこれ、お互い様だと思うんです。
特にレフェリーの世界では、サッカーを支えるという共通の目標があるので、
もっと協力してやればお互い前向きに進めるのにな、と思ったりします。
会社でも一緒なんだろうな、と思います。
「会社の利益のため」に意見を言えるのか、
「先輩のメンツのため」に意見を言えないのか、
せっかく同じ目標に向かっている仲間なので、
みんなで優先順位をその目標にするような空気感で進めたらいいのになと思います。
少し脱線しましたが、
先輩のみなさんは、
自分が出来ることは後輩に全力で教えてみませんか?
後輩が自分を超えたのであればそれを喜んでみませんか?
後輩のみなさんは、
教えを受けた先輩のことをもっとリスペクトしてみませんか?
大事にしてみませんか?
このお互いの歩み寄りがあると、
学びが「継承」されていくんじゃないかなと思います。
今日はこの辺で。
それでは。
Vol.9 自分と合わない上司、組織との向き合い方編

このnoteも9回目を迎えました。
今日は、自分に合わない上司の元で、合わない組織の中でどのように生きていくか、ということを書きたいと思います。
まず、すごく当たり前のことから書きます。
合わない上司、組織に当たってしまった時、僕らには2つの選択肢が用意されています。
続けるのか、やめるのか。
そこにいる価値を何も見出せなかったり、
そこにいるデメリットの方が大きいのであれば、やめればいいと思います。
少しでもそこに価値を見出せたり、
やめることのデメリットの方が大きいと考えるのであれば、続ければいいと思います。
そしてこの時、続けるにもやめるにも「覚悟」が必要です。
一番ダメなのは、やめることではありません。
中途半端な覚悟で組織に残り続けることです。
僕はこのnoteの中でこれまで何度も書いている審判養成コースのことが好きではありませんでした。
そこにいる講師のことも好きではありませんでした。笑
1年生、2年生の時は、
Vol.7の先輩としての振る舞い編でも書いているように「いけてないやつ」のレッテルを貼られ、特別この組織にいるメリットも感じていませんでした。
でも、僕にはやめるわけにはいかない、明確な理由と覚悟がありました。
それは、絶対に「コースをやめたやつ」というレッテルを貼られる訳にはいかない、という自分のプライドを守るためでした。
この組織には歴代の先輩も後輩も含め、多くの東京都所属のレフェリーがいます。
僕も東京都に所属しているレフェリーです。
レフェリーってすっごく狭い世界なんです。笑
なので、今後東京でレフェリーに関わり続けるならば、この組織で4年間耐えることと、今後そのレッテルを背負い続けるのことを天秤にかけた時に、
そのレッテルを背負う方がよっぽどデメリットが大きいと考えていました。
実際、この時の判断は間違っていなかったと思います。
あの時やめていれば、
「やめたやつ」のレッテルとともに暮らさなきゃいけなかったし、
先に書いてしまうと、
何より僕は最終的にこの組織で自分の信念を貫き、満足のいく活動が出来てしまったんです。笑
おもしろいものですね。笑
ここからは、自分に合わないと感じていた組織で自分のやりたいことを満足にやってしまった、そんな僕の苦労と成功の記録を綴りたいと思います。
ではまず、先ほど間違っていなかったと書いた僕の判断を見直すところから始めましょう。
これは半分は正しくて、半分は間違っています。
というのも、
もし4年間、1つのミスも犯さず完璧に「良い顔」をし続けられるのであれば、デメリットを回避するという目標は達成できると思います。
ですが、この組織での活動を片手間で完璧にやるほど僕のキャパはないし、そんなに甘い世界ではないし、そもそもそんなの全くおもしろくない。
なので、このモチベーションで組織に残ってしまった場合、
結局、「あいついけてなかった」というレッテルが貼られ、
卒業後も、何のためにやってたんだろうという喪失感が残るはずです。
これでは、じゃあもっと早くやめて、好きなことに時間使えば良かったね、となってしまいます。
こんな風に時間を使うのはあまりにももったいない。笑
こんなことを悩んでいた3年生の夏の終わり、
僕はNetflixであるドラマ達にに出会いました。
ひとつ目は、小栗旬と西島秀俊がW主演をしていた『CRISIS -公安機動捜査隊特捜班-』というドラマで、僕は第5話でのセリフに深く心を動かされました。
小栗旬演じる稲見という公安に務める刑事が、
ある暴力団に潜入捜査をしていたのですが、国家の上層部がその暴力団が握っていた都合の悪い真実を隠すために、稲見の潜入中に暴力団を殲滅させました。
その行為に加担してしまった責任を感じ、許せなかった稲見は、上層部の誰が黒幕だったのか、彼の上司である鍛治を問い詰めるのですが、
この鍛治さんのセリフが全てでした。
鍛治
「死んだ暴力団員のために復讐でもするのか?
勘違いするなよ、死んだ連中は善人じゃなかった。この国に薬物を蔓延させようとしていた悪人だ。」
稲見
「だから殺されても構わないって言うんですか?(中略)
私の流した情報で人が殺されたんです。
私は薄汚い仕組みに加担したんです。」
鍛治
「薄汚い仕組みを変えたかったら、
正義感に縛られて動きを不自由にするな。
善も悪も全て取り込んでしなやかに動け
そうやって蓄えた力で、いつか本物の悪を叩けばいい」
この言葉は、講師から言われたことや、納得がいかないこと、理不尽なことにいちいち反応し、
自分の正当性を主張しようとしたり、
真っ向から組織を否定しようとしていた僕のことを思いとどまらせてくれました。
また、篠原涼子主演の刑事ドラマ『アンフェア』の寺島進演じる山路管理官も僕に組織での生き方を教えてくれました。
流されても染まらなきゃいい。
組織の中に入り込まなきゃ、信念は貫けないってことを
流されたフリをしてやれば裏でしたたかに動くこともできる
それに組織の中にいるからやれることがある
はじき出されたらおしまいだ。
どんなに正しいことを主張したって、
はじき出されたら終わりなんですよね。
僕は気づきました。
あまりにも子供だったな、と。
声高に正しいことを主張することは全く正義ではないんだと。
組織で生き残らなければ主張さえも出来ないんだと。
信念を貫くためには、
時には流されたフリをして、おかしいなと思うことをグッと堪えて笑っていなければいけないこともあります。
そして組織での立ち位置を確立できた時に初めて言いたいことが言えるんだな、と。
僕はこれに気付いてから明確に考えを変えました。
いきたくもなかった大人との飲み会に顔を出し、盛り上がり、
後ろ向きにやっていたコースでの活動に全力で取り組むことにしたんです。
その全力で取り組んだ最初の活動が、Vol.6で書いたプレゼン活動でした。
僕が「変わる覚悟」を持ってからラッキーなことにすぐチャンスがやってきました。
いや、もしかしたらチャンスはどこにでもあって、それを掴もうと足掻くだけなのかもしれません。
僕はプレゼンで自分を曝け出し盛大にリセットボタンを押しました。
通常の研修会でやっていた映像分析では「結局何をやっていいのか伝わらないのでは?」と疑問を感じていたので、
学生間での映像分析会を自主的に企画しました。
そしてそれが評価されました。
飲み会で盛り上がり、評価されました。
後輩達への指導方法にずっと疑問を持っていたので、
自分は全く別のアプローチで後輩に向き合い、後輩を全力で守った結果、それが評価されました。
勇気を出して、
後輩達に向けて、「マル」や「バツ」だけで評価してしまう組織、「良かったね」と言ってあげられない組織の評価に囚われすぎないでねというプレゼンをしました。
でも、飲み会に顔を出して、盛り上がったので「お前変わったな」と評価されました。
合宿で、
圧力に負けそうな後輩達に向けて、組織の顔色を伺ってレフェリーをしないでね、何のためにレフェリーをするのか見失なわないでね、というメッセージを伝える研修会をしたら、それが評価されました。
そして飲み会で盛り上がり、「嬉しいよ」と評価されました。
結果的にどうでしょうか。
僕は信念を貫くことが出来ました。
そして、「良かったよ」と評価されました。
皮肉なものです。
でも、僕が嬉しくも悔しいのは、
この組織に熱を注げば注ぐほど、
嫌いだったはずの講師と絡めば絡むほど、
どんどん距離感が近くなっていって、どんどん活動がしやすくなっていって、
自分の信念と僕が悪だと思っていたものは、根本は実は同じだということに気づかされました。
レフェリーとして、どのように成長するのか
レフェリーだけでなく、どう人として成長するのか
これは全く一緒でした。
ただ、そのアプローチ方法が違っていたり、
考え方が違うところがある、ということなんです。
ある組織に属すると決めてしまったのであれば、
研修会に来てしまったのであれば、
合宿に来てしまったのであれば、
飲み会に参加してしまったのであれば、
「覚悟」を決めなければなりません。
その覚悟がないのであれば、やめた方が自分の健康に影響は出なさそうですね。笑
そして、この組織で生きると覚悟が持てた人は、
その組織に両脚突っ込むと決めた人は、
中途半端な覚悟で参加している人よりも、
確実にそこから得るものがあり、成長します。
全てが正しい完璧な組織なんてありません。
僕は4年間を終えた今、この組織が全て正しいとは思いませんが、
全てが間違っているとも思いません。
人によっては楽しいことが、人によっては苦しいかもしれない。
だから、同じ組織にいても得られることは人それぞれです。
でも、一つだけ絶対的なのは、
両脚突っ込む覚悟が持てた人にしか、本当に正しいことと、間違っていることは見えないということです。
両脚突っ込んでない人は、その本質が見えていないので批判する権利も与えられません。
「文句言う前にやれば?」と。
事実、僕は本気で向き合ってから初めて、自分と組織の共通点に気づきました。
そして、間違っていると思うことは勇気を持って伝えましたが、それに対して批判をする講師はいませんでした。
だから僕は思うんです。
自分の信念さえしっかりしていれば、
何を企画しようが、生意気なこと言おうが、ちゃちゃ入れられたとしても、本質的な批判って受けないんです。
今、組織と自分の思いとの違いに苦しんでいる後輩達には、
まだその思いは、絶対的な信念ではないんじゃない?
その思い、まだ人前で表現できるほど自信は持ててないんじゃない?
だから潰されそうになっちゃうんじゃない?と伝えたいと思います。
何が正しいのか、正解を模索するのではなく、
自分が何を信じるのかという信念を探す旅に出てください。
それが固まっていないうちは簡単に潰されてしまうので、
今いる組織のことを全力で取り組んでみてください。
そして、これは納得出来る、これは納得出来ないという自分の思いを、決して表には出さず、でも自分の心の内に大切にしまっておいてください。
もしそこで苦しんだとしても、それは「これは絶対に人にはしない」という自分の確固たるポリシーになります。
このポリシーはそう簡単には潰されません。
そして、全力で取り組んでみた時に、
ふと振り返ってみてください。
自分の後ろには、全力で取り組む中で築いた信頼があり、
自分が心の内に大切にしまってきた良い経験と悪い経験は、自分の絶対的な信念を導いてくれるはずです。
これが僕の4年間の学びです。
合わないなと思う上司がいる人、合わないなと思う組織にいる人、
一度批判する自分を抑えて、逃げないで向き合ってみませんか?
すると、見えてくる景色があると思います。
この景色はとっても素晴らしい眺めでした。
前回に続きだいぶ焦げ付いてしまいましたね。笑
それでは。
Vol.10 選手のためのレフェリー編

ついに最終回を迎えました。
10回目の今日はこれまでの記事をまとめていくと共に、
そこから見えるレフェリー像を言葉にしていきたいと思います。
まず、僕がここまで書き連ねてきたnoteは2種類に分けることが出来ます。
一つは、レフェリーとしての学びを書いたもの。
もう一つは、人としての学びを書いたものです。
この2つの学びは並列しているもので、密接に関係していると思っていますが、
今回はあえてオンザピッチ、オフザピッチによって学びを分けて考えたいと思います。
Vol.2からVol.6では僕が思うオンザピッチでのレフェリーのあるべき姿をまとめ、キーワードをちりばめてきました。
Vol.2 選手の勝利への思いを受け止められるレフェリー
Vol.3 ルールを破る選手の気持ちを受け止められるレフェリー
Vol.4 ミスがあった時、正直にそれを認められるレフェリー
Vol.5 自らが判定したことに対し説明責任が果たせるレフェリー
Vol.6 自分でハラオチさせた言葉で伝えられるレフェリー
この5つの共通点は、
その理由が全て「選手のため」であることだと思います。
Vol.3で書いたレフェリーの目標をもう一度思い返してみましょう。
サッカーの魅力を最大限に引き出すよう、試合環境を整備し、円滑な運営をする
サッカーには多くの人が関わっていて、
運営をする人や応援する人、様々な立場があります。
彼らは選手のために、努力します。
キックオフの何時間も前に会場に集まったり、設営をしたり、必死に声を出して選手を鼓舞します。
サッカーは、その全ての人達のパワーが結集した時により魅力的になると思います。
サッカーに関わる多くの人が「選手のため」を考えて努力するからこそ、良い試合環境やムードが作られて、サッカーの魅力に繋がるし、
またそれを受けた選手達が、「応援してくれる人のため」にプレーするからこそ、より良いプレーができ、サッカーの魅力に繋がっていると思います。
何が言いたいかというと、
レフェリーもサッカーの魅力を最大限引き出す目的がある以上、「選手のため」に努力しなければいけない、ということです。
でもここでこんな疑問を持つ人はいませんか?
あれ、運営する人や応援する人は「選手のため」にやると、
選手からは「応援してくれる人のため」が返ってくるんだよね。
でも、レフェリーは「選手のため」にやっても、
選手は「レフェリーのため」は返してくれないんだよね。
なんで「選手のため」に頑張るんだっけ?
これがこの「選手のため」という綺麗すぎる言葉の怖いところです。
一番大事な目的を見失うと、自分が本当は何のためにやっているのか分からなくなってしまい、「選手のため」という言葉だけが1人歩きしてしまいます。
「選手のため」って実は綺麗事なんじゃないの?と思っているレフェリー、
「選手のため」がハラオチしていないままグラウンドに立っているレフェリー、
僕は意外といるんじゃないかなと思います。
僕もそのうちの1人でした。
レフェリーって良い人しかできないよね。
レフェリーって見返りあるの?
僕らはただ良い人で、選手に文句を言われても選手のために頑張れるようなそんなすごい人ではありません。
僕らにも実は見返りがあって、それがあるから頑張れるんです。
その答えは、
レフェリーの目標を達成した先にあります。
サッカーの魅力を最大限に引き出すよう、試合環境を整備し、円滑な運営をする
僕らレフェリーは、「サッカーの魅力を最大限に引き出すため」にいます。
でもその目標を達成するためには、僕がこれまで書いてきたように「選手のため」に全力を尽くさすことが不可欠なんです。
日常的には「魅力的なサッカーのため」が抜け落ちて「選手のため」と表現されていることが多いと思います。
選手とレフェリーの関係の中では、判定されるという立場上、どうしてもストレスが発生します。
このレフェリーに対するストレスをなるべく減らし、
選手に、サッカーに集中して気持ちよくプレーしてもらうことがサッカーの魅力を引き出すために必要な手段だと思います。
サッカーの魅力を最大限に引き出すために、
選手の勝利への思いを受け止めることで選手のストレスを減らし、
ルールを破る選手の気持ちを受け止めることで選手のストレスを減らし、
ミスがあった時、正直にそれを認め、選手のストレスを減らし、
自らが判定したことに対し説明責任を果たすことで、選手のストレスを減らし、
ハラオチさせた言葉で伝えることで、選手のストレスを減らすことが僕らの仕事です。
では、ストレスを減らす一番の近道は何でしょうか。
それは、正しい判定をし続けることです。
選手にとって大事なのは、判定が正しいのか、間違っているのかです。
判定が間違っていれば、ストレスが溜まります。
正しい判定をし続けることが魅力的なサッカーの一番の近道です。
でもそれは、レフェリーにとって一番難しいことなんです。
正しい判定のために導入されたはずのVARでも、問題は解決してませんよね?
むしろ、ゴールの喜びが薄まったという、サッカーの魅力が半減してしまうというような、新たな問題も生じてしまっています。
正しい判定とは、それくらい難しいことなんです。
でも、Vol.2の感動した試合の話を思い出してみてください。
まだ読んでいない方は、ここでぜひVol.2に戻って欲しいです。
レフェリーの正しい判定や声掛けによって選手のストレスは限りなく減り、
選手はサッカーに集中してプレーを続けてくれました。
そして彼らが勝利を目指して戦った結果、
最高に魅力的なサッカーが繰り広げられました。
この魅力的なサッカーは、
多くの観客に感動を与え、
選手自身にも戦い抜いた満足感と、リスペクトの関係性を与え、
副審の勇気を引き出し、
レフェリーチームも魅力的なサッカーの一員になりました。
この魅力的なサッカーに関わることができるというのが僕らの最大の見返りなんです。
こんな試合はなかなか出来るものではありません。
でもだからこそ価値があります。
僕も一度だけ、
試合後、負けたチームのキャプテンがわざわざ本部まで来て挨拶をしてくれたことがありました。
そのキャプテンは、
「レフェリー今日はありがとうございました。レフェリーのおかげで今日俺ら負けちゃいましたけど、楽しくサッカーできました。またお願いします!」と言ってくれました。
試合中、そのチームにカードは出したし、厳しく注意する場面もあったのにです。
良い試合だったね、魅力的な試合だったね、ということを選手と共有することが出来たわけです。
こんなにレフェリー冥利に尽きることはないですね。
こういう時は、
今日は魅力的なサッカーをフィールド上の全員で協力して作れたんだな、と
頑張っていて良かったなぁと心から思います。
僕は今、レフェリーに出会ったことで、初めて本気で人の為に走ることが出来ています。
中学、高校の部活では、
僕はチームのために走る、とか人のために走るということを本気では思えていませんでした。
どちらかと言うと、なるべく楽できるなら楽したいタイプでした。
しかし、僕は一度サッカーの魅力を知ってしまったので、
こんな魅力的な試合にまた関わりたくて、出会いたくて、
「選手のため」に正しい判定を追求するために、キツくても判定が見えるところに頑張って走ります。
もしかしたら、
「人のため」って最終的に「自分のため」なのかもしれないですね。
「仲間のため」に走れるのは、仲間で協力して掴んだ景色が1人では見れないものだから。
「お世話になった人のため」に努力できるのは、その人達に喜んでもらえることが嬉しいから。
「選手のため」に走れるのは、また魅力的なサッカーに出会いたいから。
でも、その「自分のため」はあるべきなんだと思います。
「自分のためだけ」ではなく、「自分のため」です。
「自分のためだけ」だとなかなか応援されにくいですし、
かと言って、「人のためだけ」に頑張って潰れてたら意味ないですし、
最終的に自分が楽しくないと続かないですからね。笑
綺麗事だって思う人もいるかもしれませんね。
でも、サッカー界って事実綺麗で、純粋な世界だと僕は思います。
だから、感動が生まれるんだと思います。
僕の好きな長澤監督もこう言います。
何かを成し遂げる人は無邪気な心を持っていて、
"無邪気"、読んで字の如く、邪気が無い人って言うのは、
まぁ原さんももちろんそうですし、湘南の曹貴裁もそうだし、
みんな邪気がないと言うか、
このサッカー界って僕はピュアな世界だと思っていて、
もちろん結果がついてきて、いろんな評価が下っていく厳しい世界ではあるんですけど、
本当に綺麗な世界ではあるので、
サッカーが発展していくこととか、
またサッカーで生かされていく人が増えていくって言うのは素敵なことなんじゃないかなと思います。
サッカーが純粋に好きな人が世界中にたくさんいて、
その感動や情熱が世界中で共有されていて、
だからこそサッカーが共通言語になるし、
サッカーで人が繋がるし、
サッカーが世界最大のスポーツになっているんだと思います。
素敵なことですよね。
そんなスポーツの中に自分の居場所を見つけられて僕は今、本当に幸せです。
さぁこれで僕の長かった話がようやく終わります。
第10話までお付き合いいただきみなさん、本当にありがとうございました。
このnoteを更新したこと自体の感想はまた後日記述しますが、
ひとまず本編はこれで終わりです。
何かみなさんに一つでも伝わるものがあったでしょうか?
良い意見も、悪い意見も含めて、みなさんの中でレフェリーに関して何か感じることがあれば、僕のこの12日間の執筆活動は成功だったと言えますね。笑
最後に、
この文章を書き上げる上で、お世話になった全ての方へ改めて感謝申し上げたいと思います。
今回noteとして自分の経験を形にしたことで、
これまで僕が経験してきた、嬉しかったこと、苦しかったこと、全てが糧になっているんだなということを、改めて実感を持って、自分自身振り返ることが出来ました。
辛いこともけっこうありますが、そっちの方が多かったりしますが、無駄な経験なんて一つもないですね。笑
これもまた僕の大きな学びです。
僕の心に溜めている思いが溢れそうになったら、
このnoteに帰ってきて、また文字に起こしたいと思います。笑
ひとまず、それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
