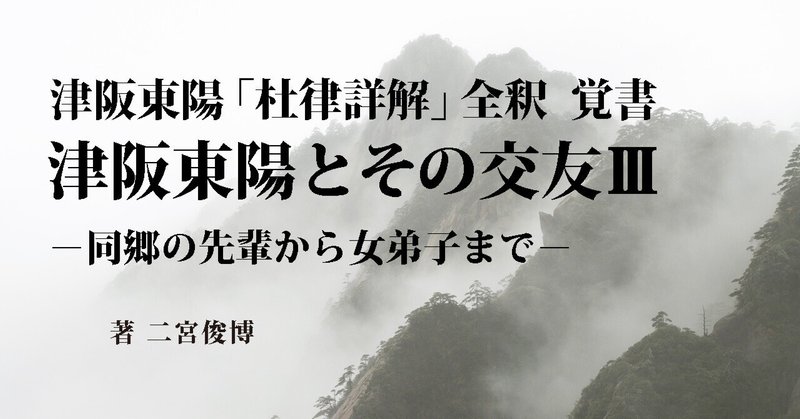
覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(6)
著者 二宮俊博
画人―十時梅厓・大原雲卿・岡田米山人
ここに便宜上、画人として一括りにしたが、東陽との関係からすれば梅厓はむしろ儒者として扱うほうがよいし、また雲卿も『国書人名辞典』には「経世家」とするように、たんなる画師という枠には収まりきれない人物である。
十時梅厓(寛延2年[1749]~享和4年[1804])
名は業、字は季長。半蔵はその通称。大坂の人。伊藤東所に学び、天明4年(1784)ごろ趙陶斎の紹介で伊勢長島藩主の増山正賢(号は雪斎)の知遇を得て仕えることとなり、長島に移住。藩校文礼館を再興したが、寛政12年(1800)致仕し、大坂にもどった。東陽より8歳上。
七絶「桑名の客楼にて十時半蔵を憶ふ」(『詩鈔』巻八)は、天明8年の大火で郷里に帰り職を求めて「諸方に浪遊」(「寿壙誌銘」)していた時期の作。梅厓は伊勢長島で文教振興の任に当たっていた。おそらく東陽の在京時代に大坂で知り合ったとみられるが、仔細は不明。
鴻雁聲中獨倚樓 鴻雁声中 独り楼に倚る
悩人風月海城秋 人を悩ます風月 海城の秋
長洲此去無多遠 長洲此を去りて多遠無し
好棹江湖一夜舟 好し棹さん江湖一夜の舟
◯悩人 人は自らをいう。◯海城 伊勢桑名を指す。◯長洲 伊勢長島のこと。◯此去 晩唐・李商隠「無題」詩に「蓬莱此を去りて多路無し」と。◯一夜舟 前掲、「和して橘恵風に答ふ」詩の〈乗興〉の語釈に引く、東晋・王子猷の故事を参照。
「貴殿のいる長島はここからそう遠くありません、さあこれから舟に棹さしてお訪ねしたいものです」。
※十時梅厓については、大槻幹郎『文人画家の譜―王維から鉄斎まで』(ぺりかん社、平成13年)参照。論考に橋爪節也「十時梅崖の研究―『蒹葭堂日記』ほか資料を中心に」(『近世大坂画壇の調査研究2』所収、大阪市立博物館、平成12年)がある。
大原雲卿(宝暦11年[1761]頃~文化7年[1810])
名は翼、字は雲卿、号は呑響。奥州大原村の人。江戸に出て井上金峨に師事。天明3年(1783)ごろに一度松前に赴き、その後京に滞在。寛政7年(1795)、前藩主の松前道廣から軍学者として招聘され再び松前に行き、また京にもどった。東陽より4歳ほど下。
僧六如(名は慈周。享保19年[1734]~享和元年[1801])に寛政7年(1779)作の七古「原雲卿、松前侯の聘に応じ暫く其の国に赴くを送る」詩(『六如庵詩鈔第二編』巻六)があり、全76句に及ぶ長編の作であるが、そのなかに雲卿の風貌や多芸ぶりを次のように伝えている。
雲卿東奥一奇兒 雲卿 東奥の一奇児
壯齡観國客京師 壮齢 国を観て 京師に客たり
軀幹雖小膽頗大 軀幹は小なりと雖も膽は頗る大なり
況乃經史腹爲笥」 況んや乃ち経史 腹を笥と為すをや」
廣醼或當興酣時 広醼或いは興酣の時に当たって
兕觥彘肩不足辤 兕觥彘肩 辞するに足らず
草書痩硬作醉素 草書痩硬 酔素を作し
八叉信口吐色絲」 八叉 口に信せて色糸を吐く」
談筵妓席毎見思 談筵妓席 毎に思はれ
不邀車公誰更邀 車公を邀へずんば誰をか更に邀へん
殊藝逸才世咸羨 殊藝逸才 世咸羨む
那知雲卿心潛恥」 那んぞ知らん雲卿心潜に恥づることを」
◯奇児 枠に収まらない快男児。奇男子。◯壮齢 『礼記』曲礼上に「三十を壮と曰ひ、室有り」と。◯観国 国土を遊覧する。『易経』観卦に「国の光を観る、用て王に賓するに利あり」と。◯腹為笥 多く書物を記憶していること。〈笥〉は、本箱。『後漢書』辺韶伝に「腹便便五経の笥」と。『蒙求』巻中の標題に「辺韶経笥」がある。◯広醼 盛大な宴会。〈醼〉は、宴と同じ。◯兕觥 兕(水牛の類)の角で作った酒杯。◯彘肩 豚の肩の肉。『史記』項羽本紀に、鴻門の会で劉邦の御者兼護衛役の樊噲が項羽から与えられた巵酒を飲み干し彘肩を喰らい、さらに勧められて、「巵酒安んぞ辞する足らん」と答える場面がある。◯痩硬 書体が細く痩せて硬質であること。盛唐・杜甫の七古「李潮が八分小篆の歌」に「書は痩硬なるを貴びて方に神に通ず」と。◯酔素 草書を善くした盛唐・懐素のこと。飲酒を好んだので、かく称せらる。北宋・蘇軾の七古「王逸少の帖に題す」詩に「顚張酔素の両禿翁、世好を追逐して書工と称せらる」と。◯八叉 晩唐・温庭筠は八回叉手(腕組み)して八韻の詩を作るので「温八叉」と称せられた(『唐才子伝』巻八)。◯色糸 絶妙な言辞(『世説新語』捷悟篇)。◯車公 東晋・車胤のこと。宴会には欠かせない人物として「車公無くんば楽しまず」と評された(『世説新語』識鑒篇の劉孝標注に引く『続晋陽秋』)。白居易の七律「李蘄州に寄す」詩(『白氏文集』巻六十七)に「洛城の歓会 車公を憶ふ」と。
胸藏兵機辨鎰銖 胸に兵機を蔵して鎰銖を弁じ
孫呉輒爲撫掌資 孫呉輒すれば撫掌の資と為す
五十三家可概畧 五十三家 概略す可し
徒讀父書古所嗤」 徒に父の書を読む古の嗤ふ所」
秖道居安不忘危 祇だ道ふ安に居て危を忘れずと
草莽之臣何所施 草莽の臣 何の施す所ぞ
以此決志歸筆硯 此れを以て志を決して筆硯に帰し
儘向繪事見胸奇」 儘絵事に向いて胸奇を見はす」
疊嶂雲屯猿猱悲 畳嶂雲屯して猿猱悲しみ
絶壑濤驚出蛟螭 絶壑濤驚きて蛟螭を出だす
巴陵洞庭秋水濶 巴陵洞庭秋水濶し
月明漁舟聞竹枝」 月明漁舟 竹枝を聞く」
此境俗工詎能窺 此の境 俗工詎ぞ能く窺はん
片紙才出人爭追 片紙才かに出でて人争って追ふ
悠悠歳月一壺墨 悠悠歳月 一壺の墨
將欲呑響幽山陲」 将に響を呑まんと欲す幽山の陲」
◯兵機 用兵の機微。杜甫の五律「警急」詩に「妙略もて兵機を擁す」と。◯鎰銖 優劣。『孫子』形篇に「勝兵は鎰を以て銖を称るが若く、敗兵は銖を以て鎰を称るが若し」と。◯孫呉 孫武と吳起。あるいはその著の『孫子』と『呉子』。三国蜀の諸葛亮「後出師の表」(『古文真宝』後集巻八)に「曹操が智計、人に殊絶す。其の兵を用ふるや、孫吳に髣髴たり」と。◯撫掌資 手をたたいてうち興じる話のたね。『晋書』王羲之伝に「衣食の餘、親知と時に共に歓讌せんと欲す。興言高詠する能はずと雖も、杯を銜み満を引き、田里の行ふ所を語り、故に以て撫掌の資と為す。其の意を得るを為すこと、勝げて言ふ可けんや」と。◯五十三家 あらゆる兵法書。『漢書』藝文志に「凡そ兵書五十三家、七百九十篇」と。◯徒読父書 戦国趙・趙括は名将趙奢の子であったが、「徒に父の書伝を読み、変に合ふを知らず」、廉頗に代わって将として軍を率いたものの、秦の白起に大敗を喫した(『史記』廉頗藺相如伝)。◯居安思危 『左氏伝』襄公十一年に「書に曰く、安に居て危を思ふ、と。思へば則ち備へ有り、備へ有れば患ひ無し」と。◯草莽之臣 語は『孟子』万章下に「国に在るを市井の臣と曰ひ、野に在るを草莽の臣と曰ふ。皆庶人を謂ふ」と見える。◯畳嶂 重なり連なる山なみ。李白の雑古「族弟の金城尉叔卿に同じく燭して山水の壁画を照らすの歌」に「了然として覚へず心魂清うし、祇だ畳嶂を将て秋猿を鳴かしむ」と。◯猿猱 テナガザルの類。李白の雑古「蜀道難」に「猿猱度らんと欲して攀援を愁ふ」と。◯絶壑 深く険しい谷。◯蛟螭 みづち。龍の一種。◯胸奇 明・王世貞の七古「九友斎十歌」其七(『弇州四部稿』巻二十二)に「剩水を将て馬遠を悩ますこと莫かれ、十二幅吐く胸中の奇」と。◯巴陵洞庭 杜甫の七古「戯れに王宰の画がきし山水の図に題する歌」に「巴陵洞庭日本の東」と。〈巴陵〉は岳州(今の湖南省岳陽市)。〈洞庭〉は巴陵の西にある大湖。◯竹枝 巴蜀地方の歌。男女の情愛や土地の風俗をうたう。中唐の劉禹錫や白居易が取り上げて広まった。
短軀ながら肝がすわり学識豊かで、よく飲みよく食らい、酔いが廻って筆をとるや草書は逸品、詩は絶妙。京の文人たちの宴にはなくてはならぬ存在だったらしい。とはいえこの男、たんなる多藝多能の小器用な才人ではない。兵法に通じ国家の安危に強い関心を抱き憂慮するところがあったが、いかんせん素浪人の身。そこで鬱勃たる思いを絵筆に託したのだと、六如はみてとったのである。
また当時の京都藝苑の大立者たる皆川淇園にも七律「大原雲卿が松前に之くを送る」詩がある(写本『淇園文集』)詩二。近世儒家文集集成9『淇園詩文集』の影印による。ただし、第八句の〈忘〉字を缺く。後掲、井上通泰「浪人大原左金吾の話」によって補う)。
馳馬盤鎗近見雄 馬を馳せ鎗を盤す 近ごろ雄を見る
賦詩書字舊来工 詩を賦し字を書す 旧来工なり
陣圖傳自風山子 陣図は風山子自り伝はり
画跡賢於大雅翁 画跡は大雅翁より賢なり
洛地名凌冠冕起 洛地 名は冠冕を凌いで起り
松城聘隔海瀛通 松城 聘は海瀛を隔てて通ず
顕榮不厭期年別 顕栄厭はず期年の別
羈滯無忘日本東 羈滞忘るること無かれ日本の東
◯馳馬盤鎗 馬上での鎗術をいう。『朝野僉載』巻六、辛承嗣の条に「馬に上がり鎗を盤す」と。◯陣図 陣形図。兵法をいう。◯風山子 甲州流の兵法家。伊賀風山(名は主馬之助。正保元年[1644]~享保3年[1718])のこと。◯大雅翁 池大雅(享保8年[1723]~安永5年[1776])のこと。◯洛地 京都。◯冠冕 名門。◯松城 松前。◯海瀛 海原。◯期年別 〈期年〉は、一年。◯顕栄 重用されて高い地位につくこと。◯羈滞 いつまでもよその土地に留まること。晩唐・邢羣の七律「郡中有懐、睦州員外杜十三兄に寄せ上る」詩(『瀛奎律髓』巻四)に「如今歳晏羇滞に従ふ」と。◯日本東 日本の本土をいう。語は杜甫の七古「戯れに王宰の画がきし山水の図に題する歌」に「巴陵洞庭日本の東」と見える。
と詠じ、その武術から兵法、詩書画に至るまで多彩な才能を讃えている。
そして伊賀上野にあった東陽も松前着任後の雲卿に詩を寄せて、次のように詠じている(『詩鈔』巻五、「大原雲卿の松前に在るに寄す」)。雲卿との交流の経緯は不明ながら、在京時代に知り合ったらしい。
寵聘功成幾載還 寵聘功成りて幾載にして還る
鵬程雲外杳難攀 鵬程雲外 杳として攀り難し
天廻水海分千島 天は水海を廻らし千島を分かつ
地接金源疊萬山 地は金源に接し万山畳なる
戎狄懐來風自化 戎狄懐き来たりて風自ら化し
邦家教立政應閑 邦家教へ立ちて政応に閑なるべし
北門鎖鑰資雄鎮 北門の鎖鑰 雄鎮に資る
緩急折衝樽俎間 緩急折衝す樽俎の間
◯寵聘 格別の思召しによる召し抱え。◯鵬程 鵬の飛ぶみちのり。はなはだ遠いことをいう。◯千島 『日本紀神代抄』に「奥州黄海の中に千島有り、蝦夷の居る所。俗に蝦夷千島と謂ふ」と。◯金源 『金史』地理志上に「上京路は、即ち海古の地、金の旧土なり。国言に金を按出虎と曰ふ。按出虎水、此に源するを以て、故に金源と名づく。建国の号、蓋し諸を此に取るなり」と。〈按出虎水〉は、現在の阿什河。ハルピン南東を北流して松花江に合流する。◯戎狄 西北方の異民族。◯邦家 国家。『詩経』小雅「南山有臺」に「楽只たる君子は、邦家の基」と。◯北門鎖鑰 北方防御の鍵を握る要衝。『宋史』寇準伝に「北門の鎖鑰、(冠)準に非ざれば不可なり」と、◯雄鎮 重要拠点となる要害の地。ここは松前藩を指す。◯折衝樽俎 外交談判。前漢・劉向『新序』雑事一に「仲尼之を聞きて曰く、夫れ樽俎の間を出ずして而して知千里の外を知る、其れ晏子の謂なり。折衝すと謂ふ可し矣」と。〈樽俎〉は宴席をいう。〈樽〉には酒を入れ、〈俎〉は肉を載せる。
この詩には「蝦夷千島は古歌の咏む所、其の地極寒、海水も亦た氷る。十月自り即ち合して、明年三月に至って方めて解く。人其の上を行くこと平地を履むが如く、車馬と雖も度る可きなり。金源は女真国を謂ふ。完顔氏、国を按出虎水の源に始む。国語に金を謂ひて按出虎と為す。因って以て号と為す。其の間攅峯天を挿し、幾千万重なるかを知らず。但だ海に縁って相通ずと云ふ」との自注を附している。西行の作とされる歌に「いたけもるあまみか時になりにけり蝦夷か千島をけふりこめたり」(『山家心中集』)というのがある。
露西亜の東漸に伴い、安永七年にはイルクーツクの商人が松前藩に交易を求め、天明になると工藤兵助の『赤蝦夷風説考』、林子平の『三国通覧図説』『蝦夷図全図』が著わされるなど、北方問題が識者の一部で大きく浮上し、寛政4年にはラクスマンが根室に来航したが、東陽その人について言えば彼の地に対する知識はあまりあったようには思われない。ただ、五律「人の松前に赴任するを送る」詩(『詩鈔』巻三)には、次のように詠じている。
氷天本荒服、千島版圖民 氷天 本と荒服、千島 版図の民
教化分憂職、謳歌臥理人 教化す分憂の職、謳歌す臥理の人
方言夷語雜、土俗古風淳 方言夷語雑じり、土俗古風淳し
莫賣盧龍塞、却揚東海塵 盧龍の塞を売って、却って東海の塵を
揚げること莫かれ
◯氷天 六朝梁・江淹「雑体詩三十首」其二十八「袁大尉」(『文選』巻三十一)に「声教氷天を燭す」と。◯荒服 中央から遠く離れた僻陬の地。古代中国の五服の一つ(『書経』禹貢)。◯版図 領土。◯分憂職 地方長官。中唐・白居易「淄青を平らぐるを賀する表」(『白氏文集』巻四十四)に「臣、名は共理に参はり、職は分憂を忝うす」と。◯謳歌 民が徳政を讃え歌う。◯臥理 臥治と同じ。前漢の武帝の時、汲黯は東海太守となったが多病で、閨閤內に臥して出でなかったが、一年余りで東海の地は大いに治まった(『史記』汲鄭列伝)。◯夷語 異民族の言葉。◯盧龍塞 三国魏の時代、河北省にあった要塞の名で、烏丸の拠点。北平の人、田疇は烏丸討伐の曹操軍を案内して勝利に導いたが、恩賞を与えようとした曹操に対して「豈に盧龍の塞を売って、以て賞禄に易ふ可けんや」として受けなかった(『三国志』魏書・田疇伝)。初唐・陳子昂の五律「崔著作の東征を送別す」詩(『唐詩選』巻三)に「盧龍の塞を売り、帰りて麟閣の名を邀むること莫かれ」と。◯揚東海塵 世事の巨変をいう(晋・葛洪『神仙伝』麻姑)。南宋・陸游の七古「護国天王院(中略)之を過ぎりて感有り」詩に「古伝ふ東海会ち塵を揚げるを、君看よ此の地亦た荊榛」と。
尾聯は、「大切な拠点を異民族に売って、世事の巨変を招くような真似はなさるな」という意であろう。
後掲の森銑三「大原左金吾」には五律の詩題に見える〈人〉を大原雲卿のことだとみなしているが、詩の配列からすると文化11・12年東陽が江戸在府中の作となり、雲卿の事跡と合わない。また詩中に「分憂」「共理」という表現が用いられており、それらは語釈に示したごとく地方長官についていう語であることからすれば、当地に赴く幕府の代官とみた方がより相応しいのではあるまいか。もとより確証はないものの、疑問を呈しておく。
その後、雲卿は京に居住したが、津城下に逗留したことがあった。森氏によれば、文化2年(1805)、津藩主藤堂高嶷の招きに応じてのことらしい。東陽に「京師の大原生、我が府下に遊寓し、山水梅竹等の画十幅を作り、幷せて詩を題して献ず。剡藤紙三十番を賜はる。時に紙乏しく価甚だ貴し。故に特に此れを以て潤筆に充つ。生、京に還り賜を捐て詩画の大会を設く。葢し十品の変化千様、詩画凡て二千幅を将て、東山の芙蓉楼に展観す。餘紙は賓客の揮灑に供すと云ふ。予に題寄を需む。聊か賦して責めを塞ぐ」と題する七絶(『詩鈔』巻八)がある。〈剡藤紙〉は、『書言故事』巻十二、紙類に「剡渓、藤を出だす。紙を為りて絶妙」と。〈十品〉とは、竹・梅・菊・蘭・岩・蝶・牡丹・虎・鶏・龍をいう。
才藻多多益辨優 才藻多多益ます弁じて優なり
三千賜紙擅風流 三千の賜紙 風流を擅にす
大名天下無雙會 大名 天下無双の会
豪擧東山第一樓 豪挙 東山第一の楼
◯才藻 詩文の才。『三国志』魏書、阮籍伝に「才藻艶逸」と。◯多々益弁 前掲、「猪飼文卿に似す」詩の語釈参照。◯豪挙 豪快な行動あるいは豪勢な催し。
森氏によれば、雲卿が藤堂侯から拝領した唐紙によって京で大々的に詩画会を催したのは、文化4年。その際、雲卿は知友に題詩を求めた。そのうちの一人が菅茶山で、「千詩画引、原雲卿の需に応ず」という長編の七古(『黄葉夕陽村舎詩』巻八)を作っている。
雲卿は文化2年に津から京にもどる帰途、伊賀上野の東陽のもとを訪れたらしい。そのおり東陽の肖像画を描いてくれた。七絶「大原雲卿、予が為に真を写す」(『詩鈔』巻八)に云う、
風流到處彩毫新 風流到る処 彩毫新たなり
佳士相逢為冩眞 佳士相逢うて為に真を写す
慙媿老衰窮措大 慙媿す老衰の窮措大
何堪更作畫中人 何ぞ堪へん更に画中の人と作るを
◯彩毫 五色の筆。◯佳士云々 この句は、杜甫の七古「丹青引」に当時の有名な画師曹覇について「偶たま佳士に逢へば亦た真を写す」というのに基づく。〈佳士〉は、品行や才学にすぐれた士。〈写真〉は、真実を描くというのが、本来の意味。◯慙媿 うら恥ずかしく思う。◯窮措大 貧乏書生。『薈瓉録』巻下に措大の条がある。◯画中人 南宋・陸游の七律「新晴舟を泛べて近村に至る、偶たま双鱖を得て帰る」詩に「青嶂会《かなら》ず身後の塚と為らん、扁舟聊か画中の人と作る」と。
「貴君は行く先々で才筆を揮い、すぐれた御仁の真の姿を描かれている。おいぼれの貧書生、画にかかれるほどの人間ではなく、お恥ずかしいかぎりだ」。
この詩と同じ時期の作に七絶「雲卿を携へて昨非庵に遊ぶ。既に辞して山を下りて復た回りて留め宿し、情を書して雲卿に示す」詩(『詩鈔』巻八)があるが、これは省略する。ちなみに、〈昨非庵〉は伊賀上野にある山渓禅寺の住持、機宗和尚の庵で、七古に「機宗長老の昨非庵に宿す」と題する作(『詩鈔』巻一)がある。
さらに東陽には、七絶「雲卿の水墨の山水に題す」詩があり、
一片青山靄遠空 一片の青山 遠空に靄たり
桃花水漲下江風 桃花水漲り江を下る風
長年三老都無事 長年三老都べて無事
睡過春帆細雨中 睡過す春帆細雨の中
◯一片青山 金・元好問「髙平道中陵川を望む二首」其一(『遺山先生文集』卷九)に「一片の青山幾今昔」と。◯長年三老 杜甫の七律「悶を撥ふ」詩に「長年三老遥かに汝を憐れむ、柁を捩じらして頭を開く捷きこと神有り」と。この詩は東陽の『杜律詳解』巻中に収め、〈長年〉に「センドウ」、〈三老〉に「オヤカタ」と左訓を施す。
と、雲卿が描くところの山水画の世界を詠じている。
なお、『薈瓚録』巻上に羆の条あり、ヒグマの獰猛さについて記したなかに「牛馬取ルハ人立シテ攫ミ二ツニ折リテカツギ去リ骨ニ至ルマデ喰尽クス、松前第一ノ危患ナリト、彼人語リテ舌ヲ掉ヘリ」という。この〈彼人〉とは、おそらく雲卿のことであろう。さらに同書巻下の腐刑の条には「亡友大原呑響ガ松前ニ在リテ陰寒ニ中リ疝陰ニ入テ苦シミケルニ、針術ノ上手アリテ睾丸ヲ刺シタリ。コレニ依テ腫治リ痛ハ止ミケレドモ、自後陽具永ク痿シテ終ニ夫婦ノ道絶タリト語レリ」という。これらの記述は、大原雲卿についての論考にあまり取り上げられていないようなので、ここに補っておく。
※大原雲卿については、井上通泰「浪人大原左金吾の話」(『南天荘雑筆』所収。春陽堂、昭和5年)、森銑三「大原左金吾」(『森銑三著作集第七巻人物篇七』、中央公論社、昭和46年)がある。また中村真一郎『蠣崎波響の生涯』(新潮社、平成元年)、富士川英郎『菅茶山上・下』(福武書店、平成2年)参照。
◀覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(5)
▶覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(7)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
