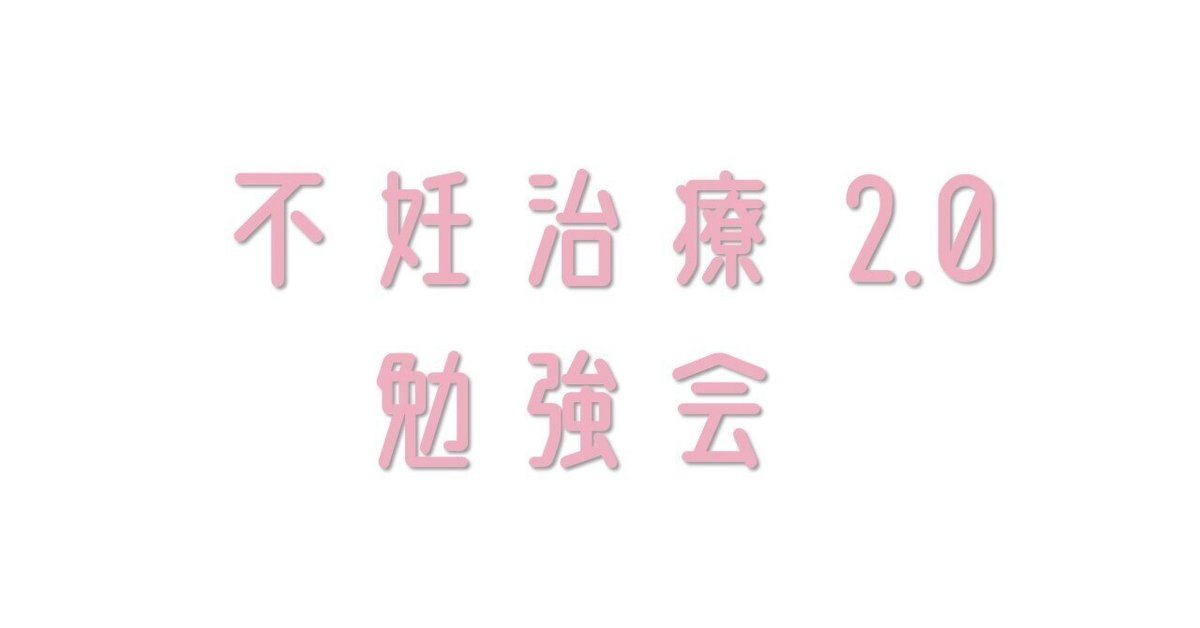
タイミング法のススメ ~卵胞計測、排卵誘発の実践~ ⑤排卵障害の種類と誘発剤の選択

先の排卵障害の考え方で、排卵障害の種類を明らかにしましょうというものがありました。排卵障害の原因についてはどのように考えれば良いでしょうか。大まかに、卵巣性、中枢性とそれ以外に分けていただくと分かりやすいと思います。これらはホルモンの基礎値(E2、FSH、LH、PRL)を測定することで鑑別することができます。
卵巣性とはすなわち、卵巣に排卵する卵子が残存しておらず、排卵するものがないため排卵障害となっている状態です。この場合、脳はなんとか排卵させようと刺激を強めていくため、FSH、LHの基礎値は上昇します。また、AMHは低値となります。卵子が少しでも残存していればまだチャンスはあるため、速やかに専門施設への紹介が望ましいと思います。
中枢性とはすなわち、卵子は残存しているが、排卵させるだけの力が出ていない状態です。脳からの刺激が低すぎるため、卵子があっても発育せず、排卵障害となります。この場合、FSH、LHの基礎値は低下しています。視床下部性と下垂体性がありますが、いずれも難治であることが多く、専門施設への紹介が望ましいと思います。
それ以外は、高PRL血症やPCOSなど、卵子が残存しておりホルモン基礎値が保たれているものになります。これらはホルモン状態の改善や排卵誘発での対応が比較的容易です。

排卵障害の原因を把握した上で、排卵誘発剤を使用します。排卵誘発剤はFSHを上昇させて卵胞の発育を促進しますが、内服剤と注射剤に分かれます。内服剤は下垂体から分泌される内因性FSHを増加させ、注射剤はFSHそのものを直接供給し外因性FSHを増加させます。内服剤、注射剤のいずれにせよ、卵子が残存しているのは条件となります、また内服剤で内因性FSHを上昇させるためには下垂体からのホルモン分泌が保たれている必要があります。FSHレセプターが機能していない場合は、FSHを注射剤で直接供給しても卵胞の発育はありません。
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
