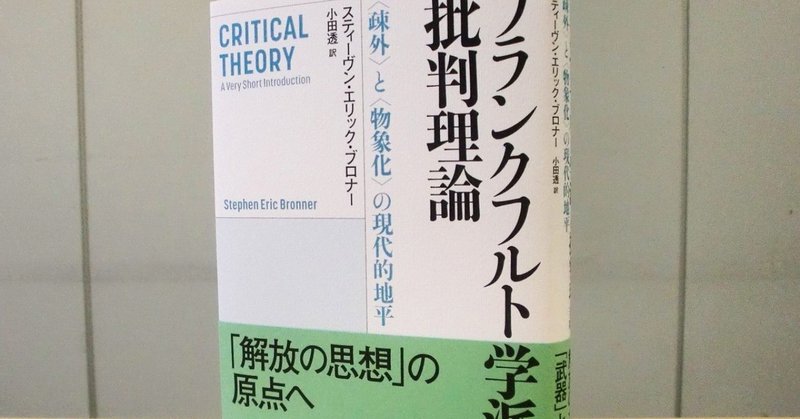
【読書メモ】エリック・ブロナー『フランクフルト学派と批判理論ーー〈疎外〉と〈物象化〉の現代的地平』(白水社、2018年)
個人的に他人の読書感想文よりもどんなことが書かれているかの方が気になるのでエリック・ブロナー『フランクフルト学派と批判理論ーー〈疎外〉と〈物象化〉の現代的地平』(白水社、2018年)の抜粋メモを作成した。(立命館大学生存学研究所のHPのarsvi.com蔵書検索エンジンのように蔵書と基本情報、抜粋が載っているものをイメージした)
目次情報などについては出版社のリンクを参照。
なお、出版社の本著のページからは訳者解説が全文読むことができ、本著の問題意識や訳者のコメントが確認できる。
その上で少しだけ感想を書く。本書は批判理論のラディカルさを再び現実の社会問題を捉える際の導きの糸として積極的に用いていこうという著者の問題意識に貫かれており、フランクフルト学派の入門書としては読みやすいのだろうと思う。個人的には学派や歴史に名を連ねる人物の本だとフロムの『自由からの逃走 新版』(東京創元社、1952年)と『グラムシ・セレクション』(平凡社ライブラリー、2001年)くらいを読んだくらいで、いまいちその独自性などは理解できていなかった。今回はアドルノの『社会学講義』(作品社、2000年)を読みながら補助的に批判理論全体のことを確認しようと手に取ったのだが予想を超えてアクチュアルな問題意識に貫かれていたので面白かった。正直、シュトレークの『時間かせぎの資本主義』(みすず書房、2016年)を読んでいたこともあり、フランクフルト学派へのイメージは「資本主義の制御可能性」を前提として社会的、文化的正当性を論じており、いわゆる「下部構造」への視点が欠けている衒学的なイメージを持っていた。一方で、本著を読むことでむしろ批判理論が「疎外」と「物象化」をキーワードにしながら、特にアドルノが実証主義論争で「社会的総体性」と呼んだ「社会」の概念を基に現実社会を分析していたことが理解できた。
アドルノが指摘するような、社会の概念、すなわち諸個人の寄せ集めではなく、その関わりによって形成されながら、諸個人から切り離された実体ではないという社会の概念は、マルクスのいう経済的形態規定という概念を理解するうえでもっとも基礎的な認識となる。
— 佐々木隆治 (@ryuujisasaki) May 2, 2018
また、訳者解説では現状に対抗する思想をめぐる闘いの一例としてナオミ・クラインの『NOでは足りない』(岩波書店、2018年)のトランプ分析をあげている。トランプが行なっていたTVショー自体が新自由主義の論理を体現するものであり、いわゆる「勝ち組」になるための競争に参加することを新たな”常識”としてメディアを通じて作っていったという内容だ。確かにそう言われるとまさにクラインの分析や著書は「私たちの生活を形成する政策や制度に埋め込まれている、様々な優先順位や利害関心」(159頁)を明らかにし、「抑圧の条件を明らかにすること、抵抗に向かう道を開くこと、解放の理念を作り直すこと」(182頁)を目指した批判理論に忠実だと言える。
社会理論系の本でこのような表現を使うのは不適切かと思うが、久しぶりに読みながらページが止まらなくなってしまった。少しでも興味がわいたら是非とも通して読んでほしいと思う。
はしがき
本書の初版が出たのは、二〇一一年のアラブの春、アメリカ合衆国におけるオキュパイ・ウォールストリート運動、南ヨーロッパにおける緊縮経済に反対するデモが勃発した直後のことだった。改訂版となる本書が仕上げられたのは、世界的な揺り戻しの只中でのことである。世界に広がる反動的叛乱は、野蛮なシリア内戦を引き起こし、西側に逃れようとする移民の波を作り出し、ヨーロッパの至る所で外国人排除を掲げるネオファシズム的な政党を再来させ、アメリカ合衆国でティーパーティの勝利をもたらし、二〇一六年にドナルド・トランプを大統領に選んだ。批判理論の政治的次元と倫理的目的に再び生命を吹き込むことは、今日、以前にも増して急務である。(7頁)
本書がはっきりと打ち出していたのは、実践にとっての理論の重要性であり、理論にとっての実践の重要性である。批判理論が変容をもたらす営為であると理解することは、批判理論の今日性、唯一無二性、真にラディカルな性格を保つための前提条件であり続けている。そう私は論じたのだった。……この新版でも強調しているのは、西洋の外、すなわち、批判的伝統がもたらす洞察を最も必要としているにちがいない国々において高まりつつある、批判的伝統の知名度(とその活性化)である。新たな形で立ち現れてきている権威主義的な過剰さ、制度的な偏狭さ、宗教的過激主義、階級的衝突、様々な構造的な権力の不均衡にたいして、批判理論の新形態は建設的に応答できるし、そうあってしかるべきである。(8~9頁)
イントロダクション――批判理論とは何か?
批判理論が拒絶するのは、制度組織や固定的な思想体系のたぐいを、自由と同一視することである。批判理論は、競合する理論や既存の実践形態が隠し持っている前提や目的を問い直す。「永遠の哲学」なるもののためにはほとんど役に立たない。批判理論の主張はこうである。思想は、変化する歴史状況から生起する新たな問題や新たな開放の可能性に応答しなければならない。批判理論は様々な領域のあいだに身を置き、他に類を見ない実験性を持ち、伝統もいかなる絶対的主張も深く疑ってかかった。物事がどのような状況にあるかということだけに思いをめぐらせていたわけではない。どうありえるかもしれないのか、どうあるべきなのか、ということにも、つねに思いをめぐらせていた。この倫理的要請に導かれ、批判理論の代表的思想家たちは一連のテーマ群や新たな批判的方法を発展させていき、それが社会についての私たちの理解を変えたのである。(11~12頁)
彼らがマルクス主義のうちで際立たせたのは、その体系的な主張ではなかった。批判的方法、疎外と物象化への関心、啓蒙主義の理念とのあいだに切り結ばれた複雑な関係、ユートピア的契機、イデオロギーへの役割の強調、個人をゆがめるものに決然と抵抗する意思的態度であった。(13頁)
第一章 フランクフルト学派
マックス・ホルクハイマー/エーリッヒ・フロム/ヘルベルト・マルクーゼ/ヴァルター・ベンヤミン/テオドール・W・アドルノ/ユルゲン・ハーバーマス
アドルノは時おり政治問題を扱った。しかし、大衆運動にはつねに恐れを抱いていた。否定はそれ自体として価値あるものになっていたし、アドルノは、個人と社会のあいだの「非同一性」を確保することを抵抗と同一視した。批判理論の現代的理解に与えたアドルノの影響は群を抜いている。自由の微かな煌めきに捧げられた批判理論の譲歩なき誓約を、アドルノ以上に見事に体現している思想家はいない。(30頁)
第二章 方法の問題
フランクフルト学派は西欧マルクス主義の提出した知的枠組み--歴史、行為体、弁証法的方法に強調を置く枠組み--からインスピレーションを受けた。ルカーチ・ジョルジュ、カール・コルシュ、アントニオ・グラムシが、この潮流を代表する主導的存在だった。(33頁)
確かに、科学的合理性のほうが有害だとフランクフルト学派は考えていた。だがしかし、学派のメンバーたちはもともと実証主義と形而上学の両方を激しく非難していた。実証主義も形而上学も、批判的省察、歴史、ユートピア的想像力に目を向けようとはしなかったからだ。
批判理論は、解放の欲望によって焚きつけられた、社会についての一般理論として意図されたものである。新たな社会状況がラディカルな実践のための新たな観念や問題を生み出し、解法の内実が変わるに合わせて、批判的方法の性質も変化するだろう、と批判理論の実践者たちは理解していた。こうして、実践の文脈を強調することが、フランクフルト学派の新たな学際的アプローチの中核になってきた。学派のメンバーたちはここから、事実と価値のあいだの伝統的切断を退ける方向に導かれていった。
批判理論は、事実を、現実の抜粋的描写というよりも、社会行動が結晶化した歴史的生産物として扱うことになる。批判理論が目指したのは、事実が意味を帯びる価値の充満した文脈のなかで、事実を、理解することだった。ルカーチはすでに史的唯物論の中心に全体性というカテゴリーを据えていた。それはマルクスが「社会諸関係の総体」と名づけたものである。全体性は様々な契機によって構成され、そこで経済は、国家や、文化的領域--これ自体、宗教、芸術、哲学に分割されうる--といったもののなかで、ひとつの契機をなすに過ぎないと見なされた。契機の一つひとつが全体性によって形作られてはいる。しかし、ヘーゲルの述べたことを繰り返すなら、それぞれの契機に独自の力があり、それゆえ現実の現用を目論む行為体(たとえば労働階級)の実践にインパクトを与えるとも言える。こういうわけで、どの契機もおろそかにできないのである。(38~39頁)
批判理論が目指したのは、若きマルクスの指令を遂行し、「存在するものすべての仮借なき批判(ルースレス・クリティーク)」にコミットすることだった。その代表的な主導者たちは次のように力説した。全体(ホール)は特殊(パーティキュラー)の中に見出さうるし、特殊(パーティキュラー)は全体(ホール)を反映する。(40頁)
マンハイム「知識社会学」/ベンヤミンの「新しい天使」解釈/ヴェーバーの影響
第三章 批判理論とモダニズム
モダニズム芸術/ニーチェの影響/「ボヘミアン」「アヴァンギャルド」への評価
第四章 疎外と物象化
1932年の『1944年 経済学・哲学草稿』の出版と言う「桁違いの知的イベント」の影響/西欧マルクス主義への影響
疎外が、そして暗黙的には物象化が、いまや、ラディカルな実践の目指すところとなる。このような考え方は一般的なマルクス主義理解を大きく変え、共産主義体制を大いに困惑させ、フランクフルト学派を活性化した。一九六八年の知的ラディカルにも増して、フランクフルト学派はこのような考え方に影響を受けたのである。(64頁)
疎外の規定する全体性が永続するか否かは、人々のモノ化、すなわち物象化にかかっている。資本主義は人間から人間性を奪う一方である。資本主義は、商品生産に従事する真の主体(プロレタリア)を客体として扱うそのかたわらで、生産活動の真の客体(資本)を近代生活の虚構の主体に転化することさえする。この「逆立ちした世界」を逆転すること--マルクスがヘーゲルから借用したアイディア--は『資本論』において「商品の物神化」となづけられているものを廃絶することによってのみ可能である。多少別の言い方をするなら、疎外の廃絶は物象化の廃絶を要求する、ということだ。(70~72頁)
ヴェーバーの影響/ルカーチ、グラムシ、コルシュが投げかけた「解放された世界のビジョン」/『歴史と階級意識』/フロム『自由からの逃走』/ホルクハイマー『権威主義的パーソナリティ』/ハーバーマス『認識と関心』/『コミュニケイション的行為の理論』における「言語論的転回」、ホネットにおける「配慮」と「承認」、生産過程や政治組織の等閑視
第五章 啓蒙された幻想
ホルクハイマー、アドルノ『啓蒙の弁証法』1944年について
この著作が精査するのは、科学的(ないし道具的)合理性がいかにして歴史的過程から自由を放逐し、物象化が社会の隅々まで行き渡すことを可能とするのか、という点である。芸術でさえ単なる商品と化し、批判性を失う。弁証法的言説はいまや、迎合主義を、奔放な作家や芸術家しか気に入らない以上の何かとして扱う。そればかりか、革新的でラディカルなひねりが形而上学に加えられる。「完全に管理された社会」に対するホルクハイマーとアドルノの対応は、体系的思考に対する体系的攻撃である。(83~84頁)
(アドルノとホルクハイマーは)真にラディカルであることとは、問題の「根源」まで行くことである(マルクス)に忠実だった(85頁)/「反ユダヤ主義」/科学的理性/ヘーゲルとマルクスを補うのに、ニーチェ、フロイト、マックス・ヴェーバーから引き出した洞察を用いる(88頁)
増大していく道具的合理性の支配と完全に管理された社会である。新たな展望が投射する新たな抵抗形態は、主体と客体--哲学的ニュアンスを弱めた言い方をするなら、個人と社会--の「非同一性」の協調を要求する。全(ホール)が偽(フォールス)であり、進歩が幻想であるかぎり、唯一可能な批判的選択肢は、のちに否定弁証法として知られることになるものを発展させることである。この道を行くことによってのみ、批判は、啓蒙に随行する幻想と正面から対峙するのかもしれない。(88頁)
主体性の喪失/自律性の倒錯/技術的ないしは感情的な判断を下す以外に何かをする能力が、個人からますます失われていると考えられる……良心を行使して自由な社会を創造することが、輪をかけて難しくなるし、まさにそれゆえに、全体主義の訴求力が高まる。(89頁)/実際の進歩とは弓矢から原子爆弾に至る運動である(アドルノ)/ゲーテの愛した楢木/『啓蒙の弁証法』で言及されるマルキ・ド・サド、ショーペンハウアー、ベルクソン、ニーチェといった反リベラル、反社会主義、反民主主義、反平等主義、反合理主義、反歴史主義/「歴史的特定化」の欠落/ヨーロッパのファシズム=自由主義と社民主義に対する自意識的イデオロギー的応答≠何か出来合いの哲学的弁証法の産物
問題は道具的合理性、元凶は商品形態、敵は文化産業である。道はひとつしかない。現在進行形の抵抗だけであり、それは真正であるかもしれないが、常に手からすり抜けていく個体性の経験の名のもとに闘われる。(98頁)
第六章 ユートピアの実験室
批判理論がなすべきはミメーシスの再定義であり、そのさい目を配るべきは、モンタージュや意識の流れなど、現実を経験するための、そして人々のユートピア的憧憬を引き出すための新たな形式--新たな幻想--である。これらの憧憬はおそらく、最も実現されそうにないときに最高潮に達するだろう。(102頁)
シラー『人間の美的教育について』(1795年)/ベンヤミン「希望なき人びとのためにのみ、希望はわたしたちに与えられている」/エルンスト・ブロッホ/ルカーチとヨーロッパモダニズム全般、ドイツ表現主義
わたしたちが持っているものは必ずしも私たちの欲しいものではないし、わたしたちの欲しがるものだけがわたしたちの持てるものだとは限らない。そのことを、ユートピアはわたしたちに気づかせてくれる。……しかし、ブロッホの営為の持つ批判的契機とは、不合理の合理を描き出そうという試みであり、それは批判理論の伝統的内部に堂々とそびえているものである。このことは、魔術や神秘主義を理解するのみならず、直感的なものや不合理なものを特権化する人種主義などの諸イデオロギーに埋め込まれた「偽ユートピア」を理解する上で重要である。(108頁)
マルクーゼ『エロス的文明』/太古の昔より抑圧されてきた開放的欲望や希望や幻想を分節しようという試み(110頁)/ユートピアが投射するのは、創造活動の昇華形態--主体と客体を結び合せ、リビドーをあらゆる制約から解放するもの--である。(112頁)/背景:(仏)サルトルの実存主義者、(独)ギュンター・グラス「四七年グループ」、(米)ビート世代/マルクーゼへの批判…ハーバーマス「〈イデオロギー〉としての技術と科学」、フロム『精神分析の危機』『精神分析の見直し』/フロム対するアドルノ、マルクーゼの批判
もしフロムが正しければ、批判理論は再び--新たなやり方で、新たな条件ではあるが--自らを実践の理論とみなさなければならない。その場合、批判理論は、搾取と抑圧に対処するための実践的なアイディアを提出すべきであるし、人間主義や啓蒙主義につらなる存在論を肯定することである。その場合、抵抗の可能性とラディカルな自由の概念を保持することを可能にするのは、否定弁証法と人類史的断絶のヴィジョン以外にないことになる。理論が実践をやり込める。臨床治療を優先し、個々人の心理的苦境の改善を旨をすれば、現状と妥協し、抑圧に適応することになる。アドルノは『ミニア・モラリア』でこの問題を衝撃的なかたちで書き記している。「間違った生活は正しく生きられない」。だがしかし、間違った生活の間違いの度合いには幅があるかもしれないし、それを生きる際の正しさの度合いには幅があるかもしれない、ということもありうる。(117頁)
ユートピア小説・ディストピア小説/最良の生活の夢という人類不朽主題とユートピア/「統一された多様性」を推し出し、より豊穣で複雑な個体性の形態を育むもの、そういうものとしてユートピアを見ようではないか。(119頁)
第七章 幸福な意識
主体性と自律の内実の危機、外在的な力に抗う個人の意思と能力/大衆社会に反対することは、大衆文化に反対することである。それがフランクフルト学派の前提だった。(123頁)/文化産業は完全に管理された社会の本質的な特徴である、とフランクフルト学派は信じていた。(124頁)/アドルノ「音楽における物神的性格と聴取能力の退化」(1938)/文化産業による経験の標準化と、日常を生きる人々の伝統や権威への従順化/ハーバーマス『公共圏の構造転換』/「公共圏」…国家に属する組織化された政治制度と、市民社会の経済的諸力とを媒介するもの/『後期資本主義における正統化諸問題』(1973)
物象化が公的生活を掌握している。そればかりか、虚偽意識の存在論が主体性や道徳的判断を下す個人の能力を脅かしている。従って、幸福な意識の力にたいする抵抗は倫理的要請となる。少なくとも、フランクフルト学派そう信じた。ここで問われるべきは、ほかならぬ次の点である。そのような抵抗は何を含意し、何が随伴するのか。もし完全に管理された社会が真に全体的で、どんな批判的企ても自らのうちに取り込み、飼い慣らすことができるなら、政治活動のための見通しは暗い。政治実践としての抵抗は無価値な営為となる。否定が唯一可能な選択肢となり、否定弁証法が批判的プロジェクトを定義しなければならないことになる。だがそれとは反対に、もし組織的活動に実効性があると証明できれば、システムは完全に管理されていないことになるし、(政策や綱領にかんして)実質的なオルタナティヴが存在するがゆえに、否定弁証法とは異なる批判的アプローチが要求されることになる。完全に管理された社会を内在的な傾向と見なしても、事態は改善しない。否定弁証法と実践の理論は相互に排他的な選択肢である。(128頁)
ドイツ帰還後の学派の政治的態度/寛容…(かつて)宗教由来の偏見や支持的権威の批判、実験、判断力の行使←→(現在)現状維持の砦/マルクーゼ「抑圧的寛容」(1965)/『一次元的人間』/ポピュラー・カルチャーへの無関心
第八章 大いなる拒絶
1960年代学生運動の知的刺激/労働者階級に代わって革命的意識が立ち上がるとすれば女性、有色人種、システムの周縁での反帝国主義運動、知識人、ボヘミアンが新たな感性を労働者に提供/マルクーゼ『解放論の試み』/「軍産複合体」、ジョンソン大統領「偉大な社会」プログラム、「フリーダムライダーズ」/ニューレフトは文化的変容に特権的地位を与えた最初の大衆運動だった。それこそが、批判理論やフランクフルト学派と、ニューレフトとのあいだに、類縁関係を生み出したのである。(140頁)/1980年代アメリカでの保守派のバックラッシュ/ホルクハイマー「完全なる他への憧憬」/宗教・芸術・哲学/アドルノ『批判的モデル集3』(1969)/「諦念」は、かつてもいまも、字義通りのことを意味している。コミットメント(アンガージュマン)の拒否、制度を変えるための組織的プロジェクトからの離脱である。(145頁)
アドルノの『美学理論』(一九六九)が投げかけるのは、あらゆる客体化に抵抗する主体性、自由、ユートピアの概念である。アドルノの並外れた知力の実例であり、衰えることのない彼の魅力を立証するこの金字塔的著作は、社会のモナドとしての芸術作品から立ち上がってくる緊張関係を強調する。……アドルノが次のふたつのことをつねに目指していたのは特筆してよい。美的形式の使用を形式主義的に変質させないこと、ユートピア的な憧憬を非合理主義的に瓦解させないことである。アドルノ矯正案は、作品と虚偽状態の存在論を批判的に繋げること、間違った生を正しく生きようという軽率な試みを作品が全面的に拒否することにある。(145~147頁)
(『否定弁証法』(1966)、『三つのヘーゲル研究』(1963)について)
これら二著作は、進歩についての歴史的理解に全く言及することになしに、否定それ自体として確証する。個人と社会のあいだの緊張関係の解決は不可能である。解決を投射しようという試みは自滅的だ。否定弁証法がそれに代えて肯定するのは、主体と客体、個人と社会、特殊と普遍の非同一性である。しかしながら、非同一性は簡単に公言できるようなものではない。特定の状況でどのように表現されるのか、所与の経験がどのように客体化を逃れるのか。そこを説明するためには、批判的省察が必要となる。……そこに残るのは、定義もできなければ規定もされていない憧憬についての省察--その実現を否定する現実が顕現させた、自由に対する憧憬についての省察だけである。ここには連帯の痕跡の名残しかない。メタクリティークには、商品形態、官僚的位階制、文化産業に支配された世界で連帯を具体的に育て(ないしは、妨げ)ていける制度や組織のための余地が、まるで残されていない。(148~149頁)
「続けられない。続けよう」(ベケット『名づけえぬもの』)/新たな形而上学的形態/唯物論よりも形而上学の優位/「一度時代後れになったように思われた哲学が今なお命脈をたもっているのは、その実現の機を逸したからである」(アドルノ『否定弁証法』)
第九章 諦念から再生へ
しかしながら、フランクフルト学派は第二次世界大戦の勃発をだどりながら、次のように結論した。開放的なオルタナティブが消え失せてしまっていた、と。(151頁)/マーティン・ジェイのアメリカでの紹介/(ハーバーマスを指して)批判理論における形而上学的転回は、ハーバーマスの異議申し立てに抗ってきているし、自家薬籠中のものとしてきたと言ってもよい。(154頁)/一方で政治的敵対者からすれば「だから何?」/『権威主義的パーソナリティ』
批判理論の形而上学的転回は精密に吟味されなければならない。完全に管理された社会や虚偽状態の存在論のようなカテゴリーについても同様である。完全に管理された社会に関するフランクフルト学派の経験主義的主張は無効であるし、虚偽状態の存在論への哲学的依拠はそうした主張を有効にする手助けにならない。革命的行為体としてのプロレタリアを排除したことの帰結は、完全に管理された社会ではなく、むしろ、特定の社会政策、文化価値、制度的発展をめぐってのエリート--ないしは支配階級--の内部分裂である。これらが労働者やサバルタン・グループに及ぼした影響は非常に異なっている。それに、マルクスが資本の政治経済、労働の政治経済と呼んだものは依然として対立関係にある。(156~157頁)
現に存在しているイデオロギー的で物質的な利害の衝突、社会内部のアクチュアルな衝突の再認識/抵抗、支配、歴史的特性性、そして具体性の回復/疎外と物象化はかつて、支配の経験と変容的実践の要請に語り掛けていた(158頁)
官僚制や道具的合理性の形式的性格が重要なのではない。重要なのはむしろ、それらをどう使うのかという問題のバックボーンをなしている(隠れたままになっていることも珍しくない)価値観や利害関心の方だ。批判理論が精査していくべきは、目的論的目的である。私たちの生活を形成する政策や制度に埋め込まれている、様々な優先順位や利害関心と言ってもいい。道具的合理性の形式的性格に執着することそれ自体が、物象化の表出である。それが科学とその方法の解釈に対して及ぼした影響は、弱体化につながるものであった。
批判理論はそもそも、社会の調査を自然の調査から峻別することで、正統派マルクス主義と対決した。しかしながら、認識論的形式主義という観点から道具的合理性を取り扱うと、この区別が切り崩されていく。科学理論や技術革新を文脈化しようという社会学的試みは正当であるし、広く行われてもいる。しかしながら、基本的理論が、科学理論や科学技術の内的なはたらきについて判断を下すというのは、また別問題である。単純化すれば、次のようになるだろう。アルベルト・アインシュタインが導入した相対性理論を例にとろう。批判理論は相対性理論の歴史的起源や社会的使用について有益な視座を提供できる。だが、相対性理論の真実性について、哲学的判断を下そうと試みるべきではない。(159頁)
批判理論は、……(ポパーの)「反証可能性」の概念を基盤に置くことで、うまい具合になるだろう。(160頁)/フランツ・ノイマン「政治権力研究へのアプローチ」(1950)/政策における合理・非合理性における基準を位置付ける/啓蒙の遺産の継承/人権、寛容、コスモポリ多ニズムの理念←→宗教的狂信主義、文化的地方主義、権威主義的反動(反啓蒙)/『サタデー・ナイト・ライブ』の批判性と文化産業の可能性/ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」(1935)/公共哲学としての批判理論
ラディカルな公共哲学を育むことは、公的な問題を問い質し、社会が個体性の成長を阻害するやり方に対してオルタナティブを提出することによってのみ、可能となる。……そうした営為の基盤となるのは、既存のイデオロギーや制度が隠蔽する方向にある価値観や違い関心を明らかにすることである。そうすることで、市井の人々がそれらに判断を下し、適切に対応できるようになる。……(批判理論に影響を受けたC・ライト・ミルズ『社会学的想像力』(1960)での主張のように)……力を持つ人々の無数の制度に、力を奪われている人々に対する説明責任を果たさせるためである。(170~171頁)
多面的な変容(トランスフォーメーション)のプロジェクトを抱きながら世界と対峙することによってのみ、批判理論は、自らの唯一無二性を改めて主張し、生命をみなぎらせる理念を際立たせることができる。連帯、抵抗、自由という理念を。(172頁)
第十章 未完の課題――連帯、抵抗、グローバル社会
抵抗が求めるのは、リベラルでコスモポリタンな原理と、経済的な階級利害とをリンクさせることである。これは間違いなく、植民者より、被植民者の方がよく理解してきたことだ。……階級理念は依然として実現待ちの状態である。解放をめぐる過去の遺産はまだこれから奪還=再生していくべきである。この自律性は依然として宗教や権威主義に脅かされている。個の自律性は依然として宗教や権威主義に脅かされている。(173~175頁)
批判理論の再構築かつ脱構築/ネオ・ファシズムへの抵抗/「物欲の後にくる」欲求の重要性を力説することは、蓄積過程に気を配ることを妨げ、権力の経済的不均衡をうやむやにし、アイデンティティをめぐる文化的執着の強調をもたらしてきた。(175頁)/現代の反動主義運動/イラン革命のフーコーの誤った判断/グローバル化
批判理論に必要なのは、社会についての批判的政治理論として再起し、そのコスモポリタンな意思を改めて肯定することである。わたしたちは依然としてわたしたち自身や私たちの伝統のほう内向きな視線を注ぎがちである。……カントはかつて、コスモポリタニズムを、どこにてもくつろぐこのとのできる能力と定義した。……今日の倫理的命法とは、わたしたちのいたるところで「他に」くつろぎを感じてもらうことである。(180頁)
新形態の批判理論は、イランにおけるグリーン・ムーブメント、アラブの春、オキュパイ・ウォール・ストリート、緊縮経済に対する南ヨーロッパでの反対運動の、組織的、戦略的弱点について考えをめぐらすべきである。現代における反革命の勝利を説明することも必要だ。フランクフルト学派は自らの時代のためにそれに取り組んだし、その過程において、学派メンバーたちは、家庭、性的抑圧、教育、虐殺、娯楽、文学分析、それからその他さまざまな事柄についてわたしたちの理解を豊かなものにした。経済、国家、公共圏、法律、グローバル・ライフに刻印を押している権力の構造的不均衡を明らかにするのに助力した。抑圧の条件を明らかにすること、抵抗に向かう道を開くこと、解放の理念を作り直すこと、これらは批判的伝統の革新的な企図であり続けている。しかしながら、グローバル化していく社会の内部で変容の見通しを育んでいくには、新たな視座が必要である。次に必要となるのは、批判理論を、現在進行中の批判的問い質しに従属させることである。そうあらねばならない。そうすることによってのみ、批判理論は、批判的営為の根源的な精神に誠実でありつづけることができるのである。(182~183頁)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
