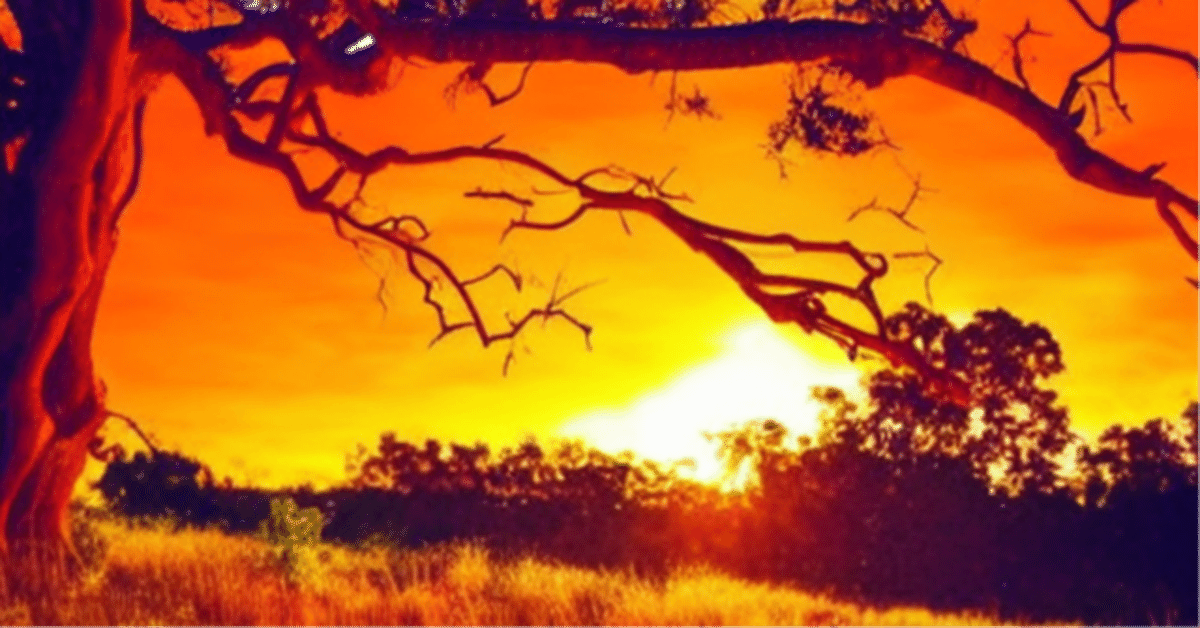
つかっちゃんの文学エッセイ1000①
適宜更新します。
(YouTubeに投稿した動画の文字起こしします)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#988「最近に読んで面白かった小説を4冊ほど紹介します」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと僕が最近 読んで
面白かった小説4冊を
紹介しようかと思います最近は色々 小説を読んでまして特に今回 紹介する4冊は今年ですね2024年に発売された最近の小説となっております早速やっていきましょう1冊目①豊永浩平
『月ぬ走いや、馬ぬ走い』
講談社 2024こちらは今年の群像新人文学賞
の受賞作となっておりますね言ってしまえば沖縄文学になるわけですねこの作者の人も沖縄出身で書かれている内容もずっと沖縄の話なんですけどこれは群像劇になってまして複数の主人公がいるんだけど普通の群像劇じゃなくて時代とかも全部 違っててつまり戦時中ぐらいから現代までに渡ってだいたい3世代から4世代ぐらいの間をずっと書いてる例えばですけど現代だったら中学生が1人いて 男の子がいてその子は学校の帰り道にある女の子と
一緒に帰るっていうか
一緒に喋るところがあってその子にグラップラー刃牙を貸してあげるみたいなそういうことで いわゆる青春みたいな書くんだけど今度はその女の子視点になってその女の子はお母さんが毒親みたいな感じでそのお母さんからどうしても逃げたいって思ってたりとかその彼氏も実はいてその彼氏はバイクに乗っててなんとかとかというのがあったり もしくは戦時中に沖縄だから地上戦があるんですよねその地上戦で 天皇から直接もらった恩賜の軍刀というのを持っている兵士がいてそれで相手の敵軍を切りつけて攻撃するっていう戦闘状態に入っているシーンがあったらその敵軍のアメリカ人の男の人が今度 主人公になってその人は実は日本人の女の人と結婚しててその相手の軍刀を実は持っていると自分を攻撃してきた兵士の軍刀を実は自分が持っていてその戦後に軍刀を返しに行きたいと思ってたりとかこれ結構 繋がりもあるから昔の兵士の子孫が 実は今の
中学生のうちの1人だったとか繋がりもわかるんでこれ謎解きじゃないけどこの人はこの人の関係者だみたいな
見ていくっていう面白さもあった僕 普通にこれ 泣いちゃっためっちゃ良かった 素晴らしいと思いましたね2冊目2冊目は②西尾維新『鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの
汲めども尽きぬ随筆という題名の小説』
講談社 2024年こちらは西尾維新の純文学小説ですね西尾維新といえばライトノベルとか
ミステリーとか書いてる作家でもう20年ぐらいやってると思いますけれどもこの小説は「群像」掲載なので実は「純文学」っていうことに入る小説なんだよねこの小説を読んでみたら
とんでもない奇書だったっていう話でストーリーを言うと鬼怒楯岩大吊橋ツキヌっていう女の子がいるんですよその子が脳外科医の
犬走キャットウォーク先生っていう
お医者さんがいてそのペットシッターになるって話で究極 それだけの話なんだけど犬走キャットウォーク先生は猫を飼っているんですねまず その猫には1つ秘密があるんですよこれはここでは言わないけど すごい秘密があってあと この小説の特徴は全然 話が前に進まないっていうことなんですね言ってしまえば主人公の一人語りなんですね会話文とかがあるわけじゃなくてタイトルにもあるように随筆のように自分の考えとかをバーって語る話なんだけどだけど自分の言った言葉に対して自分でツッコんでいや実はそうではないだろうみたいなとかあと言葉尻みたいなだからちょっとコンプラみたいなを過剰に意識しすぎてて説明がうまくできないんだけどこの小説って160ページぐらいあるんですけど文字びっちりタイプねさっきの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』
も文字びっちりタイプなんだけどこの小説はもう全く前に進まないから結構ね 僕の知り合いとかでも
脱落した人がいっぱいいるんですよだから話の展開が後半にちょっとあるんですよね猫の秘密とかちょっと言うと これが主な猫の秘密じゃないけどその猫の特徴としては猫も餌を食べるでしょ餌を食べた量よりも もっと糞尿が多いっていうそれも特徴の1つもっとすごい秘密があるんだよそれにも ある秘密があるわけなんだけど謎は もっともっと後半に出るから後半まで行けるかどうかっていうのを試されている読者が試されている小説なんだけどなんか独特だよねやっぱり群像に来る感じはあったね昔から僕 西尾維新は純文学を
書いた方がいいみたいなことを言ってたから ついにと思いましたね嬉しかった この小説を読めてよかったと思う3冊目3冊目③赤松りかこ
『グレイスは死んだのか』
新潮社 2024年この赤松りかこさんっていうのは去年の新潮新人賞っていうのを『グレイスは死んだのか』の中に入っている「シャーマンと爆弾男」っていうのがあってこれで受賞して作家デビューしてるんですねこの小説の中には「グレイスは死んだのか」そして「シャーマンと爆弾男」の2つ入っていてどっちも良かったんだよね「グレイスは死んだのか」を説明すると主人公が獣医さんなんですね獣医さんの元にある犬を連れた男の人がいるとその人は元々競馬の躾をやってる男の人なんだけど足を悪くして仕事を辞めたとその犬がいて グレイスっていう犬がいて昔 その男の人はグレイスと山に入ったと猟師もやってたんですね その人それで山に入ったら遭難してしまうとその遭難した時に足をやられちゃって山の中で身動きが取れなくなって 座ってたらグレイスが食料とか持ってきてくれるわけよそのグレイスが取ってきた食料を食べて生き延びるんだけどこれ 逆転するわけねその男の人はしつけだって言って
グレイスもしつけてたんだけど山で遭難した時に逆転して言ってしまえばグレイスが男をしつけてるみたいな餌を持ってきてやってるのは俺だぜみたいな感じになって関係性が逆転した後に 2人は助かるんだけどそこからなぜかグレイスが謎の病気にかかってしまってそれで獣医のところに来るんだけど獣医も 結構 すごい獣医で色々 調べていったりするんだけどその病気はなんかその遭難の時の逆転現象に関わってきてんじゃないですかみたいなことになってきて みたいな話犬と人間の関係性とかもっと深い部分をやってる感じがあってとても良かったですねあと「シャーマンと爆弾男」もとても良くて主人公が女の人なんだけどお母さんが元々 南米の人で南米で主人公とは多分血が繋がってないんだけど赤ちゃんの時に南米から日本に来たわけよそこで主人公をシャーマンの末裔
みたいな感じで育てていくんですよ主人公も自分はシャーマンなんだ
と思って育っていくんだけど近くに川があって普通に川の中を
どんどん歩いていくんですね周りの自然とかを見ていったりするわけよその時に排水溝みたいながあるでしょ排水溝っていうか水を流すパイプみたいなところあるじゃないですか川のところにそこに小さな鳥がいるとだけど その主人公はシャーマンだからここにデカい洪水みたいなが来るのを予知するんですよねその大水が来た時にこの鳥たちがまだ飛び立っていないと 雛鳥だからその大水にやられてしまうんじゃないかと思ってその大水を阻止するためにはもっと上にある住宅地っていうのかな宅地みたいなところを爆破すると水の流れがうまく分散して雛たちを助けることができるって考えるんですよその時にちょうどホームレスのおじちゃんみたいなのが来てその人が昔 革命家で 爆弾を作ってたとその2人が友達みたいになってその男が「俺が爆弾を作って住宅地に
爆弾つけて爆発させてやるよ」とか言ってそれで洪水の日がやってくるみたいな話になってくるわけそこがめっちゃ良かったこれも1つ2つ深いところで書いた感じがあってやっぱりいい小説だと思うわこの赤松りかこさんもそれこそ『月ぬ走いや、馬ぬ走い』の豊永浩平さんもまだ新人ですからこの2人の今後の活躍を見届けたいという感じはしてますね最後 4冊目④町屋良平『私の小説』
河出書房新社 2024年これ 本当にすごかったわ町屋良平ってまだ作家 8年目か9年目なんですよ2016年にデビューしてるから『1R1分34秒』で過去に芥川賞も取ってる作家なんだけどこの小説の中には5編の小説が入っていていわゆる私小説なんですよね町屋良平って私小説って初期の方は書かなかったんですよ青春群像劇みたいなのをよく書いてたんだけどもうなんか この小説を読むと全部わかるっていうか「書くことがなくなったんだ」
みたいなことを赤裸々に語るわけだいぶ赤裸々に書いてるんですよねというのは お母さんが毒親でそのお母さんのお母さん つまりおばあちゃんもだいぶ毒親だったみたいな話から始まったりするんですねそれで自分はそれに育てられたから自分は自分のことをあんまりケアできないセルフネグレクトじゃないけど そういう感じであるとあとところどころフィクションが入ってるんですね私小説なんだけど5編の話 全て何か引用されるんですよね明らか存在しない詩人の書いた詩とか存在しない作者の何かしらが引用されるんですけどそれともちろん関連する内容が出てくるわけねもう自分のことをずっと書いてるわけよ私の私の私みたいなことをずっと書き始めるのよだからめちゃくちゃこの小説は難しいよ最後に大江健三郎の話があって めっちゃよかったんだよね昔 大江健三郎が生きてる時に中国の作家の人たちとの交流みたいのを大江健三郎と同時代の人たちがやってたんだってそれが今でも続いてるから今の現代の作家陣も中国に行って中国の作家と交流するっていう そういうのがあるんだってそれで町屋良平が行くんですよ島田雅彦先生も一緒に行くって言って
実際に出てくるわけ島田雅彦がそれで向こうに行って色々喋ったりするんだけど自分は大江健三郎の小説をずっと読んでるとそれで「大江先生
なんで亡くなったんですか」
みたいなことを言うわけ自分が作家としての立ち位置を確認する際に多分 大江健三郎をある種 目標にしてる
というか 参考にしてるというかあと父性みたいな話だと思うんだよね島田雅彦を最後に「この人は私の父だ」
みたいなことを言ったりするんだけど大江健三郎にも多分言えるんだと思うんですけどつまり自分の中の父性・母性みたいなのが親との関係性であまり獲得して
こなかったんじゃないかなと思うそれで作家になってしまって青春群像劇を書いてたら書くものがなくなっちゃって自分の私小説をずっと書くようになったんだけどその時に私の私の私の私みたいなも意識し始めて変になってるんですよねそれで自分の作家性を
最後の最後に大江健三郎に
ぶつけるみたいな話ってなんか あ〜作家だなと思うわけ素晴らしいなって本当に思うわだから本当に『私の小説』よかった本当にボロ泣きさすが町屋良平今後の日本文学を絶対に背負っていきますよそんな感じで 今回は最近 読んだ本を4冊紹介しましたけど今回のは全部 今年に発売された本でしてこういうことを結構したいんだよね 僕ね昔の小説もバンバン 僕 読むんだけどやっぱり最新作っていうのをどんどん追っかけていきたいわけですねそれの方が紹介しがいがあるというかタイムリーだからねそれをいかにYouTubeとかSNSとかで面白さを表現していけたらなと思ってますね今後もこういう動画を
出していけたらいいなあ
と思っておりますねそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#986「先日行った文学フリマ大阪についてのレポートと購入本の紹介です。あの伝説的な作家先生たちとめちゃくちゃ会いました!マジで嬉しかった〜!すごく面白かったです!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日9月8日に文学フリマ大阪12
っていうのがあったんですね僕はそれにお客さんとして行きました全体的には5冊 買ったんですけれども今回は その買った5冊の本の紹介とあと文学フリマ大阪で結構色んなことがあったのでそれを色々紹介できたらなと思っておりますね早速やっていきましょうまず僕は開場の12時には
文学フリマに行ったんですそしたら人が多かった
すごい人が多くて友達1人と一緒に行く予定だったんだけどその友達がちょっと遅刻するっていうことで僕1人でバッと行ったんですよそしたら まあまあ色々見てたんですけどそこで まず買った本が
1冊あって それを紹介するとこちらになってますねこちらは①七色祐太
『とびっきり楽しい脱力ホラー映画の世界』これは映画の書評っていうのかな評論みたいな感じなんですけど僕 こういうの大好きで
いわゆる1ページに1作品
紹介されててそれが100個 並んでるんですね僕もB級ホラーは詳しくないが例えば 有名な「死霊の盆踊り」とか「夜霧のジョギジョギモンスター」とか「女切り裂き教団チェーンソー・クィーン」とか「ドラキュラ対フランケンシュタイン」とか色々あるのようちのおかんがこういう映画が好きで特にこういうB級ホラーみたいなゾンビ系とかが好きなんでこれは僕のためにというよりかはうちのおかんのために買ってあげたっていう感じかなその後に友達と合流して片っ端から全部見ました全部見るのに結局 僕文学フリマ大阪の会場にずっといたのが4時間いたんですよ12時から4時までいて会場がジャンルごとで分かれているのでここが純文学コーナーとか
ここがエンタメコーナーとか評論・エッセイ・ノンフィクションとか短歌・俳句とかいうのが
場所で決まってるんですねブース自体は800ブースぐらい
あるのかな 結構 多いんですけどその後に買った本があって買った5冊のうち2冊目なんですけどこちらになりますねこちらは②吉村萬壱『萬に壱つ』吉村萬壱っていうのは『ハリガネムシ』っていうので2000年代に芥川賞を取られた作家先生です20年ぐらい作家やってて
単行本もかなり出ています頭にバンダナを巻いてるっていうのが
トレードマークなんですけどその吉村先生がいらっしゃったんですね僕も吉村萬壱は大好きでもうなんかアウトローっていうかバイオレンスっていうかエログロ的な小説を書かれるんですそれがすごくてねめちゃくちゃ片っ端から読んでるぐらい好きなんですけどその先生がいらっしゃってうわーと思って列になってるぐらいこの本とか その他色々あってなかむらあゆみさんっていう
作家の先生もいらっしゃって 隣にいてそこで僕も列に並んでこれ 持っていったらなんと 向こうからですよ 先生が「つかっちゃんですよね」みたいな言ってくださっていわゆる認知されてたっていうか僕 ツイッターとかよくやってるんだけどそれで吉村先生がいいねとかリツイートとかしてくれる時があるんです顔を見て分かってくれてたっていう嬉しかったねなんか そういう時ってこういう活動してて
良かったなって本当に思うんですけどこれは写真集なんですけどね萬壱先生ってツイッターで写真を撮られてひと言ぐらい書いて よく投稿してるんですよねそれ 僕もいい写真だなっていつも思うわけよこれがその撮った写真の厳選したやつだと思うんですがしかもですよ これ サインいただきましたこちらでございますねこちらが萬壱先生のサインでなんとここに「つかっちゃん様」と書いていただきました嬉しかったねやったと思って 嬉しかったです ありがとうございました吉村萬壱先生
あと なかむらあゆみ先生も
ありがとうございました先生にもお会いしてテンション上がったまま
バーって色々 また歩いてたんですけど今度 凄いものを見つけてしまってそれ 買っちゃったんだけど5冊のうち3冊目を紹介するとこちらですよねこれ 装丁がここに目のマークがあって
あと もう全部真っ黒なんですねこの状態で売られてるんですけれどもこれ 何かって言うと③古橋秀之
『ブラックロッド(全)』これ おいくらするかっていうと3850円するのよここの装丁とか金ぴかで結構 お金かかってるんだろうと思うけど「ブラックロッド」って何かって言うと90年代とかなのかないわゆる電撃文庫でいわゆるライトノベルですよ 電撃文庫で全3巻 出た 伝説の本があるんですよいわゆる三部作になってて1『ブラックロッド』2『ブラックジャケット』3『ブラックライツ・ホーリーランド』いわゆる「ラノベ奇書」として知られているかなり初期のラノベで僕 これ三部作のうち
『ブラックロッド』だけ
読んだことあるんですよこれ かなり今 高くなってますアマゾンで数千円とか全然するんですよ1冊もうプレミアついてその時に これが合本されてるわけその3冊が1冊に入ってるのが
これで 3850円するんですけどこれも実はですねサインいただきましてこちらでございます古橋先生も実際にそこにいらっしゃって「つかっちゃんさまへ」と古橋秀之と日付が書いてるんですね本当に嬉しかったね古橋先生って有名だからねラノベ界ではかなりの重鎮っていうか『ある日、爆弾がおちてきて』っていうやつとか有名でしょあれとか書かれてたりとかだから良かったですよこういうのが文学フリマの醍醐味っていうか素晴らしいと思いましたねその後も友達と会場をぶらぶら歩いてたんですけどその間にですよ 声を結構かけられましたつまり「つかっちゃんさんですか」って言って僕 YouTubeで顔出しなんかさせてもらってるからあとツイッターで「僕 文学フリマ大阪行きます」って言って前日ぐらいに言ったんですけどそれを知ってか声かけていただいて結局10人ぐらいから声かけていただきましたよマジで嬉しかったなと思って縁っていうのかなご縁とか大事にしたいと本当に最近 思いまして僕なんか全然人間嫌いの気があるような人間なのにちょっと大事にしたいなっていうのがあって声かけていただいて 挨拶したり写真を撮ったりとか なんか色々したんですけれどもそういうのがありながら またバーっと行ったんですよその後に 僕 エリーツのところに行ったんですねエリーツっていうのが有名な同人サークルで言ってしまえば作家集団なんですねデビューして何十年とか
経ってる作家先生が入ってる集団でまずphaっていう人がいてこの人は作家というか なんていうの エッセイというか高学歴ニートとかで売り出していた人が入ってるんですよねあと佐藤友哉 あと滝本竜彦とかあと海猫沢めろん先生もいらっしゃるわけね海猫沢めろん先生も 実際 今回いらっしゃってお話しさせていただいたけど海猫沢めろん先生といったら『左巻キ式ラストリゾート』で驚愕のデビューされてそこから純文学の方に行って野間文芸新人賞の候補とかいくつもなってたりとかする人がいるんですけれどもエリーツで僕でミスったなと思って
後悔してることが1個あってまず友達と合流する前にブラーッとで会場を全然パッと見たんですそしたら前からほしかったエリーツの海猫沢めろん先生の書かれた
『ディスクロニアの鳩時計』
っていう本が売られてたんですねこれ 4000円するんですよ4000円だけど めっちゃいい本っぽくてしかも いわゆる奇書みたいなミステリなのかな 変な本らしいのよ知る人ぞ知るっていうか
これもアマゾンとかで売られてない
いわゆる同人誌なんですけどこれ 4000円で売られてたんですよ買おうか悩んだの僕 軍資金 ないないって
最初の方 思っていたから
そんなに買えないなと思ってブラブラって回って 友達と合流して
もう1回 そこのところに行ったんですそこに滝本先生と あと海猫沢めろん先生がいらっしゃってちょっとお話しして(僕が)「『ディスクロディアの鳩時計』
売ってないんですか」と言ったんです見たら なかったからそしたら「売り切れました」とアラーと思って やっちゃったなと思いましたしかも その後 話を聞くとですけど今度 僕12月の文学フリマ東京の方に
出店するんですけれどもその時に「『ディスクロニア〜』
は出るんですか」って聞いたんですそしたら「いや分からない」みたいなことを言っててしかも今回のやつって
「特装版」って言って
豪華仕様らしいんですねでも豪華仕様なやつって ほぼほぼ在庫がなくて売れないらしいの 向こうも(物理的に)次に「一般版」っていうのが今度出るらしい「それは来年とかになるだろう」みたいに言ってたんだけどそうすると通販とかで買えるようになるらしいから「それまでちょっと待つしかないかもね」
みたいなことをおっしゃってたんであーと思って 買っときゃよかったと思ったわけ来年 ちょっと待たせていただこうと思ったんだけどそこで喋ってた時に 隣に隣も もちろんブースがあって
他の人がブースしてるんだけどその近くで先生と喋ってる時に横の人が
「つかっちゃんさんですか」
って声かけてくださったのそのところに行ったんですねそこで この本が売られててこちらは④灰野葉『火』この人は 言うとアレだけど 素人さんっていうかプロの作家さんではなくて っていうかもちろん文学フリマってほとんどが素人さんっていうか作家デビューされてない人なんだけど声かけてくださったの この灰野葉さんが聞いてみると 僕のファンっていうか動画とかめちゃくちゃ見てくれてて僕の よくある この本棚の動画「めっちゃすごいですよ」とこれ 見るともう驚愕します みたいなおっしゃっててっていうか その人もこういう小説も書いてるわけだから作家志望の人らしいんですね しかも純文学のそれで この本が10年かけて書いた本らしいのね その人がじゃあ僕もさすがにケチな人間なんだけど声かけてくださってファンの人が色々お話し
してくれたんだったら
僕も買おうと思ってこれ 買わせていただきましたなんと この灰野さんも実はサインしていただきましてこちらですねここに灰野葉ってあって
「つかっちゃんさまへ」と
書かれていますね 嬉しい文学フリマの日付とかも絶対 僕
入れてもらうようにしてるんだけどそうすると やっぱり自分の思い入れっていうか特別なものになる可能性があるからこういうのはやってもらうように最近はしてるそんなことがあってこの時点も3時間ぐらい過ぎてるんですけどそこからまたパーッと見ると最後の方になんとね 最後の本を紹介しますけれども僕 ツイッターやってるんでそれで文学フリマの情報とか見たりしててこの人たちが出品してるっていうのを知ってたんですよそこに最後に行って これ買って帰るかっていうことにして最後にそこに行ったんだけど
それは何かって言うとこちらになりますねこちらは⑤市街地ギャオ・衿さやか
『毎日は書けない Vol.1』市街地ギャオさんっていうのは実は作家さんなんですね太宰治賞ですよね去年の太宰治賞っていう筑摩書房がやっている純文学の新人賞があって それね 「メメントラブドール」っていう
作品で受賞して作家デビューした言ってしまえば新人作家さんなんですけど僕は太宰治賞は毎年チェックして微妙に虫食いあるんですけど
まあまあ読んでるのよ「メメントラブドール」
も単行本化されたら読む
って絶対に決めてたんだけどそれで僕も このお二方が並んでて衿さやかさんというのはまだプロ作家デビューはされてないみたいなんだけど結構 SNSとかでは有名な名前は僕 めっちゃ知ってたから全然 次とか来るような作家な
ような気がするんですけどそこで僕は行くかどうか悩んだのよ(ブースに)何でかっていうと 僕 正直このお二方の作品を読めてないのよ何でかっていうと 僕はこういう時に悪い癖で単行本派なので僕 単行本だったら読もうと思うような人間で雑誌掲載時には なかなか読めてないのでこういう時に行くの アレかなと思ったんだけど全然 行こうと思ってそこも列になってたから 列に並んでこの本を買おうと思ったんですその時に 僕が並んでた時にこの市街地ギャオさんが
「つかっちゃんさんですか」
って声かけてくださったんですね嬉しかったですよこういう時に顔出ししててよかったなって本当に思う一応 市街地ギャオさんと衿さやかさんの
ツイッターの方をフォローをさせてもらってるからその関係で知っていただいたのかなと思ったんだけどそれで お二方と色々 雑談させていただいて僕 これも僕 まだまだ調べたらんかったなと思ったんだけど今度 市街地ギャオさんの
『メメントラブドール』が10月28日に単行本化されて売られるらしいのよそれ 知らなかって マジか!と思ってそしたら単行本化されるから 絶対に
読むぞって思ったわけなんだけどその時に僕からっていうよりかは話の流れですけど僕 今度 これ宣伝もあるかもしれないが12月1日に文学フリマ東京で
僕は同人誌を出品するんですよそれが『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
っていう そういう話に自然となったわけよそうすると「俺の本も入れてほしいな〜」
みたいな市街地先生が言ってたからアッと思って 僕も入れるのギリギリなのよ12月1日に発売でしょ11月には絶対に原稿を完成させないといけないから僕 9月末に原稿を一応完成させると思ったんだけど一応 この空白の10月っていうのがあって10月には 結構色々 整理整頓したりとか推敲したりとか内容をチョコっと変える まだ猶予時間があるわけねだから そうかと思って10月28日だから ギリ行けるかな みたいな僕も「入れます!」と市街地先生
僕も読みたかったから『メメントラブドール』
が気になってたので絶対に
読もうと思ってたからせっかく こう ご縁があって僕なんか全然素人ですよ読者でしかないわけね 別になんか色々文壇で影響力がある なんか全然思わないしもっともっと地道な下積み修業時代と僕は思ってますけど10月28日だし 絶対に読んで
絶対入れますって僕も言ったので市街地ギャオ先生
『メメントラブドール』
はたぶん僕の1000冊に入っていると ここで宣言しておくと入れなきゃいけないから
絶対に入れると思いますけれど
(忘れないように!)これ 最後に見せると 実はこの本にも
サインを入れていただきましたよこちらに「つかっちゃんさまへ」と衿さやか先生と市街地ギャオ先生のお二方のサインをいただきまして嬉しかったねここに 市街地先生って ヘビみたいなイラストみたいに入ってていいなと思いました嬉しいと思った 超嬉しいと思いました 素晴らしいそんな感じで文学フリマの会場に4時間ぐらいいて買ったのは5冊ですけどかなり濃い5冊だったと思うから個人的に良かった文学フリマ
だったんじゃないかと思いましたその後に 友達と「しゃぶ葉」に行きましたしゃぶしゃぶのチェーン店ですけどね食べ放題の 全然安いところですよねそれで家に帰ったっていう次第でございますやっぱり文学フリマ楽しい 良かったね色んな人にも色んな本にも出会ったりして良かったですよ 素晴らしいと思ったまた大阪は毎年9月にあるんで来年の9月もまた行こうと思うし東京12月にも もちろん出店するしっていう感じでこれからもずっとフリマで僕も本 多分 同人誌 まだ1冊も作ってないけど作り続けていっぱいいっぱい商品を作ろうと思ってますのでそんな感じでございますお会いした皆さん 声かけてくださった皆さん作家の皆さん 本当にありがとうございましたまた機会がありましたら ぜひ何かお話させていただけたらと思いますそんな感じで 今回
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#984「僕つかつが芥川賞・直木賞の贈呈式に招待されたので、その行ってきましたレポートです!なんと二次会にも行きました。まさかの、あの作家先生が…(半年ぶり2回目の参加です!)」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというとなんとですね 先日 私 2024年8月23日に
第171回 芥川賞・直木賞の贈呈式に
招かれまして 行かせていただきましたそこでお会いした皆様がた
ありがとうございました僕もめっちゃ嬉しかったし
とても良い経験させていただきました実はですね 半年前の2月の方にも
芥川賞の贈呈式に行かせていただいたんですねその時は前回『東京都同情塔』で芥川賞を取った
九段理江先生にお招きされたんですけれども今回は実は『サンショウウオの四十九日』を書かれ芥川賞を
取られた朝比奈秋先生になんとお招きして頂きました結構 背の高い方で スラッとしててちょこっとお話しさせていただきましたけどとても良い人でしたよトントンって(僕の)肩を叩かれて
頑張ってください(って言ってくれました)
みたいな そういう感じだったとても良かったねこれは もう終わったから
言っていいと思うんですけれども(贈呈式の)そのために
僕は3泊4日で8月23日前後に東京に行かせていただいたんです贈呈式以外にもいろんな人と
会わせていただいたりとか結構 6〜7人ぐらいの 東京に住んでる昔からの知り合いとか Twitterで
知ってたんだけど初めて会う人とかあと急に連絡してくれて
お会いできませんかみたいなで
それで会った人とかもいてみんな 小説が好きな人っていうので別に東京観光をするわけじゃなくてずっと小説とか文学の話をしてたんですけど1番最初 夜行バスで大阪から東京に行って友達の家に泊めてもらったんですけどそれで なんやかんや過ごして8月23日まあ これ言っていいと思うけど
夕方から贈呈式が始まるんですよもちろん僕もスーツで上のジャケットもネクタイ着用で行くから
暑いわけですよ こんなん言ったらアレですけどそれで行ったら そこが帝国ホテルなんですね 会場がこれね 前回の『東京都同情塔』の時は
前は東京會舘っていう違う場所やったんですよねだから僕はどっちも楽しんだっていう今回 帝国ホテルに行ったら
ウェルカムドリンクとかあって
それを飲みながら周りをこうキョロキョロしてもうちょっとで始まるけど別に知り合いもいるわけじゃないから1人でぼーっとしてたんですけどそうすると ここはちょっと言わないけど前回にお話しさせていただいた人がいて声をかけてくださって その人と
ちょこっと喋ってたりしたんですけどその後に時間が来ると始まるわけですよ司会の方がいて マイクであって 壇上があって選考委員の先生とかの挨拶ぐらいから始まるわけですよ芥川賞だったら今回 奥泉光先生だったかな直木賞だったら宮部みゆき先生のコメントがあって
おめでとうございます みたいなのがあるわけねその後に受賞された3人いらっしゃいますからね朝比奈秋さん 松永K三蔵さんそして直木賞で一穂ミチさんがおられて1人ずつ「ありがとうございます」「私はこうでこうで」っていうのがあるんだけどみんな 素晴らしいことをおっしゃってたとても良かったけど 僕ねこう言ってはアレですけど1番 直木賞の一穂ミチさんの言葉が
めちゃくちゃ刺さっちゃって一穂ミチさん どんな話されてたかっていうとゾーマの話 してたんですよねゾーマっていうのはドラクエ3のボスのことなんですけどドラクエ3にゾーマっていうラスボスがいてこいつを倒せば 世界は救われる
みたいなゾーマがいるんだけれどドラクエ3って
ファミコンとかの世界で
めっちゃ古いゲームなわけよRPGとか そういうゲーム自体がそんなに最初から成熟しているというか
パターンがないのに 1から作ってるみたいな世界のドラクエ3のラスボスが
めっちゃかっこいいんですね悪役なんだけど めっちゃいいこと言うのよそのことを一穂ミチさんが引用されてたんだけどその時に引用した言葉が勇者がいて 勇者に向かってゾーマが 1番最後のこれ言ったら最後の戦いが始まる
って言う直前に言うセリフで「勇者よ なにゆえ もがき 生きるのか」
って言うんですねそれも存在理由っていうか
レゾンデートルのような哲学めいたことを1番最後の
最後に言ってくるわけね僕 ちょうどですよたまたま ここ1年ぐらい僕の中でゾーマブームが来てたのよ「ゾーマってかっこいいな」って
ここ1年くらいハマってたんですねそれで一穂ミチさんが
ゾーマの話をされてたからうわーって来たんですこれ ちょっと
言ってることが違うかもしれない
僕の解釈かもしれないけど一穂ミチさんがおっしゃってたのは「なにゆえ もがき 生きるのか」を
常に自分に問いかけてきたと小説を書く時に
「なんで自分はもがき生きるのか」
「書くのか」と一穂ミチさんもスピーチの中で
多分そうだよなと思うのはやっぱりずっともがいてきたと
人生を つらかったと直木賞を取れて嬉しかったとは
もちろんおっしゃってたんだけどやっぱり その1つの報いっていうのかなご褒美みたいのが直木賞だった
みたいなことには繋がっていくんだけどそこで僕 それを聞いて めっちゃ
ドアーって涙が出てきて僕も思ったわけ
「つかつよ なにゆえ
もがき 生きるのか」「なにゆえ本をたくさん読んで生きているのか」と僕は常にゾーマに問われていると
「何のためにやってんのか?」と僕は何のためとかもないっていうか死なないためぐらいの感じなんですけど僕もこんなん自分で言うとアレですけどつらかったんですよ 人生が父親が結構ひどい男で典型的なDV男というか俺が世界の中心だ みたいな悪く言うと自己中みたいな そういう男なんで何回も殴られて生きてきたし今 考えると
全然 僕が悪くないのに
僕のせいにされたりとかうわーって向こうが言ってくるわけよ子供の時からされてるからある種の虐待だと 最近 僕は気づいたんだけどそれされると 僕 今でもそうだけどね「自分ってダメ人間なんだな」
っていう気持ちがずっとあるの心の中で自分の人間の基盤がないんですね
もうグラグラしてるのよだから僕 本当に今でもそうだけど自分で
自ら死にたいみたいなこと
なんかいっぱいあったし死にたいと思うし そういうこと
実行したこともあるんだけどでも僕はそこは文学しかなかったの だから自分の基盤がグラグラグラって
なっていたら生きていけないから自分の軸を後から人工的に
作らないといけないわけそれが多分 僕にとって文学だったんですね文学で 例えば
1000冊 読みましたとか動画900本 作りました
みたいなのは これ事実だから数字は裏切らないから
僕 それを軸にしてるそうしないと僕はバーンって倒れてしまうんですねそのために僕は文学をずーっとやってきたしこれは楽しいからとかじゃないからね自分の軸を定めるために文学を読むわけだから僕 よく言ってるでしょ やっぱり
小説っていうのは修行なんだと修行が楽しいことは全然ありますよもちろん僕だって本を読んで楽しいと思うんだけどでも それは 特に僕は純文学っていうジャンルを幅広く全部 読みたいと思ってるわけねだから全然知らない作家とかにも
チャレンジしたりするんだけどそうしないと僕の純文学軸が
弱く弱くなってしまう知らない作家とかが出てくると「いや お前 文学 全然 知らねえじゃねえかよ」みたいな僕が言うから 僕が自分に言うからそうすると僕はもっと修行しなきゃ
もっと勉強しなきゃと思って
ずーっとやってきたそうしたら 前回もそうだけど 今回も芥川賞・直木賞の贈呈式に呼ばれたと嬉しかったですよ もちろんあ〜 報われることがあるんだと こんな僕でもこんな見てくれの 全然 トークも下手だし動画編集もしょぼいよこんな人間でも朝比奈秋さんとか九段さんが
見てくださってたらしい動画をそれでこいつを呼ぼうと思ったらしいのそれは嬉しいですよねだから 僕は なんて言うのかなよく「熱意がある」みたいな言われるんだけど熱意っていうか
自分が死なないために文学をやってるだけなんでだから ちょっと邪悪な邪道な
文学の読み方なんじゃないかな文学の付き合い方なんじゃないかって思うのよ 最近はだけど まあ そういうこともあるのかなと文学ってそういうことだってできるどんな付き合い方でも許してくれる
度量の広さみたいなが文学にはあるからそれで文学が好きになったんだなと思うけどそれで 今回 行かせてもらってそのゾーマの話を聞いた時に僕に置き換えたらなにゆえ文学をこれまでやってきたのかとなにゆえもがいてきたのかと
あ〜と思ったわけそれで 僕 泣いちゃったしあと一穂ミチさんももがいてきたんだなって思ったっていうか みんなもがいてきたんだなと思ったっていうか朝比奈秋さんは結構
そういうことをおっしゃっていた直接「もがいてきた」とかじゃなかったけど小説にかける思いみたいな
めちゃくちゃおっしゃってたしなんか そういう文学のパーティーに呼ばれた時に色んな作家先生とか編集者とか色んな先生がいるのよその人たちも文学やってきたわけじゃないですか ずっとそういう人たちこそ僕よりもっと
もっと文学をやってきたわけだからだから そのパーティーの末席に
僕は立たせていただいたっていうのがなんか それで 感極まっちゃってそう気づいて 泣いちゃってた僕 会場でっていうのは あったんだけどめっちゃ話が長くなったけど その後に日本文学振興会の偉いさんみたいな人が最後に「御三方 受賞おめでとうございます」最後の締めの言葉みたいな言ってたんだけどその時にも ちょこっとだけ触れると人間存在とか実存みたいな言葉が結構出てきたのよつまり例えば 今回だったら
『サンショウウオの四十九日』で結合双生児の2人とかの話になってきてそのお偉いさんが「この作品には人間存在が描かれてます」みたいな「実存が描かれています」とか言うわけよその言葉って今あんまり使わないっていうか近代文学とかの ちょっと古い
言葉な気がしたの 僕 一見聞いて人間存在って結構わざわざ今言うかな?でも やっぱり文学って 人間存在
なんだなって思ったの それ聞いてはーっと思ったの人間存在とか実存とかを
書くのが文学なんだって思ったら結局 僕の話になっちゃうんだけど僕の実存とか僕の人間存在とかを
こう反射されてね っていうか自分で考えて はあ〜と思ったわけ文学をやっててよかった
って本当に思ったわ 今回行ってやっぱり文学っていいもんですねびっくりした僕 こんなに贈呈式で色んなことを思うなんか思わなかったパーティって美味しいご飯もあるわけよ いっぱいねバイキングみたいな感じで置いてるから
食って これも食って これも食ってとかドリンクもお酒からジュースとかまであるからそれもたくさん飲んで周りに人いるんだなーとか言って今回 斉藤紳士さんがおられて僕からちょっと声かけさせていただいて斉藤紳士さんですか って初めて会いましたもちろんTwitterとかSNSではちょこっとととか僕だって斉藤紳士さんにコメントしたりとかしてたんだけど初めて会って結構1時間ぐらいかな 喋らせていただいて色んな裏話とか色々聞かせていただいて
僕もちょっとしゃべったりして
っていうのがありましたけれどもそれが終わって
僕 2次会の方にも行かせて
もらったんだよね2次会はダイニングバー
みたいなところで
少人数でやるんだけど今回 ちょっと前回より…言えないこともあるだろうから
色々ごまかして言いますけど前よりちょっと人数が多かったんですね人が多かったんですよ50人ぐらいかな僕もお店に入るタイミングとか順番とか
順番は別に たまたまだけど あって奥の方の席に座らせてもらってねそこで周りの方々と喋りました名刺交換もさせていただいたりとかしたんだけどある出版社の編集者の方とか文芸評論されてる方とか作家先生もいらっしゃったんだけど色んな人と話させていただきましたねここで1つ 猛反省というか あるんだけど1次会の 贈呈式の時に朝比奈秋さんと5分ぐらい
おしゃべりできる時間が
あったんですけど僕も2次会に行くって言ってたんで2次会でお話しましょう って僕 言ったんですねだけど2次会が ちょっと結構 人が多かったしもう すごい偉い先生も
来られたの 作家の先生でこの動画を見てる誰でも知ってるような超偉い先生とかが何人も来ててその人が朝比奈秋さんのお隣とか周りにいらっしゃった というかその受賞者がメインだから いらっしゃったんでなかなか こう入りにくかった
というか 言い訳なんだけど僕なんか全然 無名の人間が 無名の素人がすいません とか言って行きにくいっていうのがあったんで僕が悪いですよ ひと言 5分とかでも ちょっとお声かければよかったなと
今本当に猛反省しておりますけれども
(朝比奈先生 すみませんでした!)それで2次会もだいたい2時間ぐらい
喋ったりして終わって そのまま
帰ったっていう感じですねあと東京の他の話
ちょこっとだけして
終わろうかと思いますが6〜7人ぐらい色んな人と会ったのよそこで なんて言うのかな
作家志望の方にもお会いして「俺はもう本気で作家になるんだ」
みたいな人いるわけですよ僕も文学談義に花を咲かせてっていうか その3泊4日 ずっと文学の話してた贈呈式だけじゃなくて会う人会う人が小説に関する何かをされてる方とか普通に小説が大好きな方とか
いう人たちと もう3泊4日で1日2人ぐらいお昼に会って 違う人と夜に会って
みたいのを3泊4日ずっとやってたわけよそしたら僕 ほんと
この東京の文学旅行みたいな「つかつ東京文学旅行2024夏」
みたいな感じでなったわけ
結局 そんな感じなのよだから僕自身も
めちゃくちゃ
なんていうのかな文学熱みたいのが入ったっていうか向こうもやる気めっちゃあるわけね「私この作家好きなんです」みたいなっていう人がいたらやっぱり その熱みたいな 来るわけです頑張らなきゃと僕も文学 これから頑張っていかなきゃと本当に思ったこれだけ 例えば純文学にしかり 何だってそうだけど活字離れだとか他の娯楽があるんだから読書なんか廃れてるみたいなことを言う人いると思うんですけど本屋さんとかも潰れていってると思いますけれどもでも やっぱり文学好きな人 いますよまだまだいますよ いっぱいいると思うだから僕はYouTubeとか自分の同人誌を作ったりとかに今 注力してるんで書いてはないんだけどね 小説を
書いてるわけじゃないんだけれどやっぱり書いてる人とかその人も何年後かに俺は作家になるんだって言って見せてもらったりもしてる人もいるのよつかつさん
これ読んでくださいと
俺 本気で書いてますから厳しく何でも
いいんで言ってください
みたいな人もいるわけ僕もそう言われたら ほんまに真剣にその人の小説を受け取ってwordで送られてきて僕もそれを印刷して 赤ペンを持って僕なりに素人なりに ここはめっちゃいいとかここはちょっと
いらないんじゃないとか
言って めっちゃ赤でバーって消したりとか編集者かみたいな 校正かみたいなそういうことを
何回かさせてもらったり
とかもしているのよ 今 実はそういう人と実際に会って さらに
文学の話を深められたと僕は思ったの色んなことをしゃべった
ホントに文学の この小説の話小説の作法というか 創作の話とかそれにまつわる周りの音楽とか演劇とか映画とか そういう隣接領域っていうのかな芸術の話とかもしたりとかして
なんかめっちゃ良かった今回の東京旅びっくりするほど良かった僕も異常でしょうこんなに なんで文学しなきゃ
いけないんだと思うわけよ 僕も別にしなくたって いいじゃない
文学なんか 小説なんかこんなん言うと 小説・文学の
否定だろうけどでも しないといけないわけね
さっき言った通りねそういう人たちがやっぱり多いよ小説好きな人・文学好きな人
僕の直感ですけどねあるんじゃないのかな
心の欠損・魂の欠損
みたいのがあって僕は特にだけど そういう欠損を埋めるために文学をどんどん詰め込んでるわけねそれがYouTubeとか同人誌とかに僕は繋がってるし書いてる人は創作に繋がってるわけよだから もがないと いけないねなにゆえ もがき 生きるのか
だから 本当に もがいて もがいて
もがいての世界が文学な気がしたのっていうことに僕は 今回の
3泊4日文学旅東京2024で
気づきましたこんなん気づくようなこと
でも何でもないというかなんで僕 東京に行ったんだろうね ほんまにいやでも 良かったですよ 贈呈式ありがとうございました 朝比奈秋先生また機会がありましたら 松永先生もいつかどこかで もしよければ
よろしくお願いいたしますお二方 もしくは
一穂ミチ先生も素晴らしいスピーチ
ホントおめでとうございました素晴らしかったです
ありがとうございましただから みんなもそれこそ 小説を書いてる人は
めちゃくちゃ頑張って書いていったらいつか新人賞を取ったりとかもしかして芥川賞を取って
パーティーのメインになること
だってありうるわけだから僕なんか書いてないけどこういう こういうことになったわけだからもっとみんなで文学を盛り上げていこうって本当に思うこういう良いことあるから本を読んでて 何のために本を
読んでるねん みたいな言われた時に俺は受賞パーティーに行くんだみたいな贈呈式に行くんだ みたいな言えたらいいね皆さんも文学系のYouTuberになりましょう盛り上げていこう みんなでこの素晴らしき文学を
盛り上げていけたらなと思います僕自身も まだまだ もちろんこれから僕は死ぬまで 一生 文学
YouTubeもしくは同人誌とか
そういう活動しますので皆さん 末永く どうぞ
よろしくお願いいたします僕も皆さんにほんと
感謝しております
ありがとうございます東京で本を僕は
30冊ぐらい買ったのよそれ また動画で
紹介できればと
思っていますので皆さん どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#982「現代文学地図2000→2020を見ていこう!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと現代文学地図 2000年→2020年現代文学地図とは何かと言いますと先日 この本を買ったんですよこれは河出書房新社が出してる雑誌『文藝』それの2017年の秋号なんですねこれの特集に「現代文学地図」って書いてるでしょ地図と書いてシーンと読むらしいんだけど2000年→2020年ってあるわけですよこれ 興味があって この本を買ってみました今 これ アマゾンで入手できないんじゃないかな僕 これ 2500円で買ったんですよ アマゾンで 中古でそこから もう出品されてない
んじゃないかなと思うんですけど読みたい人は 図書館に
行くしかないんですけどこの雑誌の大きな目玉はこういう表が2つ入っていてこっちのピンク色の方は「現代文学地図 2020」なんですねこれの裏側があってこっちは黄色で
「現代文学地図 2017」
って書いてるんですよ2017と2020って何が違うかっていうと多分だけど こっちの黄色い方は
結構 プロ作家が多いんですねデビューして
10年とか20年とか
中堅以降ぐらいの作家ピンクの方は ここ10年以内ぐらいなのかな新人が書かれてる感じはするこれ 作家陣を 全員は言えないけど 言うと村上春樹が中心にあるんですね2つの軸でマトリックスになってて「社会-個人」っていうのが縦の軸であるのよ横の軸で「言語-物語」っていうのがあってそのど真ん中に村上春樹が入ってるんですよ社会軸に つまり上の方に行くと川上未映子 古川日出男 阿部和重 とかがいるわけ下の方に行くと つまり個人の軸に堀江敏幸 絲山秋子 町田康 がいるのよね言語軸 右の方に行くと大江健三郎 佐伯一麦 蓮實重彦左の物語軸に行くと石原慎太郎 松浦寿輝 吉田修一 とかがいるわけですよ文学って よく人の心を描いてるとか言うじゃないですかだけど ホントは言語実験の面もあるわけね言語で描かれるんで 言葉をいかに使って表現するかとか「言葉そのものとは何なのか」
みたいなことも文学の領域なので人の心を別に描かなくても
言語的に突き詰めていってる文学
だって評価されるわけですよ例えば 言語軸の 右の方にいる作家で言うと円城塔 福永信 黒田夏子朝吹真理子 山下澄人 鹿島田真希高橋源一郎 とかがいるわけね物語軸に行くと中村文則 島田雅彦 佐藤亜紀
西村賢太 とかがいるわけね社会と言語の真ん中ぐらい
って説明が難しいけど そこに
「他言語」っていうのがあってリービ英雄 多和田葉子 楊逸
小野正嗣 とか入ってるわけですね「私小説の更新」みたいな
ちょっとしたコーナーがあって笙野頼子 古井由吉保坂和志 柴崎友香 とかがあったりとかあと「横断」っていうのがあって片岡義男 舞城王太郎 とかがいたりするのよねっていうか「横断」結構 あるな吉田修一 角田光代 江國香織桐野夏生 高村薫 筒井康隆 も横断って書いてるんだけどもちろん もっと いるんですけど
これが「2017」の方なんだよねあと ピンクの「2020」の方に行くとこれも さっきと同じく
社会-個人軸があり
物語-言語軸があるわけねその中心にいるのは
さっきは村上春樹だったけどこっちは村田沙耶香がいるんですよこれからは「村田沙耶香の時代」だと
いう感じなのかもしれないんだけどそこから社会軸に行くと上田岳弘 加藤秀行 崔実 とかがいるんだよね個人軸に行くと滝口悠生 小山田浩子 高橋弘希
川崎徹 とかがいるんですよあと物語軸に行くと宮内悠介 島本理生 とかがいるわけね例えば これ ちっちゃなコーナーっていうか
グループもちょっと書かれている場合があって「女性性の更新」っていうところがあるのよ
これは物語と個人軸の間ぐらいなんだけど谷川直子 谷崎由依 栗田有起 今村夏子がいてプラス 牧田真有子 がいるんだよね牧田真有子 っていう作家がいるんですけどこの人は(2007年に)
文學界新人賞を受賞して
作家デビューしたんだけど結構 作品も色々出てるしこの文藝にも牧田真有子の作品が出てるんですけど1回 センター試験かな今「大学入学共通テスト」に
名前が変わったと思いますけどそのセンター試験にも
牧田真有子の小説は
出たことあるんだけど単行本が1個もないわけよだから 僕 牧田真有子 さっさと
短編を集めて 1冊 本を出してほしい僕 よく言ってるけど 単行本 1冊もないと
なかなかアプローチしにくいもんで0冊と1冊では
もう全然 違うので
こういう純文学の世界1冊 とにかく どっかの出版社
牧田真有子を出してくださいと
僕は思うんだけどこの牧田真有子が
「女性性の更新」の
コーナーにいるんですねあと「政治・文学の更新」っていうのが
あって 物語と社会軸の方にあるコーナーが木村友祐 岸川真 っていう人と
あと本坊元児っていう人いるのよね
(ほんぼう・がんじ)「この人 誰かな 知らないな」と思ったら
下の方に「芸人」って書いてるのよ僕も調べたら 芸人さんって
自叙伝っていうか 自伝エッセイとかもしくは 私小説的な そういうのを書いたり
するでしょ そういう本があるらしいの この人そういう人が こういう
ザ・文学みたいなところに
載ってるの珍しいと思ってさあんまりないでしょあと「ストリート系」っていうのがあってこれ 言語と社会の間ぐらいにあるんですけど植本一子 宮崎誉子 金原ひとみ が入ってるんだけど金原ひとみ ってストリートって言うのかなあと「言語的前衛」っていうコーナーがあるのよ ここに乗代雄介 青木淳悟 木下古栗 がいるんですよこの3人がまとまるかって思うけど
結構 前衛だからね マジであと 色んな作家陣がいますよ水原涼 山下紘加海猫沢めろん古谷田奈月松田青子鴻池留衣 町屋良平あと言語軸にめっちゃ寄ってる
「肉体言語系」っていう
謎のグループがいるんですよ坂口恭平 荻世いをら高尾長良 松波太郎
この4人が入ってるらしいこれ 誰が決めてるんだろうね 肉体言語系とかこのグラフを持ってるだけでも
「文学偏差値 爆上がり」みたいな本
だと思うのよ僕も買ってよかった これそれこそ
この前 購入本紹介で
ちょっと紹介したけど長谷川町蔵 っていう人がいて
この人 映画関係の人らしいんだけど小説をいくつか書いてるらしくて
その人の本を この前 買ったんですよそれは この本 この文藝を このグラフを見て「こんな人いるんだ」と思って買ったっていう とかこの特集 かなりのページ数が割かれていて佐々木敦 栗原裕一郎 小澤英実 の3人の鼎談があって「2000年〜2017年の文学を振り返りました」
っていう鼎談があるんですよねプラス もう1個 鼎談があって江南亜美子 倉本さおり 矢野利裕 の3人の
「来たるべき作家たち 現代文学地図 2020」
っていう鼎談もあったこの2つの鼎談もかなり良いもう1個 これだけ言って終わりますけど「38人による来たるべき作家たち2020」
っていう そういうコーナーもあるのよそれは38人の文学系の 編集者だったり
作家だったり 書店の店主だったりとかそういう人たちに「これから どういう
作家陣が来ると思いますか」って言って1人1ページぐらい 結構な量で「私はこの作家を推しております」みたいなのが
バーってあって それ 38人分あるっていうのとあと もう1個 アンケート
っていうのがあって
これも似てるんだけど「131人による来たるべき作家たち2020」ってあってこれは131人いるんで
1人1人のスペースが
めっちゃ小さいんですよ数行とかで終わって「私はこの作家を推す」
って書かれてるだけみたいなとかが
それが131人いるっていうだから これもかなりいいさっきの黄色とピンクのグラフに
書かれてない作家陣も紹介されてるんですよねだから かなりこの本 いいですよっていうか こういう特集
たくさん作ってほしい
色んな文芸誌「今この作家が来てますよ」みたいな
そういう特集 これは文藝だけどね別に 新潮 群像 文學界 すばる
でもやってほしいですよあったら教えてください僕も文芸誌が めっちゃ詳しいか
って言ったら詳しくないので「そういうの 過去に この文芸誌 やってますよ」
っていうのがあったらコメントで教えてくださいそんな感じで 今回
文藝 2017年 秋号を
見ていきましたけど皆さんも 今 この作家が
来てるんじゃないかと「現代文学地図2024」がありましたら
ぜひコメントで何でも書いてください僕も全然 知らないこと あるので
結構 皆様から教えていただくことも
多いので そんな感じでございますまた こういう本を見つけたら
紹介の動画を出そうと思いますので
どうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#981「僕の2024年上半期の読了本ランキング ベスト5を発表します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと2024年上半期ベスト5僕が今年の2024年の上半期
(1月から6月)までに読んだ本僕は180冊ありますけれどもその中からベスト5を決めて
発表するという動画でございます早速やっていきましょう第5位第5位はこちらでございます⑤大藪春彦
『餓狼の弾痕』
角川書店 1994年この本 知る人ぞ知る
大大大大大問題作
なんですよね大藪春彦先生自体は日本のハードボイルド小説の
先駆者の1人なんですけどこの『餓狼の弾痕』は
大藪春彦先生の
後期の作品というか亡くなる前ぐらいに
発表されてるんですねあらすじ主人公が 裏の組織に所属してるんですねいわゆる義賊的なことだと思うけど悪い権力者がいたら
その悪い権力者のところに行って
悪いことを脅してもう めちゃくちゃ金を奪うと
それを繰り返していくっていうノワールって言ったら
ノワールかもしれないんだけどこの小説の何が大問題作かというと
同じ描写が50回ぐらい続くんですね最初は 政治家絡みのゴルフ会員権というのが
この当時 バブルの時だろうけどそれをめちゃくちゃ出すと 乱発すると乱発してゴルフ会員権を受け取った
政治家が30人ぐらいいると主人公は その30人のところに行ってそこにいる
お手伝いさんとかも
平気で殺したりするし政治家を脅し取って
政治家の金庫から金を奪って政治家にそれ 言わせないように金を奪われたと 警察沙汰にさせないように政治家のお腹を切って中に爆弾を仕込んでお腹を閉じて「俺はこの爆弾のスイッチを持ってるぞ」と「お前が怪しい動きしたら爆破させるからな」
って言って 政治家を黙らせるんですそれを50回ぐらいするの 本当に土地の名前と政治家の名前だけをちょろっと変えてやってることは全く同じそれで主人公は30人以上の政治家から
1900億円を奪うっていう話なんですこれ 1回 読んでほしい知る人ぞ知る 大大大奇書
と言われてはいますよね第4位第4位はこちら④伊良刹那『海を覗く』
新潮社 2024年これは今年の新潮新人賞の
受賞作になっておりますしかも これ 書いてる伊良刹那さんは
なんと現役高校生だったということですねあらすじ主人公が 高校2年生の
速水くんっていう男の子が
いるんですよこの子は絵を描いていると美術部に所属しててたまたま同級生の
北条司くんっていう
男の子がいたとこの子を見た時に
「美しい」
って思ったんですねこの子を絵に描きたいと思って
美術室に呼んで絵を描く
っていう話になってくるのだから男と男の
恋愛までは行くか行かないか
微妙なところだけど「美しさ」っていうのが
1つのテーマになってくるともう1個 実は その美術部の
部長っていう人がいてそっちも主人公パートがあってその部長は
彼女がいるんですね
彼女がいるんだけれどその部長を好きな ちょっと
ブサイクな女の子がいてその子が部長に告白すると部長は それを断らなくて
ゲームのように楽しんでいたとそしたら彼女からしたら「ちょっと私がいるのに
なんでこんなブサイクと付き合ってんのよ」とか言って喧嘩するっていうか
そこの三角関係を描く
パートもあるわけ特徴としては
漢字とかが難しい日本語自体が
難しく書かれているちょっと難解ではある
だけど かなりいいね最近 こういう小説
あんまりないかもしれないねそういうのをやってるところが
評価されたのかなと思います第3位第3位はこちらでございます③藤枝静男
『田紳有楽』
講談社 1976年今 講談社文芸文庫に「空気頭」
と一緒に入ってますけど藤枝静男も前から
読みたい読みたいと
思ってた作家で結構 奇想系の ちょっと
シュールレアリズム的なそういう作風を書くという噂は
聞いておりましたから
今回『田紳有楽』を読みましたあらすじお茶碗が主人公なんですよねある骨董屋さんがあるわけですよ
その骨董屋さんの横には池があるとその池に3つのお茶碗が沈んでいるとこのお茶碗がそれぞれ意思を持ってるんですねこのお茶碗たちが主人公になっていると1人はその池に金魚が泳いでるんですねその金魚と恋愛関係になって 金魚と交接をして赤ちゃんが生まれるとお茶碗と金魚の
赤ちゃんが大量に生まれる
っていう話が1つあるのよあと2つ目が そのお茶碗は
変身する能力あるんですねなので そのお茶碗が人間に変身して普通に その骨董品屋さんに主人がいるんだけどその主人のところに行って
処世術を教えるというか変なものを売ろうと
したりとかするっていう平成狸合戦ぽんぽこみたいな
変身譚みたいなが1つあると最後1つは そのお茶碗は
元々チベットにいたとチベットのお坊さんが
チベットの山を歩いて行く時に一緒に連れていった
お茶碗があるんですよそのチベットのお茶碗は触手を
出すことができるんですよね触手を出して あと空も
飛ぶことができるんですよそれで違う池とかに
行くこともできたりとかして結構 やりたい放題 やってるのよ この小説ある種のファンタジーかもしれないんだけどこれが純文学だと思いますよここまでむちゃくちゃやってもいい
っていうのが もう純文学だなと本当に思う第2位第2位は こちらでございます②小泉綾子『無敵の犬の夜』
河出書房新社 2023年こちらは去年の文藝賞の受賞作になってますね僕がこの本を初めて読んだ時に令和の大江健三郎っぽいと思ったわけですよあらすじ九州の片田舎が舞台でそこに界くんっていう
中学生の男の子がいるとこの子は右手の小指と あと
薬指の半分が失われてるんですね昔 小さな時にタンスに隠れようとしてたら親が気づかずにタンスをバーンってやっちゃって指が飛んだっていうエピソードがあるんですねその界くんは田舎でフラフラしてるのよ学校にも最近 あまり行ってないと
でも なんか やりたいこともなくてそこに高校生の橘っていう人が出てくるとその橘は「俺 東京に今度 行くんだ」とか「俺 ブランド物もいっぱいつけてるぜ」
とか言って ちょっと意識が高いわけよ「俺はこんな田舎のやつとはちょっと違うんだぜ」
っていう優越感みたいなのを持ってるわけ界くんは別にそこにあんまり興味ないんだろうけどでも友達みたいなのがやっぱり欲しいものでその橘さんに ちょっと毎日 家に行って
色んな話を聞いたりとかしてるわけですよそしたら橘が 東京に
しょっちゅう行ってるんだけど
東京に女がいるとその女っていうのが
東京でブイブイ言わせてる
流行りのDJみたいなのがいてそのDJの女だったと 本当は
だから そのDJから脅されてるとそれを聞いた界くんは
「俺が逆にボコボコにしてやりますよ」
みたいなことを言って 橘を助けようとして界くんは単身 東京に行く
っていう話になってくるのよいや これが本当に面白い
めっちゃ考えどころがあるまた東京の描写がいいわけよ東京で変な奴らに
絡まれたりするの 界くんが
それがかわいそうで界くんはそれに対して どう自分の力で突き進んでいくか
っていうのが試されてるところの面白さがあるのよだから この小泉綾子さん 早く 2冊目 本を
出してほしいなと本当に僕は思っておりますよ第1位第1位は こちらでございます①小島信夫『残光』
新潮社 2006年小島信夫も 僕は前から本当
読まなきゃなと思ってました小島信夫ってめっちゃ古い「アメリカン・スクール」で
芥川賞を取ってる昭和の作家と言ってもいいんですけど意外と定期的に本を出していてこの『残光』も2006年に出てるんですねこの後に亡くなってしまって 実はこの
『残光』が遺作になってるんですよあらすじ主人公が まず90歳の小島信夫なんですよだからこれ 私小説になるわけなんだけどこの90歳の小島信夫が
20世紀文学研究会っていう
研究会があるらしいそこに90歳なんだけど 参加したりとかあと保坂和志が出てきて
保坂和志と対談したりするんですねとか あと奥さんがいるんだけど
奥さんが老人ホームに入る話とかあと息子さんがいたらしいんだけど息子さんは小児麻痺で
プラスアル中だった
らしいんだよねその息子さんが先に
亡くなってしまうって
話も入ってたりとかあと 過去の小島信夫作品を
めちゃくちゃ長く引用して「ここの文章はこうでした」
みたいなを自己解説するみたいなそういう描写が多くあるんですね僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃないけど小島信夫って私小説的な小説を
大量に残しているんだけどその私小説を さらに引用して
解説するとメタ構造になるんですよね「小説の中に小説がある」
って言うことになっちゃってそれを さらに解説するんで
多重層になってくるんですよだから小島信夫ってすごいな
って言われてる点としてはぐにゃ〜ってしてるらしいあとは あっち行ったりこっち行ったりとかしてもしくは多重のメタとかに入ってきて今 過去の話をしてたり
現在の話をしてたり
もっと過去の話してたりとか時間軸とかもしょっちゅう
移動するらしいんだよね超前衛的っていうか現代文学的な手法を
当時から使ってたっていうので結構 好きな人は好き
っていう作家らしいんだよね小島信夫って神格化されてるのよ本当にちょっと読まなきゃなーって僕は思いますそんな感じで 今回
2024年上半期ベスト5を
発表しましたけど実はですね
上半期ベスト6〜10も
一応 作ってはいるんで次回以降の動画に
それを作って出そうと
思っておりますね僕も2024年上半期は 結構
良い本を読んだつもりだし現代文学から ちょっと
昭和文学に移行したというかその辺も読むようになった
っていうところが
変化だったかなと思いますねぜひ皆さんの
上半期ベスト5もありましたら
ぜひコメントで教えて下さいそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#980「僕の同人誌の表紙イラストが完成しましたので発表します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというとついに 私つかつの 今度
文学フリマで出そうと思っている
同人誌の表紙が決定いたしました!いやあ〜 素晴らしい!今回は それを発表する
ということでございます早速やっていきましょうもう いきなりなんですけど
ここに出そうと思います今回の
『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
の表紙はこうなりますこれ 表紙 本当に素晴らしいと思いますよこれは きちんとした
イラストレーターさんの方に
依頼して描いていただきました浜渡浩満(mochihama)さん
という方が描いてくださいました何回も言ってますが
同人誌の説明をすると今度
「文学フリマ東京39」
っていうのがあって2024年12月1日に
東京のビッグサイトで
開催されるんですよそこで僕は初めて
文学フリマに
出店するんですけど基本的には
この本を出店しますこの本は 僕が
この3年間に読んだ1080冊の本の
あらすじと感想が
載っているわけですね今のところ まだ原稿は
実は完成してなくてというのも あと51冊を
読んだら完成予定とだから2ヶ月後ぐらいかなこの動画を撮ってる2ヶ月後
9月の末には完成して10月と11月で
印刷所屋さんにどういう製本をするか
紙はどれを選んで印刷方法を
どうするか とかを
自分で決めたりとか1回 試し刷りをしたりとかする
期間が2ヶ月 一応空いてますこの本って 僕の中で
「構想3年 制作1年半」
かかっておりますだって この3年間に
読んだ本を紹介してるから
3年かかってるんですよね「この本を作ろう」って
思ったのは1年半前なので僕の中でもワクワクドキドキしてるわけよ
「どんな本ができるんだろう」とか言ってその「本の紹介」だけじゃなくて
前書きがあります 後書きもあります中にコラムっていうのを5つ入れてます
例えば「純文学とは何ぞや」みたいな結構 読み物として
まあ面白いんじゃないか
という感じをしてます手前味噌で なんですけどそれが残り4ヶ月になったわけですよね今 撮ってるのが
8月の初めの方8月 9月 10月 11月
あと4ヶ月で完成
というか発売になるんで皆さん ぜひ
買っていただけたら
と思います今のところ
こういうファイルに
本文とかを ずっと印刷して
やってたんですよ今のところ 毎ページ 全部
印刷して見てるんだけどやっぱり表紙が出来ると違うね表紙って その本の顔になるわけだからここにも印刷して
表紙を入れてるわけだけど表紙ができて 本当に嬉しいなこの表紙 もう本当に嬉しい僕の一生の宝物っていうかだから早く この本を完成させたいんだけどこれ 最後に言いますがこの本は「文学フリマ東京39」で
売ると言いましたが お値段の方は1500円いわゆるA5版
って言って
漫画のワイド版よく同人誌とかでは
使われている
本のサイズになりますもちろん東京で売るわけだけど「ちょっと東京は遠い 行けない」
っていう方もいらっしゃると思いますがのちに通販を考えています
でも来年になるよね12月にそれがあって 次の月ですよね2025年1月の どこかには
通販の「BOOTH」っていう
サイトがあって今のところ まだ計画段階だけどそのBOOTHっていう
同人誌の販売サイトを使って
通販を考えておりますので遠方の方は 通販で ぜひ
お買い求めいただけたら
と思いますこういう本はないからね1000冊とか紹介している
ブックガイドって
ほとんどないですね普通に売られている
一般の本でもないのでかなり珍しい本だと思うんで中身としては 200ページあるんで
かなりのボリュームがあります文字数的には今の段階でも
16万字以上あります原稿用紙 400枚以上 あるんで 本当に
普通の1冊の本ぐらいのボリュームがあるんで全然 高くないので むしろ
安いぐらいまでのお値段なんで12月以降ですが
ぜひ買っていただけたら
と思いますねもう表紙ができたので
僕も完成させなきゃ
いけないわけね そりゃこれだけ言っといて
これだけ素晴らしい表紙を
作っていただいて「12月1日に間に合いませんでした…」
じゃ 許されないことではありますから僕も この4ヶ月 真剣に同人誌制作を
頑張っていこうと思っておりますそんな感じでございます今日は 短い動画
だったかもしれませんが
そんな感じでございます僕も頑張っていきますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#978「絶対に役に立つ小説のトリビア2選」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと本に関してのトリビア2つ小説とか読書とか執筆に関して「これは役に立つだろう」っていう知識ですねそれを2つ言っていこうと思います早速やっていきましょう1つ目ある本があった時
作者名と書名があると
するじゃないですか「読み方が分かんないな」
っていう時 ないですかめっちゃ難しい苗字とか下の名前も「これどっちかな」みたいなとか作品名も カタカナとかで
書かれたら誰でも読めるけど難読漢字とか使われた時に「これどうやって読むんだろう」って思ってネットで調べても出ないな
みたいなこと ないですかこれ 1発で分かる方法があって例えば この本があるとするじゃないですかこれは1年前ぐらいに
芥川賞を取った作品ですけど皆さん この作家名と作品名を 正しく
読めますかっていう話なんだけどこれは正解は「さとうあつし」の
「あれちのかぞく」なんですねこの状態では
ルビが振ってないから
分かんないじゃないですかでも これ正しくわかるんですどうするかっていうと
奥付を見るんですね「奥付」っていうのは
本の1番 後ろに書いてある
データのことなんですけれど最近の本では 作者名と書名には
必ずルビが振ってあるんですね「荒地の家族」と「佐藤厚志」に
ルビが振っているでしょう「家族」っていう言葉は
誰でも読めるけど
家族まで振ってるんですねこれは ここ20年ぐらいの本では必ずルビが振ってますなので 本さえあれば 奥付を見ると絶対に
読み方がわかるようになってるんですね元々 本って 読み方って特殊な読み方するやつも
まあ あるじゃないですか表紙でルビが振ってない場合どこを見ても読み方が分かんないっていう本は例えば図書館とかデータベースとかに
登録ができなくなっちゃうので必ず出版社は読み方を書くようになってるんですよ例えば ですけど
この本があるわけですねこれは20年前ぐらいに
直木賞を取った作品ですが作家名と書名 皆さん お分かりでしょうか
意外と これ 難読問題というか
(車谷長吉『赤目四十八瀧心中未遂』)さっきと同じように奥付を見ると
絶対に分かるようになってて奥付を見ると 答えとしては車谷長吉(くるまたにちょうきつ)の
『赤目四十八瀧心中未遂』
(あかめしじゅうやたきしんじゅうみすい)これが正解となるんですけど
これももちろん書いてます著者名と書名にそれぞれルビが
振ってあるということですね例えば 作者名とかはプロフィール欄が
本の後ろの方に書いてあったりしますよねもしくは文庫だったら1ページ目をめくったら
表紙の裏側に書いてたりとかするんですけど作品名のルビって奥付ぐらいしか載ってない場合もある「読み方を正しく知っていること」って
僕はめちゃくちゃ大事だと思っていて例えばですけど ちょっと
特殊な例かもしれないけどこうやって僕みたいにYouTubeとかで
本を紹介する動画を作ろう とか思う時に読み方が分かんなくて
「〜〜〜」みたいな言うと
失礼になると思うんですね作家名も間違えて
作品名も間違えたりするとやっぱり ちょっと
「この人 知らないのかな」
とか思っちゃうしあと作者とか出版社に
失礼な感じにもなりかねないので正しく作家と作品名を知っておくことは
僕 大事だと思うんですよ とてもだから僕は 必ず本を買って
「これ読もうかな」と思う時必ず最後の奥付から見ますよこれ 結構 マニアックな読み方かもしれないけど奥付はとても大事です
データは知っておいた方がいい奥付って あと出版年とか
出版社とか色々書かれてるんで僕も迷った時は
奥付を見るようにしてるこれは 結構 役に立つ
「とても役に立つ」と
思っております 個人的に2つ目皆さんは
普通の鉤括弧(「」)と
二重鉤括弧(『』)って
あるじゃないですか「それの違いを知ってますか」
っていう話なんですよこれは文中で出てくるものではなくて例えば ある本をツイッターで紹介しようってなった時に作者名を書いて その後 二重鉤括弧で括る場合と
一重の普通の鉤括弧で括る場合があるでしょ 作品名をこれは 全然 意味合いが違ってて言ってしまうと二重鉤括弧で括られた場合は
「書名」を表すんですね例えば ですけど
ここに1冊の本がありますこれは井戸川射子『この世の喜びよ』
っていう芥川賞を取った作品ですが例えば この本をツイッターとか
YouTubeで紹介しようってなった時に井戸川射子『この世の喜びよ』と書くのと
井戸川射子「この世の喜びよ」と書くのでは
意味合いが かなり違うんですね二重鉤括弧は基本的に
「本のタイトル」なので「本そのもの」を紹介する時は
二重鉤括弧で書くわけですよだけど一重鉤括弧は何かっていうと
「作品名」を表す時に使うんですね「作品名と書名って一緒じゃないか」
っていう人いるかもしれないけどこの本には 実は 3編の
小説が入ってるんですね「この世の喜びよ」と「マイホーム」と
「キャンプ」が3つ入ってるんですよ普通の一重鉤括弧で
「この世の喜びよ」
って指す場合はこの中の「この世の喜びよ」っていう
小説作品だけを表すことになるんですね「これ 別にどっちでもいいでしょ」
って言う人いるかもしれないけど特に純文学の場合
全然 違うものに
なっちゃうんですよねどういうことかって言うと純文学においては
「単行本化されない場合」
がありますよねまず文芸誌に作品が掲載されますとそれが人気があったりとか
なんとか賞とか取った場合は
単行本化する場合があるんですね逆に言うと
単行本化されない場合も
あるわけですから単行本化されていない「◯◯」っていう作品に
二重鉤括弧で これ面白かったですって書くと「こういう本があるのかな」
って思う人も出てくるんですよねなぜなら「二重鉤括弧は
本のタイトルを意味する」
っていう慣例があるからですねこれと同じ問題ですが
芥川賞と直木賞の違いがあって「芥川賞と直木賞の違い」
ってよく言われると思いますが芥川賞は雑誌に掲載された「作品」に与えられる賞で
直木賞は「単行本」に与えられる賞なんですね直木賞で考えると「単行本」を表すから
二重鉤括弧が確実になるわけですだけど 芥川賞の場合
「作品」に与えられるんで例えば この本があると
井戸川射子『この世の喜びよ』
があるんだけど正確には これ「芥川賞受賞」と書いてますがこの中に入っている「この世の喜びよ」
という中編に与えられる賞であってこの本自体に与えられていないんですねですから この併録作品の
「マイホーム」と「キャンプ」は
これは芥川賞ではないということですよ直木賞の場合は「短編集」
というものがあるわけですね短編集には色んな短編が入っていて
「それをまとめて短編集ですよ」
っていう直木賞の候補の場合その全体を直木賞として与えるんだけど芥川賞の場合は 単行本の場合 短編集になっていても短編集には与えられていないということですよこれ かなり純文学では ややこしい問題というかエンタメ小説よりかは純文学の方が問題化しやすいというかこれがまたややこしいのは例えば『この世の喜びよ』の中に入っている
「この世の喜びよ」とかになるわけですね受賞した作品名と
同名の単行本の書名になる
場合があるので『◯◯』の「◯◯」とか
言うことが出てくるわけですねその場合は 二重鉤括弧の
一重鉤括弧っていう表し方をするとただ 最近の芥川賞は
受賞した作品だけで単行本化
するということも多いのでこういう場合は 区別は
厳密にした方がいいけど別に勘違いする場合があんまりないので
いい時もあるとは思うんですけどねでも これは知っといた方が とても面白いそれこそ 例えば
文庫本の表紙の
裏側に書いてある作者のプロフィールでは
明らか使い分けられています
(出版社によりますけど)だから そういうところも
ちょっと気にして
プロフィールを読んだりとかウィキペディアを読んだりとかすると
面白いなと僕は思っていますねそんな感じで 今回 2つの本に関する
トリビアを言ってきましたけれど僕は このYouTubeっていうのを
5年間ほど やっているんだけどYouTubeをやる時に どっちも
大事になってくるんだよねこれは いわゆる
アウトプットの問題でインプットする時は 別に
どっちでもいいわけですよ一重と二重とか 作家名とかはインプットする時は
究極的には
どっちでもいいけどアウトプットする時に 人に伝える時に とても
大事な本のトリビアというか ルールというか知っておきたいことかな
と僕は思いましたねそんな感じで皆さんも もし本とか
読書とか執筆とかに関して役に立つよ っていう
トリビアとかがあったら
ぜひ僕に教えて下さい僕も全然知らないことがありますので
ぜひコメントで書いてみてくださいそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#977「皆さん、文学通ならこれは読んどけ、っていう作家や作品を教えてください!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと僕は 今年の12月1日にある
文学フリマ東京39っていうのに出品者として初めて 参加
しようと思ってるんですけどそこで売るのが
『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
っていうブックガイドなんですねこれは僕がこの3年間で読んだ
1080冊の本を全てまとめてあらすじと感想を 1080個
並べたっていう本なんですよこれ自体は まだ原稿が
完成していないんですねなんでかというと まだ
1080冊読んでないからね残り なんと
59冊 読んだら
完成するんですよここで1つ問題というかあと その59冊 何を読むか
っていう問題があるんですねそれについて考えていこう
っていうのがこの動画なんですけど僕がブックガイドを作ろうって思って特に現代の純文学を中心に読んできたわけですよやっぱり色んな多くの作家を紹介したいじゃないですかだから同じ作家ばかりだったら
あんまり面白くないというか僕は この1冊さえ読めばこの現代の純文学作家を
大体 把握できるだろうっていう
ブックガイドにしたいわけですよ最低でも「1作者1作品」は
入れてるつもりなんですね結構 読んできて
色んな作家陣を
入れてきたわけですよ残り59冊ねもう ここは ほんまに
文学通の人が読むだろうって
思ってる本を入れたいわけですねもちろん僕がまだ読んでなくてでも これを入れなきゃ現代純文学は
語れないよ みたいな本ってあるわけですよここで皆さんに相談したいのがあってつまり皆さんが思う
「文学通なら読んどけよ」っていう作家 もしくは作品をコメントで書いてほしいんですよね僕に教えてほしいんですよそれは基本的には「日本文学」にしたいです海外文学は今回は多少入ってますが残りの59冊は日本文学にしたいと考えています大体は「戦後以上」ですね戦前の作家は今回 あんまりほとんど入っていませんタイトルが「現代純文学」と言っていますからできるだけ現代に近い2024年に近い方が僕はありがたいがでもやっぱり文学通と言ってたら戦後ぐらいから始めてもいいかなと思ってる最近は僕 1970年〜1980年代の作家とかをめっちゃ調べて「あ〜この作家を入れなきゃな」とか
そういうのはめっちゃ考えていますだから その辺りでもいい戦後とか1970〜80年代でも全然OKです 現代もOKです僕の読書状況とかを全然考えずに
バンバン言ってもらったらいいです1人1個とか10個とか20個とかいっぱい書いてください作者陣をいっぱい書いてくださったら「あ この作家 そういえば」とか言って僕もそれを思い出して それを
調べて また読んだりします例えば 具体例を挙げるとするじゃないですか59冊のうち 結構 実は事前に この作家をこの作品を読もうと思ってる作品があるんですねそれをちょっと言おうと思います例えばですよ これは古い作家になりますが深沢七郎深沢七郎は『楢山節考』とか有名だけど今回 読むのは
『みちのくの人形たち』(1979年)
を読もうかなと思ってる田中小実昌田中小実昌も文学通が読んでるイメージがあるのよ直木賞を実は取ってるんだけど『ポロポロ』(1979年)っていう作品が
谷崎潤一郎賞を取ってるんですねだから『ポロポロ』を読もうと思ってる吉田知子この人もちょっと古い人ではありますよ芥川賞を取ってるんですけど1番 有名なのは『お供え』(1993年)
っていうやつが有名なんだよねこれは川端康成文学賞を取っていてホラーっぽい とか言うのを聞いたことある庄野潤三庄野潤三を好きな人いるでしょうあの辺の私小説系列の作家陣が好きな人いますよね上林暁とか庄野潤三は
『プールサイド小景・静物』
で芥川賞を取ってるんだけど今回『夕べの雲』(1965年)を
読もうかなと思ってますとか あと小川国夫小川国夫も渋いよね今回『ハシッシ・ギャング』(1998年) かもしくは『逸民』(1986年) を読むかで悩んでる竹西寛子竹西寛子も名前は聞くし例えばですが『兵隊宿』(1982年) が
川端康成文学賞を取ってるらしいんですねそれを読もうかなと思ってるの先に言っておくと2000年以降の芥川賞受賞作品は全部読んでます今回の僕のブックガイドには2000年を超えた芥川賞受賞作は全部入ってるからそれらの作家は一応 1作家1作品を
通過しているというか やってるんでそれらの作家は今回は 残りは
読まないということですよだけど90年代より以前ですよね はまだまだ読めてない作家陣がいますのでその辺も教えてくれたら嬉しいですね例えば 芥川賞受賞作で
これから ちょっと読んで
いかなきゃなと思ってるのは室井光広『おどるでく』『おどるでく』(1994年) は
文学通はちょっと読んどけよ
っていう作品でしょ僕もめちゃくちゃ昔に読んだことありますよアンチロマンというか アンチ文学みたいなストーリーがほぼなく 文字びっちりタイプ僕が大好きな文字びっちりタイプで書かれている『おどるでく』は今のところ読んでいないのでこれからちょっと読む予定尾辻克彦尾辻克彦は『父が消えた』(1981年)
で芥川賞を取っているんですけど尾辻克彦はサブカルの人というか赤瀬川原平っていう芸術家なんだけど小説を書く時のペンネームが尾辻克彦なんだよね『父が消えた』も どちらかというと
ポップアートとか言われたりしてちょっと当時としては かなり新しかったというかこれも また読もうと思ってます宮本輝『螢川』『螢川』(1978年) は すぐ読める
ような作品だとは思うんだけどそんなに分厚くないからね僕はできる限り ご存命の作家を
読んでいきたいなっていう気持ちもあるのよつまり まだ亡くなっていない
作家ね なんでかって言うとこれからも
新作が発表されていく
可能性があるでしょ文芸誌をチェックする時に目につくわけね「この人の新作が出てるんだ 」
そういう面白さがあるわけだから 生きている作家は
とりあえず読んでおきたいわけだから結構 デビューして50年みたいな作家もいるわけね超ベテランの作家 その伝で言えば村田喜代子『鍋の中』『鍋の中』(1987年) は
芥川賞を取った作品ですよ村田喜代子も超ベテランの作家ですよね髙樹のぶ子髙樹のぶ子『光抱く友よ』(1983年)
これも芥川賞を取った作品です草間彌生『クリストファー男娼窟』草間彌生っていうのは現代美術っていうのかなアーティストですけどこの人 実は 小説も書いてて1番 有名なのは
『クリストファー男娼窟』(1984年)
だと思うけどこれはちょっとまた読みたいと思ってるんだよねあと この辺 読もうと思ってるのは皆川博子皆川博子は
ミステリとか幻想小説とか
そういうのを書いてるんだけどちょっと読んどかないといけないな
と思って 1冊 入れてるんですよ
『蝶』(2005年) っていう作品石牟礼道子石牟礼道子は読んどかないといけないだろっていう
よくよく突っ込まれるようなマジもんの人なんで今回は『苦海浄土』じゃなくて『椿の海の記』(1976年)
を読もうかなと思ってますあと最後に この作家だけ
言って終わろうと思うけど橋本治橋本治は『桃尻娘』とかで有名なんだけど今回 読めそうだなあって思うのと
あと入手ができたっていうのが『暗野 (ブラック・フィールド)』
(1981年)っていう本当に初期のやつちょっと古い河出文庫ってあるのよそのバージョンの『暗野』が
最近 ちょっと手に入ったんで
それを読もうと思うんだけど橋本治も最低1冊は入れとかないと怒られそうな感じがして
ちょっと読もうと思ってますね僕はまだまだなんです 正直ね僕はまあまあ読んでるつもりではありますが「ほんまもんの文学大好き人間」
とは やっぱり言えないな読んでない本がまだまだあるからだけど
「ほんまもんの文学大好き人間」
になりたいわけね 僕はだから「ほんまもんの文学大好き人間」が
読んでるような本を追っかけていきたいわけねそういう本を読むことによって
やっぱりほんまもんになれる本物の読書家になれると僕は思ってるからそういうのを調べてるわけね 今ね僕が このYouTubeチャンネル
もうちょっとで5年になるんだけど皆さんに教えてもらったもの
めちゃくちゃ あるんでね
(マジで感謝しております!!)これからも皆さんに色々
教わっていきたいなと
本当に思っていますのでぜひとも ばんばんコメント 本当に作家の名前だけでもいいんで1人でもいいし100人でもいいんで
本当にたくさん教えてくださいどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#975「第171回芥川賞・直木賞の受賞作を予想します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと先日から第171回の
芥川賞と直木賞の候補作を
ずっと読んできてそのあらすじ・感想を言ってきましたがついに今回の企画で最後の動画となりました芥川賞・直木賞の受賞作の予想でございますねこの私つかつは何が受賞すると予想するのか
っていうのを発表する動画でございます早速やっていきましょうまず直木賞から行きますけれども1つ1つに僕は点数をつけてきましたがそれをまず全部 言っていこうと思います①青崎有吾『地雷グリコ』90点②麻布競馬場『令和元年の人生ゲーム』85点③一穂ミチ『ツミデミック』80点④岩井圭也『われは熊楠』92点⑤柚木麻子『あいにくあんたのためじゃない』99点こちらで1番 点数が高かったのは柚木麻子『あいにくあんたのためじゃない』99点ですねこれは本当に良かった短編集なんだけど僕は本当にボロボロ泣いてました複数回 感動したっていうので
僕は99点をつけましたねなので僕は直木賞はこの柚木麻子さん
『あいにくあんたのためじゃない』
これを一押しすると受賞予想するということですねもう1つ もしダブル受賞があればですよもしダブル受賞があれば岩井圭也『われは熊楠』ですねこちらを推そうかと思います『われは熊楠』は時代小説・伝記小説でしたからこの候補作の中では一風変わってたという感じですねまず作品も伝記小説っぽくなくて夢とか幻とか そういうのを多用することで熊楠っぽさを表しているっていうところが
特徴的だったんじゃないかなと思います他の作品も全部 良かったですよ『地雷グリコ』は僕好みのゲーム小説だったんだけど直木賞は取るかな どうかなっていうところもあるかな『令和元年の人生ゲーム』はこれはかなり飛び道具というか問題作ですからもしかしたら全然 直木賞を取る可能性はあります『ツミデミック』はホラーとか犯罪小説とかそういうのに入るような作品だったと思いますが結構 色んなオチ方があってそこをどう捉えるかっていう感じかなでもやっぱり直木賞 良かったね毎回 言うかもしれないけど僕はエンタメ小説って最近はもう読まなくなっちゃって純文学ばっかり読んでますからこうやって半年に1回直木賞っていうお祭りの候補作5作品読めることは良いと思うんですねやはり純文学とは違う面白さがエンタメにはあると僕はいつも思っておりますね
素晴らしいと思います続きましてですね
芥川賞の方に参ろうかと思います芥川賞も同じく点数を
まずは言っていこうかと思います①朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」98点②尾崎世界観「転の声」93点③坂崎かおる「海岸通り」97点④向坂くじら「いなくなくならなくならないで」90点⑤松永K三蔵「バリ山行」95点ということは 1番点数が高いのは朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」98点でございますこれは本当に良かったね結構 複雑な話だと思う設定が結合双生児の話なんだけどこれにさらにお父さん・伯父さんの胎児内胎児が入ってきて設定だけでお腹いっぱいみたいなところはあるんだけど実は もっともっと主人公たちの悩みだったりとか主人公たちの社会的な位置づけだったりとかそっちの方がおそらくメインなんですね一見イロモノに見えるんだけどやってることはスタンダードな純文学って感じがして「あ〜とてもいい」と僕は思いましたねもしダブル受賞があるなら坂崎かおり「海岸通り」ですねこれも本当に良かったですよこれもザ・純文学っていう感じだと思う適度適度にシンボリックっていうか象徴的なモチーフが多く出てくるから解釈のしがいがあるわけですね僕はやっぱり解釈が好きなんだよね一見 読んでもわからない物語でももしかしたら これとこれが繋がっているのかなとか言って色々 頭で考えていって「あ これってもしかして?」みたいな一種ミステリ的な 謎解き的な考えで
やっていくのが好きなんですよそう思うと 例えば 松永K三蔵「バリ山行」は物語としては めちゃくちゃ面白いんだけど象徴とかではなくて もっとリアルの方に寄ってるんですね普通に読んでも 普通に面白いっていうか社会と山の対比っていうのはあるものの普通に面白いって感じで
リアリズムの方に行っててちょっと心の内側の表象みたいなのはあんまり出てきてないような気がするんだよね僕の好みとしては やはり
「サンショウウオの四十九日」や「海岸通り」的な
象徴塗れみたいなのが
めっちゃ好きなんですよ他の作品ももちろん良くて尾崎世界観「転の声」ですね「転の声」はちょっと自意識が高いんですよねそれを面白いと思う人もいると思うこういう自意識の暴走系小説も好きな人いると思うんですよそれに終始しない もっと社会にも焦点を当てて転売とプレミアと無観客ライブっていうどんどんおかしな方に社会が寄っていってるっていうのがストーリーとして展開されていく
っていうところの面白さもあるのよだけど自意識高い小説の一人称ってちょっと濃すぎるっていうか客観的な 中立的な登場人物の語りとかがあんまりないのでそこをどう
選考委員が言及するのか
が僕は見物だと思うんですね向坂くじら「いなくなくならなくならないで」これはこれで超良かったですねこれも言ってしまえば
テーマはちょっと古いというか
よくありがちなんだけどだからと言って 新しい要素とかをちゃんと入れてるので 全体的に偉いですよ偉いっていうか芥川賞候補って何かしら新しさを絶対にあるのよ今まで味わったことのないような
小説の面白さが全部入っているこの「いなくなくならなくならないで」は
共依存とか自立とかをテーマにしてるんだけど最初は お化けとか幽霊とか
そういうところから話が始まるんでちょっとドロっとしてるんですねこれはどちらかと言うと 主人公の自意識のなさって言うか自我が確立してなくて人から頼まれたら断れないから どんどん相手の幽霊というか友達が迫ってくると入ってくると プライベートを侵食されていくそことの戦いになってくるので その面白さがありましたね僕はこれは全部 雑誌で読みましたけど単行本でも もう1回 読もうと思っていますこれは僕の読書のルールの1つで文芸誌掲載の 雑誌で読んだ場合意外と雑誌掲載時と単行本化された時って微妙にちょっと変わってたりとか単行本にはプラスアルファで短編がつくとか もう1個 中編がつくとかあるので基本的には僕は単行本派なので単行本でも もう1回芥川賞候補は読もうと思ってますねそんな感じで 今回 第171回の
芥川賞・直木賞の候補作を
振り返ってまいりましたけど半年に1回のお祭りですからね僕は毎回 参加できてよかったですよ今回で僕 10回目なんですよね過去5年間 全ての候補作を読んでこうやって動画で出すっていうのを毎回やってますこれは「文学賞メッタ斬り!」リスペクトですけど最近 やってる人が増えたねYouTubeとかTwitterとか あとブログとかラジオとかでも芥川賞と直木賞の候補作を全部 読んで
予想するっていうの増えたと思いますそういう文化が広がってほしいね今まで「純文学」っていうものが あまり
普及してないと思うんですね 現代の純文学ミステリとかに押されて
エンタメの方がみんな
読んでると思うんですけど純文学の良さっていうのがこの芥川賞の候補作5作品を
読んだだけでも本当にわかるよ最近の候補作は全部 単行本化されてるんで手に入りやすいので ぜひ読んでみてください今回 第171回 芥川賞・直木賞が終わりましたけれども最後に ぜひ皆さんが この作品が
受賞するだろうって思った作品をぜひコメントで書いてください予想するのはタダなんで
どんどん書いちゃってくださいそんな感じでございます今回もとても楽しかったですねあと7月17日 受賞作発表日を
待つだけでございますので皆さん 一緒に待ちましょうそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#974「芥川賞候補⑤朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかと言うと先日 第171回の芥川賞の候補作が発表されましたけど今回 読んだのは こちらになってますねこちらは新潮5月号になってますがこの中に朝比奈秋
「サンショウウオの四十九日」
新潮 5月号早速やっていきましょうあらすじまず主人公が杏と瞬っていう双子なんですよねどちらも女性で 年齢は29歳とこの杏と瞬がとてつもない設定を持ってるんですねそれは杏と瞬は「結合双生児」なんですね昔の言葉で言うとシャム双生児になるわけですがこの杏と瞬の特殊な面で言えば体の半分半分がそれぞれ杏と瞬なんですね見た感じ1人の人間のように思えるわけですよだけど実は 半分半分に杏と瞬の肉体があると脳味噌も2つあったりとかして特殊な体の作りをしてるんですね二重人格との違いとしては1度に瞬と杏の2つのそれぞれの
意識が同時に存在してるのでそれぞれ思うこととかも違うんだけどその相手の考えてることは
自分にも分かったりするんですね相手が感じている感情とかも
共有することができるっていう
特殊な体を持ってるんですよその瞬と杏にはお父さんがいてお父さんが若彦って言うんですけどこのお父さんも特殊な出生の仕方をしていて若彦には勝彦っていうお兄さんがいるんですけど勝彦は生まれた時に
そのお母さんのお腹の中に
入っていたのは勝彦だけだったんですね勝彦が生まれて でも勝彦のお腹の中がちょっとデカいとっていうか 風邪とかひきやすいかなんかで病院に連れてってもらって CTスキャンをするとなんと勝彦のお腹の中に もう1個 赤ちゃんがいるとこれは「胎児内胎児」って言われる現象らしくて元々 双子で生まれる予定だったのが一方が一方を吸収してしまって胎児の中に胎児がいるっていうことになったんですねその勝彦の中の胎児を摘出して 出してみたら実はその赤ちゃんも生きていてそれが実は若彦なんですね2人とも どっちも元気に育って 今は
おじさんみたいになってるんですけどその勝彦っていうのが 主人公たちの杏と瞬からするとお父さんのお兄さんになるので伯父さんになるわけですねその伯父さんが急にですよ 亡くなってしまったと今度 葬式があるんでみんなで 家族みんなで参加しましょう っていう話がこれ 四十九日ってありますからそういう話になってくるとこのタイトルの「サンショウウオ」っていうのが結構 キーワードですけどこれは作中に「陰陽図」っていうのが出てきてよく中国とかで言われる中に勾玉が2つある みたいな図ってあるでしょこれの勾玉みたいなやつが
サンショウウオに見える
っていうんですねもちろん これは双子を表してるというか主人公の杏と瞬を表していると思うんですけど言ってしまうと この2人が伯父さんの葬式に参加してその後 ちょこちょこっとストーリーがあって2人はどうなるか
という話になってくる
っていう話なんですけどここからは僕の感想になりますけどこの小説って めちゃくちゃ難しいというか色んな要素が入っていて超面白いですねさっきも言ったけど 杏と瞬が
交互に一人称で語っていくんですけど途中で交ざる時があるんですね杏が一人称で語ってるのに途中で瞬のターンになることがあるんですよ瞬の時も杏になる時があってこれは この特殊な体がないと
そんなのできないじゃないですかただ 先行作品みたいのがあって例えば 島口大樹
『遠い指先が触れて』
っていう小説があってこれは男と女がいるんだけど一人称で混ざっていくっていう試みをやってるんですよだから ちょっと似てるもう1個は
舞城王太郎が
『短篇七芒星』とかあと
『好き好き大好き愛してる。』
の単行本の中に入ってる「ドリルホール・イン・マイ・ブレイン」とかあと『淵の王』とかこの辺りって 一人称のさらに もう1個外側っていうか意識の外に もう1個の意識があってつまり1つの肉体なのに2つの人格が存在しどっちの語りも使えるみたいな
特殊な一人称があるんですけれどそういう流れの1つに
「サンショウウオ〜」があると
僕は考えてるんですけどこの小説は
「究極のマイノリティ小説」
と言ってもいいわけですよお父さんも特殊
主人公たちも特殊って
いうところも良かったしこの2つが対になってるんですよね 明らか伯父さんが亡くなった時に主人公の杏の方が めちゃくちゃ
パニくるシーンがあるんですけどこれって ここが繋がっていると考えれば伯父さんが勝彦 勝彦に対応するのが杏お父さんの若彦 そして瞬って対応することができるわけねお父さんと伯父さんの関係って胎児内胎児なんで「輪っかの中に輪っかが入ってる」
みたいな考え方をすればいいわけですよでも これって食い合ってる関係っていうか一方的に搾取されてる関係でつまり 1歳になって
お父さんが伯父さんの
体内から出てきたんだけどそこから五十何年が過ぎてるんだけど伯父さんはそこから体調がそれほど
良くないんですね つまり体が弱いそれに比べてお父さんはかなり元気で風邪1つ引いたことがないみたいなタイプなんですよだから かなり対照的なんですねこれは何でかって言うと
「食い合っていた」
みたいな説明されるわけ体の中に もう1個 胎児がいるってことは中の胎児は外の胎児のエネルギーを吸って成長してるんで一方的な関係の 搾取関係になってるんですねそれは大人になっても そうなってるのよそれに比べて この杏と瞬は半分半分ですから食い合うことはないわけですねその 多分 関係性をずっと考えていくって話だと思うさっきの陰陽図 太極図とも言われるやつだけどあれって サンショウウオが2つ
尻尾を食いあってるように見えるとこれは やっぱり
伯父さん(と父との)
の関係だと思う陰陽図ってバランスを表してるわけですね光と影がそれぞれあるんだけどこれ バランスが崩れると食い合っちゃうんで今は落ち着いてるけど例えば 影の方が弱くなると
光が影を食ったりとか逆もしかりなんでこの小説って杏と瞬がお互いに食い合わないために
どうしていくかみたいなのを考える話だと思ったつまり太極図では食い合ってしまうから太極図から いかに脱却するか
っていう話かなと思ったけどねだからサンショウウオから脱却する話かなと僕は思ったけどだから多分 最後に主人公たちが喉を
めちゃくちゃやられてしまうと喉に炎症ができて救急病院に行くっていう話になっていくんだけどこれは明らか 中のバランスがおかしくなってるわけですね杏は息を吸うのがうまくて瞬は息を吐くのがうまいっていう描写があるんでということは 最後 呼吸器系がやられちゃうっていうことはそこのバランスが崩れてるってことなんですね大体 文学作品で『ハンチバック』もそうでしたけどもしくは同じ候補作の『バリ山行』もありましたけど大体 喉やられるのよ心のバランスが悪くなると
大体 体が悪くなるっていうのが純文学ではよくあるんで「ハンチバック」も喉やられてましたし「バリ山行」も喉やられてたんですよだから この小説って肉体と精神
っていうのが直接つながってるしその外側には
お父さんと伯父さんの関係
っていうのがあるっていうところで色々 リンクしててめっちゃ面白いめっちゃ考えさせられるところがあって超良い小説だと僕は思いましたもっともっと語りたいけどちょっと時間の都合上 語れないんですねそんな感じで 毎回 候補作に点数をつけていますけどこの「サンショウウオの四十九日」は98点ですとっても良かったですねぜひ芥川賞を取ってほしいと思いますただ ちょっと設定が特殊すぎるからそこで賛否両論あるのかもしれないんだけどそこが凄いと思った普通 そこまでは もしかしたら考えれるかもしれないね一般人でも 体半分半分の人間がいるみたいなのは考えられるかもしれないしかし ここまで深く深く設定を追求したっていうのがこの朝比奈秋さんにしか
できなかったんじゃないかな
っていうところはやっぱり思いますねぜひ文学史に残していくべき1篇じゃないかなと僕は思ったりはしましたけど 皆さんはどうでしょうかねそんな感じで 今回で なんとですよ直木賞・芥川賞の候補作を全て
動画にすることができました素晴らしい!
よく頑張ったね最後にですね 芥川賞・直木賞の受賞作の僕の予想ですねそれぞれ何が受賞するか当たるも八卦 当たらぬも八卦ですがそういう動画を最後1本 動画を出そうと思います受賞作の発表が7月17日ですからそれより前の日に動画を出そうと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#973「直木賞候補⑤麻布競馬場『令和元年の人生ゲーム』の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何をするかというと先日 第171回の直木賞の候補作が発表されましたけど今回 読みましたのは こちらでございますこちらは麻布競馬場
『令和元年の人生ゲーム』
文藝春秋 2024早速やっていきましょうあらすじこちらは短編集になってまして
4つの話が入ってるんですねただ 共通する登場人物が1人出てくるんで連作短編集と言ってもいいわけですねまず1番目が「平成28年」なんですけど舞台が慶應義塾大学のビジコンサークルなんですねビジコンっていうのはビジネスコンテストのことでつまり自分が新しい会社を建てたいじゃあ具体的に何をするかみたいな企画を立案したりとか運営していくにはどうするかみたいなのをそれぞれのサークルで競い合うとそれの大会が 今度 開かれて主人公たちはその大会に向けて
頑張っていくって話なんだけれどこのビジコンサークルの偉いさんみたいのに吉原さんっていう男の人がいるんですねこの人は なんと過去に高校生起業家として活躍してた時期があってサークルの中でも一目置かれているとその時に吉原さんのライバルみたいなキャラがいてこれが沼田っていう男がいるんですね沼田はみんなが色んな会議とかしてて結構 おちょくるタイプの人なんですね「それはダメだよ」とか言ったりとか「そんなに必死になってどうすんの」とか言ってちょっと上からっていうか心をくじけさせるような言い方をしたりとかするんですね「なんで沼田さん このサークルにいるんだろう」みたいな「あれだけケチをつけるんだったら
やめたらいいのに」みたいな人なわけですねなんだけど これ 主人公がのちのち吉原が 実はそんなに
中身あるような人間に思えなくてそうなってくると 沼田が本当は
正しいんじゃねえかって考えてきて沼田に接触するっていう話が第1話ね第2話に「平成31年」っていう話があってこれは会社編に入るんですね主人公は変わって女性の人なんだけど人材系の最大手企業「パーソンズ」
っていうところが舞台なんですね新入社員なんで同期もたくさんいるわけですよみんなで会社を頑張ろうぜって言って みんな意識高いわけよだけどパーソンズはデカい会社になってるんだけどそこまで仕事自体に発展がないんですよね同期も色々辞めていくんですね「私 本当にこの会社で良かったのかな」みたいな思うわけこれ なんと 同じ同期だったと思うけど沼田がまたいるんですね時間が第1話から第2話に何年か経っているので沼田もさっきまで慶應義塾大学にいたのにこれ パーソンズに入ってるんですね沼田とは沼田でいつもの感じで「せっかくこの大手のパーソンズに入ったんだから定時で帰って その後に皇居ランに行って人生 のんびり暮らしたいよ」みたいなそういうスタイルの生き方を望んでるんですねだけど主人公はどんどん周りの同期が辞めてって「仕事って何だろう」って思ってたら色んな人が
「人生は仕事だけじゃないよ」
とか言ってくるから「じゃあ 趣味を作ろうか」って言って皇居ランを走るんだけどそこに沼田がいたりして沼田と一緒に
色んなことを考えていく
って話になってくるっていう第3話「令和4年」ですけどこれはシェアハウスの話になっててこれ また違う主人公ですけどそのシェアハウスって意識高い系シェアハウスでそこで主人公は一般の企業に入ってていわゆる「チューター」って言って
シェアハウスの人たちを教える教師役みたいな立場にいる
人が主人公なんですねそこに同じ立場に沼田がやっぱりいるんですね地域猫問題の話になってきてシェアハウスがある地域には「地域猫」っていって野良猫なんだけど地域の人たちで保護したりとかむやみに繁殖しないようにそういうのをコントロール
するようなことをやってるんですよだけど地域でやろうって言ってるんだけど嫌な近所の人もいるわけね「猫なんか嫌いだよ」とか「勝手に敷地に入るんだよ」とかいう人たちがいてそこをどうやってまとめようかっていうのをこのシェアハウス全体が立ち上がって地域猫問題を解決するって話になるんだけどこのシェアハウス 何人住んでるかわかんないけど途中で100人ぐらいいるんじゃね
みたいな感じになってくるんだけどなんでかって言うと妙に被害者意識みたいな持ち出す奴がめっちゃ出てくるのつまり 1人2人
クレーマーみたいなやつが
近所のやつが出てくるわけねそしたら「俺たち正しいことやってるのになんでこんだけ言われないといけないんだ」って言って「俺たちは被害者なんだ 俺たちが正しいんだ」とか言って急にそのサークルがカルト宗教みたいになりだして「正しくないやつを追い出せ」とか言い出してめちゃくちゃ面倒くさいことになって
どうなるかっていう話なんだよね最後の第4話「令和5年」ですけどこれ 銭湯の話なんだよねある地域の銭湯があった時に銭湯って今 本当に潰れていったりするんで「昔ながらの銭湯を支えていこう」って言ってある会社っていうか ある人々が例えば
クラフトビールを銭湯に入れて
独自性を担保するとかあと例えば サウナを導入するとか色んなことをしようって言って
考えたりとか実行したりするんですねそこで
ある銭湯の2代目の坊ちゃん
みたいな人がいるんですよその坊ちゃんは本人の軸みたいのがないから「これどうですか これどうですか」って言われると「いいかも いいかも」とか言って「全部採用」とかすると銭湯としてのコンセプトが
グチャグチャになっちゃうんで
どうするかっていう話なんだけどそこにサポート役っていうか 秘書的な感じでなんと沼田がいるんですね沼田がやっぱり頭キレるやつなんですよ 全体的にだから その坊ちゃんの秘書として「これはこうした方がいいですよ」とか「これはこうしない方がいいですよ」
とか言って アドバイスをして「沼田くん なるほどね」
とか言って やっていくっていう
話になっていくんだけど…ここからは僕の感想になりますけどこの小説って
「ビジネス書的リアリズム」
に溢れてるわけですねこの小説は
舞台・時代とかが
バラバラなんだけど出てくる登場人物の8割ぐらいは
「意識高い系」なんですねビジネス書とかで言われてるようなことを
考えてたりとか実践したりとかするわけですよこの小説って いわゆる戯画化してんだよね一部のところを強調するように書かれているのでむしろ この登場人物の中では
沼田が異質な存在として書かれる
っていうか 思われてるんだけど本当は逆だろうっていうことなんだよねこの小説って直木賞の中で
1番 問題作だと思うしむしろ その社会を皮肉ってるみたいな感じで言えば僕は芥川賞=純文学系に入れてもおかしくないと思うこういう小説って僕は初めて読んだし発明だなって やっぱり思うよね これこういうのを
タワマン文学・Twitter文学
とか言うらしくこれは麻布競馬場さんが開発した
とかいう話らしいんだけどあと これ 沼田ですよこの話って4つの話からできてるけどそれぞれに登場人物がいたとしても実質の主人公は沼田なんですね沼田の人生を追っかけてる
っていう話でもあるんですよ最後の4話目が「これでいいのか沼田」っていうちょっと沼田が可哀想になっていくんだよねだから沼田って 実力もあって意外と人と交流することもできるし結果も出してるんだよねだから沼田自体が 実は結構
ビジネス的に成功してる奴なんだけど最後の銭湯の話って これは
第1話目とめっちゃ似てるのよ第1話目に大学のビジコンサークルの話があるんだけど吉原っていう奴と
ライバル的な位置づけ
でもあるし沼田も吉原に
色んな複雑な思いを
持ってるらしいというのが第3話目のシェアハウスの話でもわかるんだよねだから「沼田 これで良かったのか」
っていう気持ちが僕は結構ある沼田は でも
それを求めていたのかな
とか思ったりするとなんか切なくなってくるんですよ意外と この小説って
沼田の点で言えば
かなり奥行きが広い一見 ビジネス的なアイデアを詰めました みたいなそういう話に思わせて 沼田の人生沼田の小説部分っていうのもきちんとあるのがこの小説の特徴かなと思ったりしましたねそんな感じで 候補作全てに点数をつけてますけどこの『令和元年の人生ゲーム』は85点ですねただしですよ これ かなりダークホース感があるんで全然 直木賞 下手したら受賞する
っていうことはありえると思いますよ新しすぎる 人類には
新しすぎた感があって賛否両論はあると思う 正直だけど まあまあ どうかなっていうところかなビジネス書をもっと小説に寄せた
みたいな感じではあるんじゃない?沼田がある種のトリックスター的な動き方をするんでそこの面白さが1つあるわけねだから面白い
とても面白い小説だと
僕は思いましたねそんな感じでなんと今回で 直木賞候補作を
全て動画にすることができましたあと芥川賞候補を1つだけ動画にしてないんでそれと あと予想動画も出したいと思ってますのであと2つ 動画を出すんでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#972「芥川賞候補④向坂くじら「いなくなくならなくならないで」の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 第171回の芥川賞の候補作が発表されましたけど今回 読みましたのは こちらでございますねこちらは文藝の夏号なんですけどこの中に向坂くじら
「いなくなくならなくならないで」
文藝 夏号早速やっていきましょうあらすじ主人公が時子っていう女の人なんですね今は21か22歳なんですけど大学生で就職活動をしていて
内定が決まってるんですね今は10月なんですけど時子がふと道を歩いてたら電話がかかってきてそれは非通知でその電話を取ったら なんと4年半前に自殺した
時子の友達の朝日ちゃん
っていう人からだったんですね朝日ちゃんは
4年半前に高校生の時に
めっちゃ仲良かったんですねだけど ちょっと
メンヘラまでは行かなくても
ちょっと病んでるんですよ何でかって言うと
家族と揉めてたりとかして生きるの辛いよとか言って交換日記までつけてた仲で春休みが何かが終わったとかなんかに学校に行ったら朝日ちゃんが来てなくて朝日ちゃんのお母さんからメールか何かがあって「朝日が死にました」みたいなそういうメールをもらってめっちゃショックを受けるんですね 主人公・時子は最初 幽霊だと思うわけね朝日から電話がかかってきて今 家がないから泊まらせてくれないかっていうわけ時子からすると「死んだ朝日から!?」と思って でも幽霊でもいいから会ってみたいと思って 会ってみるとちゃんと朝日なんだよねそれで朝日を家に泊まらせるんだけどそこから時子の地獄が始まるっていう話なんですけど時子は1人暮らししてるんですよね今は大学生なんで大学に近い部屋を借りてるんだけど今度 社会人になるんですね4月から社会人になるので会社から近いのは実家なんですよだから1人暮らしの部屋を引き払って
実家に帰ろうと思ってるんですね朝日に聞くと朝日は家がないっていうからずっとこの部屋にいてくれたらいいよって言うんだけど朝日が家を出ていかないんですね4月から実家に帰らないといけないから「朝日どうする?」って言ったら「実家にも行きたい」とか言うんですね「実家に泊まらせてくれ」って言うんですねそこで時子は時子で「お母さんに相談するわ」って言って時子の実家にはお母さんとお父さんがいるんですね2人に相談したら「朝日ちゃんでしょ」って言って「死んだと思ってたけど生きてたんでしょう」って言って「友達だったら泊めてあげなさいよ」って言ってお母さんとお父さんがオッケーを出したので朝日も一緒に実家に来て朝日がいつのまにか家族みたいになってて時子は最初は良かったんだけどずっと一緒にいられるとやっぱり嫌なのでそこで半分好き・半分嫌いっていうかこのタイトルが
「いなくなくならなくならないで」
っていうタイトルなんでいなくなってほしいしいなくならないでほしいとそういう両存する気持ち
アンビバレントな気持ちを
持ち出して時子と朝日が もう大変なことになる
っていう話になってくるんだけどって話ここから僕の感想になるんですけどこの小説って言ってしまえば
時子と朝日の関係をずっと書いてる話でストーリーらしいストーリーってあんまりないんだよね実家に帰った後に実は時子にはお姉さんがいた
っていう話に繋がっていくんだけどお姉さんは若くして男と結婚して
家を出ていってるんですね今度 子供が生まれるっていうので実家に帰ってきてそれでお父さんとお母さんが
これまた変な人なんだよね 実は「みんな仲良く」みたいな精神を持っているというか共同体っていうか支え合って生きていこうよみたいなことを言うんだけど実際は自立を阻害してる感じもちょっとあるのよ それってこの小説 言ってしまえば共依存と自立がテーマなのねだからこれ ずっと後半朝日を家から追い出すぞっていう計画を立てては挫折を繰り返すのがめちゃくちゃページが割かれるんですね「私は覚悟を決めた」とか言って「朝日を家から追い出す」とか言ってるんだけど「負けた」とか言ってやっぱり朝日を追い出す
ことはできないとか言って
それを永遠にやってるの本当に嫌だったら主人公が家から飛び出したらいいはずで実家だけど別にまた1人暮らしして会社の近くに また部屋を借りてそこから会社に
行ったらいいだけなのに
それもできないんだねだから本当に離れたいんだったら離れられるんだけど主人公は離れたくない気持ちもあるからそこでめちゃめちゃ悩んでると
葛藤があるわけですね小説ではよくよくある話で女性3世代とかの話があった時にだいたい親子でベタベタしてあいつが憎いんだけど愛もあるみたいな離れられないテーマって結構あるのよめちゃくちゃ
僕が似てるなって思うのは
山下紘加『あくてえ』ですね『あくてえ』は何回か前の芥川賞候補になりましたがあれは女3世代の話で家族にめっちゃ腹立ってるのに離れることもできないと「あくてえ」っていうのは悪態のことで悪態を吐くって言うわけだけどこれは別に悪いことではなくていわゆる自立するために相手を
ケチョンケチョンにけなして離れさせるっていう心の変化なんでこの小説だって途中で朝日に対して「死ねよ」みたいなことを
主人公が言い出すシーンがあるんですねだから それは悪態なので かなり似てるんですねそういう象徴っていうかモチーフはいくつか出てきてて主人公が結構グロい映画が好きで就職してて仕事してる時に駅か町か何かの人々がゾンビに見えてチェンソーで切ってるみたいな想像する時があるんですけどこれは朝日がゾンビみたいなものなんだよね1回 死んでるんだけど蘇ってきたっていうのでゾンビでしょゾンビをチェーンソーで切るっていうのはいわゆる切断のテーマなんでこれ1番 時子に求められているのは朝日との関係を切るっていうことなんで共依存みたいになってる関係を切断して切ってもうさよなら〜っていうのが1番なわけですよだけど それがなかなかできないんだけどゾンビとチェンソーでそういう想像したりとかあと お姉ちゃんが赤ちゃんを産むっていうことでそれを聞いた時に「臍の緒を切るのは痛いだろうか」
って考えるシーンがあるんですね 時子がもちろんこれも
臍の緒を切るってことなんで
母子分離なので繋がりを切って
自立するっていうのが
主人公には求められてるとそういうのが描かれてはいますよねお姉ちゃんのキャラクターもそれに近いお姉ちゃんは自立してるんだよね妙にこの時子の家族ってベタベタするのが大好きでお父さんが父性的な機能がないんですねお姉さんはどちらかというと
自立を中心として考えてる人なんですねだから主人公はお姉さんから
学んでいかないといけない
っていうことになるわけよね最後のオチは必然でうまい切断能力になってないから
本当に極端な切断能力が働いて相手のことを〜!みたいなことになるわけねその点から見ると わかりやすい話ではあるんだけどそんな感じで 全ての候補作には点数をつけていますが「いなくなくならなくならないで」は90点でございますねこういう依存関係を描くっていうのは意外と昔からあるがこれは朝日ちゃんが1回死んで
帰ってきてるっていうところで友達との関係っていうのは珍しいと思う僕 1つ思ったのはこれ 本当に朝日ちゃん本人なのかなって思って妖怪の類みたいな感じにも思えてくるんだよね例えば水難事故っていうか(朝日が)
入水かなんかして死んだと その時にその朝日の記憶とかを受け継いだ妖怪みたいのがいてそれが朝日の形を取って 4年半後に現れて時子に接触して時子の家を侵略してやろうみたいなそういう妖怪の仕業のような気がするの最後の方で
交換日記のことを朝日が知らない
っていうところがあるんだよねもちろん朝日が忘れてるだけなのかもしれないんだけど微妙に「本当に朝日なのかなこれ」
みたいなのがちょっとあるような気がするのそう思うと これ バーバパパが
ちょっと効いてくる気もするのねバーバパパのクッションを
朝日が買うみたいな話があってバーバパパって不定形の妖怪みたいなものじゃないですかだからバーバパパ的な存在
だったような気がするんだよね
(朝日が)向坂くじらさんはこれが初めての小説だと思いますがエッセイ集がいくつか出ててそっちもまた近いうち読もうかなと思っておりますねそんな感じで 残りは芥川賞候補1つ 直木賞候補1つなのでプラス予想動画を出すので残り3つ動画を出そうと思いますのでみなさんどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#971「芥川賞候補③坂崎かおる「海岸通り」の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 芥川賞候補が発表されましたけれども今回 紹介するのはこちらでございますこちらは文學界の2月号なんですけどこの中に坂崎かおる
「海岸通り」
文學界 2月号早速やっていきましょうあらすじまず主人公が久住さんっていう女の人なんですねこの人は雲母園っていう老人ホームですね
の清掃員をやっているということですねその老人ホームにサトウさん
っていうおばあちゃんがいるんですね主人公はそのサトウさんと喋るのが好きなんですよ老人ホームの中にバス停があるんですねこれは本当に使われているバス停ではなくて主人公曰く「ニセモノのバス停」とこれは例えば
老人ホームの入居者の人が
家に帰りたいって言った時にそこでバス停が置いてるとじゃあ一緒に待ちましょうかとか言って職員と一緒に待っててでも本当のバス停じゃないからバスは来ないわけですねそれで諦めて また明日帰りましょうかみたいなことを言ってある種のごまかしというかこの作中ではクールタイムのために
設置されていると書いてるわけですねこのバス停の名前が「海岸通り」ここでタイトル回収ですがこれ 主人公が佐藤さんに
「私はミサキよ」って
何回も言うんですね久住さんが勤務してない日にも
わざわざ久住さんは来てサトウさんの部屋の中に入って「私はミサキよ お母さん」って言うのよサトウさんは
「いやお前はミサキじゃないよ」
って言うわけね「お前はナギサだよ」って言うわけよナギサとかミサキって誰なのかっていうとナギサっていうのはサトウさんの息子さんがいるんですねそれの嫁さんがナギサって言うんですよでも本当は久住さんは別にナギサじゃないわけねだからサトウさんはちょっと惚けちゃってて久住さんのことを
ナギサって呼ぶんだけど
それは違うとミサキっていうのは誰かって言うとサトウさんの娘さんがミサキっていう名前なんですよねだけど そのミサキっていうのは若い時に 男ができて
子供ができちゃったんで
すぐ家を出ていったとサトウさんはそれに腹立ってるんだけど完全に縁を切ったみたいな感じになってるんだけどサトウさんの中ではやっぱり
多分ミサキが好きだったんだね 娘がだからサトウさんの中では好きっていう気持ちと
憎いっていう気持ちが両存
していると思うんですねそれと同時に久住さんが働いている清掃の会社に後輩としてマリアさんっていう人が来るとマリアさんはウガンダから来た人で旦那さんが日本人で日本で働くってことになって
そこの会社に来たと主人公の久住さんの下についていわゆる部下みたいな感じで 後輩みたいな感じでマリアさんを色々教えるわけですその後にコロナ禍になっちゃって主人公も仕事が色々なっちゃって家にも帰れないと主人公って ちょっと大雑把な人みたいで家賃とか滞納していて家を出ていけって言われるんだよねそこにマリアさんがアパートがなんかで
コミュニティを開いてるとか言って「うちのところに来たら」とか言われて久住さんがマリアさんのそのコミュニティに行くんですよそのコミュニティっていうのはウガンダ人のコミュニティで実際はウガンダ人だけじゃなくて幅広く外国人とかアフリカの人達とかを呼んでちょっとしたパーティを開いたりとかあと色々喋ったりとか社会的な活動をしたりとかするっていうコミュニティがあるんですよ主人公はそこに行って
色んなことをするっていう話に
今度なっていくんだけどっていう話ねこれは僕の感想になるんですけどこの小説で1つ謎が僕はあると思ってて主人公の久住さんは 実は本当に
ミサキなんじゃないかっていう話ね本当として読んだ時に
めちゃくちゃ最後
感動できるんだよねというのは まず久住さんは(自分で)
ミサキだミサキだって言ってるのとあと久住さんの下の名前がわからない久住さんは名字は「久住」って言うんだけど下の名前は マリアさんに
聞かれても教えないんですね少なくとも文章中には出てこない1つヒントがあってウガンダのコミュニティに行った時に「私の下の名前は蛇に関係するんだよ」
っていうシーンがあるんですねこの蛇っていうのが これ「ミサキ」だったら「ミ=巳」なので「蛇」になるわけですね普通「ミサキ」って山に甲って書く岬を思いつくしこの作中の中でも海がかなりテーマになっててその岬もよくよく出てくるんだけど別にこの作中でサトウさんの娘の
ミサキは片仮名で書かれるので本当の漢字は 例えば
蛇の己が付くかもしれないし意味的にもそういう意味なのかもしれないからこれミサキと蛇っていうのは
繋がるんですね ギリギリねもう1個ね これ超面白いなって思ったのはこの主人公の久住さんの年齢が
わからないっていうところなんだよね主人公の久住さんって年齢不詳なんですよ作中に多分出てきてなくてだから若いかもしれないし意外と40ぐらいの可能性もあるわけねサトウさんは八十何歳っていう記載があるんでそれの娘さんだったら50ぐらいの可能性だってあるわけねだから それは当てはめようと思えば当てはめれるんですねもう1個は久住さんの過去話がほぼ出てこないんですね1回だけ 小学校の時に掃除が好きであと友達がいなかったみたいな話あるんだけどそれ以降の思春期・青年期辺りのその辺りの過去話が一切出てこないのこれ 純文学には珍しいでしょ年齢不詳だし 過去の1番感情がピークの
時代の話って書かれてないからだから これ 久住さんの正体は
ほとんどわかんないまま進んでいくんだよね久住さんに意外と感情移入できるかっていったら久住さんのバックボーンが分からないから分かんないわけよこの久住さんがミサキだと仮定すると作中にずっと海の話が出てくるんですねサトウさんが
ミサキを身篭っていた時に
岬の方に行くんですよ岬っていうか突堤みたいなところに行ってそれはどういうことかって言うとサトウさんの旦那さんが漁師をやってたとある日 海がめちゃくちゃ荒れてたとその時に漁師で船で行っててそこから多分 帰ってきてないっぽいんだよねそこで多分 漁師の旦那さんは死んだっぽいですよねその時のタイミングでサトウさんのもちろん若かりし頃にミサキを妊娠してて海の様子を見に海の突堤のところまで行って海を見るとその時の海は岸に近いところは全然穏やかだったとそういうシーンをサトウさんがよく言ってるとこのシーンが何回も出ていくんですねもしミサキだと考えたらサトウさんのお腹の中にミサキ=自分がいたわけでミサキとサトウさんはずっと喧嘩してると 現在ねだけど その時だけは一体感があったというかそこが唯一の作中で現われる
仲の良かったシーンだと思うんですね主人公もそれを求めているし
サトウさんもそれを求めてるわけですねお互いに多分仲直りはしたいと
もちろん考えてるわけだからそのシーンを求めるわけですよまず冒頭に偽物のバス停が出てくるっていうところがあってそれを読んだ時に 僕 最初「あ これは本物のバス停が出てくるな」って思うわけこれは小説の読み方としての基本だと思うけど偽物とか出てきた場合 絶対 本物に繋がるわけで最終的に本物のバスが出てくるから最後の本物のバス停のところで
「匂い」の話があるんだよねその直前ぐらいのシーンにサトウさんに「今何がしたいか」って
主人公が聞くシーンがあるんですよそしたらサトウさんが「海が見たい」って言うんですねこの海が見たいっていうのは もちろんさっきの嵐の日の身篭ってる時に
サトウさんが海に行ったシーンに
もちろん繋がってくるんだけどその時に主人公と あとマリアさんが2人でじゃあ海を見せに行ってあげようよって言うんだけどその作戦がちょっと失敗しちゃって最後のシーンに繋がって バスのシーンなんだよねバスのシーンで主人公がサトウさんと一緒にバスに乗って2人横に並んで バス出発っていうシーンがあるんだけどその時に前に座ってる親子みたいなのがいてその子供が「なんか変な匂いがする」って言うんですよ何だこれって言ってお母さんもそうねとかって言うんだけど男の子が「でもこの匂いに会ったことがある」というわけそれを見て主人公がニヤって笑うみたいなシーンがあるからその匂いの元は主人公なんでしょうよ何の匂いかは最後までわかんないんだけどこれは直前のシーンから考えると
「海の匂い」と考えられるわけですね海の匂いっていうことは 多分 主人公がその前に1人で海に行って 足とか僕が想像したのは全身ズバーンっって海に投げ出して全身 海の水だらけでバスに乗ってるのかなと思ってさすがに注意されそうだけどだから主人公から多分 海の匂いがするんですよその匂いをサトウさんに嗅がせたかったとサトウさんは海が見たいねって言ってるんだから海を見せにあげたかったっていう主人公はその匂いだけでも海の匂いを嗅がせてあげたっていう最後のオチなんだけどこれはもちろんミサキとしてだろうね だからこの作中では海っていうのはサトウさんとミサキの2人の身篭っていた時のシーンを表しているのでつまり海=母娘なんだよね母からすると娘を思い出す娘からすると母を思い出すっていう構図になっているので最後 めちゃくちゃ綺麗な感じで終わるんですね1つ ウガンダの話がどう繋がるか
っていうところもあるんだけどウガンダは名前の話と絡んでくるだろうね久住さんが下の名前が明かされないんだけどウガンダのコミュニティでウガンダの
民族的な名前を決めましょう
とかいう話が入ってきてウガンダでは名前っていうのは2つあって1つは親が子どもにつける名前ねこれ 日本でもある名前の付け方だけどもう1個は 民族ごとに民族ネームみたいのがあってそれを自分の名前に付けるっていう方法があって主人公はウガンダのコミュニティに入るんでそのコミュニティのちょっと偉いさんから久住さん その部族の名前を決めてくださいよって言われて主人公は「海」って名付けるんだよね海の生き物たちとかを
それぞれのメンバーがつける
ことができるんだけどこの小説って言ってしまえば「名前をめぐる物語」もう1個は「名前を取り戻す物語」
って言ってもいいわけですねだから久住さんは「ミサキ」
って名前を取り戻すって考えた時に母-娘間の関係の復活ね仲良くなりましたっていうところに繋がってくるのでこれ かなり 色んなことが繋がってる色んなものが想像できる物語なんだよねだから これ かなり芥川賞っぽい
だから僕は この「海岸通り」は芥川賞を取ってもおかしくないと思います僕の中では
とてもとても面白い小説だった
ということでございますねそんな感じで僕は候補作全てに点数をつけていますけどこの「海岸通り」は97点でございますめちゃくちゃ僕好みだったと思いますね坂崎かおるさんの小説を僕は初めて読みましたねよかったなと思った『嘘つき姫』っていう河出書房新社から
既に出ている短編集があるんでそっちもまた近いうち読もうかなと思っておりますねそんな感じでございます芥川賞候補は残り2つ 直木賞候補は残り1つなんで あと3つとプラスアルファ予想動画を出したいんで
あと4つ動画を出そうと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#970「芥川賞候補②松永K三蔵「バリ山行」の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 芥川賞候補が発表されましたが今回 紹介するのは こちらでございますねこちらは群像の3月号になりますがこの中に松永K三蔵
「バリ山行」
群像 3月号早速やっていきましょうあらすじまず主人公が波多っていう男でまだ若くて20代後半ぐらいかなと思いますけどその波多は今 新田テック建装という会社に勤めていてそこは建築とかの修繕工事を
やってる会社なんですけど最初 そこの同僚から「山登り行かない?」って言われて波多は「行ってみるか」と思って行くわけですね関西圏の低い山を中心に登山部が色んな山に行って登るっていう活動があってそれ 定期的に行われるから主人公も行くんですね主人公も登山にハマっちゃって装備とか山登りグッズも買い漁るんですよ波多には奥さんがいて娘は1歳とかその辺で奥さんには
「また山登りのグッズを買って」って
ちょっと怒られたりするんだよねある日 また登山部の活動があるって言ってその後に藤木常務っていう人がいてその人はもう退任するって言って会社の中でも偉いさんなんだけど年なんで辞めちゃうっていうことで飲み会・お別れ会をしましょうみたいになってそれは登山部の活動の後にお店に行くっていうことでそこに今まで来てなかった
妻鹿(めが)さんっていう人が
来るんだよねこの妻鹿さんが第2の主人公というか波多くんと妻鹿さんの交流の話になってくるんだけど妻鹿さんは普段はあんまり会社の中で
人と交流をあまりしないんですね飲み会とかもほんまに来ないぐらいのレベルでだけど職人気質っていうか1人で色々仕事したりとか 仕事の実力はある人なんですね妻鹿さんは実は山登りが以前から趣味で主人公とかも
「妻鹿さん山登ってるんですね」
とか言って 聞くんだけど妻鹿さんは1人が好きと 基本的に1人で山登るのが好きでさらに「バリ」っていう独特の方法で山を登ってると「バリ」っていうのはバリエーションの略で登山って登山ルートがあるわけですね舗装された道とか
人が通れるようになってる道
っていうのがあるんだけどバリっていうのは そういった通常の登山ルートとは違う藪とか草っぱらのところを降りたり登ったりするっていう下手したら全然死ぬレベルの危ないルートがバリなんですよ妻鹿さんはそのバリがめちゃくちゃ好きなんですよねその藤木常務のお別れ会をした後に今度 その会社が方向転換して経営が変わっていってそこの社長が2代目なんだけど初代が作っていったちっちゃな企業とかとも もちろん契約していってチョビチョビとお金を稼ぐ手法をやってたんだけどめちゃくちゃデカいアーヴィンっていう会社があってそこの下請けをするっていうことに変わったんですねアーヴィンは確かにめちゃくちゃデカい企業なんだけどアーヴィンも実はよくよく見ていくとそんなに経営がうまくいってないらしいとだから その下請けを中心にしようとしてるのにあんまり仕事が回ってこなくて方向転換は失敗だったんじゃないかって言って結構な登場人物が出てくるんだけどね会社の同僚とか先輩とかが大量に出てくるんだけど「いやこれじゃウチもヤベエんじゃねえか」ってなって「クビとか切られるかもよ」ってなるわけよその時に 主人公が妻鹿さんと
ちょっとした交流みたいななった後に妻鹿さんに「バリ教えてください」って主人公が聞くわけよ最初は妻鹿さんは断ってたわけね「バリっていうのは1人がいいんだよ」
って言って断るんだけど何回かアプローチしたら「よっしゃ波多くん バリ行こうか」とか言って向こうから誘ってくれて主人公と妻鹿さんの2人でバリに行く
っていう話なんだけどって話ねこれは僕の感想になりますけどこの小説ってスタンダードな感じするんだよね逆に他の候補作が結構 変な技ばかり今回 使ってくるんで飛び道具みたいながめっちゃ多いのよでも この「バリ山行」はスタンダードな感じがして逆にそこが好感を持てる感じはあった言ってしまえば この小説って
会社編と山編に分けられるわけよこれが日常と非日常になるわけですねこれは明らか対比的で波多くんが言うのは妻鹿さんとバリに登ってた時に結構 危ないルートを進むんで転んだりとかホント死にかけたりするレベルの
危ない状況に陥るんですね波多くんが逆ギレっていうか 妻鹿さんに「死んだら意味ないじゃないですか」みたいな言って「これは遊びなんですよ」「山っていうのは遊びなんですよ」って言うんだけどこれ 妻鹿さんは多分そうは思ってなくて波多くんの考えで言えば
(山は)人との交流する場とこれは首を切られないために
やってるところもあるんだよねだから意外と波多くんからしても実は(山は)遊びというよりかは
(仕事と)陸続きではあると僕は思うんだけどだけど妻鹿さんは多分そう思ってなくて「これが本物だろう」って言って妻鹿さんは言うわけ「この危険さは本物だよ」って言って「これが楽しいんだよ」みたいなこと言うわけよ波多くんと妻鹿さんは最初の方はかなり対比的っていうか妻鹿さんは山を登るの1人が好きって言ってるんだけど1人で行くことで色んなことを考えたりとか大自然を1人で味わうことが贅沢だろうとか言って山の中でコーヒーを作って飲むことに
かなりの喜びを覚えてるわけねあと妻鹿さんが言うにはバリっていうのはルートが最初からあるわけじゃないと行けるかどうかがバリなんだと行けたらそこがバリなんだということを言うんだよね誰かが切り開いてくれた道を我々は進んで安心安全を確保して遊びとして山に登るわけなんだけど妻鹿さんは行けるかどうかを試してるわけですよね これね失敗したら死ぬ可能性あるからめっちゃ危ないんだけどある種の先駆者というかパイオニアっていうかそこは自分と向き合ってるっていうか自分の実力をぶつけてるっていうかそういうことを妻鹿さんはやってるわけよ後半になると波多くんも気づいて「妻鹿さんもバリに行ってる時って不安を
感じてるのかな」みたいなを思う時があるんですねもちろん これ 感じてるだろうよ妻鹿さんってマイペースにもちろん行くんだけど色んな不安って妻鹿さんだって持ってるし2人でバリに登ってる時に色々質問するんだよね波多くんが かなり妻鹿さんに質問するんだけど妻鹿さんは答えなくて「行こっか」とか言って質問を全く無視して「山登ろうぜ」みたいなこと言うわけよそれは完全に無視してるわけじゃなくて妻鹿さんも妻鹿さんでわかってるんだよね妻鹿さんももちろん考えてはいるんだよねバリって多分違うことを考えると
足を滑らせて死ぬとか平気で
あるようなことだからある種 現実逃避でもあるし現実とも向き合ってると思うんだよねこの現実っていうのももちろん 山のことも言ってるし
生活のことも言ってると思うんだよね妻鹿さんからすると どっちも同じものだって多分考えてるつまり日常と非日常を分けながらも分けてないっていうのが妻鹿さんだと思うんだよねある種の陸続きで考えてるっていうかむしろ山の方が危ないまでは考えてるとは思うんだけど妻鹿さん的に言うと会社で例えばクビになっても別に死ぬわけじゃないけど山で失敗したら死ぬ可能性があるんでどちらかというと山の方が超危ないんで波多くんは どちらかというと
人の目をかなり気にしてるんだよねクビにならないように上司とかの顔色を窺ったりとかあと奥さんの顔色を窺ったりとかはしてるんでだから最後 主人公は
その妻鹿さんの境地に達する
っていう話ではあるんだろうね細かいところは言わないけど主人公は
「妻鹿さんのようになりたい」
っていう気持ちになるわけねだから妻鹿さんは変な格好して山を歩いてるんだけどその格好を求めたりもするわけねだから これって よくある話で今村夏子『むらさきのスカートの女』とかも似てるわけねもしくは ちょっと違うかもしれないけど又吉直樹の『火花』とかああいう2人の関係性ね師匠・弟子まではいかないかもしれないけどそういう関係性が「バリ山行」にはあるわけですね候補作には全て点数をつけていますがこの「バリ山行」は95点ですね個人的にはとても良かったですよ松永K三蔵の小説はこれが初めて
だったんですね(僕が読むのは)っていうか単行本化が今度されるんだけど(7月29日)松永K三蔵さんの1冊目になるわけだからね妻鹿さんのキャラクターがとにかく
良かったっていうことだろうね妻鹿さんは変わり者なんだけど誰もが もしかして憧れるような
そういう感じのキャラクター作りだったね僕も妻鹿さんみたいになりたいなって本当に思いましたねそんな感じで芥川賞候補作は2作目ということで残り3つと あと直木賞候補1つあるんであと4つ動画を出していこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#969「芥川賞候補①尾崎世界観「転の声」の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 芥川賞の候補が発表されましたけど今回はこちらでございますねこちらは文學界の6月号なんですけど この中に尾崎世界観
「転の声」
文學界 6月号早速やっていきましょうあらすじ主人公が
最近 地上波に出た「GiCCHO」
っていうバンドがあるんですねそれのボーカルの「以内右手」っていう
変な名前の人が主人公なんですねこの人はちょっと自意識が高くていわゆる ずっとエゴサーチをやってるんですね以内右手には1つ悩みがあってボーカルなんだけれど
声が詰まって うまく
歌が歌えないんですねそれが さらに自分でめっちゃ気になって声が出てないことを さらにエゴサーチしてで「腹立つ」みたいなのを
永遠に繰り返してるんですよそれと同時に世の中では転売ヤーが認められる世の中になってきてというのも得ノ瀬券っていう通称「エセケン」って呼ばれる男が【Rolling→Ticket】っていう会社・サイトを仕上げていわゆる転売なんだけどローリングチケットと契約したアーティストにはプレミアがついたチケットが売れた場合そのグループにも利益を還元できるシステムを作ったわけよめちゃくちゃエセケン自体がテレビに出まくって「転売っていうものはいいもんなんですよ」って言って転売の評価をガラリと変えていった
っていう世界ではあるんですよGiCCHOも最初ローリングチケットと契約してないし以内右手自体はツイッターとかで「転売屋からチケットを
買わないでください」
って言ってるんだけどだけど以内右手は自意識が高いので自分たちのグループのチケットが値上げされててプレミアついて どんどん高くなっていることにかなり興奮っていうか喜びを覚えるんですねやってることで言ってることが矛盾してるわけ そもそもがGiCCHOはどんどんライブとか出ていって色々 活動していくんだけどライバルグループがいてLIVE IS MONEYっていう通称「ライマニ」っていうライバルバンドみたいなのがいて今めっちゃブイブイ言わせてるわけですよ途中から転売の話はあんまり関係なくなってきて無観客ライブの話になってくるんだよね世の中が転売でチケットがめっちゃ高騰していくっていうことになった時に例えば 最初の
ライマニのチケットなんか
30万円とかになるわけですよ30万円でライブのチケット買った時にいざ そのライブに行った時に普通のライブだったら面白くないじゃないですかせっかく30万円のライブを買ったのに通常のクオリティのライブだったら もったいないんでその人は逆に「行かない」っていう
選択肢を取る人も出てくるんですよそのライブに行かないことで30万円の価値を永遠に保存するっていうかライブに行かないからこそ無限の楽しみを得られるっていうアメリカでは なんと
無観客ライブを達成してる
アーティストっていうのがいてエセケンとかが「日本でもやるんだ」って言ってエセケンと なんと主人公の以内右手が ここが組み出して無観客ライブを一緒にしようよとか言うわけよだけど これ同時に LIVE IS MONEYも同タイミングで「俺たちも無観客ライブを達成するぞ」って言い出してここがバチバチにぶつかってきて同じ日に 2つのグループが無観客ライブをします
ってなった時に
世間がワーってなって「どうするどうする!」ってなって最終的に そのライブはどうなったのか
っていうのがオチっちゃオチなんだけどこれは僕の感想になるんですけどこの小説は問題作だと思いました今回の芥川賞・直木賞がそれぞれ5作品ずつあるんだけど直木賞の方は麻布競馬場
『令和元年の人生ゲーム』が
問題作だと思うんだよ芥川賞はこれだろうね尾崎世界観「転の声」が問題作だと思う問題作って別に面白くないとかそういうことじゃないよかなり評価が難しいっていうか変なんだよね めちゃくちゃ話がこれまず主人公・以内右手は自意識がめっちゃ高いわけしかも これ一人称で語られてるんで一人称で自意識高い系の主人公って読者とちょっと距離が近すぎるあんまり共感できるタイプの主人公じゃないと思うだから ちょっと偉そうに
「ファンたちはこれはこうでこうなんだけど
俺からしたらちょっとおかしいと思う」みたいなを地の文で書いたりするんですねだから ちょっと上から目線なんですよなんだけど 実は主人公も
それに振り回されてる人間だからツイッターでエゴサーチをずっとやってそれに一喜一憂してるってことは人々のことを批評したとしてもそれが 結局 自分に帰ってくるのでそこが滑稽な話ではあるんだよね そこが面白いあと登場人物が意外とそんなに多くなくて主人公が以内右手くんなんだけどグループの他のメンバーのことは一切出てこないんだよね多分 以内右手がリーダーなのかわかんないけど以内右手がローリングチケットと契約しようぜって言ったらもう そのまま次の瞬間には契約してたり他のメンバーが反対したりとか他のメンバーの気持ちとかほとんど一切出てこないからちょっと以内右手が中心的すぎるのよプラス エセケンが以内右手と
交流してくるんで 出てくるんだけどエセケンはエセケンで最初からちょっと胡散臭いまともな人物ってあんまり出てこないプラス 音楽評論家の
絵萌井さんっていう人も
出てくるんだけど実際に出てきて 会話とか
するわけじゃないからねただ僕はそこに重きを
置いてなくて(主人公に)もっと後半になると世の中がぶっ壊れていくっていう
ところの面白さがあるんだよね「論理の暴走系小説」だと僕は思うつまり設定の最初に「転売ヤー」の話を導入することでそれが どんどん暴走していって
無観客ライブに入っていくんだけど無観客ライブも なんかよくわかんないよね一応 作中で説明はあるんだけど絵萌井さんとかは途中で「それはもう音楽じゃねえだろ」みたいな「なぜ無観客が素晴らしいのか私にはわからん」
みたいなブログかなんかで表明するんだけど僕はどちらかというとそっちなのよねだから論理が暴走してて 最後
無茶苦茶になっていくんだよねこの面白さがあるのよそこをどう捉えるかっていうのが
この小説のキモっていうか評価のポイントだとは思うんだよあと音楽の裏側みたいのをずっと書いてるのは面白いライブに行って「地蔵」っていうライブとかだったらワーとか言って
ファンとかが応援したりとかするけど「地蔵」っていって全く何も動かないと地蔵がポツポツといると一体感がなくなってライブとしては面白くなくなっちゃうみたいなそういう解説っていうかあとライブをやった時に「かわいいー」とかそう言われるのが主人公はめっちゃ嫌で何をやっても「かわいい」と純粋な歌で勝負してても「かわいい」とか言われると それは打ち消されてしまうとあと手拍子を客がよく入れるんだけど手拍子を入れると こっちはこっちで 音楽 バンドのドラムとかギターとかの繊細な音楽をやってるのにそれが全部潰れてしまうと手拍子でうるさくなっちゃって全然聞こえないとっていうので苛立ってたりとかするっていうライブとか音楽とか現代だったらサブスクばっかりでCDとか売れないとかそういう話がふんだんに入れられてるんでこれ 読み物として面白いんだよねある種のお仕事小説・職業小説なんでバンドマンとはこういう生活やってますよっていうそこの読み物もあるんでという感じではあるんじゃないかなと思いますね候補作には全て点数をつけていまして今回の尾崎世界観「転の声」は93点ですね「転の声」っていうタイトルは
僕は素晴らしいと思うんだよね作中でローリングチケットっていう会社っていうのかなそれのサブの事業みたいなのがたくさんあってそのうちの1つで「ローリングボイス」っていうのがあってこれが直訳して「転の声」になるんだけどあと主人公が声が出ない声が詰まってうまく歌えないっていうのがずっと続くんですそれと もう1個ツイッターの声っていうのがあるんだね
まあ これファンの声っていうかねエゴサーチするんで作中にめちゃくちゃツイッターの文面が出てくるんですねそれの声っていうのもあるのよだから「声」っていうのがテーマになっているんでそれに「転がされてる」っていう主人公とか もしくは世の中を
表しているタイトルだと思うからこれ めっちゃ秀逸だと思うんだよねあと尾崎世界観って前の小説「母影」っていうのがあって芥川賞候補1回目になったやつがあるんだけどこれは全然違う作風で主人公が子供でお母さんとの関係を書いたやつだったんだけどこの「転の声」は どちらかと言うと その前の尾崎世界観のデビューの小説の「祐介」にめっちゃ似てる「祐介」にもエセケンみたいなちょっと怪しい胡散臭い人物が出てきたりとかそもそも主人公がバンドマンなんだよねだから言ってしまえば「祐介」の進化系がこの「転の声」になるとは僕は思ってはいますけどねそんな感じでございます今回で芥川賞候補作 1作品目ということで残り4つとあと直木賞の最後の作品を飛ばしてやってきたんであと5つ候補作をまた動画に出そうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#968「直木賞候補④柚木麻子『あいにくあんたのためじゃない』の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 直木賞の候補が発表されましたけど今回 紹介するのはこちらになってますねこちらは柚木麻子
『あいにくあんたのためじゃない』
新潮社 2024この小説 めちゃくちゃ良かったですよ僕 何回も泣いちゃいましたね早速やっていきましょうあらすじこの小説は短編集でして6つの短編が入っていますね1つ目「めんや 評論家おことわり」あるラーメン屋さんがあってめちゃくちゃうまいラーメン屋さんがあって主人公があるラーメンブロガーみたいな人でその人はちょっと辛口で色々ラーメンを評論してるんですよそれで そこのめっちゃ
うまいラーメン屋さんから
出禁を食らってるんですだけど そのお店のことを語らないとラーメン評論の中でやっていけないぐらいめっちゃデカいラーメン屋になってるからなんとかして黙ってでもそこのラーメンに行こうかなって考えてる時にラーメン屋さんから出禁を解除しますよ いうのになって主人公がそのラーメン屋さんに行くと…っていう話2つ目「BAKESHOP MIREY'S」主人公が女の人で今は転勤で 東北の町に来てるんですねそこの商店街があってその商店街にうどん屋さんがあるんですよそこのアルバイトしてる女の子が未怜っていう女の子がいてその子がイギリスのお菓子とかケーキとかも好きなんですねいつか自分でベイクショップっていういわゆるパン屋・ケーキ屋を作りたいと思ってるんだよね主人公は未怜と関わっていく中で夢を応援したいって気持ちがあるんだけど未怜は口だけは言うんだけど 実際の行動に移さないっていうか 1回もケーキとかを
完成させたことがないんですよだけど こだわりみたいなのは強いからデカいオーブンが欲しいって言うわけよオーブンさえあれば 私は
パンもケーキも作れるのよ
って言うから主人公がそのプレゼントとして何万円もするオーブンを送ると…
っていう話になってくるんだね3つ目「トリアージ2020」主人公は女の人で 今 妊娠してるんですね主人公には趣味があって「トリアージ」っていう医療ドラマが
めっちゃ好きっていうのがあるのよその「トリアージ」のことを
ツイッターで私好きとか言ったらある人が「私も好きなの」って言ってトリアージ友達みたいなのができるんだよね主人公が妊娠していて
1人ではなかなか動きづらいとそれをその友達に相談するとその友達のお母さんがいてそのお母さんが主人公の家の近くに住んでるからお母さんを使いにやって食べ物を送ったりとか雑談するようにお母さんをやるよっていうわけよ主人公も友達のお母さんが毎日家に来て色々お世話になっててめっちゃ助かるわけよそれでお母さんとも仲良くなっていくんだけど実は2人には…みたいな話になってくるっていう4つ目「パティオ8」これはあるマンションというかアパートみたいな話でそのアパートは真ん中にデカい庭があるとそこで子供たちを遊ばせることができるのよ大体 住人はお母さんがめちゃくちゃ多くて子供たちがいるわけね それぞれの家族にだけど これもコロナ禍で公園とかが封鎖されてたり遊具が使えなくなってたりとかした時の話なんで子供たちは遊びたがるんでこのアパートには
パティオ(庭)があるから
そこで遊ばせてあげる住人の1人に ある男の人がいてネットで取引先とめっちゃ喋ってるらしいとでも その男曰く庭で子供たちが遊んでるとうるさいとだからお前たち庭で遊ぶなって言ってめっちゃ怒るわけだけど その男の言うことを
なんで聞かなあかんねんとか言ってそのお母さんたちは怒ってるわけねそこで お母さんたちが結集してその男の取引を先にこっちが取引してやろう
とかいう よく分かんないことになってきてみんなでどうやってそれするか…みたいな話なんだよ5つ目「商店街マダムショップは何故潰れないのか?」主人公がアラサーぐらいの子がいて友達がいるんだけど友達は1個世代が下で20代ぐらいなんだよねでも その2人で地元の喫茶店でお茶してるんだけどその地元の商店街ではマダムショップっていっておばちゃんみたいな人たちが買うようなちょっと年齢層が高めのファッションとかアクセサリーとか売ってて しかも
1個1個の単価がめちゃくちゃ高いとそこのマダムショップはあんまりお客さんも入ってないのに20年くらいあるとどうやって儲けてるんだろう
ことを2人で喋ってるんだけどそれで どんどん調べていくと
なんと そのマダムショップには
1つの真実がありました みたいな話で6つ目「スター誕生」主人公は昔めっちゃデカい
アイドルグループにいた
男の人なんだけど昼番組の司会ももらってるんだけどあんまり評価が高くなくてこのまんまだと芸能界から
消えてしまうんじゃないかっていう
不安を抱いてるんですねその時にYouTubeとか
ネットでめちゃくちゃ流行った
動画っていうのがあって登録者数1万人ぐらいのおじさんみたいな人がファミレスで飯を食べるだけの
動画みたいなを流してたんだけど店の中なんで普通に一般人の人とかも
後ろのカメラに映っちゃうわけねそれで後ろに お母さんと子供がいるんだけどそのお母さんが
「私たちは映ってしまったでしょ」
って言って「消しなさい」って言うわけねおじさんの方は それに対して喧嘩越しにあとで編集してモザイクかけるから確認してくれって言ってメールアドレスを教えてくれって言うんだけど女の人は「なんで私がそんなこと
しなきゃいけないのよ」って言ってめっちゃ喋るのがラップ口調みたいなめっちゃ舌が回って上手いトークっていうか韻を踏んでたりとかしてそれがなぜかネットでめっちゃ流行って主人公はこのお母さんを利用しようとか言って一般人なんだけど 隠れたスターだから芸能界に呼んできて自分の番組とかに出して色々喋ったりしたら盛り上がるぞ とか思って利用しようとしてるんだよねそのお母さんを探していく…っていう話なんだけど以上 この6作品が
『あいにくあんたのためじゃない』
のあらすじなんですけどこれは僕の感想になるんですけどこの小説はまず素晴らしいと思うこの小説 何回も泣いた何が良いかっていうと 多いのは女性が虐げられてるっていうパターン多いんですよ最初のラーメンの話も女性がラーメン屋の主人だからっていうので男が偉そうに評論するみたいな形だし最後の芸能界のお母さん利用するみたいなのもそれに近い途中のアパートの話もお母さんの地位っていうのがめちゃくちゃ低く設定されてるのよだけど それで終わらなくてこの小説って女性たちが立ち上がって男とか もしくは環境とかに働きかけて突破していくっていう話なんだよねだからスカッとするのよこの小説って帯もめちゃくちゃ秀逸で例えば この下に橋本愛っていう人が「うちらの代わりにヤキ入れてくれる
頼もしい姉貴小説」って書いてるのこの後ろにも書いてて「差別、偏見、思い込み… 他人に
貼られたラベルはもういらない自分で自分を取り返せ」
って書いてるの下に「この息苦しいこの世を
生き抜く勇気がムクムクと湧いてくる全6話からなる
強炭酸エナドリ短篇集」
って書いてるの僕は政治とか世の中のことってあんまり知らないけどここ最近 本当に息苦しい世の中だとは思うよだけど その息苦しい世の中で終わらないで頑張って生きていこうよ っていう応援の話なんだよね本当に僕なんか 生きるの下手だから 不器用だからねもう全然 上手く生きられないんだけどこういう小説を読むと本当に明日頑張ろうって思えるわけよこういう小説を僕は待ってたなあこういうのこそ直木賞に本当に入ってほしいこの時代に生まれた素晴らしい小説だと僕は思うなただ1つ 言われそうなのは女性が主人公が多くて男が結構ダメ男みたいなのが まあまあ出てくるのよ男女差で評価は分かれそうな気もする優しい世界ではない この世界を
いかに優しくしていくかみたいな
話でもあるからさ読んでてよかったなって本当に思いましたね毎回 候補作に点数をつけていますけど『あいにくあんたのためじゃない』は99点ですね素晴らしいと思った これ柚木麻子さんは直木賞候補作 6回目なのでまあ取るでしょうと僕の中では思ってますけどねそんな感じで今回 直木賞候補4冊目になりましたけど残り1つ 直木賞はあり芥川賞候補はあと5つありますからこの6つの候補作の動画をこれからもどんどん出していこうかと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#967「直木賞候補③一穂ミチ『ツミデミック』の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 直木賞の候補作が発表されましたが今回はこちらでございますこちらは一穂ミチ
『ツミデミック』
光文社 2023この小説は短編集で幅広く色んなテーマを扱っていて面白かったと思います早速やっていきましょうあらすじこちらは短編集で 6編の小説が入っておりますこれ タイトルが『ツミデミック』ってあるんだけど「ツミデミック」っていう短編はなくてこの小説の総合的なタイトルということになってますねそして 1つ 特徴的なのは全てにコロナ禍が関わってるっていうことですね「ツミデミック」ってのは多分 造語で罪とパンデミックを掛け合わせてますからコロナ禍に振り回される人々が
どうなったか みたいな短編集1つ目「違う羽の鳥」これは主人公が男の人で飲み屋さんのキャッチをしてる男がいてそいつが ある女の人と会うんですよねその人の名前を聞くと なんとその男の人の故郷があってその故郷で めちゃくちゃ昔に電車に自ら突っ込んで自殺したっていう
女性の名前と一緒だったんですよね(その女性が)実は死者なのか死者じゃないのか
っていうのを見つけていくみたいな話なんだけどね2つ目「ロマンス☆」これはちょっと問題作っぽいんだけどある主婦がいて夫がちょっとダメ男みたいな感じでちっちゃな娘もいるんだけどその主婦の人は たまたま街で
イケメンを見つけるわけですよそのイケメンはUberEatsみたいのをやってるっぽくて主人公がイケメンに会いたいと別に不倫とかしたいわけじゃなくてイケメンの顔をただ見てみたいっていうのでUberEatsを毎日のように頼んでそのイケメンの顔をガチャるっていう話なんだけどこのオチが大変なオチだったっていう話なんだけどね3つ目「憐光」これは15年前に町に洪水があったんですねその洪水で流されて亡くなって
しまった女の子がいるんだけれどその女の子が急に15年ぶりに 幽霊となって この世に現れるわけよ15年経ってるからみんなスマホをいじってて なんだあれとか思ったりとかあとコロナ禍なんで
みんなマスクをしていて
不思議に思うとかがあるんだけどその女の子が もう15年経ってるから友達とかがいて みんな30歳とかになってたり学校の先生も出てくるんだけどその人たちについていくわけね自分は幽霊だから相手から認知されないんだけどそうすると自分の死の原因っていうか15年前に自分の身に何があったか
っていうのが分かってくるみたいな話ですねあと個人的に好きなのは
4つ目「特別縁故者」これは今 仕事してない男がいて奥さんと息子がいるんだけど主人公はコロナ禍の色々があってクビになっちゃうわけね料理が好きで 調理師の免許を持ってるんだけどなかなか仕事に行けないとその時に 息子が 近所におじいさんが住んでてそこの家にフラフラって入っちゃってでも そこと仲良くなるんだよねおじいちゃんが
めっちゃ昔の1万円札を
子供にあげるんですよ 小遣いおじいさんは
子供と喋れて嬉しかった
みたいな感じであげるんだけどそれを見つけた主人公の男が息子に聞きまくって家にめっちゃ その1万円札があるらしいって聞いてそのおじいさんに接触して大量の1万円札を得ることができないか
って考えていくって話なんだけど5つ目「祝福の歌」これも結構 僕は好きだったんだけどこれもお父さんが主人公でお母さんがいてちょっと大きな娘がいるわけよその娘が高校生だったと思うけど妊娠しちゃってて娘は産みたいって言うわけねだけど高校生が妊娠してまだ若すぎて
育てられないんじゃないかって
お父さんは反対するわけですその時に 主人公にも もちろんお母さんがいてお母さんも高齢になってるからね介護っていうか 様子を見に行ったりとかしてたらひょんなことで自分の出生の秘密がわかるみたいな話ですね6つ目「さざなみドライブ」これはみんなで集団自殺しようっていう話なんだけどこれが1番テーマらしいテーマっていう感じするねTwitterで繋がってるグループがあって6人いたと思うけどその6人で 人生が辛すぎるんで
みんなで自殺しましょうって
いうことになってそのうちの1人が車を持ってきて練炭自殺しましょうか何かでみんな その車に乗ってドライブ行くっていう話なんだけどそのグループで1つテーマがあってコロナによって 人生が
ぐちゃぐちゃにされた人たち
っていう人たちを集めてるのよねそれで1人ずつ私はこういう理由で コロナによって
人生がおかしくなってしまいましたともう生きていけませんっていうので
自己紹介していくっていう話なんだけど以上 この6篇の短編集が
『ツミデミック』っていう話
なんだけどこれは僕の感想になりますけどこの6篇の小説はコロナっていうので繋がりはあるんだけどもちろん1個1個は独立してますこれ 前の
一穂ミチ『スモールワールズ』
でもそうだったと思うけど結構 オチ方がバラバラなんだよねそれが良いか悪いかは 僕にはちょっとわからないけどつまり
ハッピーエンドで終わるのと
バッドエンドで終わるとか色々 終わり方があるのよだから 読んでてこれはハッピーか これはバッドか
っていうのはわからないから(最後まで)そこが逆に面白いかもしれないねそれこそ「ガチャ引く」って言ったら怒られるけど出だしはホラーっぽいなみたいな もあるのよ出だしがホラーっぽいなって思ってたら
最後 ヒューマン的に感動で終わるとかそういうことも結構してくるんであとコロナもそうだけど例えば ガチャとか あと家出少女とかモチーフっていうのかな使われてる道具っていうかそういうのは最近のやつも多いですね全ての小説に言えるかもしれないけどこの小説って悪い人は出てくるよね良い人と悪い人が顕著に描かれてる短編だからね長編ぐらいの小説だったら1人の人物の中で 良い部分もあれば 悪い部分もあるとそこが人間の厚さっていうか人間味みたいなところだろうけど短編を書く時ってはっきりとその人の性格みたいのを顕著にした方がいいんで悪い人とか良い人とかで決めておいてそれは変わらないみたいな方がはっきりとはしてるんだけど結構 悪い人は悪いのよガチャの「ロマンス☆」って話の旦那さんとかも悪い人っていうか自分のことしか考えてないみたいな人で主人公は奥さんで 娘がいるんだけど結構 積んでるのよね 人生がそれはかなり辛いのよ個人的に「ロマンス☆」はちょっと問題作かな終わり方は辛い感じになっちゃってそれは でも仕方ない状況だからね打破できない状況に主人公がいたっていうのはわかる単に旦那が悪いみたいな話なんだけどちょっと辛かったなまあ しかし感動話も全然あるんで僕はちょっと良かったなと思いましたよ全部がホラーとか全部が感動ではないところのガチャの感じがこの小説の特徴なのかなっていう感じはしたかなと思いますそんな感じで 毎回 僕は点数をつけてますけれどもこの『ツミデミック』は80点かな僕は一穂ミチさんは『スモールワールズ』と
『光のとこにいてね』を読んだことあるんですけどこの『ツミデミック』は完成度は高いと思うな結構 シリアスな部分がまあまああるから大人の読み物としては面白いんじゃないかと思うし全然 高校生とか そういう若い人でも全然 楽しめる作品かなと思いますねただ これはまた別の動画でも言いますけど個人的にコロナ禍を取り扱っている短編集で今回の直木賞候補で言えば柚木麻子『あいにくあんたのためじゃない』もまあ ちょっとコンセプトが似てるんだよねあれもコロナ禍が出てくる短編集だったんです個人的には
『あいにくあんたのためじゃない』も
もう読んでるんですけどあっちの方が良かったんですよねこれは賞レースなんで普段だったら
あんまりどっちが上とかどっちが下とかは
僕はあまり決めたくない人間なんだけど今回は直木賞
っていう賞の中の話だから
仕方ないと思いますがでも全然 面白かった作品ではありますねそんな感じで
今回 直木賞候補3冊目
ということで残り2冊と あと芥川賞候補5個ありますので残り7つ 読んでいこうかなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#966「直木賞候補②岩井圭也『われは熊楠』の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 直木賞の候補が発表されましたが今回はこちらでございます岩井圭也
『われは熊楠』
文藝春秋 2024僕 南方熊楠ってあんまり知らなかったんだけどこれを読んで めっちゃ勉強できた 超面白かったです早速やっていきましょうあらすじこちらは南方熊楠っていう人の時代小説なんですけど南方熊楠っていうのは明治時代以降から
昭和に生きた博物学者っていうのかな植物とかキノコとか そういうのを研究しててさらに それ以外の星座の話とか あと性についてとか結構 幅広くやってて「知の巨人」と呼ばれたり当時の日本では1番頭が良かったとか
そこまで言われたりする人らしいんですよね南方熊楠って和歌山県生まれでお父さんが金物屋・両替屋っていうか幅広く色々商売をやってたらしいんですよね結構 お金持ちの家に生まれて兄弟も何人かいたんだけど1番上のお兄さんが結構やらかしてるお兄さんらしくてお金を浪費してしまうから継がせられないっていうわけよその次に熊楠がいるんだけど熊楠 まだ15歳の時ですよ 最初お父さんから「お前 店を継げ」って言われるんだけど熊楠は15歳の時に 近くに山があって山で植物を採集するのがめちゃくちゃ好きで学校の勉強とか全然できないっていうか もう興味がなくて試験とかほっぽり出して ずっと山に行ってるんですよね熊楠の頭の中に複数の声が聞こえるっていうので熊楠って後にも出てくるんだけど 癲癇の発作とか持ってたり熊楠は自分の声が複数 天使と悪魔みたいな感じで脳に直接 響いて めちゃくちゃ
うるさかったらしいんですね
この小説曰くお父さんは商売の人だから「お前 学問だけだったら食っていけないぞ」って言われて熊楠はどうするかって言うと「俺 大学行くわ」って言うわけよ当時の大学といえば東京大学しかなくてその後に勉強して東京大学の予備校みたいなに入るんだけど大学の試験を受けても受からなかったんですよねでも本人はもっともっと勉強したいとこの表紙にも書いてるけど「知ることこそが生きること」って言って南方熊楠は世界の全てを知りたいって思ってるんですよそれは自分を知ることとも言えて自分と世界を同時に知っていくっていう目的があるんですねそれを分かってくれる人も何人かいて例えば 学校の先生が同じく植物採集が好きな先生がいてその先生のところで色々やり方を教えてもらったりとかあと後輩っていうのかな 下級生に繁太郎っていう子と その弟の蕃次郎っていう子がいてこの2人からかなり慕われるんですよね繁太郎と蕃次郎は
お医者さんになりたいって
めっちゃ勉強してて2人の友情がどんどん出来ていくんですけどのちに熊楠って海外に行くんですよね日本では大学にはもう行けないってことになって海外に若い時から行っちゃってアメリカに行って その後 イギリスに行くんですよイギリスで色んな人と繋がりを持って最終的には「ネイチャー」っていう雑誌があってそのネイチャーに何本も論文を出す
ってことができたらしいんだよねその成果から イギリスで
めちゃくちゃでかい図書館に
入れる資格も与えられてそこで ずっと勉強するんだけど熊楠ね アホなのかどうか分かんないけど熊楠ね のちのち効いてくるのは脳味噌の問題があって発作みたいなのも起こっちゃうんだよねあと酒とかも飲んじゃって結構 人と喧嘩になったりとか逮捕されたりとかするぐらい暴れ尽くすんですよそれ イギリスでもそうなってせっかく無料で使える図書館の中で腹立って バーンって人を殴っちゃってそれで もう出禁を食らっちゃってそれでイギリスに居づらくなっちゃって日本に帰ってくるって話なんだよねその後は和歌山県でいわゆる在野の研究者になるんですよねつまり どこかの大学の教授とかになるんじゃなくていわゆる ずっと民間で1人で研究 ずっとしててでも色んなところに
論文を送ったりとかするっていう
生活に入っていくんだけど結婚とかもするのよ あと息子が
生まれたりとかするんだけどこれ 最初に出てきた
繁太郎と蕃次郎っていう
兄弟がいるんだけどこれ 途中でわかるのは熊楠がイギリスに行ってた時に結核で2人とも亡くなってしまうんですよねその2人は でもこの後も出てきてっていうのも この小説って熊楠の夢とか幻とかの描写が
めちゃくちゃあるんですねその中に繁太郎と蕃次郎とかもしくは他の死んだ人たちとかも結構 ドンドコ出てくるんですよね全て言っちゃうと
ネタバレになるんで
この辺ぐらいにしとくけど最終的に天皇陛下に直接 博物学っていうか
粘菌の研究で教えるっていう凄い仕事もするっていうことに
なっていくんだけど っていう話でめっちゃ面白かったですねこれは僕の感想になるんですけどこの小説って僕的にはいくつか特徴があると思ってて1個はあんまり人間関係のことって
そんなに言わないと思うんだよねつまり熊楠が主人公で熊楠1人の世界みたいなのが中心にあって周りの人たちは
そのちょっとしたサブ
みたいな感じな気がするのよというのも この小説って
330ページぐらいしかなくて僕は時代小説にしては短いなって思うんだよね結構 コンパクトに収まってるんだよねだから登場人物もまあまあ出てくるんだけど1人1人はそんなに深い繋がりではないんですね強いて言えば 家族の話は深いっちゃ深いかな弟との関係がのちのち響いてくる
っていう話は長く続くんですよあと熊楠が後に結婚して息子が生まれるんだけどここも結構シリアスになっていくんだよねこの小説って僕が最初に読んだ時
結構 軽いなって思ったんだよねストーリーもポンポンと進んでいって熊楠の葛藤みたいなが僕 そんなに書かれてないような気がするんだよね特に序盤は熊楠って研究・命っていうか勉強・命みたいなところあるからずっと勉強するのが好きなわけよだけど のちのち金の問題とか現実の問題が後半部分にめっちゃ来ちゃってそれで熊楠 病んでいったりとかするっていう話があるのよ後半 重たくなるんだけどでも他の登場人物とはあんまり深く関わらないんだよねだから僕は熊楠の精神世界みたいのを
かなり重要視している小説だと思うわけそれは悪いっていうわけじゃないよ結構 珍しいと思ったわけ時代小説って そこまで
精神世界みたいなのを多分
重要視しないと思うんだよねだけど熊楠だからね熊楠って結構そういうイメージもあるわ夢・幻とか ユング的な感じはちょっとしたこの小説ではないけど
結構マンダラ的な考え方に
行き着いたり仏教的な考え方に行き着くんですよねその辺 ユング的だと思う自分こそ世界なんだ 世界こそ自分なんだ みたいなかなり精神世界みたいな
エヴァンゲリオンみたいな世界に
多分 入っていくんですよ 熊楠それは1つ脳味噌の話もあるのかなと思うのよね熊楠って この小説でもあるけど自分が死んだのちに 自分の脳味噌を
どこかに保存しておいてくれって言って今でも東京大学かどこかに熊楠の脳味噌が保存されてるらしいのよこれ 結構 この小説っぽいんだよね脳味噌の中に色んな自分の知識とかが
ずっと詰まっているというわけなんだけどこれが ある種の精神世界であってこの脳味噌の内側が実は外界なのだと「世界を知れば自分が知れる」
ってのをよく熊楠は言うんだけどそれって
「内と外をなくしていく」
ってことだと思うんだよねだから脳味噌の内側には実は世界そのものがあるし世界そのものこそが自分なのだみたいなそういうことを
熊楠は発見していくっていうか
悟っていくみたいなところがあるからそこがめちゃくちゃ面白い小説だと思ったそんな感じで 僕は毎回
点数をつけてますけどこの『われは熊楠』は92点かな個人的には 南方熊楠の人生が分かった
っていうのがめちゃくちゃ良かったですねあと熊楠って変人なんだなって本当に思うよね一見ダメ男みたいな感じもちょっとあるのよやりたいこと=夢はしっかり持ってるんだけど現実適応能力が
あんまりないみたいな
そういうタイプなのかなとでも1人でやっていく力ってあるから結局 自分で勉強して論文をどんどん出していってその功績が膨れていって社会的立場に立てる人だったからこういう生き方したいなって本当に思う僕もあまり人間っていうものをあんまり好きじゃないし自分のやりたいことだけやっておきたい人間だから実際できないんだろうけど熊楠的な生き方は憧れますよねそんな感じで
今回で直木賞候補2冊目
となりましたが残り3冊 芥川賞候補は5作ありますからあと8作品
頑張っていこうかと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#965「直木賞候補①青崎有吾『地雷グリコ』の書評」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 第171回 直木賞の候補作が発表されましたがそのうちの1つですね こちらですねこちらは青崎有吾『地雷グリコ』
KADOKAWA 2023めっちゃ面白かったねこういうのが直木賞の候補になるってあんまりないんじゃないかとは思うんですけどね早速やっていきましょうあらすじこちらはゲーム小説みたいな感じで主人公が 高校生の
射守矢真兎(いもりや・まと)
っていう女の子なんですよ射守矢真兎は普段は結構のんびりしてるっていうかちょっと気だるい感じの人でだけど実はめっちゃ頭が良くてその真兎が色んなゲームに
巻き込まれていく
っていう話なんですよそのゲームがオリジナルのゲームでだけど ちょっと既存のゲームにプラスアルファでオリジナル要素が加わってるっていう結構 とっつきやすくはあると思うんですけどねまず最初に文化祭の話から始まって高校生ですからある高校の文化祭が今度あるとそれぞれのクラスの出し物があるんですけどそれぞれの出し物に沿って
適切な教室・場所とかがある
と思うんです例えば 屋上を使えるんですけど屋上で主人公たちの出し物はカレーを出したいとでもカレーって匂いがきついんで教室の中ではできないとだから屋上とか外とかじゃないといけないんだけど屋上の方が特別感があって
お客さんが来るんじゃないか
というので 屋上が取りたいだけど それとかぶって他のクラスが屋上を取りたいってなった時にそこでどうやって解決するかっていうとこの小説では「愚煙試合」という謎のゲームをして勝った方がそこの場所を取れるというルールがあるんですよ今回だったら その愚煙試合のゲームは「地雷グリコ」っていうゲームなんですね地雷グリコっていうのは「グ・リ・コ」っていうのあるじゃないですかジャンケンして勝った方が前に進んでいけるんだけどグーだったらグ・リ・コで3歩パーだったらパ・イ・ナ・ッ・プ・ルで6歩とかチョキだったらチ・ヨ・コ・レ・イ・トで
6歩進めるっていうのをやるんだけれどある神社の階段を使うんですけどそこが46段あって46段目まで行けた人が勝ちなんですけどそれぞれ お互いに事前にゲームの前に地雷を埋めることができる地雷っていうのは 別に踏んだら
爆発して怪我するとかじゃなくてゲーム上の設定なんで前から何段目に地雷をとりあえず埋めるとそこに相手が止まると相手を10歩下がらせることができて自分が止まると相手にその地雷の場所がバレてしまうと何か音が鳴って ここに
地雷が埋めてありますよ
っていう効果があるとそれが それぞれ3つ
地雷を埋めることができる
っていうゲームなんですよそういうゲームがあと4つ 合計5つあるんです途中で発覚するのは真兎ちゃんがいる高校と別の高校ではチップを使って そのチップで争って勝った人が何千万円とか何億円とかっていう賭ケグルイみたいなことが行われてる高校があるんですよね真兎ちゃんの中学校の頃の友達が その学校にいて昔になんか因縁があるらしいとその因縁を晴らすために主人公はその別の高校の子たちと
どんどん戦っていくみたいな
構図になっていくんですけれどこれがまた面白いんだよね言ってしまえば
カイジとかライアーゲームとか
そういう類のやつなんだけど個人的にはこういうの好きなんだよねここからは僕の感想になりますけれども僕はこういうオリジナルゲーム めっちゃ好きでライアーゲームとかに一時期どハマりしちゃってコミックスでも読んでたし ドラマでも見てましたけどああいうオリジナルのゲームをやる
お店みたいなのってないのかなとかって
めっちゃ調べてたりするんですよボードゲームとか
リアル脱出ゲームとかは
結構お店とかがあるんだけどああいうライアーゲームみたいな聞いたことのないオリジナルゲームをしますみたいなお店ってあんまりないじゃないですか僕 そういう店あったらめっちゃ行くのにな〜みたいなこういうのめっちゃ好きなんですよただ僕これちょっとネタバレ気味にはなるかもしれないけど『地雷グリコ』では言ってしまえば
連作短編集みたいな感じで5つの話があって 全部 主人公が真兎ちゃんでそれぞれゲームをやっていくっていうスタイルなんですよこの小説は350ページあるんですよ5で割ると 1つのゲームが70ページなんですね結構 コンパクトに収まってると思うんですだけど 僕 ちょっと長い目の
こういうのあったら
良かったなと思うわけこの『地雷グリコ』いくらでも
多分 シリーズにできるんですよ「真兎ちゃんシリーズ」みたいなで作っちゃえばこの真兎ちゃんが次々ゲームに
巻き込まれていくっていうことで小説でシリーズで出せるから今回は連作短編みたいななんだけどめっちゃ長いゲームとか今後
作っていったらいいと思うんです僕 ライアーゲームの中で
「椅子取りゲーム」っていう
ゲーム めっちゃ好きでライアーゲームも
1ゲーム1巻ぐらいで
大体終わるんですけど椅子取りゲームって3巻ぐらいあるライアーゲームの中でも1番長い
長編のゲームがあるんですよあれ めちゃくちゃ面白くてルール 一見 簡単なんだけどかなりゲームとして複雑で難しくなっていくんですね僕 それが好きだから これ 結構コンパクトだからそこ ちょっとコンパクトだなって思うのとあとルール的な欠陥としてはあるゲームがあった時にもちろん その相手の裏をかいて心理戦で 裏の裏をかきあってとんでもない勝負の仕方してえーみたいなになって
でも勝ちましたみたいな
パターンなんだけどこれ 詳しくは言わないから ちょっとごまかすけど例えば 5回戦のゲームがあるとするじゃないですか最終的にポイントが高い人の勝ちみたいなパターンで1回戦目 2回戦目 3回戦目 4回戦目
負けちゃいました ってなっても5回戦目に掛け金を大量にバッて払ったら5回戦目だけ勝ったら勝ちっていうことになるんですよねだから それって 今までの
4回戦あんまり意味ないんじゃないか
っていうことになるじゃないですかもちろん それはそれぞれの布石があって伏線みたいのちゃんと張って
5回戦目にきちんとやってますよ
ってことになるんだけどだけど そのパターンってクイズ番組で最後のポイント100万ポイントですよ みたいなクイズで今までの何やってん みたいなことにもなりかねないので僕 その逆転はあまり好きじゃないんですよねだから このゲーム自体はめっちゃ面白いしこういう小説ってあんまりないと思うんだけどコンパクトになりすぎててこの最後の1回戦 勝てば勝ちみたいな
パターンがちょっとあるんですよねやってることは多分ライアーゲームみたいな感じで盤外戦術みたいな感じなんですよルールの穴をついた作戦みたいなが
出てくるんだけど 僕はそれ好きなのよこういうゲームって頭の中でルールを整理整頓してこれでやればこう勝てるなって思うんだけど実はそのルール よくよく考えるとルールには書いていない もしくは
きちんと明言化されていないルールがあってそれを利用して勝ちましたっていうパターンは結構 ライアーゲーム ではよくあるんですよこれも ちょこっとあって 好きなんだけどこのゲームも開発するのはもちろん
めちゃくちゃ労力かかると思うし色々 考えてらっしゃると思うんだけど僕はもうちょっと骨太な奴が
好きだったなっていう感じかなあとストーリーとしてのストーリーって
そんなにないから こういうタイプってあと直木賞向けなのかなっていうのはちょっとありますよつまりリアリズム的ではないからねつまり この主人公の名前が
「射守矢真兎」っていう
マンガ・アニメ的な名前だしあと登場人物も結構出てきていわゆるライバルキャラとかあと最初は敵だったんだけど
味方になりますとかいって 心強い!
みたいなパターンもあるんだけどキャラの造形がマンガ・アニメ的なんですよ直木賞って もっともっとリアリズムの世界なんでだから こういうのって
新本格ミステリの流れでは
あるんだけど直木賞には採用されにくいんではないか
というところはあったりするけどねそんな感じで 僕 毎回 候補作に点数をつけていますけれどもこの小説は90点ですね90点は僕の中ではデカイですよ小説自体は僕好みではありますこういう心理戦・頭脳戦
僕は本当に大好きで一時期 ボードゲームのゲームバーみたいなところに毎週 絶対 通って全然 知らない人たちとずっとボードゲームやってたりとかあとリアル脱出ゲームにも一時期めっちゃハマって月に何回か絶対に通ってみたいなを
何年かやってたりとかしてましたからこういうの好きなんだよ 基本的にただ 直木賞的には
どうなのかなっていうのは
さっき言った通りなんですけどだから これ シリーズで
5冊ぐらい出してほしい
アニメ化してほしいそういうの向きではあると思うんだけどねあと「自由律じゃんけん」は
友達とできそうだから
(作中のオリジナルゲーム)ちょっとやってみたいなって気はしますけどねそんな感じでございますまずは直木賞1冊目ということであと芥川賞・直木賞を含めて
9作品 読まなきゃいけないんだけど
頑張っていこうと思いますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#964「第171回直木賞の候補作を解説します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというと先日 6月13日の午前5時に第171回 芥川賞・直木賞の候補作が発表されました今回は直木賞の方なんですけどなかなかの変わったメンバーが揃っていてへーって思って こういうのが候補に
なることがあるんだなあと思っております早速やっていきましょう早速 直木賞の候補作を言っていきますが1つ目①青崎有吾
『地雷グリコ』
KADOKAWA2つ目②麻布競馬場
『令和元年の人生ゲーム』
文藝春秋3つ目③一穂ミチ
『ツミデミック』
光文社4つ目④岩井圭也
『われは熊楠』
文藝春秋5つ目⑤柚木麻子
『あいにくあんたのためじゃない』
新潮社以上 この5作品が直木賞の候補となっておりますね1人ずつ言っていきますと1人目 青崎有吾青崎有吾さんは1991年生まれ明治大学卒業だって2012年『体育館の殺人』で
第22回鮎川哲也賞を受賞して
デビューしていますね僕はこの館シリーズは知ってますよ綾辻行人の館シリーズではなくて『体育館の殺人』とか『水族館の殺人』とか「◯◯館」がつくシリーズがあるんですね他には『アンデッドガール・マーダーファルス』とか『ノッキンオン・ロックドドア』『早朝始発の殺風景』『11文字の檻』とか色々あるみたいですが去年ですね『地雷グリコ』っていうのが出てこれがなんと第24回本格ミステリ大賞第77回日本推理作家協会賞第37回山本周五郎賞を受賞しているとこの時点で3冠を取っているということなんですね今回は直木賞が来るかどうかということでございますまず青崎有吾さんはミステリの方であって新本格の流れだと思うんですよねここまで新本格の人が直木賞の候補に来るっていうのは珍しいいわゆる警察ものとか そういうのは
全然 直木賞に来ることあるんだけれどいわゆる探偵ものみたいなのは
あんまり来ないんですね 基本的にもう1個 この『地雷グリコ』なんと
デスゲームみたいな感じらしいよねいわゆるカイジとかライアーゲームとかああいうゲームして戦っていくみたいな小説らしくてそういうの直木賞の候補に来るんだなあと思ってこれ 面白そうなんだよ 普通にちょっと読みたいなと思っておりますね2人目 麻布競馬場麻布競馬場さんは1991年生まれ慶應義塾大学卒業だって2022年に
『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』
でデビューしているとこれぐらいしかプロフィールないんだよねでも僕はあんまり詳しくないがいわゆるツイッター文学・タワマン文学とか
言われたりしてる流れだとは思うんですよねこの辺 僕は柔らかいと思ってたんだよねこういうのって直木賞の候補に来るんだなと思ったけど結構 人気あるのは知ってるのよ今回の直木賞候補 全部に言えるんだけどそんなにめちゃくちゃ長い作品って入ってないんだよね全ての直木賞候補は200ページ台か300ページ台しかなくて400ページとか500ページとかの本は
今回の直木賞はないみたいですね『極楽征夷大将軍』とかめっちゃ分厚かったし前回だったら『なれのはて』とかそういう極厚みたいなやつはなくて今回の直木賞候補は全体的にソフトな感じがするんですよね本屋大賞とかに寄っても
おかしくはないみたいな候補が
並んでるような気はしてます3人目 一穂ミチ一穂ミチさんは1978年生まれ関西大学卒業だって2007年に『雪よ林檎の香のごとく』でデビューこの人は元々BL作家で 著作が
めちゃくちゃあるんですよね2021年には『スモールワールズ』っていうので吉川英治文学新人賞を受賞し
直木賞候補1回目になってますね2022年に『光のとこにいてね』っていうのが直木賞候補
2回目になってまして
今回で3回目なんですね僕は『スモールワールズ』
『光のとこにいてね』は
読んでおりますのでどちらかというと内容的には
人間関係を重視してるような小説
な感じはしてるんですけど僕は今
候補作全部 一応買いまして
手元に全部があるんですけど噂によると短編集が多いらしいんですよね直木賞ってもちろん短編集ってありますけれども短編集が沢山あるっていうのは
あんまりないと思うんですね
(候補作 3/5 は短編集)今回 それでこじまりとした感じ
なのかなあと思っていますね4人目 岩井圭也岩井圭也さんは1987年生まれ北海道大学大学院農学院修了らしいですね2018年『永遠についての証明』で 第9回
野生時代フロンティア文学賞を受賞しデビューし単行本も結構あるみたいです 作品としては『永遠についての照明』『夏の陰』『文身』『プリズン・ドクター』『水よ踊れ』『この夜が明ければ』『竜血の山』『生者のポエトリー』『最後の鑑定人』『付き添うひと』『完全なる白銀』『横浜ネイバーズ』『楽園の犬』『暗い引力』などがあるらしいです2018年にデビューして
今年2024年で6年間で
ここまで本を出せるっていうエンタメ作家って めっちゃ本を出すの早いよね純文学小説って芥川賞とかだったら中編が多いんだけど年に本1冊出たらいい方みたいな が純文学なんですよでもエンタメ小説って半年に1冊とか3ヶ月に1冊とかで本をどんどん出してたりするんでそのエネルギーどこから出てんねんとかそのアイディアとかどうやって
ひねり出してねんっていうのはいつも思う今回の『われは熊楠』ですけどこれはいわゆる南方熊楠の話らしくていわゆる時代小説ですよねちょっと最近 僕は時代小説も好きになってきましたんでだからこの本かなり楽しみになってまいりましたね最後5人目 柚木麻子柚木麻子さんは1981年生まれ立教大学文学部フランス文学科卒業だって2008年に
「フォーゲットミー、ノットブルー」で
第88回オール讀物新人賞を受賞して同作を含めた単行本『終点のあの子』でデビューこの柚木麻子さん なんと2013年に『伊藤くんAtoE』で直木賞候補1回目2014年に『本屋さんのダイアナ』で直木賞候補2回目2015年に『ナイルパーチの女子会』で直木賞候補3回目2017年に『BUTTER』で直木賞候補4回目2019年に『マジカルグランマ』で直木賞候補5回目なんと 今回
『あいにくあんたのためじゃない』
で直木賞候補6回目なんですよね全体的に見ると一穂ミチさんが今回 直木賞3回目なんですが他の人は1回目なんで柚木麻子かなって思いますけど どうなんでしょうか前回では万城目学さん6回目の候補で『八月の御所グラウンド』で
直木賞を受賞しておりましたからそのパターンかなと思ったりはしますけどしかし僕自身は実は
柚木麻子さんっていうのは
読んだことないんですね候補作も微妙に全部僕がYouTubeで候補作全部読むっていうのより前なのでちょっと微妙に読めていないんで今回 初めて読むってことで楽しみではあるんだけどねそんな感じで 今回
第171回直木賞の候補作を
全て見てきましたけど僕自身 実はこうやってYouTubeで芥川賞と直木賞の候補作を全て読んで動画に出すのは今回で10回目なんですよね僕は2019年下半期から現在に至るまで全部 候補作を全て読んでいます僕もよくやってるなって思わないですか頑張ってきたなあと本当に我ながら思うんですけど今回は特に直木賞がそれほど分厚くないっていうので皆さんもやりやすいと思いますよぜひチャレンジしていただければと思ったりするんだけどどうでしょうか?そんな感じで 僕はこれから候補作を全部読むのに時間を費やして動画もバンバン出していきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じ 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#963「第171回芥川賞の候補作を解説します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何をするか
というと先日 6月13日の午前5時に第171回 芥川賞・直木賞の候補作が発表されました僕自身は午前5時まで徹夜してパソコンの前で待機してて5時になった瞬間に
ずっと更新して
見ましたけどとても良かったんですけど今回は芥川賞の方ですねの候補作を全部見ていくっていう動画でございます早速やってきましょう早速ですが 候補作を1つずつ言っていきます1つ目①朝比奈秋
「サンショウウオの四十九日」
新潮 5月号2つ目②尾崎世界観
「転の声」
文學界 6月号3つ目③坂崎かおる
「海岸通り」
文學界 2月号4つ目④向坂くじら
「いなくなくならなくならないで」
文藝 夏季号5つ目⑤松永K三蔵
「バリ山行」
群像 3月号以上 この5作品が候補作となっておりますね1人ずつ見ていきますと1人目 朝比奈秋朝比奈秋さんは1981年生まれ2021年に「塩の道」っていう小説で
第7回林芙美子文学賞を受賞しています翌年 2022年には
同作を収録した単行本
『私の盲端』でデビュー2023年『植物少女』っていう
小説が刊行されてるんですけどこれが なんと
三島由紀夫賞を
受賞しているそして同じ年の2023年には『あなたの燃える左手で』で
野間文芸新人賞を受賞している
ということですね意外とこの人は芥川賞の候補には
1回も入ったことなかったんで今回で候補1回目としかし もう既に三島賞と野間文芸新人賞を取っていますからもうかなりの実力者だっていうことが分かるわけねさらに今回で芥川賞を取ったら三冠王になるわけですよつまり芥川賞・三島賞・野間文芸新人賞を
全てを取る人のことなんですけど今回の候補作を見ていくと基本的には 文壇のド真ん中を
進んでる人って逆に少ないんですよねだから この三島賞・野間文芸新人賞とか
取ってる方が箔が付いてるわけだから芥川賞をあげやすいみたいな そういうのは
あったりするかもなかったりするかもね2人目 尾崎世界観尾崎世界観は1984年生まれ2001年 結成の
ロックバンド「クリープハイプ」
のボーカル・ギターと2012年に アルバム
「死ぬまで一生愛されてると思ってたよ」
でメジャーデビューしています2016年に初めての小説『祐介』を書き下ろしで刊行他の本 めちゃくちゃ実はあってエッセイとか多いんですけど2021年に刊行された『母影』っていう小説があってこれが実は芥川賞の候補になってましてこれは 他の作家で見てみると 実は
(過去に)芥川賞候補になってる
作家は尾崎世界観しかいないんですね他の作家は候補1回目なのでいわゆる有名人枠ではありますけど僕は前の『母影』を読んで とても良かったと思うんだよね僕は個人的には泣いちゃった
ぐらいの完成度高かったと思うしあと僕は個人的にクリープハイプを聞いてたんですよねメジャーデビューしたアルバムと次のアルバムは
この2つはめちゃくちゃループして聞いててこういう世界もあるんだなと思ったこういう音楽家が芥川賞の候補に入るって最近ではなかなかないんじゃないですかね歌手から来る人は珍しいかもしれないね
(過去には町田康・川上未映子など?)3人目 坂崎かおる坂崎かおるさんは1984年生まれ2020年に「リモート」っていうので第1回かぐやSFコンテスト審査員特別賞を受賞しています2022年には「嘘つき姫」っていうので第4回百合文芸小説大賞「あたう」っていう作品で第28回三田文学新人賞佳作を取ってるんだよねあと「ベルを鳴らして」っていうのが
小説現代7月号に掲載されたんですけどこれが第77回日本推理作家協会賞の
短編部門を受賞しているということですね結構 この人はアンソロジーとかこういうちょっとした賞
っていうと怒られるけれど
を受賞したりとかして下積みっていうか
ずっとやってたんですけど単行本はなかなか出なかったんですがつい先日ですよね2024年に『嘘つき姫』って単行本が
河出書房新社からついに出たと長い下積みを経て単行本化したすぐにこうやって「海岸通り」っていうので
芥川賞候補に入るっていうのが面白いね個人的な私見と考えてもらったらいいですけど最近の作家ってどメジャーのなんとか新人賞を取って
文壇デビューしましたっていうよりかは下積みを経て ちょくちょく 名前を売りつつ単行本をポコポコ出してって
有名になるっていう方法も
あるんですよね同人活動みたいのもあるので今 文学フリマとかあと ひとり出版社とかリトルプレスから本を出すとかそういう方法があったりするんで意外と今 SNSとかもあるんで文壇デビューとかする前から みんなに
名前を知られてるみたいなことができるから坂崎かおるさんは個人的には僕それのイメージあるんだよねっていうか そういう作家が
増えているんじゃないか
と僕は思ってるんですけど4人目 向坂くじら向坂くじらさんは1994年生まれ慶應義塾大学文学部卒業僕 これ知らなかったけど2016年にGt.クマガイユウヤとのポエトリーリーディング×
エレキギターユニット「Anti-Trench」を結成あと2022年に詩集『とても小さな理解のための』刊行2023年に『夫婦間における愛の適温』っていうのを百万年書房さんっていうところから
いわゆるこれエッセイ集だと思いますが
を刊行していると2024年に今回の「いなくなくならなくならないで」を初めての小説として文藝に掲載したところなんと芥川賞の候補になったということですねこの向坂くじらさんも僕は『夫婦間における愛の適温』は
読んではないけど知ってましたね今 百万年書房っていう出版社が「暮らし」っていうエッセイシリーズみたいなを出しててこれ 僕 前から気になってたっていうか周りの人たちというかSNS付き合いしてる人たちが読んでたりするんで僕も読んでみるかと思ったわけそのうちの1つに この人がいたからさ名前ぐらいは知ってたんだけどあと個人的に面白いなと思ったのはサカサキかおるとサキサカくじらがいるっていうのがこれ ちょっとややこしいんだよねサカサキなのか サキサカなのか
ってところで絶対間違える人いると思うしあと これ どっちも濁らないのが面白いサカザキでもサキザカでもないんだよねあと直木賞の方に青崎有吾っていうのがいてこれはアオザキではないっていうんだよね尾崎はいるんだけどね尾崎世界観だけは濁るんだけどそれ以外のサキは濁らないって
覚えておいた方がいいと思いますよ最後 5人目 松永K三蔵松永K三蔵さんは1980年生まれ関西学院大学卒業2021年「カメオ」で第64回群像新人文学賞の
優秀作を受賞して作家デビューしていますむしろ 松永K三蔵さんの方が
どストレートで文壇デビューして芥川賞候補になるっていうパターンなんですよ他の人って色んな活動をしててプロフィール めっちゃ長いんですよねいわゆる純文学の文壇から外れた
ところでエッセイを出してたりしてる
っていうパターンは逆に珍しいわけでもそっちの方がプロフィールが分厚くなったりとか既にファンを獲得してたりするわけ純文学一本でやるとプロフィール少なかったりするんですよ僕はどちらかというと純文学中心で
やってる人の方が応援したいんだけど今は色んな そういう称号っていうか過去の遍歴とかが重視されるというかあった方が面白くなったりする時代だと思うんですもう自分たちで同人活動とかもできると思いますからそういう作家が増えるんじゃないかなと思ったりしますね純文学作家だからといって純文学だけではなくて色んなことをやったりとかSNSで発信したりとか
する時代についになってきたんじゃないか
っていう気はせんでもないんだよねそんな感じで今回 第171回 芥川賞の候補作を全て見てきましたが実はですね もうこの時点で
嬉しいお知らせがありまして実はこの5作品 全て単行本化が
決定しているということです僕はそこばっかり気になってて出版社のホームページとかアマゾンで調べたりとかすると全て単行本化するらしいということで僕自身はこの5作品全て読んで全てのあらすじ・感想の動画を読み次第 どんどん出していこうと思っておりますね毎度やってますが いつもギリギリなんで少しでも余裕を持ちたいなとは思ってるんだけど頑張っていこうと思っておりますねそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#962「第171回 芥川賞の候補作に入りそうな12作を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何をするか
というと今 6月なんですけど6月と言えば 芥川賞・直木賞の候補作の発表があるんですねこれは もう日時が決定してまして6月13日(木)の午前5時に発表されるということですねそれの約1ヶ月後に受賞作発表ですねこれは7月17日(水)に発表されるということなんでなんで今回の動画は芥川賞の候補作に
なるんじゃないか小説12選早速やっていきましょう1作目①福海隆
「日曜日(付随する19枚のパルプ)」
文學界 5月号これは今年の文學界新人賞の受賞作になってまして僕は雑誌はあまり読めていないので内容はわかっておりませんが次に紹介するのと合わせて注目度が高い作品だと思います2作目②旗原理沙子
「私は無人島」
文學界 5月号先ほどと同じく今年の文學界新人賞の受賞作と芥川賞は半年に1回ありますが
上半期と下半期があるわけですね上半期に発表される新人賞は文學界新人賞と群像新人文学賞になるわけですよここの新人は 大体どれかは入ります 毎回前回だったら(2023年上半期)
市川沙央「ハンチバック」も
文學界新人賞でしたから年森瑛「N/A」は(2022年)
受賞はしなかったけど
候補で入ってましたから文學界新人賞は入りやすいということですね3作目③尾崎世界観
「転の声」
文學界 6月号これ かなり周りの噂を聞くと超面白いとむしろ これ受賞するんじゃないか
という声がやっぱりありますね尾崎世界観は
「クリープハイプ」っていう
バンドのメンバーで1回「母影」っていう作品で
芥川賞の候補になってますので
(2020年 下半期)今回 次来たら2回目なんですよね過去に1回候補になってると2回目になりやすいと僕は思っていますので評判もいいんで これは来るんではないかと思いますよ4作目④朝比奈秋
「サンショウウオの四十九日」
新潮 5月号朝比奈秋さんと言えば『植物少女』で三島由紀夫賞を受賞(2023年)『あなたの燃える左手で』で(2023年)
野間文芸新人賞を受賞してますので芥川賞の候補は意外と1回も
入ったことないんですけど主要な純文学の新人賞を取ってますので今回 ここで来なかったらちょっとおかしいだろうっていう感じだとよく言われてます僕は朝比奈秋の単行本は全て読んでおりますので個人的には来てほしい作家ではありますね5作目⑤内村薫風
「ボート」
新潮 2月号内村薫風って謎の作家で10年以上前でしょうけど「MとΣ」っていうので 1回
芥川賞の候補になってるんですよ
(2015年 上半期)でも その時も顔とかも
分かんないわけよデビューも何とか新人賞を取ってデビューとかではなくて急に新潮でポーンって来たんですよだから正体は誰も知らない謎作家・内村薫風がなんと急に10年ぐらいの沈黙を破ってこの新潮で「ボート」っていう作品を発表したっていうこれ 来たらダークホース感がありますよ6作目⑥豊永浩平
「月ぬ走いや、馬ぬ走い」
群像 6月号これは次に紹介する作品と同じく今年の群像新人文学賞を受賞した作品なんですねこれもかなり評価が高いですね僕はまだ読んでないですが 沖縄の話らしくて僕の大好きな「文字びっちりタイプ」ね改行が全然ないタイプの小説らしくて周りの反応を見ると旗原理沙子か尾崎世界観かこの豊永浩平あたりはもう来るだろうと言われていますので注目度が高い この時点で と思います7作目⑦白鳥一
「遠くから来ました」
群像 6月号これは群像新人文学賞の優秀作を取った作品でよく公募型の新人賞で言えば受賞作というのと その下に佳作とか優秀作とかがあってそれは「受賞作」にはなってないんだよね 一応ねちょっと1ランク下がるけどデビューはさせてやろうみたいなそういう ちょっと下に見てる賞だけどでも全然そういうところから
芥川賞の候補になった人とかも
全然いますからそう思うと今回も来る可能性は
あるんじゃないかと思います8作目⑧松永K三蔵
「バリ山行」
群像 3月号松永K三蔵さんも この人も過去に群像新人文学賞の優秀作を取ってるんですよねそれ タイトルが「カメオ」っていうタイトルなんですけどその時って2021年の時なんですが石沢麻依『貝に続く場所にて』と島口大樹『鳥がぼくらは祈り、』
の時の優秀作なんですよね優秀作は単行本化されないものなんで松永K三蔵さんだけは単行本が出なかったんですよ今回 この作品で芥川賞の候補に入った時に初単行本化されるっていう感じなんで個人的には願ってはいますけどね9作目⑨草野理恵子
「名前を呼ぶ」
群像 1月号草野理恵子って元々詩人の方で僕は1冊だけ 本を
読んだことあるんですけど
(『黄色い木馬/レタス』)今 文芸誌で小説とか
発表されているのは
凄いなと思います今回の芥川賞の候補を色々調べたら面白いですよ凄いメンバーがいますよね今回の第171回は
色々集まってきてる感じがあって
超面白そうな感じがします10作目⑩石田夏穂
「世紀の善人」
すばる 1月号石田夏穂は芥川賞候補に
過去に2回なっていますから「我が友、スミス」(2021年 下半期)
「我が手の太陽」(2023年 上半期)
が入っていますから 3回目来てもいいんではないかという感じ全体的に「お仕事小説」っていう感じかなストーリーもあるし一般の人はそれほど知らないな みたいな
その世界を描く面白さがあっていいですよね11作目⑪長井短
「存在よ!」
文藝 春季号長井短ってモデルさんなんだよねだけど ここ数年は
小説とかエッセイとかを
色んなところで書いてまして僕は 実は『内緒にしといて』っていう
エッセイ集は読んだことあるんですよね朝日新聞出版から
『私は元気がありません』
っていうのとあと河出書房新社から
『ほどける骨折り球子』っていうのが
近いうちに刊行されるんですけど今 結構
「ノリに乗ってる新人」
という感じがします長井短さん 来てくれたら面白いと思う最後 12作目⑫大原鉄平「森は盗む」
小説トリッパー 春季号これは今年の林芙美子文学賞を取ってる作品で僕 林芙美子文学賞って純文学なのかなっていうちょっと まだわかってないっていうか最近できたっていうか
10年ぐらいでしょうけど
(2014年 創設)でも最近「小説トリッパー」っていう雑誌が芥川賞とか もしくは直木賞の方にも候補を出すことがあってどっちもありなんだ みたいな真ん中ぐらいの立ち位置じゃないですか前回は 宮内悠介
『ラウリ・クースクを探して』が
小説トリッパー 掲載だったんですよでも それ直木賞の方に行ったんですよねでも今村夏子の候補作とかは
小説トリッパーだったから
どっちもありみたいな凄いところを獲得した
小説トリッパーっていう
雑誌があるんだけど普通はありえないからねこの大原鉄平はまだ単行本が出ていませんから今回 候補に入って単行本化するっていう方法は
あるんじゃないかと思いますねそんな感じで 今回第171回 芥川賞の候補作に入るんではないかと
勝手に思っている作品12選を紹介しましたが正直 12作品を集中的に紹介したけど まだまだあるのよね二瓶哲也なんか めっちゃ昔に
文學界新人賞を取ったきり
単行本1冊もないみたいな人が例えば 今回 入ってくると
単行本化 ほぼ確定なんで
芥川賞候補になるだけでどんどん単行本化してほしいなっていう感じはするしかし もう6月7月は
芥川賞・直木賞の季節と
なってまいりましたので僕も毎回と同じように芥川賞と直木賞全ての候補作を読んで1冊ずつの感想動画を全部出していこうと思っております結構 これ エネルギーが必要で終わった時にヘトヘトになるんだけど頑張っていきたいと思っておりますねそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#961「最近のつかつの近況と文学フリマの進捗【ヤバい!】」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何をするか
というと最近のつかつの近況と文学フリマの進捗最近あんまり動画を出せていなかったんですね別に これは動画をやめたわけじゃなくて本も読んでないわけじゃなくてかなり忙しかったっていう話なんですけど文学フリマが残り半年なんですよね「文学フリマ東京39」っていうのが今年の12月1日(日)に開催されて僕はそこで出店予定なんですねもうすでに文学フリマのエントリー料ですよね出店料っていうのはもう支払っていますなので もう出るのは確定だけどまだ原稿の方が完成してないんですよね
(あと107冊の本を読めば完成します!)僕が出したいのは
『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
っていう本で僕がこの3年間に読んできた1080冊の本のあらすじとか感想とかを1冊140文字前後で
1080個並べた
って本なんですけどそれのレイアウトとかをめっちゃこだわっててワードで作ってるんですけど僕もあと半年でしょ(文フリまで)だから何回も推敲して細かい文章を直したりとかあと並び替えですよね小説を紹介するわけだからどこから読んでも読めるような作りですよブックガイドなんで途中からめくってもそこに「この本はこういう本で〜」
って書いてるからわかるんだけど僕のこだわりがありますからこれを1番最初に持ってきてとか もしくは今まで読んできた本があるんだけどあんまり小説と関係ない本とかも入っているわけですよそうすると 僕はそれを抜いて代わりにまた新しい純文学を入れたりとかすると統一感が出てきてそれをずっと先週から先々週ぐらいずっとやってました完成形としては約200ページですねA5のサイズになりますA5っていうのは普通の単行本ではなくてワイド版の漫画のサイズになります上下段になっていて1ページに6冊の本が紹介されているという感じかな今はこうやってパンチで穴を開けてこうやってファイリングしてって管理してるんだけどもちろん これ製本化するんでまだ先だけど 印刷所とか今調べたりとかあと表紙と裏表紙にイラストを入れたいと思ってるんですねそのイラストに関しても僕は知り合いっていうほど知り合いじゃないけどツイッターで仲良いあるセミプロみたいな人かなにちょっとお願いしてるんですよね今6月でしょ7月ぐらいにはイラストも完成する予定なんでそれが本当に嬉しいんですよね僕はそのイラストレーターさんの絵が好きなのでその人に書いてもらうっていうのが本当にそれだけで嬉しいわけ究極的にはどんな絵がやってきても僕は嬉しいし同人誌もちょっとずつ完成していく感じがあって今 ドキドキワクワクしてるのよ初めての文学フリマ出店
っていうのもあって
緊張はしているんですけどまだ先だし 言うのもどうかと思うがとりあえず150部は刷ろうと思うんですね150部って文学フリマでは結構チャレンジングらしくてもちろん全然売れなかったら赤字になりますよ僕は今回の文学フリマで例えば東京への交通費とかあと文学フリマの出店料とかもちろん印刷・製本してもらうお金があってそれ 大体10万円ぐらいの予算なんですよ10万円って結構な額じゃないですかだからちょっと僕もギャンブルではあるんだけどさっき文学フリマの
エントリーが終わった
って言ったじゃないですか普通 文学フリマって1ブース 長机の半分だけなんですよだから2人ぐらいしか人が座れないぐらいの狭いんですよねでも 僕は初めての出店なのにお金を払うと 長机の半分が2つ
ブースを広げることができるんですねつまり長机丸々1つを借りることができるんですよこれは倍ぐらいのお金を払ってるんですけどだから1万5千円前後くらいのお金を払ってあと椅子とかも お店側で座る椅子があるんですけどその椅子も普通2つだったと思うけど3つぐらい借りてますので 結構 金かかってんのよってか初めてなんで そこまでする
必要あるのかって思うんだけど初めてだから気合い入れて お金を使って
頑張るぞって思ってはいますただ1個だけ言っておくと前 この僕の同人誌を
1冊1000円で売る
って言ってたんですけどあとあと ちょっと計算し直すと1冊1000円じゃ赤字になっちゃうみたいなんですねなのでちょっと 僕も心苦しいですけれども1冊1000円じゃなくて1500円で販売しようかと思います1500円ってちょっと高いかもしれないけど僕のこの本は200ページあるんですね結構 情報がかなり詰まっているので文学フリマって1冊50〜100ページとかの本が多くて200ページある本ってあんまりないですよそれで1500円って普通ぐらいな感じかなと僕は思ってますし僕のこの本は
1500円以上の価値あると
僕は本当に思っているのでめっちゃ良い本だと僕は思っているので1500円ちょっとお許しくださいっていう感じでございます
(完成までに3年という年月がかかっていますので!)1500円より上は絶対に値上げはしません1500円だと僕は黒字が出てその黒字が出たら さらに次の同人誌も刷れますので僕は単に収入が欲しいとかじゃなくて次に繋げたいわけですね僕は次の12月1日に
『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
って同人誌を出すが予定では まだまだ先ですが例えば その次の文学フリマ文学フリマ東京は半年に1回ありますので12月の次 5月か6月だと思いますけどそこに さらに僕は新刊を出そうと思うんですねそれは 次に出したいのは僕が8〜9年前ぐらいに最終選考に残った「存在しない川」っていう小説をついに出そうと思ってます2016年だったかな文藝賞 最終選考に残った作品があるんです僕はこれをあんまり外に発表してないんですけどせっかくだしと思うし 8〜9年前なんでもう1回 文学フリマに出店したんだったらもう次々とどんどんと新刊を出していった方がいいと思うし僕のモチベーションが高まるんでついに「存在しない川」を製本にして同人誌にして 文学フリマで売ろうと思ってますんでそれに繋げるためには資金が必要なわけですねその資金を 今回の
『つかっちゃんの現代純文学1000冊』
で手に入れようと思ってますそれが商売っていうか資本を使って さらに資本を作って その得た資本でさらに次の資本を作っていくっていうのが資本主義なんで次の同人誌 またそれが売れたら次の同人誌また売れたら次の同人誌って出せるように途切れないようにちょっとそこは考えて文学フリマに参戦しようと思っていますねこれだけ言って終わりますけど僕 本当に文学フリマの同人誌は自分の総決算っていうか総まとめみたいな本だと思っています僕は4年半 文学フリマの時は もう5年に達成してますがYouTubeを5年やって それの総決算としての1冊の同人誌だと僕は思っていますから僕の中で この本を好きになりたいのよ僕は僕自身を好きになることはあんまりできなくて僕ってダメなんだな みたいな気持ちばっかりあるんだけど本にするとその本を好きになることは僕できると思うんだねその本のために僕はやっぱり頑張りたい僕がこの5年間 もしくは この3年間読書記録っていうのを始めて
1080冊読んだっていうその結果を1冊にまとめたものを僕は心の底から愛したいと思っているんだよねこれも赤字になってもいいのよ僕が好きで この本ができた 完成した家に1冊2冊置いておく 僕自身がそれだけでいいんで別にこの本に対して
力を抜きたくない
っていうことなんだよね自分が満足した 自分のこだわりが詰まった本を早く早く完成させたいとそのために ちょっと
動画の更新頻度が下がっても
僕は仕方ないと思うし同人誌完成の方が今のところは優先度が高いのでちょっと本当に視聴者さんには申し訳ないですけれども
僕はちょっと頑張りたいと思いますね
(次の芥川賞・直木賞の候補作の動画は全部出しますよ!)一生懸命 取り組んでいこうかなと思ってはおりますねそんな感じで 色々語ってきましたけど僕の文学愛みたいのはずっとあり続けるからずっと文学の話してるんで僕は基本的にはYouTubeとtwitterとnoteっていうこの3つはやっていますんでもし良ければ登録とかフォローとかしていただければモチベーションに繋がりますんで皆さん どうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#960「僕が読みたい40人の純文学作家とその作品を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何をするか
というと僕が読んでいない40人の作家とその作品僕は今度12月の文学フリマ東京39に
自分の同人誌を作って出そうと思ってるんだけど
(『つかっちゃんの現代純文学1000冊』)その同人誌を作るためには
僕はあと113冊の本を
読まなきゃいけないんですけどその同人誌に僕が
まだ紹介していない作家が
調べると40人いるとこの40人はぜひ入れたいと思ってその意気込みとして
この動画を作ろうと思いました早速やっていきましょう1冊目①三輪太郎
『憂国者たち』
講談社 2015三輪太郎さんは元々群像新人文学賞の
評論部門を受賞しデビューしてるんだけどのちに小説を書いて『憂国者たち』で三島賞の候補に
1回なっているという作家でございます2冊目②内田春菊
『キオミ』
ベネッセ 1995内田春菊さんは元々漫画家ですが『キオミ』で1990年代ぐらいですけど
芥川賞の候補に1回入っているんですね実は3冊目③松家仁之『泡』
集英社 2021松家仁之さんは元々 実は新潮社の
編集者をやっていたんですけどのち小説を書いて 読売文学賞とか色々取って今は三島賞の選考委員の方を
されているという方でございます4冊目④上村渉
『うつくしい羽』
書肆侃侃房 2020上村渉は元々 文學界新人賞を
受賞し作家デビューしましたが長らく単行本が出なかって『うつくしい羽』で
書肆侃侃房から本が出て
単行本化デビューとこれ1冊しかありませんけどね5冊目⑤はあちゅう
『通りすがりのあなた』
講談社 2017はあちゅうさんは元々ブロガーなんだけど『通りすがりのあなた』で初めての小説集を出して実はこれ「群像」掲載が多かったので 実は
純文学になるということで僕は読もうと思ってます6冊目⑥エリイ
『はい、こんにちは』
新潮社 2022エリイさんは「Chim↑Pom」っていう
アーティストグループに所属していて『はい、こんにちは』はエッセイ集なんですよね「新潮」で掲載してたっていうのを
ちょっと読もうと思ってます7冊目⑦桐山襲
『パルチザン伝説』
河出書房新社 2017桐山襲っていわくつきの作家で学生闘争とか そういうことを書いてたんだけど1回 出版停止とか食らっちゃう 昔なんだけど(1983年)『パルチザン伝説』は最近 復刊された
っていう伝説の本ではあるんだよね8冊目⑧法月ゆり
『彼女のピクニック宣言』
集英社 2002法月ゆりさんは 実は この
『彼女のピクニック宣言』は
3つ小説が入っていてその内2つが実は2000年代ぐらいの
芥川賞の候補になっているんですよね芥川賞候補に入っていたら僕も読まねばならぬと思って これ読もうと思います9冊目⑨佐川光晴
『生活の設計』
新潮社 2001佐川光晴って『生活の設計』で
新潮新人賞を受賞し作家デビューし芥川賞候補も何回か入ったんだけど芥川賞は取らなかったっていう作家なんですけどね10冊目⑩福島次郎
『蝶のかたみ』
文藝春秋 1998芥川賞候補も
この『蝶のかたみ』の中に入っている
「バスタオル」っていう小説があってタイトルすごいけどねそれで芥川賞候補に1回入ってるんだよねのちに三島由紀夫との手紙を発表して裁判になったっていう作家でもありますけど11冊目⑪伊達一行
『沙耶のいる透視図』
集英社 1983伊達一行さんは この『沙耶のいる透視図』で
すばる文学賞を受賞して作家デビューしています芥川賞候補も何回か入ってると思いますが取らなかった作家でありますね12冊目⑫角田光代
『幸福な遊戯』
福武書店 1991この角田光代さんは 実は元々は海燕新人文学賞=福武書店がやっていた
純文学の新人賞でデビューしてるんですね『幸福な遊戯』の中に入ってるやつが
そのデビュー作になるんですけどデビュー作を読みたいなと思います13冊目⑬村上政彦
『ドライブしない?』
ベネッセ 1991村上政彦さんも
実は海燕新人文学賞を
受賞して作家デビューと『ドライブしない?』がデビュー作ですね芥川賞の候補も何回か入ってたと思いますが1990年代だったなっていう感じかな14冊目⑭下井葉子『うみ』
講談社 1997この人は実は
群像新人文学賞を受賞して
作家デビューしてるんだけど確か この『うみ』が
野間文芸新人賞の候補に
入っているんですよね15冊目⑮伊井直行
『さして重要でない一日』
講談社 1989伊井直行さんは『草のかんむり』で
群像新人文学賞を受賞して作家デビューこの『さして重要でない一日』は
野間文芸新人賞を受賞しているんですねだから有名な方かな16冊目⑯デビット・ゾペティ
『いちげんさん』
集英社 1997デビット・ゾベティさんは この『いちげんさん』で
すばる文学賞受賞して作家デビューしていますこの人は外国の方ですが 日本語で小説を書いたといういわゆる「越境文学」で よく言われる作家ではありますね17冊目⑰中沢けい
『海を感じる時』
講談社 1978中沢けいさんは この『海を感じる時』で
群像新人文学賞を受賞して作家デビューこの作品は映画化もされてるしあと今 講談社文芸文庫にも入っている作品でございます18冊目⑱室井光広
『おどるでく』
講談社 1994室井光広さんは元々 評論でデビューしてるんですけどのちに小説を書いてこの『おどるでく』で実は芥川賞を
受賞しているという作家でございます19冊目⑲新井千裕
『復活祭のためのレクイエム』
講談社 1986新井千裕さんは 『復活祭のためのレクイエム』で
群像新人文学賞を受賞して作家デビューしています僕はこれ昔 読んだことあって
独自性があって超面白いんだよね群像新人文学賞の隠れた名作っていう感じは僕してますよ20冊目⑳野坂昭如
『骨餓身峠死人葛』
中央公論社 1969直木賞(作家)なんだけど
結構やってることが
純文学っぽいんだよねこの『骨餓身峠死人葛』か
『死刑長寿』っていうのがあってどっちか読もうかな とはずっと思ってきた今回 これを読もうと思ってます21冊目㉑又吉栄喜
『豚の報い』
文藝春秋 1996又吉栄喜は『豚の報い』で芥川賞を受賞しているんですねこの人は沖縄の人で
『豚の報い』も沖縄文学なんで沖縄文学ってファンがいますから僕もこれ読まなきゃなと思ってます22冊目㉒目取真俊『水滴』
文藝春秋 1997目取真俊さんは『水滴』で芥川賞を受賞しています目取真俊も沖縄の文学を書いてて結構ファンがいるんだよねこの辺の芥川賞は1990年代なんですね1990年代の芥川賞 また再読しなきゃなと思っています23冊目㉓玄月
『蔭の棲みか』
文藝春秋 2000玄月の『蔭の棲みか』は芥川賞を受賞しております芥川賞はいずれ全てのものを読みたいと思ってるんだけどまだまだ90年代で止まってる感じなんで一気に読みたいね24冊目㉔金井美恵子
『カストロの尻』
新潮社 2017僕は金井美恵子って あんまり読んでこなかったんだよね金井美恵子ももちろん昭和文学の
巨匠みたいな人なんですけども「この『カストロの尻』が面白いよ」っていうのをあるポッドキャストの人が言っててあーちょっと読まなきゃなと思ってこれ読もうと思いました25冊目㉕若合春侑
『腦病院へまゐります。』
文藝春秋 1999この若合春侑さんは『腦病院へまゐります。』で
文學界新人賞を受賞して作家デビューしていますこの作品もそうだけど 3回 芥川賞の候補になっておりますね26冊目㉖シリン・ネザマフィ
『白い紙/サラム』
文藝春秋 2009シリン・ネザマフィはこの『白い紙/サラム』で
文學界新人賞を受賞して作家デビューしています芥川賞候補も2回なっておりますが単行本は この1冊しかありません27冊目㉗田山朔美
『霊降ろし』
文藝春秋 2009田山朔美は『霊降ろし』で
文學界新人賞を受賞して
作家デビューをしています田山さんはこの1冊しかありません28冊目㉘中山智幸
『さりぎわの歩き方』
文藝春秋 2007中山さんは この『さりぎわの歩き方』で
文學界新人賞を受賞して作家デビューしています確か1回 芥川賞の候補に入ってるんですよね29冊目㉙河林満『渇水』
文藝春秋 1990河林満もこの『渇水』で
文學界新人賞を受賞し
作家デビューしています30冊目㉚佐藤亜紀
『喜べ、幸いなる魂よ』
KADOKAWA 2022佐藤亜紀さんは色々小説を出していてエンタメのイメージありますが純文学の文学賞を取るとかは結構あるんだよねこの『喜べ、幸いなるの魂よ』で
読売文学賞を受賞していますのでこれ 分厚いらしいが 読んでみようと思ってます31冊目㉛中上健次『岬』
文藝春秋 1976中上健次は戦後生まれで初めての
芥川賞を取ったという作家でこの『岬』で芥川賞を取ってます32冊㉜中上紀
『彼女のプレンカ』
集英社 2000中上紀さんは実は中上健次の娘さんでしてこの人は この『彼女のプレンカ』で
すばる文学賞を受賞して作家デビューしています33冊目㉝花村萬月
『ゲルマニウムの夜』
文藝春秋 1998花村萬月さんは元々 小説すばる新人賞でデビューしてるからつまり最初はエンタメから入ってきてるんだけど実はのちに『ゲルマニウムの夜』で
芥川賞を取るっていう作家で1990年代の芥川賞は全部読もうと思ってはいますよ34冊目㉞宮本輝『螢川』
筑摩書房 1978宮本輝は『螢川』で芥川賞を取っていますがその前に「泥の川」っていうので
太宰治賞を取って作家デビューしてますね35冊目㉟足立陽
『島と人類』
集英社 2015この足立陽さんは『島と人類』で
すばる文学賞を受賞して作家デビュー単行本はこの1冊しかないですけどね36冊目㊱淺川継太
『ある日の結婚』
講談社 2014淺川継太は『ある日の結婚』の中に入ってる作品で
群像新人文学賞を受賞して作家デビューしてます僕 この1ヶ月ぐらいで過去の群像新人文学賞を
めちゃくちゃ読んできたんですよね2000年以降の群像新人文学賞で
僕が 単行本に限ってだけど読んでいないのは 『ある日の結婚』だけなのでちょっと読まなきゃいけないんだよね37冊目㊲鈴木弘樹
『よしわら』
新潮社 2002鈴木弘樹さんは 『よしわら』で
新潮新人賞を受賞して作家デビュー元々は「グラウンド」っていうタイトルだったみたいだけど単行本化する時に たぶん改題して
「よしわら」になってると思うんですけどこれは実は芥川賞の候補に入ってるんだよね
『よしわら』 ちょっと読もうと思ってます38冊目㊳和田ゆりえ
『ダフネー』
星湖舎 2015この和田ゆりえさんっていうのは
2回 芥川賞の候補に入っていまして単行本がほぼなかったんだけど10年ぐらい経ってでしょうけどなんかよくわかんない出版社からこの作品集を出しててそこに過去の芥川賞候補が2つ入ってるんだよね僕は2000年以降の芥川賞の候補に入った作家で読んでない作家をなくしたいっていう気持ちがあってそういうのを調べて読もうと思っています39冊目㊴佐藤洋二郎
『夏至祭』
講談社 1995佐藤洋二郎さんは この『夏至祭』で
野間文芸新人賞を受賞している作家なんだよね1990年代とか2000年代とかの
知られざる傑作みたいなのもあるしそれを僕 発掘していきたいと思って
ちょっと読もうと思っています最後 40冊目㊵飯塚朝美
『地上で最も巨大な死骸』
新潮社 2010飯塚朝美さんは
『地上で最も巨大な死骸』
の中に入ってる作品で新潮新人賞を受賞して
作家デビューしていますこの作品は 僕は
過去に読んだことがありますが
なんか とても良かったんだねだいぶ昔に読んだから ちょっと再読して
もう1回 味わいたいと思ってるんですけどこの辺りも読むべしと思って読もうと思いますそんな感じで 今回
僕が読んでいない40人の作家と
その作品を紹介してきましたけれどやっぱり僕が同人誌を作る際に
幅広い作家陣を紹介したいじゃないですか僕の1000冊を紹介してる同人誌を買えばこの20〜30年の純文学の作家でメジャーなものからマイナーなものまで幅広く
1冊でわかりますみたいな本が作りたいから結構 今 調べてるんだよねめっちゃ考えてます 早く同人誌を
作りたい作りたいと思っておりますそんな感じでございますもし皆さんが「この作家 読んだ?」
みたいな 僕に訊きたいっていうか「マイナーだけど知ってる?」
みたいな作家がいましたら
ぜひコメントで教えてくださいそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#958「【17選】僕が読みたい芥川賞候補作17冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何をするか
というと読みたい芥川賞候補作17冊先日 この部屋の本棚を整理してたんですよそうすると奥の方からドカっと芥川賞候補作がたくさん出てきたんですねそれが17冊出てきたんで
それを紹介しようかな
という動画でございます早速やっていきましょう1冊目①津村記久子
『婚礼、葬礼、その他』
文藝春秋 2008津村記久子さんは『ポトスライムの舟』で
芥川賞を受賞しているんですけど(2009年)その前に『カソウスキの行方』っていうのと あとこの『婚礼、葬礼、その他』で芥川賞候補になりその後に芥川賞を取ってるんですね僕は『ポトスライム〜』は読みましたこの本は実は読んだことなくて
文庫本も持ってるんですけど単行本がせっかく出てきたんで
ちょっと読もうかなと思いました2冊目②松浦寿輝『幽』
講談社 1999松浦寿輝は『花腐し』で
芥川賞を受賞(2000年)でも その前に実は この作品で芥川賞候補になっていて『花腐し』は読みましたが
『幽』は実は読んでないですねこの『幽』は長年 文庫化されてなかったんだけど講談社文芸文庫に入って『花腐し・幽』っていうので合本されてるんですよね松浦寿輝って芥川賞の選考委員をやってるんだけど文学賞も山ほど取ってますんでまた読んでいこうかなと思っております3冊目③円城塔
『これはペンです』
新潮社 2011円城塔は『道化師の蝶』で
芥川賞を受賞(2012年)その前に『これはペンです』が
芥川賞候補になっているんですねこれは過去に読んだことあります「叔父は文字だ」から始まるおじさんから手紙が来るんだけど文字の生成について ずっと語ってるっていう小説で円城塔は『オブ・ザ・ベースボール』とか『烏有此譚』とかはもちろん読んでるんですけど微妙に『これはペンです』が抜けてるんで(読書記録から)ちょっと読んでいこうと思ってますね4冊目④墨谷渉『潰玉』
文藝春秋 2009墨谷渉さんっていうのは2007年に『パワー系181』で
すばる文学賞を受賞して
作家デビューしてるんですねそのあとに これが芥川賞候補になったんですけどこれ 結構 変態チックでいいっていう評があって「潰玉」っていうタイトルでしょ
「玉が潰れる」って書くでしょこれ 男の金玉が潰れるみたいな話らしくてちょっとSMみたいなのが入ってるらしいんだよねこれも前から気になってて昔から持ってた小説なんですけどようやく読もうかなと思っていますね5冊目⑤羽田圭介
『メタモルフォシス』
新潮社 2014羽田圭介さんは
『スクラップ・アンド・ビルド』で
芥川賞を受賞(2015年)その前に この『メタモルフォシス』とそして『走ル』と『ミート・ザ・ビート』
っていうので芥川賞候補になってるんですね僕は実は その3冊は読んだことなくて結構 最近の
『滅私』とか『Phantom』
は羽田圭介を読んでるんだけど初期・中期あたりのやつは読んでないんですよこの『メタモルフォシス』は
過去に読んだことあるんですけど1個ちょっと言っておかないといけないのは僕が「読んでない」って言ってるのはこの3年以内に読んでなくて「読書記録に入れてないこと」を
「読んでない」って言ってますので『メタモルフォシス』も再読しなきゃいけないんですねこれは『メタモルフォシス』こそSMの話で主人公がSMクラブに通ってるんですよね超面白いんでね めっちゃいいんで
これ ぜひ読んでほしいなと思います6冊目⑥内田春菊
『キオミ』
ベネッセ 1995内田春菊って漫画家なんですけどこの辺りぐらいから小説も書き始めてこの『キオミ』で実は
芥川賞の候補に1回
入っているんですよね『ファザーファッカー』って
そっちの方が有名だけどそれで直木賞の候補にもなってますけどこの『キオミ』は読んだことはないですが
『ファザーファッカー』は読んだことあってそっちは作者の実体験というか昔の私小説みたいな感じで結構つらい話だったんだけどこれは短編集らしい
これもまた読みたいな
と思ってますね7冊目⑦小谷野敦
『母子寮前』
文藝春秋 2010小谷野敦さんは色んな活動してるでしょう小説とか評論とか色んなのを書いてるけど芥川賞は2回候補になってて僕は『ヌエのいた家』は
読んでるんですけど
こっちは実は読めてなくて他にも小谷野さんって
小説を色々書いてるから僕も見つけ次第に買ってはいるんだけどなかなか読めずじまいという感じで『とちおとめのババロア』とか
『蛍日和』とか色々ありますけどちょっとまた読んでいこうと思ってはいますね8冊目9冊目8冊目⑧石田千
『あめりかむら』
新潮社 20119冊目⑨石田千
『きなりの雲』
講談社 2012石田千っていう作家は
この2冊と もう1個『家へ』で芥川賞候補になってるんですけど最終的に芥川賞は取れなかったんですけど元々はエッセイストっていうのかな今めちゃくちゃ本を書いてるでしょう僕も『家へ』は読みましたこの2冊は読めてないんですよねちょっと全部読みたいなとは思ってはいるんですけどね10冊目 11冊目10冊目⑩小野正嗣
『マイクロバス』
新潮社 200811冊目⑪小野正嗣
『水死人の帰還』
文藝春秋 2015小野正嗣さんといえば
『九年前の祈り』で芥川賞を
取っている作家(2015年)その前に この2冊と もう1個『獅子渡り鼻』っていう小説があって『獅子渡り鼻』も僕は読めてないんですよね小野正嗣さんっていうのは
田舎の港町の浦っていう場所を
舞台に書き続けている作家で『にぎやかな湾に背負われた船』で
三島由紀夫賞も受賞している作家ですがこの芥川賞候補作は読めてないんで この辺り
読んでいきたいなと思っておりますね12冊目12冊目 13冊目 14冊目12冊目⑫鹿島田真希
『ナンバーワン・コンストラクション』
新潮社 200613冊目⑬鹿島田真希『女の庭』
河出書房新社 200914冊目⑭鹿島田真希
『その暁のぬるさ』
集英社 2012鹿島田真希は『冥土めぐり』で
芥川賞を受賞している作家(2012年)鹿島田真希といえば
新人賞三冠王になってまして『冥土めぐり』で芥川賞を受賞『ピカルディーの三度』で野間文芸新人賞を受賞『六〇〇〇度の愛』で三島由紀夫賞を受賞この3つを受賞している
数少ない作家でもありますねかなり前衛的なんですよね
だから一見難しいんだけれどザ・文学っていう感じがして
僕は本当に大好きなんだよねだから この3冊は読んでいかないとなと思っておりますね最後15冊目 16冊目 17冊目15冊目⑮舞城王太郎
『好き好き大好き超愛してる。』
講談社 200416冊目⑯舞城王太郎
『ビッチマグネット』
新潮社 200917冊目⑰舞城王太郎『キミトピア』
(「美味しいシャワーヘッド」)
新潮社 2013舞城王太郎は僕の中で読書が結構早かったんですよねだから だいぶ読んでます舞城王太郎は元々メフィスト賞って言って講談社がやってるミステリ系の小説がデビューなんですがのちに純文学にやってきて芥川賞候補にめちゃくちゃなるんですよねこの後に『短篇五芒星』っていうのも
芥川賞候補になるんですが それも取れず結局 芥川賞は取らなかったとしかし三島由紀夫賞で
『阿修羅ガール』ってのを
取ってたりとかして独自の世界観で独自の路線で突き進んでるんですよね僕も舞城にハマってたのが大学生だったからね集中して再読を
どんどんやっていこうかな
と思ってはおりますねそんな感じでこの17冊を紹介してきましたけど今は僕は芥川賞の候補が発表されたら全部読んで全部 動画で感想を言うのをやってますが昔はもちろんしていなかったんでこの時代の芥川賞候補って
見たり調べたりするのが
めっちゃ面白いんだねもちろん2000年代〜2010年代とか
ちょっと古い文学になりますがその辺も詳しくなりたいなと
ホントに思っておりますねそんな感じで今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#957「【16選】伝説の編集長・矢野優のオススメの純文学16冊を見ていこう!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと「新潮」矢野 前編集長の16冊先日 文芸誌の「新潮」っていう雑誌があってそれの編集長の矢野優さんっていう人が
ご退任なさったっていう話なんですね矢野さんは
なんと新潮の編集長を
21年間やってたっていう伝説の編集長って
言われてるんですねその人が先日 ご退任なさった時 新潮の企画で矢野編集長が選ぶ
「この純文学が面白い16冊」
っていうのを出してたんですよ僕はこういう「◯◯の何冊」みたいな大好きなんで動画にしたっていう話でございます早速やっていきましょう1冊ずつ言っていきますが1冊目①大江健三郎
『空の怪物アグイー』新潮といえば大江健三郎のイメージあるわ『空の怪物アグイー』は昔に読んだっきりで本当に覚えてないし 再読しなきゃいけないなと思う大江健三郎の新潮文庫は全部揃えてますよ茶色い背表紙のやつね表紙にミャクミャク様みたいな変な人の顔っていうか目玉みたいなが映ってるシリーズの表紙でしたよねあれ好きだったなあ2冊目②堀江敏幸
『雪沼とその周辺』川端康成文学賞の
「スタンス・ドット」が
入ってたりしてお得ですよ堀江敏幸も僕そんなに読めてないんでちょっと読んでいかなきゃなとは思ってますねザ・インテリみたいな文章な感じがするんだよねそこがめっちゃ惹かれるんだけどね3冊目③古井由吉『辻』内向の世代の代表的作家ですけど僕はそれほど読めてないんですよね昭和作家はそこまで深く読めてないからこの『辻』も読まなきゃなと思っております4冊目④円城塔『文字渦』円城塔自体は 結構 僕は読んでるつもりなんですけどね文学賞を取ったやつは大体読んでるんですけどこれは読めてない単行本の時点で読まなきゃなと思ってたら文庫化されちゃうんですよね「読書家あるある」でしょうけどね5冊目⑤筒井康隆
『モナドの領域』筒井康隆は僕はほぼほぼ全ての文庫本は読んでるつもりです大学生の時に読んでるからめちゃくちゃ僕の心に染みてるんですけどこの読書記録をつけてる3年間以内にはあんまり実は読めてなくて全部再読しなきゃと思うんですけど新潮文庫からは50〜60冊ほど
筒井康隆の文庫ってあるんですよね『モナドの領域』を筒井康隆の最後の長編作品ともちろん これも読んでおりますよGODが出てくるやつね超面白いよね すごいと思うわ6冊目⑥村上春樹
『東京奇譚集』村上春樹は5年前ぐらいかなほとんど全て読んだんですよね 代表的な作品はだけど また同じくだけど読書記録をつけてないもんでまた再読したいと思ってるんですよね僕が好きなのは
『神の子どもたちはみな踊る』
かなあ 新潮文庫で言えば7冊目⑦平野啓一郎
『日蝕・一月物語』「日蝕」を持ち込みして それで芥川賞を取ってるんですよねもちろん これも読んだことあります『日蝕』って中世ヨーロッパみたいな舞台でしょよく芥川賞を取ったなと思うよねあれ世紀末だったんですよね90年代終わりでしょその時代性があったのかなと思ってさあと『一月物語』も僕は読んだことありますが最初はバラで売ってたよね『日蝕』っていうのと『一月物語』っいうのは別々の文庫本も出てたんだけど これは合本なんだよね合本系の本って なんか嬉しくなってくるんだよね8冊目⑧町田康
『夫婦茶碗』町田康の初期の作品は僕は全部読んでますよ『きれぎれ』とか『屈辱ポンチ』とか『くっすん大黒』とか先日『きれぎれ』を再読しましてとても良かったね ああ町田康だと思ったこの『夫婦茶碗』も また近いうちに読もうと思ってます9冊目⑨小川洋子
『博士の愛した数式』これは第1回の本屋大賞を取ってる作品ですけど実は「新潮」掲載だったんですよね僕 これ 本屋大賞を取ってるから僕 これ 純文学じゃないのかなと思ってた時期が長くて調べると「新潮」掲載って書いててあっこれ「新潮」掲載かと思ったこれも読んだことありますよ
映画も見たことありますし名作中の名作だと僕は思いますね10冊目⑩川上弘美
『なめらかで熱くて甘苦しくて』川上弘美は初期の方は読んでますけどね『神様』とか『真鶴』とか『溺レる』
とかは あの辺りは読んでますけどやっぱり作品数が多いんですよねめちゃくちゃ本あるでしょうだけど『なめらかで熱くて甘苦しくて』は結構 他の人たちもこれは面白いって言ってるイメージあるんですよねだから これ ちょっと読まなきゃなと思って矢野編集長が言うんだったら
読まなきゃなと本当に思いますね11冊目⑪川上未映子
『ウィステリアと三人の女たち』川上未映子も 僕 小説に関しては読んでるよエッセイとかはそんなに実は読んでないですけど初期の方から あと『ヘヴン』とか『すべて真夜中の恋人たち』とかあの辺りは大体読んでるし『ウィステリア〜』も僕 読んだような覚えがあるんですけどやっぱり読書記録を付けなきゃね話も本当に忘れてるからこれもまた再読案件になるんですけどね12冊目⑫金原ひとみ
『マザーズ』金原ひとみも 僕 初期の方はよく読んでる金原ひとみさんも大量に本ありますから全部は読めてないこの『マザーズ』も僕が読めてなくてBunkamuraドゥマゴ文学賞を
取ってるのは知ってるんですけどちょっと読まなきゃなとは思ってますね13冊目⑬朝吹真理子
『TIMELESS』僕 朝吹真理子は『流跡』
『きことわ』は読んでるんですけどそのあと『TIMELESS』は長らく読めてなくてつい最近かな 文庫化されてあ〜『TIMELESS』も文庫化かと思ったわけ『きことわ』とか本当に良かったと思うよね芥川賞を取るべくして取ったっていう感じがあって『TIMELESS』も楽しみで仕方ないんだよな14冊目⑭上田岳弘
『太陽・惑星』上田岳弘は『太陽・惑星』の「太陽」で新潮新人賞を受賞し 作家デビューしてますから新潮組なわけですよねその後もずっと書いてるから偉いなと思う上田岳弘は僕の中では滝口悠生とか町屋良平とかその流れっていうか現代の文学を担っていく感じが僕あるんですよね定期的に年に1冊ぐらいは本を出してるし読んでいかなきゃなと思ってます15冊目⑮小山田浩子
『工場』小山田浩子は『工場』『穴』『庭』『小島』っていう4冊の小説が出てますけれども『小島』以外は読んでます小山田浩子も小山田浩子にしか
書けない小説だなと本当に思うわあまり改行しない 文字びっちりタイプの書き手でしょこれ 差別になるかもしれないけど女性であんまり文字びっちりタイプ
ってあんまりいないイメージあるんだよねだから特別感があって すごいなって本当に思うね16冊目⑯千葉雅也
『デッドライン』この中では1番新しいんじゃないかなと思いますけど千葉雅也『デッドライン』ももちろん僕は読んでおりますよ芥川賞の候補にもなってましたし千葉雅也さんはその後に『オーバーヒート』と『エレクトリック』がありますよね私小説なんだけど 同性愛っていうかゲイのテーマとあと哲学的な アカデミックな感じも
合わさって面白かったですよねそんな感じで この16冊を紹介しましたが僕 本当に こういう「◯◯さんのオススメ何冊」みたいなの大好きでいわゆるブックガイドになるんでこれ 新潮の編集長がやったわけだけど各種文芸誌の編集長 やってほしいし別に編集長じゃなくても編集者さんとか書評家さんとか誰でもいいんで「◯◯の何冊」みんな出してほしいそうすると みんなやっぱり それを狙って買うし特に純文学で こういうのはあんまりないんだよね純文学で こういうのを
誰か打ち出してほしいな
って本当に思いますね皆さんのオススメ10冊とか 5冊でもいいのでぜひありましたらコメントで教えてくださいいつも参考にさせていただいておりますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#956「」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#955「難解な文学を生み出す「群像新人文学賞」について語ろう!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと群像新人文学賞について語ろう群像新人文学賞っていうのは講談社がやっている純文学の公募型の新人賞ですね有名なところで言えば村上龍とか村上春樹とかを輩出している
伝統ある新人賞になってるんですけどなんで群像新人文学賞を取り上げようかと思ったかというと主に2つあって 1つは最近 群像新人文学賞の受賞作が最新のやつが発表されたんですねそこでオヤと思ったのと あともう1個は僕は他の新人賞はだいぶ過去に読んでるのが多くて作家もその受賞作も全くわからないみたいなそういうのってあんまりないんですけど群像新人文学賞だけ「難しい」っていうイメージもあって読んでない作品が結構あるのよそれを今月5月に 7冊 読んでいこうかなと思って読んでいくぞって思って
今回 取り上げるという
感じでございます早速やっていきましょうまず最新の
群像新人文学賞の話を
しようかと思うんですけど1〜2週間前ぐらいに最新作発表っていうニュースがあって受賞作と優秀作っていうのがあってそれぞれ1人ずついて受賞作が豊永浩平「月ぬ走いや、馬ぬ走い」
(ちちぬはいや、うんまぬはい)優秀作の方は白鳥一
「遠くから来ました」僕は実はですねこの豊永浩平さんっていうのを知ってるっていうかネットで知ってるぐらいなんだけど結構 前からTwitterで 僕は
フォローしてる関係だったんですねその人はめちゃくちゃ文学の話をしてて講談社文芸文庫とかどストレートな文学を
よく読んでたりとか
ツイートしてたりするんで僕はチェックしてたんですよそこからその人が「受賞しました」って言ってたんですよはぁ〜と思って僕 その前に文學界新人賞で旗原理沙子さんっていう人が
受賞したっていうニュースもあって旗原理沙子さんも 僕は直接 別に
喋ったことあるわけじゃないと思うけどネットで活動してたし同人誌とかよく書かれてたんで名前は知ってたんですよねだから そういう
知り合いっていうのかな
ネットの知り合いが2連続で しかも今年になって2人 新人賞を受賞する
ってことがあって なんか
すごいなあと思ってだから この豊永浩平さんの「月ぬ走いや、馬ぬ走い」
っていうのも
僕 読んでみようと思うし単行本も出たら買いたいなとは思ってるあと冒頭でも言ったけど僕は群像新人文学賞に
多分 苦手意識があるのか
わかんないけど群像新人文学賞ってめっちゃ難しいと思うわいわゆる「五大新人賞」って言って各出版社がやってる公募型の新人賞の中では1番難しいと言われているし実際そうだと思うんです僕はこうやって新人賞とかは過去の受賞作とか一覧にして こうやって持ってるんですよ読んだ作品に色を塗ったりとかしてるんですけど群像新人文学賞は塗れてないのが多いんですね2000年以降で考えた時
7冊 僕は読んでないんですよ
群像新人文学賞(単行本のみ)それを1個ずつ言っていくと1冊目①萩原享
『蚤の心臓ファンクラブ』
講談社 2001萩原享さんは単行本これ1冊なんですねこれ 読もう読もうと思ってるし僕は持ってもいるんだけど 読めてないんですね2冊目②寺村朋輝
『死せる魂の幻想』
講談社 2002寺村朋輝さんもこの1冊しかないですけどね③村田沙耶香
『授乳』
講談社 2005『授乳』は僕はめちゃくちゃ昔に読んだことあって結構 話も覚えてるんですけどこの3年以内に読んでいないんでいわゆる読書記録を取っていないので再読したいと思っていますね4冊目④十文字実香
『狐寝入夢虜』
講談社 2005十文字実香さんもこの1冊しかないんですがこれ今 Amazonでめちゃくちゃ
高くなってるんですよね(29980円)僕もこれは持ってない5冊目⑤望月あんね
『グルメな女と優しい男』
講談社 2005この作品も読めてないですね6冊目⑥淺川継太「朝が止まる」
(『ある日の結婚』講談社 2014)これ確か野間文芸新人賞の候補になってるんですけどこれも昔から単行本を持ってたんだけど読めてないんですね7冊目⑦李琴峰
『独り舞』
講談社 2018それのデビュー作が この『独り舞』なんですね僕は芥川賞を取ってる作家は過去作は全部読んでいきたいと思ってるんだけど微妙に読めてなかったんだよね群像新人文学賞は
他にも有名な作家とか
よく出ているんですけど例えば今人気のある乗代雄介
『十七八より』
講談社 2015例えば芥川賞を取った石沢麻依
『貝に続く場所にて』
講談社 2021他には諏訪哲史
『アサッテの人』
講談社 2007文学好きでは有名な丸岡大介
『カメレオン狂のための戦争学習帳』
講談社 2009この辺りは僕は全部読んでいるわけですよあと群像新人文学賞を他に言えば佐藤憲胤(佐藤究)
『サージウスの死神』
講談社 2005『テスカトリポカ』で直木賞を取った作家がいるんだけどこの人は元々は純文学作家で ここ出身でのちに江戸川乱歩賞を取ってエンタメの方に行くんですけど島本理生
『シルエット』
講談社 2001のちに『ファーストラヴ』で
直木賞を受賞してるんですけどこの人も元々芥川賞の候補とか何回もなってその後に直木賞を取るってことなんだけど2000年より前だったら阿部和重
『アメリカの夜』
講談社 1994阿部和重も全部読まなきゃいけないぐらいの凄い凄いと言われ続けている作家なんですけど多和田葉子「かかとを失くして」
(『三人関係』講談社 1992)多和田葉子は今だったらノーベル文学賞の候補に
なっているんじゃないかと言われてたりもしますし多和田葉子も全部読まなきゃいけないんですけどあと最近の作家で マイナーなんだけど
僕がビビビって来た小説を言えば横田創
『(世界記録)』
講談社 2000文学好きからすると
かなりすごいと言われている
作家がいるんですねこの人も群像出身だったり早川大介
『ジャイロ!』
講談社 2002早川大介は「十三不塔」と言って(別名義)
今 ハヤカワ文庫とかから本が出てたりするいわゆるSF作家になってるんですけど元々は群像出身なんですよ樋口直哉
『さよならアメリカ』
講談社 2005これは『箱男』をリスペクトしてて紙袋を頭につけて街を放浪するって主人公がいるみたいな最終的に病院か刑務所に連れられてそこから脱獄するかしないかみたいな変な話になってくるんですけど良かったですよ崔実
『ジニのパズル』
講談社 2016島口大樹
『鳥がぼくらは祈り、』
講談社 2021最近の群像新人文学賞は
結構 単行本化するんですよ佳作・優秀作とかはあまりされにくいんですけど当選作・受賞作はほとんど
単行本化されていますので
嬉しい限りですねダブル村上を輩出している新人賞ですけど五大新人賞の中でエンタメ色はほとんどないでしょ純文学寄りの めちゃくちゃ難解な ザ・文学みたいのが基本的に集まってくる新人賞だと思うんで作家になりたい 純文学を書いてて
新人賞を応募してます みたいな人は群像新人文学賞の過去作を読むと「純文学の極北」が分かってくると思うんですよ「純文学とは何ぞや」は
群像を読むべしという
感じはしてるんですよね僕もあと7冊は読んでないんでとりあえず あと7冊
読んでいきたいなと
思っておりますねそんな感じでございます皆さんは好きな群像新人文学賞の受賞作はありますかぜひコメントの方に書いてもらえればと思っておりますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#954「【12選】単行本化されていない芥川賞候補12作品を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと芥川賞候補の中で
まだ単行本化されていない12作品を
言っていくっていう動画です今回 かなりマニアックなんですけど基本的に僕は芥川賞が大好きなんですけど受賞作の前に候補作っていうのが選出されてその内から受賞作を選ぶわけなんですけれど基本的に候補作は雑誌に掲載されないと選ばれないんですね雑誌に掲載されて それが単行本化することがあるんですしかし今回 特に2000年以降に限定しますが2000〜2023年の下半期まで
単行本化されていない作品が
12作品あるんですねこれは少ない方です何でかというと2000〜2023年の芥川賞の候補作を全て言えば257作品あるんですね257作品の内の12作品なんでごくごく一部なんだけど 単行本化されてなくてこれ ぜひ出版社さんに単行本化してほしいと思ってこの動画を作ることにしました早速やっていきましょう1作品目第126回 芥川賞
(2001年 下半期)①石黒達昌「真夜中の方へ」
(文學界 2001年10月号)石黒達昌さんというのは『最終上映』で海燕新人文学賞を受賞して作家デビュー結構 芥川賞の候補になっているんですが芥川賞は取らなかったんですね他のいくつかの作品は単行本化されていますがこれだけ単行本化されていないということですね2作品目第132回 芥川賞
(2004年 下半期)②井村恭一「不在の姉」
(文學界 2004年9月号)この井村恭一さんってあんまり名前知らないでしょう僕は知らなかったんだけどこの人なんと『ベイスボイル・ブック』で
日本ファンタジーノベル大賞を取って
作家デビューしてるんだってだから多分エンタメなんだよねだけど文學界で掲載してますので(「不在の姉」)芥川賞候補になったんだけど
単行本化されていない
ということですね3作品目第133回 芥川賞
(2005年 上半期)③楠見朋彦「小鳥の母」
(文學界 2005年6月号)楠見朋彦さんは『零歳の詩人』というので
すばる文学賞を受賞して作家デビューしてますがこの人も何個か芥川賞候補になったんですが最終的に芥川賞を取っていないんですねというか 今回12作品をあげると全員 芥川賞を最終的に取ってないんですね芥川賞を取ると やっぱり人気作家になって過去の候補作とか そういうのも単行本化されるんですよだけど芥川賞を取らないだけで
これだけ差が出るかっていうぐらい単行本化されない作品が
文芸誌の中で眠ったまんま
なんですよねこれ 超もったいないんですよねだから芥川賞を取ると取らんでは本当に全然違うんでみんな頑張って取ってほしいと思いますね4作品目第136回 芥川賞
(2006年 下半期)④佐川光晴「家族の肖像」
(文學界 2006年12月号)佐川光晴は『生活の設計』で
新潮新人賞を取って作家デビューのちに『縮んだ愛』で
野間文芸新人賞も取ってる
作家なんですが芥川賞は取れなかったということです5作品目第137回 芥川賞
(2007年 上半期)⑤松井雪子「アウラ アウラ」
(文學界 2007年3月号)松井雪子さんって元々漫画家なんですけど途中で作家デビューするんだよね4回ぐらい芥川賞の候補になってるんですが取らないまんまということで 僕もこの辺になってくると過去の1〜2作品ぐらい読んでくる作家が増えてきて面白いのになあ〜と思う時はありますね6作品目第143回 芥川賞
(2010年 上半期)⑥シリン・ネザマフィ「拍動」
(文學界 2010年6月号 )シリン・ネザマフィさんっていうのは「白い紙」で
文學界新人賞を受賞して作家デビューしています「白い紙」も芥川賞候補になっていて
これは単行本化されているんですねこの「拍動」だけが単行本化されていないと7作品目第144回 芥川賞
(2010年 下半期)⑦穂田川洋山「あぶらびれ」
文學界 2010年 11月号穂田川洋山は「自由高さH」で
文學界新人賞を受賞し作家デビュー
しているということですね「自由高さH」も
芥川賞候補になっていて
単行本にもなっているんですがこの「あぶらびれ」はなっていないんですね8作品目第145回 芥川賞
(2011年 上半期)⑧水原涼「甘露」
(文學界 2011年6月号)水原涼さんは この「甘露」で
文學界新人賞を受賞し作家デビュー
しているということですね水原涼さんは のちに『蹴爪 ボラン』
っていう作品が単行本になっているんですが作品数もめちゃくちゃあるんですけどなぜか単行本化されない作家さんなんだよねどんどん出してってほしいですけどね9作品目第146回 芥川賞
(2011年 下半期)⑨広小路尚祈「まちなか」
(文學界 2011年8月号)広小路尚祈さんは「だだだな町、ぐぐぐなおれ」で
群像新人文学賞の優秀作を受賞し作家デビューしています他の作家も同じなんだけど大体2〜3回ぐらい芥川賞の候補になるんですが最初の2〜3回は単行本化されるのに最後の1作品は単行本化されないままシュンと消えてしまうみたいなことが多いそれ なんかもったいないんだよねこういうところも
単行本化してくれたら嬉しいな
って本当に思うけどね10作品目第146回 芥川賞
(2011年 下半期)⑩吉井磨弥「七月のばか」
(文學界 2011年11月号)吉井磨弥は「ゴルディータは食べて、寝て、働くだけ」で
文學界新人賞を受賞して作家デビューしています今まで単行本が1冊もありませんいやあ〜 ほしいね僕は1作品でも単行本になっていると少なくとも後の歴史に残ると思うんで新人賞を取ったのに
単行本化されないっていうのが
悲しいなと思いますね11作品目第147回 芥川賞
(2012年 上半期)⑪鈴木善徳「河童日誌」
(文學界 2012年5月号)鈴木善徳は「髪魚」で
文學界新人賞を受賞して
作家デビューしてるんですがこの鈴木善徳さんも単行本が1冊もないんですねこういう作家たちをまとめて
1冊 本とか出せないのかな〜って
僕は思ったりするんですけど
どうでしょうか12作品目(最後)第148回 芥川賞
(2012年 下半期)⑫北野道夫「関東平野」
(文學界 2012年9月号)北野道夫も「逃げ道」で
文學界新人賞を受賞し
作家デビューをしていますこれ 1つ傾向があって
なんと なんとですね12作品 全部 紹介しましたが
全て「文學界」掲載なんですね文學界に掲載されたものが
単行本化されてないんですねということは他の出版社は全て単行本化してるんですよこれ 2000年以降で この最後の
「関東平野」が2012年なんですね実は2012年以降の芥川賞候補は
全て単行本化されてるんですよつまり この直近10年間は
全ての芥川賞候補を単行本で
読めるんですねこれは本当にありがたい文學界は確かに中編作品なので単行本化するのに分量が足りないんですね多分 もう1個ぐらい
付け加えて単行本化しようって
文藝春秋は思ってたんだけど次の作品が出ずに そのまま単行本化計画が
消えてしまったっていうことだと僕は思ってるんですがだから文學界さんは もしくは文藝春秋さんはこの文學界に掲載の単行本化されてない12作品をアンソロジーとして1つの単行本 もしくは
2つの単行本に分けて出版
とかないのかなーって思って僕はそれが1番綺麗だと思う「芥川賞候補 未単行本化集」
みたいなレーベルを作って単行本化してくれたら 嬉しいな〜って思う僕は絶対に買って読むし少部数でもいいから
出してほしいな〜って
僕は本当に思いますそんな感じで今回 単行本化されていない
芥川賞候補を言ってきましたけど僕はどちらかというと単行本派なんですよね単行本にするのに
もちろんお金かかったりとか
すると思うんですけど候補になってたら のちの未来にそれを調べて読む人がいたら
読んでみようって思うんで候補作だけでいいんで
単行本化してほしいな〜
って思いますね マジで皆さんは単行本化されてないけど
この作品を単行本化してほしいみたいな
作品あったら ぜひコメントで教えてくださいそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#953「【50選】僕が読んだ短歌・歌集50冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと私つかつ 3月〜4月あたりに自分の中で短歌ブーム 来てまして50冊 読んだんですね今回の動画は 読んだ歌集を50冊どんどん言っていくっていう動画でございます早速やっていきましょう1冊目①くろだたけし
『踊れ始祖鳥』
ナナロク社 2023年ちょっと遠い図書館に行ったんですよそしたら この本がぽつんと置かれてたんですねこれ何だろうと思って手に取ったら歌集で歌集 読んだことないと思って
それを借りて読んだら面白かってここから僕の短歌ブームが
始まったと言っても
過言ではないんですけど2冊目②川野芽生『Lilith』
書肆侃侃房 2020年川野芽生さんは作家でもあるし芥川賞の候補にもなったんだけど元々出身がこれなんですね 短歌なんですとてもよかった 耽美的でよかったね3冊目③俵万智『サラダ記念日』
河出書房新社 1987年これで短歌界がめちゃくちゃ動いたっていうすごい短歌でもちろん僕も前々から知ってたし持ってたし読んでたけど改めて読むと とても良かったね4冊目④鳥居『キリンの子』
KADOKAWA 2016年鳥居さんっていう歌人は壮絶な人生があってそれが書かれてるんだよねかなり辛い短歌だったなと思います5冊目⑤吉田隼人
『忘却のための試論』
書肆侃侃房 2015年これ 表紙がすごくてこれは「さよならを教えて」っていうゲームのデザイナーの長岡建蔵っていう人が表紙を描いてるんだけどこの表紙にやられちゃうね中身もとても良かったね これ 本当に良かった6冊目⑥穂村弘
『シンジケート』
沖積舎 1990年講談社から新装版というのが今出てるんですけどこの『シンジケート』も短歌界をだいぶ
揺り動かしたっていうすごい歌集でいわゆるニューウェブ短歌の1人でエッセイとかもたくさん穂村弘は出してますね7冊目⑦千種創一
『砂丘律』
青磁社 2015年これは今 ちくま文庫に入って読みやすくなってるんだよねこの作者さんは中東に住んでいて世界観が中東の感じなんですね独特で 瑞々しい感じがあって とても良かったね8冊目⑧平岡直子
『みじかい髪も長い髪も炎』
本阿弥書店 2021年この辺りから僕が意識したのは「現代歌人協会賞」っていう短歌の賞があってこれが いわゆる短歌界でいう
芥川賞みたいな賞らしいんですよねこの本も取ってるし この前に紹介した本もこの後に紹介している本も結構それを狙って 僕 読んでるんで とてもいいですよね9冊目⑨笹公人
『抒情の奇妙な冒険』
早川書房 2008年笹公人さんって全体的にゆるふわ系で色んなオマージュとか 実際の
固有名詞とかをたくさん使ってて笑い系の短歌っていうイメージがあるんだよねこれめっちゃよかったよ 面白かった10冊目⑩佐佐木定綱『月を食う』
KADOKAWA 2019年この佐佐木定綱は
実はお父さんが
佐佐木幸綱っていってその人も有名な歌人なんですよねだから父子として
二代で歌人やってるっていう
面白い一族なんだよね11冊目⑪千葉聡
『グラウンドを駆けるモーツァルト』
KADOKAWA 2021年千葉聡さんって有名な歌人で
先生もされてるんですよね自分が勤めてる学校の生徒たちのことを歌ったりとか自分が先生として何ができるかとかそういうのを書いてて職業的な面白さがあるんだよね12冊目⑫大森静佳
『てのひらを燃やす』
角川学芸出版 2013年これも新装版が出てて 読みやすくなってるんですけどこの大森静佳って 色んな短歌の
賞の選考委員をやっていたりして有名な歌人ではあるんですよね13冊目⑬鈴木ちはね『予言』
書肆侃侃房 2020年これは「笹井宏之賞」っていう書肆侃侃房がやってる新人賞があるんですけどそれを取った短歌になるんですよね14冊目⑭雪舟えま
『たんぽるぽる』
短歌研究社 2011年雪舟えまさんは歌人ですけど小説家としてめちゃくちゃ活動をしていて小説の方は僕は読んだことないんでそっちも読みたいなと思ってます15冊目⑮木下龍也
『あなたのための短歌集』
ナナロク社 2021年木下龍也さんっていうのは 今
若者たちに人気のある歌人の1人でこの人自身が短歌を1首1首ネットで売ってた時期があってそれをまとめたのがこれらしいのよ試みもまず面白いなと思いますね16冊目⑯笹井宏之『ひとさらい』
BookPark 2008年今は書肆侃侃房から新装版が出ててこれが笹井宏之さんなんだけど若くして亡くなっちゃったんですよねでもレジェンド的な扱いでちくま文庫で笹井宏之の歌集が出ててそっちの方が手に入りやすいと思うけどね17冊目⑰上坂あゆ美
『老人ホームで死ぬほどモテたい』
書肆侃侃房 2022年この辺りから書肆侃侃房の
「新鋭短歌シリーズ」
っていうシリーズがあってそれを意識して読むようにしてますね短歌ってどれから読んだらいいか
わかんないってことあると思うんだけどレーベルみたいのが出ててそれをずっと読むっていうのも
いいと思ったりしますね18冊目⑱岡野大嗣
『うれしい近況』
太田出版 2023年岡野大嗣さんもさっきの
木下龍也さん同様に
若者に人気のある歌人で読むとなるほどって思うわこれは音楽的な歌が多かったと思うんですよね19冊目⑲初谷むい
『わたしの嫌いな桃源郷』
書肆侃侃房 2022年書肆侃侃房って僕 小説のイメージめちゃくちゃあって面白い小説を出してるんですけど短歌もいいんだねむしろ短歌の方がめちゃくちゃ力を入れてる感じが今回 50冊 読んで なるほどって思って分かりましたね20冊目⑳榊原紘『koro』
書肆侃侃房 2023年この榊原紘さんもこの本ではないんだけど前の本が笹井宏之賞 確か取っててそれでデビューしている歌人だったと思いますね21冊目㉑東直子
『春原さんのリコーダー』
本阿弥書店 1996年この本はちくま文庫からも新装版が出てるんですけど東直子さんも歌人ですけど小説とかの方がめっちゃ刊行されている作家ではありますね22冊目㉒上篠翔
『エモーショナルきりん大全』
書肆侃侃房 2021年この辺りから
僕の中で短歌のイメージ
ぶっ壊されてきてるんだよね短歌ってこんなのもアリなんだみたいなだいたいエモさが絶対に入ってくるんだけどエモさ+言語実験な感じで良かったね23冊目㉓谷川由里子
『サワーマッシュ』
左右社 2021年左右社っていう出版社もあってもちろんのことだけど書肆侃侃房とは違う短歌の道を進んでる感じがあるんだよね今回50冊 左右社 いくつかもちろん読んでるんだけど書肆侃侃房の方が多いんですよ たぶん個人的にだから左右社の本 もっと読みたいと思いましたね24冊目㉔工藤玲音
『水中で口笛』
左右社 2021年工藤玲音さんっていうのは 今 エッセイストとかもしくは『氷柱の声』っていうので
芥川賞の候補にもなってるんですよねそっちのほうが強いかもしれないけど
実は短歌を嗜んでいるということですね25冊目㉕笹川諒『水の聖歌隊』
書肆侃侃房 2021年これもいわゆる新鋭短歌シリーズって言われる1冊で新鋭短歌シリーズってやっぱり面白いねしかし入手が難しい感じがあるというか僕は図書館を使ってたんだけどあんまり図書館に歌集ってないんだね大阪でも中々歌集を専門的に取り扱ってる図書館がなくてめっちゃ あちこち見て回りましたよ僕もっと歌集が売れてほしいね26冊目㉖九螺ささら
『ゆめのほとり鳥』
書肆侃侃房 2018年九螺ささらさんっていうのは僕 名前を知っててこの本ではないんだけどBunkamuraドゥマゴ賞を
『神様の住所』っていうので
取ってるんですよね短歌系でドゥマゴ賞とか取ることもあるんだね短歌も文学の領域の1つではありますから全般的に知っておく必要があるなって思いました27冊目㉗黒瀬珂瀾
『蓮喰ひ人の日記』
短歌研究社 2015年書いてる人がイギリス・イングランドに何年か行かなきゃいけなくなっちゃってそういうことを日記として短歌でずっと綴ってるんですよ昔のいわゆる古典的仮名遣いみたいなので
書かれてるから雰囲気が出てるんだよね短歌って多分唯一古典的仮名遣いが許されてると思うんですもちろん小説とか詩とかでもやってもいいと思うんですけど短歌は違和感ないんだよね やってもだから この読んだ本の中でも
古典的仮名遣いで ずっと
書いてる短歌もいっぱいあってちょっと勉強したいと思ったもんその面白さがあるな 短歌には28冊目㉘荻原裕幸
『永遠より少し短い日常』
書肆侃侃房 2022年この荻原裕幸さんも いわゆる
穂村弘と同じくニューウェーブの
歌人って言われててこの本も昔ながらの短歌にまどか☆マギカとか最近のアニメとかを入れてたりとかして刺激的で良かったです29冊目㉙永井祐
『広い世界と2や8や7』
左右社 2020年この本 ふざけてたねあのね ふざけてるというかとても簡単な 子供が書いたみたいな
短歌がめちゃくちゃ多いんですよ子供が書いた短歌って
「食べたらおいしいな」
みたいな そんなんでしょ逆に新鮮で めっちゃ付箋を貼ったもん僕僕 短歌を読む時に だいぶ付箋を貼ったんですけどこの本 めっちゃ付箋が多かったな30冊目㉚萩原慎一郎『滑走路』
KADOKAWA 2017年この作者の方も実は亡くなってて自ら命を絶ったっていう人でもあるんだよね映画化とかもされてるんですけど率直な感じがあってよかった「明日は頑張れるぞ」みたいな
応援ソングみたいな短歌があってとても良かったですね31冊目㉛加藤千恵
『ハッピー☆アイスクリーム』
マーブルトロン 2001年今 中公文庫とか集英社文庫で新装版が出ています加藤千恵さんっていうのは
歌人ってよく言われるんだけど同じく小説の方がめちゃくちゃ今出てるんですよね『ハッピー☆アイスクリーム』ってデビュー作なんだけどこの時 高校生なんだよねザ・女子高生みたいな そんな歌が多かったですね32冊目㉜寺井奈緒美
『アーのようなカー』
書肆侃侃房 2019年これもいわゆる新鋭短歌シリーズの1冊ですね世界観がとても良かったし表紙の絵が旦那さんが描いてるらしい途中で絵がいくつか入ってるんだけど旦那さんが描いたらしいんですね33冊目㉝田村穂隆
『湖とファルセット』
KADOKAWA 2023年この本は2023年の いわゆる最新の
現代歌人協会賞を取っている歌集で僕は現代詩を
ずっと読んでた時も
あったんだけどその時も文学賞っていうのを大事にしたんですよ現代詩の場合は
中原中也賞とH氏賞
っていうのが新人賞であってたぶん短歌は現代歌人協会賞が大事なんですよねだから僕 これから もし短歌を
もちろん読んでいくと思うんですけど現代歌人協会賞は最新作が出てきたら
読んでいこうとは思っていますよ34冊目㉞鈴木加成太
『うすがみの銀河』
現代短歌社 2022年これも実はさっきの『湖とファルセット』と同時に現代歌人協会賞を取ってるんですよねこの2つは最新の現代歌人協会賞だけど短歌って色んな色があるんだね色んな味があると言ってもいいけど よかったね35冊目㉟服部真里子
『行け広野へと』
本阿弥書店 2014年これも現代歌人協会賞ですけどさっきも言ったけど図書館に現代歌人協会賞すらなかったりしますね短歌って趣味としてやってる人が1000万人いるとか言ってツイッターとかで人気あるんだけど歌集自体はあんまり出回ってないのかな昔の本だったら特に高くなってて
買えないっていうことがあるんですよねやっぱりマイナーな出版社から出たりするとすぐ絶版になって のちのち名前だけが残って復刊とか新装版とかが出ることが多いんですよ短歌ってそういう文化があるっぽい絶版本を探していったりとか
読んでったりする楽しみもあるのかな
って思ったりする36冊目㊱犬養楓『前線』
書肆侃侃房 2021年この犬養楓さんというのはお医者さんでちょうど これコロナ禍の時でコロナの対策の現場にいるお医者さんだったらしいんですよだからコロナ短歌みたいなでずっとこれコロナのことが書かれている短歌なんだよね今はあんまりコロナのことを言われないけど当時 数年前なんかめっちゃ騒いでたでしょだからその時の雰囲気が味わえるね 良かった37冊目㊲谷川電話
『深呼吸広場』
書肆侃侃房 2022年谷川電話さんも不思議な世界観で書いてるよねこの前に『恋人不死身説』っていう歌集が出てるんだけどそっちは読んでないんですけどこの本は世界観がぶっ壊れてたこれも言語実験というか なんか最近の令和の短歌っていう感じがあって良かったな38冊目㊳林あまり
『マース・エンジェル』
沖積舎 1986年これも河出文庫から新装版が出てるんだけど林あまりも有名な歌人でこれ 女性の性的なことが書いてたりとか生々しい恋の話みたいなのを歌で書いてて刺激的でよかったよ現代短歌って80年以降ぐらいを多分 指してると思うんですというのは こういう林あまりとか俵万智とか穂村弘とかが出てきてからめちゃくちゃ新鮮になった
口語的になったって言われるからその辺以降の短歌がやっぱり面白い39冊目㊴佐藤モニカ
『夏の領域』
本阿弥書店 2017年この佐藤モニカさんは詩・小説も書いてるんですよね小説は単行本になってないけど確か「文學界」で 昔 掲載があったりとか意外と 僕の感じでは純文学作家と歌人って
あんまり関わりづらい気が
してるんだよ どうなんだろうもちろん工藤玲音さんとかも 芥川賞の
候補になったりとかあるんですけど意外と現代詩とかの方が 純文学に
近づく傾向があると思うんですよ短歌は純文学の方に
近いってことは
あまりないイメージあるだけど その辺の関わりも調べると面白いね40冊目㊵飯田有子
『林檎貫通式』
BookPark 2001年今 これ 書肆侃侃房から新装版で出てて書肆侃侃房って さっき言った
「新鋭短歌シリーズ」っていう
レーベルがあってこれは最近の歌人の本を出すんですけど「現代短歌クラシックス」っていうレーベルがあってこれこそ昔に出たっきり絶版で手に入らないっていうのを新装版で復刊するっていうシリーズがあってそれの1作目がこれになってるのよこれもレジェンドの歌集らしくて新しい読み方としてフェミニズム的な読み方ができるとかで人気になって復刊したらしいんだけど41冊目㊶小島なお『乱反射』
角川書店 2007年これもさっき言った現代短歌クラシックスのうちの1冊ですこの小島なおも実はお母さんが小島ゆかりって言って有名な歌人ではあるんですよねこの『乱反射』は実は映画化もされてるんですよね僕 映画は見てないけど
予告編とか見ると
面白そうなんだよねまた映画を見たいと思う42冊目㊷石川美南
『砂の降る教室』
風媒社 2003年これもさっきと同じく現代短歌クラシックスの1冊ですねこれも独自の世界観で良かったですよ変わってる短歌って感じそういう歌集もあるんだね43冊目㊸井辻朱美
『コリオリの風』
河出書房新社 1993年この井辻朱美さんっていうのは
SF短歌っていうのが有名らしくて宇宙船から地球を眺めているとかもしくは恐竜の話をしているとか隕石の話をするとか
そういう短歌を
多く残してるんですよねとんでもない時間の中での人類の悲しみみたいのを描けてまた別の面白さがあるんですよね とてもよかった44冊目㊹渡辺松男『寒気氾濫』
本阿弥書店 1997年今はさっき言った現代短歌クラシックスに入っていますこの本で現代歌人協会賞も取ってたりしますね45冊目㊺正岡豊『四月の魚』
まろうど社 1990年これもさっき言った現代短歌クラシックスに入っています現代短歌クラシックスは12巻あるみたいですね12巻だったら集められないこともないから集めたいんだよな新鋭短歌シリーズは40冊以上出てるからなかなか集めにくいんですけど46冊目㊻枡野浩一『毎日のように手紙は来るけれど
あなた以外の人からである』左右社 2022年枡野浩一さんも短歌はもちろん書いてるんですけど小説とかも多く書かれていて僕は小説とか昔は読んだことがあって初めて歌集を読んだけど良かったねこれもメッセージみたいな感じで応援ソングじゃないけど格言みたいな短歌が多い感じがするね47冊目㊼岡本真帆
『水上バス浅草行き』
ナナロク社 2022年とても良かったね
現代的な感覚っていうのかな短歌って多分 その時の時代の感覚
みたいなのが大事だと思うんですよそういうのをバシっと掴めていると短歌として素晴らしいと思うよね48冊目㊽内山晶太
『窓、その他』
六花書林 2012年これもさっきの
現代短歌クラシックスの
うちの1つに入ってますねこの本 とても良かったね昔ながらの難しい短歌みたいなのが書かれてる感じだけど雰囲気が綺麗な感じがするわ透き通ってる短歌っていう感じかな歌集全体を通しての雰囲気とか空気感とかそういうのはあるんだなと思って統一されているような
コンセプチュアルな歌集
ってあるんだなと思いました49冊目㊾道浦母都子
『無援の抒情』
雁書館 1980年これは 今 岩波現代文庫とかに入っててこの作者の人が学生闘争でずっとやってた人らしくて当時の学生闘争の歌をずっと書いてたっていうので勉強になった
出てくるワードとか調べたりして
なるほどって思ったりしました50冊目㊿水原紫苑
『えぴすとれー』
本阿弥書店 2017年水原紫苑さんというのはかなり有名な歌人の人でかなり端正な古典的仮名遣いで書かれてるんですよこの本自体が「紫式部文学賞」っていうのを取ってまして紫式部文学賞っていうのは
女性に与えられる文学賞の1つ
なんだけど小説とかが多いんですけど これ短歌なんだよねこれ 最後に持ってきたのは
700首ぐらい入ってるんですよ普通の歌集って300〜350首ぐらいの間らしいんですけどこれ 倍ぐらいあるんだよねかなり読むの時間かかったんですけど 良かったですねこういう昔ながらの短歌も読むと面白いなと思いましたそんな感じで今回 僕が読んだ短歌50冊を紹介しましたけどこれで 僕 短歌 いつでも また戻れると思った全く知らないものを手出すのって勇気が必要じゃないですかこれでまた読みたくなった歌集が出てきたらパッと読めるし全然入りやすくなったなと思って僕の文学的な立ち位置もちょっと変わったなと思いましたね短歌って面白いんだねそれを発見できたのが2024年の収穫だったと思いますね今度 来年ぐらいかな俳句とか川柳とか そういうのにも
手を出したいなと思っておりますねそんな感じでございます皆さまが好きな歌人とか
歌集とかありましたら
ぜひコメントで教えてくださいそんな感じで 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#952「」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#951「三島由紀夫賞の候補5作品が発表されました!それを1つずつ見ていきます!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと「第37回 三島由紀夫賞の候補作」が
2024年4月19日に発表されたんですね今回 それを見ていこうという動画なんですけど「三島由紀夫賞」というのは新人賞三賞って言って純文学の非公募型の新人賞3つのうちの1つです芥川賞と野間文芸新人賞と三島由紀夫賞結構デカい賞なんで 受賞するとまあまあ仕事が来るんじゃないかって言われるぐらいのすごい賞ではありますだから僕も注目してるんだけど早速やっていきましょう候補作品 5つありましてそれを1つずつ言っていくと1つ目①久栖博季
「ウミガメを砕く」
新潮 2023年6月号2つ目②小砂川チト
『猿の戴冠式』
講談社 2024年1月3つ目③鈴木涼美『YUKARI』
徳間書店 2024年1月4つ目④大田ステファニー歓人
『みどりいせき』
集英社 2024年2月5つ目⑤間宮改衣
『ここはすべての夜明けまえ』
早川書房 2024年3月1つずつ見ていくと①久栖博季「ウミガメを砕く」これ 三島賞 入ってよかったなと思いますよ僕自身は読めてないんですけど今回 5つの候補のうち これだけが
まだ単行本化されてないんですねさらに久栖博季さんっていうのは2021年「彫刻の感想」っていうので新潮新人賞を受賞してデビューしてるんですよしかし これも単行本化されてないんですね久栖博季さんは今まで1つも単行本化がないわけですねしかし これ
ちょうど 僕「彫刻の感想」
だけ読んでるんですよしかも これ思い入れがあって僕が2年半前から毎日1冊読むっていうことを決めて月に30冊読むって決めて ずーっと続けてきてこの2年半で950冊ぐらい
読みに読みまくったことを
やってるんだけど実はそれって たまたま2年半前に図書館に行ったんですよ久しぶりに図書館に行った時にちょうど新潮新人賞の発表の時で「新潮」があったんですねその雑誌の「新潮」を読んでこの「彫刻の感想」を読んで 面白いって思ってそこから毎日本を読むようになったんでこれを久栖博季さんには僕は思い入れがあるのよ今回 この「ウミガメを砕く」が
三島賞候補になったんで
単行本化されてほしいんですよねだいたい こういう新人賞って
最近だったらノミネートされると
単行本化されることがありますプラス「ウミガメを砕く」と
もう1個「彫刻の感想」が
入ってほしいですね全然 これ ありえる話で『狭間の者たちへ』とか『息』とか 最近
新潮新人賞って単行本化する傾向にあってその時は単行本化しないんだけど
(受賞した時)2年後ぐらい経つと新しい作品と新潮新人賞作品がセットで
単行本化するって結構あるんですよそう思うと「ウミガメを砕く」は
そのパターンになってほしいね僕はよく言ってるけど
今まで1冊も単行本がない人にこういう新人賞のスポットライトを当てて
単行本化するっていうのが僕めちゃくちゃ嬉しいんで頑張ってほしい 久栖博季さんねちなみにプロフィールを言うと久栖博季さんは 1987年 北海道生まれ弘前大学大学院
中退と書いてますね
北海道在住らしいですね2人目 行きますと②小砂川チト『猿の戴冠式』これは前回の芥川賞の候補になりましたので僕はすでに読んでいますし小砂川チトさんといえば その前に2022年に『家庭用安心坑夫』っていうので
群像新人文学賞を受賞して作家デビューしそれも芥川賞の候補になってますので僕がこれは5つの候補作品で
唯一読んでいる候補は
『猿の戴冠式』になるんですね『猿の戴冠式』は お猿さんと
女の人の共通意識っていうのかな実は2人は別れたソウルメイトだったみたいなそれは妄想かもしれないんだけど
そういう話だったんだよね結構 良かったと思いますねこの人自体は1990年の岩手県盛岡市出身らしいんですけどこの人 慶應義塾大学の大学院に行ってるんですねしかも心理学科の方に行ってますんで心理学的な作風って感じは僕はしてるんですよね3人目に行くと③鈴木涼美『YUKARI』鈴木涼美さんは1983年生まれと作家・エッセイスト・コメンテーター・元日本経済新聞社記者東京大学大学院の修士課程を取ってるらしいですがこれもよくよく言ってる話ですが結構 本を出してるんだけど2022年に小説『ギフテッド』
っていうので 芥川賞候補1回目『グレイスレス』で芥川賞候補2回
選ばれているっていう作家でその後に『浮き身』や『トラディション』っていうのがあり今回『YUKARI』が多分5冊目だと思うんですけど僕も『YUKARI』読んでなかったんだよなぁ僕は『ギフテッド』『グレイスレス 』『浮き身』まで
読んでて『トラディション』も読めてないんですけどこれ 1月刊行で僕 2月・3月は短歌の方 ずっと読んでましたので小説 新しいの 発表されたやつ
あんまり読めてないですよ 空白地帯でこの後 ちょっと頑張って
読んでいこうと思ってるんだけど特に徳間書店から出てるのが
三島賞候補になってるのが
面白いんだよね普通は五大文芸誌って言って講談社とか新潮社とか その辺が
純文学の新人賞に入るんだけどね今回 徳間が入っているのが
面白いというところかな4人目④大田ステファニー歓人『みどりいせき』この人は1995年に東京都生まれと2023年に今回『みどりいせき』で
すばる文学賞を受賞して作家デビューつまり新人というか 1冊目なんですよねすばる文学賞っていうのは
集英社の公募型の新人賞なんですけどこの『みどりいせき』も僕 読めてなくてちょうど これも2月に発売なんでうまく読めてなかったですよもちろん この後っていうか読むつもりはめちゃくちゃあるんですけど『みどりいせき』も評価がすごいと言われてて青春と闇バイトみたいなテーマだけどハチャメチャしてるとかいう噂を聞くこともあるからこれも面白そうなんだよねこういうのがドカッと受賞したりすると結構ニュースになったりするんですけど5冊目ですけれども⑤間宮改衣『ここはすべての夜明けまえ』これも いわゆる新人で間宮改衣さんは1992年 大分県出身これも2023年に「ここはすべての夜明けまえ』で第11回ハヤカワSFコンテスト
特別賞を受賞しデビューしている今回の三島賞でとりわけ注目するのは間宮改衣と久栖博季だと僕は思ってるんですね残りの3人は妥当な感じなんですよ間宮改衣さんに関しては早川なんでSFなんですよね普通 こういう三島賞とかにはあんまり こういう早川書房から
出たやつとかが入らないんですねなんでかというと 純文学の新人賞
という立ち位置だから(三島賞は)純文学って言ったら さっき言った五大文芸誌に掲載されたものが
基本的には候補になるんだけれどでも三島賞とか野間文芸新人賞の過去の候補作を見るとたまに純文学畑じゃなくて完全にエンタメ畑の人とかが入ることがあるんですよ芥川賞はほとんどないけどね芥川賞に関しては
五大文芸誌っていうのを
ほぼほぼ守ってるんだけど三島賞・野間文芸新人賞は実験的に
エンタメ作家が候補に入ることがあるんですねしかし この『ここはすべての夜明けまえ』は僕もTwitterとか見てると面白かったと言う人が結構いて評価は高いらしいですねこれはもちろん新人の1冊目になるわけだからこれからが期待っていう感じではありますけど三島賞候補に入るってこと自体がすごいしもし受賞とかすると 三島賞の歴史が
覆される感じはするとは思うんですよねだから ちょっと面白い
ダークホースっていう感じは
間宮改衣だと思ってるんだけどねそんな感じで 今回三島由紀夫賞 候補 5作品 見てきましたけど個人的には久栖博季が入ってることがとてもいい単行本化してください 新潮社さん お願いします僕も『猿の戴冠式』しか読んでませんけど他のももちろん順次読んでいくつもりですよ僕は芥川賞・野間賞・三島賞とかの
候補作もどんどん読んでいっているので受賞作だけじゃなくて 候補作から見ていくこと自体が最近の文学っていうのが分かってくるんでやっぱり面白いとは思う特に三島賞って尖った小説を
受賞させてるケースが多いもんで芥川賞より尖ってると僕は思ってますから皆々様 頑張っていただきたいと思っておりますね皆さんはどの作家が受賞すると思いますかもしよければコメントで教えてくださいそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#950「【購入】文学フリマで買った本17冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとめちゃくちゃ昔になるんですけど2023年9月10日に文学フリマ大阪11っていうのが開催されてたんです僕 これに行って そのVlog動画もあげたんですけどその後 購入本紹介の動画Part1っていうのあげたんですねそこで僕の買った本5冊 紹介してるんだけどPart2以降あげれてないんですよ数えると全部で22冊ぐらい買ってましてそのうち5冊だけなんで残り17冊紹介してないんですねそれをもう今回一気に紹介するっていう動画でございます早速やっていきましょう17冊あるんで パパパって紹介しますけど1冊目は『元祖オーケン伝説』曖昧書房さんっていうところから出てるっぽくて執筆陣が たかなんさん キタハラさんなどなど4人いてこれはオーケンなんで 大槻ケンヂですね筋肉少女帯とかで歌われた歌を小説化したっていう本ですね書かれてる歌を見ると
「ステーシー」=「再殺部隊」とかあと「釈迦」とか「人として軸がぶれている」とか有名な歌が書かれてますね続いて パパパって行くとコエヌマカズユキ『ヤクザ短歌』1人のヤクザと知り合いになってその人のことを歌にしたっていう歌らしいですよめっちゃ面白そうなんだよね僕は9月の時には多分 短歌って
ハマってなかったと思うんですけど今 めっちゃ短歌ブーム 来てるんで
ちょっと先取りしてたなと思いましたあと こちらですねこちらは数理文学研究会『円城塔研究』円城塔の評論って言ってもいいわけよ例えば『文字渦』の話とかやってるんだよねメビウスの輪がなんとかとか集合の集合が集合でないことの証明
とか言って難しそうなこと書いてるんだよね結構 面白そうだし Vol.1らしいからVol.2も出るかもしれないですね続いて こちら書肆喫茶mori
『海外マンガ読書ガイド 〜アジア編〜』いわゆるバンドデシネとか
フランスの漫画のことを言うけどこれはアジアで出た海外漫画をまとめたガイドなんですね韓国とか台湾とか中国とかタイとかそういう漫画が50冊ぐらい紹介されてますねこういう感じで
漫画の表紙とか写っていて
面白そうなんだよねこれもアジア編って書いてあるから
多分 他のもあるのかなと思ってあと こちらあって これはへにゃらぽっちぽー『ぽぽぽぽぽ』パッと開くじゃないですか 短編集なんですけどめっちゃ簡単な言葉で書かれてるんだよねぽぽぽぽぽ みたいな そういう擬音みたいのがかなり多くてひらがなを多用してて 独自の言語のようにも見えるのよこれシリーズみたいな感じでへにゃらぽっちぽーさんの文学フリマのお店の所に行ったらめちゃくちゃ こういうタイプの本 ありまくってて僕はたまたま これを取ったんだけど めっちゃあるからなんかハマるかもしれない この感覚はこれうまくやると なんかすっごいセンスだから何かが起こるかなと思ったりはしたあと続いて こちらですね手条萌
『教養としてのお笑い評論、あるいは30年史。』これはいわゆる お笑いの文化を
30年見ていこうという評論なんだけどパラパラめくると結構良くて「ゼロ年代お笑いクロニクル」とか「漫才論争 不寛容な社会と思想なき言及」っていう30年史って書いてるけど
1980年代ぐらいから書かれてて1981年に雑誌「マンスリーよしもと」創刊とか82年にNSC大阪校 開校そういうのを表にしてたりとか文学フリマって評論系 多いんですけどねお笑いとかはやってるの少ないような気がするめっちゃ面白い これあと続きまして こちらですね若林理央『後味の悪いマイナー映画20選』僕の動画も10選とか20選とか そういうの多いでしょこういうのに惹かれちゃうんだよなしかもこれ ホラーやグロテスクな描写のない
マイナーな名作映画を集めましたって書いてるのよ僕は映画ってあんまり詳しくないがちょこっとだけ言うとさよなら子供たちラブレス明日、君がいない修道女 とかそういうのあるみたいです僕も映画好きだから「映画100本見ました その感想」みたいな
そういう本あったら買いたいんですけど 同人誌でも続きまして こちらですねこちらは大阪大学SF研究部
『本当はこのループ作品がすごい!』表紙に写ってるのはキュゥべえだと思いますけどループものってもあるじゃないですか それの評論みたいしかも古今東西のループ作品を紹介「ループ作品ガイド100」っていうのもあったりとかあとループ作品の中身を徹底考察「ループ作品論25」っていう項目あったりとか結構 ありますよ 結構 項目あって200ページあるからね だいぶボリューミーですよこれ小説とかだけじゃなくて 映画とか漫画とかそういうのも全部入ってるのよかなりデータベースとして面白いと思うんですねAll You Need Is Killとか まどか☆マギカもあるし筒井康隆もあるし 西澤保彦とか その辺 入ってくるよねいいですね この本はめっちゃいいと思うあと こちらの本 買ってはるぱうす『「藪の中」考察』そのままだけど「藪の中」を考察してると芥川龍之介ですよ「藪の中」っていう 3人が3人とも違うことを言って犯人 誰やねんみたいな ミステリーなんだけど真実はわからないと 真実は藪の中という小説があるわけねそれを考察して本当は誰が犯人だったのかっていう そういう本ですねこういうのは評論だろうけど 文学ですからこういうのこそ文学フリマという感じしませんかこういう本があるから
文学フリマがあると
言ってもいいような気がするあと これだけあるんだけどまあまあ あるけど これは全部大学の文学研究部とかサークルとかが集めてるやつで大学のサークル系って文学フリマで結構出てるんだけど安く売ってたりとか 無料で
持ってていいですよって僕は言われてめちゃくちゃ無料でもらったんだけどこれ紹介しますとまずこちらですね関西大学現代文学研究部
『のうみそだま』9号9号ってついてるから いわゆる部誌みたいなやつだと思うね中を見ると いわゆるアンソロジーですよね僕も大学の文芸サークルに入ってましたからこういうのを作ったことあるんですけど部員たちに短編を書いてきてって言って それ集めて製本したっていう本みたいですねこういうのって意外と僕 持っておきたいタイプで全然 知らない大学でももしかしたら こういうところから
作家先生が生まれるとか全然あるからこういうのは欲しいタイプなんだよねあと これあってこちらが『Gegehben』104号甲南大学文化会文学研究会というのがあるらしくてそれの本ですねあと こちらが『Gegehben』105号こちらですね『幽世草子』大学の部誌は持ってても僕はいいと思ってますどのように製本してんのかなとかいう
ヒントになったりもするから僕 もらっててよかったなと思いましたあと最後なんですけどこれは名古屋市立大学文藝部
『緋櫻(あかさくら)』
2020年傑作選『緋櫻』傑作選 2021・2022『緋櫻』72号・ 77号これ4つもらってるんだけどこういうのって もらったら捨てられなくない?犬とか猫とかと例えていいのかわかんないけどちょっと情が移って こういうのもらうとせっかく製本までしてるから捨てられないんだよねこういうのも ちょびちょび 僕 読んでますよ面白いのあるんだよね いいですねそんな感じで 今回 紹介した本 こんだけあるんですよ前回 紹介した本も5冊あるんで全部で22冊あって いいですねまた文学フリマに行こうと思う大阪だったら 全然行ける距離にあるんで僕も12月にある文学フリマ東京で出品予定なんでねこういうのかなり 先輩方になるわけで 同人誌僕も学ばせていただきたいと思いましたね そんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#949「出版社60社を紹介します!あなたはこの中で好きな出版社はありますか?」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと出版社を60社 紹介しよう本好きさんだったら 好きな出版社があったりとかこの名作はこの出版社から出ているとかを
意識したりとかすると思うんですけど僕も出版社っていうのが めっちゃ好きなんですね今回 出版社60社 取り上げていく
っていう禁断の企画でございます早速やっていきましょうテンポよく ポンポンと言っていこうと思うんだけどまず純文学で言えば1.新潮社 2.講談社 3.文藝春秋
4.河出書房新社 5.集英社これらは文芸誌というものを持っていてそれぞれ新人賞とかもあって純文学を出している出版社になるわけですね続いて 純文学でプラスアルファがあるとすれば6.筑摩書房 7.朝日新聞出版 8.中央公論新社
9.書肆侃侃房 10.福武書店(ベネッセ)筑摩書房には太宰治賞があったりとか今はなき福武書店には
海燕新人文学賞が
あったりとかもあって朝日新聞出版には小説トリッパーが最近あるんでそこは芥川賞の候補が出たりとかもするから最近 僕 短歌にハマっていて
めちゃくちゃ歌集を読んでるんだけどその点で言えば
書肆侃侃房が短歌の方も
よく本を出してるんですよね「ことばと新人賞」って小説の新人賞もあるし
短歌は「笹井宏之賞」とかもやってるんだよねあと次の出版社に行くと11.岩波書店 12.国書刊行会
13.みすず書房 14.白水社 15.青土社岩波書店は岩波文庫があるわけで僕 めちゃくちゃ見つけたら買うようにしてるんだけどあと国書刊行会とか白水社とか青土社とかこの辺り 結構 高めの文学っていうかこの辺までチェックできる読書人に
なりたいな〜と個人的には思いますね続いて16.光文社 17.早川書房
18.幻戯書房 19.左右社 20.思潮社思潮社は現代詩の出版社で僕は去年 現代詩をめちゃくちゃ読んでたんだけど7割近くは思潮社ですよ思潮社って もう現代詩の出版社なんで現代詩をやるなら思潮社を
読まなきゃいけないぐらいの
出版社なんですよねあと早川は主にSFを出してるのがすごいよなって思うわ僕もハヤカワ文庫JAを集めてるんだけどSFをやろうと思ったらハヤカワ文庫を
避けては通れないとは思うんですけれどあと光文社 光文社古典新訳文庫あるでしょうあれも集めてるんだよね古典と言ったら 岩波文庫 強いけど選択できることはいいことだと思うんだけどね次の出版社に行くと21.水声社 22.平凡社
23.東京創元社(創元社)
24.双葉社 25.NHK出版水声社って海外文学が多い出版社で「フィクションの楽しみ」「フィクションのエル・ドラード」
っていう海外文学のレーベルを出してるんですよね平凡社も山下澄人『緑のさる』とか出してたりとかあと東京創元社って僕あんまり読んでないんですよね創元推理文庫とか創元SF文庫とか出してるでしょ僕 むしろ「創元社」って
東京がつかない創元社の方が
読んでたんですよなんでかって言うと 心理学の本をよく出すんです創元社はこの2つは元々1つだったけど独立したみたいな云々だったと思うんですけど次 行きますと26.星海社 27.角川書店
28.幻冬舎 29.小学館 30.徳間書店星海社 僕めっちゃ気になってるのよ星海社っていうのは 講談社系列の子会社
みたいなやつのイメージがあるんですけどいわゆるミステリとかをよく出してて
変わったミステリを出すイメージがあるもし僕がミステリを読むとしたら星海社系のミステリを
読んでいきたいなと
思ってるんだよねあと角川・幻冬舎・小学館とかは
結構 普通に小説を出すんだけど純文学は基本ないですよだけど直木賞関係で いわゆる
エンタメ小説とかよく出してるから僕も直木賞は読んでますから「これ幻冬舎か」とか思って読む時ありますね徳間書店に関しては 吉村萬壱が
よく本を出しているっていうイメージあと続いて31.リトルモア 32.扶桑社 33.ミシマ社
34.春陽堂書店 35.本の雑誌社この辺はあんまり読まないですよだけど 今回の60社っていうのは 基本的には僕がこの3年間で読んだ本があってそれを全部 僕 記録してるんですけど最低 僕がこの3年間で1冊以上は読んでる出版社になるんでリトルモアは「ストリートノベル大賞」
っていう小説の新人賞をやってたところで福永信とか宮崎誉子とかを輩出していて僕はこの2人めっちゃ好きなんでリトルモアの本はちょっとは読んでるんだよね続いて36.四谷ラウンド 37.晶文社
38.ナナロク社 39.ポプラ社 40.竹書房僕 四谷ラウンドっていうのが 最近 気になってて調べると 今はない出版社らしいんだけど向井豊昭っていう作家がいて
『BARABARA』って小説があるのよこれ 四谷ラウンドから出てて元々 早稲田文学新人賞 出身の人らしいんだけど四谷ラウンド たまに色々調べたら出てくる出版社なんですよ続きまして41.青林工藝舎 42.リイド社
43.秋田書店 44.白泉社 45.太田出版この5つは僕の中では漫画を出す出版社なんだよね僕も漫画好きなんですけどジャンプ・サンデーとかいう
そういう少年漫画系じゃなくて青年向けのサブカル漫画とかを僕は
調べたりとか読んだりするんだけれど大体 この辺に行き着くんだよね太田出版も最近
佐川恭一『就活闘争20XX』
っていうのを出してたけど『バトル・ロワイアル』も出してましたが意外と僕 昔やってた
「マンガ・エロティクス・エフ」
っていう漫画雑誌があって古屋兎丸とか山本直樹が書いてた漫画雑誌があるんですよそれが単行本化されて「F×COMICS」とか言ってそれずっと読んでたから太田出版って
漫画がすごいイメージあるんだよね続きまして46.イースト・プレス 47.七月堂 48.夏葉社
49.代わりに読む人 50.破滅派イースト・プレスも昔「COMIC CUE」って
漫画雑誌をよく出してたんですよねあと七月堂は現代詩をよく出してるんです中原中也賞を取ってるやつも
七月堂から出てるやつも
あるんですよね夏葉社は元祖「ひとり出版社」みたいなやつかな代わりに読む人も
佐川恭一『アドルムコ会全史』
っていう本がここから出てたりとかあと個人的に好きなのは破滅派かな破滅派は元々は小説家になろうみたいな
ネットの投稿サイトだったんだけど去年か一昨年ぐらいに出版社として活動することになって最近 出たのが ほろほろ落花生
『ぼくは君がなつかしい』
っていう本 出たんですよこれ読みたくて めっちゃ分厚いみたいだけど他の出版社としては51.亜紀書房 52.富士見書房 53.メディアワークス
54.マガジンハウス 55.書肆汽水域富士見書房とメディアワークスは
いわゆるラノベ系の出版社ですけどメディアワークスっていうのは
いわゆる電撃文庫の出版社ですけど富士見書房って「富士見ミステリー文庫」ってあって
結構 奇書が多いと言われてるんだよねあと書肆汽水域っていうのは
太田靖久『ののの』を
出している出版社で他に5〜6冊ぐらい本出てて 純文学系が多いですよ僕も全部 読みたいなとは思ってるんですけど最後ですね 最後に行くと56.フランス書院 57.鉄人社 58.文遊社
59.人格OverDrive 60.沖積社僕 この3年間でフランス書院の本1冊だけ読んでるみたいでたまにはいいかっていう感じかなあと鉄人社の方は
『家畜人ヤプーAgain』
っていう本を出してて友達が 鉄人社 好きな友達 いるんですよちょっとダークな感じの出版社だと思うんですけどあと文遊社っていう出版社があって鈴木いづみっていう作家のコレクションを出してるんだよね僕も1冊だけ読みましたけどあと人格OverDriveって伊藤なむあひ『天使についての試論』っていうのが出ててこれ読んで めっちゃ面白かったんだよねあとは最後 沖積社は短歌ですよね最近 読んでる短歌にも短歌研究社とか短歌・俳句・現代詩とか
そういうのって
専門の出版社あるんでそこを突き詰めていくの
めっちゃ面白いと僕 思うんだよねそんな感じで 今回60社の出版社を取り上げましたけど今回の60社は僕がこの3年間に読んだ本の最低1冊は入ってる出版社なんで漏れてる出版社もあると思うんですっていうか世の中に出版社なんか山ほどあるわけなんだけど今回はたまたま この60社になったということでこれからも出版社を愛していこうと思いますよ皆さんも好きな出版社があったら
ぜひコメントで教えてくださいそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#948「【10選】つかつ大賞2023 〜僕が2023年に読んで面白かった小説ベスト10を発表します〜!!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとつかつ大賞2023僕が2023年に読んだ360冊の中から
ベスト10を言っていくという動画でございます半年前に上半期ベスト5っていう動画も出してるんですねこれは1回やってるのでそれをまるまるベスト6からベスト10に置いて今回 新しくベスト5からベスト1を紹介しようかと思います早速やっていきましょう5位⑤ピエール・ギュヨタ
『エデン・エデン・エデン』
二見書房 1970年(榊原晃三訳)
(映ってるのは ペヨトル工房 1997年 版)今回 唯一の海外文学が入ってくるということですよ僕はTwitterで読んだ本の
あらすじとか感想とかを
書いたやつがあってそれを今回ちょっと読んでいくと××、××、××、××、××、××、××、××、××
××、××、××、××、××、××、××、××、××複数の人物が乱れて交わる描写が改行少なく270ページほど続くヤバめの奇書物語は全くない読者を破壊するテクスト 読む拷問僕はその時 感想してますけどさっき言ったようにこの小説ってストーリーがないんですね主人公とかもあんまりいなくてずーっと誰かがやってるだけの描写が続くんですけど書いてること ずっと同じなんですよねコピペみたいな感じで汚らしいワードが永遠に繰り返されてこいつとこいつがやってます みたいのをずーっとやるだけの小説なんですよめっちゃ時間 かかるの文字ぴっちりタイプなんで結構 読むの時間かかるんだけど読んだ時の爽快感っていうのかなこの時間 何やったんや みたいな感想はあると思うんだけど一生に1回は読んでおきたいタイプの小説かな本の表紙の帯かな「禁断のハード・コア テクノ文学」と書かれてるんですよねすごい読書体験だったということで今回5位に入れさせていただきました4位④佐川恭一
『清朝時代にタイムスリップ
したので科挙ガチってみた』
集英社 2022年この科挙ガチは短編集になってましてあらすじを言ってみると天才高校生が好きな女の子の
尿を飲むために科挙をガチる話や友達の書いたエロ漫画を読むために
マラソンに命を懸ける話やすばる文学賞三次通過の女の話や20浪の男が初めて東大A判定をもらった話など9編の短編集 童貞は無敵だって書いてるんだけど表題作は主人公が学校で秀才と呼ばれてる人物なんだけど急に清朝時代の中国にタイムスリップするのよその時に科挙っていう試験が当時中国にはあってめちゃくちゃ難しいとタイムスリップっていうか元々いた人に乗り移ってるんだよねその人と幼なじみの女の子がいて女の子が「科挙を合格したら私のおしっこ
飲ませてあげるわよ」みたいなこと言うわけよってか主人公が言ったんだと思うんだね 飲ませてくれってそのために主人公が頑張るみたいな話なんだけどとか結構 童貞的っていうか学歴とかワナビとか それね ちょっとコンプレックス文学なんだと思うんですねそこを描くの超うまいと思うわこの調子でずーっと突き進んでほしいと思いますよ僕は一生追いかけます(頑張って 佐川先生!)3位③水沢なお
『うみみたい』
河出書房新社 2023元々 水沢なおっていうのは詩人なんだよね『美しいからだよ』っていう詩集があってこれが中原中也賞を取ってるんですけどそのあと 第2詩集『シー』っていうやつが出て今回の『うみみたい』が初めての小説集ととても良かったんだよねあらすじを言うと主人公がうみちゃんって言うんだけどうみちゃんはみみちゃんと同棲してるんですね恋愛関係ではなくて どっちも芸術家なんですね美大で出会って卒業してから2人で活動してるんだけどむむっていうキャラクターを売ってるんだよねむむっていうキャラクターで色んなものを作って売ったりしてるんだけどそれと同時に主人公のうみは孵化コーポって言って色んな動物の ちっちゃい動物ですよ孵化させる そういうアルバイトをやってるんだよねそこに関係するのはなぜ生物っていうのは
性的なことをやって増えていくんだろう
みたいながテーマになってくるのよむむっていうのはキャラクターで人形みたいなやつだから別に性的なことをしなくても増えるのに なぜと思うわけよそうすると やっぱり自分に返ってくるんで自分はそういうことしなきゃいけないのかなとか例えば ポケモンとかも出てくるわけよポケモンって育て屋さんに預けたら卵ができるんだけど雄とか雌とかもあるんだよね ポケモンにはその辺の新しい感覚みたいのを文学に持ってきてる感じがするわしかも それは かなり
現代的な感覚なんじゃないかな
と思って とても良かった2位②御影瑛路
『僕らはどこにも開かない』
メディアワークス 2005年これ いわゆるラノベになるんですけど去年は僕 ラノベ奇書って言われるちょっと狂ったラノベをよく読んでたんですよねそれを調べる一環で御影瑛路が出てきて僕 御影瑛路って知らなかったんですねでもその界隈ではかなり有名な作家らしくアマゾンのレビューとかで「私の思春期の神様です」みたいな書いてるのよ僕もこれを読んでみたら僕も思春期に読んでたら 絶対
ハマってたなって思う作家ですね これはあらすじを言うと主人公が柊耕太っていう中学生の子なんですけどその子が普通に学校生活してたら同級生の香月美紀ちゃんっていう女の子がいるわけよその子は急に「柊耕太くんは魔法耐性がないから
私が守ってあげる」とか言うわけ魔法が使えるみたいなことを言うんだけど明らか これ 現実世界なんで魔法なんかないわけよだけど そういうこと言ってくる
女の子が付きまとってくるわけよ顔 可愛いとかで 友達みたいになっていくんだけどそれとは別に耕太くんの友達に谷原雅人くんっていうヤンキーみたいな子がいてこの子が常に鎖の音がジャラジャラって
言っている幻聴が聞こえてるんですね暴力的なんだけど 耕太くんとは仲がいいから荒っぽいんだけど そこは友情があるみたいなもう1人 委員長がいるんですねクラスの委員長の秋山秀一くんっていう子がいてこいつがサイコパスっぽい感じでこの4人の四角関係をずっと描いていくって話なんだけど殺人とかも起こるし人格移動みたいな 説明しにくいけどそういうのもあるしあと恋とか嫉妬とかそういうのが入ってる思春期ど真ん中の ぐちゃぐちゃ系の暗めの問題作なんですよねこういう小説は 多感な時期に読んでおきたかったなっていう気持ちがするな僕 絶対 どハマりすると思う1位①乗代雄介
『それは誠』
文藝春秋 2023年普通の妥当な感じでございますよ僕 結構 こういう純文学で去年に出たとかいうやつは逆によっぽどじゃないとランキングに入れないんですよねなんでかって言うと みんな それ読んで面白いとか言うから僕はもう読んで面白いんだけど僕なりのオリジナリティみたいのをこういう動画では出したいと思ってるからあんまり入れないようにしてるんだけどでも なんか僕 ランキングを作る時に去年読んだ360冊のリストがあるんでそれ バーって見てた時に『それは誠』があったわけよアッと思って良かったよな そういえば と思ったわけやっぱこれだなと僕は改めて思って1位にしましたねあらすじとしては主人公が高校2年生の誠くんっていう男の子で修学旅行に行くぞーっていうことで班で行動するんだけどその時に自由時間っていうのがあるからどこ行く?ってことになった時に誠くんが昔 お世話になったおじさんがいるとそのおじさんとは滅多に会えないからこの自由時間中にちょっと会いに行きたいなと思って班のみんなと会いに行くみたいな話なんだけど僕はめちゃくちゃ感動したね結構 泣かせよう泣かせようっていう
感じは確かにあると思うんですね『旅する練習』とか『最高の任務』も
僕は結構ボロ泣きだったんだけどそこが鼻につくとか言う人もいるんだけど僕は素直に良かったなって 誠くん〜とか言って僕は泣いちゃったところ あるんですけど純文学において 2023年を代表する1冊は
もしかしたら これかもなって僕 思ったわけよ僕の中では これが1番と言っても
過言ではないのかなと思いましたねこのあと 6位〜10位を言っていくんだけど1回 動画でやってるのでポンポンポンと言っていこうかなと思っております6位⑥中村九郎
『ロクメンダイス、』
富士見書房 2005年これもラノベ奇書なんだけど「三大ラノベ奇書」のうちの1つと
言われている伝説的な小説(諸説あり)とても良かったですね これは7位⑦村上春樹
『街とその不確かな壁』
新潮社 2023これは僕は発売されてすぐに読んでとっても良かったですね村上春樹 ノーベル賞を早く取ってほしいって僕 思いますね8位⑧田口賢司
『メロウ』
新潮社 2004年これもストーリーが基本的にあんまりない小説で主人公たちは全員外国人みたいな感じで
その群像劇を描くみたいな感じ2000年代だよね 極めて
ゼロ年代っぽい小説の作りで結構ムチャクチャやってるんだけど とても良かったねこういう小説もあるんだなあと思う小説でした9位⑨喜多ふあり
『けちゃっぷ』
河出書房新社 2008年『けちゃっぷ』は河出書房新社が
やっている新人賞・文藝賞ですね『けちゃっぷ』は僕の中でですよ「三大 文藝賞 問題作」の1つだと思ってるんですけど結構 ダジャレとかが多用されるんだけどノリと勢いみたいなでバーっていくんだけどよう これを新人賞の受賞作にしたなっていうそのまんま読むと意味がわからないと思うんですよでも なんか1周2周3周5周ぐらいすると良さがわかるというスルメ本だと思ってるからめっちゃいいよ『けちゃっぷ』10位⑩野村喜和夫
『骨なしオデュッセイア』
幻戯書房 2018年元々 野村喜和夫さんは有名な詩人なんですねその人が長編小説を書いたのがこちらで主人公が寝てて起きたら背骨が抜けてたとその背骨を水耕栽培するんだけど背骨がないけど 生きてるわけよそのまま町に出てフラフラして冒険みたいな話なんだけどあと出版されているところが
幻戯書房というところがまたいいねこういう ちょっとマイナー出版社
って言うと怒られるかもしれないけど五大出版社ではない純文学系の小説は僕 追いかけていきたいなっていう感じそんな感じで
つかつ大賞2023を
発表していきましたけど2023年も面白い本がたくさん読めましたね皆さんも1年間に読んだ小説のランキングとかつけると面白いと思いますよ毎年 出すことによって自分が何を読んだかとか 何が響いたのかとかそういうのが分かってくるんで1年の総決算になるわけですからまた来年も つかつ大賞2024も
発表したいと思っておりますのでまだまだ2024年あるんで 何が読めるかなと面白い本 あるかなとめちゃくちゃ楽しみにしているっていう感じでございますねそんな感じまた それを動画にしようかなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#947「【40選】この半年に出た小説で読みたい40冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこの半年間に出版された本で
読みたい本をたくさん挙げよう
(例外もあるけど 全40冊)僕は2023年9月からその1ヶ月前後に出た新刊をその中で読みたい本を10冊ずつ挙げてる
っていうことをやってるんですね(個人で)今回 それ結構 溜まってきたんでこれ半年間の僕がとにかく読みたいな
っていう本を挙げたいと思います早速やっていきましょう去年の9月前後に出ている本で読んだ本もいくつか挙げようと思うよ例えば①福田節郎『銭湯』
書肆侃侃房 2023年これは僕は読みましたよとんでもない話で めっちゃ面白かったんだよねみんなのつぶやき文学賞の2位になってましたよねあと②中西智佐乃
『狭間の者たちへ』
新潮社 2023年痴漢っていうか変なおじさんが主人公っていうの面白かったあと③高瀬隼子
『いい子のあくび』
集英社 2023年自分だけが損してるんじゃないか
って思う女性の主人公みたいなあと④石田夏穂
『我が手の太陽』
講談社 2023これは溶接工が主人公の 芥川賞の候補作になってるやつね⑤児玉雨子
『##NAME##』
河出書房新社 2023これはジュニアアイドルだった
女の人が主人公の芥川賞候補作ね僕がまだ読めてないやつを言うと⑥高原英理『祝福』
河出書房新社 2023高原英理って言ったら幻想文学の人でこれ短編集になってるのかな僕 1話だけ読んだんだけどあと読めずに図書館に返しちゃったんだよねこれ本当に読みたいとは思ってますねあと⑦川野芽生
『奇病庭園』
文藝春秋 2023川野芽生さんも幻想文学の人でもともと歌人の人なんだけどのちに川野芽生は「Blue」で芥川賞候補になるからこの時は全然 予想できなかったなと思いましたね次10月に行くと⑧田中慎弥
『流れる島と海の怪物』
集英社 2023田中慎弥は初期作品はここ1年ぐらいでめちゃくちゃ読んだんだけどまだまだ読めてないのありますねあと⑨長島有里枝
『去年の今日』
講談社 2023これはちょっと時間をおいて読みましたねある家族がいてその家族が飼ってた愛犬が亡くなっちゃうっていう話で結構 辛い話なんだけど家族の再生の物語みたいな感じで良かったですよあと読めてないの⑩上田岳弘
『最愛の』
集英社 2023上田岳弘って半年に1冊ぐらいで結構テンポよく新刊 出ますよね⑪上田岳弘
『K+ICO』
文藝春秋 2024上田岳弘 結構ずっとチェックしてたんだけどコンプリートしたい作家の1人ではありますねあと⑫古川日出男
『の、すべて』
講談社 2023古川日出男はメガノベルって言ってめちゃくちゃ分厚い小説を定期的に出すんですね僕はあんまり読めてないんですけど古川日出男は読んどかないといけないなって思う感じかなあと⑬甫木元空
『はだかのゆめ』
新潮社 2023甫木元空というのは映画監督でもあるしバンドもやってるのかなこの人が自分で撮った映画のセルフでノベライズしてるっていうこれ 大阪の図書館にほとんどなくて友達に借りてるんですよね近々 読もうと思ってますねあと11月になると⑭筒井康隆
『カーテンコール』
新潮社 2023著者のおそらく最後の小説集と言われるやつで僕は筒井康隆が大好きなんですけどこれ読んじゃうと終わっちゃうんだっていう気持ちあるからちょっと置いてるって言うのもあるんだけどさっさと読みたいんですけどあと⑮高瀬隼子
『うるさいこの音の全部』
文藝春秋 2023高瀬隼子は⑯高瀬隼子
『め生える』
U-NEXT 2024あと⑰井戸川射子
『共に明るい』
講談社 2023僕 良かったなと思うのは修学旅行の話台風が来て
修学旅行で無茶苦茶になる
みたいな話はあるのよめっちゃ面白いんだよね⑱永井みみ
『ジョニ黒』
集英社 2023児童小説みたいな感じでしたよね1975年の変な男がいてその男と友達になる少年みたいな話でよかったですよ⑲中村文則『列』
講談社 2023人間 皆 列からは逃れられないみたいなでも それを意識するかしないかみたいな問題も1つ入ってて人はどうやって幸せになれるのか
みたいな話をやってるのかな
と思うんだけどね⑳金原ひとみ
『ハジケテマザレ』
講談社 2023金原ひとみさんも半年に1冊ぐらいで
結構 ハイペースで本出すんですけど初期の方は読んでるんだけど最近のやつはちょっと読めてないなあと㉑長嶋有
『トゥデイズ』
講談社 2023長嶋有も作家20年ですから結構 刊行されてる本 いっぱいあるんだよね僕はあんまり読めてないな日常のゆるふわ系みたいなイメージあるんだけどどんどん読みたいなと思う㉒絲山秋子
『神と黒蟹県』
文藝春秋 2023これは架空の県の黒蟹県っていう県が出てくるんだけど定期的に絲山秋子って地理的な小説を書くでしょこれも1つそうだと思うんだけど 読まなきゃなと思うあと㉓沼田真佑
『幻日 /木山の話』
講談社 2023沼田真佑さん 6年ぶりの単行本化っていうのでめっちゃ楽しみにしてたんだけどなかなか読めてなくてこれは連作短編なのかな幻想的になっていくみたいな噂で聞いたんだけど読みたいと思います㉔西村享
『自分以外全員他人』
筑摩書房 2023なかなか読むタイミングを逸しているんですよね太宰治賞の受賞作で筑摩書房から出たんだけど僕は結構 この最近の太宰治賞を全部読んでるからこれも読まなきゃなと思ってますね㉕山下澄人
『FICTION』
新潮社 2023小説と演劇と評論みたいなが混ざってる小説みたいなやつで小説ってこういうことできるんだって思ってさすが山下澄人と思いました㉖綿矢りさ
『パッキパキ北京』
集英社 2023主人公が 旦那さんが北京で働いてるんですよ20とか30とか上の旦那さんなんですよ 年齢が旦那に会うためにコロナ禍 直撃の北京にわざわざ行くっていうコロナにもかかるとかいう話でめっちゃ良かったんだよねあと㉗鈴木涼美
『YUKARI』
徳間書店 2024㉘鈴木涼美
『トラディション』
講談社 2023歌舞伎町文学って最近 言われること増えたと思うんですけど他の作品は全部読んだんだけど『YUKARI』と『トラディション』また読もうと思いますね㉙大田ステファニー歓人
『みどりいせき』
集英社 2024早く読まなきゃな〜と思ってますよ闇バイトと青春みたいな話なんだよね 面白そうあと今月3月ですけど㉚村雲菜月
『コレクターズ・ハイ』
講談社 2024色んなコレクターが主人公らしくて
とても面白そうなんだよね㉛平沢逸
『その音は泡の音』
講談社 2024平沢逸さんというのは㉜平沢逸
『点滅するものの革命』
講談社 2022早くも2作目を出したということなんでこれも読まなきゃね㉝九段理江
『しをかくうま』
文藝春秋 2024野間文芸新人賞も取ってますからね馬の話みたいで超面白そうなんだよねあと㉞町屋良平
『生きる演技』
河出書房新社 2024ちょっと難しいらしいよね これも『ほんのこども』が最大級で難しかったけどその流れっぽいんだよなでも超楽しみなんだよねあと㉟高橋源一郎
『DJヒロヒト』
新潮社 20246年ぶりの長編小説らしいですよ昭和史と文学史を混ぜたとかいうキャッチフレーズらしいよ㊱高橋源一郎
『日本文学盛衰史』
講談社 2001めっちゃ面白そうなんだけど めっちゃ分厚そうなんだよねあと2冊紹介して終わろうと思うけど1冊は㊲飴屋法水
『たんぱく質』
palmbooks 2024飴屋法水もいわゆる演劇の人なんですけど小説 たまにポツポツ出たりするんですね㊳飴屋法水
『彼の娘』
文藝春秋 2017この『たんぱく質』も小説なんで ちょっと興味あるのよあと最後㊴松浦寿輝
『松浦寿輝全詩集』
中央公論新社 202416,500円するんですけどこれまでの松浦寿輝が書いた
詩集が全部入ってるらしいんです㊵松浦寿輝『名誉と恍惚』
新潮社 2017(岩波現代文庫 2024)この辺までちゃんと追っかけていける人は「マジの文学人」だと思うな僕もここまでなかなか手を出せてないんだよねそんな感じで何十冊も紹介しましたけれども(40冊)僕は現代文学 大好きなんでね現代文学はどんどん時間とともに更新されていくっていうか新刊 ドカドカ出てくるんで その楽しみがあるんだよなその波に乗るサーファーみたいな気分で 僕 いますんでたまにビッグウェーブとか来て 乗り過ごす時あるんだけどあとで乗ることもできるからね文学っていうのはいいなと思ったりしますねそんな感じでございます今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#946「本をたくさん売る方法を真剣に考えました」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとたくさん本を売れる方法を考えよう最近のニュースで「国が本屋さんを救済する」
っていうことが決定したっていうのがあったと思うんですこれに対して 色々言う人いると思うんですけど実際に本屋さんって潰れてきてはいると思うんです僕 やっぱりよく思うのはどうやったら本ってたくさん売れるんだろうって思うわけ別に僕は本屋さんじゃないんだけど本が大好きだしいつか古本屋さんとかブックカフェとか何かしたいなと思ってるわけその時に今から考えといたらいいかと思ってめっちゃ考えてるんですよねそれについて具体的な方法をいくつか言っていくっていう動画なんだけどまず前提条件が1つあってなぜ本は売れないのかっていう話なんだけど僕 よくよく本当に思うのは「私 本好きです」って言って「定期的に本屋さん行ってます」
っていう人いると思うんですけど基本的には「人々は本について全然 何も知らない」
っていう前提条件を作ってしまえばめちゃくちゃ売れると思うよ実際「私 本好きです」っていう人でも例えば 純文学のこと 知らないとかミステリー大好きだったとしてもSFは知らないとか得意分野はあったとしても全ての小説を知ってる人はいないでしょ全ての作家を知ってる人はいないから「知らないものを知る」っていう
だけでも本は売れると思うんですっていうか「全然 知らないものを買う」
ってことはあんまりないじゃないですかこれ スーパーとかで考えたら わかりやすくて全然 得体の知れない謎の商品があった時に 買いますかって言ったらあんまり買わないでしょでも それについて例えば 周りの人が「この商品いいんですよ」とか そういう声とか聞いたらこれちょっと買ってみようかなって思うじゃないですか本についても知らないだけなんですよ みんなだからもっと知らしめる必要があるわけよこの前提に立って僕はYouTubeでたくさんたくさん本について語ってるわけよ全然マイナーな本とかもたくさんたくさん言うわけよ僕は1冊とか紹介するんじゃなくて10冊50冊100冊1000冊とかいう そういう単位でたくさん本を紹介してるんだけどそういうことを本屋さんもやったらいいと思うんです具体的にどうしたらいいかというと例えば 本屋さんに入った時に1番 最初のところにブックガイドをいっぱい売ったらいいと思うんです僕 よくよくブックガイドの話すると思うんですブックガイドっていうのは「本を紹介する本」ねミステリーとかにはよくあるんだけど年に1回 新潮文庫の100冊とか角川のカドブンとか 集英社とかやってますよね新潮文庫の100冊とか 無料で
もらえるじゃないですか あの冊子あれ見て 面白そうと思ったら買いに行きますよね「ブックガイドが世の中になさすぎる問題」
が僕は絶対あると思うんですブックガイド たくさんたくさん みんな作って本屋さんの1番前に置いとくわけよみんな それ買って ミステリの王道10選が書いてたらみんな買うと思うんですねそれは言ってしまえば チラシみたいなものだと思うんですスーパーで考えたら もしくはヤマダ電機とかで考えたらだいたいチラシって入ってるじゃないですかチラシを見たら ここにセールの商品とかあと「これが今 旬です」とか めちゃくちゃ書いてるでしょ本屋さんってあまりチラシって見たことないじゃないですか僕が「ブックガイドを作りたい」とか言って「12月に同人誌を出すんだ」とか言って「ブックガイドを出すんだ」って言ってるのもそのためですよ だからこの1冊の本さえあれば「現代純文学 全部わかります」みたいな本があったらみんな買うと思うんですそもそも「物を売る」っていうのは1個の思想なわけよこれって消費社会というか 資本主義においては必ず物を売ってお金にするっていうのが存在しますから色んな企業が血反吐を吐くぐらい物を売ることに対して必死でしょ物を売るってことに対しての情熱って資本主義においては
人類はめちゃくちゃ
熱を持ってやってるわけよ本屋さんって なかなか 売ろう売ろうっていうそこがあんまりない気がするのよあるところはあるかもしれないけど「待ち」っていう感じはしないですかお客さんが来て 本屋さんでこう見て「あ これ面白そう」って買うっていうのがスタンダードだと思うんだけど僕は本屋さんにおいて もっとやってほしいなって思うのは本屋さんに来る前にお客さんが本のことを知って事前に知識を得てそれで本屋さんに来て本屋さんで物を買うっていう方が効率いいと思うんですよ商品さえあれば絶対買ってくれる客の方が良いと思うんですでも実際 多分ポップとか作ると思うんですね 本屋さんってポップとかを見て「面白そう」って
買う人はいっぱいいると思うんですけどそのポップを集めて チラシを作って来る前のお客さんに届けた方がそっちの方が早い気がするんだけどねポップはポップで現場にあってもいいんだけど店に来る前から客に働きかけることは僕できると思うんです僕が思うのはポップを作るのはわかるんだけどポップを作るんだったらもっと壁とかにも「この本 面白い」みたいな「うちの書店員で1番人気がある」とかそういうのをバーって壁に貼ったらいいんじゃないかと思うこれ 結構 個人の居酒屋とか行ったらメニューがめっちゃ壁に貼ってる人いるじゃないですか卵焼き500円とか何とかの何とか700円とかってバーってあるじゃないですかあれ やってもいいと思うんですよねというか それに関連してだけど本屋さんって もちろん新刊がどんどん入っていくと回転しなきゃいけないというのあるじゃないですかこれが 1個 ややこしいことだと思うんですつまり「積み重ねの問題」があると思っていて僕 よく言う話だけど例えば アメトーークの読書芸人とかあるじゃないですかテレビで芸人さんが「この本 面白いですよ」って言ったら「面白そう」って思うじゃないですか紹介された本って いっぱい売れるらしいんですよそれはもちろん 見た人が買いに行くんだけど例えば そのテレビが終わって1ヶ月過ぎるとみんなの頭の中が忘れていくと思うんですよ半年に1回とか 1年に1回ぐらい読書芸人やってるからそのたびに売れていくと思うんだけどこれ 1個のブームになっていて
(ブームはいつか廃れる)例えば 今回で読書芸人 5回目ですって言った時に5回目でも 本を あれ10冊〜15冊とか紹介すると思うんですそれらは売れると思うんですでも その時は 第1回目に放送した本はみんなの頭の中から消えてるしだって もう何年も前に多分放送されてるからねそれも残しておいたらいいわけよ僕 YouTubeを始めて やっぱり何かを積み重ねることって大事だなって本当に思うわけ例えば アメトーークで紹介された本15冊ですっていうのをA4の紙に書いて ファイリングして店の前に 誰でも見れるようなそれこそ飲食店のメニューみたいなのを置いてそこにアメトーークの読書芸人第1回で紹介された15冊です第2回で紹介された15冊です第3回で紹介された15冊です みたいのをたくさんファイリングして誰でも見れるところに置いとくわけそうしたら そのお客さんも来て それ見てあ これ そういえば紹介されてたな
とか思い出すじゃないですか知らなかったら知らなかったで
これ面白そうって買ったりするわけそのファイリングもどんどん更新していったらいいし別にアメトーークだけじゃなくて本にまつわる紹介文みたいのをいっぱい集めて置いといたらいいんですよそういうシステムさえあれば時間とともに それがどんどん溜まっていくんでそれが1つのチラシにもなるしあと本屋さんとしての厚みとしても出てくると思うんです僕 そういうの大好きだから
そういう考えしてるんだ
と思うんだけど一時のブームで終わってしまうと みんな忘れちゃうんで人の頭って そんなWikipediaみたいになってないんで忘れさせてはいけないですよそういうシステムを作れば ネットでもできるし現場に来なくてもネットで「◯◯書店のオススメ」みたいなで ホームページを作って例えばダウンロードできるように作って「オススメ100冊」みたいのを
事前に作ってもいいし
誰かに頼んでもいいと思うけどお客さんを「一種の洗脳状態」に陥らせるわけよこれ 悪いことのように思えるかもしれないけど物を売るって大体そうでしょ色んな企業が客に洗脳をかけて「これ良さげですよ」「これおいしそうですよ」とか言ってそういう宣伝するのが 一種の洗脳なんで本屋さんも それできるんですよね過去の芥川賞の全ての受賞作を並べていくとかそれだけでも効果あると思うよ本屋さんの壁とかに「実は芥川賞って面白いんですよ」みたいなを言うとかね意外と芥川賞の受賞作とかも知らない人いますんで別に直木賞でもいいし 本屋大賞でもいいです本屋大賞の歴代の受賞作品を全部リストにしてデカデカと壁に貼るとかそれだけでもみんな買うと思うよお客さんの頭を洗脳して本っていうのは めちゃくちゃ面白いんだと意外とたくさんあるけれどこれを読んでたら間違いないとっていうか面白い本なんか山ほどあるからお客さん自身に 次に読みたい本とか 次に買いたい本を自動的に選んで買ったりするように
仕向けていく方法はあると思うんですよいわゆる「啓発」だと思うんだよな本っていうのは基本的に「啓発活動」だと思いますよ知らないものを知っていただくお客さんが次々々の本を読み続ける機械となってその買いたいなって思う本をこっちが売るそれを繰り返すことで
永遠に本を売り続けることが
できるっていうシステム作りこれだけ言ってきたけど 僕は別に本屋さんじゃないけれどだけど僕はYouTubeをやってるわけだからYouTuberとして できることは何かな とかあと同人誌を作りたいなと思うのはそういうことではあるし本を売るってことは別に実は本屋さんじゃなくたって僕は関われることだと思うわけもう全然 関係ない人が でも「面白かったです この本」とか言って
Twitterでつぶやくっていうだけでも本の宣伝だからね本っていうのは「商品」だっていうことを考えた時にTwitterとかだったら「この本面白かったです」っていうのは商品を宣伝してくれる人じゃないですかそれは本屋さんとか出版社じゃなくてお客さんでもできることだからこれはインフルエンサーっていう流れに関わってくるコマーシャルの部分なんだけどでも意外と 我々のことですよ本屋さんは頑張ってると思うけど 我々 一般人なんか意外と何もしないっすよ僕はここでは言わないけど意外と人って 自分でもできること いくらでもあって無料でもできること
あっても やらないんだな
っていうのをよく思ってんのよそういう経験 たくさんしてきて結局 やるやつしかやらないんだって思ってるからできる人がやりゃいいんだけど「あそこの本屋さん 潰れちゃったな 残念だ」とか言って「活字離れがすごい」とか言って
Twitterでつぶやいてる人がいても「じゃあ お前 宣伝しろよ」って僕 思っちゃうの潰れてからじゃ遅いから潰れる前から潰れないように色んなことを我々できるんでお客さんでもできるんでそういうことをみんながやればいいみんなが 本が好きなみんながコツコツとそういう本に関わる何か活動っていうか活動って言ったらデカいけどちょっとしたことでも やりゃあ本屋さんって潰れないと思うんですみんながしないだけ僕 本当にそう思うわそれは別に 僕は他人事だから
こんだけ言えるのかもしれないけど僕は早く同人誌を作りたいの本をいっぱい紹介したいの僕がYouTubeをやってるのは
本を紹介するためにやってるんだけどみんなYouTubeやったらいいよ僕は僕のやり方があって もうずーっとそれでやり続けます本 大好きだからそれが結論じゃないけれども本を売る方法は山ほどありますよ僕はそう思う素人の僕でもたくさん出てきたでしょそれが現実可能性あるかわかんないけどまだまだできることあるんじゃないかなあっていうのは僕は思ったりはしてますよ僕自身もまだまだ知らないことあるんでどんどん知りたい色んなことを本当にたくさん知りたいなと思うからそれが本屋を救うことだと思っていますんで頑張っていきたいと思いますね皆さんが本屋さんのためにできることとかもしくは本を売るにはどうしたらいいかっていうのがもしあればコメントの方で教えてもらえたらと思いますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#945「【購入】19冊を買ってきました!また献本!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#944「最終選考に残るための小説の書き方4か条」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと最終選考に残るための小説の書き方4か条先日 ある知り合いがいてその人は小説を書いていると 公募勢であるとでもなかなか 10作品を送っても一次選考も通っていないとちょっと小説を読んでほしいと言われて僕もいいですよ って読んだんですねもちろん それ 良いところもたくさんあったんだけど言いたいところ いくつかあって1回 こうやって動画にして小説とは何か 小説ってどう書いたらいいのか
って僕なりに考えてることを ここで言っといてその人もいつでも見れるようにして
みたいな形を取ろうと思いました早速やっていきましょう最終選考に残る方法4か条って言って4つあります1つ目①評論にするな僕 結構こういうことやってるもんで10人ぐらいから 小説読んでほしいって言われて読んだことあるんだけど評論になってるパターン多いのよつまり社会問題を取り上げてコロナについてとか 虐待はいけないとか評論みたいな感じの小説になってる人は多いんですもちろんメッセージとして書くって
いうのはあってもいいと思うんだけどそれの「距離の取り方」がちょっと危うい感じなんです主人公が社会に対して何か言いたいといろいろ思ってることがあるっていう主人公に設定しがちなんですこれ うまい処理の方法があって主人公に言わせるんじゃなくて友達とか ちょっと違う登場人物
に言わせる方が効果的ですよむしろ主人公は中立的な立ち位置にしてそんなにめちゃくちゃ社会的にもしくは政治的に何か思ってる人に設定せずに友達としゃべる時に 友達がそういえばコロナについてどう思う?とか私こう思うのよ とか言わせた方が良くないですか主人公がそういう思想を持ってると読者との距離感が近すぎると思うんですよね近すぎるゆえに効果的ということもありえるよ小説って正解がないから別に絶対にそうするなってことじゃないけど「距離」は考えた方がいいですよね2つ目②読者を想定しろ見せてもらった小説には同じ内容がバーって出てくるんです何回も何回も主人公の価値観だったりとか描写だったりが出てくるんです僕が思う そういう時って2回書けばいいと思うんです2回だけ我々 意外と書きがちなんですよめちゃくちゃ書いちゃうんですよこれは 書かなくちゃ
読者に伝わらないだろうって
思っているきらいがあるわけよでも意外と読者の方が賢いよ僕 よく思うけど 作者より読者の方が賢いですよ僕 こうYouTubeをやってるけど僕より皆さんの方が賢いですよ賢くないかもしれないけど賢い人がいたら賢いから1人でも賢い人がいるかもしれないから賢いのよこれ 純文学とエンタメによって違うと思うエンタメ小説っていうのは 全部 書いてます書きすぎるほど書いてるでしょ 説明が誰でも読めるように エンタメ小説 作られてるんで空白はないけど純文学って同じこと 2回
書いたら もうそれで終わりですこれ なんでかって言うと本当に賢い人っていうのは 2回で読み取れる2回連続で何かが起こると 人ってそこには何か法則が働いてたりとか意図があったり とかっていうのを考えるんですよね例えば主人公が俺 父親との関係 うまくいってないんだとか書いててちょっとしたら また もう1回俺 父親と喧嘩ばっかりするんだ みたいな書いてたらあ これ メインのテーマなのかなとかあとで父親が出てくるのかな とか考えられるんですよ2回出てくると「メイン」なんですよね それ実は小説って全ての文章を作者がコントロールすることができるなので 極力いらない部分はカットしているけど「2回出す」ってことは意図が絶対あります 作者の何か主張したいことがあったら2回で留める3回4回5回っていうのは書きすぎだと僕は思ってますめちゃくちゃ書きすぎてる小説があった時に頭が良い読者だったら うざったくなっちゃうでしょ「何回も書くなよ」ってことになっちゃうんでどこに線を合わせるかなんだけど僕は「2回でわかるような読者」を
想定した方がいいんじゃないかと思います3つ目③行動を書け意外と小説って行動と観念のバランスでできてるんですよねこれは客観的なものと主観的なものと
捉えてもいいと思うんですけど僕が先日読んだ知り合いの小説にはめっちゃ観念が書かれてるんですね主人公がこう思った ああ思ったって書いててそれは社会が何とかだからだ とかそれは自分の過去と繋げてこれはこうだからだ とかって書いてるんだけど観念的なんですね観念的な小説もあってもいいと思うんだけど小説を読む時に 行動 行動で客観的事実で例えば「雨が降った」とかは客観的事実じゃないですか「主人公が傘を開いた」とかも客観的事実じゃないですか客観的事実の羅列っていうのが想像しやすいし前に前にどんどん進めていけるから特に冒頭とかだったら客観的事実で「主人公がこう動きました」「知り合いがこうなりました」とかをバーって書いていった方が「読ませていく力」っていうのがそこに働くわけこれが最初の評論にも繋がるよ評論っていうのは どちらかというと観念的なんで観念を 極力削って 行動で何かテーマとかを表せるようにした方が小説っぽくはあると思うけどね4つ目④原稿を削れ僕が最終選考に残った時原稿が400枚ありましたあれ 文藝だったんで 400枚まで行けたんですねだけど削りに削って300枚にしましたやっぱり そのぐらい削れますよ 小説って村上春樹もよく言ってるけど「推敲があるから小説なんだ」ってよく言うのよ小説って意外と第1稿が完成してそこから削る段階がメインだと思いますよまあしかし これは僕の体験もあるけど最終選考に残った文章をその時は 1番良いと思ったの 僕の中でとても良いなと思ったけど5年ぐらい寝かせて久しぶりに自分の最終選考のやつを読んだら「全然しょうもないな」って思っちゃったのよねそれは 自分自身が良くも悪くも
変化したからなんだと思うんですでも人って 成長っていうか変化は絶対するんで今 この文章・小説が1番面白いと
思ってるのは「錯覚」なんだよね自分がもっと未来では
成長しているって
いう前提に立つとすれば絶対 今が最高だ ってことはありえないじゃないですかだから それはいつの段階でも書き換えるチャンスがあるというか余白があるというか部分があるという感じだと思うんですけどつまり自分の小説って自分で書いてるから「思い入れ」が出てくるんですねだから それと距離を置くことは
書いた段階ではなかなか取りづらい感情移入してしまいすぎて客観視がなかなかできないのが
小説の面白いところだと思うんですだから そのためにはちょっと1ヶ月ぐらい原稿を寝かせて自分の頭が忘れてきた時ぐらいに読み直して 赤ペン入れるとかもしくは やっぱり他人に読んでもらうっていうのが1つ大事だと思いますよ他人の意見が全て正しいわけじゃないとは思うがしかし自分の意見よりかは正しい時 あるのよ全てのアドバイスを取り入れる必要はなくても相手のアドバイスはメモしといて
どこか置いとくとかした方がいいと思う小説って応募するんだったら応募先が絶対になるんで自分が出した小説が 一次選考を
通りませんでした ってなった時にそれが絶対なんですよ文句言う人 いるじゃないですか?「俺の小説は最終選考に残るぐらいの実力あるだろう」とか言う人いるんだけどそれは主観的なものなので必ず向こうの結果が出るんでそれを中心にして物を考えないと一次選考まで自分は行ってないことが
許せなくて プライドがあって俺は絶対 一次選考じゃねえ とか言ってる人は客観的にそもそも見れてないのでそれは 直していかないと なかなか無理なんじゃないかというのは思うけどねそんな感じで最終選考に残るための小説の書き方4か条なんだけどこういうことこそが観念的ですから僕の言ったことが全て正しいわけ
じゃないとは思うんですけれど1回 僕 最終選考 残ってるんでちょっとぐらいは ちょっとぐらいは説得力 あるのやもしれないんだけど僕は 人の原稿を見せてもらうっていうことはめちゃくちゃ良い経験だと思ってるの 僕がですよ上から目線で何か言いたいわけじゃなくてその人と寄り添ってどうやって良い小説を考えていくか完成していくかっていうのを 僕 色々考えたい編集者っぽいでしょ そういうのってなんか良い経験してるなって僕は思うわけだから皆さんも何かあったらいつでも言ってくださいTwitterのDMでもいいんで いつでも言ってくださいそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#943「【絵や短歌】最近のつかつが忙しかったのにはヤバい理由があります」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと最近のつかつのことを
話そうかと思います今週 ちょっとめちゃくちゃ忙しくて
あまり動画を出せれてなかったんですけど1番デカいのは 僕「短歌」に
ハマってるのかなっていう感じある前まで あんまり興味なかったんですけど周りの人が短歌を読んでたりするんですよ僕もちょっとずつ興味の水がどんどん溜まってて最終的にバッて溢れてきてちょっと短歌いいな みたいな最近 思ってるんですよあと僕もちょっとだけ詠んでます短歌を20首 作ったんですここでは言いません知り合いがいて10年来ぐらいの知り合いなんで作った20首をそいつに送ってちょっと感想を聞いたりとかしてますねあと歌集も何冊か買いました永井祐
『広い世界と2や8や7』
左右社 2020あと これも買いましたね これは上篠翔
『エモーショナルきりん大全』
書肆侃侃房 2021あと7冊ぐらい 今のところ読んでまして俵万智『サラダ記念日』とかこのあたりは1回動画にしてるやつと あと笹公人
『抒情の奇妙な冒険』
早川書房 2008これ昔 読んだことあって笹公人っていう名前 短歌を
調べると必ず出てくるんですよ有名な作品ないかなと思って調べたらこの『抒情の奇妙な冒険』ってあったんですよこれ 大学の時 読んだなと思ってめっちゃ忘れてたんですよこの人かと思ったわけ今回 もう1回 手に入れて読んだら
めちゃくちゃ良かったですね 面白かった他に 僕は前から調べてた「現代歌人協会賞」っていう
短歌の文学賞があるんですねそれを 今 調べててその受賞作品を図書館で借りたりとかしてます僕 ハマるとハマっちゃうんで40冊ぐらい図書館から本を借りてるんですよ僕の住んでる図書館があって隣の図書館も使えるのよその隣の隣の図書館も使えるのよあとはデカい図書館が2つあってその辺の図書館を全部 使って歌集をかき集めてきて買った本もあるし 持ってた本もあるし読んでた本とか加えると50冊 読もうと思ってます僕 去年は現代詩を80冊ぐらい読んだんですね現代詩は前から本当に興味があって何を読んだらいいかもわかんなかったんだけど調べまくると中原中也賞とH氏賞っていう賞があってこの受賞作品から読んでいこうと思ったんですねそれで1年ぐらい読んで 80冊ぐらい読みました 現代詩今年 なんかハマろうかなって思ってたけど短歌も 僕 あんまり興味なかったんだけどさっき言ったように ちょっとずつ興味は出てきたから今回も 一気に50冊 読むかって思ってるのこれは1つ 同人誌の部分もかかってくるんですよねこれも100回ぐらい言ってる話ですが年末に僕は「つかっちゃんの現代純文学1000冊」っていう自分の読んできた本1000冊の同人誌を出そうと思ってるんだけどそれがもう そろそろ終わる感じなんですねそろそろって言っても あと180冊ちょっと読むと1080冊 行くんです残り180でしょ何 読もうかって思ってたわけよ小説も もちろん読むし 新刊とかも
読みたい本もたくさんあるんだけどちょっと自分の中でいっぱいいっぱいになってたんですよね今週と先週ぐらい めっちゃくちゃ忙しかって全然 本 読めなかったのよ僕 一応 毎日1冊 読むって決めてるから月に30冊 読むって決めてるし同人誌の方も12月が締め切りになっていますからうまい具合に 順調に読めなかったら
同人誌を出せないってことになるからどうしようと思ってでも めちゃくちゃ忙しくてどんどん本が読めなくて うわーって思ってる時にこれ 去年 身につけた方法で そうだって思って去年は現代詩にハマったわけよ現代詩は詩だから 小説とは違ってやっぱり書かれてる内容が少ないんですよねだから1日2冊ぐらい全然 普通に読めたんですよ小説で長編とかあると 1日2冊ってなかなかきついわけよでも現代詩はできるのよだから それを今回も使おうって
思ったのが1つきっかけではあったつまり短歌を読むぞ っていうことねそれで50冊を読むとまあ だいたい現代短歌わかるかなっていう感じはしてるのよ僕も結構 ネットでめちゃくちゃ調べました現代短歌って何があるのかなとか有名な歌人って誰かなとかその歌集を出してる出版社ってどこがあるのかなとかあと短歌の賞ですよねそういうのも めちゃくちゃ調べてある程度 まだまだですよ まだまだだけど基本の基本ぐらいは分かった感じがあって先 そういうのを調べると取り組みやすいんでそういうのを まず調べるようにしてます調べた内容とかも 今回は言わないけどまた動画で出そうかなと思っていますんでそうやって短歌にちょっとハマろうと思っています僕は短歌を50冊 羅列してます正確に言うと45冊ぐらいA4の紙に読みたい短歌っていうか歌集をバーって45冊書いてるんですよその45冊をどんどん図書館から借りたりとか読んだ本も もちろん入ってたりとか 買ったりとかしてその45冊をとりあえず埋めようと思ってる残り5冊は あとで良さげの短歌が見つかる可能性あるんでちょっと余裕を残しておいてるんだけどなんで ちょっと短歌 また読んでいこうと思いますこれから短歌ブームが来るっていうのと あと今週結構ね 難波の方にちょっと半分仕事 半分趣味みたいなで行ってたのがあって難波で研修会がちょっとあった時があって研修会なんで そこから自由になったらブックオフとか行けるんだけどそういうのもあって 忙しかったんだけどあと絵を買ってきたっていうのがあるなTwitterで仲良くさせてもらってる
@mochihamaさんっていう人がいてその人がTwitterで絵を発表してるんですよ僕 前から好きだなと思っててmochihamaさんの絵が売られてるんですね大阪の「gallery 魔法の生活」さんっていうところがあってそこで売られてたんで買ってきたんだよねこういう絵なんだけどちょっと これはチョイグロなんで
モザイクってか ちょっと隠すと思いますけど絵のタッチが結構レトロっていうかゆるふわみたいな絵なんですよこの絵だけじゃなくて いっぱいmochihamaさん描かれてて これ買ってきました絵初めて僕 絵というものを買ったと思いますけどこれは2000円そんなに高いわけじゃないから金があったらもっとたくさん買ってたと思いますけどそれもあったしあと今週 知り合いっていうのかな1回会った人がいてその人が小説を書いてるともちろん素人の方だけど応募していると いわゆる公募勢の方がいてその人が読んでほしいと僕も全然 読みますよって言ってたわけよそれで原稿が渡されて僕 ずっと読んでたんだけどもちろん内容とか感想とか言わないですけど ここでは結構 長かったんですよ結構 なかなか味わい深い感じはあったそれでちょっと時間を使ってたっていうかそういうこともあったっていうことでちょっと忙しかったっていうのあるね僕 でも YouTubeを始めてもしくはその前に最終選考に残ってるから知り合いとか もしくは この視聴者さんとかが読んでほしいっていうこと何回かあったよ10回ぐらいあると思う 今まで僕だって素人だから 良い感想とかないですけれどもそういうこともあって いい経験
させてもらってると思うわ マジであと ある知り合いがいてその人も視聴者さんででも3年ぐらい友達っていうか ぐらいの人がいてその人とブックオフ巡りとかも今週行ったりしたんですけどその人とコメダ珈琲に行って恋の話したりとか僕じゃないよ 相手がとか あと小説の話 文学の話あと その人は現代詩が好きで現代詩の話とかもした っていうのがあって結構 YouTubeをやっててよかったなと思う僕は色んな繋がり できたなっていう感じがするんだよねそんな感じで今週 忙しくて動画 あまり出せなかったという話なんだけど来週は特にそういうのはないからいつもの通り動画を出したいと思ってます僕は本が好きなんで本に関するYouTubeとか あとツイートとかは一生 辞めないと思うんですけど今回の動画 結構ぐちゃぐちゃ過ぎてどんな動画やねん と思うかもしれないけどたまにはこういう動画あってもいいかなと思いますそんな感じで 終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#942「【購入】また献本を頂きました。11冊を買ってきました!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#941「【25選】純文学の公募型「五大新人賞」のオススメ小説5冊ずつを紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと五大新人賞を見ていこう五大新人賞っていうのは純文学作家に 例えば なりたい人がいた時に各出版社が年に1回やっている公募型の新人賞があってそこに送って それで受賞すればめでたく純文学作家としてデビュー
できるという新人賞がありますそれは大きく5つあるんですね
(他にもいくつかあるけど)僕なんか めちゃくちゃ大好きでこうやって受賞作をリスト化して毎日のように見てこれ読んでないな とか思うぐらい好きなんですけどそれを語っていこう という回でございます早速やっていきましょう①文藝賞文藝賞は河出書房新社がやっている新人賞で文藝賞の特徴としては受賞作品が絶対 単行本化されるんですよね単行本化されると読みやすいっていうのがあるんで結構 重宝してるんだけど文藝賞の主な受賞者として山田詠美綿矢りさ宇佐見りん町屋良平とか磯﨑憲一郎とか遠野遥とか芥川賞作家とかもたくさん出ていますけれども僕のオススメ文藝賞としては藤原無雨『水と礫』(2020)1番好きなのは桜井晴也『世界泥棒』(2013)あと問題作として 僕 好きなのは喜多ふあり『けちゃっぷ』(2008)あと もう1個 マジ頭イカれてる小説は黒田晶『メイドインジャパン』(2001)もう1個 言うと大鋸一正『フレア』(1996)文藝賞はポップさがあって とても面白いですよ僕も1回だけ最終選考に残ったことがあるんですけど作家を目指す人は文藝賞を読むっていうのもいいと思います②すばる文学賞すばる文学賞は集英社がやっている新人賞です主な受賞者としては金原ひとみ高瀬隼子石田夏穂特に僕は 90年代とかゼロ年代とかのすばる文学賞は実験的なやつが多かったんじゃないかな
っていう感じはしているんですよね僕が勧める すばる文学賞の
めちゃくちゃヤバいやつを紹介すると清水博子『街の座標』(1997)あと個人的に好きなのは清水アリカ
『革命のためのサウンドトラック』(1990)あと好きなのは澤西祐典『フラミンゴの村』(2012)あと上村亮平『みずうみのほうへ』(2015)最近で言ったら木崎みつ子『コンジュジ』(2021)すばる文学賞は一癖も二癖もある
っていう感じがあって超いいですよ変わってる とても変わってる③新潮新人賞新潮新人賞は新潮社がやっている
公募型の新人賞になってるんですけど新潮新人賞は王道を征ってる感じはするんだよね主な受賞者としては上田岳弘とか 高橋弘希とか古川真人とか 小山田浩子とか石井遊佳とか僕がオススメするヤバい新潮新人賞としては青木淳悟
『四十日と四十夜のメルヘン』(2005)とか あと鴻池留衣「二人組み」
(in『ナイス・エイジ』(2018)「二人組み」も青春みたいな感じ
なんだけど 悲しい話なんだねあと小池水音
「わからないままで」
(in『息』)(2023)家族が自死してしまうみたいながテーマなんだけど高橋文樹
『アウレリャーノがやってくる』(2021)高橋文樹さんは のちに「破滅派」っていうサイト・出版社を立ち上げて自分で本を出してるんだけどとか あと太田靖久『ののの』(2020)これも新潮社が出てないですけど これもなんか良かったね3つ入ってて 3つとも良かったんだよね新潮新人賞って 僕が数えた限りでは70作品しかないんですよ単行本化されてるやつだけを数えたら多分 30冊とか40冊しかないんですよこれぐらいなら読めるでしょっていう感じなんで作家志望者は全部読んだらいいと思うんだよね④群像新人文学賞群像新人文学賞は難解というイメージがあって僕も実は 後回し後回しにしてたもんで読んでいない作品があって今ちょっとチャレンジしてるんですけどかなり難しいのが多い群像新人文学賞の主な作家としてはダブル村上が挙げられますよね村上龍と村上春樹諏訪哲史乗代雄介石沢麻依島口大樹僕が勧める群像新人文学賞のヤベえ奴っていうのは阿部和重『アメリカの夜』(1994)J文学の旗手と言われていますから 阿部和重はあと横田創『(世界記録)』(2000)往復書簡になってるんですよねお互いに違うことを言ってるんで話の繋がりがよくわかんないんだけど めっちゃ面白い早川大介『ジャイロ!』(2002)難しい よくわかんないんだよね 何じゃそりゃっていう話あと これも最近 読んだけど樋口直哉『さよならアメリカ』(2005)これ 安部公房『箱男』リスペクトみたいな感じらしい知る人ぞ知るで言えば丸岡大介
『カメレオン狂のための戦争学習帳』(2009)群像新人文学賞は
マジでヤバい文学っていう
イメージがありますよ純文学って難しいイメージがあるけどすんなり読めるやつも そりゃあるんだけどとことん難しいやつってあんのよとことん難しいやつまで僕はチャレンジしたいんで群像は 最近 僕の中でブームが来てるのよねまた読みたいと思います⑤文學界新人賞文學界新人賞は文藝春秋がやっている新人賞ですがこれは他の新人賞と比べて 1個 特徴があり短編・中編なんですよね逆にそういう特徴から芥川賞を取る作家が多いですよ主な受賞者としては絲山秋子とか モブ・ノリオとか長嶋有砂川文次沼田真佑九段理江僕が勧める これヤベえぞっていうやつを言えば松波太郎「廃車」
(in『よもぎ学園高等学校蹴球部』)(2009)話が一気に飛んだりとか よくわかんないのよねとか あと篠原一『壊音 KAI-ON』(1995)かなり耽美的で ちょっとBLもありながら世界の終末みたいな感じも 雰囲気として出してるからめっちゃ面白いんだよねあと谷崎由依『舞い落ちる村』(2009)円城塔『オブ・ザ・ベースボール』(2008)空から人が落ちてきて町の守ってる人がバットを持っててカキーンって打ち直すみたいな話なんだけど吉村萬壱『クチュクチュバーン』(2002)藤野可織『いやしい鳥』(2008)奇想系が一時期 多かったと思う 文學界新人賞はそういう文学を売り出してたような気がするんだよね最近は普通になっちゃった感じがするんだけど当時は本当にヤバかったと思いますそんな感じで 五大新人賞を言ってきましたけど僕自身もまだまだ読めてない作品 たくさんあります僕の感覚としては この五大新人賞の単行本化されてるやつだけで言えば多分200冊ぐらいしかないんじゃない?多分 作家志望の人っていうのは
めちゃくちゃいると思うんですよ各新人賞だけで見ると
大体2000人の人が
応募してるんですよねその2000人と差別化しなけりゃ
いけないわけじゃないですか作家になるんだったらやっぱり この200冊 読んだ方がいいですよ僕はめちゃくちゃ本を読んでたから最終選考に残れたのかなって思う時はたまにありますよ今 全然 応募するつもりはないけど僕は200冊 読もうと思って
今 頑張っておりますねそんな感じでございますまた200冊 読めたら 動画を
出そうと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#940「【50選】僕が読みたい50冊の小説を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと僕が読みたい本 50冊僕は12月1日の文学フリマ東京の方で
同人誌を出そうと思ってるんですけれど
(『つかっちゃんの現代純文学1000冊』)まだ1080冊 読めてなくて残り あと200冊になったんですよ残り200冊 何を読むかって いつも考えてるんだけど今回 読みたい本を50冊 まとめてきましたこれを確実に読むかどうかはわかんないけど今のところ こうやって動画に残して自分を奮い立たせてどんどん読んでいこうと思っているということでございます早速やっていきましょう50冊 一気に紹介するので1冊1冊の細かい説明はありませんけどとりあえず10冊ずつ紹介していこうかと思っておりますまず1冊目から10冊目を紹介します1冊目①九段理江
『東京都同情塔』
新潮社 2024年2冊目②青来有一『聖水』
文藝春秋 2001年3冊目③町田康『きれぎれ』
文藝春秋 2000年4冊目④平野啓一郎『日蝕』
新潮社 1998年5冊目⑤花村萬月
『ゲルマニウムの夜』
文藝春秋 1998年6冊目⑥藤原智美『運転士』
講談社 1992年7冊目⑦荻野アンナ
『背負い水』
文藝春秋 1991年8冊目⑧南木佳士
『ダイヤモンドダスト』
文藝春秋 1989年9冊目⑨宮本輝『螢川』
筑摩書房 1978年10冊目⑩中上健次『岬』
文藝春秋 1976年この10冊は
いずれも芥川賞を
取っている作品ですねこのほとんどは1回は最低でも読んでいますしかし読んだのが10年前とか大学生の時に読んだのが多くて今 再読したいと思っている作品ですね『東京都同情塔』に関しては
雑誌掲載時に読んでいますから今回 読みたいと思ってるのは単行本なんですね『東京都同情塔』は丸々 話
分かってるんだけど単行本で読むと続きまして11冊目から20冊目を紹介しようかと思います11冊目⑪大田ステファニー歓人
『みどりいせき』
集英社 2024年12冊目⑫李琴峰『独り舞』
講談社 2018年13冊目⑬畠山丑雄
『地の底の記憶』
河出書房新社 2015年14冊目⑭滝口悠生『寝相』
新潮社 2014年15冊目⑮小山田浩子『工場』
新潮社 2013年16冊目⑯藤野可織
『いやしい鳥』
文藝春秋 2008年17冊目⑰羽田圭介『黒冷水』
河出書房新社 2003年18冊目⑱中上紀
『彼女のプレンカ』
集英社 2000年19冊目⑲河林満『渇水』
文藝春秋 1990年20冊目⑳吉本ばなな
『キッチン』
ベネッセ 1988年これらの作品はいわゆる公募型の
新人賞を受賞した作品です言ってしまえば 新潮新人賞 文學界新人賞
群像新人文学賞 文藝賞 すばる文学賞ですね太宰治賞は入ってませんが『キッチン』は海燕新人文学賞になっております続きまして
21冊目から30冊目を
紹介しようかと思います21冊目㉑高瀬隼子
『うるさいこの音の全部』
文藝春秋 2023年22冊目㉒赤染晶子
『じゃむパンの日』
palmbooks 2022年23冊目㉓石沢麻依
『月の三相』
講談社 2022年24冊目㉔綿矢りさ
『嫌いなら呼ぶなよ』
河出書房新社 2022年25冊目㉕町屋良平
『愛が嫌い』
文藝春秋 2019年26冊目㉖又吉直樹『人間』
朝日新聞出版 2019年27冊目㉗吉村萬壱
『虚ろまんてぃっく』
文藝春秋 2015年28冊目㉘柴崎友香
『寝ても覚めても』
河出書房新社 2010年29冊目㉙堀江敏幸
『おぱらばん』
青土社 1998年30冊目㉚柳美里
『フルハウス』
文藝春秋 1996年これらの作家は芥川賞を取っている作家なんですねしかし芥川賞の受賞作ではなくてそれ以外の本ということですね僕は芥川賞受賞作だけじゃなくて
それ以外の作品も読みたいです続きまして
31冊目から40冊目を
紹介しようかと思います31冊目㉛三木三奈
『アイスネルワイゼン』
文藝春秋 2024年32冊目㉜三国美千子
『骨を撫でる』
新潮社 2021年33冊目㉝大前粟生
『おもろい以外いらんねん』
河出書房新社 2021年34冊目㉞木村友祐
『幼な子の聖戦』
集英社 2020年35冊目㉟水原涼
『蹴爪 ボラン』
講談社 2018年36冊目㊱内村薫風『MとΣ』
新潮社 2015年37冊目㊲舞城王太郎
『好き好き大好き超愛してる。』
講談社 2004年38冊目㊳佐藤亜紀『天使』
文藝春秋 2002年39冊目㊴久世光彦『燃える頬』
文藝春秋 2000年40冊目㊵金井美恵子
『タマや』
講談社 1987年これらの10冊は芥川賞の受賞者ではないしかし純文学の辺りの人を集めたものですね芥川賞っていうのは1番でかい賞なんだけどなかなか芥川賞を取らなかった人も過去にはいましたからしかし だからといって小説が面白くないわけではないとむしろ芥川賞より面白いみたいな本はいくらでもあるわけで今回 それらをまとめましたね最後 41冊目から50冊目を紹介しようかと思います41冊目㊶山﨑修平
『テーゲベックのきれいな香り』
河出書房新社 2022年42冊目㊷野坂昭如
『死刑長寿』
文藝春秋 2004年43冊目㊸宇能鴻一郎
『むちむちぷりん』
徳間書店 1975年44冊目㊹草間彌生
『クリストファー男娼窟』
角川書店 1984年45冊目㊺江波光則
『ストレンジボイス』
小学館 2010年46冊目㊺稲庭淳
『ラン・オーバー』
講談社 2015年47冊目㊼入間人間
『多摩湖さんと黄鶏くん』
アスキー・メディアワークス 2010年48冊目㊽浅井ラボ
『Strange Strange』
ホビージャパン 2010年49冊目㊾米倉あきら
『インテリぶる推理少女とハメたいせんせい』
ホビージャパン 2013年最後 50冊目㊿柚原季之
『ひまわりスタンダード』(上・下)
マイクロマガジン社 2000年この10冊は 後半は特にラノベ奇書と呼ばれる狂ったラノベ系が多いんですね僕 純文学だけじゃなくても「知る人ぞ知るみたいな小説」が
気になって気になって仕方ないわけよそういうマニアの人は
知ってるみたいな小説って
まあ ありますよ変な小説を読みたいんで
皆さんそういう本があったら
教えてくださいそんな感じで今回 僕が読みたいなと思ってる本
50冊を紹介する動画でしたけど皆さんも1回 作ってみてほしいんだよね読みたい本のリストも作ってみたらいいし読んだ本のリストも作ったらいいし人に勧めたい本のリストも作ったらいいと思いますそういうところまで意識して読書するとめちゃくちゃ面白いですよ無限大だもん だって今回は気になる本 50冊だけどまた読んだ本とかも動画にしようかと思っていますので皆さん どうぞよろしくお願いいたしますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#939「僕つかつが芥川賞・直木賞の贈呈式に招待されたので、その行ってきましたレポートです!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと私 つかつ 先日第170回 芥川賞・直木賞の
贈呈式に招かれまして行ってきたっていう潜入レポート的なことを言おうかと思います結構前から 僕は今度 東京に
行きますって言ってたんですよあるすごいことがあるから
行きます って言ったんだけどこれは当日までに
内緒にしといてください
って言われてたからはっきりしたアレは言えなかったんだけど2月22日に東京の東京會舘っていうところで芥川賞・直木賞の贈呈式って言って「受賞おめでとうございます」って言って賞品とかをもらったりとかスピーチしたりとかするっていうパーティーみたいのが行われるんですよ僕 怖いから めっちゃくちゃ過去のやつ 調べまくったらだいたい1000人ぐらい来るらしいんですねそれは作家先生とか編集者とかメディアの人とかあと色んな人が招かれると過去の事例だったら 受賞者の家族とか友達とかあと作家さんが取材とかするじゃないですかその取材先の人とかを招いたりするらしいんですよ今回 僕 招かれたんですけど誰に招かれたかっていうと九段さん本人だったんですよね九段理江さんは今回『東京都同情塔』
っていうので芥川賞を取られたんですけどなんで僕みたいなやつを招いたんですかって聞いたんですよそしたら僕はYouTubeやってて「芥川賞の候補を読む」みたいなやってるからそれを本人が見られたらしくて中身良かったですよみたいなDMで言われてえーと思って 嬉しいなって思ったんですけど僕以外の人も招かれてるらしいです昨日かな 斉藤紳士さんも動画を上げられてたんですけど僕 会場の時に 九段さんと会った時に斉藤紳士さんも来てますよって言われて斉藤紳士さん 来てるんだと思って めっちゃ式場を見て結構 広いんですけどあっち行ったりこっち行ったりして探したんですけど僕からは全然いなかって ちょっと挨拶したかったんですけど仕方ないと思ったんですけどその22日に行くっていうことになって僕なんか しょぼいスーツしか持ってないからこの日のためにスーツの青山まで行って新調して本番に備えてたんですけど僕は夜行バスで大阪から東京まで行って22日の朝に着いて友達がいますから 友達と色々喋ったりとかして夕方ぐらいに開催されるんですよいざ入ったらウェルカムドリンクみたいなもらえるんですよジュースとかあるし ワインとかもあるんですけどそれを持って テーブルがいっぱいあるからどこかのテーブルにつこうと思って僕はその時は斉藤紳士さんとかいるとか知らなかったから1人だなと思って 誰もいないと思ったんですけどその同じテーブルの横の人がいてその人も誰かに招かれてるっぽいなみたいなそういう話をしてるんですよ僕もちょっと声かけて すいませんとか言ってこういうパーティーとか初めてなんですかとか言って全然 知らん人と喋って私たちも九段さんに招かれたんですよ
僕もなんですよ みたいな話をしてその時に僕 名刺を作ってたんですよ僕「つかっちゃん 」名義で名刺を作ったことないんですけどやっぱり人と会うだろうなと思って僕も名刺を交換とか全然 会社でもあんまりしないんですよねだからめっちゃ緊張して すいませんすいませんとか言って名刺を渡したりとかずっとやってた贈呈式が始まった時に受賞者に賞品とか渡した後に スピーチがあるんですよスピーチが良かったですねこれ言っていいかわかんないけど選考委員の人もいらっしゃるから選考委員の代表の人がコメントをするんですけど芥川賞は平野啓一郎先生が受賞おめでとうスピーチやってて直木賞は三浦しをん先生がやってました僕 多分 生の作家って基本見たことないんじゃないかと思う作家先生に会えるって僕の人生の中で1番嬉しいことですよ僕は20年間 読書してきて色んな作家先生の本とか読んでたから京極夏彦先生とか思って山田詠美先生とかいらっしゃったけどうわーと思って ずっと見ててそれぞれとってもいいことをおっしゃってて超面白いと思ってそれが終わったら 立食パーティーに入るんですよ左右にバイキングがあってこれも過去の誰かがやってるブログを見ると和洋中で 食べ放題だとそこには寿司とかローストビーフあるよって書いてるわけよ誰か書いてるから僕もその気になってるわけよ実際にあって寿司 やっぱり食べたら超うまかった職人の人が握ってくれるの 目の前でローストビーフも食べて 美味いって思って酒とかも飲んで 美味いと思って食べてるだけではなくて実際に九段さん いらっしゃって僕のことを招待していただいてるわけだからその前も
DMとかでお会いしましょうって
おっしゃってくれてたから招待してる人が多分いっぱい
いるから列になってるんですよその後ろに並んで前の人が九段さんと喋ってると思うわけ横にはもちろん河﨑秋子さんとか万城目学さんもいらっしゃるわけですようわーと思って九段さんとちょっと挨拶させていただいて名刺も交換させていただいたんですけどなんか良かったですね 本当にこれ言ったら怒られるかもしれないけどある出版社の編集者さんが横にいらっしゃって結構 声かけてくださって「つかっちゃんさんですか」って言って「すごいですね いつも」みたいなおっしゃってくれていやいや僕なんか全然アレなんで
みたいな言ってたんですけどその編集者と名刺交換とかもしてそこから また飯に戻るんですけどやっぱり周りに色んな作家先生いるんですよこれ 変態かもしれないけど先生がご飯を食べてるわけよ隣の人と喋ってるんだけど横を通り過ぎるっていうことを僕はしてたある選考委員の超すごい先生がいて顔とかでわかるレジェンド作家みたいないっぱいいるから「あの人あれだ」とか言ってその横を通って両サイドにバイキングがあるからこっちの料理を食べて またこっちへ戻れるわけよ永遠に作家先生の横を通るっていうプレイをやってましたよだいたい2時間ぐらいで終わって解散になるんですけど僕 実はですね2次会の方にも行かせていただいたんですよね2次会は多分詳しく言ったらダメなような気がするからこの先生がいたとか多分 内々で多分やってる感じなんですよだからめちゃくちゃ詳しくは言わないけど九段さんに招待された人っていうのは
「友人様」みたいなになるらしく友人様と編集者とかがバーみたいなところだよね改めて 九段さん受賞おめでとうございます
ってやるっていう ご飯とかもあって食べる
っていうのあるんですよ行ったら やっぱり編集者が多くて僕はとても難しい立ち位置だと思うんですよね僕 別に本の仕事をやってるわけじゃないしYouTubeだって別に何万人とかいるわけじゃないわけで難しいですよ 僕の立場って1冊 本 何かを出してたらまだ挨拶しがいあるっていうか しやすいと思うんだけどすいません YouTubeっていうものを
やらせていただいてます みたいな結構 ある出版社の編集者さんとかは「あー あなたでしたか」みたいな
おっしゃってくれた人がいて僕も「あの本いいですよね」とか言って文学談義に花を咲かせたりとか僕は文学のことしか話せないのでそれ以外の格式張ったっていうか形式的な話って 僕 本当にできなくてオタクなんで 文学オタクなんであの作家のアレでアレでとか
いうことばかり 頭あるんでそういう場でもあるだろうけど意外と みんな社会人だから編集者とかもしっかりされてるから僕なんか全然そういうのは
できない人間なんで難しかった とても別に無理にそうする必要もないけどそういう場も僕は初めてだったからめっちゃ緊張しましたねその2次会も まあまあ長かったっていうか
ある程度の時間あって途中から違う作家の先生とかも来はって1次の時には来てなかった先生とかも2次にやってきて僕からするとアイドルを見てるような感覚なわけよ推しだから僕 純文学の作家 みんな推しだからえっ あの人来とるやん とか言ってずーっと僕は驚いてた 観客みたいな感じ部外者だから 言ってしまえばだから もう見てるだけで幸せみたいな感じある作家の先生とチョロっとだけ喋ってちょっと文学の話させていただいたりとかありましたけどちょっと感動したな なんかそれで2次会は終わり 解散になって僕は普通に帰るっていうか友達の家に泊まらせてもらってたんですけど 男の東京は僕 2泊5日してるんで喋れること めちゃくちゃあるんですけど神保町に行ったりとか高円寺は初めて行ったんですけどあと銀座とかも歩いたりとかしてあと国立国会図書館にも初めて行きまして僕の中で今回の旅行は
もちろん主目的は贈呈式なんですけどプラス国立国会図書館でもう本当に読めないと大阪の図書館とか 日本の図書館ではほとんど どこにも所蔵されてない本があるんですけどそれを国立国会図書館で3冊も読めたっていうのがあって めっちゃ嬉しかった それも色んな人にも会った 贈呈式だけじゃなくて東京に住んでらっしゃる人とか関東圏に住んでる人が 色々初めて会う人もたくさんいてこれだけちょっと言うと今 ラジオとか 本も出されている「第一芸人文芸部」っていう
ユニットとは言わんかもしれへんけど又吉直樹先生とはもちろん会ってませんが他にファビアンさんっていう人とピストジャムさんっていう人がいてこの人とは会いました 挨拶してあと お2人じゃなかったけど
ご飯一緒に食べさせていただきました
(ファビアンさんと)っていう貴重な体験もあった僕 人生の一生の思い出でしょ本当に本好きなんだなって思ったもん贈呈式の時は僕は上がっちゃってるし初めての そういう立食パーティーもあったし色んな作家先生もいらっしゃったからその時はめっちゃ緊張してまして感情みたいなあんまりないわけよすごいすごいみたいなすごいと思いつつ ちょっと冷静みたいなのもあるわけよ感情が追いついてないみたいな感じがあってもちろん挨拶とか色々したんだけど僕 その後に っていうか帰る時ですよ東京から大阪に帰る時にそれも夜行バスで帰るんですけど大体 夜行バスは23時とかに東京を出て翌朝の7時とかに大阪に着くんですけど酒もその時に飲んでたから疲れててバスの中に入って 椅子に座ったら すぐ寝れたんですよ眠れない時もあるんだけど 帰る時はすんなり眠れてパって起きたんですよ そしたら夜中の3時で7時に着くから まだまだ時間あるんですよちょっと寝たから 眠気がなくて消灯時間になってるから スマホを出せないわけよ音楽 聞こうかなと思ったんだけどちょっと この闇の中で目を開けて東京に来た思い出みたいのを遡ってそういえば あの時にあそこに行ったなあとかご飯 食べたなあとか思ってた時に贈呈式のことを そりゃ思い出した時に多分 感情が遅れてやってきたから泣いちゃって ええ〜と思って良かった〜と思ってこんなに幸せなことないと思ってボロボロ 涙 出て嗚咽みたいな最初ちょっと出てエッエッみたいな なってたからヤバイと思って夜行バスだからなんか喉を自分で押さえて嬉しい〜!みたいな嬉しすぎる〜!みたいな気持ちでもう感情バグってたYouTubeやっててよかったなあと思ったマジでこれ わかんないよ これから別にそういう話 全くないっていう
ことだってもちろんあるんだろうけど僕 2016年に文藝の最終選考に残ったことあるわけよその時に蟻塚哲人っていうペンネームで「存在しない川」っていう小説で最終選考 残ったんですねその時もめっちゃくちゃ嬉しかったわけよ僕は当時 誰にも理解されなかったし心の底から信頼できる人とかもあまりなかったわけよ孤独だったわけよ とにかく黙々と1人で小説を書いてた時期にその小説で最終選考に残ったから自分って報われるんだなと思ったの自分でやってたことは間違いじゃなくていいところまで行ったんだなと思ったわけ結局 落ちるから あと1歩及ばずなんだけどその2016年にそういう話があって 今年2024年でしょう8年 経ってるんだけどもちろん僕は途中で小説を書くのをやめちゃってYouTubeに転向するわけなんだけどだけど僕 やっぱり好きなんですよね小説自体がやっぱり好きで今は読むことを集中してやってるんだけどこれ言うと ちょっとアレかもしれないんだけどある出版社の編集者の人がいらっしゃってその人と二次会の時 ちょっと喋ったら蟻塚哲人のことを知ってたんですよね「蟻塚哲人」が「つかっちゃん」になってるっていうこの矢印があるわけじゃないですかそれを知ってらした編集者の方 いらっしゃって「あの人がこうなってるんだね」
みたいなことをおっしゃってたわけ
(蟻塚哲人→つかっちゃん )そう聞いた時に 本当だなと思って今まで小説を続けて良かったなと思うわけ小説を読むこととか調べたりとか本屋さんに行くみたいなことは20年間ずっとやってるからそういうことが色んなことが繋がってんだなって僕 思ってやれば何かに繋がって報われるんだなと思って僕 本当に小説好きなんだなと思って再確認できて家に帰ってきたっていう話なんだけどこれだけ言って終わりますけど僕 その2次会とかで編集者の方 いらっしゃったから「何でもしますよ」と自分を売り込もうっていう気持ちもちょっとあったんですよ同人誌の話もちょっとしたし今度 文学フリマの12月に(2024年)「つかっちゃんの現代純文学1000冊」
を出す予定ですって言ったんですよそしたら ある出版社の編集長の方も「へえ〜 1000冊かあ」みたいななんか話を聞いてくれたんですよね140文字っていうのが僕は短いかなと思ったの本を読んだ時に僕ワンツイートであらすじ・感想を書いてそれを1000個 集めるってことを僕はしたいと思ったからそういうことを言ったんですよでも140文字って さすがに短いと僕は思ってるのよ正直短いなと思ってたんだけど その編集長の方は「いや140文字で収めることの
方が難しいんじゃないの」
みたいなおっしゃってくれていやあ〜と思って 嬉しいと思ってこういうことって誰にも言ってもわかってくれないですよ本が好きだっていう人とかに言ってもなんか わかってくれないんだよね
(でもわかってくれたということね)色んな人に僕は「自分は文学のために死ぬこともできます」「文学に命を賭けれます」みたいなこと言ったら相手の人はドン引きしてましたけど九段さんにも言ったら九段さんもドン引きしてたと思うけど皆さん 酒も入ってたから 僕も入ってたけど僕も大層 失礼なことを言ってたと思いますけれども2次会は2次会で
本当になんかいい経験させて
もらったなあと思いました僕も頑張ろうと思ったもん色んな作家先生が来てて僕は作家先生には なかなか声かけづらかったけど遠くで見てるだけでも幸せですから見てたんですけど僕は大体の作家の出版した
リストが頭の中に入っているのよ僕はWikipediaを編集するのも趣味でやってるからこの先生のアレとアレ 僕 読んでないんだよなとか思って全部 読んでおかないと失礼だろうなあと思って別に声かけてないけど僕 全部 読んでたら 声かけたかったんだよ例えば 全部で5冊あるってことになった時にまだ3冊しか読んでないってなったら声かけたら失礼でしょもっと読まなきゃと思った マジでもっと読んで もっと文学を極めなきゃいけないなって僕勝手な使命感っていうか 義務感っていうかある種 妄想的だけどそういうことは本当に思った今回の贈呈式ね 1次会2次会に行った時に本当に僕はもっと文学を頑張らないといけないなと思った僕なんか本当にペーペーで他の これを多分 見てる視聴者さんとかなんか色んな人とかは「いや つかっちゃんすごいよ」みたいな「いっぱい 本 読んでるやん」
おっしゃってくれるんだけど僕からしたらホントまだまだだと思ってるから もっと上を目指すぞって本当に思っておりますそんな感じで 今回 熱く語っちゃいましたけどでも本当にこんな自分を招いてくださって
ありがとうございます 九段理江さん僕 九段理江さんの小説を全部読もうと思ってますので
(既存のは全て読んでます これから出る本も全部読みます)今度 3月に『しをかくうま』が発売されるんですよ野間文芸新人賞 受賞作ねそれも ちょっと喋ったんですけどこれ内部事情になるから言っちゃいけないかもしれないけど僕 本当に死ぬまで文学のことをしたいし命かけたいと思ってますから皆さんね お仕事とかあったら僕 何でもしますよ無料でもするもん マジで何でも言ってください奴隷のように馬車馬のように使ってもらえたらと思うし皆さんもYouTubeやりましょうYouTubeやって 純文学の本を読んで 紹介しましょうそしたら呼ばれますんで贈呈式 呼ばれる可能性ありますんで僕はそれで呼ばれましたんで皆さんもやりましょうみんなで文学を応援していきましょう!そんな感じでございますまた違う動画でも色々しゃべるかもしれませんけど今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますつかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#938「」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#937「戦後文学とは何だったのか 1945年〜2024年の日本文学史」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと戦後文学とは一体何だったのか僕は現代文学ばかり読んでるんですけど昭和の文学ですよね特に戦後〜昭和終わりぐらい
まではあまり詳しくないんです今回 予習みたいな感じで色々 資料をまとめてきました早速やっていきましょうまず 色々資料を作ってきたんだけど僕は色んなところで勧めている本があってこちらですよね川西政明
『「死霊」から「キッチン」へ』
講談社現代新書 1995年これこそ戦後文学〜80年代までの
文学を紹介してる本なんですよ「死霊」っていうのは
埴谷雄高「死霊」という作品「キッチン」というのは
吉本ばなな「キッチン」で具体的な作品 バンバン出して
作家名とかもバンバン出るんでもう これ読むだけで戦後文学 大体
わかるみたいな感じだと思うんですけどこういうのを読むと
スッと入りやすいという
感じなんですけどそれとは別に wikipediaも僕は
資料として大事にしてるんでその辺 ちょっと言ってみるとまず戦後系の文学って
大体4つの派閥に分かれると①第一次戦後派 ②第二次戦後派
っていうのがあるんですよ③第三の新人④内向の世代
っていうのがあるんですよねここら辺までで1975年ぐらいなんですよその後 1980年文学ができて1990年 2000年代 2010年代
現代の2020年代って来るわけで大体10年ごとぐらいに区切っていくことで
分かりやすいイメージがあるんですがまず第一次戦後派っていうのがいるんですけどこれは1946年〜1947年の間に現れた
日本文学の新人を指すらしいんですけど主な作家としては野間宏とか 武田泰淳とか埴谷雄高とか 梅崎春生とか椎名麟三とか 花田清輝とかあと さらに加藤周一 中村真一郎 福永武彦なども入ることもある第一次戦後派の小説の傾向としては戦争文学が多い戦争体験の与えた文学的意味
について論じられることが多いとこれが第一次なんですけど 第二次があって第二次は1948年〜1949年に登場した
新人作家のことを言うらしいですね主な作家としては大岡昇平 三島由紀夫安部公房 島尾敏雄 堀田善衛井上光晴 長谷川四郎 などを指すらしいですね特徴としては戦前の私小説・心境小説的な方法論を捨てて20世紀小説の手法を積極的に取り入れることによって多くの優れた長編小説が生まれた点があるともう1つ特に海外からの評価が高くて三島由紀夫・安部公房などは
ノーベル文学賞候補にあげられるなど本格的な西欧型長編小説の骨法が初めて日本に根付いた時期と位置づけられるあと この次に「第三の新人」というのが現れるんですね第三の新人は 1953年〜1955年にかけて
現れた新人作家のことを言うらしいですね主な作家としては小島信夫 小沼丹近藤啓太郎 安岡章太郎阿川弘之 庄野潤三 遠藤周作吉行淳之介 三浦朱門 曽野綾子 など第三の新人の特徴としては私小説の方に1回帰ってるっていうのがあるんですよね戦前に流行ってた私小説っていうのを第三の新人が再び取り入れているっていうのが特徴的だとあと第三の新人って芥川賞をどんどん取っていくんですよね芥川賞は1935年からあるんでこの辺の作家たちは芥川賞が存在する時間軸にいるんで取る人もいれば取らない人もいるんですけど第三の新人って1953〜1955年なんだけどなんと1955年に石原慎太郎が登場するんですね石原慎太郎は第三の新人に入らないんですよねその後に1957年に大江健三郎が現れて同じく1957年に開高健が出てきて1959年に北杜夫が現れるんですよこの人たちは第三の新人には入らないわけですねつまり戦後派がいて 第三の新人がいて
このビッグの人たちがいるわけですwikiの説明によると第三の新人はこの間で埋もれていくだろうとあまり実は評価されてなかったと 当時は特に芥川賞は石原慎太郎が取った時にめちゃくちゃピックアップされたって言われますよね今だったら芥川賞・直木賞は誰かが取ったらニュースで報じられるけど当時なんか出来立てみたいなものなんで全然 評価がなかったらしいですけど石原慎太郎がドカーンと出てきたことで「芥川賞ってすごいんだ」が
みんな色々言われたりとかテレビとかマスコミとかも多分あったと思いますけどこの後に内向の世代っていうのが出てきて僕は内向の世代を勉強したいんだよね内向の世代は
1965年〜1974年にかけて
台頭した一連の作家を指すと代表的な作家としては古井由吉 後藤明生 日野啓三黒井千次 小川国夫 坂上弘高井有一 阿部昭 柏原兵三 などそして 大庭みな子 富岡多恵子 上田三四二やこの一派の擁護に回った 秋山駿 柄谷行人
などの文芸評論家を含める場合もある特徴としては 60年代における
学生運動の退潮・倦怠・嫌悪感から政治的イデオロギーから
距離を置き始めた作家や評論家自我と個人的な状況の中にだけ
自己の作品の手応えを求めようとしており脱イデオロギーの内向的な文学世代ということですねこれがwikipediaの情報なんですけど第一次戦後派 第二次戦後派 第三の新人 内向の世代この後に なんと1979年に
村上春樹がデビューするんですよね
(村上龍は1976年デビュー)村上春樹は まだご存命で
作品をたくさん書いてるわけでノーベル文学賞の
候補じゃないかと
言われてるんだけどだいたい80年代以降ぐらいの人たちがまだ小説を書いてる人が多いですねこれ 70年代デビューとかになると50年以上前になるわけだから結構 亡くなってる率が高いんですよ80年代には高橋源一郎デビューとかあと山田詠美とか島田雅彦とかその辺がデビューしてるんですよだいたい80年代デビュー以降の人たちが今の芥川賞の選考委員をやってることが多いのでだから僕からすると「現代文学」っていうのは1980年
以降のイメージがありますねうまくまとまったかどうかわかりませんがこれだけ言って終わろうかと思いますけど結構 2000年代あたりに出た文学書があってさっき『「死霊」から「キッチン」へ』を紹介しましたけどこれは1945年〜1980年代ぐらいまでなんですけどこの後ですよね80年代以降の文学 どうなったかというとたまたま手元にあったから出してるだけではありますが石川忠司『現代小説のレッスン』
講談社現代新書 2005年これ結構 80年代以降の現代小説を取り上げてるんですよね最初は村上龍からだけどその後 保坂和志とか村上春樹があって阿部和重があって舞城王太郎 いしいしんじ 水村美苗 があるんですよね結構 これもいいですよあと やっぱりこれもよくて佐々木敦『ニッポンの文学』
講談社現代新書 2016年登場作家としては 村上春樹でしょ高橋源一郎 吉本ばなな 筒井康隆もいるし保坂和志 阿部和重 舞城王太郎も西尾維新 伊坂幸太郎 円城塔又吉直樹とかって書いてますねこの3つは昔 読んだことあって再読したいと思って 今も机の上に置いててちょびちょび読んでますけどこういう 文学を
流れで見ていくことは 僕
大事だと思うんですよこの人がいるから次こういう
作家が生まれて 次こうこうとかそれが戦後だったら
70〜80年あるわけだから
(1945年〜2024年)それをまずパッと把握しておきたい僕はその辺 多分 僕より皆さんの方が詳しいと思います戦後文学とか昭和文学とか詳しい方 多分いらっしゃるんでなんで その辺のオススメの小説 ありましたら
ぜひコメントを書いていただけたらと思います不勉強なつかつに色々と
教えていただければと
本当に思っておりますそんな感じでございます今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#936「最近読んだマジでヤバすぎた小説5冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと最近読んで良かった小説5選僕はあんまり読んだ本の紹介とか動画で最近してないんですけど僕は最近 月に30冊 読むように色々頑張ってるんだけど読んだ本を紹介していったらそれだけで動画をバンバン作れるんだけどあんまりしてないんですけどこれからどんどんやっていきたいと思っておりますね早速やっていきましょう1冊目①湯浅真尋
『四月の岸辺』
講談社 2021年この作品は群像新人文学賞の受賞作となっていまして中学生の男の子が主人公なんだけどその子は小学校の時にスカートを履いて 小学校を通学してたんですよなので周りから変な目で見られてたと中学校になった時に制服を着なきゃいけないんで男の子だから 男はズボンだということでズボンを履いて 中学校に行ってるんですよもう1人 女の子がいてその女の子は「森の子供」って呼ばれててその町では奥の方に森があるんですよそこに20〜30人で生活している謎の集団があるんですよ多分 1つの宗教団体なんですよねそこに子供ももちろんいますからそこから女の子が来て主人公と仲良くなっていくって話なんだけどこれ 言ってしまえば どっちもマイノリティなんですよねマイノリティとマイノリティが対峙するっていうか独特の文体で 1文がかなり長いんですよねそれが1つの小説的な効果があると思いますけどかなり良かったですよこういうことってあんまり純文学でも書かれないと思うんですよそこをうまく書いてたような気がしますね2冊目②津原泰水『五色の舟』
河出書房新社 2023年「五色の舟」っていうのは元々何年も前にある短編集に
入ってた1つの作品だったんですね
(2010年に初出)その短編1つを河出書房新社は単行本にしたんですよプラス 宇野亞喜良さんって言って有名なイラストレーターの人の絵が入ってて豪華版みたいなあるんですよ「五色の舟」の話は戦時中の見世物小屋の話なんですよ見世物小屋の一座がいるんだけど5人ぐらいしかいないんだけど主人公は腕がないんですよね腕がないし しゃべることもできないんだけど同じ一座にいる女の子とはテレパシーで
喋ることもできたりもするんですよその一座のリーダーみたいな お父さんと呼ばれてる人が「件」っていう「にんべんに牛」って書く妖怪ですけどどこかに件が生まれたっていうのを知って件に会いに行くんですよね件っていう妖怪は未来の予測ができるっていうことで日本軍とかも件を頼って件を捕まえようとするんだけど件には もう1個 特殊能力があってこの世界線とは違うつまりパラレルワールドに自分が移動して1つ 幸せな道の方に行くことができるとマルチバースの自分になることができるっていう能力があるってことが発覚して見世物小屋の一座はどうするか
っていう話になっていくんですよ結構 面白い僕は近藤ようこさんっていう漫画家が描かれた『五色の舟』ビームコミックスから出てる漫画があるんですよ1巻完結なんだけど僕 好きすぎて同じ本を3冊持ってるぐらい好きなんですけど小説も小説でいいなって本当に思いましたね3冊目③保坂和志
『この人の閾』
新潮社 1995年『この人の閾』は芥川賞を取ってる作品でこの中に4編 小説が入ってるんですけど保坂和志は現代文学を語るにおいて欠かせない人になってるんですよね小説と あと小説論もよく書いてて有名なのは『書きあぐねている人のための小説入門』とか小島信夫と対談してる『小説修業』とかもあるわけだけど僕も保坂和志は読まなきゃなと思っててだいぶ昔『この人の閾』は読んだこと
あったんだけど 再読したんですよ改めて読むとストーリーみたいなストーリーはほとんどないんだよね表題作の「この人の閾」は 主人公がいて大学時代の先輩だった女の人がいるんですよその人は他の人と結婚して子供もいるんで お母さんみたいになってるんですよ友達・知り合いみたいな感じなんで久しぶりに会うかと言ってその人の家に行ってその人と ただ喋るだけ 本当にそれだけなんですよね他に入ってる話は玉川上水のところに家を借りるって言って近くに猫がいっぱいいるんだよっていうそれだけの話とか自然教育園っていう植物園みたいなのがあってそこを男と女の2人がただ歩いてしゃべるだけみたいなすごいと思うわ マジで意外と純文学ってこういうことをしてくるんですよエンタメ小説では絶対ありえないと思うね純文学って本当に何も起こらない小説ってあるんですよそれが面白かったりするんだよね『小説の自由』っていう本もあるんだけど保坂和志の小説を読むと何でもありなんだなって本当に思う不思議な小説ですよね4冊目④山野辺太郎
『こんとんの居場所』
国書刊行会 2023年『こんとんの居場所』には2つの話が入ってて1つは表題作の「こんとんの居場所」主人公が男の人で ちょっと貧乏してると遠いところなんだけどお仕事をもらえるっていうことでなんとか研究所っていう怪しすぎるところに行くと海のところにある島みたいのがあるとこの島っていうのが生き物なんだっていうわけよ「こんとん」っていう昔の中国の妖怪・神様の名前を冠した島みたいな生物を調査するっていうアルバイトなんだけどそこに主人公と同じ目的で来た女の人がいてあと「こんとん研究所」みたいなの所長とか調査する人とかで 何人かで船に乗って最終的にこんとんに着くんだけどそこで大変なことが起こるっていう話なんだけどめっちゃいい めっちゃ面白いもう1個 併録されている「白い霧」っていうのが僕 好きで主人公が男の子なんだけどハッカーみたいな感じでお父さんが防衛省で働いてて主人公が防衛省のシステムをハックするんですよそうすると 防衛省の近くの人間がパムッて言って蒸発するんですよねそれが東京中に広がって人々がみんないなくなるっていう それだけの話なんだけどその ある種 恐怖みたいのもあるけど意外と「こんとんの居場所」が効いていてドロッとしてんだよね とても良かったと思いましたね最後 5作目⑤深堀骨
『腿太郎伝説(人呼んで、腿伝)』
左右社 2023年深堀骨って僕 前から読みたいと思ってたの単行本としたら2冊しかなくて『アマチャ・ズルチャ
柴刈天神前風土記』
早川書房 2003年これがデビュー作っぽいんですけどそこから20年の沈黙を経て2023年『腿太郎伝説』が発売されたんですよねストーリーとしては 腿太郎っていう主人公がいるんですよ川から女の太腿だけが流れてきたとその太腿の中から生まれたのが腿太郎なんですよこれ 最終的に仲間たちを集めて悪いやつをやっつけるって話になってくるわけよこれ 仲間たちがまず変で 苔子っていう女の子とかあと猫っていう名前の犬とかあとルネ・フロア・オカモッっていう人とかあと長瀬悲惨太っていう名前の人が仲間になってくるのよ僕の最初 読んだ時の感想はもうボボボーボ・ボーボボに近いわけ これもうメチャクチャしてんのよ何したっていいや みたいな感じなのよだから小説界のボーボボだと僕 思ってますけど これこれは公式のAmazonの説明によるとハイコンテクスト、ハイファンタジー、ハイテンション、
メタノヴェル っていう名前がついてるんだけどこれ 説明不可なんで読んでほしいんだけどなんか意外と 早川書房の「ザ・SF」ではない変わった わけわからん「奇想」
みたいな流れのSFってあるんですよ一時期 僕 ラノベ奇書とかに
ハマってたんだけどあれってラノベより奇想の流れなんですよSFにも似たような流れってあるのよ これこの奇想を僕はちょっと もうちょっと
調べていきたいなと思っておりますけどねそんな感じで今回 この5作品を紹介しましたけれどもまた読んだ本 こうやって5冊とか何冊とかで
紹介できたらいいなと思っております僕は変わった小説
たくさん読みたいと
思っていますから純文学を中心としていますけれども別にその枠にとどまらず「クセが強いんじゃ」っていうぐらいヘンテコな小説ってありますからそういうの僕 大好きなんでもし皆さんも そういう小説とかありましたらぜひコメントで教えてください最近 読んだ「とても面白かった本」がありましたらコメントを書いて教えてください お願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#935「ディストピア小説」を15冊ほど紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は何するかというとディストピア小説15選この前 芥川賞で
九段理江『東京都同情塔』が
受賞したわけですけれども『東京都同情塔』は
ディストピア小説の面も
ありました前から僕 ディストピア小説を
まとめたいなって思ってたんですよ海外のやつは顕著に有名だけど日本の純文学作家が 結構 書いてますだからそれ めっちゃ紹介したいと思ってました今回 15個 選んでおります早速やっていきましょうまず海外のディストピア小説を5つ紹介します①ジョージ・オーウェル『一九八四年』これは超有名な作品でビッグ・ブラザーが出てきて全体主義国家の延長線みたいなやつなんですけどそもそも「ディストピア」って何かっていうと「アンチ・ユートピア」と昔は言われていてユートピアは「理想郷」っていう意味なんだけどこれ よく言われる話なんだけどそもそもユートピアっていう意味は
「存在しない場所」を表していたそれが「理想郷」になりそして1周回ってディストピアになるっていう話なんだけどジョージ・オーウェル『一九八四年』が1番有名と②ザミャーチン『われら』これはソ連の作家なんでソ連で書いたんだけどソ連では出版不可だったらしいんですよ違う国で出版し めっちゃ50年ぐらい経ってからようやくソ連でも発売されたっていう話なんですね時代設定が26世紀らしいですねこれも共産主義の延長で全ての国民が監視下に置かれるみたいな話③オルダス・ハクスリー
『すばらしい新世界』これ俗に「一九八四年」「われら」「すばらしい新世界」
で「三大ディストピア小説」って言われるらしい僕 一応 この15冊は 全部 読んでるんですけど『すばらしい新世界』って薬を
めっちゃ飲むイメージは残ってるだいぶ昔に読んだから覚えてないのもあるんですけど生まれた瞬間にも階級みたいのが決まっていてだいたいディストピア小説って国民全員が同じ考えを持ってるんだよね違う意見とかを持った
瞬間に粛清されるっていう
そういう構図なんだけどこの3つはそうですよね④レイ・ブラッドベリ『華氏451度』これは本を所有することが認められなくて「ファイヤーマン」って言って本を焼却する人っていうのが制度的に存在するとだいたいディストピアって真実を上書き・捏造していくのが多いから『一九八四年』とかも真理省って言って辞書とか直したりとか事実をねじ曲げたりとかするのが多いんですよディストピア小説ってだいたい本を焼くんだよね都合の悪いものは見えないようにしなきゃいけないから本を焼くっていうことは それが
真実だっていうことなんだけどね⑤カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』これ ネタバレっていうか
中間で確か出てくると思うけど日本でもドラマしてましたが臓器移植のための子供たちみたいな話ですよねオリジナルがいて 子供たちはそのコピーでオリジナルのための臓器のための子供たちだからいずれ殺される運命みたいなだいたいディストピアって制度なんですね国家とかのレベルで近未来 人類はこういう国家になってますよっていうそれは 一見 理想郷なんだけど本当は裏に めちゃくちゃ闇があってそれに気づいたやつがだいたい殺されたりするんだけどこの5つが海外のディストピア小説として有名な作品だと思いますこの後 日本のディストピア小説を
10個 言っていこうと思うんですけど通しで言えば 6つ目は⑥砂川文次『臆病な都市』これ 実はコロナ禍が起こる前に書かれた小説で鳥を媒介する感染症が流行る世界なんですよだけど実はそんなウイルスはなくて人々が「ウイルスのせいだ」とか言って俺は「××菌のせいで体調が悪くなった」とか言い出してみんな めっちゃ流行るわけよでも調べても科学的にそんな菌・ウイルスが出ないんだけど人々が暴動みたいになっちゃうから政府とかも「あります」って言わざるを得ないわけそうすると その存在しない菌なのにその隔離所とかも出てきて国が動き出しちゃう みたいな話になってくるのよそれがコロナの1年前ぐらいに書かれてるんだよこれ 天才だと思いますね⑦金子薫『道化むさぼる揚羽の夢の』この小説は主人公がいて主人公たちっていうか100人とか1000人単位の労働者が地下に施設があって そこで作っていくんですよ 工場みたいなところでそうしたら そこの職員がめっちゃ殴ってくるのよ 棒でそこから逃げたいんだけど多分 契約上 地下から逃げることができないわけカイジみたいになってるわけよ主人公が気ぃ狂っちゃってピエロみたいになっちゃって道化として振る舞っていって 人を笑かしていくみたいなそういう話になってくるのよねそこにちょっと狂気が入ってるのが面白いんだよね⑧いとうせいこう
『小説禁止令に賛同する』この小説は近未来が舞台で主人公が なんと「いとうせいこう」っぽいんですよね「いとうせいこう」と書かれてないが昔 エッセイで何か賞を取ってたりとか書き物をずっとやってたりとか自分も色んなことをやっているとか書いてて
明らか いとうせいこうさんっぽいのよその人がおじいさんとかになってて監獄みたいなところに閉じ込められるんだよねその世界って「日本」っていう国が多分無くなってて違う国から支配されてるんですよねそうなった時に 小説っていうものは人間に害しか与えないから小説禁止令っていうのが日本中にあって小説が読めないし書けなくなってるんですよこの小説はエッセイっていう体で書かれるんですよ私はエッセイを書いていますって言って
エッセイがずっと あるんだけどそこに「小説っていうのは本当に人間に対して
害しかないですよ」とか言うんだけど実際 読んでいくと小説の面白さが
書いてるようでもあるんだよね「小説はこういうところがダメです」って言った時に「感動を与えるからダメです」って言った時に「そこがいいんじゃん」みたいなことになるわけでしょだから意外と「表と裏」って反転するからダメなところを書いていくと 実は
面白いみたいなこと あるんだよねそういうことで主人公が小説の
ダメな部分を書いていくっていう小説⑨古川真人『ギフトライフ』これこそ近未来が舞台で普通に日本っていうものがあるんだけど電車に乗ってる時も広告がめっちゃ出てくるとかCMとかが車の中で運転してても「なんとか保険」とか言って
めちゃくちゃCMしてくるっていうこれは逆転させて 多分
資本主義の延長線だと思うんですよもう1個ね 障害者っていうテーマもあるのよ古川真人さんって これの1個前に『ラッコの家』っていう小説があってその中に「窓」っていう中編があるんですよそれも なんか障害者を焦点に当てたディストピア小説なんですよそれ めっちゃ面白いんだよねそれが多分 延長して この
『ギフトライフ』ができてる
と思うんですけどめっちゃいい
とてもいいと思う⑩李琴峰『生を祝う』李琴峰さんも『彼岸花が咲く島』
っていうので芥川賞を取っています『彼岸花が咲く島』自体がディストピアっぽいんですけど『生を祝う』は いわゆる反出生主義の延長線なんだよね女の人が子供を妊娠した時にお腹の中の赤ちゃんに電波みたいのを送ることで赤ちゃんと会話ができるっていう装置があるのよ「あなたはこの世に生まれてきたいですか?」
っていうのを質問するのよ「イエス」って言ったら そのまま生まれるんだけど「ノー」って言ったら そのまま堕ろさないといけないんだよ反出生主義者にならないように
念のためにそうやってるんだよね例えば「私は生まれたくなかったよ」って言って「お母さんが勝手に私を産んだんでしょ」って言った時に「産む時に検査をしてるから あなたは
イエスって言ったわよ」みたいな返せるわけよそうすると生きていかなきゃいけなくなるっていうそういう制度があるんだよねそれに振り回される主人公たちみたいな話 めっちゃ面白い⑪村田沙耶香『殺人出産』これも産むことに対してのディストピアこの世界では基本的には試験管ベイビーになっててお母さんとか もしくはお父さんでも
子供を産めるように手術できるんだけど基本的にはそういうことはしないともう人が人を産むことはあまりないんだけど自分から手を挙げて
「私10人子供を産みたい」
って言った人がいた場合この世界では子供を自分のお腹を使って10人産んだら人を1人 合法的に殺せるっていう世界なんだよね「あいつ憎くて憎くて仕方ない」と思った時に私10人子供を産みますともちろん10人子供を産むっていうのは時間もかかるし肉体的にもどんどん疲れていくから耐えないといけないんだけどねそれでも
あいつ殺したいって思ったら
もう殺せるっていう世界ねそれは男でも女でもできるということですよ⑫多和田葉子『献灯使』これは一時期 話題になった本ですけど近未来になっててまず日本っていうのが鎖国しているとちょっと右翼化してるわけですね もちろんねおじいさんとかおばあさんとかは100歳とかになっても医学的なものが発展してるんで全然 死なないわけよその代わり 赤ちゃんとかが二足歩行ができないとかそこまで体力がないんですよねそういう世界を描いていくって話なんだけどこれと次の⑬吉村萬壱『ボラード病』『ボラード病』も『献灯使』もそうだけど震災があった後に書かれてるんだよね2011年以降に
結構 ディストピア小説って
色々生まれてるんですねだから その時に日本で
ディストピア小説って多分 意識
されたような気がするんだね『ボラード病』は最初は日常っぽいんですよね子供が主人公なんだけどクラスからどんどん
子供がいなくなったって
いうか 死んでいったり町全体が変な感じ おかしな感じ気持ち悪い感じになっていって最後 どうなるかっていう話なんだけど吉村萬壱は『CF』っていう小説も出してるのよこれは僕 ちょっと読めてないんですけどこれもディストピアっぽいんだよねある工場というか 企業みたいなのがあって責任だったっけ 何かを有耶無耶にしてくれるみたいな金を払えば やった罪とかも全て消えるみたいなそういう すごい企業があるみたいな話らしいんだけどちょっと読まなきゃなと思ってますね⑭高見広春『バトル・ロワイアル』これ デスゲームものの走りなんだけど実はバトル・ロワイアル法みたいな
法律から来てるから(映画だけかな?)国家が関係してるから かなりディストピアなんだよね 実はこれ 有名な話なんだけどこの小説って 元々
日本ホラー小説大賞に
送ったらしいのよ 作者がそこで最終選考まで行ったんだけどちょっとヤバすぎるぞ この小説は
って言って落としたらしい今だったら全然デスゲームものとかもしくは人を撃ち合うゲームとかも多いわけなんだけど昔はそんなん なかったから人の命で遊ぶな じゃないけどそういうので大賞は取らなかったんだよねなんだけどそのヤバすぎる小説があるっていうのを知った太田出版がウチんとこで出しませんかって言って『バトル・ロワイアル』を書籍化したという話その後に山田悠介とかが多分入って今じゃ普通の分野になってるんだけど(デスゲーム)そこで国家の話になってるっていうのが1つキーワードなんじゃないかな バトロワね⑮沼正三『家畜人ヤプー』これはフェティシズムが1つあるっていうかエロを特化させたディストピアですよね(あと差別)つまり西暦3000年ぐらいにイースと呼ばれる地球にでっかい国があってそこは男尊女卑ならぬ女尊男卑になってて制度的に「日本人」っていうものは
「ヤプー」と呼ばれて差別されてるんだけどヤプーっていうのは肉体改造とかもこの時点で医学的な進歩があるから人間をちっちゃくさせたりとか人間を家具にしたりとか人間を変な動物に変えたりとかできるんですよねそれでエロの方に走ってますよね だいぶ三島由紀夫とか澁澤龍彦とかに褒められたりとかしてる伝説の小説なんですよね幻冬舎アウトロー文庫から全5巻で出てて僕もこれ 読んだことありますけどもう1回ちょっと再読したいなと思ってますけどねそんな感じで 今回「ディストピア小説15選」
ということで紹介してきましたけど結構 ディストピア小説って好きな人いると思うんですよ最初 SFの流れから来てると思うんですなんだけど意外と日本では純文学作家が書くことが多いですねエンタメ作家でディストピア小説ってある?SFのハヤカワ文庫とかだったらあるかもしれないんだけどやっぱりディストピアって思想が1つ入ってますからそれこそ さっき言った『彼岸花が咲く島』とかあと『東京都同情塔』みたいに芥川賞とかの流れに吸収されてるような気はしますけどね皆さんも もし好きなディストピア小説がありましたらこちらコメントの方まで教えてくれたらと思いますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#934「嬉しい事と悲しい事がありました!(東京へ行くぞ!)」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと最近にあった 嬉しいことと
悲しいことを言おうかと思います早速 嬉しいことを1つ言うと今度 2月22日〜23日あたりに僕は東京に行きますちょっとした旅行みたいな感じですごいことが起こっていますまだ この時点では言えません22日23日以降じゃないと言ってはいけないということを言われておりますので 詳細は言えませんが1つ 僕が1番 嬉しいことが起こりましたそれは先に言っておくと別に「本を出す」とかそういうことじゃないんですしかし東京に行かないとできないことで今まで 僕 YouTubeを4年間ちょっと やってましたけどYouTubeをやっててよかったな
って思うことが起こるみたいですね今 詳細を言ったらオジャンになるんで 今は言えませんが2月末ぐらいには言えるでしょうその時に楽しみにしておいてください2月22日と23日あたりは僕は東京にいますのでもし東京の方 いらっしゃったらぜひお会いできたらいいなと思ったりします僕 21日ぐらいから夜行バスで22日に行きたいんですけど多分 22日の昼(もしくは朝)は 僕国立国会図書館に行きたいなと思ってたりもしますね国立国会図書館でしか読めない本っていくつかあって僕が今 読みたいなと思ってるのは『好き好き大好き!』っていう 昔にあった電波ゲームのノベライズっていうやつがあってこれ 本当に入手が不可能で アマゾンで3万円して電波ゲームのノベライズって普通の市の図書館とかにはないんですねでも国立国会図書館というのは原理的には全ての資料・本を集めてる図書館なのでそこに行ったら読めるんですよ この本はそれ 22日の9時半以降に読むかなと思ったりします国立国会図書館は9時半から開館してるみたいですね僕も行ったことないんで 初めて行くんでちょっとやり方がまだわかってなくて 今調べてたりしますよ僕の予定では 23日の夜に夜行バスに乗って 大阪に帰るってことをしたいんだけど23日も空いてるから 誰かと色々喋ったりとかどこか本屋さんを巡るとか
そういうのしたいなとは思ったりは
してるんですけどねあと悲しかったことが1つあってまた父親と喧嘩したっていう話なんですけどいやー なんか僕は父親と本当に確執があってすぐ喧嘩するんですよ実家の近くに住んでいるもので時々 実家に帰ったりするとやっぱりダメなんだなぁ僕はこんなん言うと本当にアレだけど幼い時から父親に殴られてきたしモラハラに近いような本当に
ひどいことを言われて育ってきたんで僕 自尊心ゼロなんだよねマジで自分ってすごいっていう気持ちが全くなくて俺ってダメなんだみたいな気持ちで僕34年間生きてきたから本当にいつ死ぬかわかんないぐらいのしんどさあるのよあと これと 時同じくしてニュースとして 原作者と脚本家の問題ってあったでしょうあれで僕の心をドーンって来ちゃったんだよね僕 傷つくことに とても弱いっていうかそういうニュースとかでもバーンって来るんですよそれで結構 多分 精神的に落ち着かなくなっちゃって父親と会った時に爆発しちゃったんだよねそういう然るべき相談機関に僕は行こうと思ってるのよ今回のことがあったから ちょっとカウンセリングみたいな受けようかなって最近 思ってて今まで なあなあにしてきたっていうかそういう心理学の大学とか大学院に僕は行ってましたから結構 それでも だいぶ楽になったんですよね色んなことを学んだことでだいぶ楽になったんだけど実際 ちょっと行こうかなっていうのは考えています前の前の職場とかでも僕 自尊心がないもんですから色んなことが言えなかったなぁこういう時に 何かを言うべきっていう時にやっぱり「待ち」っていうかこんな自分がしゃしゃり出ていいんだろうか
みたいな気持ちにずっとなってるしあと 然るべきに何かもらう時とかあるじゃないですかお菓子とかじゃないよ 大事なものをもらう時とかに断ってたりとかしてたんですよねこんな自分にもらうもんなんかないとかそういう気持ちばっかりなんですよ 僕 本当にかなり不安定なんですよだから 喧嘩 数日前にして本当に何も手が付かなくなっちゃって会社もちょっと休んであと本も読めなかったし動画も作れなかったんですよねこれは全ての人に言えるけど休む時は休まないといけないんで僕は今ちょっと お休み気味っていう感じかな精神を回復しようと今やってるって感じ僕もここ数日は本当にキツかった色んな意味でキツかったんだけど友達に相談したりとかそういうのはしてて ちょっとは収まった感じするからまた平常運転で行けたらいいなっていう気持ちはありますこれもちょっと焦りであると思うが12月の同人誌のために本も読まなきゃいけないもんでそれが ちょっとずつの圧迫っていうかストレスっていうかそういうのになってる可能性もあるかなでも 僕の人生さ 山あり谷ありという感じをするけど去年 2023年も1月だったと思いますが東京に行って 新潮社の本社に行って対談したんだよねそれは「小説新潮」っていう雑誌のためのお仕事みたいな感じで行ったんですけど今年も まさか東京に行けるとは って本当に思ってねやっぱり東京なんだね日本っていうのは東京なんだなっていうのは思いますけどね本の話 ちょっとだけすると1週間前ぐらいにこれは読まなきゃいけないな っていう本がいくつかあって中西智佐乃
『狭間の者たちへ』桜井晴也
『世界泥棒』これ 結構 分厚いんですよね分量が多くて 後回しにしてたんですよなんだけど 今年 頑張るかっていう気持ちでこの2冊を続けて読んだんですよそれで読み終わって やったーと思ったわけこの2つは 僕が読みたい本リストの20冊の中の2つだったんでそれも とても嬉しくてやっぱり僕 本を読むことが楽しいと思うし人生 とんでもなく辛いことばかりなんだけど本を読んでいくしかないんだなって僕は思ったYouTubeをやっててよかったですよこれからも もちろんやりますけどね今度 東京に行くから頑張るしかないと思った人生を変えるには 然るべきタイミングで然るべき行動をして頑張っていくしかないんだなっていう気持ちはしておりますねまた 本にまつわる動画を出していけたらいいなと思っておりますので皆さん どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#933「マジで素晴らしい本を16冊を買ってきました!&献本も!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#932「【本棚】本が1万冊あるヤバ部屋のルームツアー(2024年ver.)」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#931「2023年の国内の文学賞16賞を受賞した小説23作を振り返ろう!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと2023年の文学賞を振り返っていこう日本の主な文学賞って だいたい16個あって(純文学で)1年の中で その16賞の受賞作が発表されるということですねそれを今回 1個ずつ振り返っていく動画でございます早速やっていきましょうまず非公募型から行くと1月に芥川賞があるんですね2023年1月に発表されたのは井戸川射子「この世の喜びよ」佐藤厚志「荒地の家族」「この世の喜びよ」はデパートがあってその中におばさんと女の子がいるその2人の心の交流を書いてるって作品でめっちゃ面白い「荒地の家族」も超良かったね東北の地震のことが書いてて植木職人の人生が書いてて悲しいんだけど とても良かったですね2月に読売文学賞が発表されるんですね受賞したのは佐藤亜紀『喜べ、幸いなる魂よ』僕は佐藤亜紀って実は読んだことなくて佐藤亜紀って僕の中でエンタメ作家のイメージあるんだけど意外とこういう純文学系の賞に来る時 あるんですよこの作品か もしくは違う作品もちょっと読んでいきたいと思ってはいます4月には川端康成文学賞が発表されまして受賞作は滝口悠生「反対方向行き」これは『鉄道小説』というアンソロジーに入ってる作品でこれも僕 読めてないんですね滝口悠生 めちゃくちゃ すごい作家だと思う滝口悠生を読まなきゃ純文学好きとは名乗れないんじゃないかって思われるぐらいのマジやばい純文学作家なんで5月に三島由紀夫賞が発表されました受賞作は朝比奈秋『植物少女』これは僕 読みましたね植物状態になってるお母さんがいてその娘さんが主人公という話で悲しかったねあと7月になると芥川賞が発表されました芥川賞は1月と7月に受賞作が発表されますんでこの7月は市川沙央「ハンチバック」障害っていうものをテーマにして衝撃の最後のオチっていうのもあってとても良かったですねあと8月になると谷崎潤一郎賞が発表されまして今回の受賞作は津村記久子『水車小屋のネネ』谷崎潤一郎賞はベテランの賞なんですよね津村記久子さんも だいぶ書かれているでしょう僕も全部は読めてないなあ初期のやつは読んでるつもりなんですけどねこれもちょっと読めてないんでまたちょっと読もうと思いますね9月になると泉鏡花文学賞っていうのがあって今回の受賞作は北村薫『水 本の小説』朝比奈秋『あなたの燃える左手で』北村薫さんって元々エンタメ小説を書いてて直木賞も取ってるんだけど僕は北村薫を読んでないんですよね読まなきゃなと思うよねだから この『水 本の小説』もちょっと また読みたいと思いますね朝比奈秋さんは さっき三島賞も取ってたんだけど泉鏡花文学賞も取ってるんですよだから2023年 文学賞としては朝比奈秋 めっちゃ来てるんだよね(後述の賞も)すごいと思います マジで同じく9月にはBunkamuraドゥマゴ文学賞がありますこれは選考委員が1人しかいない文学賞で2023年は俵万智さんが選考委員だったみたいです選ばれたのが山崎ナオコーラ『ミライの源氏物語』僕 これは読んでないですね山崎ナオコーラも初期の作品はめちゃくちゃ僕 読んでますよ芥川賞候補も5回ぐらいなってて僕 多分 全部 読んでるんだと思うんだけど特に初期の方は 恋愛とかが多くてそこが とても良かったんだよね次 11月になると野間文芸新人賞ですよね2つあって 1つは朝比奈秋『あなたの燃える左手で』九段理江「しをかくうま」さっきも泉鏡花文学賞で『あなたの燃える左手で』が選ばれてるんだけど野間文芸新人賞も選ばれてるのよ僕は『あなたの燃える左手で』は読んでますウクライナの問題をやってるっていう国際派だったんですけど とても良かったですね九段理江「しをかくうま」なんだけど僕 これ読めてなくてなんでかって言うと 単行本化されてないんで僕 単行本派なんで雑誌掲載のままのやつだったら読めてないのが多いんですけどでも やっぱり僕 気になってるから野間文芸新人賞を取ってるやつは最近のやつは ほとんど僕 読んでますんでこれも近いうちに読もうとは思ってます最後ですね同じく11月に野間文芸賞っていうのがあって野間文芸新人賞は新人が取るんだけど野間文芸賞はベテランの賞で今回の受賞作は川上弘美『恋ははかない、
あるいは、プールの底のステーキ』これ 僕 読んでないんですけど川上弘美さんも僕 初期の方は結構 読んでるんだよね最近のやつ 読めてないから また読もうとは思ってますねこれまでのが 非公募型の文学賞 10賞ありましたが次は公募型が6賞ありますこれを1つずつ言っていくとまず4月には文學界新人賞がありました市川沙央「ハンチバック」この「ハンチバック」が文學界新人賞を取りそのまま芥川賞を受賞したというパターンですね市川さんには次 2作目 めちゃくちゃ期待しております次 5月になると群像新人文学賞があるんですね今回は2作品 受賞があって 1つは村雲菜月『もぬけの考察』夢野寧子『ジューンドロップ』僕はどっちも読みました村雲菜月『もぬけの考察』はホラーなんですよねマンションの ある部屋に住んでる人が突然 行方不明になるんですねまた新しい住人がやってくるんだけどその人も行方不明になるのよそれをいくつか繰り返してサイレントヒル4みたいなそういう話だと思うんですけど とても良かったですねあと夢野寧子『ジューンドロップ』これも とても面白くてコロナ禍が舞台で 女性が2人いてその交流を書くみたいなやつでしたけどコロナ文学の1つだと思いますけど とても良かったね続きまして 5月になると 太宰治賞があるんですね今回の受賞作は西村享『自分以外全員他人』僕 これ 読めてないんですよ周りの文学好きの人から聞くと面白いという噂がありますからめっちゃ読みたいとは思っています次 9月になると すばる文学賞 あるんですねこれは なんと伝説の大田ステファニー歓人『みどりいせき』これはまだ単行本が出てなくて2月に単行本化されるらしいんですよその時に僕は読もうと思ってますけどすばる文学賞は毎年一応 単行本化されるんで待ってたら単行本が来るんでとても嬉しいとは思ってます 毎回次 9月になると 文藝賞が発表されるんですが今回の文藝賞は ちょっと特別で受賞作品が5作品もあるんですね言ってしまえば 長編賞と短編賞っていうのがそれぞれあって長編賞は3つあって 1つは小泉綾子『無敵の犬の夜』2つ目は佐佐木陸『解答者は走ってください』3つ目が図野象『おわりのそこみえ』短編賞が2つあって西野冬器「子宮の夢」才谷景「海を吸う」これ 僕には珍しく全部 読んでますよ『無敵の犬の夜』は令和の大江健三郎みたいな感じだし『解答者は走ってください』は
マルチバース文学って書かれてましたけど『おわりのそこみえ』は人生オワコンみたいな主人公がいてどうやって生き延びていくか みたいな感じの短編の2つは とても難しい前衛小説みたいな感じだったね「子宮の夢」ってタイトルの通り夢の世界なんで シュルレアリズムがだいぶ入ってるし「海を吸う」も人間が水を吸っていくみたいなよくわかんない設定なんだけどでも とても良かったですね最後 10月になると新潮新人賞がありまして受賞作は2つあって伊良刹那「海を覗く」赤松りかこ「シャーマンと爆弾男」この2つは僕 読めていませんねこの2つは まだ単行本化されてないんですね僕は雑誌で あんまり読まないもんですから単行本化されてないやつは中々 手を出せてないっていうのが実情なんですけどでも いつかの どこかの段階で文芸誌の方にチャレンジして単行本化される前から情報収集したいなっていうのはずっと思ってるんですけどねそんな感じで 今回2023年に受賞した小説 紹介してきました日本の純文学って基本的には文学賞を中心に動いていると言っても過言ではないと思うんですねその辺を探っていくと現代文学っていうのはスッと入ってきやすいと思いますまた文学賞今年も2024年も発表されていくと思うんですけどもし発表されていけば また動画 それの関連する動画どんどん撮っていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#930「私つかつの「2024年の抱負 7選」を語ります」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何を話すか
と言うと「2024年の僕の抱負 7選」ついに2024年になって新しい1年が始まるっていうことなんですけど私つかつ 今年やりたいことがいっぱいあるのよそれは文学的なものもあるしYouTube的なものもあるしもっと自分の個人的なものもあるんだけどそれを1個1個 話していこうかなと思っておりますね早速やっていきましょう今年の抱負 まず1つは①「同人誌を作ること」2024年12月1日に文学フリマ東京39 っていうのがあってそこに初めて僕が出品したいということですね「つかっちゃんの現代純文学1000冊」という本ですねこれについては色々 動画を出してるから それ見てもらったらいいんだけど僕は 今年 2024年はYouTubeでの活動が5年に入るんですね9月に入ると5年経つんですけどそれの総決算っていうのがこの同人誌になると思っております逆に言うと この5年間 YouTubeで ずっと色々 活動してきてさ辛いこともあったし しんどいこともあったけど楽しいこともありましたが本について めちゃくちゃ動画を出してそれのまとめ みたいのが書かれていると僕の考えだったりとか僕の読んだ純文学の1000冊とかそういうのが載ってるわけでそれ 本当に出したくて出したくて仕方ないんですね一応 原稿もちょっとずつ進んでいます約11ヶ月後ぐらいにあるんでまだまだ時間はあるんで ゆっくりやればいいんですけどそこから派生してやらなきゃいけないこと っていくつかあってそれもちょっと言うと同人誌は僕が読んだ純文学1000冊を1個1個 レビューしていく内容なんですよそうすると1000冊 読まなきゃいけないわけね そりゃね僕 今 860冊ぐらい読んでるんで実はまだ足りてなくてあと230冊弱 読まなきゃいけないってことなんでそうなると 今年の目標・抱負としては②「あと230冊 読む」皆さん もし あと230冊 読めって言われた時に何を読みますかって話なのよ230冊って聞いた時に 多いなって思う人と少ないなって思う人がいると思うんですよ僕は「少ないな」って思うし「やった! 230冊もあと読めるんだ」っていう嬉しさがある今から めっちゃ考えてるもんね「これも読んでこれも読んで紹介したいなあ」とか言ってめっちゃ頭の中 ぐるぐる回ってんですよある種の躁的状態になっていてちょっとヤバいぐらいになってるんだけど同人誌に載せる 僕が勧めたい本みたいなまだ読んでない本 って山ほどあるんでそれを読んでいこうと思ってますもう1個 同人誌から派生した やらなきゃいけないことは③「貯金」同人誌を作るのに お金 かかるんですね原稿を印刷所に頼んで本にしてもらうのに もちろん金かかるんですけど僕の同人誌は 200ページで100部ちょっと 刷ろうと思っているんですけど高いところは10万円とかかかるし僕が調べて 安いところは5万円も行かないぐらいのところがあるんですよそれが5万円として残り5万円ぐらい文学フリマに申請するのも金かかるし大阪から東京の移動費とかもかかるし色々ちっちゃなもの買わなきゃいけないというのもあるからもろもろの諸費としてプラス5万ぐらい かかると思うんですよそれを足して10万円ぐらい かかる予定なんですね僕は万年貧乏なんで今の貯蓄からでも出せるんだけどでもやっぱり目標としては今年 10万円を貯めてそれを使って同人誌を作るっていうのをしたいから貯金箱を買って そこに入れていこうかな と思ってますこのYouTubeでも ちょこっとだけ収益 出てるんでその収益を同人誌代に全部回そうと思ったりしております同人誌編は終わりで 次 YouTube編なんだけどYouTubeの目標としては 2つあって 1つは④「登録者数 1万人になりたい」今 登録者数は8000人ちょっとぐらいいるんだけどだいたい僕のYouTubeのチャンネル的に1年間で2000人ぐらい増えるんですよ頑張ったら多分 今年中には1万人に行くと思うんですね僕 もう1万人いたら もう求めるものはない僕は別に登録者 増えたら増えたら嬉しいんだけどそこを目標とは僕はしてないから自分のやりたいこと 自分の伝えたいこと本のことを ずっと言い続けるチャンネルにしたいから僕は長く長くしたいだけなんで長くやれば 自然に増えるかもしれないんだけど1万人ぐらいいたら もうええかって思ってるのよ 僕の中でこれはよく言われる話だけどYouTubeの全チャンネルがあった時にその中で「1万人以上いるチャンネル」っていうのは全体の3%しかいないと言われるんです僕はその3%に入れたらもうええかなと思ってるわけ1万人でも5万人でも10万人でも変わらんなと思うしそこまで行けるかもわかんないから現実的に考えたら 1万人ぐらい いたらまあまあ箔がつく感じあるでしょ1万人超えたら 僕は登録者数のことを考えたくない 逆に逆に1万人までの時がしんどいね意識しちゃうから今8000人でしょう1万人まで あと2000人だって頑張らなくちゃ とか思っちゃってるんですよ 僕の中でそれしんどいのよ早く1万人にはなりたい1万人になったら もう考えない
っていうことをしたいなと思っていますYouTubeに関して もう1個あって⑤「動画の投稿数を1000本にしたい」今 僕のチャンネルは900本弱ぐらいなんであと100何本か出したら1000本になるのよこれは自分でコントロールできる問題だから僕が頑張れば できるわけね登録者数っていうのは結局は 他人が登録するっていうシステムだから僕自身ではコントロールはできないんだけど動画を投稿するってことは僕自身でコントロールすることができることなので僕の頑張り次第なんで できるんだけどしかし 僕も今 元気がなくて(今年)100本ぐらいだったら できるのかなっていうギリギリのラインって思っています1000本 投稿するっていうのは多分 すごいことなんだろうなって思わないですか1000本っていうのは 4桁なんで僕は「数字マニア」みたいな感じなんで結果っていうのは 全て数字に出るもので「登録者数1万人で動画1000本出してます」って言った時にその数に驚くでしょう 僕自身も驚くもん自分で自分を褒めてあげたいから「よくやったなお前」って自分自身に言ってあげたいから僕はそれは 今年 目指したいなと思っています最後 僕のプライベートの目標が1個あって⑥「ダイエット」これ 毎年言って 毎年できてないんだけどでも今年 もう1月20日ぐらいになってるんだけど目標のために やることをやってますそのやってることっていうのは自分の食べたものと 体重を全部 記録しています僕は「データ魔」なんでデータに何か取って それを継続する
っていうのが多分 好きなんですね去年も僕 自分の食べたものと体重を記録し続けて1〜2ヶ月ぐらいやってたら 意識するのかダイエットの結果 出てきてめっちゃ痩せたことがあるんだけど やめちゃったんだよね僕 うまい具合に1月から始められたから それ(記録)12月まで その記録は続けたいと思うしあと 賛否両論あるかもしれないけど僕 この20日 白米を食べてないんですよねおかずとかは食べてるんけど僕 白米を食べるの 山ほど食べちゃう人間で米って美味しいでしょうだから今 ちょっと封印してるんですよ炭水化物自体は他のパンとかあと麺類とかそういうので取ってはいるから 多分 大丈夫と思うんだけど白米は今年 ちょっと禁止したい⑦「2024年 白米 食べない」これも だいぶ昔だけど白米を僕は1年ぐらい食べなかった時期 あるんですよその1年 続けた後に久しぶりに食べたんですよ ご飯そしたら めっちゃ甘かったおかずなしで米だけで食えるぐらいの舌になってたんですよだから1回 封印するっていうことも僕 必要だと思う 何事もそれで封印を解いた時の良さ そういうのあるでしょそういうのを今年やってみたい 白米でそんな感じで 今年の抱負を言ってきましたけど実行できるかどうかは 結局 継続次第全然ダメでしたと 無惨な結果になるかもしれないんだけどそれでも こうやって動画に出すことが
大事と思っておりますからそれを皆様の目を通して「つかつ お前 全然できてないじゃねえか」って叱咤激励していただければと思っております僕自身も今年 頑張って頑張っていきたいと思います色んなことにチャレンジして精進していきたいと思っておりますので皆さん 私つかつのことをぜひぜひ応援していただければと思っておりますどうぞよろしくお願いしますそんな感じでございます 今回は終わり高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#929「【購入】これぞザ・文学って本を16冊を買ってきました!」
購入本紹介動画のため、購入本を羅列します。
1.万城目学『八月の御所グラウンド』
2.河﨑秋子『ともぐい』
3.加藤シゲアキ『なれのはて』
4.村木嵐『まいまいつぶろ』
5.宮内悠介『ラウリ・クースクを探して』
6.嶋津輝『襷がけの二人』
7.青木淳悟『このあいだ東京でね』
8.町屋良平『坂下あたると、しじょうの宇宙』
9.谷崎由依『囚われの島』
10.松家仁之『優雅なのかどうか、わからない』
11.菊池良『芥川賞ぜんぶ読む』
12.西沢正史『あらすじダイジェスト 日本の古典30を読む』
13.木尾士目『Spotted Flower』5巻
14.講談社『ファウスト』Vol.7
15.佐々木敦『ニッポンの文学』
16.川端康成『美しい日本の私』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#928「【予想】第170回芥川賞・直木賞の受賞作を予想します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと第170回 芥川賞・直木賞の受賞作を
予想するという動画でございますいやあ〜 長かったですねこの1ヶ月は僕はずっと この芥川賞・直木賞の候補作を読みその動画を1本ずつ出していきました今回は9回目の試みなんですけど我ながら よくここまで来たと思うしあとせっかくなんで受賞作を当てていこうじゃないかということでございます早速やっていきましょうまず直木賞の方から予想しようかと思います候補作の1個1個の動画で 僕は点数をつけていきましたそれを今回 全部 振り返ってみると加藤シゲアキ『なれのはて』92点河﨑秋子『ともぐい』85点嶋津輝『襷がけの二人』82点万城目学『八月の御所グラウンド』80点宮内悠介『ラウリ・クースクを探して』87点村木嵐『まいまいつぶろ』90点この中で1番高いのは加藤シゲアキ『なれのはて』92点となっておりますね今回 珍しく直木賞ではミステリがこれだけなんですよねいつも いくつか入ってくるんだけど意外となかったっていうのとあと今回の直木賞の特徴は時代物が多いってことですね『まいまいつぶろ』は徳川家重の
人生について語るというのと『ラウリ・クースク』に関しては
エストニアを舞台にしていますからそれの歴史もあるしあと『襷がけの二人』も 大正・昭和
っていうところを描いたというのもあるし『ともぐい』も だって日露戦争の前後なんで現代を舞台にしてるのが少ないんですね むしろ万城目学『八月の御所グラウンド』は現代『なれのはて』も現代なんだけど戦前からやってくるから 何十年みたいな50年とか そういう単位で動く小説が多かったあと もう1個は友情ものが多いっていうのが
特徴として あるんじゃないですか『ラウリ・クースクを探して』も友情ものでしょ『まいまいつぶろ』も友情ものでしょ『襷がけの二人』も友情ものなんですねだから結構 作風自体は もしかしたらだけどちょっと偏ってるっていうか似てるようなところはあるかもしれないそこでバチバチ言ってるかもしれないねこの中で言えば
異色作なのは『ともぐい』
っていうパターンもあるのよ『ともぐい』は ある猟師の
エロスとタナトスをずっとやってて死ぬか生きるかみたいな世界でやってて最終的にドロドロの世界になっていくっていうそういうのは『ともぐい』しかない感じはあった僕は 正直 加藤シゲアキは何回か前の『オルタネート』は読んだことあったんですよこれも直木賞の候補になってたからでも 結構 青春だったんだよね あれ僕は青春ものってあんまりハマる時とハマらない時があるわけよ僕もいいおっさんなんで陽キャのことを書かれると僕は陰キャなんで 合わない時 あるんですけど『オルタネート』もこんなん言うと悪いけど ちょっとハマらなかったんだけど『なれのはて』良かった大人の読み物みたいな感じがあって かなり重厚的今回 もし加藤シゲアキが直木賞を取った時にかなりデカいニュースになると思うんです誰かが「芸能人だからあげたんじゃないか」
とか言うやついるかもしれないけど芸能人だから
贔屓をしてるわけではない
ということですよ 僕はもしダブル受賞があるとしたら村木嵐『まいまいつぶろ』が僕の中で次の点数として高いのでこれかなっていう気はする前回の直木賞って時代小説・時代小説で「ダブルちょんまげ」と呼ばれていたんだけど最近 時代小説 直木賞でかなり評価されてるんだよねむしろ現代劇っていうのが あまり
来てない傾向にあると思いますがでも この徳川家重 良かったね徳川家重の話も泣けるんだよねだから個人的にダブルが来るとしたら『なれのはて』『まいまいつぶろ』かなでも 今回は 単品で
単体で『なれのはて』1本に
しておこうと思います 僕は続きまして 芥川賞 受賞予想になりますがさっきと同じように1個1個の点数 言っていこうかと思います安堂ホセ「迷彩色の男」90点川野芽生「Blue」94点九段理江「東京都同情塔」98点小砂川チト「猿の戴冠式」92点三木三奈「アイスネルワイゼン」96点ということは 1番高いのは九段理江「東京都同情塔」98点となりますね今回の芥川賞候補はどれも良かったですねちょっと社会派が多かったという傾向はあるでしょうね「東京都同情塔」「迷彩色の男」
「Blue」は明らか社会派だと思います「アイスネルワイゼン」「猿の戴冠式」は社会派ではないがやっぱり それぞれ本当に良かったね特に「猿の戴冠式」って今回だったら猿と人間の心の通じ合いっていうかでもそれも一種の妄想っていうか勘違い
みたいな捉え方もできると思うからかなりやってること 難しい僕は難しい小説が好きだから簡単な小説は簡単だから読む価値ないまでは言わないけどやっぱり実験精神は欲しいよね 純文学は特に芥川賞なんかは 結構そこら辺は試されてる感じはあるからね「新しい文学」としての入門として芥川賞のレースに選ばれるってことはそれぞれ それぞれのやり方で「次世代の文学」へ行くっていうことなのでそこを試されてる感じはするんだけどでも僕がやっぱり1位なのは「東京都同情塔」これこそ実験精神あったんじゃない?現代的ですよ 極めて未来のことをやってるっていうのも1つ面白い2030年が途中で舞台になるんだけどそこにバベルの塔よろしく1つの塔があってそれは刑務所なんだけど 新しい刑務所だっていうやつねこれ結構 キャラクターが かなり誇張されてるっていうかそれぞれの役割があったよね結構 分量が多い小説だと思うが主な登場3人ぐらいしか出てこないんだよねそれぞれに決められた役割みたいなのがあってそこの交流で多層的にしてるんだと思うこれと対比的なのが「アイスネルワイゼン」「アイスネルワイゼン」も中編だけどこれは登場人物が10人以上出てくるしでも それぞれに表と裏があるんですね文学って この2つだと思うんです1個は登場人物を ある特徴を持って ある性格を尖らせて鋭くさせて 1つの戯画化するっていうかその小説の役割として置くっていう方法ともう1個は 人物をリアルにするために表と裏を描くってことねつまり両面性を描くっていうのが
あって どっちもあるよね これここが対比的だったような気がする「東京都同情塔」は文字びっちり書いてるんだけど「アイスネルワイゼン」はかなり会話が多くてパパパってテンポよく 改行が出てくるんですね頭と体みたいなところはありませんでした?静と動みたいな感じで「東京都同情塔」は理論派でずっと理論の話をやってる感じがあるんだよねだから物語自体はそんなにドカッと動かないストーリー自体がそんなにないんだけど「アイスネルワイゼン」はめちゃくちゃ
主人公があっち行ったりこっち行ったりしてあらすじを言うと長くなっちゃうわけよだからこれ もしダブル受賞あるとしたら「東京都同情塔」と「アイスネルワイゼン」かなと思いますねこれは周りの人たちもこの2つはめちゃくちゃ面白いって言ってるんで実際 どうなるか分かりませんが少なくとも どっちかは受賞するんじゃないかな
(僕の予想は「東京都同情塔」単体です)そんな感じで 今回第170回 芥川賞・直木賞の受賞作を予想しましたけどこれ 最後に言いますけど僕はエンタメ小説より純文学の方が好きなんですけど芥川賞ってのはお笑いで言えばM1みたいなものなんだよね直木賞は違うよ直木賞はTHE SECONDみたいな感じかもしれないだって中堅・ベテランが多いのが直木賞で芥川賞は新人だからねM1で考えると やっぱり優勝した方がいいと思うんですねなんでかと言うと 一生言われるからこの前のM1を見たら 歴代の優勝のコンビが1個1個 出てくるわけよ中川家・ますだおかだ・アンタッチャブルなんとかかんとか とか言って バーって出るでしょ毎年 言われるわけよ負けた人は言われないわけよ僕も大学生の時は 芥川賞の受賞作をずっと遡って読んでたっていうのがあるんですよその時 候補作までは見てなかったんですね意外と賞レースの「結果」を見るのも もちろんいいんだけどその「過程」ですよね 今回は過程だからね これねこの5作品 芥川賞の候補が出てそれぞれ どんなネタをやってこいつが強いとかあいつが強いとかで下馬評がありながら最終的に結果が出るってことなんで優勝した人のネタを見るのもいいんだけど負けた人たちも 後ろには山ほどいるわけだから意外とそっちの方が面白い みたいなことも全然あるんで今回もそうだけど 最近の芥川賞は候補作 全部 面白いんでもし皆さん よければ 受賞作だけじゃなくて候補作も全部 余裕があったら読んでほしいなって本当思うよ全部 一応 単行本化される予定ですから本当に面白い 超面白いんで みんな読んでほしいそんな感じで この1ヶ月間 続いた企画も今回の動画で最後ということでまた本に関する動画 色々と
出していきたいと思っていますから皆さん どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#927「【書評】芥川賞候補⑤三木三奈「アイスネルワイゼン」」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらになっておりますねこちらは「文學界10月号」なんですけどこの中に三木三奈
「アイスネルワイゼン」これは今回の芥川賞の候補作となっておりますね「アイスネルワイゼン」めっちゃくちゃ面白かったですねとても凄みを感じる小説だったんじゃないかと思います早速やっていきましょうあらすじ主人公は「琴音」っていう女の人で 32歳なんですけどこの人はフリーのピアノ講師はやってるんですよ最初 ゆあなちゃんっていう教え子がいて小学生のピアノを習ってる女の子がいてそこに通ってるとピアノの家庭教師ですよねをやってて 色々教えてるんだけどゆあなちゃんは今度ピアノの発表会があるんだけど本人はちょっと参加したくないとなんでかって言うと自分より年下の子がうまくピアノをやってると嫌な気分になるからって言って今度の発表会 ちょっとしたくないんですよとか言うわけよゆあなちゃんはプラス漫画を描くのが好きで琴音に漫画を見せたりするんですよそれが終わり 琴音は今度 小林っていう人と電話すると小林とは 友達でもあるだろうし仕事を紹介してくれる人でもあるんですよだから結構 フラットに喋るんだけど その時に結構 悪口っていうのかな「ゆあなちゃんは漫画を見せて
くるんだけど それ下手で」みたいな「ゆあなちゃん このままだったら
ピアノやめちゃうかもね」みたいなちょっと 悪い言い方を 琴音は
使うことがあったりするんですよ小林の方も結構あるんだけど それその小林から今度 仕事の依頼があって今度 ケアホームっていう高齢者がいるところで伴奏の仕事を任せたいとよし子っていう歌手の人がいて自分より年上の人 おばちゃんみたいのがいてその人は歌うからピアノの伴奏してほしいっていう依頼が来るんですよその日が なんとクリスマスイブで主人公は その後に予定が入ってるから 最初 断るんだけど小林に言われて「それ お昼だからお願いするわ」とか言われて「わかったよ」とか言ってその時に 車のところがめっちゃ面白くてよし子と合流してそこからケアホームに向かうんだけど車で行かなきゃいけないとよし子と主人公しかいないからどっちかが運転手にならないといけないんだけどよし子は「私 運転しない」って言うわけよ「あんたして」って言うわけよ主人公はペーパードライバーで一応 免許を持ってるんだけど高速とか乗るのが苦手で車線変更とかも うまくスムーズに行かなくてよし子にどやされるんですよねあとケアホームに着いてからピアノの伴奏するんだけどその時に あとで「あそこ やっぱり間違ってたわよ」とかって結構グチグチグチグチ言われちゃうっていうのでよし子のこと 腹立ってるわけよ 主人公はそのあと 用事っていうのが中学校の友達だった「優」っていう女の人がいてその人の家に行くと優はもう今 結婚していて旦那さんいて 子供を1人いるとそこで クリスマスイブだからご飯をご馳走になるっていう話があるんだけどこれ 結構 悲しい話があって優さんは目が見えなくなってるんですよね後天性で目の病があって今はかなり見えなくなってきている優の子供が太子っていう 小学校の子がいてその子がクリスマスだからサンタさんが来るんじゃないかとか言ってスイッチを頼んでいるとNintendo Switch がほしい
ってサンタに頼んでるんだけど優の夫がいて夫が 太子君が もう寝ちゃってそこに なんか紙があったとそこの紙を見ると「Nintendo Switch はいらないから
お母さんの目を治してくれ」っていう願い事が書いてるわけよ僕なんか これだけでも泣いちゃうんだけどそれで夫が それを言わないんだよね 優に妻に言わずに「また太子はSwitchって書いてたよ」みたいな言って優は目が見えないから わかんないから「またSwitchって書いてるの?」みたいな「1回 頼んでるのになあ」みたいな言うんだけど本当は「目を治してくれ」っていう願いでそれを主人公も見るわけよそしたら多分 主人公もウルッと来てるんだよね それね子供の純粋な愛みたいのにやられちゃって主人公・琴音がトイレで吐いちゃう
っていうシーンもあるんだけどそこのシーンも終わり最後 バスに向かうっていう話があるんですよ元々 琴音っていうのは遠距離恋愛をしてるらしいと夜行バスで行かなきゃいけない
ぐらいの距離のところに彼氏がいて25日に会うためにこの日ですよね クリスマスイブの
夜中に深夜バスに乗るんだけどそれが 最後 すごいところに行くっていう話なんだよね僕の感想になるんだけどこの「アイスネルワイゼン」あらすじだけ聞くと なんじゃそりゃって思うと思う僕もなかなか まとめられないんだけどこれ とてもすごい小説だと思いますよまず登場人物がやたらと多い長さ的には中編ぐらいで原稿用紙200何枚って書いてたような気がするけどこの中に10人以上 出てくるんですよ基本的には 琴音を中心とした人間関係なんですけどまず主人公の琴音が性格が悪い人の悪口とかをよく言ってるんですよでも実は この出てくる登場人物がほとんどの場合 これなんだよね例えば 小林っていうやつもあと よし子もそうだしあと意外と優の家族のところもそういうのがあるつまり人の悪口を言うと例えば 主人公がいてゆあなちゃん自身とか そのお母さんとかの悪口をまず小林に言うところもあるわけよしかも その小林の悪口をゆあなのお母さんにするシーンもある当人がいないところで第三者に人の悪口を言ってしかも その当人に対して さらに違うところで悪口を言うずっと悪口の話をやってるんだけどだから これを小説のテーマって 多分善意と悪意のバランスなんだと僕は思ってるんですけどこれを小説の前半は悪意が かなり満ち満ちているんですよだけど 後半になると優の家に行くわけで優っていうのは もう目が見えてないんだけど結構 主人公に対して優しいんですね優の息子がいて小学生の子がお母さんのことを労るシーンとかもあるわけで後半は善意が多いんですよねだから そのギャップが僕はあると思うんですよ最後のオチみたいながあるんですよとんでもないオチが1個あるんだけどそれって多分 主人公が善意と悪意のバランスが崩れてしまったんだと思うんだよね多分 主人公は自分が性格悪いと思ってると思うんですよ自分が性格悪いってことをずーっと突っ切れる人っていうのは僕いいと思うんですよ「俺って性格悪いし」みたいなことを
言える人はいいと思うんですよでも優しいことをされることに多分慣れてないだから善意を受けると気持ち悪くなるんだと思うんですよね善意を受けると自分の悪意を見なきゃいけないでしょう他人から優しくされた時に「ありがとう」って言えるのはいいんだけどじゃあ自分も誰かに善意を振りまかないといけないっていう交換みたいな「善意と善意の交換」みたいなが発生すると思うんですよそこに悩んでると思うんですよね自分は人に優しくできるのかできないまま 悪のまま 貫くことはできるのかっていうところで 主人公が最後そのバランスに耐えられなくなってしんどくなっちゃう っていうことだと思うんだよねこれ 意外と我々もそうで僕もそうだし この動画を見てる人もそうだろうけど完全な悪な人って多分いなくて完全な善な人もいないでしょう私は性格良くてみんなに優しくしてるんですっていう聖人君子みたいな人がいたとしても絶対 誰かに対しては悪意を持ってたりとか嫌なことを言ったりとかしたりとかする人いると思うし完全に悪い人がいたとしても特定のこの人だけは優しくしちゃうとかあると思うんですよそこのバランスをうまくやっていくのがこの世間との付き合いだと僕は思うんですよねだから「この主人公は性格悪いよ」みたいな言う人いるかもしれないけどこれ 意外と自分に返ってくる話でこの「アイスネルワイゼン」の登場人物は
みんな裏と表があって かなり 妙にリアルがある「両面を描く」っていうところがやっぱりうまいしそれがテーマなんだろうな っていうのは思いますねそんな感じで 点数を言っていこうと思いますけどこれは96点ですね僕の中ではかなり刺さった とてもすごい小説だと思う1個前の「アキちゃん」っていう小説があってその「アキちゃん」も良かったし「アイスネルワイゼン」もとてもいいですね三木三奈さん すごい作家だと思いましたそんな感じで 今回でなんと芥川賞候補作5作品 全て読むことができました次回 最後ですよね この企画 最後「芥川賞と直木賞のそれぞれの受賞作予想」の動画を1本出そうと思っております第170回の両賞の候補作全て 本当に面白かったんでどれが取ってもおかしくはないと思いますがその中で 僕が 個人的に受賞の予想を
しようかと思っておりますのでどうぞ よろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#926「【書評】芥川賞候補④安堂ホセ「迷彩色の男」」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは「文藝 秋号」なんですけどこの中に安堂ホセ
「迷彩色の男」これは今回の芥川賞の候補作となっておりますね「迷彩色の男」めっちゃ良かったね1つ 社会派っていうのもあるんだろうけどミステリっていう構造になってるとも思いましたね早速やっていきましょうあらすじまず舞台が2018年の12月23日なんですよね主人公が名前がないんですよね会社に勤務してるんだけどそこでのあだ名は「ノンプレイヤーキャラクター」って言って「NPC」と呼ばれてるんですよねその主人公は「ファイト・クラブ」っていう名前の謎の施設に通ってるんですねそこは言ってしまうと 男と男のハッテンバなんですよねゲイ同士が性的なことをするための施設なんですよそこに通ってる主人公だけど主人公はミックスなんですねいわゆるブラックミックスなんで黒人と日本人のハーフと 肌も黒いと身長が190cmある って書いてるんですよ26歳ねその男と仲いい「いぶき」っていう男がいるんですねいぶきもブラックミックスで 同じ26歳なんですよ結構 体の関係をよくやってるんだけどこのいぶきは動画配信サイトみたいのをやってて有料チャンネルみたいのやっててそれは男と男が絡むっていうアダルトの有料チャンネルを自分でやってそれでお金を得ているっていう男でこのいぶきって実は安堂ホセさんの1個前の『ジャクソンひとり』に出てくる「イブキ」っぽいんですね『ジャクソンひとり』にもイブキっていう男が出てきてこの人も配信サイトをやってるからおそらく同一人物かある種のパラレルワールドみたいな感じかなと思いますねここで1つ 事件が起こって主人公といぶきがいつもの通りイチャイチャしてるわけよファイト・クラブは色んな人と性的接触できるからいぶきも違う人とか自分も違う人って多分やってるんだと思うんだけど急に ある日 この12月23日にいぶきが血まみれの状態で発見されるとこれ 死んでないっぽいんですよねのちに病院に送られた送られてないみたいなことを主人公が言ってるから 多分 死んではないんだけど血まみれで血と排泄物の匂いが めちゃくちゃすごくてあとティッシュねそういう施設なんで ティッシュが
ゴミ箱にいっぱい入ってるんだけどゴミ箱のティッシュがめちゃくちゃ いぶきの周りに付けられてると結構 恥ずかしめる感じの発見をされたとこれ 主人公は見てるんですよね主人公は「いぶきどこかな」って探したら ある部屋があってそこでいぶきがその状態で発見されてそのハッテンバでは 20人ぐらいの人物がいるんだけどみんな 結構 そそくさと帰っていくんですね誰かが警察を呼ぶとかじゃなくて俺 知らんぺ みたいなでどんどん帰っていくとこれ 主人公も そうするんですよねこれ 1つ理由があって主人公には職場があるわけその職場でゲイであるってことは言ってないんですよねだから これ 事件に巻き込まれた時に警察から 例えば 連絡とかが来てそのファイト・クラブっていう施設で傷害事件が起こった ってことで参考人とか第一発見者とかで呼ばれた時に職場に連絡が来るんじゃないか とか職場まで警察が来るんじゃないかって思った時にそうなると なぜ自分は
ファイト・クラブっていうところに
いたのかということを会社に言わなきゃいけなくなって自分がゲイだって発覚するいわゆるアウティングされてしまうんじゃないか
っていう恐怖が主人公にあるから主人公は その事件があっても帰らざるを得なかったとそうなんだけど そのあと もちろん発覚して警察とかがファイト・クラブの周りに結構いるようになった主人公は「誰がいぶきをこんなことしたのか」とだから これ ミステリみたいになってくるんだねそれで 結構 半分ぐらい行った時に「第3の男」が出てくるんですね「単一な男」っていう そういうやつが出てくるんですよその「単一な男」にも名前がないんだけどそいつは日本人っぽいんですね肌がイエローって書いててブラックミックスじゃないんですねその男もファイト・クラブに入っていて主人公と なんやかんやで 恋人みたいになるんだよねその単一な男っていうのは最初主人公はそいつは普通の人かなと思ってたんだけど裏で悪いことしてるっていうことがわかってきてこの「迷彩色の男」っていうタイトルは多分こいつのことを言ってる
っていう考え方もできるんだけど単一ではなくて 迷彩していると 隠しているその迷彩がどんどん剥がれていって主人公が「こいつがいぶきを
やったんじゃないか」と思うわけよ本当に最後の レストランのシーンというのがあって2人で「ちょっとトイレでやろうぜ」っていうことになって2人でトイレに行って とんでもないことが起こるっていうこのオチね めっちゃくちゃすごいと思ったねこれは僕の感想になりますけど最後の最後で出てくるからこれ ちょっと言っておきたいのは「ヘイトクライム」をテーマにしているってことですよ「ヘイトクライム」っていうのは何か
っていうと「憎悪犯罪」っていうのでつまり相手が「黒人だから」相手に犯罪を犯すとか相手が「同性愛だから」相手を殺すとかそういう犯罪を「ヘイトクライム」というわけよこれ 言っちゃうとこの最初のいぶきが血まみれになった事件っていうのは「ヘイトクライムだ」って主人公は考えてるわけですねということは「いぶきが刺されたのはなぜか」っていうホワイダニットは「ブラックミックスだから」っていうだけなんですよねこれ 例えば ミステリっていう枠組みで考えた時ですよ金田一とかコナンくんとかがあった時にそういうオチって基本的にはないし 多分許されないんだけどだけど現実では全然あり得るわけですよね「ヘイトクライムで相手が死ぬ」
みたいなことは全然ありえるわけですよねミステリをぶっ壊してるミステリというかもっと現実に即して「こんな殺人も本当はあるんだよ」っていうことを言いたいじゃないかって僕は思うわけこれ 後半の引用になるけど「ヘイトクライムの犯罪者と被害者に
ほとんどの場合 接点がない」
っていうことなんですね主人公は最初 いぶきが刺されたことはいぶきに対する愛情だったりもしくは憎悪だったり が誰かがあってそれでいぶきが刺されたんじゃないかと思ったんだけどそうじゃないとヘイトクライムっていうのは本当に単純な犯罪で「相手が黒人だから」って言うだけでその2人には そもそも接点がなくてもそういうことはありえるんだってことなんですよねそれを最後の最後 うまく利用してるんですよね主人公はブラックミックスで しかもゲイであるっていうダブルでマイノリティがあるわけなんだけどっていうか この2つは
ヘイトクライムの対象に
なり得るわけですねだから「自分は常に被害者なんだ」と自分が例えば加害をするとするじゃないですか主人公が誰かをナイフで刺したりとかするじゃないですかそうすると まず自分は加害者であるってことは認識されないなぜならヘイトクライムという文脈がある限り自分は被害者になり得るんだから自分が被害者であるっていうことで迷彩できるとこれ 最後のオチを言わないと なかなか伝えづらいというかわかりづらい説明かもしれないんだけどいぶきが刺されたこととあと最後にすごい事件が起こるんですけどこれってかなり似ているっていうかこの小説の中でも言われるのは「ひとりずつ役がずれて知らない男が〈犯人〉に彼が〈被害者〉にそして空席だった〈恋人〉の役に私がそれぞれ迷彩していた」って書かれるわけよ最後の最後の言わないけどとんでもない事件が起こるんだけどそこに「第4の男」がやってくると第4の男が今までの3人の配置に入ってきて1個ずつずれて結局 この三角形ができてこれを三角形が強調されるってことだから結局 やりたいことは この三角形を示したいと というのが1つ テーマだろうしめちゃくちゃ話がシンプルで 読みやすいしメッセージ ドカンってくる感じは僕はしたんだよねこれ 点数をつけてみると「迷彩色の男」の点数は90点ですね とても面白かったですブラックミックスをテーマにしてるっていうかまだ2作品目ですけど連続で書いている作家は安堂ホセしか今のところいないとは思うから日本では僕『ジャクソンひとり』よりかは
めちゃくちゃ分かりやすかったと思うんですよ『ジャクソンひとり』って結構
複雑なことをやってるような気がするのよそれを1回シンプルにしたっていうのがあるんじゃないかなただ今回 芥川賞の候補 社会派がかなり多くて「迷彩色の男」でしょ 「Blue」もそうでしょ「東京都同情塔」も そう言ってもいいと思うんですけどその中でどうやって戦っていけるか
っていうの感じはあるとは思うんですけどそんな感じで芥川賞候補は残り1つです三木三奈「アイスネルワイゼン」を残していますのでそれをまた読んだら動画にしようかと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#925「【書評】芥川賞候補③川野芽生「Blue」」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは「すばる8月号」となってるんですけどこの中に川野芽生
「Blue」これは今回の芥川賞の候補作となっておりますね「Blue」とても良かったですねトランスジェンダーをテーマにしてるんだけど僕 もう1個ね深い読み方ができるんじゃないかって思ったんですよね早速やっていきましょうあらすじこれは ある高校の演劇部が舞台になってるんですねそこの演劇部では「人魚姫」をテーマにした演劇がしたいと人魚姫が主人公なんだけど普通 人魚姫は 王子様に恋をするんだけどこれは もう1人 お姫様を設定して人魚姫が 地上の人間のお姫様に恋をしてしまうクィア的な演劇であるというのが1つ変わってるわけですそれを演じる演劇部の人たちが結構いて基本的には主人公は「真砂」っていう人なんですね真砂は今は女性として生きてるんだけど実は元々は男の人なんですね朝倉正雄っていう人なんだけど肉体に成長を止める注射とかをやって名前も変わって「正雄」から「真砂」に変えてるんですよねあとの登場人物滝上ひかりっていう人がいて劇の脚本を担当してると元々は小説を書いてて自分はト書きではあまり書いてなくて小説のまま 提出してると「小説しか書けないんで僕は」とか言う滝上ねあと宇内っていう この子も女の子ででも身長が178cmあるんですよねっていう人とか あと水無瀬っていう人もいてあと栗林っていう女の子もいますその5人が色々 人魚姫について考えていくんだけど途中で 半分ぐらいの時に急に 3年後に変わるんですよね3年経つと みんな大学に入るんですけどこの時に 真砂が 1つ変化していてもう1回 男に戻ってるんですよねこれは「マサオ」に戻ってるんだけど漢字があって 真の難しい「眞」っていうのとあと青の旧字体で「眞靑」って
読ませる名前に変わってるんですよね眞靑は自分が女として生きていくと思ってたんだけどまず性別適合手術っていうのを受けたいとこれは女性が男性になったりとか
男性が女性になったりとかするために肉体の性的な部分を取り除いたりとかつけたりとかするっていう手術があるんだけどこれは成人済みじゃないとできないと つまり20歳この手術を受ける前に実は2年前ぐらいからホルモン注射っていうのを打っとかないといけないというか打つべきっていうのが推奨されてるんですね18歳にホルモン注射 20歳に性別適合手術をしたいとしかし 金もかかるとだいたい200万円ぐらいかかると言われるんですねだから その時 大学生なんでめちゃくちゃアルバイトをしまくって200万 貯めないと無理なわけ結構 真砂が焦っている中なんとコロナ禍に入ってしまってなかなかアルバイトも決まらないし大学も全部 Zoomになっちゃうし みたいながあってしんどくなっちゃうわけよこれ 真砂が大学に入った時に葉月っていう女の子が好きになっちゃうんだよね葉月っていうのは女の子でしょ真砂は今 女性になってるわけよ女性が女性を好きになることは基本的に相手が無理って言ったら終わっちゃうわけよ相手の葉月は普通にヘテロセクシャルなんで男性じゃないと恋愛対象にならないわけよだから そこで結構 悩むんだよね今 結構 お金の問題とかでホルモンとか手術とかできないんだったら いっそのことを男に戻っちゃえば葉月のことが好きになれるんじゃないかとだけど そうなってしまうと今まで高校生の時に演劇部で会っていた人たちは「自分は女として生きていく」っていうのは言ってるしそういうこともやってたんだけど3年経ったら 男に戻ってた っていうのでなかなか言いにくいからこれ 3年経った時に もう1回「姫と人魚姫」っていう高校の時にやった演劇を再演したい というのがあった時になかなか行きにくかったんだけど勇気を出して行く っていう話が第2部になるのよねこれは僕の感想になりますけどこの小説の読み方って 1つは
トランスジェンダーの読み方が
あると思うんですね真砂の心っていうのとあと人魚姫の心っていうのがリンクしてくると自分は人魚姫なんだけど人間になりたいとか男なのか女なのかみたいな中途半端って言ったら超怒られるけどどっちにも行けない感覚みたいながリンクしてくるっていう読み方はあると思うんですけどもう1個 めちゃくちゃ 僕ね
これ 大事なんじゃないか
って読み方があってそれは この小説って2部構成のように思われるんだけど実は これ3部構成なんですよねというのは この「すばる」で言えば
160ページから始まるんだけど最初 人魚姫の話 ちょこっと入るんですよその後に水無瀬・滝上・栗林・宇内・真砂っていう
ト書きが入ってくるんですよここは小説じゃなくて演劇的なト書きで セリフですよね最初の言葉が めちゃくちゃ大事で水無瀬 どこまでト書き?滝上 言っただろ 小説しか書いたことがないって栗林 誰だよ小説家先生を脚本に起用した奴は宇内 いいじゃん文学的で 俺こういうの好きこれの繰り返しで163ページになると「真砂」っていう章のタイトルが来るんですね途中で 3年後に入る時に「眞靑」っていう章のタイトルが入るんですねこの163ページの「真砂」っていう章のタイトルの前に(暗転)って書いてるんですね「暗転」っていうのは明らか演劇の中ってことでしょうその前がト書きでバーって書かれてるってことはここの部分は全部 演劇だっていうことにならないですかねなぜ ここが演劇なのかってことですね滝上っていうやつが脚本を書いてるわけですね人魚姫の脚本は 滝上が書いてるわけよこの滝上は「ト書きは俺 書けない」って言ってるんですね「俺は小説しか書けないだろ」みたいなことを言ってるわけということはこれ 小説とト書きっていうのは僕 逆転してるような気がするんだよね1部2部3部があった時に
1部の最初の冒頭3ページぐらいは人魚姫の話が小説で書かれていて演劇部の会話がト書きに書かれてるわけよなんだけど 2部3部の真砂・眞靑の部分は演劇部の方が小説で人魚姫の方がト書きで書かれてるでしょうこれ 逆転してるんですよねそう考えた時に何が起こるかっていうと真砂・眞靑の部分ね2部3部の主なメインの話っていうのが実はこのこと自体が演劇なんじゃないかって僕は思うわけよつまり 人魚姫って明らかフィクションでしょアンデルセンが作った人魚姫をモチーフにしてこのファンタジー世界を作った人魚姫っていうのがあって子どもたちだってこれが現実のものだって考えないじゃないですか人魚姫が魔女に言って人間の足を得て地上に上がっていく なんかファンタジー世界でしょそれはわかるじゃないですかでも もしかしたら この滝上とか水無瀬とか真砂とかいう方もファンタジー世界として捉えることができると僕は思うんですよしかも これ最後の最後に 滝上っていうやつが今も小説を書いていて 3年後に小説投稿サイトみたいなところで小説を書いてて最後 主人公の真砂がその小説を読むっていう終わり方になってるのよだから この小説って結構 メタ的に小説の中に小説を入り込むような形になってると僕 思うわけこうなってくると後半部分の眞靑の部分って かなりしんどい話でトランスジェンダーの人たちが現実的に陥っているしんどさが出てくるんですねトランスジェンダーの人たちは普通の人たちより鬱とか精神疾患になりやすいとかあと貧困になりやすいとか2年間の中で200万円を貯めないといけないから大学の授業もできないわけよ バイトしなきゃいけないからそれで大学が落ちたりとかあと そこで めちゃくちゃ しんどくなっちゃって手術を諦めたりするみたいなことがこの中に書かれるわけトランスジェンダーの厳しさみたいなが書かれるわけこれは 実際の この現実っていうものを演劇化する もしくは小説化することでフィクション化することでトランスジェンダーの人たちが陥ってるしんどさを無効化させようとしてるんじゃないかと僕は思うわけ意外と この小説は「トランスジェンダーの現状はこれだけしんどいですよ」みたいな「説明的な小説」だと みんな読んでるのがある僕もいくつか調べたら(ネットで)「これはただの説明的な小説ですわ」みたいな感想を持ってる人がいるんだけどそれを1個 逆転させようとしてる工夫っていうか 企みがあるんじゃないのかな僕が言ったことが 1つ妄想としても最初の3ページに書かれた その部分の説明が必要だから
(Q.なぜト書きで書かれているのか? 暗転とは何か?)僕は そう読んだに過ぎないんだけど皆さんはどう読みますかっていうことですよそんな感じで この小説の点数をつけようとすると94点かなさっき言った文学的企みがあるっていうのがあるけれどそうは言っても社会派的な側面の方が多分強調されているのでそういった点では1個前の「ハンチバック」とかに近いっていうか連続で多分 そういう小説
芥川賞に来るかなっていう気も
せんでもないからだけど やっぱり僕は面白かった とても面白かったですねそんな感じであと芥川賞候補は 2作品 ありますからまた動画を撮っていこうかなと思っておりますねそんな感じで 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#924「【書評】芥川賞候補②小砂川チト「猿の戴冠式」」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは「群像12月号」なんですけどこの中に小砂川チト
「猿の戴冠式」これは今回の芥川賞の候補作となっております「猿の戴冠式」めっちゃくちゃ面白かったですねかなり心理学的な話なのかな というのは1つ思いましたね早速やっていきましょうあらすじこの小説には 2人の主人公がいて「しふみ」と「シネノ」っていう2人がいるんですよシネノはボノボなんですよねつまり お猿さん なんですけどシネノは ある動物園で飼育されているんですよシネノは昔人間たちによって実験させられた過去を持ってるんですねというのは 単語カードみたいのを持って例えば カードに何かの絵が描いてるとそれをシネノが出すと人間も絵にまつわる何かを返すわけですよそうすると その絵と意味っていうのが一致していくからこれが言葉ですよ 人間の言葉として猿にも学習させていって最終的には 猿と人間が会話できるようにするっていうそういう実験を過去に受けてたんですよねなんだけど これ しふみの方もそうなんだけど「バッドボーイ(わるい子)」っていうのが キーワードで途中で バッドボーイ バッドボーイって
めちゃくちゃ出てくるんですよ多分 その実験が厳しかって間違えたカードとかを出すと バッドボーイって言われててそれ ちょっと トラウマみたいになってるわけよシネノは もう1個自分の子供を 昔 産んだことがあるんですよ双子の子供を産んだことがあるんだけど1人が すぐ亡くなってるんですよね 生まれてからもう1人はいるんだけどシネノは育児放棄をしているっていう
お母さんでもあるわけですね シネノはもう1個は しふみっていう人がいてこれは人間の女の人なんだけどこのしふみは 競歩の選手なんですね競歩の選手なんだけど過去に事件を起こしてしまったと普通に競歩のレース中にドリンクっていうのがあると色んな人のドリンクがあるんだけどしふみは そこにあるドリンクは全部バーってやって他の人たちにドリンクを飲ませない
ようにするっていう技を使ったともちろん反則なんでそこから めちゃめちゃ掲示板で叩かれて今 ちょっとバタンキューになってるとこのしふみとシネノが2人出会う
っていうところの話なんですねシネノは動物園にいるので動けないんですけどその時にしふみがお客さんとしてやってきて「あなた ここにいたの?」とか言ってしふみはシネノに言うわけよシネノもしふみっていう存在が特別なように思われるとお互いにお互いの存在を特別だと思っていて生き別れた兄弟のような感じで心が通じ合ってるんですよねその2人が特別な関係である
っていうのが分かったのが
1章なんですよこれ もう1章あってもう1章が途中で台風がやってきて動物園からシネノが脱走するっていうそういう話になってくるんですよ街の中に猿が脱走するって危ないことなんで猟師とかが出てきて銃で狙ったりしてくるんですよねそれをしふみがニュースで見てるのかもう1個 なんかシネノの頭の中にジャックして見てる感じもあるのよだから これ三人称なんだけどお互いにお互いの一人称に侵入して外界を知覚してる描写もあるんですよねここはかなり新鮮だと思うんですけどそれで脱走したシネノはどうなるのか
みたいな話になってくるっていう話かなこれは僕の感想になりますけどこの小説は2つ読み方があると思うんですけど1つは「魂の双子」的な読み方これは猿と人間なんだけど例えば 男と女とかでやると「君の名は。」とかの話になってきて運命が導く2人の出会いみたいなやつあるでしょ よく今回はシネノとしふみなんだけどこれ 名前が面白くて「シネノ」っていうのは
=「どういたしまして」
っていう意味らしいですねシネノには元々お姉さんがいたんだけどお姉さんは動物園に運ばれる移送の時にショックで亡くなってしまってんですよこのお姉さんは「ありがとう」
っていう意味なんですね 名前が「ありがとう」「どういたしまして」でセットなんだけどそのセットがもう既にバラバラになっているもう1個 「しふみ」っていう名前も「じゃんけん」っていう意味らしいんですねしふみは 結構ちょっと妄想的なんだけどじゃんけんには「ポン」が必要だろうって思ってるわけよでも 私には「ポン」がいないとだから1人なんだっていう双子の片割れみたいのが たまたま2人出会ってしまって補完し合う関係になる っていうのが1つあるのよねこれ 二項対立みたいのをずっとやってる気がしてバッドボーイっていうのが大事だと思うんだよねバッドボーイ バッドボーイって言って2人とも言われてきたと「悪い子ね」って言われてきたんだけどもちろん「バットボーイ」があれば
「良い子」があるわけですね多分 この2人っていうのは
「グッドボーイ」になれなかった
2人だと思うんですよだから これで最後 戴冠式っていうのが急に出てきてかなり解釈が難しいんだけどおそらく この「猿の戴冠式」の戴冠式っていうのは「グッドボーイになるために」
っていうことなんじゃないかなしふみもシネノもどっちも自分に対して
結構 抑うつな気持ちがあるわけよ抑うつっていうか「私ってダメね」みたいな気持ちがあるしそれと もう1個「自分は特別な人間(猿)なのか」とかいう気持ちも2人とも持ってるんだよねこれ 間に挟まれてるでしょ「自分は特別な人間なんだ」っていうのとでも「バットボーイ」っていうのが下にあってここをずっと行き来してるわけですね これちょうどいい存在がないともう1個の読み方っていうか 流れとして言えるのはかなり「対象関係論」的に読めるんじゃないかと思うわけ対象関係論で何だっていう話なんだけどこれ 元々 作者が小砂川チトさんっていう人なわけよこの小砂川チトさんは元々1個前に『家庭用安心坑夫』っていう作品で群像新人文学賞を受賞して作家デビューしてるわけこれも かなり心理学的な話だったと僕は思うんですねサイレントヒルみたいな世界って
僕 めっちゃ言ってたと思うけどこれ 小砂川チトさんってプロフィールを見ると慶應大学出身で慶應大学の大学院を出てるんですけど心理学科なんですよねこれ多分 かなり心理学的な要素を詰めたっていうかそういう作風で行ってるんじゃないのかな今回の「猿の戴冠式」は「対象関係論」っていう精神分析の一派をもとに作られてるんじゃないかなこれ「対象関係論」って何かって言うと「赤ちゃんの心」を分析するんですよね有名なのは「妄想-分裂ポジション」と
「抑うつポジション」というのがあるんだけどこの辺は もう全部 調べたら出てくるんですけどそれをやってる気がする赤ちゃんというのは 二分化されてるんですよね真ん中がないというのが「妄想-分裂ポジション」
って言われるところの1つ理論的な基本なんだけど赤ちゃんっていうのは自分が中心であるがゆえに世界っていうのは「良いもの」か
「悪いもの」しか存在しないとまず「バットボーイ」とかいうのも基本的に二項対立で語られるので「自分がバットボーイなのだ」
っていうのがもちろんあるんだったら「世界がバットボーイなのだ」
っていうのもあるんですよねさっき言ったように 世界っていうのは基本的に1つしかないんだけど我々って この世界って
「良い世界」と「悪い世界」
というのを認知してしまうと中間があれば 1番いいですよ意外と「良いことだけ」っていうのは存在しなくて良いことがあるんだったら絶対に悪いことがあるからねだから良いだけではしんどいのよ 本当はねなんだけど この世界では主人公たちは結構良い世界・悪い世界で生きてるしそれを統合してるのが「母」とか「私たち」「ひとまとまりの未分化的なパンの塊」なんだみたいなことを言う時があるんですよ我々って「個」っていうものを持ってしまってるとでも猿の世界には あまりそもそも個っていう概念がなくて個っていうのは全体から切り分けられた「私」なわけよこれが結構しんどいわけよ私というものが存在するから悩んだりとか俺ってダメなんだとか 世界
はこうなんだとか言ってしまうわけこれが後々「母」っていう言葉に置き換わるんですよねその母から戴冠しなきゃいけないんですよねこれ「猿の戴冠式」ってタイトルだけど
途中で「女王」っていう言葉も出てくるんだよ「バットボーイ」と「女王」を
対比するのもできると思うんですけど「女王」っていうカードがあって「女王」っていうのは もちろん女の王なんで戴冠されてるとこの小説っていうのは「バットボーイ」から「女王」になるための話なんだけど母から個になるんだけどその個=我々=バッドボーイからもう1回自分が「女王」となるそれは この世界から冠をいただいて自分の「個」として生きていくっていうのがこの小説の読み方なんじゃないかなというのは 1つ思うんですけどねだから1回 赤ちゃんになってまた大人になるということだと思うんですよこの小説の点数を言おうかと思いますこれは92点ですね 僕としてはかなり興味深いなぜなら僕も心理学科出身で僕は心理学の大学院まで行っておりましたからこういう小説 大好きなのよ最近 あんまり 精神分析的な小説ってあんまりないと思うんですよねだから 小砂川チトさんこういう作風でどんどん続けていってほしいなと僕は思うよ独自の路線なんじゃないかな とは僕は考えてはいますけどそんな感じでございます芥川賞候補は残り3つ ありますからまた動画にしていこうかと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#923「【書評】芥川賞候補①九段理江「東京都同情塔」」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは「新潮12月号」なんですけどこの中に九段理江
「東京都同情塔」これは今回の芥川賞の候補作となっておりますね「東京都同情塔」めちゃくちゃ面白かったですねとても現代風の作品だしディストピアが入ってるんですよね早速やっていきましょうあらすじ主人公が牧名沙羅さんっていう人で40代なんですねこの人は建築家をやっていると牧名沙羅は あるコンペに参加することになるわけですよそれは「シンパシータワートーキョー」っていうものを新宿御苑のところに建てるので建築家の色んな人に頼んでいい建築を出してくれっていうわけですよシンパシータワートーキョーっていうのは何かっていうと刑務所なんですよねだけど普通の刑務所じゃなくてある思想に基づいて作られた刑務所なんですよその思想っていうのはマサキ・セトっていう人が提唱した『ホモ・ミゼラビリス
同情されるべき人々』
っていう本があってそこに載ってる思想なんだけど犯罪者っていうものは
同情されるべきであるって
いうことなんですよ犯罪を犯してしまう人っていうのは生まれ育った環境が悪かったと我々が単に犯罪を犯していないのは我々の人格が素晴らしかったのではなくて我々が育ってきた環境が良かったからだと環境が悪かった人は犯罪を犯すことが多いとだから彼らは我々より劣った人間ではないと同情されるべき人間であるとそういう思想があって「犯罪者」っていう言い方とか「受刑者」とかいう言い方は差別的だから「ホモ・ミゼラビリス」っていう言い方に変えましょうっていう本があるんですよなんだけど 牧名沙羅さんは昔男の人に乱暴された過去があってそこから自分の言語っていうか論理っていうのを1から構築していって言葉っていうのを 本当に丁寧に
使わないといけないっていう一種の強迫神経症になってる人でもあるのよだから牧名沙羅さん自体は犯罪者を憎んでるっていうのはわかると思うんですよねなんだけど これで途中で拓人っていう人物が出てきてまだ20代前半ぐらいだと思うがこの拓人が めちゃくちゃ顔が美しいとアイドルぐらい顔が美しい拓人がいて服屋さんで働いてるんだけどたまたま 主人公・沙羅が行った時に
「君 美しいね」って言って恋人みたいになるんだよねその拓人曰く このシンパシータワートーキョーっていうのは「東京都同情塔」と言い換えられるでしょうって言うわけよ単に日本語にしただけなんだけどねでも この感じがやっぱり違うでしょっていうことねこの小説の中にはAIが広がってる世界でこれ 現代というよりかは ちょっと未来なんですね202?年とかで最終的に2030年まで行くっていう SFが入ってるわけよその時に AI技術みたいのが発展していてこの世界では 基本的には
っていうか今の世界もそうなんだけど浮浪者っていうことをホームレスって言ったりとか育児放棄のことをネグレクトって言ったりとか菜食主義者のことをビーガンって言ったりとか少数者のことをマイノリティって言ったりとかカタカナに直すことが多いとカタカナに直すことによって 角の取れた柔らかいニュアンスになるわけじゃないですか浮浪者って言う時に「浮浪」っていう言葉の持つインパクトってあるけどホームレスにすると カタカナだから漢字の持つ微妙なニュアンスがなくなるわけよこれ だから逆転して「シンパシータワートーキョー」も
カタカナだから柔らかい言い方なんだけどこれを「東京都同情塔」に変えることで何か変わるんじゃないか
っていうのが1つ
あるわけよこの世界もう1個 この世界っていうのは すごいのはパラレルワールドなんだよねこの世界とは違って 2つ違うところがあって1つはザハ・ハディドの新国立競技場が
できている世界でもあるんですよこれ 東京オリンピックのことを
出してきてるのが
僕 すごいなって思うんだけど東京オリンピックの時って最初 ザハ・ハディドっていう人が新国立競技場を作るっていう建築家として作るっていうのをやってたんだけど3000億円 かかるっていうことでめちゃくちゃ形がきれいな流線型みたいな形なんだけどそれ ボツになっちゃってそのあと 日本人の隈研吾とかの事務所が今の新国立競技場を作るっていうのがこの世界なんですけどこの「東京都同情塔」の世界ではザハ・ハディドの新国立競技場が通った世界なんですよもう1個は
2020年に東京オリンピックを
行った世界であるんですよこっちの我々の世界では 2020年には実は行われてなくてコロナで1年 延長してるので2021年に東京オリンピック できてるんですよなんだけど こっちはコロナの時に
無理やり やるっていうことでオリンピックをやったんだけど 結構 死者が出たとコロナによる死者が出たっていうのがある世界この2つが現実では違うとあと もう1個ねこれなんと途中で 何年か経って2030年になってるわけよ2030年になると 沙羅さんがコンペに勝ち取って実際に東京都同情塔ができた世界があるんですよねそこに拓人が働いてたりするんだけどもう1人 これ 面白いと思うのはマックス・クラインっていう人が出てきてマックス・クラインというのは外国の記者の人なんだけどこの人は自称レイシスト・人種差別主義者だって言って日本人に対して かなり人種差別を持ってる人でこの人が記者なんで 東京都同情塔の方に行ってその記事を書きたいというわけよ実際に来て 色々 記事を書くんだけど結構 レイシストだから かなり記事が丸々 載ってるんだけどその記事が だいぶ言葉がきつい感じがあるわけよそういうのが出てくるとかいう話なんだけどねこれは僕の感想ですけどこの中にも出てくるんだけど東京都同情塔っていうのは1つのディストピアだっていう話なんだけどどうディストピアかっていうと「言葉狩り」があるわけですねつまり さっき言ったように微妙なニュアンスが入っている言葉を
どんどん消していくことによって誰も傷つかない言葉っていうのを
確立させようとしてるわけよ「言葉狩り」っていうのは実際
「1984年」とかでもそうなんだけどディストピアで よくよくある話なんですねジョージ・オーウェルの『1984年』の言葉狩りっていうのはビッグ・ブラザーに反抗しないために反抗するような言葉をどんどん辞書から消していくことで実際 反抗できないようにする っていう考えなんだけどこっちは別に良いことに使われてるわけよ人を傷つけないようにするために言葉を丸くしましょうっていうことが行われてるわけよこれは本当は悪いことなのかとコンプライアンスを
めちゃくちゃすることは
悪いことなのかとあと面白いなと思うのは主な登場人物3人の個性ですよね沙羅さんは めっちゃ金持ちなわけよ拓人くんは めっちゃイケメンなわけよマックス・クラインはめっちゃ口が悪いわけよこの3人って例えば共産主義的な国家ではありえないでしょつまりこれ人を いかに傷つけないようにするかみたいなことをやってるんだけど金を持ってるだけで人は傷つくっていうか人から羨まれることって全然あるじゃないですかイケメンであることも 1つ暴力性があるわけよもちろん口が悪いことも暴力性なんだけどこの3人って 意外と資本主義国家の象徴なんじゃないかって僕は思うんだよなこれをなくしていきましょう みたいな世界が
ある種 コンプラ的な世界だろうしバベルの塔的な世界観なんだよねこれ最初から バベルの塔みたいのを ずっとやってんだけどバベルの塔っていうのはこれまで人類というのは 1つの言語で色々 喋ってたんだけど神の裁きを喰らい みんな言語が
バラバラになってしまったと多分 それをもう1個 統一しようとすることで今のいわゆるコンプラ的な物の力によってAI的な 「AI語」みたいのが出てきてるわけよ一昔前だったら 日本語がぐちゃぐちゃになってるとかよく言うじゃないですか語彙も少なくなって全てがヤバイとかウザいとかになってるとでも今はその段階を1個 超えて「AI語」っていうことが起こってきてると標準語を超えたAI語ね誰も傷つかないようにした丸い言葉っていうのがあってこれが 1つコンプラ的には標準語になってるわけよこれはなんとバベルの塔的なことでしょこのコンプラ語をみんなの中心語に変えましょう
みたいのが今の芸能界だったりとか作家とかも そうなってきてると思うんですよねつまり言葉の共産主義みたいなが1つあるしそれがディストピアなんだっていうことなんだよそれがいいのか悪いのかっていうところの判断をこの本を読んだ人たちはしてくださいっていうのを 多分
やってるんじゃないかな
と僕は思うんだけどねそんな感じで この小説の点数を言おうかと思うんですけど98点かな とても良かったですこれ 最初に読んだ時に「何かすごいことが行われてる」って思ったもん僕も全てがわかってるわけじゃないしもっともっと深読みできると思ってるんですけどなんだけど 最初に読んだ時に「いや これはすげえな」って思ったからその直感みたいなを点数に表してみたっていう感じかな芥川賞候補は あと4作品ありますからそれをまた動画にしていこうかなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#922「【書評】直木賞候補⑥宮内悠介『ラウリ・クースクを探して』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらになっておりますねこちらは宮内悠介
『ラウリ・クースクを探して』
朝日新聞出版 2023これは今回の
直木賞の候補作の1つと
なっておりますねとても良かったですよかなり社会派的ですよね今回の直木賞の候補の中では
1番 社会派だったんじゃないか
と思いますね早速やっていきましょうあらすじを言うとこれ舞台が エストニアが舞台なんですねエストニアっていうのは バルト三国の1つで元々はソ連の連邦のうちの1つだったんですけど1990年代に独立するんですね主人公がラウリ・クースクっていう男の人でその人の人生を書いてるんだけど1977年にラウリ君が生まれて生まれた時にラウリ君はめっちゃ数が大好きだったと数字っていうものを知って ずっと数字のことを考えたり数字で遊んだりするんですよその時 父親がパソコンをもらうんですよそのパソコンも古いやつですよ80年代とかのパソコンなんで「パソコン」っていうよりかは
コンピューターの古いやつなんだけどそれをもらってきて ラウリ君にパソコンをさせるわけよラウリ君はパソコンにどハマりしちゃってプログラミングとかを勉強していくんですよ独学でプログラミングをどんどんしていって自分でちっちゃなゲームみたいのを作ってそのゲームで遊ぶみたいのをやるのよねラウリ君が小学校になった時にクラスメイトにいじめられたりもするんだけどそこにいる先生が「これからはパソコンの時代だ」とか言って学校でパソコンの授業をするのよだけど他の子供たちはポカーンなわけよ当時 パソコンなんか 誰も知らないみたいな時代に子供たちも全然わかんないから「どうしたらええねん」ってなってるんだけどラウリ君だけは家にパソコンがあるからめちゃくちゃすごくできるしむしろ自分で教科書みたいのを自分で作って他の子供たちに渡すぐらいのことができるんですよね1回 ラウリ君が作ったゲームをゲームコンテストみたいのがあって そこに送ったらかなりいいところまで行くんですねなんだけど 3位で1位は いつもイヴァンっていう男の子が作ったゲームが1位になってるのよ「イヴァンって誰やねん」って思って「イヴァンに負けずに俺も頑張るぞ」
ってラウル君は頑張るわけ主人公 まだ小学生なんだけど次 中学校になる時にそこはちっちゃな村なんだけど
都会に出るかっていうことで都会の中学校に 寮に行ってそこでパソコンを学ぼうとするわけその時にイヴァン君も入ってくるんですよねそこでイヴァン君とラウリが会って中学校でお互いに切磋琢磨してプログラムするわけなんだけどそこで友情ものになっていくんだねもう1人 女の子がいて主人公・女の子・イヴァン君の
この3人の友情ものになってくるわけよだけど 時代がちょっと悪くて1990年ぐらいになってくるとバルト三国がロシアから独立したいということで
独立運動を起こしていくわけよ結構 デモとかするんだけどそこにロシアは独立してほしくないから軍隊をバルト三国に置いたりとかするんですよね主人公が これ中学校なんだけど独立派に入りたいか
ロシア派に入りたいかみたいな
派閥ができちゃって女の子が独立派に入るんだけど主人公は のちのち ロシアのモスクワとかに行ってもっとプログラムを勉強したいと国のために頑張りたい みたいな気持ちがあるからもしエストニアが独立してしまうと自分はモスクワに行けないわけよモスクワはロシアだからねロシアとの関係が悪くなると行けなくなっちゃうからちょっと主人公は どちらかというとロシア側なんですよねなんだけど歴史としてはエストニアが独立するとその時にイヴァン君ね イヴァン君は実はロシアの子なんですよねロシアのレニングラード出身でだから どちらかというと
ロシアとエストニアが悪くなっちゃうと家に帰れなくなる可能性があるから独立云々になってる時にイヴァン君は1回 祖国に帰るんですよね女の子は独立のデモに参加してたんだけどちょっと そのデモで怪我しちゃうんですよ結構 重い怪我をしちゃって主人公 1人になっちゃうんだよね主人公は何もかもが やる気出なくなっちゃってパソコンもやめちゃうんですよねそれでラウリ君はその後どうなるか っていう話があるのともう1個 この話って 2つのストーリーで進んでいって1個は そのラウリ君の人生を書くんだけどもう1個はラウリ君を探している
現在軸の話っていうのがあるのよある人が今 ラウリ君が何をしているかっていうのをラウリ君の関係者とかに聞いていってラウリ君を探していくっていう話があるんですよねこれ現在なんで ラウリ君はもうかなりの年っていうかおじさんみたいになってるわけなんだけどでも所在がわからないもしかしたら死んでるかもしれないけど生きてるかもしれないと わかんないってことでその探している主人公は誰かわかんないんだけどその人が探していくって話なんだよねこれは僕の感想になりますけどこの小説って「友情もの」なんですよね今回の直木賞ね『襷がけの二人』っていうのは昭和の日本の女同士の友情を書いててあと『まいまいつぶろ』は徳川家重と大岡忠光っていう将軍と部下の友情を書いてるわけだから友情が今回 めちゃくちゃ多いわけよだけど この話は歴史の波に翻弄された子供たちの友情ものみたいな感じかなこれは明らか ウクライナとロシアのことを今回は エストニアを舞台にして言ってると言ってもいいと思うんですね国家間の対立みたいなが1つあって庶民がそれを被害 被ってるみたいな話なんだけどエストニアが なぜ舞台なのかっていうとエストニアって実は IT先進国なんですよねデジタルのものが めちゃくちゃ すごいらしいんですよラウリ君もデジタルのものを
ずっとやっているわけなんだけど時代として とても早かったらしいんですよね過去と現在を行き来するストーリーだから現在軸はもちろんあってそこで出てくるライライ教授っていうパソコンに詳しい学校の先生がいるんだけどそのライライ教授が言うにはある国があったとしてでも その国って 他の国から攻撃されて なくなっちゃうことだってあるわけですよ特にヨーロッパはそういうことはかなり多かったわけだから今が平和でも未来ではなくなってるかもしれないとそれをずっと残すためにはどうしたらいいかっていうと全てをデータ化するっていうことなんだよねこの作品の中にも出てくるんだけど(エストニアでは)
お墓とかを全てネットを使って
調べることができるらしいんだよねマイナンバーカードとかも
かなり早い時から導入されてたりとかライライ教授 曰くもし国がなくなったとしてもデータさえ残っていれば 1回 国が滅ぼされてもそのデータを元に再現することができるって言うわけよだからデータというのは とても大事なんだって言うわけそのためにエストニアっていうのは結構早い段階からIT先進国としてやってきたとかいう話ね国家の危機とIT産業というのは実は繋がってくる問題なんだ みたいなことを多分この小説では言ってるんだと思うんだよねそういった意味でも かなり社会派なんだよねこれ最後とかも めちゃくちゃ面白いですよつまりラウリ君の現在みたいな…これ全部につけてるけど 点数ね『ラウリ・クースクを探して』の点数は87点かな とても良かったです舞台が日本ではないっていうので最近の直木賞は日本人が主人公で 日本が舞台じゃないとなかなか取らないというのがあるんだけどでも これウクライナの問題があるんでかなり現在のウクライナ・ロシアの問題に肉薄してくるような内容ではあると思うんですよねだから直木賞としては取る可能性は
あるんじゃないかと思います小説として とても面白いしかなり勉強になりますどちらかというと 海外文学みたいな感じの近さがあるけどこれだったらエストニアっていう国の歴史っていうのがわかってくるし世界では何が起こっているのか みたいな感じの
ドキュメンタル的な要素もあるんじゃないかなその中にラウリ君っていう 主人公を立ててそのラウリ君の周辺を描くことで物語として ストーリーとして描いた
っていうのが とても良かったと思いますねそんな感じで今回で なんと直木賞候補 6作品を全て読むことができました今回の直木賞候補 本当に全部 面白いんでどれが取っても不思議ではないっていう感じはしますね次からは芥川賞候補の方に入ろうかと思います僕は純文学大好き人間なんで芥川賞候補は解釈のしがいがあるんでとてもとても難しいんだけどめっちゃ気合いを入れて 頑張ろうと思います芥川賞候補は5作品あるんで動画も5本出したいな と思っておりますのでどうぞ よろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#921「【書評】直木賞候補⑤嶋津輝『襷がけの二人』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは嶋津輝
『襷がけの二人』
文藝春秋 2023これは今回の
直木賞の候補作と
なっておりますこの小説 良かったですよ僕の好きそうなタイプの小説だなあと思いました早速やっていきましょうあらすじを先に言いますとこれ 時代背景が現代ではなくて大正から昭和になるんですよねこれまず 第1章が 昭和24年なんですねこれネタバレじゃなくて 冒頭からわかるんだけど「再会」っていうサブタイトルあって主人公が千代さんっていう女の人がいてこの千代さんが初衣さんの家でお手伝いとして働くっていうところから始まるわけよ初衣さんは盲目になってるんですけど三味線の師匠をやってて弟子とかがいてそれで生活をしてるっていう人なんですね千代さんは喉がガラガラでしてこれは昭和24年なんで1回 戦争 入ってるんですよね東京大空襲があったからその煙を吸っちゃって喉ガラガラになってるのよこれほんとネタバレじゃないけど 最初にわかるが千代さんと初衣は実は知り合いなんだよねなんだけど初衣さんが盲目になっちゃっててしかも千代さんが喉ガラガラなんで初衣さんからすると 千代さんが昔の知り合いということをわかんないわけよ千代さんはわかってるんだけど それは言わないわけよその2人がまず再会するってところから始まって次の2章目に大正15年に戻るんですね千代さんが もちろんまだ若いんですけど千代さんが
知り合いの家に嫁入りに行く
ってところから始まるわけ千代さんがいて
千代さんのお父さんがいるわけお父さんの友達がいてその息子さんと千代さんが結婚するってことになるわけ嫁いでいく その家っていうのは
製缶工場っていうのをやってて結構でかい家なんですよねそこの家は結構でかいので女中さんがいっぱいいるわけですねそこの女中頭が 実は初衣さんなんですよねこれ どういうことかというと千代さんはお嫁さんとして行ってるから権力があるわけ その家ではその女中頭の初衣さんの方が もちろん身分っていうか雇われてる側だから 位は下なわけよなんだけど 現在になると初衣さんが千代さんを雇ってるっていう逆転現象が起こってるわけよなんだけど2人は結構 どんどん仲良くなっていくんですねその製缶工場は忙しいらしくていわゆる旦那さんになる人は途中で違う工場に派遣されてあんまり家に帰ってこない ってことになるんですよそうすると 家にいるのは千代さんと初衣さんと もう1人 女中さん いるんだけどこの3人になっちゃってみんなで料理を作ったりとかして身分っていうか雇う雇われる関係のそこら辺が結構 みんな仲良くなっていくんですねそこから いくつか事件がもちろんあって噂好きのおばさんが家にやってきて「あんたの旦那さん
外で浮気してるわよ」
とか言ってくるやつとかあと主人公のお母さんがいるわけよ主人公は 嫁入りに行ってるからもちろん 家は違うんだけどお母さんが ちょっと厳しい人で母-娘 間はあんまり仲良くなかったりとかあと これ途中でわかるのは 千代さんの体が実はちょっと おかしな部分がある
っていうことが途中で分かってきて結構 これ 女性とかだったらかなりシリアスな部分なんだと思うんですけどそれもあって旦那さんとはあんまり仲良くないんですよね嫁いだ先の旦那のお父さん 舅になるけど舅とはそんなに仲悪くないんだけど結婚した夫が実はそんなに良い人じゃないというかあまり干渉してこないんですよねそういうのが どんどんあるんだけど 途中で第二次世界対戦が始まって 空襲が起こったりして家族がバラバラになっていって千代はどうしていくか
っていう話になっていく
って話なんだけどこれは僕の感想になりますけど結構 地味な話ではあるめちゃくちゃドラマチックっていう
感じではないとは思うんですよデカい事件とかもあんまり起こらないんですよねむしろ日常のどんどん進んでいく
生活の先みたいな感じだからめちゃくちゃキャラが濃い人とかも出てこないんだよね悪そうな人は ちょこっといたりするんだけど意外とそれも極悪ってほど悪くないんだよねこういうちょっかいかけてくるおばさんいるよなみたいな全然 日常にいるような人だったりとかするから話としてはかなり地味だと思う今回の直木賞では1番 地味だと思うんですよだけど この地味さが僕 良かったと思うわ結構 エンタメ小説ってドカンドカーンドカーンと劇的に事件が起こってええっまさか みたいな感じの
ストーリーだったりするじゃないですかジェットコースターみたいな感じってよく言われるけどあまり これはないわけよこっちの方が僕 安心して読める感じがするなテレビ番組で言ったら芸人がたくさん出てくるバラエティよりかはNHKのちょっと静かな番組みたいなイメージなんだけどそっちの方が僕 最近ねそういう物語の方が好きになってきたなこれ 1個 キーワードとしては食事もあるのよね千代さんと初衣さんが一緒に食事を作ったりするんだけど結構 美味しそうなのよ和食とかがやっぱり多くてそこが1個テーマであるような気がするのよつまり この物語自体が和食的な感じで和食って別に味が濃すぎるとかじゃなくて素朴な感じするでしょマクドナルドみたいなそういうファーストフードとかそういうのじゃなくて出汁がついてて美味いみたいな
そういう感じな気がしたんだよね現代が舞台じゃないから昭和の感じの物語ではあるんですよ基本的には「女性の話」っていう感じだと思うよテーマとして「女性性」みたいなのもあるだろうね現代で言ったらシスターフッドものだとは思います女性の友情みたいな感じかなと思うんだけど「いつまでも平和でいてね」みたいなそういう気持ちになる小説ってあるでしょ「尊い」みたいな そういう感じかもしれないけど何回か前の直木賞の候補で『光のとこにいてね』
っていうのがあったでしょ
一穂ミチさんかなあれも女性2人の友情物語みたいな感じであっちの方がめちゃくちゃドラマチックなんだけどその流れではあるよね千代さんが主人公なんだけど初衣さんの話ももちろんあって初衣さんは昔 元芸者なんですよね元芸者っていうのもかなりキーワードで今は女中をやってるんだけど昔は 人には言えないような過去があるわけよ詳しくは言わないけどある芸を巡って 色々あったりするんですよこれも結構 女性性に関わっていくんだよねだけど女性の自立みたいなのも あると思うんですよねこの表紙が まず いいんですよ女性2人が映ってて1人が千代さん 1人が初衣さん なんだろうけどここ 猫が座ってたりとかあと手前に植物が2つ描かれてるんだけどこれも実は作中に出てくるんですね本の表紙って 元々ある絵画とかそういうのを表紙のイラストとして使うっていうのともう1個 内容から多分イラストレーターとかに頼んでその作品専用の表紙にするっていう2つあると思うんですけどこれは後者の方なんでこれ表紙だけでも めっちゃいいのよねここに感動があると思うんですよねこれ毎回言ってますが 点数をつけるとすると82点かな 個人的にはとても良かった最後 僕 泣いたしこの帯の後ろに書いてるのは「大正から戦後を舞台にした2人の女性の不思議な絆幸田文・有吉佐和子の流れを汲む
女の生き方を描いた感動作」幸田文・有吉佐和子っていう名前を出してくるのがいいよねあと表紙の帯には「この2人がタッグを組めば絶対大丈夫」って書いててその下に「『奥様と私』物語を
また1つ更新した新しい時代の名作」柚木麻子って書いてるんだよねこの物語は冒頭で再会しましたよ
っていうのがすぐわかって1回 過去に戻って 2人の出会いとかをやってからどんどん現在に近づけていって最終章で その冒頭の続きをやるっていうサンドイッチ形式みたいな感じなんでネタバレっていうのが
あんまりないと思うんですよね
冒頭でわかっちゃうからだけど その間がいいんだよね紆余曲折あるっていうか人生の摩訶不思議っていうか運命みたいなことが間にあって千代と初衣はどうなっていくのか
というところが書かれてるのが
やっぱり面白いよねそんな感じで今回『襷がけの二人』で直木賞候補 5冊目になりますが残り1つありますからそれもまた読んだら動画にしようかと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じでございます
今回は終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#920「【書評】直木賞候補④村木嵐『まいまいつぶろ』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこれは村木嵐
『まいまいつぶろ』
幻冬舎 2023これは今回の
直木賞の候補作の1つと
なっておりますこれ 良かったですよ
最後 泣いちゃったね早速やっていきましょうあらすじを言うとこれは時代小説でして江戸幕府の第9代将軍
徳川家重の話なんですね徳川家重っていうのは
第9代なんだけどその1個前に
第8代将軍の吉宗が
いるんですよね吉宗・家重・家治が
いるわけですよ家重は実は
生まれつきの障害が
あるんですよね家重は 今で言ったら脳性麻痺
じゃないかと言われている
症状を持っていて生まれつき 体に麻痺があって片足をずっと引きずって歩かなきゃいけないとあと口も うまく回らないので言葉が不明瞭だったっていう話なんですねあと体の器官的な問題で尿を貯めることができなかったため漏らしてしまっていたっていうのがあるんですねこのタイトルの「まいまいつぶろ」っていうのは「カタツムリ」のことなんですよね徳川家重が歩いて行ったらそこにずっとおしっこが残っちゃって水・液体を歩けば歩くほど垂らしていったっていうので「まいまいつぶろ」って言われていたらしいんですねそうなってくると 吉宗の子供が家重なんだけどそういう障害があると次の将軍にできないんじゃないかっていうので家重の弟もいるわけよ弟の方が めちゃくちゃ
素晴らしいというか
頭も切れるみたいな人で弟かお兄さんか どっちを
次の将軍に選ぶかっていうのを
めっちゃ 吉宗 悩むわけよこれ 家重が主人公ではなくて主人公が色々いるんですよ全部で8章からなっているんだけど章ごとに主人公 変わってたりするんだよね最初の第1章はなんと大岡越前から始まるんだよね大岡越前って言って 町奉行の大岡裁きで有名な大岡越前は同時代に存在していて大岡越前の はとこがいるんですよねそれが大岡忠利っていう人なんだけどそれの息子さんが大岡忠光って言うんですよね家重は言葉が不明瞭なので実は誰も徳川家重の言葉を
聞き取ることができないんですよねでも その大岡忠光っていうのが まだ子供なんだけどめっちゃ耳が良くて鳥が喋っている言葉も全部 聞き取れるっていうか聞き分けられるんですよね耳がとにかくいいから徳川家重の言葉が忠光だけに聞き取れるんですよね忠光はまだ子供なんだけど唯一コミュニケーションが
できるから 通訳みたいな感じで忠光自体はそんな位が高いわけじゃないんだけどそういう能力を持ってるから いきなり江戸城に派遣されてそこで小姓として生きていくわけですよなんだけど それをよく思わない人もいるわけねなんでかって言うと
家重の言葉を通訳して言ったことをそのまま言えるのかと本当は嘘ついて忠光が勝手に喋ってるんじゃないかとだって それを証明することは他の人にはできないからねだから 忠光っていうのは
危険な存在なんじゃないかって言って老中みたいな人は反対派の人がいたりするんだよねそこから ちょっと大きくなった時にもう結婚するっていうことになって京都から比宮(なみのみや)っていういわゆる正室を迎えることになるんですよまだ家重は将軍じゃないから自分の障害のあることっていうのが遠いところにいる人は知らないんですよねだから京都にいる比宮さんも言葉が不明瞭とか足を引きずってるっていう事は知らなくていざ嫁いできた時に めっちゃびっくりするんですよねなんだけど 実はこれ めっちゃロマンチックなのは家重は植物を育てるのが好きで薔薇を育ててるんだよねその薔薇を毎日1本ずつ比宮に送ってたっていう話があってそれで比宮はキュンって来て一生 仕えますとか言って 手のひら返して良き友達っていうか良き恋人みたいになっていくんですけどでも実際の歴史もそうだけど徳川家重は第9代将軍になるわけよその後に遠いところで一揆が起こったりとかするっていう話ここで面白いのは田沼意次が出てくるんですよね田沼意次ってめっちゃ天才キャラみたいなになってて子供の時から完全記憶能力者みたいな感じで色んな数字とかをスッて取り出して言えたりするんですよそれで各地で一揆が起こるんだけど田沼意次が解決するとか そういう話があったりとか最後は最後で 年を取ってきて家重の老後みたいな
話を書くんだけど
めっちゃいいのよねこれは僕の感想になりますけど1つは「ハンチバック」的な感じはあるでしょうねつまり「障害」っていうのを1つテーマにしていますから前回の芥川賞は『ハンチバック』が取ってますからもし今回『まいまいつぶろ』が取るとそういうテーマが続くんですよねもちろん こっちは将軍っていうトップの話があってそこに障害っていうのをどう捉えていくかっていう話で今の時代でも もちろん差別っていうのはあるにしても当時は江戸時代ですから意地悪とかされてるわけよ 家重も将軍家の生まれなのに色んな大臣とかから意地悪されたり嫌なことを言われたりするわけよおそらくだけど 徳川家で
1番苦労してる将軍じゃないかな
と思いますよでも そこに忠光っていうこれ1個 テーマとして 家重と忠光っていうのは唯一コミュニケーションができる
人間として書かれるんだけど年とかも近くて 友達みたいな感覚なんだよねやっぱり こういう人がいると家重も良かっただろうなって本当に思うわ後半になると家重もめっちゃ頭が良くなっていくんだよね家重も実は頭が切れる人で一揆の話とかも家重の機転みたいなで発覚したりするから頭はとにかくいいと思うんですよでも これ何でかわかんないけど
やっぱり本人の良さかなと思うけど仲間もいっぱいいるんだよね忠光もそうだし正室の比宮とかもかなり親しみを持って家重に接したりとかもあるし途中で家治が生まれるんだよね家治も家重がお父さんだから家茂を庇ったりとか
するシーンとかあって
泣けてくるんだよねだから言ってしまえば ずっとパワーバランスっていうか権力の問題だから 江戸幕府の権力闘争みたいなことで自分が障害を持ってるっていうこんなん言うと怒られるけどディスアドバンテージみたいのがあるわけじゃないですかなんだけど それに屈せずに将軍になりました みたいなサクセスストーリーみたいなそんな単純な話じゃないけどそういうのが書かれてて めっちゃいいと思ったなあ毎回ですが 点数をつけることにしてまして『まいまいつぶろ』の点数は90点かな個人的にめちゃくちゃ感動したんですよねこれが実際にあったことっていうのが また面白いよねもちろん小説だから脚色されてる部分はあるにしてもwikipediaを僕はサブテクストとして読んでましたよこういう時代小説って実際にあったことを元にしてますからwikipediaに書かれてたりするわけよあと時代小説だから難しかったりするんだよね昔の役職の名前とか江戸時代の文化とかが書かれてたりするからわかんないわけよ 僕もわかんないことがめっちゃあって 調べながら読むしあと人物とかも出てくるわけねこれ 最初に関係図が載ってるからずっと事あるごとに ここのページを見ながら吉宗・家重・家治とか家重の正室がこうで 他にはこうで みたいな吉宗の時の老中と家重の時の老中が また違ったりするからそういうのも 全部
wikipediaに書いてますから
全然ググったら出るのよね実際にあった話として読むと
めっちゃ感動できるわ24時間テレビじゃないけど僕はどちらかというとこういうの泣いちゃうタイプで感動ポルノとか24時間テレビ
言われたりするんだけど障害に対しての自分たちの偏見っていうか障害観みたいなのは我々絶対に持っててそこに対して くすぐられると思うんですよそこに対して嫌だとかいう気持ちが
多分そこから出てる人はいると思うんですよ我々障害に対してあんまり理解してないというかそんなに知らないことだってあるわけじゃないですか僕はなんか こういうのは見たり聞いたり読んだりすることは
とても大事だと思うんだけど 僕はそんな感じでございます今回で直木賞候補 4冊目ですけどあと2冊 残ってますからそれ また読んだら 動画にしようかと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#919「【書評】直木賞候補③加藤シゲアキ『なれのはて』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらですねこちらは加藤シゲアキ
『なれのはて』
講談社 2023これは 今回の
直木賞の候補作の1つと
なっておりますねこれ めちゃくちゃ面白かったですねページもかなりボリューミーでめっちゃ楽しめたっていう感じかな早速やっていきましょうまず あらすじの方に行きますと舞台が現代でして主人公が守谷っていう男の人なんですよ守谷さんはテレビ局に勤めてるんですよね昔は報道局にいたんですね報道局のADをやってたんだけどある事件があっていわゆる1つの罰としてイベント事業部っていうところに飛ばされてしまうんですよそのイベント事業部で やる気ないわけよ「俺は報道がしたいんだ」って思ってるんだけどそのイベント事業部の 同僚の
吾妻っていう女の人がいるんですよその吾妻が守谷に相談するんですよねその内容は「1つ展覧会しましょう」というわけよその展覧会というのは吾妻自身が持っている1枚の絵があるんですよねその1枚の絵で たった1枚の絵で展覧会をしたいって言うんですよその絵っていうのは少年が写っている絵でそれで その2人はその企画を通したいと思うんだけど2つぐらい問題があって1つは たった1枚の絵だけで展覧会するのは集客の問題で あまり金にならないんじゃないかっていう上司に言われそう っていうのとあと もう1個は 権利問題があるんですよねその絵には「ISAMU INOMATA」って
後ろにサインが書かれてるんですよイノマタイサムさんっていう人が
書いただろう と思うんだけど調べても出てこないと無名の画家であるっていうのがあってそうなってくると 権利問題で勝手に その絵を展覧会にすることはいけないとまず この絵を描いた作家を訪ねて権利をちょっともらわないといけないっていうことでデータベースで調べるとある新聞記事が見つかって1961年の新聞記事に秋田にある石油会社があるんですめちゃくちゃデカい石油会社があってそこの社長の猪俣傑さんっていう人がいてその人が焼死体で見つかってるんですよその猪俣傑さんの弟が猪俣勇っていう名前なんですよこの時点で同一人物かは分からないんだけどその猪俣勇さんはその後 行方不明になってるんですよね未だに見つかっていないっていう事件があったと主人公たちは この猪俣勇っていうのが
ISAMU INOMATAじゃないかと思って秋田県まで飛ぶっていう話なんですよそうすると その殺人事件を
解決していかなきゃいけなくなっちゃってこれ いわゆるミステリになってるんですよね主人公たちが秋田県に飛んでそのデカい石油会社はまだあるので そこに行くとその社長の猪俣輝さんっていう人がいて猪俣輝さんは焼死体で見つかった
猪俣傑さんの息子なんですよねその人のところに行って自分たちの持っている
ISAMU INOMATAの絵を
見せるわけですよ「この権利は今 誰が持ってますか」って言ったらその猪俣輝さんが持ってるって言うわけよ猪俣輝さんに「権利を一瞬お借りしたい」と「展覧会させていただきたい」
って言うんだけど「ダメだ」
っていうわけよむしろ逆に輝さんがその絵を「1億円で買い取りますよ」って言うわけよどうして猪俣輝はISAMU INOMATAの絵を
めちゃくちゃ集めてるのか
っていう問題とあと 秋田県に刑事さんがいてその刑事さんは実は石油会社の事件に関わってて仲間みたいになって一緒に調査してくれたりするんですよねそうなってくるとその事件の関係者をどんどん聞き込みをしていって猪俣一族には兄弟がいて 傑と勇がいて傑の息子が輝なんだけど勇にはどうやら養子がいたらしいとどこの家系かわからない謎の子供がいてその子供が自閉症っぽいと発達障害を持っていて なかなか
生き辛いっていう子がいたとその人は一体 誰なんだってって さらに探っていったりとかそれを聞き取りしていくから小説の中で 途中で断章が入ってて関係者の言った物語が途中でちょびちょび入ってって色んな視点から
物語が多層的で書かれる
っていう話なんですよめっちゃ面白かったですねこれは僕の個人的な感想ですが舞台が 現代を舞台にしてるんだけど事件自体が1961年から始まるわけよだから昭和・平成・令和みたいな時代を3つ跨ぐぐらいの話になっていくんですよ登場人物も まあまあいるんで結構 ややこしいっちゃ ややこしいけど僕 最後に本当に泣いちゃったねよかったっていう感じもちろん事件の謎も全部 解かれていやあ〜 すごいと思ったもんこれ 加藤シゲアキっていうNEWSのアイドルっていうかミュージシャンが書いた作品なんだけどこういう小説 書けるんだって思った悪い言い方だけどしかもこの作品 書き下ろしなんですよねこういう分量を書き下ろしで書けるって僕 すごいと思ったあと めっちゃ勉強になるよ「石油会社」っていうのが 1個
大事なワードになっていくんだけど実は日本でも石油は取れるんですよねほとんどの場合 海外から輸入に頼ってるんだけど実は国産の石油っていうのもあって秋田県が1番取れるらしいんですよその石油っていうのが上手いと思う これうまく使われている ギミック・ガジェットっていうかかなり最初から最後までずっとあって超面白いあと途中で「デーモン・ストーリーズ」っていうアニメ番組が出てくるんですよ「鬼滅の刃」っぽいめちゃくちゃ売れてるアニメみたいのがあって元々 漫画原作なんだけどテレビ局が舞台だからテレビ局の裏側もわかっていってこれ 主人公がいて
主人公には昔 お世話になった
先輩がいるんだけど最初の時点で その人は
亡くなっているということが
わかるんですよねなんで その人は亡くなったのか とかあと主人公が なぜイベント事業部の方に
飛ばされてしまったのかっていう主人公の事件もあるわけですよそれには大きな裏側の報道を巡る メディアを巡る 1つの闇みたいのがあってそれもダブルで描かれるっていうあと これ 巻頭言っていうのかな引用っていうか エピグラフっていうのかな作品の最初に誰かの作品とかを引用して巻頭言にするってあるじゃないですかこれもあってソポクレス『オイディプス王』の1文を引用してるんですねめちゃくちゃ直接的じゃないですかオイディプス王っていうのは いわゆるエディプスなのでエディプス・コンプレックス的なことが
最初からわかるんですよねエディプス・コンプレックスというのは
フロイトが提唱した父親と息子の確執みたいなことを言ってるわけですよ猪俣一族も父子とかが結構ややこしくて
喧嘩ばっかりしてるっていうのとあと主人公にもお父さんと自分と弟がいて主人公は酒屋さんなんですよ 元々はそこから独立っていうか上京して テレビ局を務めてるんだけど昔は酒屋を巡って色々あったらしいとあと女の子の吾妻さんっていうのも実はお母さんと揉めてるっていうのもあってみんな家族関係 ちょっとややこしいというのがあるんですよそこも超面白い昔ながらの小説でもあるだろうし全然 古びてる感じはしないかな途中でコロナとか
そういう現代的な話も
入ってたりとかしてとても良かったと思いますこれ最後に 点数を言おうと思うんですけど92点かな 個人的には
とてもとても良かったですタイトルが『なれのはて』っていうわけよこれにも意味があるわけよ もちろんなんか上手い なんか全部が僕は噛み合ってるような気がするのよこれ最後に後ろの帯に書かれてるのを読むと「死んだら、なにかの熱になれる。
すべての生き物のなれのはてだ」
って書いてるんだよね全然 直木賞を取れると僕は個人的には思うし映画とかドラマとか全然やっても面白いと思いますよ秋田県を襲った土崎空襲っていうのも結構 キーワードで8月14日に 終戦の1日前に秋田県にアメリカから空襲があってめちゃくちゃひどい空襲があったとそれもずっとあるんですよ秋田県が舞台だからね秋田県の話がずっとあって とても良かったですねそんな感じで今回で直木賞候補 3冊目ということであと3冊 残ってるんですけどまた読んだら動画にしていこうかと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで今回はそんな感じで終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#918「【書評】直木賞候補②河﨑秋子『ともぐい』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらに
なっておりますね
こちらは河﨑秋子
『ともぐい」
新潮社 2023年こちらは今回の
直木賞の候補作と
なっておりますめちゃくちゃ良かったですよドロっとしてる感じがあって今回の直木賞の候補の中では特徴的な作品だったんじゃないかなと思いますね早速やっていきましょうまず あらすじを言うとこの作品は
明治の後期の
北海道が舞台でそこに熊爪っていう
男がいるんですねその熊爪は 町から離れた山の中で
1人で暮らしてる猟師なんですよねそこで鹿とか熊とかを撃ってそれで得たものを自分で食べたりもするんだけどちょっと離れた町で換金してその金で食べ物とか塩とかあと酒とか そういう必要品を買ってまた小屋に戻るという生活を
ずっとやってるんですよ町も半日ぐらい歩いた先に
白糠の町っていうのがあってそこになじみの男がいるんですよねその男が良輔って言って 変なやつなんですよ熊爪自体も変わったやつになってるわけ 町から見るとこの時代でも猟師は猟師グループを組んでみんなで獲物を取るっていうのが一般的らしくて1人で単独行動で山でこもってるっていうやつはあんまりいないらしいんですよねだけど その良輔は変わったものが好きみたいなでそれで山の暮らしとかも良輔は熊爪で聞いたりして結構 コミュニケーションできてるんですよねあと熊爪は自分の相棒として犬を飼ってるんですよね犬も一緒に狩りをしてくれる犬だけが仲間みたいな感じなんですよ熊爪が山の中である男を助けるところから展開していくんですねいつもの通り熊爪が山に入っていくと山で血まみれの男がいるんですよね目の部分がえぐられてるんですよでも死んでなくてその男も意識があって
「助けてくれ」って言うわけよ熊爪も「めんどくせーな」って思うわけよちょっとサイコパスって言ったらアレだけどどちらかというと自分中心で動くんですよね 熊爪は他人のために何かをするってことはあまりないんですよ自分1人で死ぬか生きるかの世界でやってるから人を助けても それが自分の何かに繋がらないと助けなかったりするんだけどでも ちょっと気まぐれで 助けるかと思って血まみれの男を自分の小屋まで引っ張って助けるんですよそいつに話を聞くとそいつは隣町ぐらいの猟師で隣町から「穴持たず」っていう超デカい熊がいてそいつを殺そうと銃で戦ってたんだけど逆に返り討ちにされたと穴持たずを隣町からこっちの熊爪のテリトリーの山まで
引き連れてしまったって言うわけそうなると熊爪も困るわけよ自分の山で そこの生態系っていうか他の熊とかも もちろんいて熊爪はその辺も考えてるからその辺の熊が育っていくように とか考えてるから穴持たずが来ると ぐっちゃぐちゃにされるから「俺が穴持たずを殺してやるよ」って言って仕事を引き受けるわけよ熊爪は穴持たずを倒せるのかっていう話ともう1個 町に盲目の少女っていうのがいるんですよね良輔は変わった人 好きだからその盲目の少女っていうのを引き取ってるんですよね盲目の少女に なぜか熊爪は惹かれていくっていうのとあと日露戦争が後ろでどんどんなってて時代がどんどん進んでいくわけよその時に北海道の町もどんどん変わっていって町が変な感じになっていってそれに対して熊爪も関わっていかなきゃいけないからそこの交流が展開していくっていう話なんだけどこれは僕の個人的な感想ですがエロスとタナトスみたいのをずっとやってる感じはあったな熊爪が生きるか死ぬかみたいなのをずっとやってるわけよ良輔とかも言うわけだけど1人で小屋で暮らしてたら いつ死ぬかわからないと「町で一緒に暮らさねえか」みたいなこと言うわけよでも主人公は 町っていうのが大嫌いで何でかと言うと 人から変な目で見られてしまうとまず山で暮らしてるから臭いとかも獣の匂いみたいな感じでまず お風呂にもほとんど入ってないし体もごっついわけよだから普通 変な人って思われてしまうから それも嫌だとでも 熊爪も なんか人間らしいところがあって性欲みたいのがあるわけよだから町に体を売る女みたいのがいてたまに買ってるっていう描写があるんだよねここも1つ エロスとタナトス的なんだよね最後の 盲目の少女の部分ってもう本当にぐちゃぐちゃになってくるのよ熊と戦う猟師の話と思っていたら実は「そっち」に行くんだみたいなもちろん熊との戦いも かなり面白いですよもちろん鹿とか撃ったりして鹿を解体するシーンとかもあったりとかあと熊も解体して熊の胆嚢を生でペロって食べるとかあるんですよねそういうワイルドなんだよね 全体的に個人的に思ったのは猟師版の『コンビニ人間』だと思ったんだよね『コンビニ人間』って村田沙耶香さんの小説でありますけどあれはコンビニでアルバイトをずっとしててコンビニの仕事が自分でも好きだし 事務的にできるからって言って長年ずっとやってるんだけどでも世間の評価的には「何年もアルバイトかよ」「正社員になれよ」とかあと「結婚しないのか」とかいう違う視点っていうかちょっと偏った視点で見られてしまうから本人も気になっちゃってコンビニバイト1回 辞めようかって
辞めちゃったりするっていう自分の道を突き進めばいいんだけど社会がそれを許さないみたいな そういう話なわけよこの『ともぐい』も 主人公の熊爪は自分の猟師の仕事をずっとやりたいわけなんだけど途中で それも考えるシーンがあるわけよ「俺 猟師 もしかしたらこの先
できないんじゃないか」って思って町の炭鉱があって炭鉱で働こうかとか言ってめっちゃ考えるシーンがあるんですよねなんか 可哀想な感じ するんだよね僕はどちらかというと 熊爪側に立ちたいわけよ色んなこと 考えてしまうでしょ 人間ってそれこそ熊とか鹿とか
動物とかだったら
そんなの考えないわけよ結構 出てくるよ そういう描写「俺は人間じゃなくて動物だったらいいのに」とか途中で自分のことを「半端もの」って言って山側にも立てないし 人間側にも立てないしその中間で「どうしようもねえんだ」みたいなことをめっちゃ悩むところ あるんですよ俗世間とは違うところに住んでるからある種 仙人みたいな人ではあるわけよ 熊爪はこういう人いると思うんだよねそういう生き方も全然やっていいと思うんだよねむしろ現代の方が どこか社会の歯車となって社会を回していかないといけないっていう世界でしょう社会から孤立して そこで自立する
っていうことは あまりできないような
気がするんだけどそういう人を描いてる
っていうところがとても面白いそういう人が最後 本当に人間関係ぐちゃぐちゃになってってタナトスの側に引っ張られてしまうっていう感じが僕は なんか泣けてきたねこれ 点数をつけてみると85点かな
とても良かったです結構 グロいシーンとかもあって血まみれの男が
目 えぐられてるわけよ
これ 熊にやられてんだけど片方の目が 眼球が潰れちゃっててもう1個も ポコンと出てるわけよ 眼球がでも熊爪はその処理の仕方って わかっててまず潰れた眼球があってこれ 放置すると腐っていくらしいんですよね腐っていくと目からずっと顔全体が腐っていくから潰れた眼球を引っ張り出して引きちぎって捨てなきゃいけないらしいんですよ熊爪がやることは男の このポッカリ空いた目のところを口つけて吸うんですよね吸って 眼球の破片みたいのを全部吸ってそれでペッてやって出して を繰り返すわけよ男は意識があるから めっちゃ痛いわけ痛いけど そうしないと顔面が全部腐るからそういうことをするっていう
シーンがあるんですよ
結構グロくない?熊爪も淡々とやるんですよね それを嫌だとかじゃなくて淡々と「これしなきゃお前 死ぬぞ」とか言ってパッパッとかやるんですよ めっちゃ面白いの そこが「もののけ姫」みたいな世界ではあるよね今だったら
「ゴールデンカムイ」とかが
あったりするじゃないですか主人公はアイヌの一族じゃないらしいんだけど北海道だからアイヌの描写とかもあってそこら辺の「自然と神」とかそういうことをやってるような気がするんだよねそんな感じで また候補作を読んだら動画にしようかと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じ 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#917「【書評】直木賞候補①万城目学『八月の御所グラウンド』」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうとこちらになっておりますねこちらは万城目学
『八月の御所グラウンド』
文藝春秋 2023年これは今回の直木賞の候補作となっておりますこれを読みましたので あらすじ・感想を述べていこうかなと思っております早速やっていきましょうあらすじなんですけどこの本の中に 2つの話が入っています1.「十二月の都大路上下る(カケる)」2.「八月の御所グラウンド」まず「十二月の都大路上下る」から言うとこれは駅伝の話なんですね「女子全国高校駅伝」っていう大会があるんですよそこに参加する女の子たちの話主人公が坂東っていう女の子なんですねこの子は1年生なんですよある高校で駅伝に出るっていうことなんだけど坂東は補欠なんですね 1年だからね駅伝は5人が出るらしくて1人1人に襷を渡していくんだけど大会の前日から始まって5人の出場選手のうち1人が貧血で出られないんじゃないかっていうことになって補欠の中から1人 走者を
決めなきゃいけないってことになって色々 補欠いるんだけど
その坂東が選ばれるんですよ坂東は急に選ばれることにびっくりして「いやあ〜行けるかな」と思うわけしかも この坂東っていうのがめちゃくちゃ方向音痴で道を覚えるのがほとんど無理という子なんですよその辺 監督もわかってるから「あんた5番目ね」っていうことになっていわゆるアンカーになっちゃって自分がかなり責任重大だってことになっちゃってそのまま本番に行くんですけどこれ短い話だから 最後まで言わないけどその本番の中で 1個めちゃくちゃ不思議なことが起こるっていう話なんですね観客の中に新選組の服を着て並走する観客がいるとそれを本人 走ってる中で こう見て「そんな人もいるんだな」って思うわけよでも実はその人たちはまさかの…っていう話これ ザ・青春みたいな感じがして 良かったですよ表題作「八月の御所グラウンド」なんだけどこれは大学の4年生の男の子が主人公で朽木くんって言うんだけど大学4年生だから就活とかしなきゃいけないんだけどちょうど彼女に振られちゃって傷心状態になってるわけよその時に 友達の多聞くんっていうやつがいてそいつが焼肉を奢ってやるから話を聞いてくれっていうわけ主人公が行ったらある草野球大会があるとメンバーが足りないから
お前ちょっと入ってくれよ
っていう話なんですよ主人公はめんどくさいなと思ってるんだけど多聞に借金もしてるから
ちょっと仕方ねぇかと思って
参加するんですよこの草野球が 京都にある
御所グラウンドっていう場所で
行われるっていうことでさっきの駅伝の話も舞台が京都なんで 京都・京都で
ストーリーになってるのが面白いんだけどその草野球大会ってここはとても大事だから言わないけどある目的があって みんな大会に出場してるんですよ全部で6チームあって主人公のチームは「三福チーム」って言って三福っていうのは多聞が所属している大学のゼミの先生の名前が三福って言うから 三福チームになってるんですよ他にもなんとかチームって言って 6チームあるんですねこの大会で優勝すると あるものがもらえるっていうことでみんな 必死になって頑張ってるわけよここはもう言わないけど 結構すごいなんか「どんなんやねん」みたいな優勝商品なんですけどこのチーム自体が三福教授が勝ちたいから
って言って チームを集めてるんだけど結構 ギリギリなんですよね集まった人が8人とかで 残り1人足りなくて本番になってて どうすんねんってなった時にその場所にいたシャオさんっていう中国から来た交換留学生の女の子がいて1人でもチームが欠けてると
その時点で敗北になっちゃうからどうにかして人を入れないといけないということでシャオさんを無理やりチームに入れるんですよシャオさんも実は後で聞くと日本のスポーツについて勉強しに日本に来てる子で特に野球を勉強しているということででも本人はあんまり野球のルールをわかってなくてもちろん野球もやったことないから
9番ライトに置かれたりするんですけどだから その寄せ集めチームとかで
どんどん戦っていくっていうのが
この話なんだけど「沢村栄治」っていう 昔に
プロ野球にいた選手がいるんですよその沢村栄治は もうすでに
めちゃくちゃ昔に亡くなってんだけどその人にめっちゃ顔が似てる
「えーちゃん」っていう子がいてその「えーちゃん」と沢村栄治の
関係性がどんどん出てくることになってつまりこれ ただの野球の小説じゃなくて1個 裏に でかい物語があってその謎をどんどん解いていく
っていう話になっていくんですよそれで最後どうなるかって話なんだけどこれ 僕自身の感想になりますがこの2つのストーリーって
関連性があって面白いんだよねまず舞台が どっちも京都っていうことで京都の話がたくさん出てきて京都は夏はめちゃくちゃ暑いよとか京都の土産物がたくさん出てきたりとかして結構 面白いんだよねもう1個は どっちも青春だっていう話なんだけど高校生と大学生が主人公で女性と男性で対比的になってるのとあと その後ろに 1つ不思議な話が入ってるめちゃくちゃ昔に起こった出来事が 現代とオーバーラップしてくるみたいな話なんだけどその2つを1冊にまとめたっていうのがこの時点で完成度が高いと思うストーリー自体は とてもシンプルだと思うんですねめちゃくちゃ複雑になってるわけじゃないし場所自体も駅伝の話と野球の話なんであっち行ったり こっち行ったりとか何年後とか そういうのは全然ないんであと個人的に僕 結構スポーツ好きなんですよねプロのスポーツのやつとか
オリンピックとかあんまり見ないんですけど高校生・大学生とかの野球とかサッカーとかそういうのは めっちゃ好きで特に野球 これ草野球だけど僕 甲子園とかめっちゃ好きで大学生の時なんか暇だから
ずっと毎日見てた時あったし僕 元々 パワプロが好きで ゲームのコナミの実況パワフルプロ野球が好きでもう5年間ぐらい
あの時は毎年新作が出てたから5年間ぐらい ずっと買ってやってたぐらい野球 好きなんだよね 意外とこの前の阪神の優勝のやつも見てましたからねオリックスとの戦いのやつも一応全部見てめっちゃ良かって
めっちゃ泣いちゃったぐらい
見てたんだけど結構 野球 これめっちゃ面白いしかも このキャラクターのシャオさんっていうのがまたちょっと変で面白いんだよね「烈女」ってストーリーの中で言われてて結構はっきりと物事を何だって言うんだけどあと研究もしてるから日本の野球の歴史みたいなも途中で出てきたりするんですよあと相手のピッチャーとかをめっちゃ観察しててこのタイミングで相手は投げるからこう振ったらヒットするだろうとか言ってシャオさんも参加してるから野球初心者なんだけどそれでヒットを飛ばしたりとかするとかいうそういう面白キャラがいるんですよねあと 野球がしたいんだなーっていう最後のところがあるんですよ これ野球が本当にしたくてたまらないんじゃないかみたいなこれ以上 言わないけど野球への情熱みたいのが入ってるんですよねまあ ただ強いて言えば オチがちょっとエモすぎる感じがあるかな結構 エモく終わるのよこのエモさがダメとは言わないよ 僕は結構好きなんだけど人によっては「そういう終わり方ね」
っていう終わり方と思う人いると思うんですよねスポーツ・野球・京都・夏みたいな感じで
言えば エモくてもいいと思うんだけどねスポーツっていうのをテーマにはしてますからスポーツの情熱とかスポーツの良さみたいなが小説で語られていたんじゃないかなと思うんだよねこの帯の後ろを読むと「今度のマキメは、じんわり優しく、少し切ない」あと「人生の、愛おしく、ほろ苦い味わいを綴る傑作2篇」毎回 やってるんだけど芥川賞・直木賞の時は点数をつけるようにしています今回の『八月の御所グラウンド』は80点を
とりあえずつけようかな
これを基準点にしてM1みたいに他の作品の点数を
上下させようと思うんですけど全然 これ直木賞を取っても
僕はいいんじゃないかと思うよもう6回目だしっていうのあるんだけどこういうシンプルさも僕はいいなと思いますよまあ そんな感じかな今回 まだこれ 直木賞1作品目なんでこれからまたどんどん
候補作を読んでいったら動画にしようかと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#916「第170回直木賞の候補作を解説します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと先日 12月14日に
第170回 直木賞の候補作が
発表されました今回は1つずつ
それを見ていくっていう
動画なんですけど今回の候補作も
とても面白いメンバーだと
僕は個人的に思いました早速やっていきましょう第170回 直木賞 候補作品1つ目①加藤シゲアキ『なれのはて』講談社2つ目河﨑秋子『ともぐい』新潮社3つ目③嶋津輝『襷がけの二人』文藝春秋4つ目④万城目学『八月の御所グラウンド』文藝春秋5つ目⑤宮内悠介
『ラウリ・クースクを探して』
朝日新聞出版6つ目⑥村木嵐『まいまいつぶろ』幻冬舎以上 この6作品が
第170回 直木賞の候補作と
なっております1つずつ見ていくとまず1つ目が加藤シゲアキ『なれのはて』ですが加藤シゲアキさんは1987年生まれ
青山学院大学法学部卒業だって2012年『ピンクとグレー』で作家デビューと「NEWS」のメンバーですね今 話題のジャニーズのタレントではありますがでも ずっと作家活動されていて2020年『オルタネート』っていうので
直木賞の候補に1回なってるんですよね今回で2回目なんですけど『オルタネート』は僕 読みましたよまさしく青春群像劇みたいなので主人公が3人いて それぞれの話が進んでいくと遺伝子を使ったマッチングアプリで… みたいな話でしたねその『オルタネート』は
吉川英治文学新人賞を
受賞してるんですね過去1回 直木賞の候補だった時は文字通りニュースになってましたけど今回2回目なんで期待値みたいのはちょっと上がってるかもしれないね今回 もし受賞とかするとテレビでめちゃくちゃ
取り上げられるってことは
あるでしょう2つ目 行きますと河﨑秋子『ともぐい』ですね河﨑秋子さんっていうのは1979年生まれと北海学園大学経済学部卒業後ニュージーランドで1年間 麺用飼育を学ぶと2012年に北海道新聞文学賞というのを受賞し2014年『颶風の王』っていうので三浦綾子文学賞2017年『肉弾』っていうのが
大藪春彦賞も受賞していると2019年『土に贖う』が新田次郎文学賞を受賞とあと三島賞の候補に1回なっていると2021年ですね『絞め殺しの樹』っていうのが
3回前の直木賞の候補になっていますこれは僕 読みましたけどねめちゃくちゃ暗い話である女の人が丁稚奉公に行くんだけどめちゃくちゃ
いじめられる話で
悲しすぎた話ね河﨑秋子さんは作品数とかも結構あって文学賞も結構取られていますから妥当な2回目っていう感じはしますよね3つ目ですね嶋津輝『襷がけの二人』
っていうのなんだけど僕 本当に申し訳ないけど
嶋津輝さん 知らなかったんですよね嶋津輝さんは1969年生まれと2016年「姉といもうと」っていうので
第96回オール讀物新人賞を受賞してるとこの受賞作を収録した2019年に出た
『スナック墓場』っていうので
単行本デビューしてるとその後
結構アンソロジーにたくさん
色々収録されてるらしくて単著があんまりないみたいですね今回 この
「襷がけの二人』っていうので
1回目の直木賞候補ですけどだから多分 この中で1番
新人じゃないかなと思います『襷がけの二人』の書影を見てみると時代小説っぽいんですよね今回 6作品中 この『襷がけの二人』と『まいまいつぶろ』っていうのが 後で出てくるんだけどこの2つが時代小説かなっていう
感じの雰囲気がありました4つ目万城目学『八月の御所グラウンド』ですが万城目学さんがこの6人の中では1番ベテランなんじゃないかなと思います1976年生まれ 京都大学法学部卒2006年に 第4回
ボイルドエッグズ新人賞を受賞した
『鴨川ホルモー』でデビューと『鴨川ホルモー』は映画にもなってますからねその後に『鹿男あをによし』ですねこれドラマもやってたの 僕 覚えてますがこれで1回目の直木賞候補とその後『プリンセス・トヨトミ』
っていうので2回目の直木賞候補『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』
っていうので3回目の直木賞候補『とっぴんぱらりの風太郎』で4回目の直木賞候補『悟浄出立』で5回目の直木賞候補と今回でなんと6回目の直木賞候補なんですね他のメンバーを見てみるとやはり万城目学が6回目でしょう次の宮内悠介さんが4回目なんですねあとは2回か1回しかないので
直木賞候補歴も1番高いということですねそろそろ もう万城目さんに
あげちゃっていいんじゃないかと
個人的には思いますね5つ目宮内悠介『ラウリ・クースクを探して』ですね宮内悠介さんは1979年生まれ
早稲田大学第1文学部卒業2010年『盤上の夜』っていうので第1回創元SF短編賞山田正紀賞を受賞しているとこの『盤上の夜』で単行本デビューし
直木賞候補1回目になってますね次に『ヨハネスブルグの天使たち』が
2013年に出てて 直木賞候補2回目とその後『カブールの園』が2016年に出ててこれが なんと芥川賞候補1回目なんですねそして しかも三島賞を取ってますからねその後 2017年に
『あとは野となれ大和撫子』が
直木賞候補3回目2017年『ディレイ・エフェクト』で
芥川賞候補2回目になってますだから芥川賞候補は過去に2回
直木賞候補は今回で4回目ということでエンタメと純文学を
行き来している作家なんだけど僕はどちらかというと
純文学大好き人間なんで『カブールの園』と
『ディレイ・エフェクト』は
読んでいますどっちもSF的でしたけどねSFっていうのが
前々回だったら小川哲さん
っていう人が直木賞を受賞していますから最近 SF作家っていうのが
ちょっと来てるんじゃないか
というのはありますよね直木賞候補とかにも
全然上がってくるように
なってるとは思うんですけど今回どうなるか
という感じはしますね最後 6つ目村木嵐『まいまいつぶろ』
っていうやつですね僕は村木嵐さんって作家
ちょっと知らなかったんですよね1967年生まれ 京都大学法学部卒2010年「マルガリータ」で
第17回松本清張賞を受賞してデビューこの人は時代小説作家みたいでその後に色々作品があるんですが今回の『まいまいつぶろ』がすでに第12回日本歴史時代作家協会賞の作品賞を受賞してたりとかこの『まいまいつぶろ』が第13回
本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞している今回 この『まいまいつぶろ』が
直木賞候補1回目ということですね僕は時代小説作家は
知らないことが多いのでかなり勉強になりますね毎回 言ってるかもしれないけど日本文学の最先端なわけですね芥川賞・直木賞は
1935年から続いている
歴史ある日本の文学賞なのでそれを追いかけていくだけでも
僕はかなり勉強になるし面白いなって本当に思いますね今回で直木賞候補を読んでいくのも9回目ですけど読んできて良かったなと本当に思いますよ知らない世界が広がってるっていうので言えばもしかしたら 僕の場合は
直木賞の方なのかもしれないな
と思ったりしますねそんな感じで今回 直木賞の候補作6作品を見てきましたけど今回 見てみると この6作品 そんなに分厚くないみたいです1番 分厚いのが加藤シゲアキ『なれのはて』みたいで400ページ超えるぐらいなんですよあとは300ページ台と200ページ台もあるみたいで6冊あると言っても めちゃくちゃ分厚くて読むのしんどい みたいのはないっぽいんですね前回の直木賞『極楽征夷大将軍』が
ヤバすぎるぐらい分厚かって内容としては とても面白いんですけど1日では絶対読めないぐらいの分量あったんですよ今回はそういうのはないみたいですね芥川賞・直木賞のどっちもですが1月17日に受賞作発表なんでそれまでに僕は全ての候補作11作品を読んで動画で1本ずつ やっていくと毎回やってることをしようかと思っておりますんでとにかく頑張るしかないんで頑張りますそんな感じで
今回は終わろうかと
思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#915「第170回芥川賞の候補作を解説します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと先日12月14日に
第170回の芥川賞の
候補作が発表されました今回はそれを見ていくっていう動画なんですけどなかなかすごいメンバーじゃないですか僕はとてもいいなと思いましたよ早速やっていきましょう第170回 芥川賞 候補作1つ目①安堂ホセ「迷彩色の男」文藝秋号2つ目②川野芽生「Blue」すばる8月号3つ目③九段理江「東京都同情塔」新潮12月号4つ目④小砂川チト「猿の戴冠式」群像12月最後 5つ目⑤三木三奈「アイスネルワイゼン」文學界10月号以上5作品が芥川賞の候補となっております1つ1つ見ていくと安堂ホセ「迷彩色の男」ですが安堂ホセさんというのは1994年生まれと2022年に「ジャクソンひとり」で
第59回文藝賞を受賞してデビューしてますねこの「ジャクソンひとり」が前々回の
芥川賞の候補となっております今回 2作品目が「迷彩色の男」と「迷彩色の男」は単行本になってまして僕はすでに読みました候補作をすでに読んでるっていうのは珍しいんですけどとても良かったですよ「ジャクソンひとり」からの流れでブラックミックスとゲイっていうのを結構 先鋭化させてる感じがあった文体とかも純文学にしたら珍しく短文短文っていうのかな改行がめちゃくちゃ少ない純文学って結構あるんだけどそれの逆みたいな改行だらけみたいな感じで一見読みやすいだけど最後のオチがとても良かったですよ僕はもう1回読んで
動画にしようと思いますけど
良かったですね2つ目は川野芽生「Blue」ですが川野芽生さんというのは1991年生まれと東京大学大学院博士課程在籍・
大学非常勤講師らしいんですね2018年に短歌連作「Lilith」っていうのを第29回歌壇賞を受賞してるんですねだから 元々 歌人なんですよねこの『Lilith』が単行本化されて第65回 現代歌人協会賞を受賞していると僕は何回か前の動画で歌集を紹介するっていう動画 あるんですけどその中に この『Lilith』あるんですけどこの後に幻想文学の方に行くんですよ
いわゆる小説の方に行くんですけど『無垢なる花たちのためのユートピア』『月面文字翻刻一例』『奇病庭園』っていうのを立て続けに半年に1冊ぐらいでポンポンポンって出してた純文学の方じゃなくて
エンタメ系だと僕は
思っていたんですよね文芸誌にも発表してないと 僕 思ってたんだけどでも今回 すばる8月号に
「Blue」というのを出していて
今回 入ったということですよ僕の中ではダークホース感 ありますね僕の この前の動画の「30選」っていうやつね芥川賞候補になるんじゃないかっていうのを30作品ね選んだ動画 あるんだけど この中に入ってないんですよね多分 誰も入るとは
思ってなかったんじゃない
かなと思うんだけどこの「Blue」は今のところ
単行本の情報は出てないんだけど芥川賞候補になったということは単行本化されると思うんですけどね きっとね3つ目ですね 九段理江「東京都同情塔」ですけど九段理江さんっていうのは1990年生まれと2021年に「悪い音楽」ですねこれは文學界新人賞を受賞してデビューしているとその後に「Schoolgirl」っていうのを発表してこれが4回前の芥川賞の候補になっています単行本としてはさっきの「悪い音楽」と
「Schoolgirl」を合体させた『Schoolgirl』という本が出ていて 僕は読んでいますその後に今年ですよね「しをかくうま」っていうので野間文芸新人賞を受賞しているとこれはまだ単行本がありません今回 その流れで「東京都同情塔」が芥川賞候補とこの「東京都同情塔」はもうすでに
単行本化されるというのが決定していて1月だったかな に出ます今回 全体的に見てみると作家歴が短い作家が多くて10年とか15年とかやってる作家は入ってないんですよしかも後の作家もそうだけど みんな1990年以降に生まれた作家なんですね僕は1989年生まれなんで僕より若い作家だらけなんですけど歴史がちょっとずつ動いてる感じしないですか僕 こういう文学の移り変わりみたいな本当に大好きなんで今回 もう誰が取っても僕はいいなって思ってるんだけど4つ目ですね小砂川チト「猿の戴冠式」ですね小砂川チトさんは1990年生まれと慶應義塾大学の文学部卒業と同大学院の社会学研究科心理学専攻修了と2022年に「家庭用安心坑夫」っていうので群像新人文学賞を受賞してデビューとそれは3回前の芥川賞の候補に1回なりまして今回で2回目ということですね僕は「家庭用安心坑夫」は読んでおりますね「猿の戴冠式」は僕は読めてませんがなんと これ もう単行本化するの 決定みたいですねこの前 僕 講談社のHPを調べても情報 出なかったんだけどAmazonの方に出てるみたいで書影の方も出てるんだよねこれ芥川賞の時だけで特殊な出版の情報が出るみたいで普通はそれぞれの出版社のホームページに2ヶ月後ぐらいまでの出版情報が出るんですよねなんだけど芥川賞の時だけ2ヶ月後の情報から漏れててAmazonの方を調べると出るっていうことがあるんですよこれ 前の児玉雨子『##NAME##』もそうで河出書房新社のHPを見ても
『##NAME##』の情報は
出てなかったのにAmazonの時は出たっていうことがあって調べにくいんですよね
そこが僕は面白いと思う僕としては どんどんどんどん単行本化してほしいからだから僕はこういうサプライズはとても嬉しいんですよね最後ですね 5つ目の三木三奈「アイスネルワイゼン」ですが三木三奈さんは1991年生まれと2020年に「アキちゃん」ですねこれで文學界新人賞を受賞してデビューとそして この「アキちゃん」は速攻で
芥川賞の候補になりましたが 落選し単行本も出ていない状況と今回の「アイスネルワイゼン」で2回目の候補になってます前の動画でも言いましたが「アイスネルワイゼン」は
単行本化する情報がまだ出ていませんほとんどの場合 芥川賞候補になると基本的には単行本化されるんですね僕が調べた限り 芥川賞候補作で単行本化なってないのは 2012年までさかのぼってて2012年に北野道夫さんっていう作家の「関東平野」っていう作品が芥川賞候補になってるんだけどこれは単行本化されてないんですよでも そこから2012年から現在2023年まで行くと芥川賞候補になったのに
単行本化してないのは
「アキちゃん」だけなんですよなぜ?と思うわけでも今回 2回 三木三奈さん
芥川賞候補になってるわけだから「アイスネルワイゼン」と「アキちゃん」あたりを含めて
単行本化してほしいと僕は本当に思ってますねそんな感じで 今回この芥川賞候補作 5作品を見てきましたけどもちろんこの全てを読んで1作品ずつの動画を出そうと思います僕は芥川賞・直木賞の候補作を全て読んで動画にするっていうのを過去に8回やってて 今回9回目なんですね2019年の下半期の古川真人「背高泡立草」の時から始めたんで今回 9回目になるみたいですね僕もずっと続けてきたなと思って続けることに意味があると思ってますからどんどんやり続けると思うんですけど最後に これ1個だけ言いたいのが今回の5作品 雑誌が全てバラバラっていうかつまり5大文芸誌がそれぞれ1作品ずつ出てると文藝・すばる・新潮・群像・文學界と これ綺麗ですよねそれぞれの出版社同士の戦いということになりますからね芥川賞っていうのは受賞すると とても売れますから売れると売れないでは作家のこれからの人生も変わるし出版社の売り上げにも変わってきますからもうみんなライバルという感じでこのバチバチ感がとてもいいんじゃないかと思いますよ僕は個人的にこの5作品に文句はないですね僕は与えられたものを全て受け入れて「いやあ 素晴らしいですね」って言うだけの人間なんでとてもいいと思うけど 個人的にめっちゃおもろいと思いますね今回は芥川賞の方をしましたが次回の動画では直木賞の方を見ていこうかと思います芥川賞・直木賞 どっちも頑張って
読んでいこうかと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#914「第170回 芥川賞の候補作に入りそうな30作を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと今度 12月14日に
第170回 芥川賞の候補が
発表されるんですよ僕はとてもとても待ち望んでいたんですけれども今回 その候補作に選ばれるであろう
作品を30作品 選んできましたのでそれを全て発表しようかと思います早速やっていきましょうまず「文藝」から紹介しようかと思います河出書房新社が出している「文藝」という雑誌で候補になるんじゃないかっていうのは6つあります1つ目1.日比野コレコ
「モモ100%」
文藝秋号単行本が実は10月26日に発売されておりますね僕はまだ『モモ100%』読めてないんですよ日比野コレコさんは1個前に
『ビューティフルからビューティフルへ』
で文藝賞でデビューしておりますから今回も期待大ということですね2つ目2.安堂ホセ
「迷彩色の男」
文藝秋号これも9月27日に既に単行本化されておりますねこれは実は僕 読んでましてブラックミックスとゲイっていうので1つの殺人みたいなが起こるみたいな話なんだけどとても良かったですよ前回『ジャクソンひとり』っていうので
文藝賞を取ってデビューしていますそれは芥川賞の候補に前回なりましたが今回 2連続で来るかどうかということですね3つ目3.山下紘加
「煩悩」
文藝秋号これも実は10月25日に単行本化が既にされています山下紘加さんは前回『あくてえ』で芥川賞候補になってて今回も来るかどうかという感じですね単行本は今回を入れて5冊 出てまして僕は今回の『煩悩』だけ読めてないんでこれちょっと読まなきゃいけないなと思っています4つ目4.小泉綾子
「無敵の犬の夜」
文藝冬号これは11月21日に単行本化されましたこれは僕は雑誌掲載時に読みましてこれとても良かったですよ個人的に今回 芥川賞の候補に来てもいいと思ってるし受賞してもいい とまで僕は思ってますけどね5つ目5.佐佐木陸
「解答者は走ってください」
文藝冬号これも同じく11月21日に単行本化されていますこれと もう1個
6つ目を紹介すると6.図野象
「おわりのそこみえ」
文藝冬号これも同じく11月21日に単行本化されています「無敵の犬の夜」「解答者を走ってください」
「おわりのそこみえ」は今年の文藝賞受賞作と
優秀作ということでここは完全に新人なのでここから1人誰か
入ってくるんじゃないか
っていう感じもします次 行くと「すばる」ですねすばるは集英社がやっている文芸誌ですがすばるは候補になりそうなのが5つあって7つ目7.足立陽
「プロミネンス☆ナウ!」
すばる7月号この足立陽さんっていうのがだいぶ前のすばる文学賞を受賞作で
『島と人類』で取ってるんですね(2014年)単行本は多分 これしかなくてだいぶ昔に僕はこの足立陽『島と人類』は読みました長らく本を出してなかったから
今回 これが来ると熱いですよ8つ目8.大谷朝子
「僕はうつ病くん」
すばる8月号大谷朝子さんは前回の
すばる文学賞『がらんどう』
の人で(2022年)『がらんどう』は僕は読んだんですよこの作品は読めてないんですけど先に言っておくと僕は基本的には単行本派なので雑誌掲載されただけでは読んでないのが多くて後に単行本化されたら それは読むってことやってるんだけどこの辺は全然 単行本化
今されてないので
読んでいないの多いです9つ目9.天埜裕文「糸杉」
すばる9月号この天埜裕文さんもだいぶ前の
すばる文学賞受賞者で(2008年)『灰色猫のフィルム』っていうので取っていて僕はそれは読んだことあるんですけど
単行本も持っているんですけどこの人もそれを出したっきり単行本は出てなくて今回 この「糸杉」が入ると熱いですね10作目10.温又柔
「二匹の虎」
すばる12月号温又柔さんも だいぶ前の
すばる文学賞を取ってる
んですけど(2009年)単行本としては
5冊〜6冊とかあって
僕もまあまあ読んでます1回『真ん中の子どもたち』っていうので
過去に芥川賞候補になってますから(2017年)今回 全然来る可能性はありますよね11作目11.大田ステファニー歓人
「みどりいせき」すばる11月号この「みどりいせき」は今年のすばる文学賞受賞作なんでいわゆるデビュー作ということでして調べると これ単行本化が決定なんですね集英社のHPには2月5日に単行本が出る予定なんですよすばる文学賞は基本的には単行本化するので今回もするっていうのはあるんだろうけどもしかしたら集英社が考えるのは芥川賞が1月の半ばぐらいに発表があるんでその流れで2月の頭に単行本を出してもし受賞すれば
ドカンと行くみたいな
計算があるかもしれない続いての雑誌は「群像」ですね群像というのは講談社が出している純文学雑誌になりまして今回で言えば 6作品ぐらい候補に
なるんではないかという作品があります12作目12.鈴木涼美
「トラディション」
群像8月号これはもうすでに12月8日に単行本化されましたね鈴木涼美さんといえば 過去に2回
芥川賞の候補になってますから『ギフテッド』と『グレイスレス』ですね小説で言えば 今回 4冊目ということで結構ノリに乗ってる感じではありますね今回 3回目 全然来る可能性はありますよね13作目13.平沢逸
「その音は泡の音」
群像9月号平沢逸さんというのは何回か前の群像新人文学賞の受賞で『点滅するものの革命』っていうのがデビュー作で単行本もなってて それは僕は読みましたね(2022年)幼い子が主人公なんだけどお父さんがちょっとダメ親父みたいなでダメ親父の友達グループに入るみたいな話なんだけどとても良かったと思いますよ14作目14.西尾維新「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの
汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」
群像10月号西尾維新は確かもう20年ぐらい作家生活をやってるんだけど初めての純文学小説ということですね僕は西尾維新をめちゃくちゃ読んでて西尾維新って実験作が多いんですよだから僕は昔から「純文学を書かせてやったらいいんじゃない」っていうのを誰に対して
言っているかわからんけど
結構 言ってたんですよねそうすると なんと群像さんね西尾維新に純文学を書かせたと話題性あるからね もし芥川賞候補になるとだから僕はかなり応援してますよ15作目15.小砂川チト
「猿の戴冠式」
群像12月号小砂川チトさんといえば何回か前の群像新人文学賞受賞で『家庭用安心坑夫』っていうのがあってこれ1回 芥川賞の候補になってるんだよね(2022年)だから今回 全然2連続で来るっていうのもありえるだろうし僕自身もちょっと読んでみたいんだよね16作目16.村雲菜月
「コレクターズ・ハイ」
群像12月号村雲菜月さんというのは前回の群像新人文学賞の『もぬけの考察』ですねを書いてデビューして 単行本もあるんですけど(2023年)『もぬけの考察』は読みましたが
ホラー小説っていうのかな1つのアパートで行方不明者が
出てくるみたいな話だったんだけどなんか変な感じがあって とても良かったですよ今回もちょっと期待かなっていう感じかな17作目17.青木淳悟
「春の苺」
群像12月号青木淳悟ってだいぶ中堅ぐらいに入ってね元々『四十日と四十夜のメルヘン』(2005年)
っていうので野間文芸新人賞を取ってて三島賞も『私のいない高校』で取ってるのよ(2012年)今回 芥川賞 来るかわかんないけど来て受賞すると三冠王になるんですね実は結構 中堅だから入るか わかんないだけどでも青木淳悟って単行本も
だいぶ6〜7冊とか出してんだけど
ここ数年 出てないのよだから ここ数年の勢いとして
今回 芥川賞候補とか入ると
まあ単行本化するんで青木淳悟って実験小説が多くてわけわからん小説 多いのよ僕 そういう小説 好きじゃないですかだから青木淳悟の小説を読みたいのよ講談社さんは単行本にしてください お願いします次は「新潮」になります新潮は新潮社が出している純文学の雑誌なんですが候補になりそうなのは4つありまして18作目18.伊良刹那
「海を覗く」
新潮11月号これは次のやつもそうなんだけど
今年の新潮新人賞受賞作ですねつまりデビュー作ということで前評判としては とてもいいからこの辺から候補に入るってことも全然ありえると思うからね入ったら単行本化が
ほぼ決定みたいなものなんで
入ってほしいですね19作目19.赤松りかこ
「シャーマンと爆弾男」
新潮11月号これはさっきの「海を覗く」と同じく新潮新人賞の受賞作とあと新潮新人賞っていうのは確定で単行本にならないからなるやつもあれば ならないやつもあるのよ個人的にはなってほしいので新潮社さん もう全ての新潮新人賞
単行本化してほしいと思ってるんだけど20作目20.野々井透
「石榴のもとで」
新潮12月号野々井透さんっていうのは
前回の太宰治賞ですね(2022年)『棕櫚を燃やす』っていう作品があってこれは単行本化されてて 僕は読みましたけどなんか良かったね切ない話だった
お父さんが癌かなんかでもう寿命というのが
残り少なくなっている
お父さんにどうやって交流していくかみたいな話だったんだけど21作目21.九段理江
「東京都同情塔」
新潮12月号九段理江さんというのは
『Schoolgirl』っていうので1回 芥川賞候補になっていて(2022年)その後になんと野間文芸新人賞ですよね前回の野間文芸新人賞「しをかくうま」
っているの受賞してるんですよ(2023年)しかし それ 単行本がまだ出てないんですね1つ決定事項があってなんとこの九段理江「東京都同情塔」っていう作品が新潮社から1月17日に単行本化
されることが決定してるんですねだから新潮社はこれにかなり気合を入れてると思うんですね前回「しをかくうま」で野間賞も取ってるから今回 芥川賞 来るんではないかと読んでると思うんですよ嬉しいですよ とてもとても嬉しい 僕 これは絶対 読みますけどね新潮はこれでおしまいでして次 太宰治賞の1個だけあるのがあんのよ22作目22.西村享
「自分以外全員他人」
12月1日 単行本化これは今年の太宰治賞受賞作で下馬評としては とても面白いと言われていますよね僕も単行本化 これされてるから
絶対 近日 読むつもりですけど最後は「文學界」ですね文學界は文藝春秋が出している純文学の雑誌でして1つずつ言っていくと23作目23.水原涼
「誤字のない手紙」
文學界7月号水原涼さんね
かなり作品
出しているのに単行本も1作しかないですね『蹴爪(ボラン)』(2018年)
単行本が1個だけ出てるんだけどだけど全然
文藝春秋さんは
水原涼の作品短編だって短編で
短編集でもいいから
単行本化してほしいですよ水原涼さんもだいぶ前 デビューだから(2011年)中堅ぐらいまでなってるはずなのにちょっと文藝春秋さん ケチじゃないですか単行本化してください お願いします24作目24.石原燃
「いくつかの輪郭とその断片」
文學界8月号石原燃さんといえば『赤い砂を蹴る』というのがだいぶ前の芥川賞候補に1回なってるんですね(2020年)石原燃さんっていうのは太宰治の孫なんですね太宰治には娘さんが津島佑子っていうその人もだいぶすごい作家がいるんだけどそれの娘さんが石原燃さんなんです石原燃さんは演劇の方をやってるんだけど小説も発表しているということで今回ももしかしたら2連続で
芥川賞候補になるんではないかと
考えられるということですね25作目25.仙田学
「その子はたち」
文學界9月号仙田学さんっていうのが
早稲田文学新人賞っていうのを
取ってデビューしてて(2003年)単行本としては
『盗まれた遺書』
っていうのが河出書房新社から短編集で出ていて(2014年)それは僕は読みました早稲田文学新人賞を取った
「中国の拷問」っていう作品も
入っていて結構 奇想系なんだよね 変な感じの小説が多いあと1個 ライトノベルで
『ツルツルちゃん』(2013年)
小説を書いていて実はそれも僕は読みました 最近 読んだんですけどそれもオチがとんでもないオチっていうか変な感じがあって とても良かったです今回 これが芥川賞候補とかになると仙田学の名前がドーンと来るわけだから 嬉しい感じですね26作目26.三木三奈
「アイスネルワイゼン」
文學界10月号三木三奈さん そろそろね単行本 1個ぐらい 出してくださいよと文藝春秋さん って思うんだけど三木三奈さんはデビュー作「アキちゃん」っていうので何回か前の文學界新人賞を取ってデビューしそれは速攻で芥川賞の候補になったんですが(2020年)単行本化されてないんですね今回「アイスネルワイゼン」が もし候補になるとしたら「アキちゃん」を足して単行本にしてください「単行本が1冊もない作家」
っていうのが僕にはもう許せないのよ単行本 出しておくれ って本当に思ってますので27作目27.奥野紗世子
「享年十九」
文學界11月号この奥野紗世子さんも単行本が今のところないんですね奥野紗世子さん自体は
何回か前の文學界新人賞を受賞して
デビューしています(2019年)作品もいくつかあるので今回あたりで芥川賞の候補に入ってそして文學界新人賞とセットで単行本化すると綺麗ですよ これ本当に僕は心の底からそれ望んでるんでね文藝春秋さん お願いします28作目28.杉本裕孝
「ジェイミー」
文學界11月号杉本裕孝さんも なぜか知らんが単行本が1個もないですねこの人も だいぶ前の 文學界新人賞を
受賞してデビューしてるんですよ(2015年)結構 実は三島賞だったかな「ピンク」っていう作品が
野間文芸新人賞候補に
入ってるんですよ(2021年)だけど それも単行本化なってないわけ
1冊も今まで単行本になってないわけよ僕 本当に応援してますからねこの辺の単行本1個もない純文学作家応援芸人なんで僕はこの辺り本当に光を当ててほしいと思いますよマジで29作目29.朝比奈秋
「受け手のいない祈り」
文學界12月号林芙美子文学賞っていうのを
受賞してデビューしてるんだけどそれが『私の盲端』という作品ね
(この中の「塩の道」が受賞)次に『植物少女』っていうのが三島由紀夫賞を受賞して単行本があるんですよ次が『あなたの燃える左手で』っていうので
野間文芸新人賞を受賞したんですね今回 もし「受け手のいない祈り」が芥川賞を候補に入り そのまま受賞するとしたら三島賞 野間文芸新人賞を
取っているので
三冠王になるんですよね今ノリに乗ってるから全然これ 候補に入れてくる可能性ありますよ最後 30作目30.加納愛子
「かわいないで」
文學界12月号加納愛子さんっていうのは「Aマッソ」っていう女性2人組のお笑い芸人なんですよねでも最近 文藝にめちゃくちゃ掲載があるんですよ今回 文學界にも掲載されているから
純文学作家と言ってもいいと思うんですねエッセイ集も
いくつか出してるんだけど
僕はそれを読んでなくて小説の短編集『これはちゃうか』っていうのが
河出から出てるんだけど それは僕 読みましたよ芸人さんらしい感じはあっただから今回 この「かわいないで」が
芥川賞の候補に入るじゃないですかそうすると なんと芸人さんで言えば
又吉直樹に次ぐ2人目だと思うんですね受賞とかすると それこそ
めちゃくちゃニュースになると
思うんですけどこの流れをいかに活かせられるか
っていう感じはあるんじゃないですかそんな感じで 今回第170回 芥川賞の候補に入るんではないかなと思われる30作品を見てきましたけど12月14日の午前5時に
今回の芥川賞の候補作が
発表されますいつも通りめちゃくちゃ朝早いので僕は徹夜しますけれどもさらに受賞ですよね受賞作発表が1か月後になるんですけど今回それもわかってて 1月17日に受賞作発表ということで今年もこの季節が参りました僕は候補作全て読んで
また1個1個 動画を
出していこうかと思います頑張っていきたいと思いますので
皆さん どうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#913「14年前、僕がニコ生で読書の楽しみを知った6年間の話」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと先日 ちょこっとだけ言ったんだけど僕のニコニコ生放送の時の話をしようかなと思いますよそこで1人の師匠という人がいて仮にDさんという名前で呼ぼうと思うんですけど僕がニコニコ生放送を始めたのは大学生の時なんで今から14年前ぐらいですよその時 YouTubeっていうものがあまりなくてニコニコ動画が1番強かった時代があったんですよその時に僕は大学生の時なんで筒井康隆とかミステリとかそういうのをばっかり ずっと読んでたんですよその時に僕は本が好きだったから誰かと喋りたいという気持ち あるじゃないですかその時にリアル生活では読書をしてる人と喋れないっていうことでネットの方で探してたんですよねそうするとニコニコ生放送っていうのがあってニコニコ動画は動画の方なんだけどいわゆる今のYouTubeライブ僕が毎週土曜日にやってるYouTubeライブみたいな感じでニコニコ動画でも生放送っていうのがあったんですよそこで結構 探してたんですよね当時もハッシュタグみたいな感じで#読書とか#文学とかで調べてたんですよそうすると その時 DさんっていうこれはイニシャルですけどDさんっていう人が読書系の生放送をやってるってことがわかったんですよ僕はそこに入り浸ることになるんだけどDさんは小説もそうなんだけど哲学書とか編集の技術みたいなを勉強してる人で十何年前に読書のことで生放送とかやってる人って多分いなかったんだよね僕はそれ1年とか2年とかずっと入り浸ってたDさんは別に毎週何曜日とか決めてるわけじゃなかってランダムに生放送しようって思って生放送されてたから僕もずーっとパソコンの前でニコニコ生放送を開いてDさんが生放送したらお知らせが入るように設定して待ってたんですよ ずっと当時 僕は今 結構ペラペラこうやって
なんやかんや喋るじゃないですか僕 その時 大学生の時本当に人見知りで
全然 人と喋れなかったし恥ずかしかったし何もできなかったんですよねだけど それが1〜2年 続いた時に僕も生放送をやってみたいなって思ったんですよ生放送するのはプレミアに入る必要があってニコニコ動画のプレミアは月500円で入れるんだけど 当時はそれで入って 生放送をやってましたね1〜2年 Dさんところに入ってたから実はDさん界隈みたいなのがあってDさんのことが好きな人っていうのが
何人もいたんです 僕みたいなその人たちも同じ界隈だったから僕のところにも来てくださってたんですよねそれでちっちゃいちっちゃいコミュニティで僕も生放送のことをやってました僕は当時 今もニコニコ動画の僕のページがあって消してないんだけどニコニコ生放送っていうのは生放送なんで記録(アーカイブ)が残らないんですよねだから中身は全く見れないんだけどタイトルとかは全部 残ってて僕が何を話したかみたいな大雑把な概要みたいなが ちょこっとわかるんですよ 今でもだいたい僕は1回30分みたいなで
ほぼ毎日ニコニコ生放送やってたんですよつまり夜の11時〜11時半の時間に毎日ですよ ほぼその時間に 読書について あるテーマを決めてある本について喋る っていうのをずっとやってたんですよねそれ 6年間ぐらい続きましたよもちろん僕も大学を卒業して大学院に入ってぐらいの時 ちょっと忙しくなったりとかその後 仕事するからその辺になると自然になくなっちゃったっていうか引っ越しとかもあって 生放送できない環境になっちゃって自然消滅しちゃったんですよねだけど その経験を生かしてそこから何年も経ってYouTubeを始めることになるからだから僕はDさんに出会ってなかったら
今YouTubeやってないしここまで本当に読書に
ドハマりしてるってことはないと思うだから本当に僕はDさんに感謝してるところはありますよ僕の読書を支えてくれたんだなって今思ったら本当に思いますよだからニコニコ生放送の時に思い出がたくさんありますよ1回オフ会を開いたりとかニコニコ生放送の時にめっちゃ海外文学が好きだった人がいてパスカル・キニャールとか莫言とか そういう現代作家ですよそういうのがめっちゃ好きな人がいてそういう人が生放送することになってその人は夫婦でやってた っていう稀有な人だったんですよ夫婦で読書系の生放送をやるっていうRさんって言ってもいいんだけどその人のところにも 僕 よく行っててその人からめちゃくちゃ現代の海外文学を教わりましたよその人から1回 本が送られてきたこともありますよSkypeだったかな 住所を交換してプレゼントを送り合うみたいなで 本とあとメッセージカードみたいのが その人の荷物の中に入ってて今 そのメッセージカードは壁に飾っていますそこには「つかっちゃん
作家デビューしたらソープに連れてってね」
っていうコメントがあるんですよねいやあんた結婚してるんでしょ みたいなあるんだけどそういうのずっと飾ってます 僕の思い出だよねこの人形あるじゃないですか僕がこれ「白ピカくん」って名付けてるんだけどこれはなんとその十何年前のニコニコ生放送の時から使ってますよだからこれYouTubeからじゃなくて僕 十年来の友達みたいなもんで僕がニコニコ生放送やってた時は
顔出ししてなかったんですよね顔出しせずに机にWebカメラみたいなつけてこれを映してたんですよこれの横に本を映して「今日はこの本について語ります」みたいなことで僕は30分やってたんだけどだからこの人形はめちゃくちゃ思い入れがあるんですよねDさんは癒し系みたいな人だったんだよねDさんは感情的にあまりならない人で怒りとか悲しみ みたいなよりかは読書の楽しみみたいのをずっとアピールしてたんですよ自分はこういうことがやりたいんだとか言ってその人 僕より年上だったけどある学校に途中で入るようになって勉強とかめちゃくちゃしてる人だったんですよねでも嫌味じゃなかったのよよくよくあるんだけど 勉強が大事だとか学びは大切だとか言ってよくYouTubeとかでも これだけ成功しましたとか成功するにはこうだみたいな
そういうビジネス系みたいな人
だっているんだけどDさんは独特の雰囲気があって
そういうのじゃなかったのよ僕はどちらかと言うと陰キャだったからなんか惹かれ合うものがあったんだと思うんだよねだから それで 僕はDさん界隈というかニコニコ生放送でずっと活動してたんだけどそれが全部 今のYouTubeの方に繋がってるんだな っていうのはよくよく思いますよニコニコ生放送の経験は僕の人生の中でかなり重きを占めてるっていう感じはしますねこれ 最後に言いますけど僕のこのYouTubeのチャンネルも言ってしまえば
そういうことをしたいのかな
っていうのは最近 思うわつまり僕がDさんのことが好きっていうかよくよく行ってて 色んなことを学んだように僕もそういう場所を作りたいなって思いますよ今 読書系のYouTuberとかSNSとか そういうのあると思うんですけどそういう場があると読書は進んでいくからこのつかつの このチャンネルもその1つの場として運用していきたいという気持ちはありますよニコニコ生放送のDさんのようにいわゆる師匠のように 僕は弟子ですから弟子が師匠のようになりたいなと思ってそういうことを考えて やりたいなというのはありますね結構まだまだ ニコ生のことについて話せるんだけど今回はここで終わろうかと思いますよ高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#912「最近のつかつについて」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと最近のつかつについて
ということなんですけど12月に入りまして 今年は残り1ヶ月ということですよ皆さん どうお過ごしになっておりますか僕は最近 ちょっと風邪気味でしてね咳がずっと出てて 1ヶ月ぐらい咳が続いてるんだよねだからちょっと体調 良くないんですよね12月に入ったでしょう来年の2024年の12月1日に僕が出したいと前から言ってる 文学フリマ東京があるわけですよだからちょうど1年後になるんですね1年を切ったわけなんですけど今はそれのことばっかり考えてるね同人誌の原稿を早く完成させたいなあとか残り読む本も数えたりしてて1080冊 紹介するって言ってるんだけど今 816冊まで読んだんですよ1080から816を引くと残りの数が出るんだけどでもちょっと考えたら僕 芥川賞・直木賞の候補作をずっと読んでるんですよまた近く芥川賞もあるわけですね12月の中旬ぐらいに次回の芥川賞と直木賞の候補作が発表されてだいたい1ヶ月後なんで 1月の中旬ぐらいに受賞作発表と僕 これ 4年間やってるんですよ僕 YouTubeを始めたのが2019年9月からなんで2019年の冬の芥川賞・直木賞からやってるんですよちょうどで4年目ということで8回目になるんですね 今度のでその時に だいたい芥川賞って雑誌掲載のものじゃないと候補にならないんですね直木賞は単行本化されたものが候補になるんでそれを読めばいいんですけど芥川賞っていうのは純文学の5大誌っていうのがあって新潮・群像・文學界・すばる・文藝というのがあるんですよ基本的にはこの5つの雑誌に掲載されたものの中から芥川賞の候補は選ばれますだから僕は芥川賞の候補が発表された時に候補が掲載している雑誌を入手してそれを読んで「読みました」っていうことにしてるんですよつまり雑誌掲載の その中篇を読んでも僕の読んだ1冊に入れてたんですねそれは別にいいと思うんだけどだけど後に その小説が単行本化された時にそれも絶対に僕は読むようにしてるんですね単行本化された際に加筆修正されたりとかもしくは過去の作品プラス1個とか付け加わって単行本化されたりするんで 別物なんですよねだから僕は その単行本した本も読むんですよそしたらそれも 1冊に加えてたんですよねそうなると 同じ作品なのに2冊にカウントされてることになるじゃないですかだからそれでちょっと直すかと思って話 飛んじゃうんだけど先日 ちょっとした知り合いと会ってファミレスあたりで飯を食いながら色々喋ってたんですねその時に これですよ今 作ってる途中の この同人誌をそいつに見せたんですねこれを実際に人に見せるのは初めてだったんですよこうやって動画でパラパラめくっていくつか見せてることはあったとしても実際に他人に「これをちょっと見てよ」って言って見てもらうことは初めてだったので僕も緊張したんですけどまあこれ自身は まだまだ6割ぐらいの途中のアレなんですけどその時にいくつか指摘があってさっき言った雑誌掲載時と単行本化された状態が2つ載ってるけどどうするのって言われてああ そうなんだよなって思ったの僕は本来 直すつもりはなかったんだけどタイトルが「1000冊」って書いてるから
カブリはちょっと直すかって…僕はさっき言ったように 4年間
芥川賞の候補作をずっと読んできたから雑誌掲載の時の作品と単行本化された時の作品がかぶっているやつを数えてみたんですよねそうすると14あることが発覚して14ってことは これを直すには新たに14冊違うものを読まなきゃいけないと
いうことになったわけですねつまり816冊 今のところ読んだんだけどプラス14を足さなきゃいけないんですよ1080から816を引くと264になるんだってその264に14を足さなきゃいけないんで278冊 残り読まなきゃいけないということですよちょうど1年なわけですねその残り1年のうちに 僕は
残り278冊 読むつもりなんですけどここ最近はそれのことをずっと考えてたっていうのが1つかなあと動画も最近 あまり全然出せてなくて週に2本ぐらいしか動画を出してないのがちょっと気がかりで12月中旬から さっき言った芥川賞・直木賞の候補発表があるから1月中旬まではずっと多分それが動画になると思うんですよ年末年始を挟むんで2023年のつかつのやったこととか2024年の抱負とかそういうのを出したいとは思ってるんだけどまあしかし もう冬で寒いでしょう僕 毎年なんだけど 冬って本当に調子悪くなるんですよ全体的に鬱っぽくなって しんどくなっちゃうんだよねだから今回もちょっとそれ来てるんだよね動画ね もっともっと頑張りたいと思っています動画も例えばですよ僕の目標としては
来年(の12月)までに
動画1000本を投稿したいとか登録者数1万人まで
行きたいとかあるんですよねそうするとちょうど 文学フリマの時までにそういうことを言えると面白いじゃないですか 面白いというか僕はやっぱり 本が好きなんですよねまあ 結構 知り合いが言うには例えば つかつは小説を書いた方がいいよとか違う知り合いが言うにはつかつは自分の小説を 昔 書いてたけど何回か応募したけど ダメだったから違う人の小説を紹介することで自分を売り込もうとしてるんじゃないかみたいなことを言う人もいたんだけど僕は でも小説を書く前から小説を紹介するっていう活動はやってましたから僕は10年以上前にニコニコ生放送っていうのを ずっとやっててそこでも本を紹介するような活動をしていましたからそれの延長線がYouTubeだということでそこで1人の「師匠」と呼んでる人がいてそれは今度 また違う動画を出そうと思うんだけどその人と出会って色々教わったりとかしてそこから10年経ってこうやってYouTubeで活動しているっていうのは面白いなと思いますよ 本当に僕の作りたい同人誌 早く完成したいと思ってる同人誌はこれが僕のこの10年間の活動の集大成みたいな感じだと僕の中では思っているんですよねだからこれ どんどん形になっていってるわけですよこうやって途中だけど 本の形にしたりとか今 まえがき とか あとがきとか途中のコラムとかも書いたりとかどんどん本を読んでいって その分
ページ数を増やしてたりとかしてるんだけどもう今はそういうことしか考えられないねまあ でもこれは
本を読んでいかなきゃいけないんでその中で この本 良かったよとかいう動画をまたどんどん出せていったらいいな
っていう気持ちは今ありますねまた動画に力を入れようと思いますたくさんたくさん 動画も出したいし動画でしかできないことだってありますからそういうことをちょっとやっていこうかなと今思ったりしますねはい そんな感じかな今回 まとまりのない動画でしたけれどもこういうことをつかつは今 考えてるっていうことがわかっていただければいいかなっていう感じではありますねはい そんな感じでございます皆さん 何でもいいんでぜひコメントを書いてもらえたらと思いますよそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#911「僕が読んで良かった歌集ベスト5を発表します」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと僕が最近読んだ歌集5選最近 僕は
前から現代詩は
読んでたんですけど最近 歌集を読み始めるようになりました短歌はあんまり
わかんなかったんだよねだけど どちらかというと世間的には
現代詩より短歌の方が流行ってると文学フリマとかでも 歌集って
結構 人気あるらしいんですけど最近になって
歌集を読み始めて5冊読むことができましたねめっちゃ面白いなって
最近 思えるようになりましたねさっそく紹介
していきましょう1冊目①くろだたけし『踊れ始祖鳥』
ナナロク社 2023年この本自体は
「第2回ナナロク社あたらしい歌集選考会選出作品」
らしいんですね僕はツイッターに
読了ツイートってやってるんだけど僕の読了ツイートでは僕が気に入った
好きだった
印象的だった3首を記録として
書くようにしてるんですよねそれを読んでいこうと思うんですけど1つ目「日常に刺激を求めなくなると冷蔵庫からポン酢が消える」2つ目「僕たちがわかりあえたということは
どのようにしてわかりあえるの」3つ目「ひき肉を牛になるまで巻き戻す科学はなくて今日も戦争」全体的に見ると諦めとユーモアみたいな感じなのかなと思いましたどちらかというとシュール系の短歌だと思うんですよちょっと斜めから見てそれをユーモアと諦めてる感じをうまく出してんだなっていう歌だったと思うんですよね歌集はこれまであまり読んでこなかったけどこれ読んで 読めてよかったなと思いました2冊目②川野芽生『Lilith』
書肆侃侃房 2020年川野芽生さんっていうのはこの後に実は 小説をたくさん書かれていてどちらかというと幻想文学の作家に今なってますよね元々は実は歌人でしてこの『Lilith』は「歌壇賞」っていうのと「現代歌人協会賞」っていうのを2つ受賞してるみたい「歌壇賞」は確か応募するタイプでこの「現代歌人協会賞」っていうのがこの後にもたくさん出てくるんだけど短歌の中で1番名誉がある賞らしいんですねこの『Lilith』も僕の印象的だった
3首を紹介しようかと思うんですけど1つ目「剥き終へて魚卵のごときピオーネを
王女のきみにひとつ差し出す」2つ目「炭酸水うつくし 魚やわたくしが
棲むまでもなく泡を吐きゐる」3つ目「こころとは巻貝が身に溜めてゆく砂
いかにして海にかへさむ」さっきのと比べるとかなり
耽美の方に寄ってるんだよねどちらかというと僕は昔から耽美なものが好きですから耽美系の短歌を読んでいきたいなとは思ってるんだよね3冊目③俵万智『サラダ記念日』
河出書房新社 1987年これは言わずもがな サラダ記念日ですけどこの『サラダ記念日』は実はですねこれさっき言った「現代歌人協会賞」
っていうのを受賞してるらしいんですよ僕が印象的だった3つを言うと「また電話しろよと言って受話器置く
君に今すぐ電話をしたい」2つ目「君の香の残るジャケットそっと着て
ジェームス・ディーンのポーズしてみる」3つ目「思い出はミックスベジタブルのよう
けれど解凍してはいけない」基本的には恋の話が多いんですよねプラス故郷に帰ったり家族と会ったりあと中国に旅行に行ったりとかあと学校の先生やってたらしいんですね俵万智はその学校の話とか結構 実は恋だけじゃなくて
幅広く題材があるんですけど実にいいですね4冊目④鳥居『キリンの子』
KADOKAWA 2016年この『キリンの子』も現代歌人協会賞を
受賞している歌集なんですけどこの鳥居さんっていうのが元々お母さんが自死してしまうんですねそこから児童養護施設で預けられるんですけどそこで虐待を受けるんですよねそこから学校はもちろん行ってたんだけど不登校になっちゃって漢字とかも全然 読めなかったらしいんですよ1回ホームレスか何かになってその辺の新聞とかを読んで
図書館とかに行って勉強して字を読めるようになった
っていう人らしいんですよねその人が自己流で短歌をめちゃくちゃ書いてたらこういう本になって すごい賞も取られたっていう話印象的な3つの歌を詠むと「強すぎる薬で狂う頭持ち上げて前視る授業を受ける」2つ目「児童相談所で食べし赤飯を最後に止まった我の月経」3つ目「友達の破片が線路に落ちていて私とおなじ紺の制服」短歌って結構ストーリー性がある時 あるんだなと思って『キリンの子』に関しては情景情景でどんどん歌っていくんだけど第1章 第2章みたいな感じで◯◯篇◯◯篇みたいなあるのよ途中で友達が踏切の中に入って電車に轢かれてバラバラになる
っていうのを実際にこれ見てるらしいんですよそれを歌ってる歌のパートがあるんですよそれがこの
「友達の破片が線路に落ちていて〜」
みたいな話なんだよねすごいと思うそういうのも歌になるんだね歌って何でもありなんだと僕はこれ読んでて思いました最後 5冊目⑤吉田隼人
『忘却のための試論』
書肆侃侃房 2015年この本も現代歌人協会賞を受賞していますこれ中にも書かれてるんだけど 表紙はこれすごい表紙なんだよね「長岡建蔵」っていう人のイラストらしくて「さよならを教えて」を作った人なんですよ「さよならを教えて」っていう
かつて出てた電波ゲームがあって結構 有名な電波ゲームで三大電波ゲーの1つと言われたりするんだけどその表紙を描いてる長岡建蔵っていう結構なんかすごい絵を描く人がいるんですよそれの「内省天使」っていう絵を
使わせてもらってるらしいんですねこれ読んでみました僕の好きな3つの歌を詠むと「冥福の冥とはいづこ葉あぢさい
月のうらがは愛のうらがは」2つ目「交接ののちこひびとを愛づるごと
闇あをき夜の虚無を抱き締む」3つ目「うすき胸 なほうすき呼気 自慰のとき
にんげんでなくなることがある」これも『Lilith』のように耽美系だとは思うんですこの本自体 結構いろんな歌が入っててこれも多分 友達が死んだみたいなテーマもあるし中に ある女子高生だったかな がある人を殺したっていう実際の事件があるらしいんですよその子はブログかなんか書いててそれが全部ブログで見ることができてそれにインスピレーションを受けた
短歌も書かれてるらしいですよそんな短歌もあるんだと思ったんだけど
結構 面白い とてもこれそんな感じで今回
歌集を5選
選んだわけだけどこれからもどんどん
短歌を読んでいきたいと
思っています今年やっぱり新しい試みとしては
現代詩と短歌っていうのを始めましたこれ良かったと思うね僕も幅広く そういうのを
読んでいきたいなと思っていますからもし良ければ 皆さんの好きな
短歌・歌集・歌人がありましたらコメントの方に書いていただけたらと思いますそんな感じで 今回は
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#910「【購入】ヤバ目な小説とヤバ目のマンガ16冊を買ってきました!」
購入本紹介動画のため、購入本を羅列します。
01.堀江敏幸『その姿の消し方』
02.日日日『のばらセックス』
03.村上隆『芸術闘争論』
04.福井県立図書館『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』
05.やまじえびね『女の子がいる場所は』
06.山川直人『澄江堂主人』前篇
07.カネコアツシ『EVOL』1〜2巻
08.大橋裕之『太郎は水になりたかった』2巻
09.知るかバカうどん『君に愛されて痛かった』6巻
10.ありま猛『連ちゃんパパ』1〜4巻
11.タイザン5『タコピーの原罪』上下巻
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#909「【コラボ】Kさん・カワシさんと「純文学のベスト9」のチーム打線を組んでみた!」
はーい こんにちは つかつですということで 今日もやっていきましょう
今回は なんと「コラボ動画」ということでして、伝説のお二方が来てくれております
ちょっとした自己紹介してもらおうかと思いますのでよろしくお願いします
今回はコラボしていただき ありがとうございます「Kくんの純文学読書会」というチャンネルを普段やっているKとカワシです
普段は小説家志望のKと純文学初心者のカワシが読んだ本について気ままに語り合う純文学の読書会を中心に動画を作っています元々つかつさんの動画のファンでそれもあってチャンネルを始めたので今回つかつさんとこうやってコラボさせていただけるのは すごい夢みたいな話でとても嬉しいです よろしくお願いします「Kくんの純文学読書会」のカワシです純文学初心者ですけど 今日はつかつさんとお話できるということですごい楽しみにしてました よろしくお願いしますそんな感じで 今回ねKさんとカワシさん 来てもらっているんだけど何するかというと純文学小説で打線を組んでみた!この3人がそれぞれ 自分の好きな小説で打線ですよ 野球の打線をいわゆる9人を選んできてチームとして設定したんでそれを1人ずつ発表しよう っていう企画でございますまずカワシさんから打線を発表してもらおうかなと思っておりますよろしくお願いしますカワシ9を発表します1番 センター1.日比野コレコ
『ビューティフルからビューティフルへ』2番 二塁2.高瀬隼子
『おいしいごはんが食べられますように』3番 三塁3.乗代雄介『それは誠』4番4.村上春樹 訳 J.D.サリンジャー
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』キャッチャー5番 ショート5.カズオ・イシグロ『日の名残り』6番 レフト6.小川洋子『ミーナの行進』7番 一塁7.市川沙央『ハンチバック』8番 ライト8.小砂川チト『家庭用安心坑夫』最後 9番 ピッチャー9.年森瑛『N/A』以上 9名になりましたどうして そういうメンバーにしたのか とかお気に入りの選手とかを言ってもらうかなと思います打線を組む時にですね打線の組み方みたいなのを調べてみたんですよそしたら1番打者は出塁率が大事と 走力が高い方がいいとということで 速そうな日比野コレコさん筆が速そうってことねあとですねこの4番5番の助っ人外国人なんですけど5番が大事みたいで なんでかっていうと4番が1番 良いバッターなんだけど4番で勝負をせざるを得ないだけの威圧感が5番にないとダメらしいだから 5番にカズオ・イシグロいるよ村上春樹 訳 のJ.D.サリンジャーでも
勝負しないと っていうこの4番5番あと『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を
キャッチャーにしたかった他の選手はどうですか好きな作家さんばっかりなんで8番は
意外性があるバッターがいい
みたいなの聞いてパッと思いついたのが
『家庭用安心坑夫』なんですよね予想外のところでホームランを打てるような
バッターが8番に来るといいなみたいなピッチャーを『N/A』にしたのは
何か理由あるんですか?DH(指名打者)と迷ったんですよでも年森瑛さんには期待というか
推したいというか 期待してて9番だけにするのは
ちょっと忍びないなあと思って9番だけどピッチャーですよ
立たせたかった 推したかった9番ライトとかだと
かわいそうな気がした1番好きな選手は誰ですか1番好きな選手は6番 小川洋子さんですね4番にしようとも思ったんですけど6番の役割としては走攻守 走る攻める守るが
揃ってる選手らしいんですよ僕の中で 揃ってるっていうか勝負強さもあるし 長打力もあるし守備も攻撃もできる
強いプレイヤーといったら小川洋子しかないだろうと『ミーナの行進』はどんな話なんですか?『ミーナの行進』は主人公がいとこのミーナちゃんっていう子のところにひと夏 過ごしに行くお話ですごいお金持ちなんですよ ミーナちゃんのお家はすごいお金持ちなんで主人公が色んな刺激を受けながら普段できない色んな経験をしていく話で小川洋子さんの話って結構死人が出るんですけど『ミーナの行進』は出なくて穏やかな休日にのんびりと読んで気分が良くなるような小説ですねどうですか つかつさんはこの9を見て新人とベテランが混ざっているのが面白いなとカズオ・イシグロはノーベル賞を取ってるからメジャーに行ってた選手3番の乗代雄介さんは打順の3番は万能じゃないと
務まらないみたいなんですよ万能って誰かなと思って万能… うーん乗代雄介さんかなみたいなすごい万能そうなオーラをすごい感じてこの人 多分 何でも
書けるんだろうな みたいな3割打ち ホームランも
30本くらい打ち
盗塁もするみたいな次に春樹とカズオに
繋がるわけですまあ怖い打戦ですよ
ぜひこの打線に挑戦してみてください僕らに言ってるの?これはぜひ読んでいただいて打線を味わっていただけたらと思いますありがとうございました続きまして次 Kさん 打線を発表
してもらおうかと思いますじゃあ発表していきます私 Kが考えたチームですね1番 センター1.『乳と卵』川上未映子2番 セカンド2.『この人の閾』保坂和志3番 サード3.『コインロッカー・ベイビーズ』村上龍4番 ライト4.『限りなく透明に近いブルー』村上龍5番 ファースト5.『歌うクジラ』村上龍6番 ショート6.『かかとを失くして』多和田葉子7番 キャッチャー7.『タイムスリップ・コンビナート』笙野頼子8番 DH8.『告白』町田康9番 レフト9.『あの子の考えることは変』本谷有希子そしてピッチャー『殺人出産』村田沙耶香以上が私の考えたチームになりますDH制を導入してるんですねじゃあ そのチームにしたきっかけとかどういう感じなのかをザクッと教えてもらおうかなと思います僕は強いチームを作ろうと思って1番『乳と卵』これはやっぱり
1番バッターってカリスマっぽいイメージが
イチローのせいなのか
そういう感じがするんでこれは川上未映子さんだろうと2番は保坂和志さん2番バッターは地味なんだけどめっちゃいい仕事するみたいなこれはあるんじゃないかなと思ってクリーンナップ 申し訳ないんですけど村上龍さんが大好きなんでクリーンナップは村上龍さんにさせていただきました3番は泣く子も黙る
『コインロッカー・ベイビーズ』ということでバッティングのエースみたいな感じで4番はやっぱりこれ外せないんで『限りなく透明に近いブルー』はもう絶対これもう1番最初に決まりましたね 打線組む時「文学の4番」みたいな感じあるもんね5番が『歌うクジラ』ちょっと電子書籍なんで持ってこれなかったの 残念なんですけど1発を期待できる5番バッターさっきカワシが威圧感とか言ってたけどその威圧感ある感じで『歌うクジラ』にしました6番は『かかとを失くして』才能ある感じ多和田葉子さんのデビュー作なんですよね今やノーベル賞候補とかって言われてますけどドイツのリーグで頑張ってるってことですね7番も大好きな笙野頼子さんの芥川賞受賞作『タイムスリップ・コンビナート』ですね知性派のような印象があるんで キャッチャーにしましたね8番はちょっと1発を期待して下位打線なんだけど 1発あるぞっていう傑作長編『告白』持ってきました熊太郎っていう人物の実際にあった大量殺人事件河内10人斬りをモチーフに書かれた小説それでバッティングの最後がちょっと変わり種で 本谷有希子
『あの子の考えることは変』シスターフッド小説みたいな感じ23歳の女性2人が互いにコンプレックスがあるんですけど同居してて その生活を描いてるんですけどもうめちゃくちゃ面白くて 一気読みですね薄いし 初心者の方とかもおすすめですピッチャーですね『殺人出産』これめちゃめちゃ強そうですよねもうバッタバッタと相手を三振に打ち取っていただきたいと投げる専門で行っていただきたいと思いました1番好きな選手はやっぱり村上龍ですかこのクリーンナップを形成している村上龍さんも1番なんですけどうちのチームの売り的なところで言うと『タイムスリップ・コンビナート』は
一押しかなと思いますねこれはちょっとシュールな話である日 電話がかかってきてその電話の相手も よくわかんないんですけど「海芝浦に行ってください」とかって言われるんですよ実際にそういう駅があるんですよねそこは片側が海になってて どん詰まりなんですよねじゃあ何があるかっていうと東芝の会社があって東芝の会社員の人がそこに行くっていうそれだけの駅でそういうちょっと変わった駅なんですけどそこにお家から行くっていう そういう話なんですね僕も実際 どんな駅なんだろうって
これ読んだら気になるんでもう行ってみたんです これ持って鶴見駅から乗り換えていくんですけどちょっと巡礼も楽しめる芥川賞受賞作なので非常に一押しの作品でございます『歌うクジラ』なんで電子書籍かっていうと坂本龍一さんとコラボしてて音楽がちょっと流れるっていうやつだったんですよあー これはじゃあ
電子書籍で読んでみようかな
と思って読んだんですけど音楽はそんなに入ってなくて同じ曲がちょこちょこ時々入ってくる感じだったんでうんって感じでしたけど電子書籍 当時そんなに流行ってなかったんでほんと始まった頃だったんで 新鮮でしたここにあげた本は全部オススメ 超オススメなんで未読のものありましたら ぜひ読んでみてくださいじゃあ 続きまして僕 つかつの打線 発表しようかと思います1番1.町田康『きれぎれ』(2000)2番2.吉村萬壱『ハリガネムシ』(2003)3番3.阿部和重『グランド・フィナーレ』(2004)4番4.磯崎憲一郎『終の住処』(2009)5番5.赤染晶子『乙女の密告』(2010)6番6.鹿島田真希『冥土めぐり』(2012)7番7.滝口悠生『死んでいない者』(2015)8番8.上田岳弘『ニムロッド』(2018)最後 9番9.古川真人『背高泡立草』(2019)以上 この9人が僕のつかつ9になっておりますねこの作品の後に番号ついてると思うんですけどこれは背番号ですね監督も決めてるんですね監督は菊池寛監督なんですね2000年代〜2010年代の芥川賞ですねこの中からベスト9位を決めてるわけですねこの背番号はその年に受賞した作品だとなんと 補欠ももちろんいるから全部のベンチメンバーとか入れると47人いるんですねこれは2000年代と2010年代の
全ての芥川賞作品が
47作あるということですよ意外と2000年代〜2010年代の芥川賞って結構ね名作が多くて 名選手と言ってもいいんだけどこの中で僕が超オススメするとすれば『乙女の密告』かな京都の外国語大学が舞台でそこで『アンネの日記』をドイツ語で勉強しようっていうゼミがあるわけ主人公たちは色んな女の人がいてそこで女子の諍いみたいなのが起こってきてアンネ・フランクは密告されて
収容所に送られて死んでるのよねその中で女子の集団があるから(ゼミ内で)「あいつは実は…」とか言って
密告しあったりとかする
っていう話なんだよかなり完成度が高いっていうか超面白いキャプテンは磯崎さんですか
赤染さんですかキャプテンは僕 阿部和重かなって思う阿部和重はヤバい小説多くてこの『グランド・フィナーレ』の話なんか ロリコンの話で阿部和重って90年代終わりぐらいにデビューしてて90年代後半ぐらいから日本文学ってめっちゃバグりだしてくるのよだからさっきの 笙野頼子
『タイムスリップ・コンビナート』とか保坂和志とか多和田葉子とかは80年代後半とかにデビューして90年代ぐらいに芥川賞を取ってるんだけどその先のメンバーがこれに繋がってくるこの辺ぐらいから文学の中にそういうポップとか変なテーマみたいなのが出てき始めてめっちゃ面白くなってくるんだよね吉村萬壱『ハリガネムシ』も
暴力描写みたいなのがめちゃくちゃあってそれでよく芥川賞を取ったなあっていう内容2000年代から2010年代になるとちょっと洗練されてくると思うめちゃくちゃクールな感じの小説が多くなってくるのよ 『ハンチバック』もエグいっていうかパンチ効いてたじゃないですかと比べると2000年代のエグさっていうのはちょっと違う種類のエグみっていう感じなんですかね2020年代 過ぎて
また変化があるみたいな
ものって感じますか?2020年代は 基本的には震災から10年とかコロナとか「障害者」が『ハンチバック』のテーマとすればコンプライアンスっていうか多様性とか ポリコレとかそういうのが2020年代のテーマとしては特徴的だと思う意外と『ハンチバック』はすごい衝撃的だけど2000年代の方がすごいよ『ハンチバック』よりすごい
作品なんか山ほどあるよ 2000年代今むしろ落ち着いてきた方だと思うけどオカルトブームとか90年代終わりって世紀末になってくるからそれをメタ化すると2000年代ぐらいに来るんで2000年代って精神的なヤバいドローっとした作品とかだって『蛇にピアス』『蹴りたい背中』も
2003年だったと思うんだけどだから芥川賞は今から遡って2000年ぐらいまでの
全部 読んでほしいと思うけどもしピッチャーを選ぶとしたら誰ですか?ピッチャーは
鹿島田真希
『冥土めぐり』かな鹿島田真希 自体がかなり変化球なのよキレがとてもすごい鹿島田真希も前衛小説みたいな感じなのよデビューのやつなんか
もうわけわからへんもん本当に文藝賞で『二匹』っていう
伝説の小説があるんだけれどもう見たことない文学だと思うそんな感じで僕が このベスト9 発表したわけなんだけどこのベスト9だったらもうアレのアレとかも目指せるかなとそんな感じで今回この3人の打線を見てきましたけど皆さんはどの打線がいいですか? 好きですか?ぜひコメントに書いてみてもらったらと思いますね今回はKさんとカワシさんと
コラボさせていただきましたけど今回 Kさんからすごい
お知らせが1つありますのでKさんお願いします今回コラボさせていただいて なんと私たちのチャンネルの方にも
つかつさんに出演していただいていますぜひそちらもご視聴ください
よろしくお願いしますつかつさん ありがとうございました実りがあった もう読みたい本のリストが
積ん読どころじゃないですね読みたい本がいっぱいです
ありがとうございました今回のチームも こうやって出してみたらやっぱりつかつさんの
チームには敵わないなと
そういうふうに思いましたこれからも自分でも頑張って強いチーム作れるようにもっとどんどん色々読んでみたいと思います
ありがとうございました今回 お二方とコラボして
僕もとても楽しかったですまたコラボいつかさせてもらおうかなと思いますので
お二方 ありがとうございましたそんな感じで 今回
終わろうかと思います高評価・コメント・チャンネル登録どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#908「否定する読書/否定しない読書」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと僕の本の読み方の「1つの哲学」
を話そうかと思うんですよ僕は色々 本を読んだりするの好きなんですけど読み方として
1つ決めてることが
あるんですよねそれは「絶対に否定しないこと」ってことですねつまり「これ面白くないよ」とか「この作者ダメだよ」とか「このストーリー浅いよ」とかそういう否定語から始まる感想は基本的には持たないということですねということは 逆に言えば絶対に僕は褒めたいんですよね意外と 人って貶すより褒める方の方が難しいですよ貶すことなんか簡単だと思うエネルギー 多分 使わないですよだって「自分にそれ合わなかった」
とかいうことだって言えるし「◯◯と比べて駄目だった」とか結構 否定する言葉って多い と思うんですよ僕の中で「否定すること」と「肯定すること」ってそれぞれのその先の 向かう方向が本当に真逆で「肯定する方」で考えるとその人は何が書きたかったんだろうとかこの登場人物の心はこうで
この後 こう来るのは
確かにこうでわかるなあとか共感みたいなところと
くっついてくるじゃないですかもしくは物語を「深読み」
していけるわけですよだけど「否定する方」っていうのは
こっちが拒絶してるわけだから考えないわけですよねもちろん否定する言葉は
どんどん論理的にくっつくだろうけどそれって でもさ結局それが駄目だっていうことを
論理的に言いたいわけだから自分とその本に
関わりはないことに
なっちゃうでしょなっちゃうっていうか否定する時の感覚って
自分に酔ってるっていうか自分の方を持ち上げて
他を下げてることが
多いと思うんですよねこれ つまりエゴっていうか
悪いプライドの方に関わってくるから何か 本を読んだ時に「面白くなかったな」って言った時にその無意識の中で「いや俺の方がもっと面白いの書けるぜ」とか「こんな低俗なものを
読むのは子供だよ
俺は読まないけどね」みたいなことが隠れてる可能性は絶対あるから読書って もしくは執筆も同じだと思うけど「自分の無意識との戦い」だと思うんですよ無意識をいかに意識化していくことでもっとフラットなつまり
自分のコンプレックスとか
ぐちゃぐちゃなものが出て来ずにフラットに色んなものを楽しめる
ってことをできると思うんですよくよくあるんだけどとある人が ブログみたいのを書いててその人はもう何十年も小説を
書き続けて 応募しているとしかし1次選考も通りませんなんでなんだ って言った時に俺の小説はめちゃくちゃ面白くて素晴らしいし文学的に価値があるのになぜ認めないんだ っていったらその文学賞が駄目だからだと不公平だからだとコネとかで受賞者を決めているからだ って論理になって「現代の文学は腐っている!」みたいな言い方を
する人って まあいるよ
結構いるんだけどそれになっちゃうと
自分の成長じゃないからね人を否定するっていうことは
自分は変わらないわけよ相手を肯定することが実は自分を高めることだと
僕は思っていますよく「他者」っていう言葉がありますけど「他者」っていうのは 基本的には 相容れない人コミュニケーションもできなくて全くわからない他人のことを鉤括弧つきの「他者」と
よく言ったりするんだけどその人と接触して
コミュニケーション
することっていうのはとても疲れることなんだよねだけど その疲れることっていうか自分を相手にくっつけて相手を中心に自分を動かしていく人でも本でも そうだけどどんなものが来ても 相手に焦点を合わせて相手の方にパッと行けるとそれって自分が動いてるので自分が今まで持っていなかった感覚とか概念とかそういうのを めっちゃくちゃ考えながら身につけさせることができる と僕は思うわけ僕は「自分」っていうものを切り捨ててるから滅私っていうのかな自分ってものがあるから 否定してしまってるわけでしょこれは面白くない
あれは面白くない というのは
自分があるからなんだよねそれすらなくすれば
全ての本も楽しめると
思いませんか我々はなぜ 全ての本を楽しめないのか?小説を片っ端から どんなジャンルの本でもエンタメとか純文学とかラノベとか何だってあるけどそれを全て楽しめないこと
ってあると思うんですよそれはもちろん
自分の趣味趣向の問題で究極的に言えば 好き嫌いの問題なんですよでも好き嫌いだけで 読書するっていうのは僕は 特に僕は
読書っていうのは
修行だと思ってるからいかに自分っていうのを
なくしていって相手を褒めていくか相手の素晴らしさを引き出していくかこれに僕は命を賭けてる
って言ってもいいかなすぐに人を否定する人って
無意識なんですよ否定してるって意識してないのよ
だって無意識なんだもんうちのオトンとかもそうなんだけど自分はめちゃくちゃ人を否定しててあれはダメだこれはダメだって言ってるんだけど自分がいざ
誰かからお前ダメだよって否定された時
めっちゃキレたりするんですよねそこって 何でかって言うと否定する時は わざと否定してないから勝手に 自分の防御反応みたいので
無意識で人を否定してるんですよだから気づいてないんですよだから「あなた人を否定してたでしょ」って言われても「いや俺してない」って言うんですよなんだけどそこは無意識っていうことは
コンプレックスなので 1つだから 人から否定された時に
めっちゃ敏感なんですよ その人はつまり何か
本を否定すること
っていうのは自分の防御反応の可能性が
ありえるということは言えるんですね無意識で否定していないか っていう自分を常に僕は顧みて自分の一言一句とか言動とかを客観視して 読書を
僕は心がけているつもりですだから僕の動画とかtwitterとかでも基本的にはほとんど9割9分は否定してないと思います人を否定するっていうのは 自分の弱さだと思う自分の弱さに直面できない人が人を否定するんですよ直面してるんだったら 否定しないでおこうとか相手に攻撃するのはやめておこう
っていう客観視的なことはできるからそこの弱さと僕は
戦っていきたいんですよね「この本は自分に合わないな」と
思うことは別にいいことだと思うけど「自分に合わないけれど
じゃあこっちから合わせていこう」
っていうことを僕はしたいわけ特に純文学なんかさ癖が強い小説
たくさんあるからさ自分を中心にしてしまうと そりゃ
合わないことなんかたくさんあってそうすると
純文学を楽しむということも
できなくなっちゃうわけよ純文学を特に読む時は
癖の強いそれぞれに対して自分がこう接近していく
っていうイメージでやった方が僕は純文学全般を
楽しめるんではないかなと
思ったりはしていますけどねこれ全然
需要あるかどうか
しらんけど僕の「読書の哲学」みたいなのをまた話せる動画を
作れたらいいな
と思ったりしてますねそんな感じで
今回は終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#907「僕の同人誌のプロトタイプ版が完成したので、少しだけ公開します!」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと私つかつ この1週間 かなり忙しかってあとちょっと風邪気味になっちゃって咳が結構 出たりとか動画もあんまり撮れなかったし 作れなかったんですけどでもその間に1つだけ ちょびちょびと
やってきた作業があって それは…こちらになりますねこれは僕が今 作っている同人誌のプロトタイプ版ですね「つかっちゃんの現代純文学1000冊」って書いてますけどこれは普通にコピー用紙で印刷してホッチキス止めて ここにテープで
ちょっと綺麗にしてるんですよこれ中身を開けると本格的な本の体裁になっていて今のところ131ページまで出来てます来年に出品するのは 約200ページ予定なんでまだ6割ぐらいですけどこれこの前も見せたかもしれないけどこれまで僕が読んできた本を1ページの中で 上下段で6冊紹介してるんですねそれがずーっと続いていくんですけどそれが今ところ786冊まで完成しています完成予定は1080冊まで行くつもりなんですよねこれ 表紙を付けてみたんですよ結構 雰囲気 出ると思いませんか?この1週間 めちゃくちゃしんどかったんですけどこれをちょびちょび 中とか確認して文章も1個1個チェックしたりあと印刷する時に 左右とか上下の余白を考えたりとかそういうのを ずーっとちょびちょびやってたの1日では終わんないよ だいぶ時間 食いましたしあとこれは A5の紙なんですよねA4の紙の半分のサイズなんですよこの紙ってあんまりないみたいですねA4のコピー用紙って コンビニとか
でも売ってると思うんですけどA5のコピー用紙が 僕 色んなお店とか行ったんですヤマダ電機とか 他の電気屋さんとかに行ったんだけど売ってなくて あれーと思って普通にアマゾンで買ったんだけど 結構 高かった500枚入りが800円とかしてたんだけどそれを手に入れて 1個1個 刷ったりとかしましたねこれ 手前味噌で申し訳ないけど自分でこういう同人誌を作る
ってことをあんまりしたことなかったからめちゃくちゃ今 興奮してるんですよこれまだ完成の6割ぐらいなんですけどこれだけでも全然 良い本だなあと思ってんの僕はやっぱり本が本当に好きなんで本の紹介されているブックガイドは
大好きで大好きで仕方ないんだけれどもちろん自分が読んだ本を並べてるからあ そういえば これ読んだなとかそういうのを思い出してきて めっちゃ感動するんですよね完成版には これにプラス 前書きと後書きを入れてあと途中途中に ちょっとしたコラムっていうかエッセイみたいのも入れたいと思ってるんですよこれは印刷所で どれだけお金を使うかっていう問題もあるがだいたい1冊1000円ぐらいで
文学フリマで設定しようかと思うんですけどこの1週間 これを「概念」から「物理的なもの」に変えていく っていう作業をやってたからそれもあって 疲れたのかもしれないねせっかく僕も本を作るから 完成度 高いものにしたいわけよ僕はこういうことは かなり真剣ですよ一切 手は抜かないし 手を抜けない性格してるからむしろこういうコツコツした作業は
多分 得意だとは思うんですよねていうか めっちゃ好きなんですけど今回 これを作ってる時先日 大阪の文学フリマで買った他の人の同人誌とかパラパラめくって他の人はどういう風に本を作ってるんだろう
とか思って 色々見たりしてましたいや これ 本当にみんな買ってほしいなって思うよまだまだ途中だけどかなり読み物として面白いと自分で言うのも ダメなんだけどめっちゃ良いからブックガイドとして めっちゃ面白いと思うよもちろん完成までは まだまだかかるし
1年後の話ですから 結構 遠いけどあとこういう表紙の装丁とか どうするかとか例えば 誰か イラストレーターさんに頼んでかっこいい表紙にしてもらいたいとか色々まだまだ 決めないといけないこと あるんだけどその作業も含めて 楽しいな って本当に思ってますねこれだけ言って終わりますけど実は僕は 来年2024年は僕自身の読書20周年なんですよね僕は15歳から読書を始めてるから来年 僕35歳になるんで 読書歴は20年とあと僕YouTubeの方は 2019年から始めてるから来年は5周年になるんですよだから それの記念としてこの本は絶対に出したいと思ってるのよね僕の読書人生の集大成みたいな形かなと思いますこういう本にしてしまうと ずーっと残るから僕は1つ 恩返しみたいなのが したいと思っているから本当に早く これ完成させたいなー
っていうのは 1つ思うんですよねやっぱり僕は本が好きなんだなー っていうのをこれを作り始めて 思ったんですよねこの1週間 動画 あんまり出せてなかったんですけど自分の中では
価値のある1週間だったんじゃないかと
実はちょっと思ったりしますまた小説とか文学とかの動画どんどん撮っていこうかなと
思っておりますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで 今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#906「あと300冊… ちょっとだけ公開…【ついにカウントダウン!】」
はーいこんにちはつかつです
今日もやっていきましょう今回は
何するか
っていうと残り300冊これ何が300冊
かっていうと僕が来年 2024年の秋に
文学フリマ東京で同人誌を
売りたいと思ってるんだけどそれは 前から言ってるように
「つかっちゃんの現代純文学1000冊」
っていうタイトルなんだけど正確には1080冊の
僕が読んだ本のひと言感想を
まとめた本なんですね今ちょうどこれまで
読んできた本が
780冊あるんですよということは
1080冊まで残り
300冊ということで先日11月11日に
文学フリマ東京が
あったみたいですね僕は参加
できなかったんだけど
もう来年の日程が
発表されてるみたいで来年は
2024年の12月1日(日)に
東京でやるらしいですねこれはなんと
東京ビッグサイトで
行なわれるらしいです僕はそこで なんと初めて
自分の同人誌を売る
ということをしたいわけです僕は同人誌も
作ったことないし
文学フリマで出品した
こともないので1年前なんだけど
めちゃくちゃ
緊張しているんだよね
うまくいくかなとかあと何部 刷ったら
いいんだろうとかって
めっちゃ考えてるんですよ自分の中では
僕 YouTubeも
やってるから100部か
多くて150部とか
一応 刷ろうかなと
思うわけそりゃ同人誌を作るのに
印刷所に原稿を持っていって
製本してもらうから金かかるのよね
その金分は回収したいと
思ってるんだけどできますかね
どうなんですかね
それは置いといてねもう1個
1つやりたいな
と思うのは知り合いと
今 相談していて僕が その文学フリマで
出したいのは さっき言った
1000冊 紹介するやつともう1個
小説集を出そうかな
言ってるんですよ
その人と僕が昔
書いた短編があって
それと あと
知り合いが1人いてもう10年来の
付き合いの
知り合いですよその人も小説がいくつか
あるので それを混ぜて
アンソロジーっていうか2人の共著の
短編集を出そうかな
は考えてるんですよねまだ1年前だし 確定で
そうなるかはわかんないけど
個人的には出したいなと思ってる僕 同人誌
たくさん作りたい
と思っていて今回はその2つかな
最大その2つだと
思うのよその次回以降ですよね
僕が昔 文藝賞っていう
2016年のことでしたけど河出書房新社がやっている
文藝賞っていう新人賞の最終選考に
残ったことが1回あるんですけどそれも同人誌にして
発売したいなと思うしもう1個
長編を書いてるから
それも出したいと思うしあと昔 僕 詩を
たくさん書いてたんで詩集にしてまとめたい
っていうのもあるし
結構 出したいもの
いっぱいあるんだよねこれ よくよく
考えてみると僕が今度
作ろうとしている
「純文学1000冊」
っていう同人誌はこれ
何でもできるな
と思ったわけこれ「つかつ流」
とか何でもいいから
名前つけれると思うのはっていうか
やってる人いると
思うんだけど僕がまとめるのは
ツイッターの
読了ツイートなのよこれ140文字しか
ないわけ 1個ね140文字の読了ツイートを
1000ツイートまとめたいのが
僕の同人誌なんだけどこれ漫画とか映画とかでも
できるなと思ったわけ僕は漫画が好きで
変な漫画ばっかり買っては
読んだりしてるんだけどそれはあんまり
読了ツイートって
しないんですねそれも例えば
読んだら 毎回 読了
ツイートしてってそれを1000個 集めると
「つかっちゃんの現代漫画1000冊」
みたいな本もできるわけじゃないですかあと映画ね
僕あんまり映画って
見ないもんで大体
年に2回 行ったら
良い方なんですよ映画
あんまり見ないものだけど
「つかっちゃんの映画1000本」
みたいな同人誌だって(映画を)見たらツイートして
それをまとめればできるわけだから
そういうのを作りたいなと思ってだって読了ツイートを
遡るだけでいいので原稿自体は時間とともに
出来上がっていくんですね
皆さんでもできるのよ これ皆さんも本を
もちろん読むと
思うんですけれど読み終わったら
ちょっとしたあらすじと
感想を140文字程度で
毎回ツイートするわけよそれが1000個たまったら
もう同人誌が作れるんですよこれを
僕は「つかつ流」と
名付けたいんですけどっていうか
本って基本的には
口コミなので「誰かが面白いですよ」
って言わないと 次の人に
行かないんですよねほとんどの人は
9割9分の人は世の中の全ての本
っていうのが どんな本が
あるかを知らないわけよ全部を知ってる人って
まあまあいないから誰か知らない人の
ツイートとかが来て「この本 面白そう
私も読んでみようかな」
みたいな感じで
読んだりするわけよなんだけど
これ つかつ流の
同人誌 作って例えば 文学フリマで
「◯◯の小説1000冊」
みたいな同人誌が
めちゃくちゃ出てきたらそういう
1つのムーブメントとして
めちゃくちゃ流行ったらみんな それを買って
みんながオススメする1000冊を見て
「これ面白そう」とかできるでしょこれすると
文学とか小説とかが
活発化するような
気がするんだねだから皆さんも
ぜひやってみてほしい
まず僕が完成させないと
いけないんだけどねあと僕も
読了ツイートを
まとめるだけなんで
原稿自体は簡単で今 ワードで
書式とかを設定して
どう並べようかとつまり中のアレンジメント
みたいな感じなんだけど
めっちゃ難しいね当初 僕が考えてたのは
四六判で作ろうかな
と思ったわけよこれ 適当に出すけど
「四六判」っていうのは
普通の単行本サイズねこのサイズが四六判って
言われるサイズなんですよ四六判のメリットとしては
本棚がバーってあった時に芥川賞受賞作とかが並んでたら
横に僕の同人誌をパッと置けるわけよ
大きさが同じだったら
いいなと思うんだけれどこの四六判のサイズでは
あんまり文字数って
入んないっぽくて1回 四六判で設定して
ワードを作ったんだけどページ数が
250ページとか
行っちゃうんですよもし完成形が
250ページになると
するじゃないですか結構 金が
かかるのよね今 製本所もチビチビと
調べたりしているんですよ印刷所によって
料金設定は
変わるんだけど大体 ページ数で
金がかかるのよね100ぺージの本と
200ぺージの本があったら
単純計算 倍の値段
かかるんですよもし250ページで
100部 刷ると
するじゃないですかそうすると8万〜10万とか
かかる可能性がある
っていうのが調べると出てきて8〜10万
ちょっと高いなと
思ったわけよ少しでも費用を抑えたいと思うから
四六判では無理だなっていう
結論に今のところになってるのよどうしようと思ったときに
ワイド判で行こうかなと思うわけワイド判っていうのは
この漫画で言うと
ちょっと大きいサイズの
漫画あるでしょこのサイズで
同人誌を作ってる人って
結構いるんですよねワイド判って意外と
文字の文字数
かなり入るらしくてあと上下とかで
書いてる人も
いるでしょノベルスみたいな感じで
2段組みたいのが
ワイド判ではできるんですねそうすると
ボリュームがかなり
詰め込められるみたいで僕もちょっと
ワイド判を採用
しようかなと思って今のところ
縦書きで上下2段組
にしてるんですよそうすると200ぺージ
行かないぐらいで収まるんですね
150ページぐらいになる
かもしれないねしかもワイド判で
設定すると 見た目も
かなり綺麗に作れて上段3つ 下段3つの
1ページで6冊
紹介できるんですよ
(実際の様子)見開きで12冊
紹介できて それが
ずっと続いていく
っていうそういうスタイルになるかな
という感じになってますねいやこれめっちゃ嬉しいわ
早く完成品を出したいホチキスでもいいから
作ってみようと思ってねこの動画でも
この同人誌は
残り1年ちょびちょびと途中経過で
動画を出していきたい
と思ってるんだよね「こんな感じでできます!」
みたいな感じで 出せる日が
早く待ち遠しいなあと
思っておりますそんな感じで
今回 残り300冊
読まなきゃいけない
話だったんだけど残り300冊も
何を読もうかなと
思ってますよみなさんだったら
「残り300冊読め」と
言われた時に
どんな本を読みますか僕は
ちょっと短歌にも
今ハマっていてこれまで4冊の
歌集も読んで
短歌って面白い
んだなあと思った僕が作る同人誌は
僕の読んだ順に
本を並べるんで結構ランダム
っぽいわけだけど意外と僕が
何を読んできた
っていうそういう3年間の読書の遍歴が
載ってる本だって
言ってもいいんですよそうすると
ここでつかつ
現代詩に
ハマったなとかここで海外文学
ちょっと読んでるなとか
ここで短歌を読んでる
とかがわかるから個人的には
良いアルバムだと
思っているんだけど基本的には
純文学を多めにしたいけどね
そんな感じでございます皆さん この同人誌について
アドバイスとか意見とか
感想とかありましたらぜひコメント欄で
お書きください
よろしくお願いしますまた文学・小説についての
動画 出そうと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回 終わろうか
と思います高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#905「【購入】お固い文学とサブカルな文学11冊の本を買ってきました」
購入本紹介動画のため、購入本を羅列します。
01.松田青子ほか『早稲田文学5号』
02.中上健次『熊野集』
03.クセノフォン『ソクラテスの思い出』
04.町田康『湖畔の愛』
05.寺山修司『寺山修司少女詩集』
06.滝本竜彦『NHKにようこそ!』
07.滝本竜彦『僕のエア』
08.最果タヒ『モグ∞』
09.根本敬『人生解毒波止場』
10.道籏泰三 編『葉山嘉樹短篇集』
11.佐竹謙一『スペイン文学案内』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#904「2020年代の芥川賞 全10冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです。
今日もやっていきましょう今回は
何するか
って言うと2020年代の芥川賞を
振り返ってみよう2020年代の芥川賞を
実は これ数えると
10作品あるんですね
結構ある今回はそれを 一気に
パッと振り返っていく
っていう話でございますさっそく
やっていきましょう
第163回(2020年上半期)
①高山羽根子『首里の馬』
②遠野遥『破局』
『首里の馬』は沖縄の話で
しかもクイズっていうのも
関わってきて知識・記録とかをどうやって
次の代に渡していくかみたいな
話もあると思うんですね『破局』は
筋トレばかりしてる
男子大学生が女性をめぐって
破局していく
っていう話なんですけど個人的には『首里の馬』は
めっちゃ完成されてると
思っているんですよねでも『破局』もいいよ
遠野遥節ってのもあってルールに従っていく主人公で
「自分の心」っていうのが
あんまりないんだよねちょっとサイコパスじみた
そういう特徴がある登場人物が
多いんですよねこの2つは 読みやすいから
読んでみたらいいと思いますね
第164回(2020年下半期)
③宇佐見りん『推し、燃ゆ』
『推し、燃ゆ』は
芥川賞を受賞する前から注目されてて
その時点から売れてたと思うんですけどでも意外とけっこう
暗い話だと思わないですか主人公が推しのアイドルを
追っかけてるんだけど
そのアイドルが炎上しちゃって主人公は
発達障害を
持ってて自分のリアルな生活が
本当にしんどくて
しんどくて仕方ないと「どうしよう」
ってなってて最後…
みたいなね宇佐見りんさんは
母娘の関係みたいなのを
結構やってると思うし生きづらさみたいなのを
やってるんだよねだから意外と暗い作家なんだよね
でもそこがいいよ そこが
純文学らしいっちゃらしいし『推し、燃ゆ』は売れてますから
ぜひ皆さん 手に取ってみて
もらったらと思いますね
第165回(2021年上半期)
④石沢麻依『貝に続く場所にて』
⑤李琴峰『彼岸花が咲く島』
『貝に続く場所にて』
っていうのはドイツが舞台で主人公は日本人で
ドイツに行ってたんだけど
丁度コロナ禍が起こっちゃって昔 3.11で津波に流されて
亡くなっちゃった人が
幽霊となって ドイツに
現れるっていう話結構 モチーフとして
かなり耽美的なものが多く文体とか語彙とかも
かなり難しい作品では
あると思うんですよあと
『彼岸花が咲く島』
なんだよね主人公が ある女の子がいて
ある島に漂着するんですよねその島では2つの言葉があって
でも漂着した主人公も 実は
もう1個 言葉を持っていて
3つの言葉が出てきて「なぜその言葉が出来たのか」
とかがのちに語られるっていう李琴峰さんって
大体レズビアンとかあと越境文学的な つまり
中国とか台湾とか そういう人たちが
日本に来て言葉の壁を感じたりとかいうダブルマイノリティみたいな
そういう世界を描くのが多いですね僕は李琴峰さんの全ては
読めてないんだよねだから ちょびちょびと
全てを追っかけられるように
していきたいなと思っております
第166回(2021年下半期)
⑥砂川文次『ブラックボックス』
主人公は
メッセンジャーっていう
いわゆるウーバーイーツ
みたいな感じだけど食べ物じゃなくて
ちゃんとした荷物とかを
自転車で運ぶっていう
そういう職業をやってるんだけど主人公は感情を
抑えられなかったりとか
自分で自分を諦めて
しまったりとかしてどこにも居場所がないというか
逃げ場所がないみたいな主人公で最終的には
人をバンって殴っちゃって
逮捕されるって話なんだけど砂川文次さんは元々
自衛隊に所属していてそこから
戦争3部作と言われる
作品を書いたりとかあと1つ
ディストピア小説の
『臆病な都市』ってのも
書いていましたけど『ブラックボックス』は
若者の辛さみたいのがあるから
みんな読んでみてほしいんだよね
なんかとてもいいと思う
第167回(2022年上半期)
⑦高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』
この話って
主人公が男の人で
2人の女性と
付き合ってるんですよで どっち取るか
みたいな話なんだけどホラー小説とも
言われますね これね高瀬隼子さんって
過去に5作品出ていて
それらは大体HSP的な
感じだと思うんだよな敏感な人が主人公で
色んなことを考えてしまうと大体 相手って
感じないやつだから
こっちが空回りしてる
っていう話が多いんだけど芥川賞って
もちろん小説なんだけど
童話・御伽噺っていうか
(寓話的な)メッセージは
かなりわかりやすい話
だと僕は思うからこれ超オススメなので
みんな読んでほしいですね
第168回(2022年下半期)
⑧井戸川射子『この世の喜びよ』
⑨佐藤厚志『荒地の家族』
『この世の喜びよ』の方は
これ 主人公は デパートで
勤めてるおばさんなんだけどそこに中学生の女の子が
デパートのご飯を食べる所で勉強してたりとか
1人でいるんで
声をかけたりする
っていう話でこの2人の関係性に
なってくるんですけど年齢差もあるわけ
じゃないですかでも主人公は女の子が
どんどん好きになるわけよ自分に重ねたりとか
自分の娘さんもいるから
そこに重ねたりとかして自分の人生みたいのが
女の子に投影してるんだ
と思うんだよね井戸川射子さんって
そういう日常の幸せを
見つけるのうまいな
っていう感じはするよあと
『荒地の家族』ですけど
主人公が40歳の
植木職人なんだけど主人公が 3.11の時に
植木職人として独立
しようと思った時に津波で植木の道具が
全部 流されちゃったりとか奥さんが病気で
亡くなっちゃったりとか
辛い話なんですよこれだけど主人公は
仕事を頑張る
しかないと仕事をすることによって
何とか精神の緊張を
保ってる人だと思うんですだけど それが
なんだかんだ最後に
うまく着地して主人公も
色んなことを思っていく
っていう話なんだよね『この世の喜びよ』と
『荒地の家族』って意外と遠いように思えて
意外と近いような話
なんじゃないかな
と思うんですよ「主人公の心」みたいのが
テーマになってるような
気がするんですよ「魂の癒し」みたいのを
多分やってるんだよねだから この2つは同時受賞して
本当に良かったんじゃないかな
と思いますよ
第169回(2023年上半期)
⑩市川沙央『ハンチバック』
主人公はミオパチーっていう
こう背骨が曲がってしまう障害に
かかってるんですよね1つの
グループホーム
の中に住んでいてだけど 結構
エネルギッシュな人で
放送大学に参加したりとか自分で小説を書いて
それで稼いだり
とかしてるっていうだけど だからこそ
自分がどれだけ
頑張ろうとも自分が障害というものがあって
自由に動いたりとかできない
っていうところの社会的な圧迫っていうか
迫害みたいのは絶対あるのでそこに
「なんか俺って負け組だよな」
みたいなヘルパーの男がいてそいつと1つ 契約を結ぼう
みたいな話なんだけどあと この回が
とても良かったねつまり第169回の候補作が
全体的にレベルが高くて石田夏穂『我が手の太陽』
児玉雨子『##NAME##』千葉雅也『エレクトリック』
乗代雄介『それは誠』が
ノミネートされていてどの作品も
全然 受賞できる
レベルっていうかすごい とても
面白い作品が並んでいた
印象がありますよね市川沙央さんは
新人作家なのでたくさん たくさん
小説を書いていただきたい
というのが思いますね
そんな感じで 今回
2020年代の芥川賞 10作品を
振り返ってまいりましたけど意外と芥川賞作品って
面白い作品 山ほど
ありますよ純文学って
よくわからないなあ
だけど純文学
読みたいなと思う人はまずは
この10冊を読んでみる
っていうのがいいと思いますこういう作品が世の中に
認められているんだ
芥川賞を取っているんだ
っていうのが分かりますからね純文学の ある程度は
把握できるんじゃないかな
と思ったりしますね
そんな感じでございますまた 文学・小説についての
動画 出そうと思いますので
どうぞよろしくお願いしますそんな感じで
今回は終わります高評価・コメント・チャンネル登録
どうぞよろしくお願いしますではでは
つかっちゃんでした
バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#903「僕が気になっている純文学の新刊8冊を紹介します!」
はーいこんにちはつかつです。今日もやっていきましょう。
今回は何するかっていうと、
僕が個人的に「発売が気になる新刊8冊」ということでございます。
僕は毎日のように出版社のホームページを覗くんですね。
だいたい出版社のHPって来月と再来月に発売される本まで載ってるんですよ。
それを見て「えっこれ発売されるの?」みたいなのを絶対チェックするようにしてるんです。
今回それで気になっている8冊の本を紹介しようかと思います。
さっそくやっていきましょう。
1冊目
①井戸川射子『共に明るい』
講談社 2023年11月9日
井戸川射子さんは 前回
『この世の喜びよ』で
芥川賞を取ってるんですよ今回 その芥川賞
受賞後第1作に
なるわけですね僕は井戸川射子さんの
作品は全部 読んでいて1.『する、されるユートピア』
(第1詩集)2.『遠景』
(第2詩集)3.『ここはとても速い川』
(第1小説集)4.『この世の喜びよ』
(第2小説集)つまり過去に
4冊出てるんですけど
今回5冊目ということですねストーリーとしては
早朝のバス 公園の端の野鳥園
付き合って間もない恋人の家誰もが抱える痛みや不満・
不安・葛藤・目に見えない
心の内に触れた時「他人」という存在が
繋がりたい他者に変容する待望の芥川賞受賞後第1作
心を震わす傑作小説集素晴らしい!
これ絶対 読もうと
思ってますね2冊目これ 一気に
2・3・4冊目と
一気に紹介すると
2冊目
②小泉綾子『無敵の犬の夜』
河出書房新社 2023年11月22日
3冊目
③佐佐木陸『解答者は走ってください』
河出書房新社 2023年11月22日
4冊目
④図野象『おわりのそこみえ』
河出書房新社 2023年11月22日
『無敵の犬の夜』
『解答者を走ってください』
『おわりのそこみえ』は今年の
文藝賞の受賞作となっておりますね僕には珍しく
文藝を買ってましてこの中に実は全て
載ってるんですけどなんと早くも単行本が
発売ということです「無敵の犬の夜」
は読んでましてだけど単行本が出ても
単行本で読もうとは思ってるんだけど
これめっちゃ良かったですよストーリーを言うと
「この先 俺はきっと何もなれん
と思う 夢の見方を知らんけん」北九州の片田舎 中学生の界は
地元で知り合ったバリイケとる男
橘さんに心酔するのだが…
第60回文藝賞受賞作佐佐木陸さんの
『解答者は走ってください』はこの世界は
壊すべきである
◯か×かアクアグリーンの髪を持った
怜王鳴門をめぐる驚愕のマルチバース文学が
読むものを挑発する 第60回文藝賞優秀作同じ優秀賞の図野象
『おわりのそこみえ』は「あのさ その『死にたい』も
ファッションみたいなものでしょ」買い物依存を抱え 破滅への道を
一心に転がる美帆が 終わりの底で見た
予想外の景色とは? 第60回文藝賞優秀作大体 この季節って 文藝賞と
すばる文学賞と新潮新人賞が
発表されるんですね文藝賞は本当に早くて
単行本にすぐなるんですよねすばる文学賞と
新潮新人賞は
けっこう後なんだよね新潮新人賞は確定で
(単行本に)ならないので新潮新人賞 2作品 受賞作が
あったみたいですが(今年)新潮社さん 単行本化
よろしくお願いします
5冊目
⑤永井みみ『ジョニ黒』
集英社 2023年11月24日
永井みみさんは
『ミシンと金魚』っていう作品で
集英社のすばる文学賞を受賞して
デビューした作家で今のところ
それ1冊だけだったんですけど
今回2冊目ということですねストーリーを言うと
1975年 横浜 少年アキラと
「犬」とのひと夏の冒険が始まる4年前 海水浴中に
はぐれてしまった父さんは
今もまだ帰ってこないあれ以来 母親のマチ子は
時々どっかから拾ったオスを
連れてくるようになったままならない世界の悲しみと
愛しさが胸に込み上げる
すばる文学賞 受賞作「ミシンと金魚」
著者待望の最新作こういう新人賞から
デビューしてきた人って
2冊目3冊目を書かずして
消えてしまう人もいるんだけど2冊目3冊目が出ていくと
順調にキャリアを重ねていける
っていう感じがあるからこういうのは 本当に
どんどん読んでいかなきゃな
と思っておりますね
6冊目
⑥山下澄人『FICTION』
新潮社 2023年11月29日
山下澄人も『しんせかい』
で芥川賞を取っている作家で『緑のさる』で
野間文芸新人賞も
取っているんだけど山下澄人さんの作風って
子供みたいな主人公が「神の目線」みたいなを持って
いわゆる「移人称」と言われる独特の視点移動みたいなが
できる小説なんですよこれはそうか
どうかはわかんないけど
ストーリーとしては「FICTION」は著者が立ち上げた
演劇集団の名前でもあります四半世紀を超え
人が入れ替わる中で
夭逝した者脳溢血の後遺症で
体の半分が動かなくなって
小説に挑もうとしている
者がいます本書には死臭が立ち込め
そこから反転するかのように演劇及びフィクションについて
自由に奔放なスタイルで考察される「まだ死ぬまでにずいぶん
時間はある」と嘯く著者の強靭な
語りと思考に魅せられますこれ あらすじは
公式のあらすじだけど小説なんだと思うんだけど
演劇の話なのかなあ?これだけでも
超面白そうって感じがして
超読みたいですね
7冊目
⑦鈴木涼美『トラディション』
講談社 2023年12月8日
鈴木涼美さんは過去に2回
芥川賞の候補になってまして1.『ギフテッド』2.『グレイスレス』3.『浮き身』今回で4冊目になるんですね
僕は過去の その3冊は全て
読んでいますから 楽しみでしてストーリーとしては
ホストクラブの受付で働く私
ホストにハマる幼馴染夜の世界を
生き場所とする彼女らの
蠱惑と渇望を描く傑作小説もうずいぶん前に
夜と心中するような女は
いなくなったし今では男と
心中するような女も
少なくなった表面だけ明るく
少し退屈になった街で
皆がごく個人的に
病んでいく鈴木涼美さんの小説は
夜の街とかを描くのが多くてこういう小説も
とてもいいですね
引き続き読んで
いきたいと思います
最後 8冊目
⑧沼田真佑『幻日/木山の話』
講談社 2023年12月8日
いや僕は
もう嬉しくて嬉しくて
仕方ないですね
なんでかというと沼田真佑さんっていうのは
何年も前に「影裏」っていうので
文學界新人賞を受賞し そのまま芥川賞を
受賞した作家なんですね(2017年)しかし それから
1冊も単行本が
出なかったんですね雑誌には 小説を
発表してたみたい
なんだけどなぜか単行本にならずに
しかも芥川賞を取っているから全然 色んな出版社は 作品を
単行本にすればいいはずなのに
してこなかったんだよねそこから
2023年になって
(6年経って)ついにようやく
芥川賞受賞後 第1作が
発売されると 嬉しすぎますストーリーを言うと
コロナ禍を含め 4年の歳月をかけ
書き継がれた オーガニックな
魅力の連作小説「木山の話」自然のまま 言葉の流れのまま
音楽に身を任せるように耽溺して
没入する小説体験自然への 生命への
名もなき人への眼差し人と動植物 水と土と空気
社会が影響しあって成り立つ
この世界を生き過ぎゆく時間を
そのままに描き出す
計8本収録『影裏』も
1回映画にも
なってますから「次の作品を読みたいな」
っていう人 いっぱいいた
と思うんだよねだからその人たちのために
今回のこの本があると言っても
いいんじゃないですかね
僕は超嬉しいと思ってますね
以上 8冊の本を紹介してきたんだけど、
現代純文学の楽しみ方の1つって、現在進行形で最先端の文学をずっと追っかけていけるっていう楽しみがあるんです。
その中に推しを見つけてその人が何とか賞を取ったとか新刊が出たとかいうのに嬉しくなるっていうアイドルのファンみたいなそういう楽しみ方ができるのが現代純文学の1つの魅力だと思うんですよね。
僕はそこが超大好きなんでこれからも新刊情報をどんどん見つけていって動画にしていこうかな思っておりますね。
また小説とか文学の動画をどんどん出していきたいと思いますので、皆さん どうぞよろしくお願いします。
そんな感じで今回は終わろうかと思います。
高評価・コメント・チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。
ではでは、つかっちゃんでした、バイバイ!
https://www.youtube.com/watch?v=TM1noSDJGZc&t=6s
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#902「ザ・文学という12冊の本を買ってきました!」
購入本紹介動画のため、購入本を羅列します。
01.宮内勝典『南風』
02.黒川創『暗殺者たち』
03.吉本隆明『現代日本の詩歌』
04.高橋源一郎『いつかソウル・トレインに乗る日まで』
05.髙村薫『土の記』(上)
06.髙村薫『土の記』(下)
07.松浦寿輝『もののたはむれ』
08.松浦寿輝『あやめ 鰈 ひかがみ』
09.阪田寛夫『土の器』
10.檀一雄『リツ子・その愛』
11.池澤夏樹『カデナ』
12.長嶋有『もう生まれたくない』
https://www.youtube.com/watch?v=sFqsDk-_E0A
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#901 「つかつ大賞2022 〜僕が2022年に読んで面白かった小説ベスト10を発表します〜」
はーいこんにちはつかつです。今日もやっていきましょう。
今回は何するかっていうと、「つかつ大賞2022」っていうことで、僕が去年 2022年に読んだ小説の中で ベスト10を決めようっていう動画でございます。
僕が去年に読んだ本は360冊ありまして、そこからベスト10を決めるんですけど、去年に実は動画で「2022年の上半期ベスト5」って動画を出してるんですよね。
これを「ベスト10〜6」と位置づけて今回 新しく「ベスト5〜1」を先に発表します。
あとからベスト10〜6をパパパッと早めに出すっていう感じにしようかと思っておりますね。
早速やっていこうかと思います。
第5位
⑤舞城王太郎『短篇七芒星』
講談社 2022年
僕は舞城王太郎をめちゃくちゃ読んでいまして新刊が出たら絶対に読むようにしてるんですけれど、『短篇七芒星』は7つの短編が入っていて、これは僕がツイートで読了ツイートをした時の文言を言うと、
1.足を切断する犯人を当てる探偵の話でしょ
2.狙撃手の弾がワープして世界中の悪人を殺す話でしょ
3.毎夜うるさい飛び降りの音とマジ怖い影の話でしょ
4.石にストーカーされる青年の話でしょ
5.サイコパスの少年と入れ替わった背後霊の話でしょ
6.犬を探す女と
7.子供が生まれてくる前に一緒にいた豚に襲われる話
があるんですよ。
個人的に好きだったのはサイコパスの少年と入れ替わる背後霊の話で、主人公がある少年の背後霊みたいな存在でその存在自体は「幽霊」っていうか誰にも感知されてない存在があるんですよ。
ある少年がいて その少年はめちゃくちゃ犯罪行為を行うサイコパスなんだけど、突然 少年がバーンで倒れて気がついたら後ろの背後霊と入れ替わってるんですよね。背後霊がその少年の中に入って人格を持ってるわけ。
その背後霊はずっとその少年のことを見てきたから、その少年が悪いことをめちゃくちゃしていることを知っているわけよ。
だけど周りから「お前 罪を償え!」みたいなことで その少年にめっちゃ言われるんだけれど、中身は入れ替わってるから「なんで俺がそんなの言われなあかんねん」と思うんだけど、今まで少年を見てるから「少年の罪は俺の罪なのか?」みたいな感じになるっていう話。超よかった超よかった!
あと この小説の表紙がめちゃくちゃ怖いんですよ。
謎の影がいるんだけど、これおそらく3つ目の話でホラー小説なんだよね。
舞城王太郎ってめっちゃホラー小説を書くのが上手くて、心がぶっ壊れるぐらい
怖い話が1個入ってるのよ。
舞城王太郎はマジ天才的だと思うから、僕はずっと追いかけていこうと思いますね
第4位
④大前粟生『死んでいる私と、私みたいな人たちの声』
河出書房新社 2022年
あらすじを説明すると、主人公・窓子っていう人がいるんだけど、彼氏からDVを
受けてるんですよ。
最初 生きてる感じかなと思ったら、実はDVの末で殺されてしまって、今 幽霊みたいになってるんですよ。
幽霊のまま自分は生きていると思いながら、歩いてたらある女子高生がいてその子は幽霊が見える体質なんですね。
そこで窓子と出会ってそこから悪人をやっつけていくっていう話になるんだけどなんだけど、窓子がもう幽霊で何でもできるってことにあとから気づいて、ワープとかもできるし
あと時空間移動っていうのが全然できるようになって過去にタイムスリップしてこの男が悪いことをするっていう時間より前に飛んで 最初からこいつを殺しとくわけよ。
そうすると悪いことっていうのは もう起こらないっていうことになってつまり悪人をどんどん殺していくって話なんだけど、結構 大前粟生さんの小説もいくつか読んでて『回転草』という作品から僕 読んでいましたけど奇想系なんだよね。
あと映画に今なってるんだよね。『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』っていうので映画になったりとかしててけっこう今 人気ある作家になってると思うんですよ。
この作品から入るっていう技 あります。
話としては最高だと思う。
第3位
③三浦俊彦
『これは餡パンではない』
河出書房新社 1994年
三浦俊彦さんというのは90年代ぐらいに活躍していた作家・哲学者でもあるんですよね。
何回か芥川賞の候補に入っているんです当時ね。この『これは餡パンではない』も芥川賞の候補になっているんですよ。
ストーリーとしては、美大生のカップルがいて、その人たちが教授に誘われて
前衛芸術の展覧会に行く、って話なんですけど、
そこで絵の影を見る絵や自分の絵を見させない作者の絵や絵を燃やす絵や
電流に触れないと見れない絵や動物を苦しませる絵など謎の芸術があったと。
「前衛芸術とは何か」 みたいなのを 小説でやっちゃったみたいな話で、
その展覧会には色んな絵があるんですよ。
それらの絵って本当にバグってて空間的に奥に絵が飾ってあると何かなあと思ってそこまで行こうとすると床に電流が流れてて電流を踏まないとそこまで行けないんですよ。
実はその電流を設置した絵の作者っていうのは奥に絵を飾ってる作者とは違っていて半分 邪魔してるんだけど「これも芸術なんだ」とか言い出すわけよ。
あと蛙とか猫とかの死体を使ってある絵を作った絵とかもあるし、
あと後半このカップルがめちゃくちゃ巻き込まれていって、「君たちカップルなんだろう」とか言って「君たちそこでやっちゃいなよ」とか言って「それも1つの芸術なんだよ」とか言って「そうしないと単位を上げないよ」みたいなことを言われて2人のカップルはどうするか とかいうちょっとぶっ壊れた小説だと思うんだよね。
先日 ツイッターで「新しい3大奇書を決めよう」みたいなちょっとしたムーブメントみたいながあった時に、三浦俊彦さんの名前が候補にあって、やっぱり三浦俊彦 ってそういう立ち位置なんだと思いました。
変わった本や奇書が好きな僕からすると、三浦俊彦を読んでいかなきゃいけないなと思っておりますね。
第2位
②平山夢明『ヤギより上、猿より下』
文藝春秋 2016年
平山夢明さんって最近の小説はぶっ壊れた作品ばっかり書くっていうので有名で、
この作品のあらすじを言うと
1.父親からDVを受ける母子の話
2.狂女の娘を探す探偵の話
3.妙に優しい殺し屋の話
4.山の麓の売春宿の話など
ヤバい4篇の短編集
特に表題作の話をすると、
売春宿っていうか昔はめっちゃ盛り上がっていた1つの
そういう娼館があるんですよ。
なんだけど、今もう全然若い女の人とかいなくて、ババア3人しかいないんですよね。
ババアが客の取り合いとかするわけよ。
でもそこに娼館の主人みたいのがいて、その人はやっぱり売上が落ちてるから経営していかないといけないから、どうするかって言ったら、
猿とヤギを呼んできて2人に仕事させる
っていう最低な話になってくるんだけれど、意外とマニアックな人が通ってるからその2つがいいとか言ってその動物たちに負けていくババアの話なんだよね。
最後とんでもない展開になってきて 結構 感動するみたいな話なんだよすごいと思う。
なんだこれっていうふざけた話だなと思うわ。
あと実は この本って「イエロートラッシュシリーズ」っていうシリーズっていうか短編集で 1個1個の話は独立してるんだけど、一応シリーズって言ってこれの1個前に『デブを捨てに』っていう作品とかあったりとかして、本当にくだらない だけど
捨てがたいっていうか1つ間違ったらゴミみたいな作品のシリーズがあるんですよ。
それが僕 もう本当に読みたくて仕方なくて、また平山夢明に
チャレンジしようと思うんですけど、エンタメ小説をバカにするわけじゃないんだけどエンタメ小説でも本当にヤバいやつってたまにあるからそういうのはめちゃくちゃ読みたいなっていうのは最近 思うことはありますね
第1位
①佐川恭一『アドルムコ会全史』
代わりに読む人
2022年、僕が去年 2022年の読書体験の中でやっぱり1番すごいと思ったのは佐川恭一だろうね。
佐川恭一との出会いっていうのが僕の中では読書っていうのを本当に1つランクを上げたっていうか下げたのかもしれないんだけど(笑)。
あらすじの方に行きますと、
1.男がアドルムコ会という宗教による世界征服に巻き込まれる怪作や、
2.朝 起きたらキムタクになっていた怪作や
3.市役所の人間関係で『虚航船団』をやった怪作や
4.風俗に騙される怪作や
5.関西弁の外国人たちの怪作など5編の短編集。
この「アドルムコ会全史」っていう表題作は もう本当に無茶苦茶しているんですよ。
主人公は昔 あるアイドルグループ・バンドみたいなに所属していて人気があったんだけど途中でやめちゃって 今は工場で働いているんだけど、実は その主人公は
催眠術が使えて 人を思い通りに操ることができるっていうのと、あと大学時代にアドルムコ会っていう宗教を立ち上げたんですよね友達に任せて 自分はそこから引退みたいなのしてたんだけど、なんだかんだ話が進んでいくと、
工場の出張みたいな感じで海外の工場ではどうしてるかっていうのでフランスかなんかどっか行くんだけどその時に発覚するのはヨーロッパではアドルムコ会って宗教がめちゃくちゃ強くなっていてキリスト教とかもなくなっちゃってるんですよ。
そのアドルムコ会っていうのは実は自分が昔に作った宗教でその任せた友達がそいつも洗脳能力を持っていてヨーロッパでみんなを洗脳してるんですね。
主人公はスカウトされるわけよ元々 友達だったから。
だけど俺はちょっと嫌だなと思って「やめとくわ」って言ったら命を狙われる感になってきてそこでアドルムコ会の世界征服と戦っていくっていう話になっていくんだけど、
佐川恭一先生は今めちゃくちゃ人気者になりましたけれども僕は去年からずっと知ってたし『終わりなき不在』って伝説の本があってある出版社が文庫化するっていうことになって僕が帯を書いたんですけどその時から佐川恭一に注目しておりましたから、古参ぶるわけなんだけれど、
佐川恭一に出会って良かったなと本当に思います。
誰か三島賞とか野間文芸新人賞をあげてほしい佐川恭一に。
超いいから超いいから!
以上 これが僕の2022年のベスト1〜5なんですけど、ベスト6〜10もあってこれ1回 動画で言っていますから、軽く名前だけ列挙する形にしようかと思うんですけれど、
第6位
⑥町屋良平『ほんのこども』
講談社 2021年
第7位
⑦市原佐都子『マミトの天使』
早川書房 2019年
第8位
⑧高原英理『観念結晶大系』
書肆侃侃房 2020年
第9位
⑨佐川恭一『舞踏会』
書肆侃侃房 2021年
第10位
⑩山下澄人『君たちはしかし再び来い』
文藝春秋 2022年
これが僕が2022年に読んだベスト10になっております。
2022年もいい本を読めました。
今2023年の10月なんですけど、2023年は上半期ベスト5っていう動画を過去に
出してるんだけど、また下半期ベスト5も出そうかと思います。
そして、つかつ大賞2023年そういう動画も作ろうかと思っておりますね。
今度は10ヶ月遅れないようにしたいと思います。
そんな感じでございます。
皆さんは2022年 もしくは最近 読んだ本の中で とても良かった本はありますか
ぜひコメントで教えて下さい。
そんな感じで今回は終わろうかと思います。
高評価・コメント・チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。
ではでは、つかっちゃんでした、バイバイ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#900 「ラノベ奇書10選 Part2」
はーいこんにちはつかつです。今日もやっていきましょう。
今回は何するかっていうと「ラノベ奇書10選Part2」ですね。
前回ラノベ奇書っていうのを10冊読んで、それを取り上げた動画がありましたけど、今回さらにそこから10冊読みましたので、それを全て紹介しようかと思います。
僕が調べた限りでは「ラノベ奇書」って大体50冊行くか行かないかぐらいのイメージあるんですよ。
だからとりあえず僕は純文学ばかり読んでるんだけど、ラノベ奇書って50冊しかないから、少ないから、読める時にどんどん読んでいこうかなとは思っているんですね。
さっそくやっていこうかと思います。
前回、10冊紹介してるので、それの続きで11冊目です。
11冊目は、
⑪つちせ八十八
『ざるそば(かわいい)』
MF文庫 2015年
ストーリーを紹介すると、ざるそばがめちゃくちゃ好きな男の子がいて、その子がざるそばを注文すると、ある女の子が配達でやってきて、その子の名前が「姫ノ宮ざるそば」っていう名前なんですよ。これ本名なんですけど。
そのざるそばちゃんは「人類」ではなくて「麺類」なんですよね。
どういうことかって言うと、お父さんが科学者でその子の体をいじくって、手からざるそばを出したりとか、唾とかそういう体液みたいなのが全部そばつゆだったりとかする、っていうそういう能力を持ってる女の子がいるんですよ。
なんだけど、これ、のちのちに甲子園球場に行って高校野球を見に行くって話に
なるんですけど、その時にざるそばちゃんが、麺類とし めちゃくちゃ興奮しちゃうと「麺類補完戦争」=ソバルゲドンっていうのを起こしちゃうんですよ。
ソバルゲドンが起こると「甲子園球場が全て麺になっちゃう」っていう、エヴァンゲリオンで言ったら「セカンドインパクト」みたいなことが起こっちゃって「世界が全て麺類化する」っていうことになるんですよ。
「設定が狂ってる」っていうタイプのラノベ奇書かなと思います。
めっちゃ面白かったこれ。
12冊目は、
⑫岡本賢一
『Virgin Crisis それゆけ薔薇姫さま!』
ファミ通文庫 2000年
設定がまず人類が宇宙に出てて、舞台が宇宙空間なんですよ。
そこで宇宙の怪盗をやってる「薔薇姫様」と見習いの「ヒナコ」っていう2人組がいるんですよね。
この2人は銀河中の政治家とか王族とかそういう権力者を実は裏で操ってるんですけど、どうやって操るかっていうと催眠術みたいなのを使えて、その権力者は大体男なんですけど、男の性癖を全部暴いちゃって全部録画するんです。
あとこれラノベではめちゃくちゃすごいけど、男のお尻の方なんですけれど、それに自分の持ってる機械の細長い機械みたいなのをバッてぶっ刺すんですよ。そういうプレイをするんですよね。
それを全部 隠し撮りして「これがバラされたくなかったら、私の言うことを聞いてね」って言うわけよ。
だから宇宙中の全ての権力者を握っているから、何だってできるんですね。
その時にちょうどアンドロメダの方からアンドロメダ帝王がやってきて、こっちの銀河に攻めてくるんですよ。
めちゃくちゃ強いテクノロジーを持ってるからこっちが弱いんですけど、そこを今度、薔薇姫様とヒナコが戦いに行くっていう話になってくるんですよ。
ちょっと性的なんですよ極めて。それをギャグに落とし込めることで、ぎりぎり許されたのかな、って思うような得体の知れない小説なんだよね。
13冊目は、
⑬深見真
『ブロークン・フィスト戦う少女と残酷な少年』
富士見ミステリー文庫 2002年
ストーリーとしては、高校2年生の空手少女の秋楽ちゃんっていう女の子がいるんですよ。その同級生の武田闘二っていう男の子がいて、この2人が主人公なんですけど。
武田闘二くんは空手部に所属しているんだけど空手自体はとても弱いわけよ。結構へなちょこな男の子で、むしろ秋楽ちゃんの方がもう大会とか出まくってすごい成績の子なんですね。
その空手部が今度「合宿しましょうよ」っていうことで、メンバーの1人が金持ちの子がいて、軽井沢みたいな所に別荘があるから「そこで合宿しましょう」っていうことで、みんなで行くんですよ。
その時に殺人事件が起こるんだけど、ここは言っていいと思うけど、ある密室があって鍵もかかってるんだけど、中に死体があって、その死体が心臓が、胸の所がぶっ壊れてるんですよ。破壊されてて。
のちに警察が来て死因を調べると「転落死」っぽいっていう検死結果が出るんですよ。でもこれ密室で普通の部屋なのに転落死ってありえないし、心臓が壊れてる
ぐらいの強力な力がかかってるんですよね。
しかもその死体が時間を置いてもう1体出てくるんですよ。
どうやって犯人はこの死体・現場を作り出したのか、っていうそこがミステリーの謎のポイントになるんですけど、ここで武田闘二くんは格闘は弱いんだけど、推理が強いので探偵役になってねミステリを解いていくって話になるんですね。
全然、奇書っぽくないっていうか普通に読めます。だけど 何が奇書かって言うとトリックなんだよね。ミステリーのトリックがかなり力業なんですよね。
実はこれアマゾンでもう品切れでして、中古ですら出ていないので、アマゾンで買うことができなくなってるんですね。
これ個人的にはミステリーとして面白いと思います。
14冊目は、
⑭軽井沢洋一
『宅配コンバット学園』
スーパーダッシュ文庫 2010年
さっそくストーリーを言うと、7人の高校生がいて、その子たちが「お金が出るっていうことで自A隊の体験合宿に参加するんですよ。
この自A隊も「自A隊」って書かれててちょっとやばそうな雰囲気あるんですよね。
その体験合宿自体は1ヶ月だったかな ぐらいあって夏休みに参加するんだけど、お金が出るんだけど、さらに「特別任務」っていうことをすると、1人100万円もらえるんですよね。
その特別任務が何かって言うと「タイムスリップをして1943年のユーゴスラビアに行ってチトーっていうリーダー率いるパルチザンっていうのに所属してナチス・ドイツと戦うっていうミッション」なんですよね。
もちろん戦争ですから自分たちも死ぬかもしれないと、死んでも文句を言えないっていうミッションだから100万円くれるわけですよ。
だから結構 怖い感じで書かれるんだけど、これ何がラノベ奇書っていうと、構成力なんですよね。
これ250ページぐらいしかなくてそもそもタイムスリップするのが半分ぐらいを過ぎたからなんですよ。
そこが多分この話のミソなのに構成が失敗してて、戦闘シーンとかめちゃくちゃ
簡単にパパパってやって最後 終わりました、とか言ってそれで終わるんですよ。
1つ小説として失敗してるんじゃないかとよく言われるんですよ。
これアマゾンの評価だったら星1つぐらいしかないんですよ。
だけど 僕あえてよかったと思うよ。
「クソゲー・オブ・ザ・イヤー」みたいな感じで、マイナスの意味で有名になっちゃった、みたいな、僕みたいな変なマニアックな、わけわからん小説を読みたいとかいう人は多分発掘するような小説なんですけど、そういう意味ではよかったんじゃないかって逆に思うけどね。
15冊目は、
⑮かじいたかし
『僕の妹は漢字が読める』
HJ文庫 2011年
これ自体は実は5巻まで続くんですね。
僕はまだ1巻しか読めてないけど、1巻は1巻で一応 完結するのでいいと思うんだけど。
これなんと「日本の文学」について書かれているっていう小説なんです。
まずこれ 舞台設定が2202年なんですよね。
2202年の日本では実は漢字っていうのがなくなってるんですね廃止されたんですよ。
だからこのタイトルは「僕の妹は漢字が読める」っていうのは、普通一般の人たちは実はもう漢字が読めなくなってるんですね。
これはどういうことかっていうと 我々令和の現代人でも平安時代とかのいわゆる古文っていうのは読めなくなってるじゃないですか。
それを1つモチーフにして今から200年後では現代文も読めなくなってると。
でも その未来でも文学っていうものがあるんですよ。
その文学っていうのが、今で言ったらラノベとか萌えとかが200年後では正統派文学としてなってるんです。
このストーリーの主人公はイモセ・ギンくんっていう子がいてこの子は作家志望なんですね。
その妹さんがいてその妹さんはいわゆる平成文学とかを読んでるから 昔の文章も読めるし漢字も読めるんですよ。
その2人がいてタイムスリップしてしまうと。その移動先が今この世の平成の世に時間移動すると。
そこに「文学」っていうガジェットが入ってるっていうのが1つ面白いですよね。
つまり純文学とラノベというものを合わせた話だからとても面白いなと思う。
16冊目は、
⑯御影瑛路
『僕らはどこにも開かない』
電撃文庫 2005年
ストーリーを言うと、まず主人公が柊耕太くんっていう高校の男の子がいるんだけど、その同級生で香月美紀ちゃんっていう女の子が急に来て「君に魔法を教えてあげる」って言うんですよね。
「君には魔法の耐性がないからこのままだと 魔法攻撃を受けちゃって 危ないから 私が守ってあげるよ」って言うわけよ。
でも 別に「魔法がある世界」とかじゃないから「なんじゃこいつ」って思うわけよ。「不思議ちゃんかな」って主人公は思うんですよ。
同時に 主人公・耕太くんの友達に谷原雅人くんっていうちょっとヤンキーみたいな不良みたいな子がいて結構 仲いいんですよね。
だけど その谷原雅人くんは実は「鎖の音」っていうのが幻聴として常に聞こえていてガチャガチャ言ってて神経 高ぶってるんですね。
もう1人 秋山秀一くんっていう委員長タイプの 頭が堅物タイプの男の子がいるんですよ。
基本的にはこの4人が主人公になっていくんですね。
これ途中ぐらいだから言っちゃってもいいと思うけど、谷原雅人くんが何者かに殺されてしまうんですね。
その犯人は誰か ってなった時に大体この秋山秀一くんっぽいっていうことがわかってきて、別にミステリじゃないから犯人当てにはならないんだけど、この柊耕太くんが最初に「魔法の耐性がない」とか言われてたのが実は効いてきて、その殺された谷原雅人くんと仲良かったんだけど、どんどん谷原雅人くんのヤンキー的な人格が柊耕太くんに宿って、柊耕太くんと谷原雅人が合体するような人格になってくるんですよ。
柊耕太くんが谷原雅人くんが殺されて自分自身みたいなものだから自分が殺されたから復讐しに秋山秀一を攻めていくっていう話になっていくんだけど、これが危険な領域になってきてどんどんどんどんシリアスになってきて、もう読んでて辛くなってくるんですよ。
とてもとても暗い青春を描いてて、でも僕 もう本当にこれ良かったと思うわ。
こういうの 大好きでこれちょっと感動しました。
めちゃくちゃよかった。
17冊目は、
⑰扇智史
『永遠のフローズンチョコレート』
ファミ通文庫 2006年
ストーリーとしては まず高校生の平瀬基樹くんっていう男の子がいるんですね。
この子は全てを諦めて生きてるなんて無駄だよみたいなダラリと生きてるんですよね。
実は基樹くんの恋人がいて上條理保ちゃんっていう女の子がいるんですよ。
この子は実は高校生なんだけど、過去に9人の人を殺してるんですよね。
衝動が抑えられなくて、その辺にいる人間をナイフでバーッて刺して殺しちゃったりするんですよ。
もちろん警察とかも動いてるんだけど、理保ちゃんもバレないように現場を隠したりするから、今までバレてこなかったんですよね。
その子がある日やっぱり衝動が抑えられなくて、ある女の人が歩いてる時にその人に対してナイフでグサリって頸動脈を切って殺したと思ったら、実はその女の人は「遠野実和」っていう女の人で、実は「死なない体」を持ってるんですよね
だから頚動脈を切られても数分後には再生してってどれだけ致命傷を与えても死なないんですよね。
その2人が運命の出会いを果たしちゃって、そこが仲良くなるんですよ
なんだかんだプラス平瀬基樹くんっていう三角関係に今度になってきて、基樹と理保は恋人関係なんだけど、遠野実和が最初に出会ったのは理保からなのに、基樹くんの方に電話してデートに行こうよとか言ってくるわけよ。
そうなってくるとこの上條理保が嫉妬を抱きだしてだけど、遠野実和は殺せないので、こっちはどうなるかっていう話でしょ。基樹くんは普通の人間なのでね。
その三角関係がどんどん展開していくみたいな話なんだけれど、別にこれストーリーっていうストーリーは実はそんなになくて、淡々と3人の日常を描いているっていう話なんですよ。
いわゆる「内面を描く」タイプの小説なので、実は純文学にとても近くて、最後の終わり方もこれも綺麗なんですよね。
こういうラノベもやっぱりあるんだね。
18冊目は、
⑱石川博品
『耳刈ネルリ御入学万歳万歳万々歳』
富士見ファンタジア文庫 2009年
この小説も 実は
3巻まで出てまして僕が読んだのは
1巻だけなんですけど
1巻は1巻でとりあえず
完結はしますこの小説は
2つの面白さがある
と思うんですよ1つは まず
設定ですよねこれ 舞台が
現実世界ではなくて
架空の国なんですこの国っていうのが
「活動体連邦」って言われる
複数の国から成るいわゆるロシアとか
ソ連とかのような共産主義的
国家なんですよね活動体連邦の中に
「本地」って言われる
中央の地域があるんですよ
(それ以外は「王国」)主人公は そこ出身で
レイチっていう男の子がいてこのレイチくんは植物が大好きで
ある学校に入学するんですよそこのクラスっていうのは
色んな地域から
やってきてるわけですねそのうちの1人に
ネルリっていう
女の子がいてこの子は活動体連邦の
中に一応入ってて
独立はしてるんだけど
(そういう王国があって)そこの王位継承者に
なっているんですよね
だから王族になってるわけよ実はレイチくんは
あんまりないんだけど普通の「本地人」
っていうのは 周りの
「王国民」を差別してる
っていう形になっててその学校の中で 学生の
自治体みたいなのが存在していて
生徒会みたいなのがあるんだけれどその生徒会と
もう1個 防衛隊
みたいのがいて委員会は本地民しか入れないと
防衛隊は王国民しか入れないのでここの戦いが今度
起こってくるみたいな
話になってくるだけど
もう1個の楽しみ方
っていうのはこのレイチくんが
まず思考回路が
ぶっ壊れてて結構 話だけ聞くと
シリアスっぽい
じゃないですかレイチくん 思ったことを何でも
地の文に書いちゃうから
ギャグがめちゃくちゃ多いし下ネタとかもあったりとか
色んなパロディのネタが多くてこれ設定自体は
現実じゃないのに
ジョジョのネタとか各種マンガ・アニメとかの
有名なフレーズとかを
使ったりとかするんでこれもカオスに
なってくるんですよねどっちかだけでいいだろう
っていう感じなんだけどどっちも入れちゃうことで
世界観が本当に混沌になってる
っていうのがあるんですよここがラノベ奇書だろうね
面白い とても面白いと思った。
19冊目は、
⑲木戸実験
『かまいたちの娘は毒舌がキレキレです』
スマッシュ文庫 2012年
この話も設定がめちゃくちゃ詰め込まれすぎてるんですよね。
まず「風海きりか」っていう女の子がいて、この子はラノベをめっちゃ読んでるんだけど「反ラノベ」っていうか「ラノベなんかつまんないよ」とか言って色々言う子なんですよ。
その子と もう1人同じクラスメイトの神前静也っていう男の子がいるんですよ。
この子は実は学生なのに中国マフィアの幹部なんですよね。
実はこの世界っていうのは人間に妖怪の力が宿った能力者っていうのが何人もいる世界で、手から風を出せるとか火を使えるとか能力者がいるんだけど、この神前静也くんはめっちゃ強い妖怪の力を持っているんですよ。
この静也くんときりかちゃんが知り合って色々ラノベについて語ったりするんだけど、のちに これは静也くん
幹部なのでなんだかんだ
きりかちゃんの家の
お母さんが麻薬を盗んだりとかして
勝手に使ってたっていうことで処分しに行かなきゃいけない
ってことで行ったら
そこにきりかちゃんがいてきりかちゃんが
目撃者になっちゃって
きりかちゃんを殺さないと
いけないってことなるんですよ静也は
マフィアの幹部なんだけれど
きりかちゃんを殺せなくて2人で逃げちゃう
っていう話に
なっていくんですよそうするとマフィアのやつが
裏切り者になっちゃうわけだから
襲いかかってくるんですよねそこで
能力者バトルみたいのが
発生するんだけどこれもう1個 実は
叙述トリックが
隠されていて叙述トリックと時間軸が
シャッフルされてるっていう
独自の構成になってる
っていうのがあるんですよそれを詰め込む
必要もあるか
わかんないんだけどやりたいことが
めちゃくちゃ
やってるんですよねだからちょっと
独自な路線
ではあると思う色んな捉え方ができるような
終わり方のような気もするから僕としては
けっこう感情がバグりました。
最後20冊目は、
⑳大樹連司
『勇者と探偵のゲーム』
一迅社文庫 2009年
これ 本当
問題作だと思うまず これも設定が
かなり入り組んでいてある町があって その町には
「日本問題象徴介入改変装置」
っていうのが導入されてるんですよその装置は
何かって言うとその1つの町なんだけど
もっとでかく見ると日本が
あるわけじゃないですかその日本で 例えば
少子高齢化とか自衛隊をどうするかとか
色んな法改正みたいのが
あったとするとそれらの問題が この町で
ある事件みたいなのが起こって
それが解決されるとその日本のでかい問題も
知らん間に解決されてるっていう
極めて社会的な装置なんですねだから実はこの町は
その装置のせいで常に毎日のように
悪の組織がやってきたり
巨大ロボットが出てきたりゴジラみたいなのが
出てきたりして それと
戦う勇者がいたりもしくは毎日のように
殺人事件みたいなのが
どこかしらで起こっててそれを解決する探偵
っていうのが出てきて全部 勇者と探偵によって
それらを解決してくれるんですよそれを解決すると
日本でも解決される
ってことだから
いいことなんだけど主人公たちは
その町に住んでるからもう毎日のように
ドンパチが行われている
わけですねなんだけど
ここで ある1つの
事件が起こってそれはクラスメイトの
野井奈緒ちゃんっていう女の子が
屋上から事故で落ちちゃったとこの事故には
意味が
ないんですね奈緒ちゃんが
自殺したわけでもなくて奈緒ちゃんが
殺されたわけじゃなくて
ただの事故なんですねこのクラスメイト・この町では
全ての事件とか事故とかには
意味があってこの意味っていうのは
日本の問題を象徴
している意味なのでそれを解決する
探偵も勇者も
いるはずなのにこの野井奈緒ちゃんが
ただ死んだだけの
事故死では意味がなくてこのクラスメートにいる人達は
この意味のない死が認められない
っていうか受け入れられなくてなんで この野井奈緒ちゃんが
意味もなく死んでしまったのか
っていうのをめちゃくちゃ考えてどうしようって考えた
時に 主人公たちが
1つ考えて導いたのはこの意味のない死を
意味のある死に変えよう
じゃないかっていうわけでどうやってするかっていうと
野井奈緒ちゃんが
事故死したことは実はその裏側に「邪教神団」
っていう得体の知れない
宗教団体がいてそのある儀式を行っていて
悪魔とかを召喚するために犠牲として
野井奈緒ちゃんが殺されたんだ
っていう設定を自分たちで作るわけそのクラスメイトたち
全員じゃないけど 十何人が
邪教神団っていうのになって変な魔法陣とかを
わざとらしく
その辺の道とかに
作ったりとか変なキーホルダーとかを作って
その辺に置いたりとかするわけですよそうすると 周りの人たちが
邪教神団って本当にいるのかなと野井奈緒ちゃんは
ただの事故死
だと思ってたけどこいつらに
殺されたんじゃないか
と思い出すわけです最終的に行きたいのは
探偵・勇者がやってきて野井奈緒ちゃんは
実は事故死なんじゃない
って言った時に意味のあるものに
なるわけなので探偵とか勇者とか
呼ぼうとしているわけそれでどうなるか
っていう話なんだけど
これ 色んな意味で
問題作なんだよねえ。
そんな感じで、以上この10冊を紹介してきました。
なんか発想がバグってるのが面白いね。
ラノベだからといってもしくは表紙が可愛らしい女の子が映ってるイラストだからと言って読まないっていうのは、もったいない気がしました。
皆さん 何かしらこういう変わったラノベを知ってたら ぜひコメントで
教えてください。
ラノベについて僕は別に詳しいわけじゃないのでヤベエやつあるよっていうのがあったら教えてください。
そんな感じで、今回は終わります。
高評価・コメント・チャンネル登録どうぞよろしくお願いします
ではでは、つかっちゃんでした、バイバイ!
https://www.youtube.com/watch?v=ETjV1Wxkszc
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・#899「【購入】エロすぎる奇書16冊の本を買ってきました!」
購入本紹介動画のため、購入本を羅列します。
1.「文藝」 2023年冬季号
2.伊藤ヒロ・満月照子『家畜人ヤプーAgain』
3.おおつやすたか『まるくすタン 学園の階級闘争』
4.柚原季之『ひまわりスタンダード』上
5.柚原季之『ひまわりスタンダード』下
6.しんかいちさとみ『ヒ・ミ・ツの処女探偵日記 金田一流の事件簿』
7.松平龍樹『発情期 ブルマ検査 十二歳の淫らな同級生解剖』
8.睦月影郎『永遠のエロ』
9.綿貫梓『インモラル古書店 〜近代エロ文学をもっといやらしく読む方法〜』
10.安達瑶『世界最終美少女戦争』
11.仙田学『ツルツルちゃん』
12.大藪春彦『餓狼の弾痕』
13.山田風太郎『奇想小説集』
14.神林長平『あなたの魂に安らぎあれ』
15.神林長平『宇宙探査機 迷惑一番』
16.グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ』(上)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
