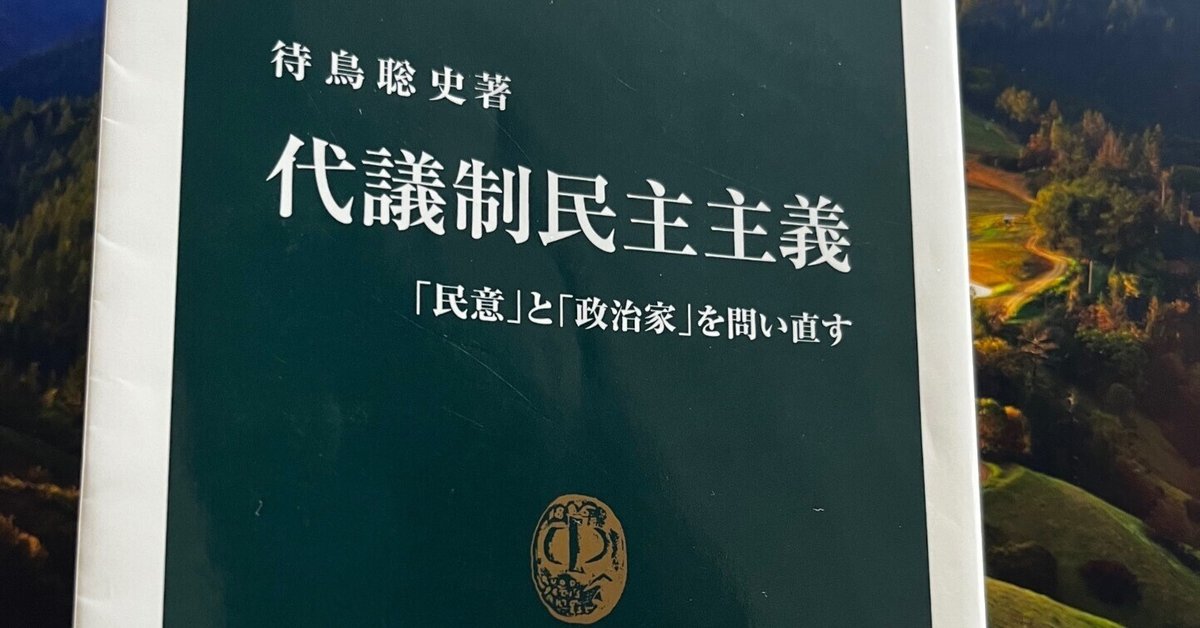
待鳥聡史『代議制民主主義〜「民意」と「政治家」を問い直す〜』(2015、中公新書)
【書評】
巷でよく聞く「民主主義」とは何かについて、一から考えさせられる本である。代議制民主主義の成り立ち、自由主義的要素と民主主義的要素によって構成されていることなど、全く気にもしたことがなかったため、まさに目から鱗であった。
近年、新聞をはじめとするマスメディアで、民意を無視した政策決定を政府与党が行ったとし、「民主主義の崩壊」という文字をよく目にする。しかし、本書で述べられている通り、代議制民主主義は、政治家に対し一定の裁量を与えている。そもそも、代議制民主主義を構成する自由主義的視点からすると、「多数者の専制」を防ぐために本制度が生み出されているのである。民意が必ずしも正しいとは限らない。従って、短期的、個別の問題に関しては有権者の意見と相違していても、中長期的あるいは社会全体にとって有益になると政治家が判断し、判断に基づいた政策決定は容認されるべきである。ただし、政策決定から政策実施、政策評価と終えたのちは有権者に対し説明責任(アカウンタビリティー)を果たす必要がある。もし、政治家による判断が間違っていたとなれば次の選挙で落選させるなど制裁を科せば良いだけのことである。
議会制民主主義を構成する両要素の関わりは絶妙である。自由主義的要素が競争によって獲得する効率性と民主主義的要素が目指す公平性は、政治以外の分野でも両立されるべき基本的価値である。そういった意味で、近代国家が目指す普遍的目標と代議制民主主義は親和性が高く、魅力的な政治制度であると感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
