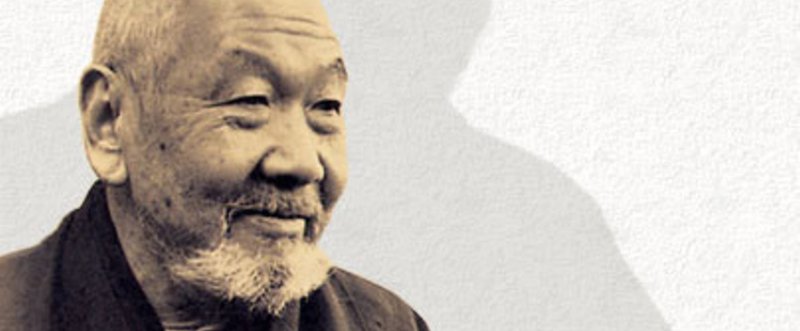
三宅雪嶺─宇宙永遠の理念「真善美」に生きた哲人
山縣有朋に向けられた「命がけの筆誅」
幸徳秋水の処刑から二週間後の明治四十四年二月六日、「大逆事件に関する立国大本講演会」の会場となった国学院大学は、三宅雪嶺の一言で大混乱に陥った。左翼勢力を沈静化させることを意図して、内務省地方局長床次竹二郎らの首唱によって開催されたこの講演会に、雪嶺は山岡熊治、南条文雄、渋沢栄一、井上哲次郎らとともに参加していた。
講演会開催前、内務省嘱託の留岡幸助は、雪嶺に登壇を依頼した陸軍中佐花田仲之助に念を押していた。
「三宅なんか頼んで、飛んでもない脱線したことを言われはしないか」
だが、花田は「ソレは大丈夫だ、我輩が懇意なる間柄で、よく斯く々々こういふことを喋舌ってくれと頼んできたから」と胸を叩いたという。
登壇者たちは、床次や花田の意図した通り、幸徳秋水非難に終始した。井上哲次郎も、「陽明学と仏国革命思想と社会主義」の危険性を説き、講演会は無事に終了するかに見えた。
だが、「四恩論」と題して雪嶺が講演を始めるや、会場の空気は一変した。雪嶺は、「大逆事件」に対する強い疑念を表明し、幸徳をあたたかく弁護したのである。しかも、「君側に妖者があるから畢竟こんな事が起こり、こんな不都合な事後策をやるのだ」と、主催者や政府・元老などを痛烈に批判した。
主催者たちは狼狽した。千数百名を超える会場は騒然となり、中央倶楽部の代議士荒川五郎は怒号し、登壇中の雪嶺に怒りを露にして、「質問だ、質問だ」と喚いた。さらに荒川は、「このような失態は主催者である床次の責任だ、処決せよ」と騒ぎ、会場は大混乱に陥った。主催者は、慌てて閉会を宣言せざるを得なかった。降壇して退場する雪嶺に、聴衆は一斉に「万歳ッ」「博士万歳ッ」と絶叫した(佐藤能丸『明治ナショナリズムの研究』芙蓉書房出版、平成十年、百五十六、百五十七頁)。
留岡幸助が懸念した通りの結果になったわけだが、こうした事態は十分予想されたことだった。雪嶺は、一貫して幸徳を擁護していたからである。
幸徳が、キリストの存在を否認する、センセーショナルな一書『基督抹殺論』を獄中で書き上げたのは、前年の十一月のことであった。幸徳は明治四十四年一月十三日、彼の親友で、『新仏教』の編集長を務める高島米峰に宛てて手紙を書き、日頃尊敬している雪嶺先生に『基督抹殺論』の序文を是非とも書いて欲しいと次のように伝えた。
「雪嶺先生の一言が願へると、僕の臨終に、此上とない引導だけれど、目下の僕から、直接先生に音信するのは、遠慮すべきが当然だし、こんなことで、多少共、先生が迷惑を感ぜられるやうのことがあっては済まぬから、強ひて願へぬが、若し出来るなら、僕は切望に堪へぬのである」
一月十八日にこの手紙を受け取った高島は早速雪嶺を訪問し、序文を依頼した。雪嶺は即座に快諾した。この日は幸徳らに死刑の判決が下された日であった。雪嶺は翌十九日、口述筆記を常とする彼としては珍しく、直筆で序文を一気に記した。
「其の性格を推すに、若し文政天保に生まれば、恐らく勤王家として、骨ヶ原の露と消えたるべく、若し規則正しき教育を受け、大学教授の職を奉せば恐らく博引傍証、微を析き細を穿ち、学術に貢献したるべし。……其の濫に神の子を抹殺するを以て、大逆を敢てするの偶然ならざるを説くは、更に疑はし。……秋水は、既に国家に在りて不忠、剰へ大不忠、家族に在りて不孝、剰へ大不孝、不忠不孝の名に於て、死を求めて死に就く、悪とせんか愚とせんか、将だ狂とせんか、誠に適当なる形容詞なきに苦しむも、窮鼠と社鼠と、執れか択ぶべしとする」
ここでいう「窮鼠」とは、権力によって追い詰められた幸徳を指す。問題は、「社に巣くう鼠」を意味する「社鼠」の解釈である。雪嶺の反骨精神、批判精神を称えた小島直記は、ずばり次のように指摘する。
「『社鼠』とは……体制側のエリートで、主君の権威の裏に隠れて、ぬくぬくと私欲、野望を満たしている元勲、閣僚、端的にいえば、俸給取りのくせに九つも大別荘を持って天下ににらみをきかせる山縣有朋…など、思い上り、腐り切っていた連中を諷するものである」
そして、小島は「秋水とそういう連中と比較した場合、人間の生き方としてどちらが『悪』か『愚』かわからないぞ、といっているのである」と、雪嶺の序文を解したのである。
この序文を受け取った幸徳は、歓喜の中で筆をとり、「先生の慈悲、実に骨身に沁みて嬉しく、何となく暗涙が催された。僕は、此引導により、十分の歓喜、満足幸福を以て成仏する」と書き残した。幸徳が処刑されたのは、その翌日一月二十四日のことであった。
現在では、大逆事件が時の権力によるでっちあげ事件であったとの説が有力になっているように見えるが、当時はそのような主張をすることは許されなかった。そうした状況の中で、敢えて雪嶺は思想的には相いれない幸徳擁護を全うしたのだった。小島は、このときの雪嶺の行動を「命がけの筆誅」と表現し、彼の文人としての「志」はここにつきていたと評している。
「渾一観」─我と宇宙の生命の連動
文人としての雪嶺の志は、犬養毅との「決闘」においても示された。
雪嶺らが旗揚げした「政教社」が発行する雑誌『日本人』は、明治二十一年六月、松岡好一(筆名は吉本襄)の「高島炭礦の惨状」を載せた。長崎市高島にある高島炭鉱は、佐賀藩から後藤象二郎が買い上げて操業していたが、後藤が三菱財閥に権益を譲ってから本格的な採掘が開始された。高島炭鉱では納屋制度によって、長時間労働、中間搾取等、過酷な労働条件を強いられ、鉱夫の暴動が相次いでいた。その現状を松岡は次のように批判した。
「人類たる三千の坑夫を使役駆遂する最苛最酷にして、牛馬もただならず、惨たんたる状況は、仏氏のいわゆる修羅の巷にして、坑夫はさながら餓鬼のごとく、事務員、海岸取締員、小頭、納屋頭、人繰は青鬼赤鬼のごとく、炭礦社長はエンマ大王のごとし」
八月三日には、雪嶺自ら筆をとり、「高島炭礦舎が三千の奴隷を虐使するは、慈仁の名ある帝国人民の体面を毀傷せんとするものなり」と批判した。
ところが、当時朝野新聞記者だった犬養毅は、松岡の書いた炭鉱事情を否定し、三菱を擁護する記事を書いたのである。これに激怒した松岡は、九月三日付で、「如何にも天下の公道に相背き候と心外無念に存候間、謹んで決闘状呈上仕候」と、犬養に決闘を挑んだ。このとき、雪嶺は、志賀重昂とともに、松岡の介添人を買って出たのである。
小島は、この事件について「三宅雪嶺という文人の熱い血、侠気のきざし」が現れていると書いている。
松岡の決闘状は社会的に大きな影響を与え、決闘の申し込みが相次ぐ事態となった。その結果、明治二十二年十二月に「決闘罪ニ関スル件」が発布されている。
私たちは、こうした型破りな行動を雪嶺の文人としての気概を示すものとして理解するだけではなく、宇宙永遠の「真善美」を求めた哲人としての雪嶺という側面から考えることができる。雪嶺は、政治イデオロギーに左右されるような狭い考えを持ってはいなかった。もっと深いところで、彼は日本人としての「真善美」を考えていたのである。
人間社会の発展に関する雪嶺の深い考察は、彼が明治四十二年一月に刊行した『宇宙』に余すところなく示されている。
ここで彼は、宇宙を単なる物質的存在と考えず、一つの活発な有機体、生命あり精神生活をさえもつ有機的大生物(超絶的に大なる我)と見た。そして、人間(我)の生命もまた絶大な、その有機体の一部と見て、生前死後、小我大我渾然たる大生命に生きているとした。この連動性を雪嶺は「渾一観」と呼んだ(柳田泉「解題」『三宅雪嶺集』筑摩書房、昭和四十二年、四百二十八頁)。
雪嶺は、自然科学、宗教、哲学を総動員して、渾一観を裏づけようと試みた。この壮大な試みは、ほぼ雪嶺で最後となった。長谷川如是閑は、近代自然科学の発展によって、人間の知識の質量が急速に拡大し、全体を統べることが困難になったことにより、総合的な哲学構築の試みは十九世紀で終焉したが、雪嶺はこの困難を克服しようとしたととらえ、その意義を称えている。長谷川は、『宇宙』が総合哲学の最後だとも書いているほどだ(野依秀市編著『三宅雪嶺先生を語る』帝都出版、昭和二十二年、五、六頁)。
渾一観に至った雪嶺は、常に宇宙の目的に沿った人間の生き方を追求していた。だからこそ、政治的対立を超越して、広い視野で理想を語ることができたのではなかろうか。
頭山満は、雪嶺のことを「あんな貧乏であんないい顔をして居るものはない。三宅は仙人だよ」と語っていたというが、渾一観に到達したからこそ、雪嶺は達観した人生観を持つことができた。実際彼は、「今死んでも何も思い残すことはない」という境地に達していた。あるとき、雪嶺はそう考える理由について、自分が仮に寛政年間に生まれていれば既に自分は死んでいる、元禄に生まれていたなら今は枯骨となっていた、実際よりも早く生まれていたとさえ思えば死ぬことは少しも惜しくはないと語っている(前掲書、三十七、四十四頁)。
『宇宙』においても、彼は「生くるも、死するも、常に宇宙に在りて絶大なる活動に与る。……宇宙間に存在する一切は相互に密接の関係を有し、如何なる微物といへども之より漏るゝあらず、身体分解後の元素若しくは化合物は永遠に何等かの関係あり」と述べ、宇宙全体の上においては「死」ということは考えることはできないとまで書いていた(『三宅雪嶺集』改造社、昭和六年、百八十五頁)。
「護国と博愛」の両立
雪嶺はいかにして、渾一観の境地に到達することができたのであろうか。
彼は、万延元(一八六〇)年五月十九日、加賀藩家老本多家の儒医三宅恒の子として生まれた。父は幕府を快く思わず、勤皇思想に傾き、時として断言明言したという。雪嶺は慶応二(一八六六)年、河波有道の私塾に入門、十二歳までそこで四書五経、『皇朝史略』などを学んだ。また、「これからは英語が必要だ」という意識を持っていた雪嶺は、英学を主とした中学東校に入った。そして、明治九年に上京し、東京開成学校予科に入学する。
翌明治十年、同校は東京大学と改称され、明治十二年に三宅は文学部哲学科に進む。すでに彼は「哲学を比較的根底あるように心得て」いたからである。ここで、雪嶺は中村正直、外山正一、フェノロサらから指導を受け、スペンサーやカーライルの著作を乱読したという。注目すべきは、雪嶺が、社会を生物体になぞらえて生成発展する有機的統合体とみなし、個々の要素が全体の中でそれぞれの機能を果たすと考える「社会有機体説」を唱えたスペンサーの思想から強い影響を受けたことである。これが、『宇宙』にも活かされている。
また、この時期雪嶺が「漸進主義」を標榜する丸山作楽らの『明治日報』に属していたことは、彼の「国粋」への着目を促すことになった(中野目徹『政教社の研究』思文閣出版、平成五年、八十二~八十四頁)。
明治十六年に卒業した雪嶺は、外山の世話で準助教授の肩書きで大学編纂所に入り、日本仏教史の編纂に当たった。ただし、彼は単に歴史編纂にだけ関心を持っていたわけではなく、例えば明治十七年には自由党関係の秩父暴動を視察するなど、時事問題にも強い関心を示していたようである。その後大学編纂所は文部省編集局に再編されたが、雪嶺は明治二十年に役所仕事に対する不満から辞職してしまう。こうして、彼はいかなる権威からも拘束されない、在野人として生涯生きていくことになる。明治四十年に京都帝国大学は初代文科大学学長に雪嶺を招こうとしたが、彼はこれを謝絶した。林銑十郎内閣においては、文部大臣への入閣の要請があったが、これも辞退している。
彼は自らの言論の自由を確保するために、大新聞への執筆すら躊躇した。書きたいことを存分に書けると判断し、世間からは評判の芳しくなかった野依秀市の『帝都日日新聞』への執筆を開始するにあたり、彼が大新聞を「富弱新聞」だと批判、「金を出しさえせば、何頁でも紙面を提供し、引札の代りにしてくれる、金を出せば針小棒大となり、金を出さねば棒大針小となり、世間を誤るを憚らない」と厳しく批判したことも、言論人としての志を示している。
さて、文部省を去った翌年の明治二十一年に、雪嶺らは国粋主義を標榜する政教社を旗揚げし、雑誌『日本人』を創刊する。彼らは、極端な欧化路線に反対し、日本の伝統文化を称揚したが、偏狭なナショナリズムとは一線を画していた。
雪嶺は『日本人』に時事を中心とする論説を書いていたが、超時代的な大理想を示す論説も少なくない。早い時期から、彼は大記者と哲人の両面を備えていたのである。鹿野政直は、現実政治への関心が強ければ強いほど、逆に〝隠遁者〟的な生活への強い志向がはたらいて、結局雪嶺はこの相反する方向への引力のただ中で生きてゆくことになったと見る。その後、明治四十二年六月に『太陽』が企画した「新進二十五名家」の「理想的記者」の部門で、雪嶺は徳富蘇峰、島田三郎、池辺三山らを断然引き離して第一位となり、一方明治四十三年六月には、『冒険世界』が発表した「現代各方面の痛快男子十傑」の「学者」の部門で、第一位に輝いている。
鹿野は、明治二十四年に雪嶺が刊行した『真善美日本人』を、現実への関心と普遍への志向の鋭い接点に著されたものと位置づける。ここには、西洋近代文明を絶対視せず、日本人が、その独特の立場から真、善、美の活動を極め、欧米人のそれの欠陥を補い、人類の真の理想を実現すべきだという雪嶺の考え方が明確に示されている。いま少し具体的に言えば、「真」においては、西洋から学んで科学的国家となるとともに、東洋の文物を研究する道をひらくこと、「善」においては、国家の独立を維持し、人権公徳の実現をはかり、進んで正義を世界に行なうこと、そして「美」においては、大いに東洋、西洋を学んで美術の各面にわたって壮大の美に進むべきことを主張した。
雪嶺は、決して日本のためだけに自己主張をするのではなく、人類文明の発展のためにこそ、日本人がその能力を発揮すべきだと強調していた。それは、『真善美日本人』の表紙に、大きく白抜きで書かれた次の一文に凝縮されている。
「自国の為に力を尽くすは世界の為に力を尽くすなり。民種の特色を発揚するは人類の化育を裨補するなり、護国と博愛と奚ぞ撞着すること有らん」
『真善美日本人』は、理想日本の実現を目指したものだが、同時に雪嶺は『偽悪醜日本人』を書き、現実日本に対する痛烈な反省批評も展開していた。文部省に支配された学問、実業の発達を妨害する紳商、政商の存在、皮相的な西洋美の模倣を批判した。そして、東洋哲学の体系化を志し、『我観小景』、『王陽明』の刊行を経て、雪嶺は『宇宙』で独自の総合哲学を固めるのである。
日本人の多種多様な活動を奨励
『日本人』は明治四十年に陸羯南率いる新聞『日本』と合流、『日本及日本人』に発展していたが、雪嶺は大正十二年に政教社から離脱を余儀なくされる。その背景には、中野正剛の存在があった。東京朝日新聞記者を務めていた中野は、大正二年に雪嶺の長女多美子と結婚し、雪嶺との関係を深めていた。中野は、大正十二年七月政教社の経営状態の悪化を見かねて、自ら主宰する東方時論社との合同を前提として資金的な支援をしようと動き始めた。その際、中野が『日本及日本人』の誌名、政教社の社名の変更を求めたことが、政教社同人の反感を買った。
それでも、八月二十一日の会合で、一旦政教社と東方時論社の合同成立が発表されたのだが、不幸にも九月一日に関東大震災が起こり事態は混乱していく。震災が原因で、政教社は全焼、雑誌、図書の在庫、紙型を失ってしまった。そこで、雪嶺は政教社を清算し、新しい経営基盤の上に立って『日本及日本人』を継続しようとしたが、同人の理解は得られず、自ら政教社を去ることになったのである。そして、雪嶺は中野とともに我観社を創設し、『我観』を創刊した。
雪嶺の離脱の背景には、雪嶺の妻花圃に対する同人の反感、また『女性日本人』の不振もあったとされている。しかし、中野目徹氏は「偶発的な出来事と見るよりも、左右対立の時代思潮を象徴する一つの思想史的な事件として捉える方が適切であるように思われる」と指摘する(中野目徹「三宅雪嶺伝記稿(五)」『近代史料研究』七号、平成十九年、七十八頁)。
「思想史的」とは、白虹事件などをめぐる民族派との軋轢を指す。大正七年八月、シベリア出兵や米騒動に関連して寺内正毅内閣を激しく批判していた大阪朝日新聞が、記事の中で内乱が起こる兆候を指す故事成語「白虹日を貫けり」を使った。これに憤激した浪人会などが大阪朝日新聞社に押しかけ、村山龍平社長を「国賊」と記した布切れに結び、石灯籠にしばりつける事件も発生した。このとき、『日本及日本人』は、浪人会を非難した。その結果、浪人会が雪嶺を糾弾するという事態に至った。雪嶺はまた、浪人会と対決した吉野作造らが大正八年十二月に結成した「黎明会」にも参加した。
さらに、大正九年には黎明会会員でもあった森戸辰男がクロポトキンの論文「パンと奪取」を翻訳して発表した結果、東大を追われただけではなく、新聞紙法第四十二条の朝憲紊乱罪で起訴された。このとき、雪嶺は吉野、佐々木惣一らとともに森戸の特別弁護人を務めた。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
