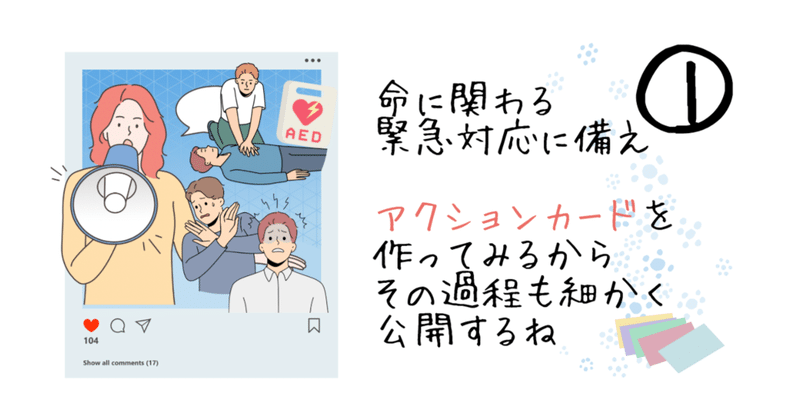
[備えよ常にプロジェクト]緊急時アクションカードを作り直す2023年春①
最終更新2023年4月22日

アクションカードとは

こちらを、添乗先で対応するツアーナース発進使用に実務で活かせるように作ろうではないかという試作。
昨年、作ってみたものの
ベースとなる行動フローに即しているようでいなかった等、お粗末な内容と気づき。なおかつ、ここ数ヶ月でアクセスが急増していたため、おそらくどこかで叩かれているのでは?と怯え。
兎にも角にも、業務上いのちを守る体制を整える意味でも重要な役割を果たすので、作り直してみます。
ご注意を
◇備えよ常にプロジェクトと大きく出てみたものの、わたし個人で使うためだけのもので。本気で拡散するのであれば、救命関係の専門家のアドバイスなど、きちんと受けなければならず。その予定も伝手もないので、とりあえず独学でやっています。緩くてすみません。
◇ご参考にして頂く分にはいくらでも。
既存のものでは使えないのか?
アナフィラキシー対応という括りで、学校団体関係で一番メジャーなのは、東京都のフローかと思います。
ー参考 東京都

そちらをベースに各自治体で工夫し、より使いやすくなっています。私が調べた限りでは、名古屋・香川県版がクオリティ高いかと。
ー参考 名古屋市教育委員会

ー参考 香川県小児科医会

何よりもわかりやすい
ただ、これらはあくまでフローだけで
アクションカードは付属せず。
学校保健会のアクションカード

こちらがメジャーであり、このカードでトレーニングをしている団体が多そう。となると。下手に新しいものを作るよりは、準じたものを…と思ってはいたのですが。
そもそも、これでトレーニングしていたら
有事にどうぞと救急バッグと共に、我々ツアーナースに渡されるはず。だが私の経験上、一度もないし周りからも聞いたことはない。
ということは、宿泊行事に備えて
アクションカードを用いたトレーニングをしている団体は多くないと、見做して良さそう。安直かしら。こちとて10年ちょいこの業界いますからね。
加えて、こちらのアクションカードは
看護師・養護教諭がいない状態の、一般職員で動けるように、事前にトレーニングを重ねた上で補助的に用いるカンペ的な役割。
一方、ツアーナース業の現状は
看護師同行するなら大丈夫っしょと言わんばかりに、有事ほぼ丸投げ状態。その即席メンバーの中で、素早く的確に冷静に指示出しして命を救わなければなりません。そんなん、仕込みなしに対応できん。
完璧にとは言わずとも、なるべく的確に役割分担ができるよう下準備としてのアクションカードはあるに越したことない。
ただ現状、看護師がいつつトレーニングを積んでいない(エピペン本体すらどんなものか知らないし、心肺蘇生法もわからないかも)な方々向けのアクションカードはこの世になかったので、己のために将来ピンチに陥る傷病者のために作成してみます。
これ、かなり時間がかかりそうで心折れそうなので
己を鼓舞するためも含めて、経過を綴りながらやっていきます。
長い前置き以上。
まずは模倣版から作成
ツアーナース版を作る前に
まずは、既存のもの=学校保健会のカードををベースに
わかりやすく諸々付け加えて作成してみます。
ー発見者

心肺蘇生法は、イラスト入りの方がいいかなと。
日本循環器学会のが一番わかりやすかったので
添付したんですが、個人利用の範疇だったらいいかなと思って。引用記載もしておかなきゃな。
そもそも発見者の立ち位置
看護師が発見者の場合:そのまま傷病者対応へ
別の先生が発見者:看護師駆けつけ次第、記録係へ
引率みんなが発見者の場合:できれば保健担当教員が記録を(管理職・担任には別の役割を振りたい)
児童・生徒が発見者の場合:上記同様だが、集まり具合に応じて
色々想定せねばならんな。キリないな。
ー管理職

管理職、人員不足に応じて
各種連絡や、救急車誘導も兼任してもらう可能性もあり。
人数少ない時の兼任要項も考えて&記載しておかなきゃなー。
ー教員A 準備

ー教員B 準備

エピペンを知らない場合はあり
あくまで、ツアーの寄せ集め人員で
訓練していない可能性が大いにある方々対象。流石に教員は簡単に研修が受けたことがあるとして、それ以外の場合ですよね。
スポーツ合宿とか、一般団体の添乗時。
そうなると、エピペンなにそれ?状態の人に持ってこいやとお願いする場合も。
よって、エピペン現物の写真は必須かと思います。
ただ、この試作品の写真はイマイチで。
別途、打ち方シートはあるのでもっと端的に。どっちが上で下かとか。
ケースあけてからな!とかそういったぱっと見情報でいいのかな思うのでやり直し。
エピペンは複数本の場合も
これは可能性大。
本人・看護師・担任の3者で持っていることもあるという可能性も想定しておかなきゃな。
どこにあるかわからない可能性
あと、エピペンのありかを本人に聞き、本人もう意識やばかったら部屋や鞄を探すなど具体的な指示も書かなきゃ混乱しそうです。
探していて時間食うよりは、とりあえず本人荷物一式持ってくる!という記載でいいかも。というわけで、UPして早々ですが修正が必要ですね。
アナフィラキシー初発で、そもそも薬ない
これは大いに可能性大なので、ない場合の役割分担=看護師側にいて傷病者対応サポートしてという記載は必須。
ー職員C 救急要請

細か過ぎと思いましたが
A4半分にしてカードという前提だと、意外と大丈夫(試作済み)。
スピーカーモード推進も大事かなと思います。
119番通報はよほど慣れていないとパニくるので、ガイド的な記載は必要ですね。
ー職員D 連絡

宮城の養護教諭さんのレポートを参考にさせて頂きました。

これ役割的に
担任がベストと思いますがどうでしょうか。
ー職員E 救急車誘導

誘導は場所にもよるので
最悪、119番通報した人がそのままやるのがいいと思うんですよね。
ー職員F 他参加者対応

超大事ですが、人員に応じては
学級委員などにお願いする可能性もなきにしもあらず。山奥で、看護師+大人3人とかなら、他の子に手が回らないかも。
ー職員G 記録

一応、カードの裏にも記録用紙を添付していますが
あくまで念の為で、別途大きなA4にプリントアウトしたものを、看護師が渡して書いてもらうようにします。
あとここは賛否あると思うのですが
救急隊は、専用の用紙を持っているので、ここではあくまで報告に使うこと・団体として対応の証拠として残すものという扱い。
よって、救急隊には渡さないという前提で作っています。
救急車に同伴する者(おそらく、看護師・担任)が、そのまま記録を持って乗ると思うし。
ーーーーーーーーーー
さて、これからプリントアウトして時の潰れ具合とか見やすさとかをチェックします。
そんで持って、あくまでこれは既存の模倣。
寄せ集めで、トレーニングしていない人たちの中でのツアーでは、そのまま使えませんし、役割として看護師が出てくるので、ちょいと作り替える必要はあります。
緊急時対応経過記録表
こちらは昨年アレンジで作成したもののまま。
そのまま行けるかなと思っています。以下、前回記事のコピペ。
ーーーーーーーー
こちらも、東京都福祉保健局が公式で立派なものを無料配布してくれています。


ごちゃごちゃしていて、
いざって時に非医療者が記入するのに向いてなさそう…と思い、若干アレンジしました。

↓ アレンジしてみた拡大

ーーーーーーーーーー
次回は、ツアー版の役割分担を考えてみます。
ベースとなるフローは、名古屋のをベースでアレンジする予定。シンプルで良い。

前述した通り、人員そんなにいない版で
保健会アクションカードの9人編成→5人まで絞って作った方が現実的かなと思っています。これ、こんなにいない時もあるから、場合によっちゃ児童・生徒になにかしらお願いする可能性もあるんだけれど、それありなのか。わからん。
①看護師
②管理職 場合によって、エピペン持ってくる 119番通報・誘導兼務
③教員A 記録
④教員B AED持ってきて、看護師サブで傷病者対応
⑤教員C 他対応、保護者連絡
とりあえず、だいぶ殴り書きですが続く。
https://note.com/tournurse/n/n59e843b295b7
