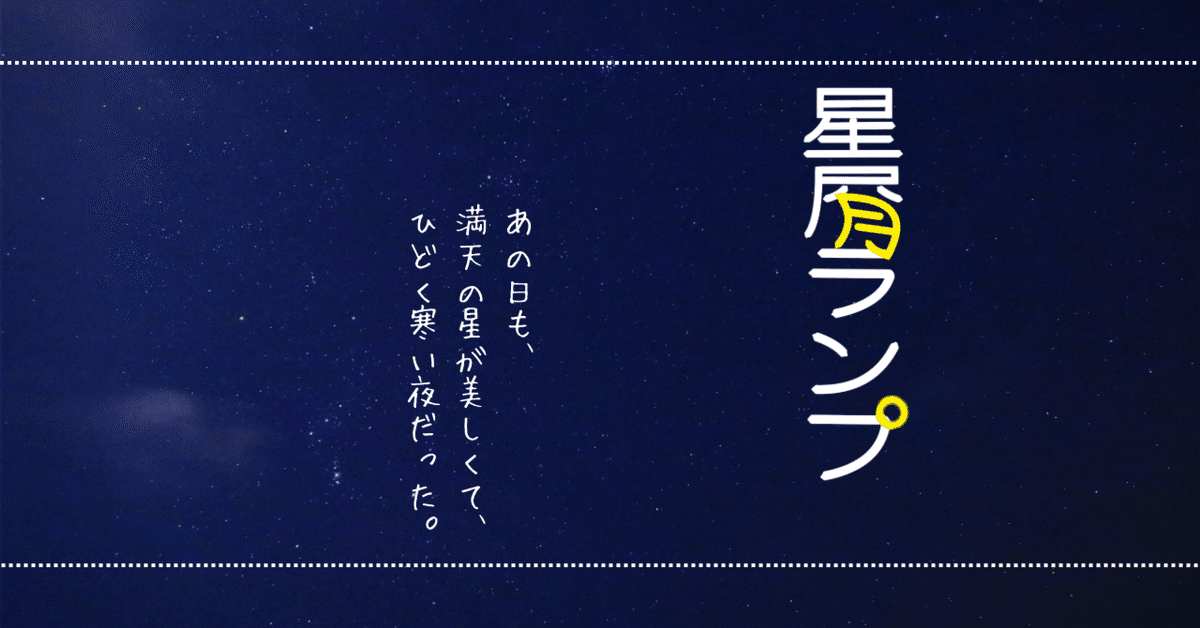
星屑ランプ【0:1:1】
「星もたくさんありすぎるとさー、
どの星がなんの星座か分からなくなるよね。」
あの人はそう言って空を見つめたまま、
冷たくなったアイリッシュコーヒーを飲んでいた。
あの日も、満天の星が美しくて月のない、
ひどく寒い夜だった。
声劇シナリオ 30~40分
【男性0:女性1:不問1】
キャラクター紹介
晶(あきら)
愛海の後輩。愛海に恋をしているが振り向いてもらえない。
演者、キャラクター共に男女不問。
愛海(まなみ)
晶の先輩で教育係だった。
仕事をする傍ら舞台役者をしている。
交通事故で死んだ恋人が忘れられずにいる。
ニュース
愛海役が兼役で読んで下さい。
特記事項
「 」 セリフ
(M) モノローグ
「『 』」 『 』内は劇中劇のセリフ
[ ] ト書(主にセリフを被せるときの指示)

1.プロローグ
晶(M)
霧の立ち込める湿原を歩いていた。
冷たい風が頬を撫でるたびにぞわりと背筋が凍りつく。
それもそのはずだ。
腕時計を見ると、時刻は午前2時を回っている。
熊笹(クマササ)にはうっすらと雪が積もって、
刺すような寒さで指先がじんじんと脈打つ。
およそアウトドアには不向きなビジネススーツ姿のまま
高原の湿地帯の木道(もくどう)を、
小さなアルコールランプを片手に歩いていた。
晶
「おっと、やっぱ滑るな。
靴を変えてくればよかった。」
晶(M)
凍ってまだらに雪が積もっている木道(もくどう)は滑りやすく、
ビジネス用の革靴は歩きにくいことこの上ない。
愛海
「星もたくさんありすぎるとさー、
どの星がなんの星座か分からなくなるよね。」
晶(M)
あの人はそう言って空を見つめたまま、
冷たくなったアイリッシュコーヒーを飲んでいた。
あの日も、満天の星が美しくて、ひどく寒い夜だった。
2.星空コーヒー
晶(M)
職場から3時間ほど車を走らせると、民家の明かりが見えなくなる。
私はオーディオのボリュームを上げて、
エンジン音をかき消すように鳴り響かせた。
やがて、道はすれ違うこともままならない急な上り坂に変わっていく。
ヒビの入ったアスファルトから自由に生えている雑草と、
石がゴロゴロと転がっている道。
時折、横から伸びた草がピシピシと車をかすめる。
道路が雪で染まり始めた頃、電波は圏外になって、
音楽の再生もいつの間にかできなくなっていた。
駐車場に着くとエンジンを掛けたまま車を止め、ゆっくりと降りる。
恐怖を覚えるほどの静寂の中、エンジン音と吐く息だけが聞こえる。
空を見上げると星の瞬きがキラキラと静かに輝いていた。
キンと冷え切った冬の空をほんのひととき眺める。
晶
「はぁーーっ 」
晶(M)
吐く息が白く染まって風に攫(さら)われていく。
あと1時間もすれば、ここも霧に覆われるだろう。
晶
「念のため厚着をして来たけど、やっぱり寒さが違うなぁ。」
晶(M)
助手席に、無造作に積んできた荷物をあさる。
アルコールランプと小さなカバンを取り出し、
駐車場から続く小道を眺める。
車のヘッドライトに照らされたそこは、
光の届かない向こう側にある闇を際立出せていた。
愛海
「[鼻歌まじりに]ウイスキーとぉー、コーヒーでしょ。
お砂糖でしょ。それから…。あっ!
ねぇ、生クリームって持ってきた?」
晶
「ないですよ。いつものフレッシュならあります。」
愛海
「フレッシュじゃなくて生クリームが良いー!」
晶
「いつもフレッシュで済ませてるじゃないですか。
ないものはないです。」
愛海
「けちー!」
晶
「ケチとかそういう問題です?」
愛海
「今日は生クリームの気分なのー。」
晶
「言っていただけたらご用意しましたよ。」
愛海
「それくらい察してよねー。使えない後輩だなぁ。」
晶
「はいはい、使えなくてすみません。」
愛海
「本当だよ、もー」
晶
「はい、カイロをどうぞ。」
愛海
「そういうところは気がきいてよろしい。」
晶
「前に怒られましたから。」
愛海
「そうだっけ? まぁいっか。行こ!」
晶(M)
ライターでアルコールランプに火を灯す。
オレンジ色のあたたかな明かりがふわりと揺れた。
愛海
「ねぇ、早く!」
晶(M)
あの人が私を呼ぶ。柔らかな笑顔で。柔らかな声で。
晶
「はいはい。すぐに行きますよ。」
愛海
「こらー、『はい』は1回!センパイに対する態度じゃないぞー?」
晶
「はい、申し訳ありません。すぐに参ります。」
愛海
「うむ!苦しゅうない。早よぅここに参れ。」
晶
「かしこまりました。」
愛海
「ぷっ…、やっぱりさっきのままでいいや。
キミがそんなに固っ苦しいと調子が狂っちゃうw」
晶
「先輩から始めたんですよ。」
愛海
「だって慇懃無礼なのがキミの定番でしょ?似合わないんだもんw」
晶
「慇懃無礼って、そりゃないですよ。」
愛海
「あははっ、ほら!行こっ♬」
晶(M)
ヘッドライトを消してエンジンを止める。
静けさが、闇とともに訪れる。
と、同時に無数の星あかりが空から降ってきた。
この瞬間がたまらなく好きだ。
ため息交じりに空を眺める。
先輩も一瞬で心を奪われたように目を丸くして、星空を見上げるのだ。
3.アイリッシュコーヒー
晶(M)
5分も歩くと湿ったベンチが見えてくる。
ビニールの買い物袋を敷いて腰掛け、ランプを隣に置いた。
豆を引いて熱いコーヒーを淹れる。
チタンマグから湯気が立ち上り、香ばしい香りが鼻腔をくすぐる。
グラニュー糖とウイスキーを入れてかきまぜ、
最後にコーヒーフレッシュをとろりと入れた。
晶
「どうぞ。熱いので気をつけて下さい。」
愛海
「ん、ありがと。」
晶
「晴れて良かったですね。星がよく見えます。」
愛海
「……。うん、綺麗だねー。」
晶
「なにか、ありました?」
愛海
「…」
愛海
「わたしね、星を見るのが好きなの。
星座とか全然わかんないんだけどさ。
綺麗じゃない?
だから、嫌なことがあったときとか、一人になりたいとき、
こうやって人のいない山奥に来て、星を眺めるの。」
晶
「知ってます。」
愛海
「そう?」
晶
「先輩がそう言ってここに連れてきてくれたんじゃないですか。」
愛海
「そうだっけ?」
晶
「えぇ。
だから私も時々この場所に来て、星を眺めるようになりました。」
愛海
「そっかー。ふふっ。そっか、なんか嬉しいな。」
晶
「はい、クッキー。」
愛海
「ありがと。……痛っ。」
晶
「あっ、大丈夫ですか?」
愛海
「うん、大丈夫。練習の時に失敗してね。」
晶
「ちゃんと病院で診てもらいました?」
愛海
「いつものことだから平気よ。」
晶
「またですか。そうやってちゃんと診てもらわないから…」
愛海
[晶のセリフにかぶせて]
「あーーっ!どうせ今夜も朝までコースでしょ?
ほーら!飲んで飲んで!」
晶(M)
私のコーヒーにグラニュー糖とウイスキーを入れてくる
先輩のいたずらな笑顔。
晶
「先輩、また勝手に入れないで下さいよ。」
愛海
「良いじゃーん。わたしも同じの飲むからさぁ。」
晶(M)
ミルクがないとコーヒーが飲めない先輩はそう言いながら、
追加でフレッシュを3つも入れていた。
それから、ついでにウイスキーも多めに。
晶
「ケガしてるならお酒は飲まないほうが良いんじゃ?」
愛海
「いいの!いいの!」
晶
「はぁ…」
愛海
「なによ。わざとらしいため息なんかついて。」
晶
「なら、勝手に人のコーヒーにウィスキーを入れないでください。」
愛海
「いいじゃない。
キミの苦手なミルクは入れてないんだからさー、
付き合ってよー。」
晶
「お?ようやく私と付き合う気になりましたか?」
愛海
「バーカw。意味が違う。」
晶
「えぇ?違うんですか?」
愛海
「キミのそれさぁ、毎回ワザと言ってる?」
晶
「今頃気づいたんです?
わざわざ言ってるんです。いつだって本気ですから。」
愛海
「……」
晶
「あ、先輩は飲みすぎないでくださいね。
お酒弱いんですし、ケガまでしてるんですよ?」
愛海
「わかってるわーかってるってば!
ここまで来て小言はなーし!」
晶
「言われないようにして下さい。」
愛海
「む~、言うようになったなぁ。」
晶
「先輩に鍛えられましたから。」
愛海
「ナーマーイーキー。」
晶
「痛てててっ!つねるのはナシっすよ。
うわっ!!あひゃひゃっ!!くすぐるのもナシですってばぁー!!」
愛海
「あっはははははっ!
はぁ~~。
山で星を見ながら飲むコーヒーはやっぱり格別だぁ!!」
晶
「それアルコールとフレッシュのほうが多いデスヨネ。」
愛海
「細かいことは言わないの!」
晶
「はいはい。」
愛海
「「はい」は1回。」
晶
「はい。」
[クスクスと笑い合う。]
晶(M)
そうして、しばらくの間、
アイリッシュコーヒーを飲みながら満天の星を眺めていた。
少なくなった虫の声と、サワサワと風で揺れる葉の音が
やたらとおおきく聞こえる。
愛海
「綺麗だねー……」
晶(M)
そう言いながら星空を眺めている先輩の顔を、横目でちらりと盗み見る。
愛海
「今日の稽古で上手く動けなかったんだよね、わたし。」
晶
「そう、でしたか…」
愛海
「……」
晶(M)
こんなとき、私はただ先輩の隣で話を聞くだけしかできない。
同意も同情も、もちろん小言やアドバイスも、
欲しがっているのではないことを知っていたから。
星空を眺めながらコーヒーを飲んで、
気持ちを吐き出す時に寄りかかれる存在でいること。
それが私に求められるもので、それ以上でもそれ以下でもない。
愛海
「役に入るとどうしても…ね。彼のことを思い出しちゃってさ。
あー、もう。どうしてこの役をやろうとしたかなぁアタシ。
今日はSEが入ってね?車の急ブレーキの音で…」
晶
「先輩…」
愛海
「フラッシュバックしてさ。固まっちゃった。
そしたら他の役者さんとぶつかっちゃってさぁー。
このザマだよ。
あはは…何をしてるんだろうね。
あ~ぁ、今日は舞台監督にも他の役者さんにも怒られるし。
当たり前だけど。危ないじゃん?
ぶつかった役者さんがケガしなくて良かったけどさー、
ダメじゃんね、わたし。」
晶(M)
私は、何も言わずに先輩の頭をガシガシと撫でた。
愛海
「ちょっ!何するのよ。」
晶
「えっとー、なんとなく?」
愛海
「下手な同情は要らない。」
晶
「なんとなくって言ってるじゃないですかw」
愛海
「ふーん…」
愛海
「……」
晶
「……」
4.綺羅星
晶
「……、あの…」
愛海
「ん?」
晶
「あの…そろそろ私と付き合いません?」
愛海
「ヤダ。」
晶
「即答ですねw」
愛海
「忘れられないからムーリー。」
晶
「振り向いてくれるまで、待ってますよ。」
愛海
「振り向かないよ。」
晶
「そうかもですねー。」
愛海
「バカなの?」
晶
「バカです。」
愛海
「可能性はほぼゼロだよ。」
晶
「完全ゼロじゃないなんてラッキー。」
愛海
「「ラッキー」じゃないわよ。」
晶
「チャンスあるならラッキーですよ。」
愛海
「やっぱりバカ。」
晶
「はは。」
愛海
「……
ね、星ってさ。キラキラ輝いててさ?
見てると嫌なことも、この瞬間だけは忘れさせてくれる。
わたしはあんな風になりたかったんだ。」
晶
「私にとっては星ですよ、先輩は。」
愛海
「ありがと。」
晶(M)
先輩の舞台を始めてみた2年前を思い出す。
仕事の時に見せる会社の先輩としての顔ではなく、一人の役者としての顔。
仕事が思うようにうまくいかなくて、
失敗続きで上司にも呆れられ落ち込んでいた時。
明るく声をかけてくれたのが先輩だった。
愛海
「ちょっと飲み行こ!」
晶(M)
無理やり連れて行かれた小さな店。
何も聞かされないまま、席に座らされる。
しばらくするとグラスを持って先輩が戻ってきて…
愛海
「ちょっと飲んで待ってて。」
晶(M)
言われるまま、ちびちびと飲んだのはアイリッシュコーヒー。
コーヒーにウイスキーを入れ、
ホイップクリームを浮かべた温かいカクテルだった。
砂糖の甘さとウイスキーのアルコールが、
熱いコーヒーとともに体を温める。
それで初めて、自分の体がものすごく冷えていたことに気づいた。
正直に言えば、生クリームも甘いものも苦手だ。
けれど、この日以上に美味しいと思ったお酒はない。
先輩の戻りを待ちながら飲んでいると、
照明が暗くなり、なにかの舞台が始まった。
やがて聞こえてきたのは……
愛海
「『やぁやぁ、これは大賢者様。
こんな薄汚いところにようこそおいでくださいました。』」
晶(M)
舞台に立つ先輩の声だった。
愛海
「『なにが問題だと言われるのですか?
……あっはっはっはっ!何を言われるかと思えば…。
ここでは、このわたくしがルールなのです。
そんな事も知らずに、のこのことここに来られるとは!』」
晶(M)
舞台に立つ先輩は普段の姿からは
想像もできないほど自信に溢れていた。
愛海
「『おい、ジョゼ!大賢者様を特別室にお連れしな!
丁重にもてなすんだ。宝のありかを聞き出すまではなぁ!
あっはっはっはっ!』」
晶(M)
一瞬で物語の世界に引きずり込まれ、あっという間に舞台は幕を閉じた。
晶(M)
あの夜。
今思えば、私にとっては奇跡のような時間だった。
愛海
「どうだった?」
晶
「……すご…かった、です。なんていうか…その、、、」
愛海
「うんうん。」
晶
「先輩、格好良かったです。
会社の中にいるときとはぜんぜん違うっていうか…。
その、、えっと……
すみません、うまく言葉にならなくて…。」
愛海
「そう? わたし、カッコ良かった?」
晶
「…はい! えっと…すごく、格好良かったです…」
愛海
「えへへー、ありがと。」
晶(M)
何も聞かず、ただ励ましてくれる先輩の気遣いに、私は救われたのだった。舞台の上で生き生きと演技をしている先輩は、
私には太陽のようにまぶしすぎる存在だった。
晶
「あの時の先輩の舞台を見て、私は救われたんです。
今でもあの舞台を覚えてますよ。」
愛海
「ありがと。
でもね、んーなんて言ったら良いかな…
明るい星はちょっとくらい周りが明るくても目立つじゃない?
ほら、オリオン座とか?
明るくて有名な星って分かりやすいでしょう?」
晶
「…? まぁ、そうですね。」
愛海
「わたしのこと、星だって言ってくれたね。」
晶
「はい!私に(とっては先輩こそが一番輝く星なんです。)」
愛海
[( )部分にかぶせて]
「あたしはね、
こんな光のない山奥に行かないと見えない小さな星なんだよ。」
晶
「そんなこと…」
愛海
「あるんだよ。役者なんて、それこそ星の数ほどいる。」
晶
「…ぁ…」
愛海
「ホラ、空を見てみなよ。
どれがどの星なんて、分からないでしょ?
気づいてもらえなくて当たり前なのよ。
星もたくさんありすぎるとさー、
どの星がなんの星座か分からなくなるよね。」
晶
「……」
晶(M)
見上げた空は、溺れそうなくらいにたくさんの星が輝いていた。
5.星屑
愛海
「知ってる?
どんなに有名になっても結局は忘れられちゃうのよ、役者なんて。」
晶
「そんなことないですよ。好きな役者さんとか声優さんとか、
ちゃんと覚えてますし!」
愛海
「それこそ世界的な大スターにならないと覚えていてもらえない。
そんな大スターでも役者を辞めたりして露出がなくなるとさ、
だんだんと忘れられて、どこにいるのか分からなくなっちゃう。」
晶
「……」
愛海
「《あの芸能人は今!》なんて番組で少し思い出してもらえたら
まだ良い方じゃない?」
晶
「…」
愛海
「この空のどこにオリオン座があるか分かる?」
晶
「あ、えーと…」
愛海
「あたしは分かんない。明るい街に行ったら分かるけどね。
その他の星は見えなくなっちゃうから。」
晶
「…」
愛海
「そんなもんよ、役者なんて。
名前がわかってもすぐに見つけてもらえないの。
特別な星以外は覚えてもらえるどころか見てももらえない。
因果な商売だよねー。」
晶
「……」
愛海
「でも、好きだからさぁ。止められないんだぁ。
演じることが大好きだから、しんどくても続けられる。
彼の事も。ずっと好きだから、忘れられない。
へへへっ。」
晶(M)
あまりにも痛々しい笑顔に、思わず真剣な声が出てしまった。
晶
「私じゃダメなんですか?」
愛海
「うん。」
晶
「…また即答ですか。」
愛海
「懲りないねー、キミも。
お芝居と、彼がいなきゃ生きていけないの、わたし。」
晶
[愛海のセリフにかぶせて]
「お芝居と、彼がいなきゃ生きていけないの、わたし。
…ですよね。」
愛海
「よく分かってるじゃない。」
晶
「先輩の一番の後輩ですから。」
愛海
「ナーマーイーキー。」
晶
「どんなに酔っていてもダメって言われるんですよね。
ホント、かなわないですよ。」
晶(M)
すっかり冷めきったアイリッシュコーヒーを再び飲み始める。
愛海
「やっぱ生クリーム持ってくればよかったなー」
晶
「フレッシュではいけませんか?」
愛海
「コクが違うのよ。」
晶
「そうですか。」
愛海
「キミがいれば生クリームだって使い切れるじゃない?」
晶
「私は生クリームを入れないので同じですよ。」
愛海
「つれないなぁ。」
晶
「本当はお砂糖だって入れないんですけどね。
ついでに言えばウイスキーも。」
愛海
[晶のセリフにかぶせて]
「ついでに言えばウイスキーも。…でしょ?知ってる。」
晶
「まったくもう、この人は…。」。
愛海
「あっ!そうだ!!そしたらさ。モーツァルト、持ってない?」
晶
「はぁ?また唐突に何を言い出すんです?」
愛海
「モーツァルト!チョコレートリキュールの。」
晶
「それは知ってます。
甘さがくどすぎるから飲まないって先輩、言ってたじゃないですか。」
愛海
「んー、今日は飲みたい気分なの。」
晶
「そんなことを言われても、いつも飲まないから持ってきてませんよ。」
愛海
「いーまー!飲―みたいの!」
晶
「ないものは出せませんて。」
愛海
「ちぇーっ。」
晶
「ふくれっ面しないでください。今度は用意してきますから。」
愛海
「ぶーー!んじゃあ、なにか良いBGMでも流してよ。」
晶
「ここは圏外ですから無理です。」
愛海
「ダウンロードもしてないの?」
晶
「してませんよ。先輩は?」
愛海
「……してない。」
晶
「でしょう?
そもそも、「ここでBGMを入れるなんてもったいない。」
って言ったの、先輩ですからね?」
愛海
「うっ…。」
晶
「どうです?思い出しました?」
愛海
「うーー、イ~ジ~ワ~ル~~~!」
晶
「事実でしょう?」
愛海
「う~~~…」
晶
「……」
愛海
「う~~!」
晶
「………」
愛海
「んも~や~だ~~!笑うなら笑いなよ~!」
晶
「ぷっ…くくくくくっ![押し殺すように肩を震わせて笑っている]」
愛海
「そんなに笑わなくてもいいじゃない!
使えない後輩のくせに~。」
晶
「先輩って、いつも酔うと子供みたいに駄々をこねますよね…
っくくくくく。」
愛海
「っな…!?っそんなことないモン!」
晶
「ほら、その言い方も駄々っ子ですよw」
愛海
「……う~~。」
晶
「…っww。っすみまっせ……wwwwww。」
愛海
「ちょっ、さすがに失礼じゃない?!」
晶
「wwwや…、うなってる先輩が可愛いなってwwwww。」
愛海
「ひょえっ?!えっ?ちょっ…」
晶
「ほら、そうやって照れて慌ててるところとか。」
愛海
「んもうっ!年上をそうやってからかわないで!」
晶
「からかってませんよ。本当のことを言っているだけですから。」
愛海
「……バーカー!」
晶(M)
ひとしきり笑ったら、また静かに星空を眺める。
ため息が、白くけむって星空に溶けていった。
愛海
「……」
晶
「……」
6.ホットウイスキー
愛海
「…ね。」
晶
「はい。」
愛海
「今度は濃い目に淹れてくれない?」
晶
「コーヒーをですか?」
愛海
「うん、ブラックで。」
晶
「え、苦手でしたよね。大丈夫ですか?」
愛海
「…うん。」
晶
「わかりました。ちゃんと飲んで下さいよ?」
晶(M)
お湯を沸かしながらゆっくりと豆を挽く。
ドリッパーにお湯を注ぐ音をただ聞いていた。
晶
「先輩、体も冷えますし、これを飲んだら車に戻りませんか?」
愛海
「やーだー!」
晶
「やーだー!じゃないですよ。風邪をひきます。」
愛海
「あっ!ならさ!ホットウイスキー作ってよ!」
晶
「え、今コーヒー淹れて…」
愛海
「良いじゃなーい!ね?
ホットウィスキーならさ、体も温まってー、
ヤなことも忘れられてー。んふふっ!
一石二鳥じゃない?あたしってば天才―!」
晶
「だから、「ね?」じゃないんですよ。
今、コーヒー淹れてるじゃないですか。」
愛海
「それはキミが飲んだら良いじゃない?」
晶
「えぇ?」
愛海
「コーヒーならいくらでも飲めるでしょ?」
晶
「いや確かに飲めますけど…」
愛海
「ねぇ、作ってー。ホットウィスキー作ってぇー♡」
晶
「ダメです。アレ飲むと手がつけられなくなりますからね、先輩は。」
愛海
「む~~~!」
晶
「ほら、もうけっこう出来上がってるじゃないですか。」
愛海
「まだ酔ってないもん。」
晶
「はいはい。」
愛海
「あー、信じてないな?」
晶
「知ってました?酔っ払いは「酔ってない。」って言うんですよ。」
愛海
「ケチー!ドケチー!」
晶
「酔っていても酔ってなくてもダメですよ。ほら、コーヒーです。」
愛海
「う~。ありがと。
…んっ…!ぅゎー…にが……」
晶
「ははっ、大丈夫ですか?…ちゃんと飲めます?」
愛海
「もうちょっと手加減して淹れてくれても良いんじゃない?」
晶
「え、これでもかなり薄めに作ったんですけど。」
愛海
「これで?」
晶
「そうですよ。
ミルクとお砂糖入れます?」
愛海
「入れても飲めなさそう。」
晶
「はぁ。なんでアイリッシュコーヒーだけは飲めるのかなぁ。」
愛海
「いいじゃん、別に……」
晶
「はい、ホットウィスキー、超薄めです。」
愛海
「そっちは薄くしないでいいのよ?!」
晶
「ダーメ。ほら、先輩のコーヒーはこっちに下さい。」
愛海
「ちぇーっ…。でも優しいね。
こうやってホットウイスキーも用意してくれるんだからさ、
キミは。」
晶
「褒めても濃くはしませんよ?」
愛海
「ちぇっ…。」
晶
「……ぁ…」
愛海
「あー、間接キス! 気にする?」
晶
「ぶっ」
愛海
「ヤダちょっときたないー」
晶
「先輩が変なこと言うからじゃないですか。」
愛海
「んふふー。なに、なにぃ~?意識しちゃった?」
晶
「っしてません。」
愛海
「お顔、真っ赤だよ~?」
晶
「そういうところなんだよなー。」
愛海
「ほーんと、ウブだよねぇ。」
晶
「…っ!違います…から…。」
愛海
「かーわいぃ~。」
晶
「[小声で]可愛いかよ。」
愛海
「なにー?なんか言った?」
晶
「なんでもありません。早く飲んで下さいよ、まったく…。
[小声で]これだから酔っ払いは…。」
愛海
「酔ってませーん。」
晶
「聞こえてるんじゃないですかぁ!」
愛海
「こんな静かなところで聞かれないとでも思ったぁ?
………クシュンっ…」
晶
「ほら、車に戻りましょう。暖房つけて暖かくしてあげますから。」
愛海
「…子供扱いしてる?」
晶
「いいえ、してませんよ。駄々っ子だとは思っていますけどね。」
愛海
「やっぱり子供扱いじゃん~~!」
晶
「してませんってば。」
愛海
「間接キッスでお顔を真っ赤にするお子ちゃまのくせに!
ナマイキだぞ!」
晶
「あはは、はいはい…」
晶(M)
先輩の残したコーヒーに口をつける。
晶
「うっす…」
晶(M)
まるで色の付いたお湯のように感じられるそれを飲み干して
片付けを始める。
やがて先輩も、渋々ながら
白湯と変わりないホットウィスキーを飲み始めた。
愛海
「ヤダ、ホントにうっす!」
晶
「せーんーばーいー?」
愛海
「……!」
晶
「勝手にウイスキー足しちゃだめですよー。」
愛海
「!!なんでバレるの?」
晶
「なんでバレないと思ったんです?」
愛海
「ふふっ…あはははははっ」
晶
「あっははははは」
7.コーヒーフレッシュ
晶(M)
息を白くして車に戻る。
愛海
「さむっ。今頃になって寒くなってきたよ?!」
晶
「ほら、毛布です。これ着てください。」
愛海
「いつも悪いねー」
晶
「いつものことですから。」
愛海
「だってキミが用意してくれるじゃない?」
晶
「そういうのを依存って言うんですよ?」
愛海
「信頼してるって言ってよね。」
晶
「そうでした。先輩はそういう大雑把な性格でした。」
愛海
「おおらかって言ってくれない?」
晶
「デスヨネー。」
愛海
「超棒読みなんだけど?」
晶
「気のせいです。」
愛海
「ってか、そもそもさー。
キミの車なんだし、一緒に寝れば良いじゃない。」
晶
「それマジでやったら先輩ブチギレしますよね?」
愛海
「あっはっはっはっwwwwww。」
晶
「笑い話で済まないですよ。」
晶(M)
車内に車中泊用のマットを敷きながら笑う。
本当は笑い事ではないのだけど。
愛海
「ごめんて。」
晶(M)
なぜ私のものではないのだろう。
こんなにも近くで、こんなにも屈託のない笑顔を見せてくれて、
弱いところも、素顔も見せてくれるのに。
先輩の愛する人はもう、この世にはいないというのに。
それでも私を見てくれることはないのだ。
これではまるで、私は…
晶
[小声で]
「コーヒーフレッシュみたいですね…」
愛海
「なにか言った?」
晶
「いいえ、なにも。」
愛海
「…そっか。」
晶
「はい。」
晶(M)
にぱっと笑う先輩の笑顔が眩しくて、私は思わず目を逸らしてしまった。
8. 夜明け
晶(M)
鳥の声で目が覚める。
寝袋とソロテントの中から抜け出し、大きく背伸びをした。
車の窓をノックする。
晶
「先輩、朝ですよ。」
晶
「?」
晶(M)
ノックをしながら声をかける。
晶
「ちょっと失礼しますね。怒らないで下さいよ?」
晶(M)
車の中で寝ていたはずの先輩がいない。
そういえば、かけっぱなしだった暖房用のエンジンも
いつの間にか切れている。
晶
「先輩?」
晶(M)
慌てて濃い霧の中を探しに走る。
10m先も見えないような深い霧だ。
晶
「はぁっ、はぁっ…先輩―?」
晶
「どこに行っちゃったんだ。
そんなに広い場所でもないのに、なんで見つからない?」
晶
「…うわっ!!! 痛ったーー…」
愛海
「わわっ、大丈夫?」
晶
「ちょっと転んだだけなんで、大丈夫です。」
愛海
「そ。よかった。
もー、気をつけてよね。」
晶
「はい、気をつけます。」
愛海
「ふふっ、寝癖すごいよw
おはよ。」
晶
「あ、おはようございます。
ってか、おはよじゃないですよ。
勝手に1人でいなくなっちゃダメじゃないですか。」
愛海
「ちょっと散歩してたの。
朝の空気、気持ちいいね。」
晶
「はーーーー。どこに行ったかと思ったじゃないですか。」
愛海
「心配してくれるの?」
晶
「そりゃ、心配しますよ。
冬眠を控えたクマだって出るんです。」
愛海
「えー?そうなの?」
晶
「そうですよ。
危ないことはしないで下さいね。」
愛海
「えへへー。気をつける。」
晶
「そうしてください。
さあ、そろそろ帰りましょう。」
愛海
「あっ! 晶は、こっちに来ちゃダメだよ。」
晶
「え、どうしてですか?」
愛海
「どうしても。」
晶
「なにか隠してます?」
愛海
「んー、どうかな?」
晶
「ってか、急にどうして名前で呼んだりしてるんですか。」
愛海
「んー、なんとなく?」
晶
「いつもどうりじゃないと、調子狂います。」
愛海
「んふーw 照れてる?」
晶
「照れてるっていうか、びっくりしてるだけです。」
愛海
「……」
晶
「……本当に、どうしちゃったんです?」
愛海
「…ね、晶。…ありがとうね。」
晶
「先輩…?」
愛海
「ずっとずっと言おうと思ってたんだ。
恥ずかしくてなかなか言えなかったんだけど。
いつもいつも、わたしなんかのために色々してくれてさ。」
晶
「やめてください。らしくないですよ。」
愛海
「ちゃんと、お礼が言えてなかったと思って。
それが心残りだったの。」
晶
「心残りって……何を言ってるんですか。」
愛海
「もう分かってるんでしょ?わたしのこと。
それなのにさぁー、ゆうべ晶に会いに行ったら
いつもの調子でコーヒーを淹れてくれるでしょー?
もうさ、あっけにとられちゃったよねw」
晶
「え?」
愛海
「いつも美味しかったよ、キミのアイリッシュコーヒー。
生クリームじゃなかったし、お砂糖も足りなかったけど」
晶
「それ、ほんとに思ってます?」
愛海
「うん、思ってる思ってる。」
晶
「思ってないでしょ。」
愛海
「ホントだってば。
暖かくて、優しくて、気遣ってくれる味で、好きだったよ。」
晶
「…アリガトウゴザイマス?」
愛海
「うふふ…
あのね。本当はキミのこと、好きになりかけてた。
あんなに一生懸命口説いてくるんだもん。
へへっ、ほだされちゃった。」
晶
「なら…どうして…」
愛海
「それでもね、忘れられないの。あの人のこと。
忘れられなくて、ずっとずっと会いたくて…」
晶
「それで…逝ったんですか…。彼氏さんのところに…」
愛海
「…うん……」
晶
「会えましたか?」
愛海
「……行けなかったの。行かせてもらえなかったの。」
晶(M)
先輩は目に大粒の涙を浮かべて首を横に振った。
愛海
「どうしてなのかな?
わたし、なんでいろいろうまくいかないんだろ…?」
晶
「それで、私に会いに来たんですか。」
愛海
「ひどい女によね、わたし。
彼が忘れられないのに。
またキミに慰めてもらおうとしてる。」
晶
「先に亡くなった彼氏さんが羨ましいですよ。
どう足掻いても私じゃ彼氏さんに絶対勝てない。
コーヒーフレッシュみたいなものですから。」
愛海
「ごめんね。」
晶
「謝らないで下さい。
こんな状況でも先輩に頼られて嬉しいって思ってるんですよ、
これでも。」
愛海
「ごめ…」
晶
「謝らないで下さいって言いました。」
愛海
「ダメっ!こっちに来ないで!!」
晶
「イヤです。」
愛海
「こっちに来たらキミまで戻れなくなっちゃう!」
晶
「イヤです。」
愛海
「バカ!!戻れなくなっちゃうって言ってるの!」
晶
「構いません。先輩のいない世界なんて私には無意味です。」
愛海
「…バカ……」
晶(M)
私は立ち尽くす先輩の腕をぐいっと引っ張り、
胸の中に抱き寄せた。
愛海
「…なんてことをするのよ…」
晶
「コーヒーと、先輩がいないと、私は生きていけないんです。」
愛海
「…なにそれ。」
晶
「えーと…、マネしてみました。」
愛海
「バッカみたい。」
晶
「あれ、ご存じなかったんですか?」
愛海
「知ってる。」
晶
「よかった。ボケたのかと思いました。」
愛海
「人を年寄り扱いしないでくれる?」
晶
「心配しただけですよ。」
愛海
「バカにしただけじゃないの?」
晶
「違います。ふふっ…」
愛海
「やっぱりバカにしてるでしょ。」
晶
「してませんって。」
愛海
「んもうっ!バーカ。」
晶
「はい。」
愛海
「ね?」
晶
「はい。」
愛海
「バイバイ…しなきゃ。」
晶
「行かせませんよ。」
愛海
「ニュース、見たんでしょ?」
晶
「……」
愛海
「だから、ここに来た。」
晶
「!?……」
愛海
「違う?」
晶(M)
そうだ。私は…
9.愛海
晶(M)
今朝は先輩が休みで、どうしたんだろうって思っていた。
上司から先輩のことを聞かれるが、私も何も知らされていない。
それを伝えると上司は舌打ちをして
「使えねぇな!」と言っていたのを思い出す。
昼になっても先輩と連絡が取れなくて、ずっと不安だった。
晶
「帰りに先輩の自宅まで行ってみよう。
病気で動けないのかもしれない。」
晶(M)
不安な気持ちを抱えたまま、その日の業務をなんとかこなす。
全く集中できなくて、ミスだらけだ。
なんとか仕事を片付けたものの、時間は0時を過ぎていた。
ニュース
次のニュースです。
昨日午前11時過ぎ、埼玉県川口市の西川口駅で
屋上から女性が落ち、一時現場は騒然となりました。
女性は直ちに病院に運ばれましたが、
現在も意識不明の重体だということです。
警察によりますと、ビルの屋上に靴と遺書が置いてあったことから、
飛び降り自殺とみて調べています。
10.バイバイ
晶(M)
そうだ。それで私は…
愛海
「きっと晶なら、ココに来てくれるって思ってたから。」
晶
「…そう、ですね。」
愛海
「だからね、バイバイしに来たんだ。」
晶
「そんな…」
愛海
「飛び降りた前の夜にね、
ほんとうは晶のところに行こうかとも考えたんだ。
でも、変だよね?
恋人でもない晶のところに行くなんて。」
晶
「来ればよかったじゃないですか。」
愛海
「晶の気持ちを知っていて、
それを利用して甘えるなんてできない。」
晶
「先輩…」
愛海
「晶のことだから、ココに来るって思ってたよ。」
晶
「なんでか分からないけど、
ココに来たら先輩に会えるような気がしたんです。」
愛海
「ずっと晶の教育係をしてたから。
やっぱり当たったね。」
晶
「全部読まれてますね。」
愛海
「うん。」
晶
「行かないでください。」
愛海
「もう逝かせてよ。」
晶
「イヤです。」
愛海
「あのひとに会いたい。会いたいの…」
晶
「行かせません。」
愛海
「バイバイ、させてよ。」
晶
「させません。」
愛海
「もう、辛いの。」
晶
「全部、私が受け止めますから、一人で抱え込まないでください。」
愛海
「それこそバカだよ。なんでそこまでするの?
ずっとずっと、わたしはあのひとのことが忘れられないのに。」
晶
「さあ?」
愛海
「さあって…」
晶
「バカだから分かりません。
でも、逝かせたくないんです。」
愛海
「楽にならせてよ。」
晶
「イヤです。」
愛海
「バカ。」
晶
「バカですみません。」
愛海
「ワガママ。」
晶
「先輩には負けます。」
愛海
「バーカ…」
晶
「愛海さん。」
愛海
「……」
晶
「私は、忘れなくてもいいと思いますよ。」
愛海
「…え?」
晶
「無理に忘れる必要も、忘れなきゃいけない理由もありません。」
愛海
「だって…」
晶
「今まで愛海さんと出会った人たちや色んな経験は、
今の愛海さんを形作ってきたんじゃないですか?」
愛海
「……」
晶
「彼氏さんがいたから、今の愛海さんがいるんですよ。」
愛海
「……うん…」
晶
「愛海さんを形作るものの中に、
家族があって、会社があって、演劇があって、
そして、彼氏さんもいるんです。」
愛海
「忘れなくて、良いの?」
晶
「忘れなくて良いと思いますよ。
それに、無理に忘れようとするのは、
今の愛海さんを否定することになりますから。」
愛海
「ねぇ、苦しい。そろそろ離して。」
晶
「イヤです。逝かないと言うまで離しません。」
愛海
「ホント…バカ…」
晶
「…はい。」
晶(M)
どれほどそうしていただろう。
愛海
「ねぇ?」
晶
「はい。」
晶(M)
腕の中の先輩の姿が、薄くなっているのに気づいた。
晶
「イヤだ。逝かないで!」
晶(M)
先輩はため息を付いて言った。
愛海
「またね。」
晶(M)
ほとんど透明になった先輩の姿が
その時
消えた。
ー終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
