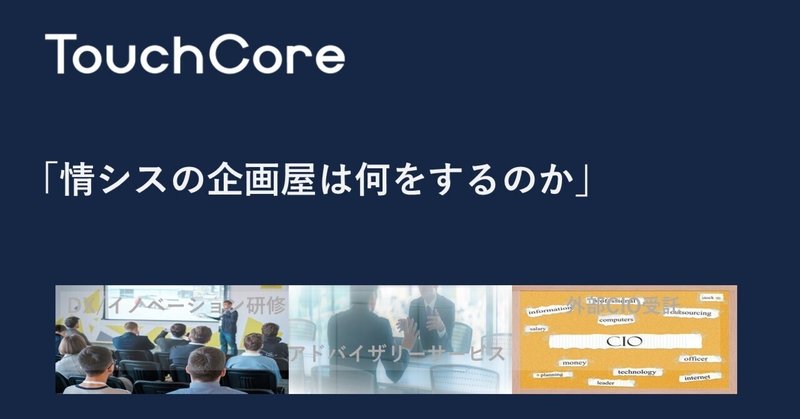
情シスの企画屋は何をするのか[20240410]
前回、ケーパビリティに着目してビジネス戦略とIT戦略を融合させたいと話をした。
テクノロジオリエントな方々は、IT戦略と聞くと技術進歩の中期計画から「すべきこと(したいこと?)」を決め戦略だとおっしゃる。
情報システムは経営価値を高める為に存在しているので「テクノロジ・ディペンド(技術依存)」である筈がない。
経営(ビジネス・フロント)からのデマンド(需要)に対して情シスを含めたITリソースは何を供給出来るのかを示すのがIT戦略である。
ITの存在意義は、テクノロジを追いかける為に存在しているのではない。
ビジネスの成長に貢献することだけが唯一の存在意義なのである。
誤解されないように説明すると、ビジネス成長の方向性やスピードは経営の意志(ビジネス戦略)である。
情シスの「企画の仕事」は、経営とITを融合させるべく経営の意志を確認し、ビジネス部門とともに如何なるケーパビリティを獲得すべきかを議論する必要がある。
情シスが「機械化」を推薦するのではなく、可能な限りフラットな状態で当社のTo Beにむけての獲得すべきケーパビリティを検討するところに首を突っ込むのである。
当たり前のことなのだがTo Beに一足飛びに行くことが出来ないのは、現状は保有していないが3年後(中期的)には獲得していなければ目標を達成できない「何らかの能力」が必要である。
多分、戦略(中期計画)を策定・立案する際には「○○○○が○○○○になっていればなあ」と頭によぎっているのではないだろうか?
その頭によぎったことを少しずつで良いので言語化し、具現化の方法を考えるのである。
IMD国際競争力ランキング第35位の日本の企業は「売上・利益を何%くらい上昇させたいか?」から中期計画を策定してしまうので、会社組織をどうしたいかという議論は完全に後回しになっていることが多い。
ビジネス戦略の策定・立案が、若干いかがわしくてもケーパビリティの議論をすれば誰もが「納得する」のだ。
情シスの企画部門は、如何なるケーパビリティを獲得して成長を遂げた企業の事例や「経営戦略」「マーケティング」面などから考察をして各部門にフィードバックする役割を担えば「戦略的な位置付けとして情シス」に変貌を遂げることが出来る。
経営から見た時に「当社の情シスは戦略的パートナーである」と映るだろう。
今回は企画屋の話を中心にしたが、プロジェクト屋も変貌を遂げて欲しい。
次回はプロジェクト屋が如何に変貌すべきかをお話したい。
合同会社タッチコア 小西一有
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
