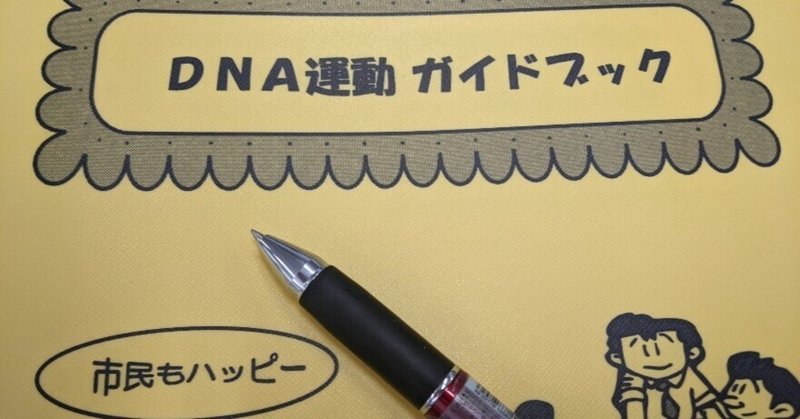
福岡市役所「DNA運動」の記憶・その165
165)DNA運動・創生「記」(137)
山﨑市長の「マニュアル化」の提案について、「スピード感が大事!」という書き込みに対して「十分に時間をかけて検討することも必要」という意見が出されましたが、この2つは単純に相反するものではないと思っています。
つまり、「スピード感」と「十分な検討」のどちらの方が優先度が高いのか、それを見極めて対応を決める必要があると考えている訳です。
このあたりのことや、公と民の違い等を含めて当時の総務企画局長が書き込みをされましたので、今回はこれをご紹介します。
******************************************
◆時間感覚(総務企画局 渡部 晶さん、平成13(2001)年10月19日掲載)
先日の私の掲示について、Yさんより、「市民の大切な税金を使うために、様々な角度から検討し、十分な時間をかけることは仕方のないことなのではないか」というご指摘がありました。
私自身として、このご指摘について共感する部分も多いのですが、他方で、このような考え方が市民からみて「時間がかかる」という場合の時間感覚の基準が違っているのではないかという批判があった場合、確信をもって反論するほどの自信がないというのが正直なところです。
私は、民間がやれば仕事がいいかげんで、公がやれば必ず民間より良い仕事ができるというような信頼感は、残念ながら、いまやないのではないかと思います。
この厳しい現状を直視する必要があると思います。
自戒を込め、また、これまでの公務員生活を振り返ってみても、日本においては、公務員の方が、退職後などに、アメリカなどと違い、民間の世界でうまく活躍できていないのは、長い間の公務員生活で、そこら辺の感覚が適応できないということではないかと思います。
昨日の日経新聞1面に少し専門的ですが、日本道路公団や都市基盤整備公団の会計処理について、建設仮勘定に計上されているうちは、金利負担が資産化されるという指摘がありました(「官業を斬る③」)。
金利が資産化するというような発想は、キャッシュフローを生み出さなくとも、公的金融あるいは公的な保証の下で、資金繰りが困らない公的な機関ならではの偽らざる行動様式が表面化しているということだと思います。ただ、これからは、国債にもみられるように、公的セクターの資金繰り問題が現実の問題として顕在化してくると考えられます。
現在、書店に、「検証特殊法人改革」(日経新聞社編)が並んでいますが、そのような緊張感のない事例がこれでもかこれでもかとあげられています。
このような弊害が、福岡市の外郭団体にもないかどうか、また、われわれの中にも潜んでいないか、今後十分検証していく必要に迫られているということだはないかと考えております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
