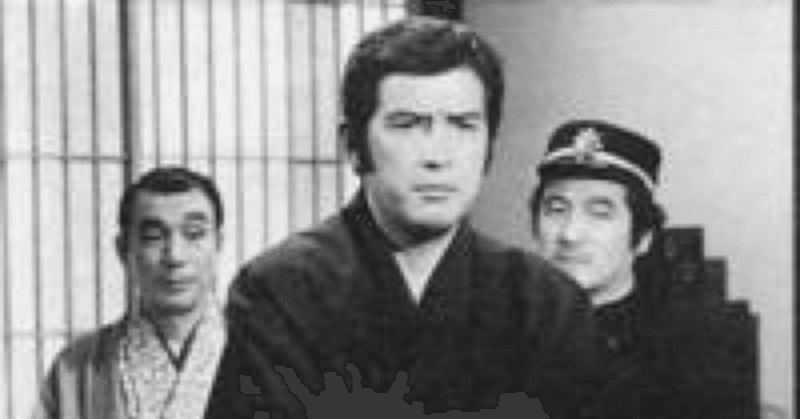
作家と読者は信用取引。
先日以来の某作家のアパルトヘイト発言。それに追い打ちをかけるチャイナタウン・リトルトーキョー発言がネットで叩かれている。しかし、まあ作家の失言の歴史の1ページを飾ることにはなっても、その作家生命を絶つほどではなさそうだ。なぜなら、既にその作家は積み重ねと権威を持っているから。
そのどちらの展開も、若い頃にその作家の読者であって、それも嫌いな作家でなかったので残念な気持ちでいる。
そこへ作家の作品が教科書にも取り上げられている、それも「誠実」という題材だという追加情報。本当にネットというのは便利なのか余計なお世話なのか。
自分がその作品で感じた誠実さと道徳で教える「誠実」は別物だったのか?
人間そんなに変われるものではないと思うが、失言してもさらに失言の上塗りをしてしまう作家の姿勢を誠実と言わずになんと言おうか(そもそも、この言い方が嫌味以外の何物でもないが)。
それとも権威あるものゆえにとれる態度なのか。
世の中、逃げも隠れもしない恥知らずはたくさんいるというけど、自分の失言は馬鹿でなければわかるはずだ。作家はわかっていると思う。でも、という気持ちもあるかもしれないし、そんなつもりはなかったという言い訳もあるかもしれないし。
一番残念なのは、もはや権威になってしまっていたら、ということだが。
いやはや、何をこんなことにいつまでも関わっているのかと自分でも思うのだが、それはやはり読者だったから。
たかが大衆小説であっても、その何万字、何百ページを自分は読んだわけで、読んで感じるところがあったから、今もそのフレーズやら場面が出てくるわけだ。そして、作者はそれを書いたわけで。ゴーストライターが居るのでもなければ、書いているのだ。読む読者も大変だが、それを書く作家も大変だよなぁって、此の期に及んでもそう思う。
それを世界の常識と照らし合わせて日本人の理解度云々と言われても、所詮はこんな読者でしかなかったというわけだが、それじゃあ、サリンジャーやチャンドラーを原書で読めたかというと、恥ずかしながら、と言うしかない。
ペーパーバックだって、翻訳を読んだから原書の雰囲気が味わえたものの、その誠実さを疑うまで読み込む力は自分にはなかった。
だから、作家と読者は信用取引をしているみたいなところがあるわけで、信用取引だから自分の読み手としてと実力と世間の評判を天秤にかけているわけだ。
たかが140字で白黒付けたり、良いも悪いも追加情報で糊塗していくのでなく、そこは過去の自分と向き合っているわけで、いろいろ残念なことも多いが、いい転機にはなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
